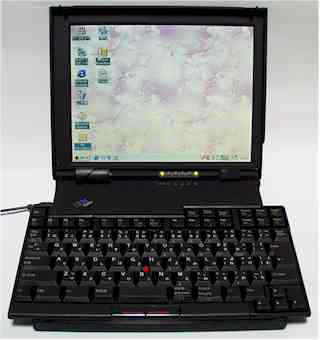 初めて見る目からは何とも奇妙な姿にしか見えませんが、非常に見易い
VGA液晶パネルと本体から張り出したキーボードが、快適なオペレーションを提供してくれます。
初めて見る目からは何とも奇妙な姿にしか見えませんが、非常に見易い
VGA液晶パネルと本体から張り出したキーボードが、快適なオペレーションを提供してくれます。ThinkPad 701Cは数ある ThinkPadの中でも恐らく最もインパクトがあり、最も有名で歴史に残る機種と言っても過言ではないでしょう。
コンパクトな本体を開くとキーボードが展開する TrackWrite機構は、如何にもアメリカ的な大胆で斬新な機構で、小型ノートとしてはトップクラスの入力環境を実現しています。
基本スペックは、CPU:DX4-75MHz,RAM:8MB,HDD:540MB or 700MB,LCD:VGA10.4" TFT
or DSTN と、既に最前線で使うには辛い仕様です。
残念ながら、TrackWrite機構のコストや構造上の問題からか、後継機の出現の可能性は低そうですが、本機だけで終わらせるにはとても勿体ないと思います。
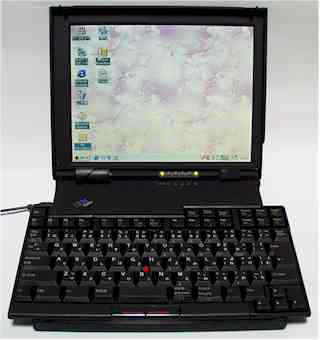 初めて見る目からは何とも奇妙な姿にしか見えませんが、非常に見易い
VGA液晶パネルと本体から張り出したキーボードが、快適なオペレーションを提供してくれます。
初めて見る目からは何とも奇妙な姿にしか見えませんが、非常に見易い
VGA液晶パネルと本体から張り出したキーボードが、快適なオペレーションを提供してくれます。
私もそうでしたが、本機は「欲しくなると魅力が見えてくる、手にすると更に面白さが判る」不思議なモデルです。
その裏で、色々と苦労が耐えない機種ですが、、、(^^;
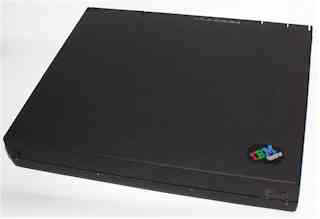 B5クラスの大きさは現在でも可搬性はまずまずです。
B5クラスの大きさは現在でも可搬性はまずまずです。
が、やや重いのが辛いところでしょうか?
それでは液晶パネルを開いてみましょう。(^^)
 この角度位までは、キーボードは沈黙を守っています。(^^;
この角度位までは、キーボードは沈黙を守っています。(^^;
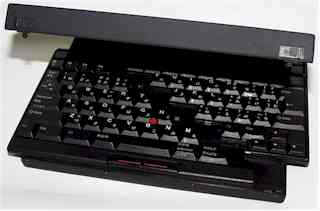 格納状態のキーボードが左右に開きます。
格納状態のキーボードが左右に開きます。
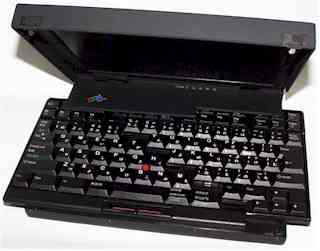 左右いっぱいまで移動すると、右側分割部分が手前に移動します。
左右いっぱいまで移動すると、右側分割部分が手前に移動します。
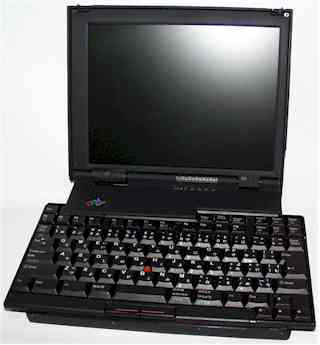 ということで、展開が完了した姿です。
ということで、展開が完了した姿です。
開発コードネーム「Butterfly」の名に恥じない、優美で驚きに値するデザインです。
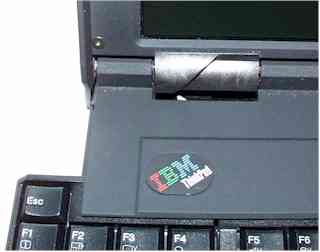 キーボードの移動をさせる重要な部分である奇妙なヒンジ部分。
キーボードの移動をさせる重要な部分である奇妙なヒンジ部分。
この付近には興味深い箇所が多く、ThinkPadエンブレムとヒンジ以外にも、キー1つ分ぴったり張り出したキーボードや、そのキーボードの分割部分(F4とF5の間)など、じっくり観察して飽きないですね。
 全備状態の 701C。
全備状態の 701C。
判りにくいですが、背面に MultiPortII(MP2)、側面パラレルポートにFDDドライブを接続した状態です。
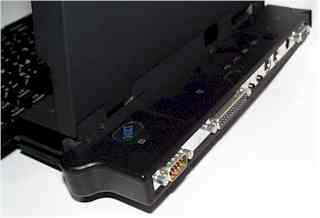 MP2には、手前からシリアル、パラレル、ライン入力、ライン出力、キーボード、マウス、電源入力、そして
CRT出力が装備されています。
MP2には、手前からシリアル、パラレル、ライン入力、ライン出力、キーボード、マウス、電源入力、そして
CRT出力が装備されています。
逆に本体にはモデム(この 5TJは未搭載)、オーディオ関係入出力ジャック、パラレルポートのみしかありません。
 単体の MP2。
単体の MP2。
如何にも・・・って感じのデザインがナカナカです。(^^;
 MP2の本体接続部。
MP2の本体接続部。
赤丸の爪は折れやすいので、取り扱いに注意が必要です。
(中古で爪が折れているケースが結構あるようです)
この爪が破損すると、MP2装着時にロックがされず、使用中に外れてしまうことがあります。
このロックを外すには、手前のレバーを引くことになりますが、ここにはケンジントンロック用の穴が開いており、ロックを取り付けると
MP2は取り外しできなくなります。
(この辺は IBMらしいですね)
ちょっと判別しにくいですが、MP2の本体チルトアップパネル(突起の出ている凹形の板)を展開した状態にしています。
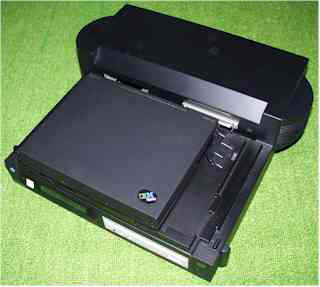 日本版ではサポートされていませんが、海外では
DockIIのサポートがされていたようです。
日本版ではサポートされていませんが、海外では
DockIIのサポートがされていたようです。
ということで、手元の DockII(3546-J01)に載せてみました。
755などは右寄りにセッティングしますが、701Cでは左手前の爪を起こし、接続コネクタをレバーで引き上げてドッキングする様になっています。
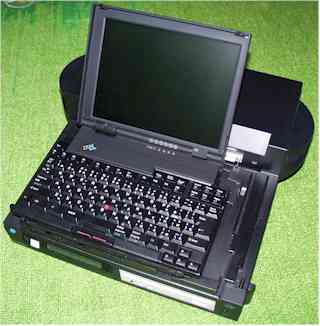 液晶パネルを閉じた状態では DockIIの大きさもあって
701Cは随分小さく感じますが、液晶パネルを開いてキーボードが展開されると、755系搭載時も顔負けの迫力を醸し出します。
液晶パネルを閉じた状態では DockIIの大きさもあって
701Cは随分小さく感じますが、液晶パネルを開いてキーボードが展開されると、755系搭載時も顔負けの迫力を醸し出します。
こうなってくると、もはや蝶の華麗なイメージを通り越してしまっていますね、、、(^^;
755系搭載時に比べるとかなり左に寄っているので、見た感じがちょっとバランスが悪い気がします。
(ちなみに 755系は DockIIのほぼ中央に本体がきます)
 701Cとの接続部・・・のはずですか、残念ながら
DockII側に 701C用のコネクタがありません。(;_;
701Cとの接続部・・・のはずですか、残念ながら
DockII側に 701C用のコネクタがありません。(;_;
このコネクタは(推定ですが)スピーカー下のレバーで昇降して、DockII内に格納できるようになっています。
(755系ドッキング時には邪魔になるので、格納可能になっています)
左の半円の張り出し部がスピーカーで、701C用コネクタの昇降レバー部がすぐ下に僅かに見えます。
中央下が DockII自身の鍵で、これをロックすると電源の入切はおろか、本体の取り外しも出来ません。
鍵の右横の楕円穴は、本体アンドッキングレバーの穴です。
 701Cの FDD
701Cの FDD
手元に ThinkPadの FDDがゴロゴロしている(^^;ので、ひょっとしたらオリジナルと違うかもしれません。
本体パラレルポートに接続しますが、本体側のパラレルポートコネクタはご覧の通りハーフピッチになっています。
本体付属品に、このハーフピッチから D-sub 25pへの変換ケーブルが付いていますが、入手した本機では紛失していました。
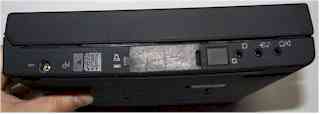 本体左側面は電源スイッチやポート類が配置されています。
本体左側面は電源スイッチやポート類が配置されています。
この電源スイッチは、非常に操作しにくいことで知られています。
 本機(5TJ)のバッテリーは Ni-Cdですが、入手した個体に装備されていたのは
Ni-MHでした。
本機(5TJ)のバッテリーは Ni-Cdですが、入手した個体に装備されていたのは
Ni-MHでした。
入手時にセルがダメになっていたので、開腹手術して単三の Ni-MHに交換しています。
(メーカー保証外ですし、バッテリーの種類などを誤ると危険ですので、実施される方は御自身の責任において作業して下さい)
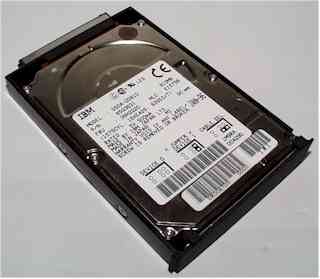 HDDパックです。
HDDパックです。
オリジナルは 540MBですが、本機では 810MBに交換しています。
(本来は絶縁シートが HDDに貼り付けてあります)
本機は E-IDEに対応しており、12.7mm厚のドライブと容易に交換ができます。
オリジナルではネジ穴は内寄りです。
(なお自力での HDDパックのドライブ交換はメーカー保証外になります)
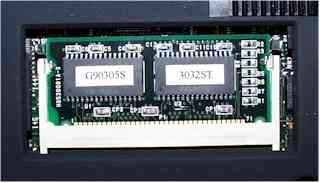 本体底面のメモリソケット部分。
本体底面のメモリソケット部分。
IBMオプションでは 16MB(計 24MB)までですが、サードパーティー製で
32MB(計 40MB)まで増設できます。
この写真の DIMMはハギワラシスコムの物で、この製品は現在でも比較的容易に入手できます。(HSD-3032ST)
本機はよく「マニア向け」という人も居ますが、後継機が出ていたら一般にも受け入れられていた気がします。
最近は薄型ノートが流行っていますが、701Cはひょっとしたら、そういった流れに対する別のアプローチが出来たかもしれません。