この時期の特徴
事件が年を越しても解決の具体的な展望が見えないという状況の中で、300万人署名、パンフ「真相」の発行など、広く市民に坂本一家救出への協力を訴える活動を開始した。中でも大きいのは、パンフレット「真相」の発行に象徴されるように、坂本弁護士宅の様子も含めて、事実を積極的に市民・弁護士に訴えていく活動に踏み切ったことである。このような取り組みが、この事件への市民の理解と共感を深める大きな転機となった。
また、坂本一家の両親も、各地の集会に足を運んで訴えたり、署名を訴えるなど、市民の中に出て支援を訴える活動を開始した。これもまた、事実の積極的な訴えかけとともに、心情面で市民が運動に協力・参加する大きな転機となった。もしも同僚だけが訴えていたら、これほど大きな運動にはならなかったことは明らかである。
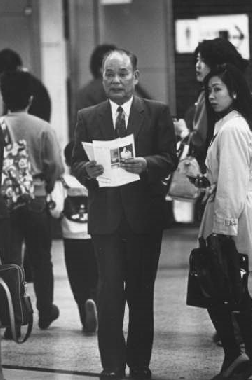
各地での集会作りにも本格的に取り組み始めた。
このように、この時期の活動は、その後の救う会の運動の基本を作り上げていったと言える。
このような活動の中で、1990年4月には、新たに赴任した県警栗本刑事部長が、坂本事件は弁護士業務に関連した拉致事件の可能性が高いと初めて公式に言明し、家出ではないかとの当初の見方を払拭することにある程度成功した。
日弁連の中に、3月16日、理事会内対策本部が設置され、横浜弁護士会は2月9日の「弁護士拉致事件の真相を語る集い」に続き、11月1日には「生きて帰れ!坂本弁護士と家族を救う第1回全国集会」を開催するなど、弁護士会としての体制も徐々に整い始めた。
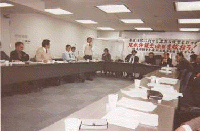
そして、全国各地の弁護士会にも坂本事件を正確に理解してもらい、今後の救出活動に協力してもらうために、「救う会」では「全国行脚」を実施。10月以降、ほぼ全ての弁護士会に足を運んで、坂本事件の報告と救出活動への協力要請を行った。
救う会の体制面では、3月3日と7月22日に全国代表者会議を開催するなど、東京・横浜の事務局中心の活動から、全国的な活動を行う体制作りを進めた。横浜と東京のメンバーによる事務局会議も、ほぼ毎週開催され(90年1月から12月までの間に42回)、且つ、会議への参加者も平均約12人など、当初の嵐のような勢いはないものの、その勢いをなお引き継いだ活動を続けた。
総じて、この時期は、全国の市民、そして全国の弁護士・弁護士会に、坂本事件が弁護士業務に関連した拉致事件であるということを理解してもらい、その力を借りながら警察に対するプレッシャーをかけることに力を注いだ時期であったと言える。
ただ、他方で、市民・弁護士会に広く救出運動への協力・参加を求めることから、オウムへの取り組みが薄くなっていった面があるのは否めない。全弁護士が加入する弁護士会・日弁連が坂本救出運動に取り組む上で、オウムが怪しいという主張をあまり前面に出すことはできない。「救出運動を広げること」と「1番の容疑者であるオウム真理教への取り組みを強めること」との綱引きの中で、救う会は、基本的なスタンスを「運動を広げること」に置いて活動を進めていった。
 次へ
次へ 救出活動の軌跡もくじへもどる
救出活動の軌跡もくじへもどる