私が現在の環境ISOにおいて一番問題だと思うのは環境法違反である。環境事故ももちろん問題であるが、報道を見る限りISOの仕組みが機能していないことによる事故は違反ほどではないと思う。
もちろん情報源はマスコミで報道されたものと私が見聞きしたものだけだから、より包括的な情報を持っている方がいらっしゃったらぜひ提供願いたい。
さて、ISO認証しました、ISO14001規格適合のEMSですといいながら、法違反が起きるのはなぜだろうか?
はっきりいって環境側面の特定、決定、法規制の把握などはどのようなアプローチであろうと、間違えた方法であろうと、実害はない。要は正しい環境側面を把握したかということ、関わる法規制をしっかりと認識しているかということである。
審査で環境側面の特定方法、著しい環境側面の決定方法について延々と議論が行われるのが審査の常である。また法規制をいかに把握して、それをどのようにまとめているかを聞き取るのは太陽が東から昇るように日本全国津々浦々変わらないようである。
しかし現実に事故を起こさないためには、環境法違反を起こさないためには、環境側面を把握する方法の良し悪しとか、その組織が自立して法規制を調査しなければならないということは、絶対にない。
本日は、とりあえず法順守に関してだけ述べる。
法を守るということは日本国民であるから当然というだけでなく、それは自分を含めた国民総体にとっての利益であるから遵守するのだと私は考えている。
法哲学とか難しい理屈はとりあえず抑えてください。
そんなことを思うと、審査において「どのように環境法規制を調べたのですか?」と聞く代わりに「規制を受けると認識している環境法規制は漏れがないか?」と調べる方が環境法違反を防ぐためになるだろうことは間違いない。JABも認証機関も、そこはちゃあんと逃げを打っている。法規制を調べるのは組織の仕事、その仕組みがしっかりしているかを見るのが審査だという。
実を言って環境側面についても「環境側面に関する手順を開発するのは組織の仕事、手順が適切であるか、それが守られているかを審査するのが審査登録機関の仕事(IAF GD66:2006)」と決めてある しかし法規制と違って、環境側面の手順を決めるのを組織に任せておけないと考える審査員が多いようです。 環境側面なら法に関わらないので間違っても安心なのかもしれません。 |
つまり仕組みをブラックボックスとして、アウトプットの善し悪しを見て判定するしかないと考える。
あまりここで論ずると長引くのでとりあえず法規制を調べること、あるいは調べる仕組みより、結果が重要であるという結論としておく。
さて、法規制を認識したとして、法違反をしないように、危険な状態にならないように運用するためには、法律の名前や目的あるいは趣旨を理解しても手の打ちようがない。
5W1Hで誰が何をどこでいつどうするということを明確にしなければならない。
そんなこと私が言うまでもなく、
ISO14001 4.3.2 b)これらの要求事項を組織の環境側面にどのように適用するかを決定する。
と記載されている。
さあて、みなさん、良く考えてください。
あなたの会社のマニュアルはこの項番についていかに対応しているのでしょうか?
ここでは文書化を要求していないけれど、4.4.6で実質的に作業手順書に相当するものを要求している。
結論を言えば、私の知る限りしっかりとこの項番の意味することに対応している組織は少ない。多くの組織は、法規制を調べました。一覧表にまとめました。すごいでしょう、で終わりだ。
そして審査ではそれでけっこうと認証されている。関係者のみなさん、4.3.2b)項を忘れてませんか?
さて、法規制の内部展開をしっかりしていないと、社内の人が法規制を知らなかったとか、法規制の詳細を知らない、法律を順守することができないことになりますね。
話が長くなるから、ここもこれではしょる。
運用段階について考えよう。
作業者は与えられた業務において、どのように操作するのか、どのような処置をするのか訓練を受け、実際に行うことができなければならない。実際に運用できることを力量という。決して何時間教育を受けましたとか、資格を持っていますといっても仕事ができなくては力量はない。
補足説明すると、その業務においていかなる危険性、環境に与える影響なども知っていなければならない。
この段階で法違反が起きるとすると、
ひとつは法規制を教えられていない場合である。正しく言えば法規制を展開した仕事の手順、基準を教えていないということだろう。
ふたつには、その手順が実行困難あるいは人がいないのでやれない場合
みっつには、作業者がその手順に従わない場合
が考えられる。
では次に行く。
さて、法規制をしっかり調べて、それをわかりやすい要領書にまとめ、そのとおりできるように訓練して、仕事をさせても、人間は間違えるだろう。あるいは手抜きするかもしれない。だから監視をし順守評価をすることになる。
もちろん、計画段階が良くて、運用段階が良ければ、監視段階は不要であるかもしれない。しかし世の中は理想はありえず、次善もなく、ミスと手抜きとルール違反がたくさんある。
だから、監視段階は最後の砦である。
不具合、手抜き、法違反が起こるのは良いこととは言えないが、それを社内で見つけ対策することが仕組みとして機能しているならすばらしいことだ。
それこそがマネジメントシステムの存在価値である 
ISO14001を認証している会社なら、マスコミで報道されるような法違反は起こるはずがないと思いませんか?でも報道されている環境法違反を起こした会社のほとんどはISO14001認証をしている。
それでは違反した会社はどういう仕組みだったのだろうか?
私はそれに非常に興味がある。
振り返ってみると、法違反を起こすためには
・法規制を良く調べていなかった
・法規制を社内展開していなかった
・よく訓練していなかった
・決まりを守っていなかった
・不可抗力・・・不可抗力の事故はあるが、不可抗力の違反はありえるだろうか?
上記のいずれかが起きて違反しても、法規制を守っているか点検していれば社内で検出して対応できるはずだ。
順守評価で違反を検出できなかったなら、それは順守評価をまっとうしていなかったということであり、それは順守評価の仕組みが悪いのか? 実施者の力量がなかったのか? 受けた部門がうそをついたのか? 順守評価者が見て見ぬふりをしたのか? あるいはそのほかどんな状況だったのだろうか?
一般論とか規格ではなんて語ったところで面白くないし、検討にならない。
具体的な事例で考えてみたい。
- 廃棄物処理を委託するにあたり、その県の許可がない業者に委託して措置命令を受けた会社があった。私の同業者ならこれだけでどこかおわかりだろう。
- 法規制を調べていなかったのだろうか?
ISO審査で調べる仕組みが悪いと言われなかったのだろうか?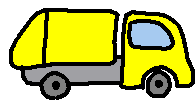
- 法規制を社内展開していなかったのだろうか?
ISO審査で4.3.2b)項を確認しなかったのだろうか? - 訓練していなかったのだろうか?
力量をどのように確認していたのだろうか?
座学で教えておしまいだったのだろうか? - 日常の業務確認を上長はどのように確認していたのか?
- 廃棄物処理法で契約書は有期と決まっている。当然契約を更新するときに、その業者が適正かどうか、許可証を含めて評価しているはずだ。
- 順守評価では何を見ていたのだろうか?
- 法規制を調べていなかったのだろうか?
- マニフェスト票を業者に書かせていて担当していた課長が逮捕された会社があった。
逮捕された課長は法律を知っていたが人が足りなかったと言っていた。
じゃあ順守評価もしてなかったのだろうか?
ISO審査ではでっちあげた順守評価の記録を見せていたのだろうか?
謎は残る - 排水の測定データを改ざんしていた会社があった。
このとき担当者は前任者から引き継いだとおりに仕事をしていたと言い訳したという。- 法規制をしっかり把握していたのだろうか?
- 社内の手順書が法規制と異なっていたのだろうか?
だとするとそれを決裁したのは誰か?
仕事をしていたのは公害防止管理者であるから、仮に手順書が間違っていても気がつかなくてはならない。善管注意義務ってものがあるだろう? - 順守評価をしていなかったのだろうか?
測定結果を第二者が確認するということはなかったのでしょうか? - そういう不備が重なっていたのをISO審査で見つけなかったのだろうか?
- オフィスで空調機を設置しておきながら騒音規制法の設置届(正確には設置申請)をしていない会社って多いです。
- 法規制を知らなかったのでしょうか?
オフィスであれば規制を受ける法律は片手か多くて両手、審査でどういった方法で環境法規制を特定していますか? なんて聞く暇があれば、思いつくものを聞いていけば終わりでしょう? そんなことしてなかったのでしょうか? - この場合、法規制を認識していなければ手順書への展開も、運用も、順守評価もモレモレになる可能性は極めて大である。
どうしたらいいのだろう?
だが、ISO規格は良くできている。内部監査で法規制を調べる仕組みが適正かどうかを点検しなければならない。
まさか法規制を特定する仕組みがあるかを聞くだけの内部監査をしているんじゃないでしょうね?
内部監査結果、環境担当取締役あるいはコンプライアンス担当取締役に「当社の遵法は大丈夫です」って報告しているんでしょう? それなら覚悟をもって調べなければいけません。
おっと、取締役に環境監査報告をしていないなら、そんな内部監査おやめなさい。
話がそれるが、ほとんどの企業で環境基本法、循環社会基本法などを該当法規に取り上げており、しかも順守が適正であったと記録している。
ISO規格の順守評価の意味を理解していないと言われても反論できないだろう。ほとんどの企業で環境基本法、循環社会基本法などを該当法規に取り上げており、しかも順守が適正であったと記録している。ISO規格の順守評価の意味を理解していないと言われても反論できないだろう。
これを読んで意味がわからんという方からお便りをいただいた。(2008.11.09)
よって蛇足を追加する。
順守評価ってどのようにしていますか?
法律の表に○、×を付けているだけなんでしょうか?
でも一つの法律でもあなたの会社・工場ではたくさんやることがありますよね。公害防止組織法であっても、組織を作るとか、統括者、代理者の選任届、公害防止管理者の育成から選任届で、異動したときの届け出・・・そういったこと、ひとつひとつについて法を守っているかどうかを確認し記録しなければならないのです。
さてそうしますと、環境基本法、循環社会基本法などの順守評価をしようとすると、はたして何を点検するのでしょうか?
努力義務があるだろうとおっしゃいますか?
そうしますと努力を何で測りどう評価するのでしょうか? 私には分りかねます?
これだけ蛇足を追加してもお分かりにならなければ、ISOの世界から足を洗ってくださいな - 法規制を知らなかったのでしょうか?
|
なにしろISOの登録証にはちゃあんと「当審査機関が貴社の環境マネジメントシステムを審査した結果、規格に適合していることを確認しました」と書いてある。
認証機関は「遵法を保証するものではない」と大書しているが「規格適合を保証している」のである。
規格適合とは
・法規制をしっかり調べ
・それを社内展開し
・力量を確実にし
・順守評価をすることでした。
もし、
・法規制をしっかり調べていなかったり
・しっかりと社内展開していなかったり、
・力量が確実でなかったり
・順守評価がしっかりしていなければ
ISO14001規格に不適合なような気がします。
ISO14001を認証していて法違反が起きるということはいったいどうしてなのだろう?
世に法違反がたびたび報道されているということは、なぜなのだろうか?
なぜだろう?で終わっては無責任ですよね、
ということで続きがあります。
ということで続きがあります。
ISO14001の目次にもどる