えー、毎度ばかばかしいお話を一席
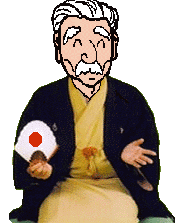 わが愛しきISO規格では不適合があれば是正処置をすること(しなければならない)を決めています。不適合とは何ぞや?とか是正処置とはなんぞや?という基礎的なことについては別途勉強していただくとして、本日は是正処置とはどう進めるべきかというバカ話をひとつ・・
わが愛しきISO規格では不適合があれば是正処置をすること(しなければならない)を決めています。不適合とは何ぞや?とか是正処置とはなんぞや?という基礎的なことについては別途勉強していただくとして、本日は是正処置とはどう進めるべきかというバカ話をひとつ・・つまらない事例をあげましょう。
誰です、お前はつまらない話しかしないとおっしゃったのは? そうでもないのですよ、私はつまらない話だけではなく、くだらない話もできますので・・
法律が変わって白熱電球というものが禁止されるそうです。理由は白熱電球がエネルギーの無駄使いなので省エネのためなのだそうです。自今以降、エジソン由来の高熱物体による発光という原始的な技術による照明機器は使っていけないのだそうです。
高温の物体は光を発し、その温度によって色が異なる。というのは物理の初歩。40年以上前、工業高校でキュウポラからの湯(溶けた鉄)の温度を光温度計で測りました。慣れると光温度計など使わずとも、見ただけでわかるようになります。 星の色もその表面温度によって決まります。だから星の色からその温度がわかり、星の年齢がわかり、あと何年の寿命なのかわかるそうです。人の場合、顔色を見ても年齢も寿命もわかりません。お金を持っているかどうはわかるようです。 |
それじゃあ電球が使えなくなったら、人は暗い所で生活しなければならないのか?なんて詰め寄られても困りますよ
 マリーアントワネットは言ったでしょう。パンが食べられなければお菓子を食べれば良いってね。
マリーアントワネットは言ったでしょう。パンが食べられなければお菓子を食べれば良いってね。ご心配はいりません、白熱電球が使えなくても、ろうそくがあるじゃないですか。それは冗談ですが、蛍光灯あるいは最近ではLED照明、更には有機ELなど効率が良い新しい照明機器がどんどんと現れています。
もっともLCA全体にわたっての資源効率が良いのかどうか私は知りません。つまり使うときのエネルギーだけを見れば、白熱電球に比べ新しい照明機器は効率が良いでしょうけど、製造や廃棄まで考えるとどうでしょうか?
電球型蛍光灯は根元に安定器などが入っているのですからね。つまり電球型蛍光灯の交換とは、従来の蛍光灯であれば器具ごと交換することですから、白熱電球よりも資源とエネルギーの無駄使いのような気がします。
おっと、白熱電球で話がそれてしまいました。本日は白熱電球と新しい照明機器についての駄文ではなく、是正処置についての駄文の予定です。どちらにしても駄文に違いはございません。
さて白熱電球を使っていたとします。あるとき、光らなくなりました。どうしましょう?
 |
⇒ |
 |
私の娘は夫がパソコンを買ってきても開梱もできないので、セットアップもネットにつなぐのも全部娘がしてやるそうです。おっと、私も実は横のものを縦にもしない男なので、家の中のことはすべて家内がします。まあ、重い物を動かすくらいは手伝いますが・・
|
修理の原則なんていうほどのことではありませんが、何事でも故障が起きたら原因を調査する順序ってのはあります。一般的に発生確率の高い順からというのがセオリーでしょう。
-
電球が光らなくなったら、
- 誰でもまず電球を取り外して耳のそばで軽く振って見るはずです。電球のフィラメントが切れていればチャラチャラ音がするでしょう。
- 次に音がしてもしなくても、買い置きの電球に取り換えてみるか、買い置きがなければ別のところの白熱電球と取り換えて光るかどうかを見るはずです。
電球を交換して光れば前の電球が切れていたわけで、原因は分かりまして処置に移ります。交換しても光らなければ次に進みます。 - さて、電球を交換しても光らなければ他のところの照明のスイッチを入れてみたり、冷蔵庫が動いているかどうか見ることになります。他の電気器具が正常に機能していれば、当該の照明機器の電線がどこかでネズミにかじられたのでしょう。
他の電気器具も動いていなければ、家全体に電気が来ていないことになります。 - ブレーカーを見てみましょう。最近は一般家庭でも大電流契約になりましたが、双子の娘がドライヤーを使って、おばあちゃんがホットカーペットを、奥さんが乾燥機とオーブントースターを同時に使ったりすると根元のブレーカーが落ちてしまうこともあります。
おっとあなたブレーカーをあげてもだめですよ。その前に双子の娘に「ドライヤー使うのちょっと止めて!」と声をかけてからにしましょう。 - ブレーカーも落ちてないとなりますと、これはお宅の外に原因があることになります。例えばお宅に侵入しようとする悪者が電線を切ってしまったのかもしれません。あるいはディズニーランドのそばの河を渡る船がクレーンをあげて送電線を切ってしまったのかもしれません。よりありそうなのはエネルギー危機で電力会社が営業を止めてしまったということかもしれません。
世の中には原因追求の手法がたくさんあるそうです。私は学がないのでQC7つ道具とか、新QC7つ道具程度しか知りません。でもいくら難しい問題対策手法を知っていても、現実の問題への適用ができない人が多いようです。
おっとこれは言いがかりではありません。
ISOの審査で問題がある、企業工場は現在の審査に不満であるということは、現時点自明のことです。その問題は組織側だけでなく、認証機関も、認定機関も認識しています。しかし現実に行われている問題対策はどうなのでしょうか?
審査が不満なのよ、審査員がイマイチなんだけどという不満や苦情があれば、まずすることは審査の実態を調査し問題があればその問題を取り除くということかと愚考します。
審査員の判定がおかしいなら、審査員を教育する、ダメな審査員には辞めてもらう、苦情を大きくならないうちに対処するように受付窓口を改善する、審査の場で苦情の処置手順を十二分に説明するなどなど、金もかからずすぐできることはたくさんあります。そういう手軽で基本的なことから実行していくべきことは、電球がつかなくなったときの対策と同様であると思います。
しかし世の優秀な方々はそう考えないようです。
審査が不満なのよ、審査員がイマイチなんだけどという不満や苦情があれば、まずすることはISO17021の改定とか、ISO9001の改定から始めるとはさすがというか、遠大で抜本的ですね。いや私にはすばらしいというよりアホかあるいは現実逃避かという感じがいたします。
たとえて言えば、電球がつかないとき「これは北朝鮮のテロで原発が攻撃されたのだ」と結論するような突拍子もないことではないですか!
もっとも前者のアプローチでは、審査員がひとりもいなくなったり、認証機関が全部なくなるという可能性もあるのだろうか?
|
私は2008年改定は審査の質には全然関係ないと考えている。そして過去JABなどが打ち出した諸施策も、審査の質向上にはいささかも寄与しないだろうと考えている。それは目の前の問題を取り除かないからです。道路が渋滞しているときに、すごいスピードの出る車を持ち出してきてもだめなのと同じです。
まあ、登録件数が減少して登録売上が減っている現在、認証機関もコンサルも今回の規格改定にからまる研修とかコンサルでほっと一息つけるのは間違いないでしょうから、全く無意味ではないかと・・
是正処置と言いながら是正処置と関係ないじゃないか!なんておっしゃってはいけません。これもまたケーススタディのひとつですから
えー、おあとがよろしくないようで 
本日の最後っ屁
だじゃれを語るだけでなく、現実のバカバカしさと闘わなくてはならないのは悲しいことだ
私はISOだけでなく、人権擁護法や国籍法改悪とも戦わなくてはならない
いずれも原因究明はできても是正処置は不可能かも・・・
あらま様からお便りを頂きました(08.11.24)
不適合とは・・・ 佐為さま あらまです 不適合に対して是正処置をするための作業手順をつくる・・・。 そうしておけば、「担当者」がいなくても、対処できるというもの・・・。 ・・・なんて言いますが、事態はそんなに単純ではありません。 例えば、佐為さまが例に挙げられた「灯りが消えた」という事態の対処法。 電球が悪いのか、電線が悪いのか、電源が悪いのか・・・と、順を追って原因を究明しますね。 しかし、自分のメガネや自分の眼球の異常、もしくは自分が突然の脳梗塞に襲われて視力が失われて、灯りが認識できないことだってあります。 小生のような未熟な作業員は、オシャカが出来た場合、材料や機械や道具が悪いのではなくて、まず、自分の腕が悪いと反省することから始まります。 料理でも、マズイものを作ってしまった場合、材料が腐っていたからではなくて、自分の腕が悪いからマズイものを作ってしまったと反省するわけです。 そうすれば、次から美味しいものを作れます。 正しい基準をつくり、それに適合しているか・・・も、大切でしょうが、正しい基準が本当に正しいものなのか。 それを常に考えることも必要かと思います。 もちろん、佐為さまは、そういうことを承知で持論を展開されていると思いますが、外国人労働者の中には、絶対に自分の非を認めない人がいます。 先日も、オシャカを隠した労働者がいました。その反省の弁が「もっと上手に隠せばよかった」と。どこの国とは言いませんが・・・。。。 「不適合」とは、何に不適合なのか ? ? でも、反省ばかりではダメですね。反省するほど、ツッコミを入れてくる国ばかりですから。 日本は「不適合」国家ではないことに自信を持ちたいものです。 |
現代の名工 あらま様にかかってはISOの価値観では立ち向かえません。 冗談ではなく、ISOの標準化の世界は並みの人間が並みの製品を安定して作るのにはどうすべきかというレベルなのですよ。現代の名工あらま様のお考えになっている技の世界、匠の世界、奥義は一子伝承なんていうものとは次元が違うのです。 ところで、不良ができたとき己を責めるというのは、日本人の美学であることは認めますが、そういう発想では南京虐殺も従軍慰安婦の嘘にも対応できません。 なにせ彼らはうそも100ぺん言うと本当になるというお考えなのです。 ここはひとつ恥ずかしいかもしれませんが、グローバルスタンダードというやつで己の正当性を大声で主張するのが普遍的な手段かと愚考いたします。 そしてISOの世界は少なくても性善説でできていると思います。記録を残せという場合、うその記録はないという前提で構築されています。 嘘があるという前提では・・・ISOじゃなくてUSOじゃないですか |
あらま様からお便りを頂きました(08.11.26)
ISOが適合するためには 佐為さま あらまです まず、訂正をお願いします。小生は同じ「メイコウ」でも、オシャカ作りの「迷工」です。 さて、佐為さまが仰るように、ISOの標準化のお陰で、並みの人間が並みの製品やサービスを安定して提供できるようになりました。つまり、コンビニやファミレスのように、画一的なマニュアル世界が実現したわけです。つまり、産業のコピペ化が実現し、アジアにも日本の工場と同じレベルのものが建てられ操業しています。 しかし、技術には「標準化」するものと「特化」するものとがあると思います。その「特化」すべきものまで「標準化」しようとしたところに ISO の問題があると思います。 小生は、ISO から規制を受ける立場でしたので、当初から「ISO は没個性化」だと感じてきました。さらに、標準化が広まるほど、モノや技の価値が下がると思っています。それが、価格の下落につながり、賃金の下落に繋がるものだと思います。 そうして「格差社会」が出現したと思います。 誰にでもできる簡単な仕事しかない職場では、仕事がつまらないし、賃金もそれなりだとおもいます。 ですから、豊かな世界を実現するためには、画一的な社会ではなくて個性的な社会で、それぞれが価値を高めあうことが必要だと思います。 1日の研修で、翌日から即戦力が可能な社会よりも、水汲み、皿洗いを数年続けてようやく立場を確保できる社会のほうが正常だと思うことは時代遅れなんでしょうか。 |
現代の名工あらま様を迷工などとは間違っても言えません。 標準化は仕事の価値をなくすのか?ということは昔から言われていることです。 そもそも標準化とはなにか?と考えると、基準を決めることでしょうし、それは互換性や量産性を向上させるためのものでしょう。それは産業にとって悪いことなのか?ということになりますが、そんなことはないと思います。 良く言われますが、音楽を記述する五線譜と音符は標準化の見本です。ベートーベンもビートルズも桑田も小室もみな五線譜に♪で音楽を書き表していますが、だれも作曲がつまらなくなったとか、没個性だとか文句を言いません。 あらま様は標準化がお嫌いなようですが、あらま様が機械を作るときボルトナット、キーといった機械要素やベアリング、リミットスイッチといって基本的な部品などをいちいち図面を書いたり仕様書を作って手配していたらたまりませんよね? 標準化とはそういうもの、たとえてみればOSとかオフィスソフトのような基本機能に適用するものではないのでしょうか? 同じペイントショップソフトを使っても素晴らしい絵をかける人もいれば、使いこなせない人もいます。 あまり標準化というものをたいそうなものと捉えずに、仕事を楽にするものと考えればよいのではないでしょうか。そして標準化された道具を使って楽に良い仕事、創造的なことができるのではないでしょうか? もちろん、そこに至らない低レベルな仕事であるなら、名工がでることはありません。今まで関わっていた単純な仕事から職人が解放されるなら、職人がいらなくなったと嘆くことはないでしょう。 卓越した技能が要らない仕事ならば、手間賃が下がって当然ですし、それこそ社会に貢献することです。 |
あらま様からお便りを頂きました(08.12.01)
佐為さま あらまです 小生の愚考にたいして懇切なお返事を戴き、恐縮です。 さて、小生は作業の標準化に対して「好悪の感情」を抱いているわけではないと思っているのですが、やはり、そう映りますか。 小生は、標準化とは言語化だと思っています。それを機械語に翻訳すれば、その作業が機械化され、それを省力化することによって更なる効率が得られると思います。 それを客観的にみることができるようになって、安全性も飛躍的に高まりました。 それが、今日の産業の発達に繋がるものとして評価します。 しかし、それはあくまでも「方法論」であり「目的論」ではないと思います。(「論」としたのは既に情報が体系化されているからです) ところが、巷の標準化、規格化の作業を見ていますと、どうもそれが目的となり、作製したマニュアルが金科玉条のごとく拝まれているように思います。 小生は、それは本末転倒だと思います。 方法が目的となっているので、まるで人間が機械とかコンピューターに使われているような錯覚に陥っているのではないでしょうか。 小生は、あくまでも、人間が「主」であるべきだと思います。ところが品質管理では「規格」が「主」になり、それに従うことが当たり前の社会になっています。 つまり、マニュアルがないと何も出来ない社会になっているような気がしてなりません。 たとえば、「企業理念」なんてものがありますが、それすらも規格化、標準化しているような気がします。本来は、創業者の意思が反映されるべきものだと思います。ところが、本来の理念が規格化、標準化されてしまっては、没個性的な企業が増えたような気がします。 家庭でも同様です。子育てにも、マニュアル本が氾濫しています。しかし、育児本を読んだところで、母親の不安は増大するばかりだと思います。やはり、頼りになるのは、母親であり、おばあさんではないでしょうか。 そういえば、小生が若い頃「HOW TO」本が、出版され、小生も隠れて「HOW TO SEX」なんて本を読んだものでした。しかし、その本から得た知識よりも、実際の体験のほうが良かったことは当たり前だと思います。 ところが、最近は、女性に対してもプログラム化され偶像化された「フィギュア」に恋愛感情を抱く若者が増えているような気がします。 つまり、「女性」を「人格」ではなくて「プログラム」として捉える傾向があるような気がします。従って、「人格」としての「女性」と付き合うのが面倒になり、アニメ化(偶像化) した女性に安心する男性が多いように思います。 さらに、「遊び」も、人間の友達と遊ぶことがあたりまえであったのが、今ではコンピューター・ゲームが圧席しています。対戦ゲームも、「人格」と対戦しているのではなく、規格化・標準化した相手と対戦しているわけです。 工場の技の伝承も同様です。今は、マニュアルに沿って先輩が後輩に懇切丁寧に教えています。しかし、それでは「カン」や「コツ」なんて覚えられるのか、はなばだ疑問に思います。 やはり、教育というものは、プログラムから学ぶのではなくて、人格から転写され、それが消化されて個性となるのではないでしょうか。 教科書だけでは子供は育ちません。それを教える「人格」が必要だと思います。 標準化された現代社会では、そうした「つながり」を失ってしまったので、日本社会が空洞化してしまったと思います。方法ばかりで目的のない社会です。 いったい、何に向っているのか分からない社会です。 話を戻しますが、標準化、言語化は、良いとか悪いとかの問題ではなく、スキとかキライとかの問題でしなく、たんなる方法論としての認識で進めるべきでした。 ところが、標準化、言語化できないものを「排除」したのが、そもそもの大きな誤りだと思います。それは、それで残しておくべきでした。 それを説明することは難しいのですが、たとえば、音楽を楽譜に沿って演奏するにしても、演奏者の個性が発揮されるから、芸術として楽しめるものだと思います。機械的に演奏してしまうのでは、感動も薄れてしまいます。 しかし、規格化されたシステムの中では、誤差が大きいことは、「不良」です。したがって、「個性」までもを「不良」として「排除」してしまったのが、標準化社会の大きな誤りだと思います。 愚昧な小生が、悪文を連ねて、はたして佐為様に理解してもらえたか、自信がありませんが、小生が、けっして標準化を卑下したり嫌っているのではないことをご理解いただきたいと思います。 |
あらま様 ご意見拝見しました。 おっしゃることに異議はありません。 ただですよ、本来の標準化というものと、現実に行われている稚拙なパターン化を一緒にしてはほしくありません。 ハウツウだけではだめ、マニュアルだけではダメとおっしゃるとおりですが、同時にハウツウも大事、マニュアルも大事なのです。教科書だけでは子供は育たないのですが、教科書なくては子供は育ちません。 前回あらま様は「ISO は没個性化」と書かれました。今回は企業理念も規格化、標準化しているとおっしゃる。そのとおりです。しかし私はそれは本来のISOではないし、あるべき企業理念でもないと考えます。 そもそもISOマネジメントシステムは企業の文化、風土、事業環境に応じてユニークでバラエティに富んだものであるはずなのです。それを規格の意図を知らないアホコンサル、バカ審査員、能なし事務局が本来のISOと似てもいない非なるものにしてしまったのです。それを私が過去6年も糾弾していることはよくご存じでしょう。 あらま様が感じていることはそのとおりなのですが、だから標準化は・・とか、ISOは・・とおっしゃらないでくださいな 私は標準化をこよなく愛し、ISOを溺愛(?)しているアホな男なのですよ。 そしてあらま様が感じているように、標準化を貶め、ISOを貶める輩を排除しようと頑張っております。 |
うそ800の目次にもどる