山田が環境保護部に異動して2週間ほど経つ。異動直後に八重洲ブックセンターでISO14001規格の対訳本を買い求め、それから毎日通勤電車の中で読み返している。対訳本は小さいから車中で読むには便利だ。
もちろん会社には1996年版と2004年版のISO14001対訳本もJIS規格票もあるのだが、山田はこういうものは自分のお金で買わないと真剣に読まないということを知っていた。 しかしこんな冊子が3000円もするとは、日本規格協会は独占企業で暴利をむさぼっていると苦々しく思った。せめて工業標準化委員会のウェブサイトをプリント可能とすべきだ。我々は納税者なのだから。 |
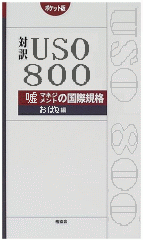 対訳本を読んでいて重要と思ったところにはマーカーを引き、一読して分からなかったところには解説本や自分なりの解釈を書き加えたりしている。そして余白が少ないときはメモを張りつけたりしている。
対訳本を読んでいて重要と思ったところにはマーカーを引き、一読して分からなかったところには解説本や自分なりの解釈を書き加えたりしている。そして余白が少ないときはメモを張りつけたりしている。そういえば何年前だろう、外部の商法の講座に行った時に講師が商法全文のプリントを受講者に渡して講習中に大事だと思ったところにマーカーを引けと言った。それから1週間大事だと言われたところにマーカーを引き、覚えていないところに色を変えてマーカーを引き、間違えたところにはまた色を変えてマーカーを引き、講習が終わる頃にはその70ページはあるプリントはマーカーやら書き込みやらで真っ黒になった。そのおかげで教えられたことはほとんど覚えた。その時は。
やはり自分の金で買って書き込みをして汚くすることが習得の秘訣なのだろう。ISOの対訳本も書き込みだらけになって読めなくなったら新しいものを買おうと思う。その時は書き込みしなくても自家薬籠となっているだろう。
しかし、対訳本を読めば読むほど平目さんのISO規格の説明とか、解説本に書かれていることと、ISO規格本来の目指すところは違うのではないかと疑問を感じてきた。ISOをやさしく解説すると自称している解説本ほど著者の思いが強く出て、規格を素直に読んだ意味とは異なっているように思える。
そして今会社でISOの活動と称しているものと、ISO規格が目指しているものとは相当ずれているのではないかとも感じるようになった。「どこが?」と言われるとうまく言い表せないが、そもそもの出発点から間違っていたのではないかと思う。過去に平目さんが社内に発信している通知文などに「ISOのため」とか、「審査のため」という言い回しがあるのが非常に気になる。いやそういう言い回しに嫌悪を感じるようになった。
いったい当社にとってISO14001認証とは何が目的で、認証にどういう意味があったのだろうか?
数日前に過去の活動記録を読んでいた時に、ISO認証提案の稟議書を見つけた。それには、当社の工場は20世紀から認証しているが本社が認証していないために、日経環境経営度が低い評価となっていると思われることを冒頭に挙げていた。
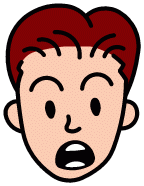 そして認証の効果として、日経環境経営度を向上させブランドイメージをあげること、また本社でISO認証すれば紙ごみ電気の費用削減が年間1000万円くらい期待できること、グリーン調達が当たり前の時代になるだろうがそのときマイナス評価を避けられることをあげている。
そして認証の効果として、日経環境経営度を向上させブランドイメージをあげること、また本社でISO認証すれば紙ごみ電気の費用削減が年間1000万円くらい期待できること、グリーン調達が当たり前の時代になるだろうがそのときマイナス評価を避けられることをあげている。費用として社員800人のオフィスなので審査費用を年180万、事務局の人件費として年間1000万、審査やISOのための活動の社内各部門の負荷を2000万と見積もっていた。山田はこれを読んではじめて知ったが、毎年ISOのために社外・社内費用が3000数百万円もかかっているのだ。
それに対して会社はどのくらいの効果を得ているのだろうか?企業であるから当然それを回収しなければならない。日経環境経営度は認証の効果かどうかは不明だが、それ以前より順位を30ほど上げている。PPC紙使用量削減を見ると一人当たり年間800枚削減、年間65万枚で約250万円である。電気と一般廃棄物処理はビル管理会社が一括処理しており、減ったとしても家賃は変わらない。もっとも削減したとしてもせいぜい数百万だろう。社外に対するイメージ改善効果、社員に対する心理的効果などどのように把握するのかわからないが、どうも投入した費用を回収しているとは思えなかった。
そもそも紙削減をISO活動の効果とするのはおかしいのではないか?現場の社員が改善活動をするように、本社だって無駄排除や効率向上に努めるのは社員の本分のはずだ。もちろんISOはそういう活動を推進するためのツールではあるだろうが、そんな当たり前のことにISOを持ち出さなくてもできるだろう。年間3000万もかけて紙削減の効果を計上すること自体みじめな話だと思う。
お断りしておく、 私が今勤めている会社はここに書いてあるようにレベルが低くない。だけど私はあちこちの会社を見ており、ここに書いたようなものじゃなく、事務局派遣業におんぶにだっこというところも知っている。 嘆かわしいことだ
|
山田も地球環境問題が重要であるとは認識している。地球温暖化が真実か否かなんてことは自分の知識では判断付かない。学者だっていろいろな意見があり、まだ科学で証明されてはいないらしい。環境は予防原則が絶対の権力を持っているように思える。
しかし企業が事業を行って利益をあげ、社会に貢献し、永続していかねばならないことは事実であり、社会の動きに合わせて経営を進めていかなくてはならないのも事実である。
それに地球温暖化が事実であろうと間違っていようと省エネを推進し、環境配慮の製品を供給することは社会に貢献するし、それは企業が存続するための必要条件である。
紙ごみ電気なんて幼稚なことは話にならない、論外だ。しかし、製品やサービスなど事業本来において環境を配慮するというのも腰が引けている。というか本腰を入れていない。事業を行っていくには損益の他に、労働安全、人権保護、社会貢献と同様に環境というものが必要条件であるというだけのことだ。トリプルボトムラインとはまさにそれだ。環境というものを特別なものと思うことこそ時代遅れなのだろう。山田はそこまで考えがたどりついた。
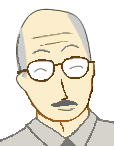
「山田君、ISOって何だと思う?」
始業早々に平目が山田に話しかけてきた。
「会社の仕組みの要件を決めたものと言えば良いのでしょうか?」
山田は平目の意図を読めずに無難な一般的な意味で応えた。
「山田君、ISOとは会社のルールを作ることなんだよ」
「はあ?」
「作る規則はお客様の要望や期待に応えるためのルールだったり、環境に対する影響を抑えるためのルールだったり、いろいろあるけど、社内のルールを作るということが僕らの仕事なんだ。僕の作ったルールで本社や工場の大勢の人たちが動いていると思うと、責任の重さを感じてぞっとするよ。いや、感動というのかなあ、わくわくするような緊張感だね」
山田は疑問を抑えられずに口をはさんだ。
「平目さん、ISOを認証する前から当社には会社規則というのがありますよね。人事管理、経理処理、情報管理から営業などなど業務の全分野を網羅しています。当社の昔からの会社規則でISO規格を満たしていなかったのでしょうか?」
「山田君、ISO規格は規格項番ごとの手順を要求しているのだよ。だからISO対応の会社規則を僕は何本つくったことか・・」
平目は昔を懐かしむような眼をした。
「平目さん、従来からある会社規則だけでは不足で新しく制定した会社規則とはどんなものがあるのですか?」
平目は相好を崩した。自慢話をしたくてたまらないようである。
「ISO規格で一番難しい項番て何だと思う。そうだよ、環境側面さ。環境側面を特定し決定する手順など以前の会社にはなかったから私がいちから作ったものさ。それから法規制を調べる手順もある。環境コミュニケーションとか、環境教育とか、環境文書管理規則、環境記録管理規則、環境内部監査規則、マネジメントレビュー規則、指折り数えると20位あるかなあ〜」
平目は本当に指折り数えながらそう言った。
「山田君、ISOとは会社のルールを作ることということは真理だね。実はね、僕はISOのメルマガをとっているのだけど、それにも『ISOの活動とは、結果的に社内のルールを作っている』ことと書いてあったのさ。」
山田は平目の話がどうもおかしいと感じた。平目の価値観はどこか一般社会の常識とはずれているのではないだろうか?あるいはISOの常識が一般社会の常識とずれているのだろうか?
「平目さん、ISOの活動って存在するのでしょうか?私はそういうものは存在しないと思うのです。まず、『ISOの活動』って言葉の意味がわかりません。 営業活動、生産活動、QC活動、5S活動、安全、サークル活動、地域貢献活動。営利目的か否かを問わず、これらは理解できます。 でも『ISOの活動』って、いったいなんでしょうか?
ISOのために規則を作ったとおっしゃいますが、今まで必要がなかっただけということはないのでしょうか?そして今も必要ではないのかもしれません。ISO規格でも文書化の必要性を組織の規模や活動、プロセスとその相互関係の複雑さ、要員の力量によって異なるとあります。ISO規格の通りに会社の規則が必要ということはないのではありませんか?」
平目の眼の色が変わった。
「山田君、君は何年この仕事をしているんだね?そういうことは、もう少し経験を積んでから言ってくれたまえ。僕はあと3月しかいないんだよ。後輩がこれじゃ引退できないよ」
山田は口を閉じた。平目の言うとおりだ。平目は何年もの間ISOの中心として活動してきたことは事実だ。
ただ、ISOが会社の規則を作ることという発想はどう考えても変だなと思った。
本日の検討課題
・ISOってルールを作ることなのだろうか?
・過去から存在している企業においてそれまでのルールで不足なのだろうか?
・ISO対応のルールが必要なのだろうか?
おお!ぶらっくたいがぁ師匠から下の句が届きました(09.10.18)
山田は、平目が聞きかじってきた「ISOとはルールを作るものだ」という話をきっかけに「ISOの活動」とはそもそも何なのかという根っ子の部分に疑問をもつようになった。引き継ぎを始めてからずっと山田が感じる違和感の正体が、そこに潜んでいるような気がしたからだ。また、ヒントになるかもしれないと思い、山田もそのメルマガを講読してみることにした。 さっそくメルマガが送られてきた。今回の内容は、「内部監査はプロセス監査で進めなければならず、そのためには部門長の協力が必要であり、部門長がISOを正しく理解して経営に活かすことが肝要だ」というものだ。また、それに役立つ書籍の購入を勧めるものだった。 「ああ、ここでも『ISOを経営に活かす』とある・・・。でも部門長はもともと経営陣の一員だし、認証取得以前から立派に部門を切り盛りしてきた。 いまさらISOを知らないと何か経営に大きな支障があるのだろうか。。」 山田はそうつぶやき、ここ数年間のことを思い出していた。 鷽八百機械工業では、いわゆるカミ・ゴミ・デンキの活動というものは一定の区切りがついたものもあるし、進行中のものもある。 前者はコピー用紙の節減であり、後者は電力削減だ。 コピー用紙の節減というのは一種の躾でもあるので、裏紙使用を徹底するというルールが定着するまでそれほど時間はかからなかった。それでも未だに用紙サイズ別の使用量を月末に事務局に提出することになっていて、煩わしいことこの上ない。 営業部の担当であった山田は、売り上げの締めといった仕事に追われて提出を忘れがちで、平目から注意されることもあった。 しかし、今度からは自分がその記録を集める立場だ。平目の話では、出し忘れどころか意図的に出さない部署もあるらしく、気が重い。現に平目が内線電話でこんな会話をしているのを聞いた。 「あのね、提出期限をもう一週間も過ぎてますよ。しかも2ヶ月連続です。 明日までに出さなかった場合は『是正処置勧告書』を発行しますからそのつもりで」 電力削減は進行中だが、正確に言うと達成できた年度もあればできなかった年度もあるので、終わりが見えない。昨年度は世界不況の直撃を受けて生産量が激減したために余裕で達成してしまった。おそらく今年度も達成できるだろう。 そういえばここに配属される直前、顧客クレームへの対策の相談で製造課長の鈴木に会ったとき、こんな会話をしたことを思い出した。 山田「製造は電力削減の主担当だから、さぞやプレッシャーがかかるでしょうね」 鈴木「最初はそう思ったさ。でもね、要領だよ、要領。」 山田「え? どういうことですか?」 鈴木「要はムリのない範囲で毎年少しずつ削減していけばいいのさ」 山田「そんなことコントロールできるんですか?」 鈴木「簡単さ。目標の設定を緩めにしておくだけだよ。ホンキでやれば1年で達成できるんだけど、それを3年ぐらいかけて少しずつやればいいんだ」 山田「え? そんなことでいいんですか?」 鈴木「これはね、『継続的改善』といってISOの基本原則なんだ。キミも規格要求事項の勉強をすればわかるよ。ボクは認証取得するときに猛勉強したからね。けっこうISOに詳しいのさ」 そのときはそんなものかなと聞き流した山田だったが、ここ数日の経験を通じてどうも違うんじゃないかと思うようになった。 山田は、平目や鈴木の話を整理してある推論を立てた。 つまり、彼らがいうISO活動とは「有形無形を問わず、ISO認証を取得・維持するために審査員に見せる必然性から作られたバーチャルな仕組み。あるいはその周知活動、文書又は記録」ではないか。 これを元に彼らの言動を振り返ると見事に全てが当てはまった。なんのことはない。実務には関係のないものを仕事のフリをしてこなしていただけだったのだ。 電力削減はコストを下げて利益を出すためであって、つまりは儲けるためだ。 そんな活動がチンタラと3年もかけていいはずがない。それが「継続的改善」とやらであれば、それを強いる規格要求事項の方がおかしい。 そう考えればなんだか件のメルマガも胡散臭く思えてきた。世の中から病気がなくなれば製薬会社が困るのと同じで、もし本当に「ISOの活動」が各企業からなくなってしまったらメルマガの発行元であるISO教材の会社はどうするんだろう? だいたい、もともと審査のために作られたバーチャルなものを経営に活かすというのは、スタートからして間違っている。そんなものはさっさと捨ててしまって、儲けるためにどうすればいいかを考えた方が手っ取り早いに決まっている。 よし、今度またJ○×の田井さんに電話して聞いてみよう。そして、製造課長の鈴木とも話をしてみよう。そんなことをしたら次の審査で困るとか言い出しそうだが、わかってもらえるだろう。 「ん? 待てよ。製造課長のところに行ったのは。。。あ、しまった」 山田は、この前のクレーム対策を顧客がどう承知したかの報告書を品証課に提出するのを忘れていたのだ。山田はあわてて品証課に向かった。 山田「多胡課長、すみません。先日の顧客クレームの件ですが」 多胡「ああ、山田君。あれならもうキミの後任者からもらったよ」 山田「そうですか。よかった。では」 多胡「まあ、せっかく来たんだ。ゆっくりしていきなよ。相談したいこともあるし」 山田「え、相談ですか?」 多胡「そう身構えるな。たいしたことじゃない」 山田「はあ」(ホントかな。この人、論理的に話してくるから苦手なんだよな) 多胡「実はね、平目さんには前から相談しようと思っていたんだが言い出しにくくてね」 山田「何でしょう」 多胡「コピー用紙の裏紙使用ルールなんだけど、あれ、廃止できないか?」 山田「え? どうしてですか?」 多胡「あれが原因で製品不良が起きているんだ」 山田「どういうことですか」 多胡「製品の製造手配をするとき、手配書に図面を添付するだろ。新製品じゃない限り、設計課は他の類似図面を引用してそれを元に製図する。 出図前のレビューのためにテストプリントするから、もし誤りがあればそれを修正して完成させる」 山田「はあ」 多胡「そうすると、完成図面と修正前図面の両方が同じ紙の裏表にプリントされることだってある。製造課は間違えて修正前図面を見て作業してしまうってわけだ」 山田「なるほど。でも裏面には大きく×を書くルールになっているから、間違えることはないはずですよね」 多胡「キミ、現場を甘く見ちゃいかん。忙しいときは忘れることもあるし、間違えて正の方に×を書くことだってある。こんなミスを根絶するには裏面使用を禁止するのが確実だ」 山田「いや、しかし。おっしゃることはわかりますが、裏面使用ルールはEMS活動の目玉みたいな存在ですから簡単に廃止するわけには・・・」 多胡「EMS活動だって? じゃあ、QMS活動はどうでもいいのかね。EMSの方がQMSに優先するとでも言うのかい? いったい、EMSとQMSのどっちが会社にとって大事なんだ。だいたいね、私は品質の管理責任者だ。前の9001審査のとき、審査員からこの問題を指摘されて困っているんだ。そのときは何とか交渉して観察事項で済んだけど、今後指摘されたらCARが発行されることは間違いない。責任を取らされるの私なんだよ」 山田はぐっと詰まってしまった。と、同時にはっとした。 無意識のうちに自分もEMS活動などという実態のないものに染まっている。 それだけじゃない。原材料やエネルギーの削減は環境負荷低減でもあるし、ロスの削減でもあるから品質の活動とも一致する。でも、今回のように相反するとき、どう判断すればいいんだろう。あちらを立てればこちらが立たずではないか。 平目さんに相談したところで答えは決まっている。環境の管理責任者として自力で考えなければならないのか、それとも品質管理責任者である品証課長の多胡さんと相談しつつ、会社にとって何が最適なのかを考えればいいのか。 だいたいISOのルールとは会社にとって何なのか? 必要なものなのか? もし認証を返上したとしたらどうなるのか? 帰りの廊下をゆっくり歩きながらあれこれ考えを巡らすうちに山田はある結論に至り、決意を固めた。 「よし。それでいこう」 本日の検討課題 ・ISOの活動って、何だろうか? ・品質と環境とで相反する問題が生じたとき、どうすればいいのだろうか? ・あなたが山田君なら、今後どうするだろうか? |
ぶらっくたいがぁ師匠 毎度ありがとうございます。 世の中のISOの何割が意味のないISOゴッコなのでしょうか? そういう会社のためにISO教材会社が存在しているようですね。本当はISOなんて仕組みが存在するわけがありません。会社の仕組みがまずあって、そのシステムを改善していくときのツールというか改善ポイントとしてISO規格を使うはずです。 紙ごみ電気が重要な環境側面という組織があるのだろうか?
オフィスの活動が重要でない組織があるはずがない。だからその活動そのものが環境側面じゃないか。 裏紙を活用する代わりに、裏紙禁止して事務能率を向上し時間外を禁止した方が、人事管理、人件費管理、機密管理、そして環境に最高に貢献するはずだ。 オフィス省エネを進める人たちが、エアコンの制御、自然光の利用、PCの省エネ設定などばかり考えて、事務能率の向上を考えず、時間外規制を思いつかないのは、アホというしかない。 京都議定書達成は遠いぞ!
|
うそ800の目次にもどる