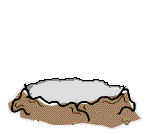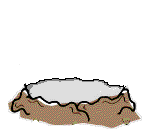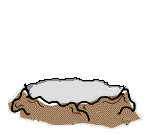15.11.05
*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。但しここで書いていることは、私自身が過去に実際に見聞した現実の出来事を基にしております。
審査員物語とは三木は潮田取締役と肥田取締役に客先からの苦情調査を指示されてから、過去のクレームや審査後のアンケートをひたすら読んでいる。読むだけならとんでもなく面白い読み物なのだが、そのとんでもない事態の対策を考えなければならない立場としてはかなりつらい。
まず審査後のアンケートを読むと問題が非常に多い。それにしても似たようなものがしょっちゅう発生している。つまり何ら根本対策をしていないということだ。
それも一番多いのが態度とか礼儀に関することだ。礼儀作法と言ってもお辞儀の仕方とか名刺の交換なんてことではなく、若い社員を下に見た発言、たとえば若手を小僧と呼んだとか、経営者にため口を叩いたとか、まあとんでもないことが多い。
そのほかに余計なお世話を語っているのも多い。ISO14001審査に行って、ごみの分別をしっかりやれば売り上げが伸びるなんて持論を語ってほしくない。聞く方はそれこそ体を張って日々の売り上げを出そうとしているのであり、実行可能で実効のあることならともかく、浮世離れした話を聞かされても精神衛生上悪いだけだ。
以前、三木が環境側面とか環境目的についての規格解釈がおかしいと考えていたが、それ以前というか社会常識、ビジネス常識的なことで問題となっているものがほとんどだ。内容にもあきれるが、対策の手を打っていないというのも問題だ。
過去2年分の審査後のアンケートを一通り読んで数日考えてから、三木は潮田取締役と住吉課長を集めた。
「十日ほど過去のアンケートを読んでみました。とりあえず考えたことについて相談したいのですが」
| ||||
「さすが三木さんだ、もう問題とその原因がわかりましたか。対策案もできているのでしょう」
| ||||
「そんな簡単ではありませんよ」
| ||||
「どうぞお話を進めてください。」
| ||||
「お借りした過去の審査後のアンケートを拝見しまして、予想に反してたくさんのご意見をいただいているということがわかりました。それで疑問を持ったのですが・・・」
| ||||
「はい、なんでしょうか?」
| ||||
「まず最初に疑問を持ったのは以前、潮田取締役とお話しした時は、審査後のお客様アンケートにはほとんど苦情がなく情報を収集しようとしてもデータがないというお話でした」
| ||||
「はい、それが」
| ||||
「住吉課長さんのお話ではお客様からの苦情が多々あり、営業担当者はその対応にだいぶ手を取られているとのお話でした。この二つは矛盾していますが、お二人の間のコミュニケーションがとれていないのか、それとも事実と異なるのか、そこを確認したいですね」
| ||||
「ええと苦情はほとんどないと聞いている。住吉課長、そこんところはどうなんでしょう?」
|
「まあ営業部員の手が取られて営業活動に支障があるというのは少し言い過ぎかもしれませんね」
|
|||
「いや住吉課長さん、ここんところは正直というか事実をお話しいただきたいと思います。住吉課長さんとお話しした時は営業部5名のうち2名の負荷になっているというお話でした。それが多少大げさかどうかはともかく、私が拝見した審査後アンケートには100件中5件くらい苦情がありました。それが多いか少ないかはともかく内容をみると同じようなものが偶発的に起きています。そのほかに電話やEメールでのご意見もあるということでした。その情報を上に報告するというのは必要ではないのですか」
| ||||
「住吉課長、私はそういった報告を見てはいないがね」
|
「うーん、あまりネガティブな報告ばかりではいけないと思いまして、問題はすべて私の決裁で処理しておりまして・・・」
|
|||
「実務をどのように処理するにせよ、真実を担当役員に伝えるべきではないですか」
|
「まあ役員の方に些事でお手を煩わすこともないと思いまして」
|
|||
「まあいろいろとお考えはあるでしょうけど、 話を変えます。ともかく現実には審査後のアンケートに相当数の苦情もしくはご提案が書いてありました。重大問題と判断されることについては従来から住吉課長が対応されてきたとお聞きしました。しかし対策がどうもモグラ叩きのように思われます」 |
「モグラ叩きとは?」
|
|||
|
モグラの上にマウスのポインタを置くとモグラが消えます。
いやはや、こんなの絵を作るのに30分もかかってしまいました・・・ORZ | ||||
「現象の対策だけで原因について対策していないために、似たような問題が再発しているということです」
| ||||
「なんかISOでいう是正処置をしていないように聞こえるな」
| ||||
「残念ながらまさしくその通りに思います」
| ||||
「住吉課長、その住吉さんが今までしていたってどんなことなんだい?」
| ||||
住吉はしばし頭を振ったりあちこち見まわしたりした後、話したほうがいいのかと考えたようで話し始めた。 |
「まず潮田取締役に報告しているのはアンケートに書かれた一部でして、正直言いまして苦情と言えるものはかなりあります。アンケートでくる苦情のほかに、電話やメールで直接私どもにご意見といいますか苦情といいますか対策を要求されるものもかなりありまして・・・その中でこれは対策しないとまずいと私が判断したものについては客先を訪問することも含めてお客様への謝罪をしてとりあえず納得していただいております」
|
|||
「そのようなものはどのくらいあるのかな?」
|
「月に数回は状況確認やお詫びに客先に出向いています。電話やメールでお詫びをしてすませてるものは相当あります」
|
|||
「私は苦情全体で100件に2・3件と聞いていたが」
|
「まあどこから問題かと考える基準次第ですが、毎月対応しているものは10数件というところでしょうか」
|
|||
「ウチの認証件数はQMSとEMS合わせて3000くらいだろう。とすると月平均250件だから、その内10数件に問題があるとすると5〜6%の苦情があるわけで、そりゃ多いんじゃないか、問題だな」
| ||||
潮田は首の後ろで手を組んで斜め上を見上げる。考え事というか困ったときの癖のようだ。 しばしの沈黙ののち潮田が口を開く。 | ||||
「ええと住吉課長、先ほど三木さんがモグラ叩きと言ったけど、そのさ根本対策というか再発防止策はどうしているのかな?」
|
「そのう、私どもの業務はISO審査ですから品物を売ったりなにかを貸し出したりしているわけじゃありません。提供するのはISO審査ですから審査員の対応とか発言によって問題が起きているわけです。つまり対策は審査員に対する教育とか指導ということになりますが、我々営業は審査員に対してああせいこうせいと言えるわけではありません。ですから営業部門のできることは、お客様へのお詫びとお客様に納得していただくことしかありません」
|
|||
「それっておかしくないか。審査員の言動や行動によって問題が起きているなら、審査員に直してもらわないと問題は収まらないよね」
|
「しかしですね、私どもが審査部に対して依頼しても動いてくれないんですよ」
|
|||
「それは営業部長が審査部長に言えばいいことじゃないの」
|
「あのですね、潮田取締役は営業部長ですから少人数の営業部員にいろいろと指示命令をすることに躊躇ないと思いますが、審査部となりますと出向元が多々あるわけでして、出向者にしろ転籍者にしろ出向元からきている取締役の指示でなければ言うことを聞きません」
|
|||
「はあ、そうなんですか」
| ||||
「今はそうかもしれませんが、そういったことを直していかないと是正処置というのはできないんじゃないですか」
|
「そうはおっしゃっても、そこがなかなか難しいところでして」
|
|||
「つまり過去ずっと問題が起きるとお詫びともみ消しの対症療法で過ごしてきたというわけか」
|
「そう決めつけないでください。私の責任ではありません。このような対応は私の前任者のときからでして、それとこじれてしまったりしますと、もうなかなか収まりがつかないこともありまして」
|
|||
「こじれるって? お客様と?」
|
「いえ社内的にですが」
|
|||
「それもおかしなことだよね。ところで、そういったことは会社のルールで決まっていないのか?」
| ||||
「あの非常に初歩的なことですが」
| ||||
「なんですか非常に初歩的なこととは」
| ||||
「当社は認定機関から認定を受けているわけです」
| ||||
「当然だな」
| ||||
「認定を受ける基準は過去からいろいろと変遷はありましたが、現在はISO17021という規格がありまして、国内的にはJABMS200というものに展開されていて、それを満たしていることが必要です」
| ||||
「おっしゃる通りだ、確かに初歩的というか基本的なことだな」
| ||||
「その規格では認証機関は苦情処理の手順を定めなければならないことが決めてあります。つまり当然ですが当社は苦情処理の仕組みがあって、その仕組みで運用していることを示さないと認定審査で不適合になるはずです」
| ||||
「なるほど、なるほど。となると今まで苦情があったときその手順通りしていなかったということになるのか」
| ||||
「私は現実がどうなのかは存じませんが、どこかおかしいとしか思えませんね」
| ||||
「住吉課長、そのへんはどうなっているのかね?」
|
「ええとですね・・・・認定審査は肥田取締役のご担当かと」
|
|||
「住吉さん、肥田さんを呼んでくれないですか」
| ||||
数分後、肥田取締役が現れた。 肥田が座ると潮田が口を開いた。 | ||||
「肥田さん、認定審査のとき苦情関係のやりとりってどんなですか?」
| ||||
「どうってことはないよ。ウチの手順の確認と前回審査以降の状況の確認、苦情処理が完了しているかどうか」
| ||||
「認定審査で見せている苦情ってどれくらいあるのですか?」
| ||||
「潮田さんのほうが詳しいと思うけど、ええと記憶だが年に7・8件あったように思う」
| ||||
「うーん今ね、苦情が多いという話をしていたのですが認定審査で示している苦情というのはどれを対象にしているのでしょう」
| ||||
「ええ、私は潮田さんというか営業の帳簿にあるものを提示しているだけですよ」
| ||||
「住吉さん、営業の帳簿って?」
|
「それはあれですよ、私が潮田取締役に報告しているものです」
|
|||
「つまり当たり障りなく作文したものということか」
|
「そういわれると困ります」
|
|||
「状況がわかりませんが苦情は二重帳簿だったというわけですか」
| ||||
「認定審査でぼろが出なかったのだろうか」
| ||||
「台帳からトレースしていっても矛盾がでるはずがありません。認定審査員側が認証されている企業の苦情を知っていて、それを基にトレースしなければボロは出ないでしょう」
| ||||
「なるほど、つまりウチの苦情は住吉課長がすべて適当に処理していたというわけか」
|
「潮田取締役、そんな言い方はないでしょう。私がこの方法を始めたわけじゃありません。先代の柴田取締役は須々木取締役たちが考えたことで、私は指示に従って今までしてきたのですよ。そもそもは苦情がかなり多いので、そのまま見せたらまずいと考えたらしいです」
|
|||
「わかりました。ともかく二重帳簿ではしょうがない。なんとか軟着陸しなければならないな。それというのも苦情が多いなら減らす方策をしなければならない。 肥田さん、苦情については三木さんのご協力を得てまとめますから、その対策について特に審査部、審査員に対する指導をお願いすることになります」 | ||||
「審査員の負担になることなのですか?」
| ||||
「どうなるか今は何とも言えませんが、まあ過ちは正さなくてはならないでしょう」
| ||||
肥田が去った後、潮田取締役と住吉課長そして三木は議論を続けた。 | ||||
「住吉課長さん、まず過去1年間でもよいですが、苦情や意見などを全部まとめて、それらの対応をどうしたのか、そのうちどのような判断基準で苦情の帳簿というか台帳に載せたのかということをまとめてもらえませんか」
|
「わかりました。しかし正直言いまして過去の苦情全体は正確にはわからないのです」
|
|||
「それはどうして」
|
「苦情や不具合に対してはあとあと問題にならないように個々に対応してきたつもりですが、そのいきさつは記録に残していないのです。つまり」
|
|||
「気持ちはわかるが、出張記録とかメールなどをあさればおおまかなところは把握できるだろう」
|
「わかりました」
|
|||
「それとさ今日以降、すべての苦情や異議その他の記録は一覧できるようにすること、これは命令だ。それから一段落したら今までの処置についての処分を考えたい」
| ||||
●
三木は考える。苦情というものの定義だが、考え方でどうとでもなるのかもしれない。JABMS200では「認定機関(本協会)又は認定された機関の活動に関し、個人又は組織(個人と対比されるすべての組織体)が回答を期待して行う不満の表明で、異議申立て以外のもの。」と定義されている。● ● (2015年版もこの物語の2012年時点でもJABMS200での定義は同じである)
ともかくお客様からの苦情、不満、改善要望なんでも収集して、不満の解消を図らねばお客様が逃げてしまうことは間違いない。 ISO規格では仕組みを作れ、仕組みに基づいて運用しろ、問題があれば是正しろと語っているが、およそそもそもの精神とかけ離れた当社の実態では救いがないと思う。 現実の審査では、企業の是正処置が徹底していないとか考え方が当面の処置にとどまっているとか上から目線で語っているのだから世話はない。 まずは住吉課長が実態をまとめたらまっとうな仕組みに見直し、それをきちんと運用することだろうと思う。当たり前のことを当たり前に実行する、それができなければ人様の会社に行って講釈を語るのはおこがましい。 しかしと三木は思う。 なぜ客から不満苦情があっても対策しないのか。以前の住吉課長の話では不具合を指摘したら契約審査員がよそに逃げてしまうとか言っていたが、そんな質の悪い契約審査員ならいない方が良いのではないのか。あるいは審査員の人件費を薄めるにはどうしようもないのだろうか。 仮に費用構造から審査員の質が決まってしまうというのならそれもおかしなことだ。 それとも各出資会社からの出向者が融合しないことによる弊害であるならそれを是正すべきだろう。業界団体系の認証機関ということで通常の企業活動が阻害されているのならそれを直さなければならないだろ。 この会社そのものが審査をすることが目的じゃなくて、出資会社の人材活用が目的なら話は支離滅裂だ。そして現実はそこが問題なのだろうという気もする。 今後対策を決めて潮田取締役あるいは肥田取締役が号令をかけたとして、皆がそれに従うのだろうか。それも甚だ疑問ではある。 三木には八方ふさがりのように思えてきた。こんな仕事を引き受けたのは選択を誤ったかと苦笑いした。 |
お断り
私は企業側からしかISO認証制度に関わっていないから、認証機関の中でどのような顧客の苦情対応をしているのか知らない。また私は認定審査というものを見たことがありません。実際にどの程度の厳しさなのか、細かさなのかまったくわかりません。
しかし私の20年にわたる経験から企業から苦情を入れても特段対策もされなかったという事実があり、その認証機関の認定審査結果が公表されたのを見ていると苦情処理について問題となっていないという事実を考え合わせると、認定審査で苦情処理をよく見ていないのか、認証機関が苦情処理をごまかしているのか、いずれかであろうと思います。
本日の物語は審査に対する企業の苦情・不満が解消されず、いつまでもおかしな審査が行われているのはなぜなのか愚考したのであります。ですから事実と異なることは重々承知、もしそのへんの詳細をご存じのお方はぜひともご教示願います。
ISO17021に基づいて認定審査が行われているにも拘らず、過去20年間異常な認証審査が行われていてそれが改善されていないのは、どうしてなのか不思議でならない。
審査員物語の目次にもどる