15.07.09
*これはISO14001:2015のDISを基に2015/7/2に書いたものである。
今後、改定や正式版が出れば見直ししたいと思うが、しないかもしれない。そこのところはご了解してお読みいただきたい。
本日は、継続的改善なるものを考えたい。
ひとつは2015年改定は変わったのかということと、もうひとつはそもそも継続的改善とは何だろうという根本的なことである。
ではいってみよう。
初めは2015年改定は何が変わったのかである。
まず2004年版の継続的改善の定義では、
組織の環境方針と整合して全体的な環境パフォーマンスの改善を達成するために環境マネジメントシステムを向上させる繰り返しのプロセス。 recurring process of enhancing the environmental management system in order to achieve improvements in overall environmental performance consistent with the organization's environmental policy.
(ISO14001:2004より)
|
では2015年版ではどうなのでしょうか?
パフォーマンスを向上させるために繰り返し行われる活動 recurring activity to enhance performance
(ISO14001:2015DISより)
|
- プロセスと活動は違うのか?
英単語も違うのだから、きっと意図するところも違うと推察する。ではどう違うのだろうか?
「プロセスとはインプットをアウトプットに変換すること(2015 3.26)」と定義されている。
アクティビティは規格では定義されていない。アクティビティはプロセスの構成要素と考えればよいのだろうか?
とすると継続的改善とは、一気通貫のプロセスでなくて、コマ切れのバラバラであってもいいよということなのだろうか?
どうしてプロセスからアクティビティになったのか私が知る由もない。
- 環境パフォーマンスの改善を達成するために環境マネジメントシステムを向上させることと環境パフォーマンスを向上させることは同じか違うのか?
もちろん違うだろう。パフォーマンスは測定可能であるが(定義3.12)、システムは相互に関連する要素の集まり(ISO9000:2000 3.2.1)だから測定可能以前にエフェシェンシィを定義しなければ話にならない。ということは2004年版ではシステムを改善しましたといえばあとは立証も否定もしようがなくOKになったけど、2015年では数値で実績を出さないと不適合となるということだろうか?
では具体的にどのような切り口で継続的改善が求められているのか? 本文中で「継続的改善」という語がつかわれている箇所は、- 5.1リーダシップ
継続的改善を促進することによって、環境マネジメントシステムに関するリーダーシップ及びコミットメントを実証しなければならない。 - 6.1.4脅威及び機会に関するリスク
継続的改善に取り組む必要がある、脅威及び機会に関連するリスクを決定しなければならない。 - 7.1資源
継続的改善に必要な資源を決定し、提供しなければならない。 - 9.3マネジメントレビュー
マネジメントレビューでは継続的改善の機会を考慮しなければならない。
マネジメントレビューからのアウトプットには、継続的改善の機会に関する決定を含めなければならない。 - 10.2継続的改善
組織は、環境パフォーマンスを向上させるとともに、環境マネジメントシステムの適切性、妥当性及び有効性を継続的に改善しなければならない。
中身について考えると、環境パフォーマンスとは省エネなどのように具体的改善を推進することばかりではない。仕事の出来栄えが本来の意味だがISO規格では測定可能な結果である。業務遂行であっても、納期達成率やミス発生率などがパフォーマンスの指標であり、そういったものを向上させることは仕事の本質だろう。
だがそれがISO14001の意図である、「遵法と汚染の予防」につながるか問えばイコールではない。いやイコールどころか重なる部分が非常に少ないように思える。このへんは大いに議論のあるところだ。
これについては後でまた論じる。
- 5.1リーダシップ
- 環境方針と整合して
2015DISでは本文から「環境方針と整合して」が抜けたが、注記に書いてあるから変わらないとみてよいのだろうか?
元々日本語でも形容詞節が長すぎると思っていたが、それを読みやすく分りやすくした程度なのだろうか?
だがシステムの改善じゃない、パフォーマンスの向上だよと言ったところで、環境パフォーマンスではなく遵法と汚染の予防を明確に掲げていないのだから、ISO規格のレゾンデートルはどうなのよという感じだ。
ではもうひとつの切り口に進む。根本的なことであるが、そもそも継続的改善とは何だろうというである。
とはいえ、あまりにも漠然としているので、それに関わる疑問をいくつか考える。
- その1
ISO14001の目的は遵法と汚染の予防である。
改善の対象が遵法と汚染の予防でないのはなぜか?
パフォーマンス一般論では手段とか無縁な指標を改善することになるのでは?
省エネや廃棄物削減は手段であり目的ではない
広い意味の「パフォーマンス」ではなく「環境パフォーマンス」であるとしても、遵法と汚染の予防に限らずなんでもよいことになる。本来なら「まず遵法と汚染の予防を第一優先し、残ったパワーで他のこともしても良い」となるはずだろう。
だが文章を読むと「全ての領域で同時に、又は中断なく行う必要はない」とうことは、遵法と汚染の予防について継続的改善をしなくても規格適合であるということになる。これは少しおかしいと思う。
遵法と汚染の予防については除外できず、かつcontinualではなくcontinuousでなければならないのではないか。まず目的と手段の一致という観点からこれはおかしいぞ

continual 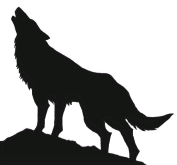 継続的あるいは定期的に何度も発生すること。オオカミが一晩中吠えているような状況。
継続的あるいは定期的に何度も発生すること。オオカミが一晩中吠えているような状況。continuous  時間が経過しても中断せずに継続すること。コンピュータのファンがずっと音をだしているような状況。
時間が経過しても中断せずに継続すること。コンピュータのファンがずっと音をだしているような状況。
- その2
規格作成者にとっては恐ろしい問題提起であるが、ぜひともお聞きしたい。
ISO規格を満たせばパフォーマンスはあがるのか? 上がるという保証はあるのか?
ISO規格を満たしてもパフォーマンスが上がるという保証がないなら、この継続的改善とはいかなる意味があるのか?
『ISO規格の要求事項としていろいろ書きました。でもそれを満たしてもシステムが良くなることもパフォーマンスが上がることも保証できません。ですから皆さんご自身の努力でシステムとパフォーマンスを継続的にあげてください。それを要求します』というなら、それは規格要求事項というよりも、たわごとあるいは願い事ではないのか?
そんなことならすべての要求事項を廃して、パフォーマンが向上した組織を規格適合というとしたら簡単じゃないですか。
本来であれば『わざわざ継続的改善を要求しなくても、他の規格要求を満たせば自動的に継続的改善が図られるのです』と言い切ってもらわないと、ISO14001はそれが書かれた紙ほどの値打ちもないことになる。
ちがいますか?
少なくてもこの質問の回答がはっきりしなければ規格要求を満たす意味はなさそうだ。
「ISO14001の有効性に信頼がおけないので、当社は自社独自の方法で遵法と汚染の予防を達成します」と言われたら、ISO14001を作った世界の英知は赤っ恥です。
しかし現実には多くの企業がそういうアプローチをとっているのは間違いない。
だからこそ認証件数も減る一方ではないのか?
- その3
継続的改善とは定向進化ではないだろう
ひとつ気になったことがある。継続的改善という言葉に何も疑問を感じないだろうか?
生物の進化ということから考えると、継続的改善というものは少し変だという気がする。改善とは物事の出来栄えとか効率と早く仕上げるとかだろうと思う。とするとそれは一定方向に進んでいくように思える。
生物の進化はもちろん突然変異とか遺伝子浮動などによって起きるのだろうが、その結果として進化の方向は一直線ではなくブラウン運動のようにランダムになる。
進化は定まったレールを走るようなものではなく、ランダムなゆらぎらしい。ともかく今では定向進化説は否定された。昔、定向進化という説が唱えられた。進化は一方方向に進むという考えで、象さんは大きくなり、キリンさんは首が伸び続けるという風な考えだ。その後の研究では実際には、過去の化石を調べると象さんは大きくなったり小さくなったりしているらしい。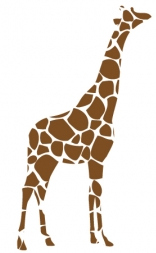
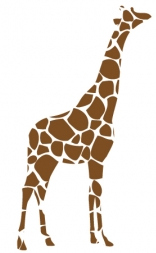

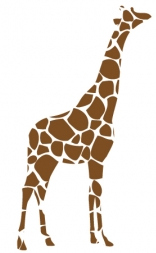

企業におけるシステムも時代とともに変化してきた。それは社会通念の変化、市場の変化などの環境の変化と、コミュニケーション手段の変化、製造方法の変化などの内部変化によって変わってきた。そしてそれは常に一方向に変化してきたわけでもない。インターネット、イントラネットの普及によって中央集権化が進んだが、それも一直線ではなかった。今後、道州制などが導入されれば、自治体の取り扱い事務は大幅に変わるだろうし、それによって情報システム屋は大儲けだろう。
例えばだいぶ前に環境情報システムなんてのが流行りだった。しかし例えばPRTRシステムを考えた時、かっては都道府県ごとにPRTR条例があった。だから全国にまたがる企業でも全社共通のシステムを作るわけにはいかなかった。都道府県によって対象物質が異なり、集計方法も違い、結局それぞれの地域に合わせなければならなかった。その後PRTR法が制定されてからもPRTR条例は生きている県もある。
省エネ法の届出もかっては事業所単位であったが、大震災以降、企業単位とか企業グループ単位での管理と報告に移った。じゃあ事業所単位はなくなったのかと言えばそう簡単でもない。
公害関連は地方分権、更には県から政令市、中核市へと事務が移譲されてきている。システムはそれに合わせなくてはならない。
外部要求が転々と変わり、それによって対応が変わり、改善方向は一方向ではなく、結局外部要求に合わせてかつパフォーマンスを上げたものということになる。それは遠くから見ればまるでブラウン運動にみえるだろう。
なにを言いたいのかと言えば、継続的改善を図らなければならないが、それは定向進化ではなく同じところをグルグル回ることになるかもしれず、あるいはまったく別の場所に飛ぶようなことになるかもしれない。なにか継続的改善という言葉のニュアンスとは違うように思う。
つまり組織であろうと生物であろうと行うべきことは、継続的改善ではなく、継続的最適化とか継続的適応化のように考えている。なにせ生物の世界では生き残るのは強いものではなく適応したものなのだから。
- その4
そもそもマネジメントシステム規格でパフォーマンスが向上するわけがない。
仕事をなすには、固有技術、管理技術、士気が必要だ。いや、そんなことは誰だって知っている。技量がなけりゃものができない。しっかり管理しなくちゃ納期も数量もままならず、混入や紛失もあるだろう。作る人にやる気がなくちゃ仕事をしません。
ISOマネジメントシステム規格とは、その三つをカバーしているわけじゃない。名前からわかるように管理だけが守備範囲だ。いくら管理をしっかりしても、技量がなければものができず、やる気がなけりゃ物を作らない。そんなことは自明だ。
となると、マネジメントシステム規格で継続的改善を記述すること自体、おかしなこと、いや間違ったことではないのかな?
うーん、縦から横からいくら読んでも、継続的改善が真かどうかはわかりませんでした。いや、分らないということが分りました。
そのうち偉大なる寺田さんが説教してくれるでしょう。
待てよ、私のような小さき者であっても一生懸命読んでも分らないということは、規格が生煮えなのか、言葉足らずではないのだろうか?
どうもISO14001はプロテスタントには向いてないようだ。
継続的改善とあるけど、本当は継続的最適化ではないのだろうか?
だって改善というのは座標が定まっていて一方に進めていくイメージだけど、現実は外部環境や内部事情によって最適値が変わり、それに合わせていくということだからね、適者生存とはある指標が良い悪いとあるわけではなく、その時の状況に合わせたものが生き残るという意味だろうし
それはISO認証した企業に求めるだけでなく、認証機関自らが己に要求すべきだろう。
おっと洗濯屋も同じだけど
この文章の出来は個人的には50点くらいかなという気がする。
とはいえ、過去のアクセスなどを見ると自信を持ってアップしたものが惨憺たる結果のこともあり、自分では面白くないと思ったものが物凄いアクセスを稼いだこともある。
ということでとりあえずアップしました。ご異議承ります。とはいえ、本質的でないツッコミはあまりうれしくありません。
レイシオ様からお便りを頂きました(2015.07.16)
継続的改善について おばQ様 いつもお世話になっております。 いつもながらよく考えられている内容だとほれぼれしてしまいます。 私ごときの脳みそではついていけるか不安ですが、感じたままにコメントします。 今までISO認証してもパフォーマンスが上がらないと言われてきたことに対してなにかエクスキューズが欲しかったということかと? と記載されているのが、改正の本音だと思います。 対外的に公開する為の設定した目標(たとえばCO2排出総量)に関してのみとれば、環境パフォーマンスの向上はそこだけで説明可能かもしれません。でもそれ以外のパフォーマンス向上(生産量増加)を優先した結果、相互作用によって環境パフォーマンスが悪化することもあるでしょう。 こんなものを回避するために環境パフォーマンスではなく、(すべての)パフォーマンスと記載したのかもしれません。もちろん、推察ですが。 だがそれがISO14001の意図である、「遵法と汚染の予防」につながるか問えばイコールではない。いやイコールどころか重なる部分が非常に少ないように思える 遵法はさておき、汚染の予防と継続的改善についてはこれまでイコールといっても差支えのない記載ぶりだと思っておりました。 JIS Q 14001(2004)における「汚染」の定義は、「あらゆる種類の汚染物質又は廃棄物の発生,排出,放出」と読める為、全ての業務のアウトプットの些細なミスも定義上は「汚染」と読むことができるのかと。 従って、パフォーマンスの低下自体を「汚染」ととることも可能であり、ロスやミス発生率を減らした後のプロセスは汚染の予防と読めると思います。 わざわざ、汚染の予防と継続的改善をわけて解釈する必要なく、労力と比較して対応が必要なロスやミスを減らす、って感じですかね。 継続的最適化論については、説得力がありまさにそうだろうと思います。 なんというか最近よく思うのが、トップは全体最適化と良くいいますけど、限られたリソースの中での実質的な選択肢は「全体最適に近い(の途中経過にある)採用可能な部分最適でしかない」ような気がしています。トップが変われば、全体最適化の目指すべき状態も違いますし。 |
レイシオ様 いつもお便りありがとうございます。 レイシオ様がおっしゃる「業務のパフォーマンスすべてが環境に関わる」というご意見について、そうだろうなあと思う気持ちも半分ですが、そうかなあと思う気持ちも半分です。 というのは「環境パフォーマンス」の定義は「環境側面に関連するパフォーマンス」であり、「パフォーマンス」の定義は「測定可能な結果」ですから、結果として「汚染の予防」になるパフォーマンスはすべて「環境パフォーマンス」であるからです。 「継続的改善」の定義が「パフォーマンスを向上するため・・」としたのは、関係者が十二分に吟味し検証した結果だと思いますから、彼らは継続的改善には「環境側面に関連しないパフォーマンス向上も含める」と決定したことは明白でしょう。今更、「環境が抜けてたわww」なんて発言はないと思います。 となるとやはり「遵法と汚染の予防」につながらないパフォーマンスも含まれると考えたのです。 レイシオ様がおっしゃるように環境パフォーマンス向上が全体のパフォーマンス向上につながらない合成の誤謬のような現象が起きるのはあり得ると思います。しかしならばそれ全体が「汚染」に関わるわけですから、環境パフォーマンスではないかという考えもあります。どうもそこがすっきりしません。 ところで環境パフォーマンスに関わらないパフォーマンスとはいったいどんなものがあるのでしょうか? 考えてみるとすべてが環境側面に関連するのかもしれません。しかし、となるとISO規格の定義が間違っているということになります。規格が正しいということもちょっとありそうがないですけど、規格の検証が不十分なのかもしれませんね。
あくまでも仮定ですけど。 | |||||||||
うそ800の目次にもどる
ISO14001:2015解説に戻る