19.05.23
�����ԑO�AISO9001�ɂ��ẮuJAB/ISO9001���J���_��v�AISO14001�ɂ��Ắu��ISO���v�Ə̂��āAQMS��EMS��ISO�̑��Ƃ������u�����ʌɊJ�Â��Ă����B�i�X�ƎQ���҂������Ă����������낤�A2013�N�������킹�āu�}�l�W�����g�V�X�e���V���|�W�E���v�Ƃ������̂ɂȂ����B��Ђœ����Ă������́A���x�������̏��Ҍ�������ė��Ē��u�������Ƃ�����B�����œ��ꗿ1���~�����C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����̍u���^��2013�N�܂ł͓��{�K�i����́u�W�����ƕi���Ǘ��v�Ƃ����������ɍڂ��Ă������A2014�N�ȍ~�A�C�\�X���Ɍf�ڂ����悤�ɂȂ����B���R�͒m��Ȃ��B
�A�C�\�X�������w�ǂ��Ă����̂�10�N�O�A���̌�ߐ�ŃA�C�\�X�����w�����Ă����̂ł����ǂ�ł����B�����ސE���Ă������w�ǂ͂����A�ʔ������ȓ��W�̂Ƃ����d�F�u�b�N�Z���^�[�Ŕ����Ă����B
2019�N6�����̍L���Ɂu��7��JAB�}�l�W�����g�V�X�e���V���|�W�E���S�u���^�v�f�ڂƂ������̂ł������Ă��܂����BISO�Ɖ�����A�܂��Ă�N�������̐g�ŎG����2000�~���o���Ĕ������Ƃ��Ȃ��̂����c�c
���̖{�͒ʔ̂Ŕ����A�͂����̂�13���������B���ꂩ�疈���������ǂ�ł����B�ǂݎ̂ĂĂ��ǂ������̂����A��͂�ЂƂ��ƌ���˂Ǝv���āA�{���͂����ǂ�ōl�������Ƃ������B
| | PART1�@��Î҈��A�@�ђ˗����� |
�@���F�ȉ��A���F�̕����͈��p�������B
���̐搶�A�ȑO����ISO�K�i���F�ؐ��x���S�R�������Ă��Ȃ��Ǝv���Ă������A2019�N�ɂȂ��Ă����ς��͂Ȃ������B���ς��Ȃ����Ƃ͊�����c�c����A������Ȃ��B
- �u�g�D�����鐻�i�E�T�[�r�X���{���ɑ��v�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��A�F�؋@�ւ��]�����܂��ip.22���il.2�j�v
ISO��O�ҔF�ؐ��x���u���i�E�T�[�r�X���{���ɑ��v�Ȃ̂��v�Ƃ������Ƃ��A�u�F�؋@�ւ��]���v����̂ł��낤���H �F�؋@�ւ̓}�l�W�����g�V�X�e�����K�i�v���ɓK�����Ă��邩��R������̂ł͂Ȃ��̂��H
����A����͎��������̂ł͂Ȃ��BISO17021-1:2015 4.1.2���u�F�̍ŏI�I�ȖڕW�́i�����j�}�l�W�����g�V�X�e�����K��v���������݂����Ă���Ƃ����M����^���邱�Ƃł���v�Ƃ���B
�ђː搶��ISO17021�ȂǓǂ��Ƃ͂Ȃ��̂��낤�B
�ђː搶����ʎs���ɑO�q�̂��Ƃ��q�ׂ��Ȃ�u���i�i����ۏ���v�ƌ������邾�낤���A�}�l�W�����g�V�X�e���V���|�W�E���ɂ����ĊW�҂ɔ����������Ƃ͂����g�̖������������������B
- �}�\2
- ������Ȃ����Ƃ�����������܂��B
- �u����CAB�i�F�؋@�ցj�͐M���ł���̂��v
���̂Ƃ��̐M���Ƃ͉��ɑ��Ăł��傤���H
�u�m�F������́v�Ɓu�M���̑Ώہv�͐������Ă���̂ł��傤���H
- �uCAB�G�m�F����v
�����m�F����̂ł��傤�H ���i�H �����\�́H �K�����H
- �u����CAB�i�F�؋@�ցj�͐M���ł���̂��v
- �}�\3
- ��F
�ǂ��ł��������Ƃł����A�L�ڂ���Ă���̂��݂�ƁA�u��v�ł͂Ȃ��u�ړI�v�̂悤�Ɏv���܂��B
- �]���@�F�\�͏ؖ�
ISO9001��1987�N�ł���2015�N�ł܂ň�т��ď����Ɏ��̕��͂�����܂��B
�u�i���}�l�W�����g�V�X�e���v�������́A���i�y�уT�[�r�X�Ɋւ���v��������⊮������̂ł���v
�܂�i���}�l�W�����g�V�X�e�������Ă��A�i�����������i�y�уT�[�r�X����������ɂ͏\������Ȃ���ł��B�i���}�l�W�����g�V�X�e�������O�ɁA���i�y�уT�[�r�X�Ɋւ���v�����������K�v������̂ł��B
���̐搶�Ɍ��炸�����̏ꍇ�A���̏����̈ꕶ��ǂݘR�炵�Č�邩�炨�������Ȃ�̂ł��B
- �]���A�F�\�͌���
�����ISO17021-1�ɂ͂���܂���BIAF������Ă��܂���B
�o�T�����߂܂��B

��L�͂��ׂđO�L��ISO�R���Ƃ͉����Ƃ��������̖��Ȃ̂ł��B
���Ȃ킿�A
�ђː搶�������u�g�D�����鐻�i�E�T�[�r�X���{���ɑ��v�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��A�F�؋@�ւ��]������v���ƂȂ̂��A�����ł͂Ȃ��u�}�l�W�����g�V�X�e�����K�i�v���ɓK�����Ă��邩��R������v���ƂȂ̂��Ƃ��������̍��Ȃ̂ł��B
- ��F
- �u�Z�����悤�Ǝv�����ꍇ�A�F�ؑg�D�ɑ��闿�����������邱�Ƃɂ���āip.24���il.-2�j�v
�����ł͂Ȃ������̂��Ƃ��A���邢�͕ۏ؋��̗����Ȃ̂��悭������܂��A�Ƃɂ����Z���ɍۂ��ĔF�̗L�����l������ƂȂ�܂��ƁA�F�ؐ��x�͍��҂ɑ��ĂȂ�炩�̐ӔC���̂ł��傤���H
��s�͗Z���ɍۂ��ď��\����ɌȂ̔��f�Ō��肵�A���̌��ʏł��t���Ă��Ȃ��ӔC���܂��i�ŋ߂͂����ł��Ȃ����ǁj�BISO�F�؋@�ւ͔F�����p�������ʂɁA�����Ȃ�ӔC���o�傪����̂ł��傤���H
����Ƃ����p�҂͏���ɔF�𗝉������̂�����W�Ȃ��̂��A���̕ӂ��������������ł��B���p�҂�����ɔF���Q�l�ɂ���Ȃ�A�F�����p���Ăق����ȂǂƂ͌����܂����ˁH
����͏����Ȃ��Ƃł͂Ȃ��AISO��O�ҔF�r�W�l�X�̍����ɂ�����邱�Ƃł��B
- �uJAB�̕s�ˎ��ւ̑Ή��ip.24���i�j�v
�s�ˎ��h�~�̂��߂ɂ��낢�����Ă����Ɣђː搶�͌��B�����Ǖi���ۏ����Ă����g�ƂȂ�ƁA�{����u�����ƌ����Ă���m�ł��܂���B
�R���Łu����Ă܂��v�ƌ����Ă��u�킩��܂����v�ƌ����Ă͂����܂���B���N���O�A���������R�������Ă��ĔF���~�ɂȂ����F�؋@�ւ�����܂����ˁA�o���Ă܂����H
�u����Ă܂��v�ƌ���ꂽ��u�؋��������Ă��������v�ƌ���˂Ȃ�܂���B
�R���N�e�B�u�A�N�V�������Ƃ����Ȃ�A���̌��ʂǂ̂悤�ɉ��P���ꂽ�̂��r�t�H�[�A�t�^�[�̎w�W�������Ă��������B�L�Ӎ��̌����5%���炢�ł��肢���܂��B�������L�ӂƔ��肳��Ȃ���A�������u���s�\���ƍ����߂��܂��B
| | Part2�@�Q�X�g�u���@�o�Y�ȁ@�㌴�p�i |
����l�炵�����J�ɂ��T�d�Ȕ����ŁA�����⌾�t���`�Ȃǂ������ȓ_�͂Ȃ��B
- �H�Ǝv�����͎̂���1�_�����������B
- �uISO9001�̂悤�Ȑ��i�̕i���Ǘ��K�i�ɉ����ip.26l.21�j�v
ISO9001�͐��i�̕i���Ǘ��K�i�ł͂Ȃ��B���Ԃ�A���₫���ƁA�ԈႢ�Ȃ��㌴����̌����ԈႢ���낤�Ǝv���B
���Ȃ݂ɉߋ��������_��Ȃǂɏo�����Ƃ����邵�A���̓��_���G���ɍڂ������Ƃ�����B���������Ƃ��ҏW�҂���Q���Y�t�Łu���̓��e�ł�낵�����H�v�Ƃ����m�F������B�c�_�̂��Ƃ�͏C���ł��Ȃ����A���t�g���Ƃ������ԈႦ�͏C�����Ă��炦��B�㌴����́c�c�ʂ����āH
| | Part3�@��u���@�R�c�@�G |
�ׂ������Ƃ͎~�߂Ă������A1�_�����ًc��\���グ��B
- p.38�}�\8��QMS�̔\�͐����̎w�W�͂Ȃɂ��H
�}�\�͒P�Ȃ�͎��}�Ȃ̂��낤���A�K�i����̂��т�ISO9001�̗v�������������Ȃ����Ƃ͎v���Ȃ��B�����Ȃ����Ȃ炻�̍�������Ăق����B
�P�ɓK�p�͈͂��L���Ȃ����Ƃ��K�p���O�����������Ƃ��A�v���������������Ȃǂ͗v���������オ�����i�������Ȃ����j���ƂɊY�����Ȃ��ƍl����B
�����2015�N����̎��A�����̔F�؋@�ւ͑g�D�̃��[���͕ς��邱�Ƃ͂���܂����A�K�i�\���ƌ������ς���������ł��ƍL�Ă����̂����A����͊ԈႢ�������̂ł��傤���H
���̒m���Ă����Ђ͂ǂ����}�j���A���̕ύX�i�Ȃ��ύX�����̂������ł��Ȃ����j�������炢�Ŏ����͉����ς����ɂ݂�2015�N�łɈڍs���Ă���B�F�؋@�ւ��F�ؑg�D���Ԉ���Ă���̂ł��傤���H
�����Ƃ����Ƒ厖�Ȃ��ƁA�ߋ�����ɂ���Ċ�Ƃ̔\�͐��������サ�����Ƃ������Ăق����B�����łȂ���ΔF����Ȃ��̂�����B
�����A���̌����������Ƃ́A�}�\8�͔[���ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
| | Part4�@WG1�@���q�떾 |
�܂��Љ��ISO�F���F�m����Ă��邩���A���P�[�g���������Ƃ������z�ɃK�b�N�������B�S�[�����u��O�ҔF�ؐ��x�̐��������y�v�Ȃ��O�ҔF�ؐ��x���邢�͑�O�ҔF�ɂ���Ă����Ȃ鐬�ʂ��邢�͕ω��������̂������ׂ��ł͂Ȃ��̂��H
���������u�P�Ȃ镁�y�łȂ��A���������y�i��.30�E�il.1�j�v�Ƃ���BJAB���F�肵���F�؋@�ւ̐R�����u���������y�ł���A�P�Ȃ镁�y�ł͂Ȃ��v�Ƃ����O��ōl����Ȃ�A�v���[�`�̃X�^���X���Ԉ���Ă���B
�܂���JAB�F��̔F�؋@�ւ����Ă���̂́u���������y�ł͂Ȃ��A�P�Ȃ镁�y���v�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��ł��傤�H
�����Đ��ɒm���Ă��邩�ł͂Ȃ��A�F�̉��l������̂��ۂ����n�߂Ɋm�F���Ăق����B�l�̔F�m�łȂ��A���p���m�F���ׂ��ł��傤�B
���ꂩ��2008�N�ł���2015�N�łɃo�[�W�����A�b�v�������ƂŁA�����Ȃ�w�W�������قǕς�����̂��ׂė~�����B
�A���P�[�g�ȂLjӖ��Ȃ��B
�ȉ�������ƒlj��A
- �u�F�ɂ��\�͌���ip.37���il.4�j�v���u�������ʁv�Ƃ��Ă���̂́A�ђː搶�Ƃ͈Ⴂ�Ԉ���Ă��Ȃ��B
- �u�g�D�ɂƂ��ẮA�F���Ƃ邱�Ƃɂ��A��背�x����QMS�\�́A���i�i���������Ă��邱�Ƃ�i���ł���ip.37���il.10�j�v
�u����ҁE�Љ�ɂƂ��ẮA�ǎ��ȕi��������\�ȏ�ԂɂȂ�Ƃ������ʂ�����ip.37���il.19�j�v
���̕���ISO9001�̏����u�i���}�l�W�����g�V�X�e���v�������́A���i�y�уT�[�r�X�Ɋւ���v��������⊮������̂ł���v���������Ă���̂ł͂Ȃ����낤���H
- �uISO9001�F�؏������̉�Ђ̔\�͏ؖ��Ƃ��Ċ��p�ip.37�E�il.21�j�v
�F�͔\�͏ؖ��ł���ƌ����Ă���͔̂ђː搶�Ɠ����ł���B�K���ؖ��Ɣ\�͏ؖ��͓������ƍl����ƁA�����Ƃ͎v���Ȃ��BISO9001�ɓK�����Ă��Ă����i�y�уT�[�r�X�Ɋւ���v�������������ƂƂ͈Ⴄ�B����Ƃ�4.2�ŒS�ۂ����ƍl���ėǂ��̂��낤���H
����ISO9001�̋K�i�v�����������ł́A���i�����Ɛ��i�i����ۏ��Ȃ��ƍl����B����͑O�LISO9001�̏����̗��Ԃ����B
| | Part4�@WG2�@�{�c�W�� |
���������č���̍u���^56�y�[�W�̒��ŁA��ԓǂ݂������Ƃ������ǂb�オ�������B
�����Ƃ�����͔�r�ł̘b�ł���A����10�N�ȏ�_�����Ă������Ƃł���킯�ŁA�����Ɛ[�x��Ƃ��������ԂƋ��ɐ[�����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������ϓ_����͂����Ɗ撣���Ă����Ƃ��������悤���Ȃ��B
�ȉ��A�v�������Ƃ��ӏ���������B
- ��`���͂����肵�Ăق����ip.49���il.9�j
���{�l���u�R���v���C�A���X�v��u�s�ˎ��v�̒�`���͂����肵�Ă��Ȃ��ƌ���Ă��邪�A�R���v���C�A���X�͈̔͂��قȂ�Ή�㈂���邱�Ƃ��傫���Ⴄ�B���̂ւ�͋c�_�̑O�Ɍ��߂Ă����Ă��炢�����B
- �F�̈Ӗ��A����͈͂��͂����肳���ė~����
�ђː搶���u�\�͌��������v�Ƃ����g����߂Ƃ����������̂Ȃ����M���I���Ă��邪�A�����ł���Εs�ˎ��Ƃ����Ă�ISO�F�Ɋւ��Ȃ��A�����A�����@�A�Z�N�n���A�}�^�n���܂őΏۂƂȂ肦��B
������ISO9001�Ɋւ��s�ˎ����N�����Ƃ��AISO14001�̔F���~�������Ƃ��������ˁB
- �u�u�R���v���C�A���X�̈ӎ����Ⴂ�v�֑Ή��ip.58���il.12�j�v
���{�l�̒͂Ƃ肠���������Ƃ��āA�ЂƂ��������B
�����ISO�����Ǝ����̕����̓�d����̉����ł���BISO���˂���l�����I�o�������ł������̓�d�\���͏����Ă��Ȃ��B����ǂ��납�ŋ߂ł͔F�ؑ�s��ЂɁA�R���O�Ɏ�X�̕����E�L�^���쐬������Ƃ��낳������B
������Ȃ����A��Ђ̎��ۂ�R������悤�ɂȂ邽�߂ɂ́A�R�����A�F�؋@�ւ�ISO�R���Ƃ������̂���������Ɨ������āAISO�F�ؑO���炠���ЌŗL�̕���…����͋ɂ߂ăI�[�f�^�r���e�B���Ⴂ��…����ŐR���ł���͗ʂ������Ƃ��K�v���B
2015�N�łɂȂ��Ă����܂��i���}�j���A����v�����Ă���F�؋@�ւ����X����̂��l����ƁA��Ƃ�ISO�R���p�Ǝ��ۂɎg�������L�^������Ă��邱�Ƃ�ӂ߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�Ƃ����JAB�̓}�j���A����v�����邱�Ƃ𐄏����Ă���̂��낤���H �˗��ҁi�F�ؑg�D�j�ɗ]�v�Ȏ�Ԃ����������Ȃ����߂ɁA�}�j���A�������Ɨv�����Ă͂����Ȃ��ƒʒm���ׂ��ł͂Ȃ��̂��H

���ꂪ�R���v���C�A���X�ƊW����̂��Ɩ���邩������Ȃ��B�\���̕���������Ȃ�A�d�v�Ȃ��Ƃ�����Ȃ����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
- �s���s�ׂ͗}�~�ł��邩
�u�i�s�ˎ��̗}�~�́j�����J�Ɛ��ّ[�u�ip.56���il.1�j�v
���͂܂�ISO9001�́u7.���j�v�Ɓu7.3�F���v�̐R�����������肷�ׂ��ƍl����B���j�̐R���Ƃ����Ƒ����̏ꍇ�A�o�c�҂Ƙa�₩�ɍ��k���ďI��肾���A5.2.2���d�v���낤�B���j���Ǘ��ҁA��Ǝ҂ɓW�J����Ă��邩�ׂ邱�Ƃ��B���̍��Ԃ̗v�������������Ɋm�F���邩���F�؋@�ւ̗͗ʂł���A���ꂪ�s�ˎ��̗}�~�́i�\�h���u�j�ɂȂ邾�낤�B
�����J�Ɛ��ُ��u�Ƃ����̂́A�}�~�i�\�h�j�ł͂Ȃ��������u���낤�B
- ����R���̌��E
JAB���u�R���H�������X�N�ɉ����ĉ�������i��.58�E�il.-9�j�v�Ƃ����l�������邻�����B�����ł̃��X�N�Ƃ͕s�ˎ��̋N���₷���炵���B
���z�͗����ł��邪�A���X�N�����邩��ƐR���H���𑝂₷���Ƃ͊ȒP�ł͂Ȃ��B�܂�������R���H���𑝂₵�Ă����挟���ł��邩����E������B
��������ISO17021-1:2015 4.4.2�̒��L�ł��u�����Ȃ�R�����A�g�D�̃}�l�W�����g�V�X�e������̃T���v�����O�Ɋ�Â��Ă��邽�߁A�v��������100���K�����Ă��邱�Ƃ�ۏ�����̂ł͂Ȃ��v�Ɩ��L���Ă���B
�R���H���i���搔�j�́A���Y�Ҋ댯�i�R���r�W�l�X�ŗ��v���m�ۂł��j������Ҋ댯�iISO�F���Q�Ƃ���l�̗����j�ɂ���ē��v�I�Ɍ��肳��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�܂��o���_�͈�ʎЉ�F�؊�Ƃ̕s�ˎ��������������قǂȂ�����i�Ë�����j�̂����͂����肳���āA����ɍ��킹�Ĕ��挟���Ȃ�ʐR���H����ݒ肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
����̕s�Ǖi�̍�����������悢�̂��A1/3�Ȃ̂��A�ꌅ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B�����ꌅ������ƂȂ�Δ��挟�������������l�Ȃ甲�搔�͂Ƃ�ł��Ȃ����ɂȂ�ƒm���B�������s�Ǖi�̍������[���ɂ���͕̂s�\���B

�Ƃ���ŐR���H����2�E3�����₵�Ă�����Ҋ댯�͂قƂ�Ǖς��Ȃ��B���������Ď���JISZ9002���߂����Ă����ԍl�����B�C�������Ƃ��p������������x�ɍH�����������Ă��Ӗ��͂Ȃ��B
����Ҋ댯�̗v���������������ł���AISO�F�r�W�l�X�͂����������藧���Ȃ���������Ȃ��B
��������O�ҔF�ؐ��x�͓�ҊԂ̌��Ō��܂�킯�ł͂Ȃ��ڋq�͕s���肾����A�F�ؐ��x�����炪���肵������Ҋ댯�Ƃ��������łق����|�����\���ׂ��ł���B����ɐ��̒������ӂ��Ȃ��Ȃ�F�r�W�l�X�͐��藧���Ȃ��Ƃ������Ƃł����Ȃ��B


�Ƃ��������ナ�X�N�̑����Ɩ���g�D�ɑ��ĐR���H���𑝂₷�Ȃ�A�Љ�ɑ��č���͐R���H���𑝂₷�̂ŐR���������̊����́���%���灛�����Ɍ������܂��B�������[���ł͂���܂���ƌ�������K�v������B
�u�R���H���𑝂₵�܂����獡�܂ł�茩�����͌���ł��傤�v�ł���A�K�L�̎g�����B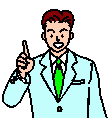

�����đ厖�Ȃ��Ƃ����A����I�ɔF�ؐR���ł̕s�ˎ������������\���A���ꂪ����Ҋ댯��菭�Ȃ����Ƃ��ؖ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����������A�s�ˎ��������Ă����ꂪ�ŏ��Ɍ��肵������Ҋ댯��������Ă���A�F�ؐ��x�͓��X�Ƃ��Ă��ėǂ��̂��B
| | Part5�@�Q�X�g�u���@����a�F |
�@BYE
| | ���� |
�v���U��ɃA�C�\�X����ǂ��A�F�؋ƊE�̋ƊE���ɓ��������悤���B�ȑO�̓A�C�\�X����ISO�ƊE�i�F��@�ցE�F�؋@�ցE�R�������C�@�ցE�R�����o�^�@�ցj�����łȂ��A�X�̃R���T���E��ƒS���ҁE���֘A��Ǘ��H�w�̊w���܂őΏۂɂ���ISO�K�i��F�ؐ��x������Ă����Ǝv���B���ۂɊw�������������Ă���̂�d�ԂȂǂŖڂɂ��Ă����B
���������͊��S�ɔF��@�ցE�F�؋@�ւ�ΏۂƂ����������ł���B�ƂȂ�ΕҏW���j���X�^���X���F��@�ւ̎��_�A����͔F�؋ƊE�Ƀt�H�[�J�X���Ă���̂��낤�B
������JAB�}�l�W�����g�V�X�e���V���|�W�E���Ƃ������̂��A�̂̂悤�Ƀ}�l�W�����g�V�X�e���ł͂Ȃ��A�F�r�W�l�X���ǂ����Ă������Ƃ������ƂɃt�H�[�J�X�����̂����R�Ȃ̂��낤�B
| | �{���̎��� |
����v���̂����A�ђː搶��ISO�F�؋K�i�����łȂ��K�����]���K�i�Ƃ�IAF���ǂ��Ƃ�����̂��낤���H �����\�V�C�Ƃ����������ƈقȂ�b�Ȃ̂ŕ����B���t�Ȃ��ߐ������ǁA�u���^�ƂȂ��CINII�ɂ����^����邵�A10�N20�N�o���Ă���������҂ɎQ�Ƃ����ł��傤�B
�u������O�Ɏ���̕����u�搶�A�����͂�����ƈႢ�܂��v�Ƃ����i�ɋy�Ȃ��̂��낤���H �R�����g����Ă��t���Ȃ��̂��낤���H
�Ƃ���ŁA���N��8��}�l�W�����g�V�X�e���V���|�W�E���Ƃ������̂������Ă��A����2000�~�����Ă܂œǂނ��Ƃ͂Ȃ����낤�B
����800�̖ڎ��ɂ��ǂ�