私の身の回りの人たちが、ことわざとか四字熟語などで間違えたのかふざけたのかわからないけど、正しい言い回しでないとか、本来の意味でないとかときどき聞くことがある。その中には筋違いだけど納得したこともあるし、まったく変だと思ったこともあり。そんなもので気になったものを書いてみた。
- 一念岩をも通す(2024.02.20追加)
知り合いの年寄り(つまり私と同年代)の人とバッタリ会った。
だいぶ前に、彼からとある習い事(マイナーなものだ。詩吟とか俳句を思い浮かべてくれれば良い)を始めたと聞いていた。
近況報告で、彼はその習い事でなんとか一人前にみられるようになったという。
彼曰く
「こけのいちねんいわをもとおすと言うように、数年頑張った成果が出た。岩に生えている苔も、年月が経てば岩に根を張りやがては岩を砕いてしまうからね」
と言う。
彼は「虚仮 」を「苔 」と理解していたのだ。話がおかしいと思ったが、だいぶ努力されたのでしょうと無難なことを言って分かれた。
家に帰ってから、私が間違って覚えていたかと思いネットで調べたが、辞書では間違いなく「虚仮」であった。
虚仮とは「嘘」とか「馬鹿」のこと。騙されたりすると「よくも俺を虚仮にしてくれたな」というのがドラマの定番のセリフである。
このことわざの場合、虚仮が苔でも意味が変わらず通じるからネットでも「苔の一念岩をも通す」と勘違いしたと書いている人もいる。
現代では虚仮なんて言葉を使わないから、むしろ苔のほうが適切なのかもしれない。
諺とかたとえ話は、生活習慣とか道具が変われば通じなくなるわけで、意味が同じでも動詞も名詞も変わっていくのが必然かもしれない。
 てんびん座という星座があるが、いまどき重さを測るのは商店でも家庭でも電子秤だから、天秤など見たことのない人のほうが多いだろう。
てんびん座という星座があるが、いまどき重さを測るのは商店でも家庭でも電子秤だから、天秤など見たことのない人のほうが多いだろう。
水瓶座と言われても、そもそも瓶 なんて見たことないだろうし、言葉さえ知らないんじゃなかろうか?
ならばてんびん座も水瓶座も改名したほうが良いのかもしれない。
でもそうすると星座占いの値打ちがなくなってしまうだろうか?

注:三瓶とか二瓶という苗字は福島県に多い。ある三瓶さんが東京に引っ越したら、名前を正しく読まれたことがないとぼやいていた。
似たようなものは多々ある。
桃太郎のお話を聞いても、各家庭に水道があり全自動洗濯機がある家庭で育った現代の子供は、川に洗濯に行くということを思い浮かべることができないだろう。
私の親父の実家には水道がなく、井戸の水は汲みすぎるとなくなってしまうので、洗濯するには100mほど離れた川まで行って洗うのを見ていた。たった60年前のことだ。
考えると昔話を聞いて情景が目に浮かぶなんてものは少なくなった。
 舌切り雀ではスズメを見たことがない人も多いだろうし、「つづら」なんてわからないでしょうね。「のり」もわからないだろう。
舌切り雀ではスズメを見たことがない人も多いだろうし、「つづら」なんてわからないでしょうね。「のり」もわからないだろう。
こぶとり爺さんに至っては、こぶのある人を見たことのある子どもはいないだろう。今は医療が発達したから、問題があれば処置してしまう。
かさ地蔵のお話を聞いても、お地蔵様を知っているだろうか?
子供に昔の生活を教えるために昔話を聞かせるのか、子供に躾とか善悪を教えるならお話を現代流に直すのか、考えなければならない。
我流天性 (2024.02.03追加)
私が引退してから水泳に凝っているのはご存じの通り。ただフィットネスクラブは数回変わった。理由は不衛生だとか、設備が壊れているとか、いじめをする爺がいるからとか、つまらないことである。
70過ぎてもいじめられているのかと言われると、残念ながらその通りである。とはいえこの歳になって殴り合いの喧嘩をすることもない。
相手を変えることができないなら自分が対応するしかない。ということでフィットネスクラブを変えた。昨年暮のことである。
尻尾を巻いて逃げたと言われればその通りだが、猫を追うより皿を引けともいう。ともかく私は嫌な気分になるのは防げたし、嫌がらせをした爺はいじめる相手を一人失っただけ。フィットネスクラブは会員を一人減らしただけ。
損したのはフィットネスクラブだけという気もするが、それはフィットネスクラブとプールガードの怠慢だからしょうがない。
プールガードはスマホをいじったり文庫本を読んでないで、しっかりとプールで溺れていないか、トラブルが起きてないか監視しろ。そしてフィットネスクラブは従業員の躾をしっかりしろ。フィットネスクラブを変えるのも悪いことではない。何事も淀むとろくなことはない。新しい仕事、新しい住まい、新しいフィットネスクラブも良いだろう。我が家には一枚も畳はないし、新しい妻とは言わない。
新しいプール友もできた。その中の一人が話が面白くて泳いだ後でお話を聞いたりしている。
彼は私より年上でいい歳である。いい歳とは「〇んでもいい歳」の省略形という話もあるが、定かではない。彼は勤めていたとき水泳クラブに入っていたそうだ。クラブの仲間からは手足の動かし方が悪いといつもダメ出しされていたそうだ。あるとき大会にクラブから数人出場したが、結果は彼だけが入賞していつもダメ出ししていた人たちは全滅だったという。
彼はそれを「わしは我流天性だ」という。初めに聞いたときは「
画竜点睛 」のことかと思った。普通は「画竜点睛を欠く」と言うが、「最後の仕上げができていない」とか「一つ足りない」という意味だ。「画竜点睛」なら100%完成しているという意味だと思ったのだ。
 ところが話をしていると、彼は自分を「
ところが話をしていると、彼は自分を「我流天性 」だと言う。「我流」は本流を習っていない自己流のこと。そして「天性」とは天からの授かりものとか生まれつきの性質のこと。要するに基礎から習ったことはないが、生まれつきの能力と努力で我流でも一流だという自負だったのである。真面目に考えるとすごいこと、素晴らしいことだと思う。基礎ができてないとスポーツも仕事もダメというのが普通の考えだろう。だが習わずとも自分の創意工夫で結果を出すなら、それは基本と言われている
セオリー よりも優れていることになる。私もISOMS規格など習ったことはない。見よう見まねでやってきたが、おかしなことを騙る審査員は未熟だと思っている。
私も我流天性と称してもよろしいでしょうか?
いやそう思っているという自慢にすぎません。
- 下手の物好き
定年後にスポーツクラブで会った方だが、若いとき特段スポーツをしていなかったそうだ。私は泳げなかったので水泳を習ったが、彼はテニスをしたかった。テニスを教えるプログラムは私の通っているスポーツクラブにはなかったので、少しして彼は別のスポーツクラブに移った。
別のスポーツクラブとはいえ駅は同じだから、月に一度くらいは駅前あたりで顔を見かける。会えばその半分くらいは昼飯を食べたりお茶したりする。そんな頻繁ではなく、年に四五回というところだ。
 会うたびにお互いの進歩を確認するというか、お互い自慢話をするわけだ。
会うたびにお互いの進歩を確認するというか、お互い自慢話をするわけだ。
私は平泳ぎが平泳ぎもどきから平泳ぎに見えるようになったとホラを吹くが、彼もウインブルドンは視野に入ったなんて吹かすわけ。
だけど話から推測するに、彼はもっぱら道具に凝っているようで、彼が言ったのが「下手の物好き」という言葉。彼が言うには腕前の上達はまだだが、ラケットは素晴らしいとのこと。
なにしろ大人買いもあるが、老人買いもある。特に孫がいないと孫に投じるお金を自分に投じることができる。私のプール仲間は水着はアメリカ製でなくちゃという。アメリカ製はそんなにいいのかと聞けば、太っている彼に合うのは日本製にはないとか。
それはともかく、彼はテニス道具やウェアなど一式50万くらいはかけたんじゃないかな。彼のヘッドバンドも腕の汗拭きもみなブランド品だ。私はスポーツオーソリティのセールで100円で売っていたのを使っている。
彼の言うウインブルドンとは、ラケットだけはウインブルドン並みだということかもしれない。下手が上手になるより、物だけでも一流を持つのが早道?
いや貶すつもりはさらさらない。腕を上げて自慢してもよし、道具を自慢してもよし。なにもなければ夢を語ってもよし。下手の横好きではない、真正面から好きなんだからいいじゃないか。
- 袖触れ合うのも多少の縁
「他生の縁」を「多少の縁」と誤解している人は多いけど、家内が見聞したのはまた別の誤解。
家内は卓球クラブに四つか五つ入っている。というのは同好の士が集まって作るスポーツクラブは、公民館とか放課後の学校の体育館を借りるのだが、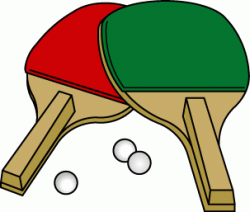 公共の施設は一つのクラブに週1回しか貸さない。それでもっとプレイしたいという人たちは仲間をいくつかに小分けして、それぞれが別のクラブを作りそれぞれが施設を借り、練習日には仲間大勢が集まって楽しむのが普通だ。仮にみっつのクラブに分けてそれぞれのクラブが施設を借りられれば、週に三日遊べることになる。
公共の施設は一つのクラブに週1回しか貸さない。それでもっとプレイしたいという人たちは仲間をいくつかに小分けして、それぞれが別のクラブを作りそれぞれが施設を借り、練習日には仲間大勢が集まって楽しむのが普通だ。仮にみっつのクラブに分けてそれぞれのクラブが施設を借りられれば、週に三日遊べることになる。
もちろん市の大会などには、登録してあるクラブで参加する。
おっと、それはともかく、家内があるクラブで新しく入会した人から言われたという話。新人といってもアラフィフのおばさんだが、家内はミドルシクスティのばあさんである。新人  「袖触れ合うのも他生の縁というから、あなたは仲良くしなくちゃならないのよ」
「袖触れ合うのも他生の縁というから、あなたは仲良くしなくちゃならないのよ」家内 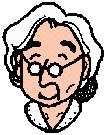 「はっ?」
「はっ?」新人  「私が欲しいものをプレゼントしてくれるとか」
「私が欲しいものをプレゼントしてくれるとか」家内 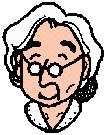 「へっ?」
「へっ?」新人が語るには、ちょっとでも知り合ったなら縁があったのだから親切にしなければならない、例えば家内の持ち物がほしいと言われたら、それをあげなければならないとのこと。
それを聞いたとき、家内は理解不能でフリーズしてしまったそうです。新人は家内にだけでなく他のメンバーにも同じようなことを言ったため、周りから縁を切られたそうです。多少の縁もなかったようです。
これは……ことわざを誤解していたというより、ちょっとおかしな人だったのかもしれません。
- 貧乏暇なし
昔、私が子供の頃、母の妹の旦那さんが失業したときがあった。高度成長期とは、辞書によると1950年から1973年までをいうらしい。しかし常に景気が良かったわけではなく山谷があり、1960年頃東京オリンピック前はかなり景気が悪い状態で、失業した人もだいぶいた。
 当時は7割が中卒で就職したが、就職できない人も多数いた。1966年だと思うが、大手企業が一斉に採用をとりやめた年さえあった。就職希望者がほとんど就職できるようになったのは、1968年以降ではないだろうか。
当時は7割が中卒で就職したが、就職できない人も多数いた。1966年だと思うが、大手企業が一斉に採用をとりやめた年さえあった。就職希望者がほとんど就職できるようになったのは、1968年以降ではないだろうか。
バブルがはじけてから氷河期なんて言葉が言われたが、私のような年寄りから見れば氷河期とは1960年頃であり、バブル崩壊後はせいぜい火山が爆発して気温が低下した程度だ。
失業して職がなく、知り合いのお店を手伝ったり、アルバイト的な日雇いの仕事をする人はそうとういた。
現在、非正規労働者が増えているという人が多い。ネットにあるほとんどの数字は1985年以降で、1973年からのものが1件見つかっただけだ。だけど1960年頃は、お手伝いとか今月だけなんて形で働いていた人がものすごくいた。
ともかくここ最近、非正規労働者は最近増えているというが、半世紀前は今どころではなかった。1968年私が就職したところでも、社員、工員、臨時工というヒエラルキーがあった。臨時工とはまごうかたなき非正規労働者であり、不景気になったら即解雇である。細かいことは忘れたが、工員と臨時工の待遇には歴然とした差があった。臨時工の人が給料が違うのはあきらめるけど、月給日が工員と違うのが差別されていると感じると言ったのを覚えている。もちろん工員と社員の月給日も違うのだけど。
その後、何年かして臨時工も正規の工員になった。そして月給日は皆同じになった。そのときみんなハッピーになったかといえば、工員の中には元臨時工の月給日が同じになったことに文句を言う人もいた。差別されることはつらいが、差別するのは気分が良いのだろうか?
おっと、叔父さんは毎日は仕事がないから、つてを頼っていろいろな仕事の手伝いをして小遣い程度をもらっていた。叔父さんは独身じゃない、妻子を養っていたのだ。大変だったろうと思う。
そういうのを見ていると「貧乏暇なし」と聞いても意味が分からない。叔父さんは貧乏だけど働く仕事がないから暇があるのだ。働くことができれば貧乏でなくなり暇もなくなるのに?
その辺に行って手当たり次第に仕事を探せとおしゃるか? 人手がいらない農家に行って仕事させてくれと言ってもダメなんですよ。貧乏暇なしというのは、仕事があるけれど賃金が安いから貧乏だという状態なのです。そもそも仕事がない状況においては、働けないから貧乏なのです。
このことわざは特殊解というか普遍性がないとしか思えない。全く手がないとなれば東京に出ていくという選択もあっただろう。当時、田舎で食い詰めた人たちはどんどんと東京に出て行った。果たして東京でどんな仕事に就いたのかわからない。皆が皆、都会で成功したとは思えないが、一度出て行った人で戻ってきた人はいなかった。今から60年も前のことだ。
- 悪友
私は少年時代からずっと「悪友」とは気のおけない友達だと思っていた。中学校(1963頃)のとき、国語の教科書に誰かの小説の一説があり、そこに悪友という言葉があって、先生が「これは悪い友達ではなく親しい友達のことだ」と説明したのを今でも覚えている。しかし大人になって、いや40を過ぎた頃、周りの人が悪友とは付き合ってはいけない悪い人、悪いことをする人の意味で使っているので驚いた。
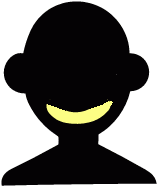 お前、阿久悠を知らないのかといいたい。
お前、阿久悠を知らないのかといいたい。
まあ時代と共に言葉の意味も変わるからと、諦めも感じながら自分もそんな意味で悪友を使うようになった。辞書を引いてみた。
1955年の広辞苑第二版では、簡単に「悪い友」とだけあった。
1980年の国語辞典では「悪い友達」と「悪さを一緒にするほど仲の良い友」とある。
2020年時点、ほとんどの国語辞典では「悪い友達、付き合ってはいけない人」とある。少し大きな辞書だと「親しい友人を呼ぶこともある」と載っているが、まあ二の次である。
これを時系列に並べると、元々は「悪い友達」のみを意味していたが、1960〜1990頃には反語的表現で「仲の良い友」の意味も併せて持つようになり、21世紀には先祖返りして「悪い友」の意味だけになったということなのだろうか?
それとも阿久悠が活動していた時代(1970頃〜2005頃)だけ、悪いイメージが薄かったのか?
- とんち無用
今はどうか知らないが、昔は会社では年に2回、棚卸というのをした。倉庫から現場まで部品や材料の品目と数量を数えた。もちろん大仕事になるので倉庫係ばかりではなく、現場の人たちも仕事を止めて総がかりで数え方をした。
私も駆り出されて数える作業をした。ある部品は細かくて数えようがなく、重さをはかって数量を把握しようとかワイワイしていた。
倉庫の人が、段ボールに「天地無用」と書いてあるのを指さして「余計なことを考えんでもいい、言われた通り数えることをしろ。とんち無用だ」と言った。その人はダジャレでとんち無用と言ったのか、その職場ではそういう言い回しがあったのかは知らない。仕事にはアイデアを出すことが重要なこともあるし、愚直に手足を動かすことが大事なこともあるから、そのとき「とんち無用」とはまっとうだと思った。
いずれにしても「とんち無用」という言葉が50年後も頭の中に残った。ところで私はずっと「天地無用」とは天地がいらないことだ、だから上下を気にしなくてよいと思っていた。その後倉庫で段ボール積みをしたとき、「天地無用」は上下があるから逆さにしてはいけないことだと教えられた。しかしなぜ「天地無用」がそういう意味なのかは分からなかった。
 50歳くらいになって、「天地無用」とは元々は「天地入替無用」と書き、「逆さまにしてはいけない」という意味だと知った。それが短縮されて「天地無用」と書くようになったという。
50歳くらいになって、「天地無用」とは元々は「天地入替無用」と書き、「逆さまにしてはいけない」という意味だと知った。それが短縮されて「天地無用」と書くようになったという。
漢語として「天地無用」を読めば、「天地が無用」ゆえに「逆さまにしても構わない」という意味で、短縮されたいきさつがなければ初めに私が考えたことが正しい理解とのこと。
現在は「天地無用」は誤解しやすいので、使わないそうだ。現在では正しくは「この面を上に逆さま厳禁」とか「この面を上にする」と表記するらしい。JIS規格では文字ではなく「↑↑」と表示するのが正しいとのこと。
現場で「天地無用」を見て頭をひねる人がいなくなることは喜ばしい。
- おっとり刀
家内はチャンバラ物が大好きだ。とはいえお金もないからブックオフに行っては文庫の古本を10冊、20冊と買ってきて読んでいる。すでに我が家の作り付けの本棚2つは家内の時代劇の文庫本に占拠されている。
 私も時々家内から借りて読むが、時代物というのはストーリーがパターン化されていて皆似たようなものだ。1冊読めばシリーズ物はもう読まなくてよい。
私も時々家内から借りて読むが、時代物というのはストーリーがパターン化されていて皆似たようなものだ。1冊読めばシリーズ物はもう読まなくてよい。
しかし家内は飽きもせずにひたすら読む。シリーズ物は読んでないものがあると、憑かれたようにそれを探す。本屋で新品を買えばすぐに手に入るが、家内は100円(税別)のものしか買わない主義なので手に入るまでそうとう探しまくる。
そして読んでいて佳境に入ると止めることができず、夜中過ぎて2時3時まで読んでいることもある。
そんな家内が言う。
「事件が起きると『おっとり刀で駆け付けた』が決まり文句なのよね。作家のひとりくらい『おっとり駆け付けた』
と書く人がいてもいいと思うけど」法律用語の意味 直ちに 即時に、すぐさま
事情あっても遅れてはならない速やかに 可能な限り早く 遅滞なく 事情の許す限り早く
つまり小説の中では「おっとり刀」はたいして意味のない事件発生の枕詞になってしまったようです。まあ現代の刑事物でも、事件が起きたからって息を切らして駆けつけるわけじゃない。そもそも警官が現場に駆け付けるスピードは、法律用語でいえば、速やか程度じゃないんですかね?
読者に「緊急事態だ!」と感じさせる新たな言葉は、まだ発明されていないようです。
- たそがれる
「たそがれてやんの」なんて言い回しをラノベでもよく見かけます。多くの場合、しょげているとか、元気をなくしている状況を表現しようとしているようです。実はここ1年くらいネット小説やラノベというものを読むようになって、初めてそういう意味に使うと知りました。
「黄昏 」とは、夕方になり日が暮れて薄暗くなるときのことや状況を言います。そもそも語源は、
夕方暗くなって顔がよく見えず「誰れそ彼は(あなたは誰か?)」といい、それが短くなって「たそかれ」ができた。もともとは名詞だけど動詞にも使われたとある。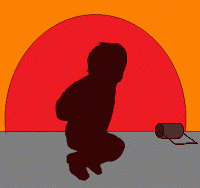
これは黄昏じゃない
日が沈んで黄昏です
やがて「人生の黄昏」という比喩が使われるようになり、更に人生を付けなくても盛りを過ぎて力をなくした状況を「たそがれ」と言うようになったそうです。
すると「定年になった親父が庭先で黄昏ている」なら意味が通るでしょうけど、ラノベでよく見る「彼女に振られた大学生が公園のベンチで黄昏る」とかゲートの伊丹二尉がチョンボをしても黄昏ることはないかと思います。
いや21世紀では「黄昏る」は、がっかりしたり、しょげている意味なのだといわれると、そうかとしか言いようがない。ところで「あらた」という会社があります。以前私が通勤の京葉線で市川塩浜あたりで看板を見ていたので覚えている。ひらがなで「あらた」とはと、気になった。
社名の由来は中国の古書「大学」からで、現代語にすれば「自分を向上させようと日々励めば、自分は新しくなる」のだそうです。ところで「あたらしい」の古い言い方は、「あらたしい」で「あらためる」の派生語だったらしい。それが平安時代に「あたらしい」となったそう。そして元々あった「あたらし」とは「惜しい」の意味であるが、「あらたし」が「あたらし」と言われるにつれ使用されなくなったとのこと。とはいえ今でも「あたら若い命を散らす」などに残っているとのこと。
「だらしない」が元は「しだらない」でその元は「ふしだら」だというから、言葉なんて流動的、正しいも正しくないもない。「ら抜き言葉」が50年後は正統日本語になっているかもしれない。私自身「い抜き言葉」を使っているから「ら抜き言葉」を批判はできない。「たそがれる」いいじゃないですか(謎)
でも同じ日本語といっても、50年も経つと語彙が変わってしまって話が通じなくなりますね。
でもねえ〜、「絶対大丈夫だよ」「おられますか?」「やばい」などは、ビジネスで使われる言葉とは思えません。
- 帯に短したすきに長し
まじめな話である。いや私はいつも真面目なのだが……家内の友人で「命短し怠惰に長し」と言った人がいる。
人生は短いが何もせずに過ごせば長いということらしい。これは誤用ではなく、まっとうに考えてそう言ったのかどうか?
だとするとこれは新しいことわざになるのかもしれない。どっちみち今じゃ帯もたすきも死語になりつつある。
あるいは「命短し恋せよ乙女」の後半を忘れただけなのか?
- 扁桃腺肥大
現場監督をしていたとき、とにかく現場で大声を出すのでいつものどが痛く、ガラガラ声をしていた。部下の一人があまりにも気になるというかかわいそうに思ったのか、自宅で作ったカリン酒を持ってきてくれた。花梨を梅酒と同じように焼酎につけておくと、花梨のエキスがでて甘い果実酒になる。これが喉に良いのです。とはいえ毎日毎日怒鳴っていては治るはずがありません。というわけで耳鼻咽喉科に通いました。診察室の前に座っていると、中から「扁桃腺肥大ですよ」と医者の声が聞こえました。扁桃腺肥大とは扁桃腺、つまりのどちんこの左右がはれていることをいいます。扁桃腺は外から入ってきた細菌によってはれてしまいます。特に抵抗力の低い子供ははれやすい。それだけの話でたいしたことじゃありません。
なぜ私が知っているかといえば、半世紀以上も前に小学校の身体検査で、風邪が流行っているときは扁桃腺肥大というのはクラスの半分以上いたからです。ところが医師の言葉の次に聞こえてきた母親らしい声が
「扁桃腺左ってなんですか? ちゃんと右もありますよ」
まあ、それだけなのですが、扁桃腺肥大という言葉を知らなければ、扁桃腺左と聞こえるのかもしれません。ところで私の喉は耳鼻咽喉科でも治りませんでした。しかしそれから間もなく私が大チョンボしたので管理職を首になりました。そしたらどうでしょう、あっという間に喉の痛みは消え、声も正常に戻りました。
その後、町でパートの人に会いましたが、その人に「以前は(私は)鬼のような顔だったけど、今は仏様のようになったね」と言われました。私も当時はつらかったのでしょう。
朝令暮改
朝令暮改とは朝出した命令を暮時には変更するように、やることなすことがコロコロ変わること。
朝三暮四 とは、昔中国で猿を飼っている人がいて、餌を朝に三つ暮れに四つ与えると言ったら猿が文句を言うので、朝に四つ暮れに三つやると言ったら喜んだというお話。目先が違っても同じことであるということ。
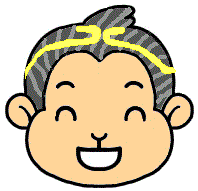
四字熟語の朝と暮れ二つが同じなので、この二つをごちゃまぜにして覚えている人がいる。それも単なる間違いでなく自分なりに納得している。私もそれが通用するような気がする。
朝三暮改 朝三つと言ったけど、夕方に改めること。
朝礼母子 朝礼を遠くから見ている母と子がいた。それって、孟母三遷?なお、次のような四字熟語はれっきとして存在する。
漢字 読み方 意味 朝雲暮雨 ちょううんぼう 男女のかたい契りのこと 朝改暮変 ちょうかいぼへん 朝令暮改に同じ 朝開暮落 ちょうかいぼらく 朝開いた花が夕べに散ること。人生のはかないこと 朝種暮穫 ちょうしゅぼかく 方針が定まらないこと。慌ただしいさま 朝真暮偽 ちょうしんぼぎ 真実と嘘が定めがたいこと。朝と夕で真と嘘が入れかわる 朝生暮死 ちょうせいぼし 生命がきわめて短いこと。人生のはかないこと 朝朝暮暮 ちょうちょうぼぼ 毎朝、毎夕
![]() 本日の反省
本日の反省
ダジャレを集めようと思って始めました。でも私の人生を思い出すと、笑って済ませられるようなことばかりではありませんでした。
まあ笑ったり泣いたり怒ったり、いろんなことがあったということで。
ひとりごとの目次にもどる