一般的に資格とは趣味でも仕事でも何事かをするために必要なもの、検定とは実行するには必要ではなく能力の有無やレベルを示すものと言われます。更に法律的には免許とか許可とかいろいろ細かい定めがあるようです。
といってもその区分はあいまいです。日本舞踊の名取は検定で師範は資格なんでしょうか? エコ検定は文字通り検定で、その上位になる環境プランナー・ベーシックも検定のようですが、更にその上の環境プランナーは資格を自称してます。もっとも環境プランナーでないとできないというものはないようです。
ISO審査員登録は2007年まではそれがないとISO審査ができない資格でしたが、ISO17021が制定されてからは認証機関が力量ありと認めれば審査員登録など関係なく審査できることになりました。では審査員登録機関は何のためにあるのでしょうか? 謎です。
博士号は教員採用時には必要かもしれないが、研究するには必要ない。中小企業診断士の資格がなくてもコンサルはできる。このような。独占資格でない業務名称独占資格というものもあるわけで、資格と検定の本質的な違いはないのかもしれません。
ともかくここは、資格と検定の境界を極めるところではありません。どうでもいいことにして、次に進みましょう。
若い時、仕事で必要だから資格を取れ、転職に有利だから資格を取ろう、自己研鑽の成果を確認するため資格試験を受ける。あなたはそんなことを言われたり、してきませんでしたか?
私もそんなこんなで結構、いろいろな細かい資格(大物ではない)を取ってきました。 工業高校を出て機械製図工になりました。二十歳の頃は会社の外でも通用するようになりたいと思いました。旋盤とか溶接のような作業ですと資格も検定も細かくあるのですが、製図の仕事では国家資格も民間資格もないんですよね。あるのは技能士の機械製図だけ。 まあなにごともチャレンジ。当時 3級技能士ってのはありません。2級技能士を受験するには工業高校卒業後に3年(今は2年)の実務経験が必要でした。
受験資格を満たすと早速受験しました。1970年頃はCADなんてありません。図面を描くにはドラフターかT定規です。いくらなんでもT定規では速く描けないので、会社に技能士受験のためと借用願を出して、ドラフターを試験場の県庁所在地まで担いでいきました。もちろん合格です。
| T定規 | ドラフター | |

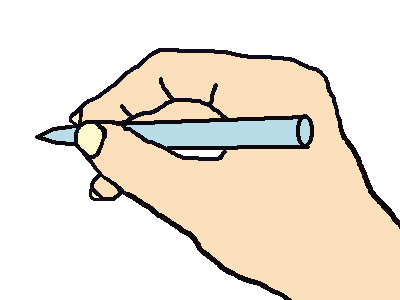 鉛筆で図面を書く練習をした。 会社ではドラフターだった。 CADが会社で使われたのは1980年 頃からだと思う。 |
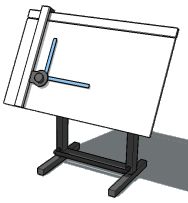 |
当時勤めていた会社では、身分制度というのか資格制度というのか社員の学歴や勤務期間で何段階も階級があった。それを上がるには勤務年限や査定だけでなく学科試験もあった。ペーパー試験には専門科目の他に数学や英語があり、英検2級以上(当時TOEICはもちろん、英検準1級も準2級もない)であれば英語は合格だった。
というので英検2級を取った。楽勝!
危険物乙種は現場の人は皆持っていて、持ってないと一人前に見なされない雰囲気でした。とはいえ私は実務経験がありませんから、総務に行って受験したいので実務経験を書いてほしいと言ったら、担当のジジイがお前なんて受験しても合格しないとうそぶきます。いやなジジイです。しょうがない受験のためと頭を下げてお願いしました。もちろん合格しました。
*ところで、実務経験がないのにあるように会社が証明することは違法じゃなかろうか?
まあ会社では忙しいときは塗装や調合を手伝うこともあり、まったく無縁だったわけでもないのでよいのかもしれない。もっとも1988年から乙種危険物取扱者の受験資格から実務経験は削除された。
数年後、甲種危険物の資格を持っている人が定年退職したので、件のジジイが私のところに来て、ぜひ甲種を取ってほしいとやってきた。社内では私が一番合格間違いないと思ったわけだ。もちろん受験料会社持ち。これも合格しました。
しかし嫌なジジイですよね。立派な反面教師です。いや私は彼を見習ったので、性格が悪くなったのでしょう。
そんなふうにして作業環境測定士とか環境計量士とか受験しました。これらはペーパー試験だけでなく、合格後に一週間も講習会に参加して修了試験に合格しないと、資格が取れません。1週間休暇取るのも大変で、しかも講習会の受講料がとんでもなくかかります。だからペーパー試験に合格してもほとんど講習は受けません。環境計量士を持っているという人も、9割は試験合格だけで環境計量士の資格を持っていません。
作業環境測定士のときは会社から指名されて受験したので、当然出張扱いで受講料は会社持ちです。しかし環境計量士は趣味です。会社が排水測定を依頼していた計量事務所の人に、計量士になると年収はどれくらいもらえるかと聞きました。その答えは……当時の私より安かった! それを聞いて講習会を受ける気はなくなりました。お金も有休ももったいない。
仕事からみだけでなく、遊び関係もあります。
1970年代、アマチュア無線が大流行しました。当時は携帯電話がありませんから、
 自動車同士で(合法的に)通信するにはアマ無線しかありません。大勢でドライブに行くと、車同士で連絡することが必要になります。信号でひっかかったから遅れるよとか、トイレによっていきますとか、今ならスマホでしょうけど。
自動車同士で(合法的に)通信するにはアマ無線しかありません。大勢でドライブに行くと、車同士で連絡することが必要になります。信号でひっかかったから遅れるよとか、トイレによっていきますとか、今ならスマホでしょうけど。
最初は電話級(今は4アマという)を取りました。これって「完全丸暗記(カンマル)」って冊子を1回読むと確実に合格します。今も「カンマル」あるのかなとググると、今もありました。しかしなんと1300円もする! 当時は300円くらいだったと思います。
でも無線電話ってすぐに飽きた。それでモールスをやろうと同僚と受験することになり、毎日お昼の休憩時間に一人がモールス信号を送り、一人が受けるという練習をした。三月くらい真面目にやった記憶があります。二人して仙台まで行って2アマを受けました。もちろん二人とも合格。でもモールスも何か月もしないで飽きた!
囲碁にも凝りましたね。どんな趣味でも同じですが、クラブに入ると周りが同類ばかりですから、囲碁段位が仲間同士の上下を決めるのです。昇段すると段位の低い人にお辞儀をしろなんて言う人もいるわけですよ。
 それでお互いに必死に上の段を目指しました。
それでお互いに必死に上の段を目指しました。
はたから見れば、段があろうがなかろうが、どちらも常人には理解できない単なる囲碁バカです。
でも段位って強ければもらえるのではありません。昇段試験で一定以上の勝率を上げて、更に何万ものお金を払わなければなりません。初段でも3万+税、四段になれば6万+税。当時はいくら払っても段位が欲しかったのですが、今はアホくさとしか思えません。だって碁に勝つのに段はいりません。強けりゃいいのです。
若い時、剣道と空手もやろうかと思ったことがありました。剣道は防具の汗臭ささに耐えられず数回で止めました。空手も……というわけで段はもちろん級もありません。
運転免許は田舎では必需品です。結婚前は二輪車で休みの日は4時頃から出かけるなんてことばかり。転んだこと、骨折したこと数知れず。
結婚して子供ができると赤ちゃんは泣くのと病気になるのが仕事で、病院へ行くのに車の免許を取りました。
さてそんな人生を歩んできた私も会社をやめて早10年、既に古希を超え、喜寿を目指して爆進しております。米寿くらいまでは生きられるでしょうか? せめて傘寿までは……
前振りが超長くなりましたが、ここからが本題です。
現役を引退して、仕事もせずぶらぶらしている日々、過去に取った資格や検定が役に立ったことがあるだろうか? 老後の暮らしで役立つ資格や検定があるのだろうか?
そういったことを考えました。
前記の資格や検定で役に立つものがあるか?
- 機械製図工
まず関係ないですね。 - 英語検定
私の老人クラブには、退職後翻訳を仕事にしている人もいるし、昔アメリカで工場長だったという人も、欧州で拠点長だった人も、娘さんが欧州に嫁いでいて毎年遊びに行く人も、毎年冬はハワイで過ごす人もいます。みなさん現地語は達者なわけ。
この年になってそういう方と競っても無理っていうもの。
ISO規格でニュアンスがわからなければ翻訳者に聞くこともあり、テレビラジオで聞いたフレーズがわからなければ向こうにいた人に聞けばいい。
私なんぞ数年に1回グアムに行く程度だから、出入国管理での応答、お店での買い物、レストランでのオーダーができれば十分。 - 運転免許
私は今年返納しました。老人クラブでは71歳の私が一番若く返納したようだ。とはいえ80超えて運転して池袋事件のようなことを起こしたくない。千葉県では免許返納するとバス料金が安くなるっていう制度がある。バス路線だけでなくJRも割引きだったらうれしいが、それがないのは残念。💥 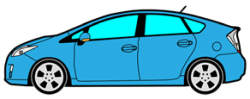

⚟ 
- 危険物取扱者、作業環境測定士、環境計量士、アマ無線、囲碁、ISO審査員まったく意味ありません。
しかしなんですね、30のとき環境計量士の資格があればものすごいと思ったものですが、70になればあってもなくても全く意味のないものです。もちろん甲種危険物も博士も技術士も同じことですが、
私が持ってない資格でも同じです。
- 博士
現役ならばとんでもない資格ですが、引退すればまったく関係ない。元企業の研究所にいた理学博士とかいっても、今なにか研究ができるわけもなく、ただの人です。 - 税理士
こうゆう資格持ちは年とっても引退せずに70過ぎてもまだ働いています。もっとも私の友人で税務署で働いていた人は、定年してから会計事務所で働きましたがすぐに辞めちゃい、今は孫守です。人生働くだけでないのでしょうね。でも老後に介護するより孫守のほうがハッピーでしょう。
おっと、老後役に立っている資格持ちもいます。
通信教育の大学で私と同年配の方と親しくなりました。彼は剣道4段で老後は道場で楽しんでいるとのことです。しかし聞くと道場に来る人は中高年というよりみな老年ばかり。それって老後に役立つ資格ではなく、老人しかいない資格なんじゃないかな?
見方を変えて老人……最近はシニアと自称するそうですが……何をしているのか?
- 折り紙
これをされてる方結構多い。昔からの鶴とかでなく、今は複雑な折り紙をして、それを額装したりする結構ご立派な趣味であります。 - お絵描き
これも多い。多種多様。鉛筆画、油絵、水彩画、描くだけでなく個展を開く方もいる。個展を開くってすごいことなんですね。 - 似顔絵
小難しい絵と違い、だれが見てもわかる。上手な人はモテます。 - 俳句
これは微妙です。素晴らしいと言われても素人はワカラナイ。川柳ならよろしいかも? - 書道
見たことがありません。もはや死語、いや死芸かも? - カラオケ
これはまったく属人的なことで上手下手関係ないです。最近は一人カラオケが多く、上手下手関係ない完全にストレス解消。
言い換えると最高の趣味でしょう。 - 園芸
うーん、まず都会では大きくやろうとしても市民農園などをゲットするのが超困難です。高い倍率の抽選で当選しても3坪程度。マンションの1階の庭の方が広そうです。
最大の問題は、自分で作るより近くにある農家の無人販売所のほうが新鮮で出来が良く安いということです。QCDで劣るのをなんでするの? - 卓球
定年後に卓球を始める老人は男女を問わずものすごく多いようです。家内は子供の時からしてますが、毎年クラブに初心者が入ってくるといいます。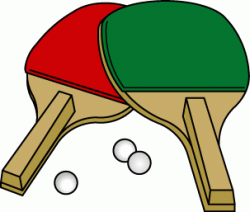 全くの初心者だと、専門のコーチについて数か月習わないと上手にならないといいます。数か月やってラリーが続くようになり、試合ができるようになるのはその先だとのこと。それまでのコーチ代は2・30万になるといいます。
全くの初心者だと、専門のコーチについて数か月習わないと上手にならないといいます。数か月やってラリーが続くようになり、試合ができるようになるのはその先だとのこと。それまでのコーチ代は2・30万になるといいます。
もちろん自己流でもいいでしょうけど、試合に出て勝ち残るようになるのは大変らしい。
とはいえ、歳とともに体が動かなくなりますから、皆に交じって試合ができるのは80くらいだといいます。 それを超えるとランクを落として楽しむか、意地でもランクを落とさず試合に出ないか、
仕事でとった資格が老後に役に立つというのはまずなさそうです。趣味でとった資格が老後役に立つというのも難しい。というのは囲碁も将棋を見てもわかるように、趣味もはやりすたりがあります。スキーの級とか指導員といっても、今の時代は……
老人は体力も視力も若い時と違います。だから折り紙程度ならともかく、細かい模型製作とか顕微鏡を使うような観察は苦手になります。
同様にジャズダンスならともかくあまり激しいスポーツもできなくなる。私の通っているプールでは、80歳を超えた方々は毎日プールに来ても、水中ウォーキングとかアクアダンスくらいになってしまいます。泳いでもせいぜい100や200。そりゃ仕方がありません。
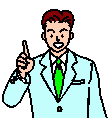 そんなわけで実を言って、老人いやシニアとなったとき役に立つ資格とか検定とか趣味はこれだ!というのはわかりません。
そんなわけで実を言って、老人いやシニアとなったとき役に立つ資格とか検定とか趣味はこれだ!というのはわかりません。
どうせ先が短いのですから、そのときそのとき興味を持ったものに熱中したらいいのかなと……
私は日々泳いでいるのですが、体力は65歳のときに比べて相当落ちてきたと実感してます。現在では一日合計2キロ以下、連続1.3キロ以下ということにしています。準備運動とか水中ウォーキングを含めてプールにいるのは1時間少しです。もし一日4キロ連続2キロ泳げるかと聞かれれば泳げます。でもその後は疲れて夕飯食べたらすぐ寝るのは見えてます。そして歳とともにこれからますます体力がなくなっていくでしょう。
それでスイミングだけではいかんと、次なる趣味というか暇つぶしを探さねばと考えているのです。そして昔取った資格が使えないかと考えましたが、役に立たないことがわかりました。
まあ考えてみれば、役に立つとか、周りから一目置かれるとか、金になるなんてことは全く無意味ですね。最終的には自分が満足できるか、楽しいか、それに尽きるでしょう。
うそ800の目次にもどる
独り言にもどる