私の書いた緊急事態その1について私のブログに、K様とあぐー豚様からご意見を承った。
いただいたコメントに私ごときが快刀乱麻にお応えするなんてできません。それでここに書くのは、緊急事態とか事業継続について私が思っていることであり、お二人の疑問やお考えにズバリ対応するものではありません。噛み合わないのは承知ですが、いろいろな見解を語り合うのも重要だし、その結果進歩があると思います。
そしてまた私の考えを先に言ってしまうとわかりにくいだろうから、その周辺というか前提から話を始めます。とりとめのないのはお許しください。
事業を始めるとは、お金儲けしたいとか、有名になりたいということではない。社会に貢献しよう、具体的に言えば郷土に雇用をもたらすとか、人々に楽しみを与えたいとか、生活必需品を安く提供したい、便利な品物を提供したい、まあそう考えて始めるわけです。
これって建前じゃありません。偉大な創業者はみなそう考えて事業を始めた。
計測器で有名なミツトヨの創業者は貧しい女性が春を売るのを見て、そういうことのないように日本を豊かにしようと考えた。山葉寅之助は人々に楽しみをと考えて、楽器、観光施設、オーディオ製品、バイク、モーターボート、スポーツ用品などの事業を始めた。ヤマハっていろんなものを作っていてとりとめがないように思えるかもしれないが、実は一本筋が通っている。そして松下幸之助は水道哲学だ。
じゃあ、その創業の意思は絶対に守り切らなければならないのか?
世の中は甘いもんじゃない。事業における競争もあるし、景気は定期的に波打っているし、経済恐慌もある。経済だけでななく、戦争もあるし、大災害もある。新型コロナウイルスのような疫病が流行すれば、世界中の航空会社、旅館・ホテル・旅行会社、鉄道・バス会社が真っ青になった。かように創業しても事業を継続していくことは難しい。
現在起業された会社で、10年後残っているのが6%、30年以上続く会社は0.002%だそうだ
 また世の中の技術は進歩し価値観も需要も変わる。いっときは世界を制覇したオートバイは、需要減退どころか需要が消滅しつつあり、新車などめったに出ない。私の二十代のあのバイクの黄金時代よ!もう一度と叫んでも帰ってこない。
また世の中の技術は進歩し価値観も需要も変わる。いっときは世界を制覇したオートバイは、需要減退どころか需要が消滅しつつあり、新車などめったに出ない。私の二十代のあのバイクの黄金時代よ!もう一度と叫んでも帰ってこない。
そんなわけで創業時の技術やビジネスモデルは陳腐化するし、創業時の理念が通用しなくなることさえある。
昔言われた総合家電メーカーなるものは今では存在しない。もうスマホも冷蔵庫もテレビも作ってますなんて会社はない。

そして生き残るための対応はそれぞれ異なる。パナソニックは家電だけでなく今では住環境というカテゴリーになったし、日立はグループを整理しているし、三菱もコアとなるエレベーターとFA以外は切り捨てた。東芝は原子力で躓いてから迷走している
自動車も同じ、トヨタもホンダもポスト自動車を模索している。トヨタは住宅でホンダはロボットと航空機なんだろうか?
造船は……いわないでおこう。
環境変化に適応することができないと会社は継続できない。更に大災害が起きれば物理的に破壊され、簡単に倒産・廃業に至る。
東日本大震災で廃業・倒産した企業は何社あるか? 調査機関や時期によっていろいろありますが、ほぼ2,000社といわれる
おっと通常は毎年年間1万社が倒産しているそうだ。だから東日本大震災で2割上積みされたということだ。2割を小さいと思うか大きいと思うかだが、大きいだろう、ばらつきの範囲ではない。
いかに自社の存続を図ろうとしても、自然災害、疫病、経済恐慌、さらには戦争には抗えない。それが現実だ。そんな時代だからこそビジネスコンティニューを願うのはわかる。だが、それは簡単ではない。
会社の終末といっても、いろいろ。製品やサービスが時代遅れで陳腐化したとか、コンペティターに敗れたとか、災害や戦争で事業継続できなくなったとか、法規制が変わって市場がなくなることもある。パチンコは法律が変われば一瞬で消滅するし、逆に合法的ばくちという産業が発祥するかもしれない。
ビジネス上のハードル、コンペティターとの競争も超えていけるとは限らない。勝ち負けという評価をすれば、負けることのほうが多いのではないか。
しかしBCMといった場合、災害やテロなどの外乱を想定しているのがほとんどだ。そういった外乱以外は事業継続のための策をどう考えているのか? ビジネスコンティニューという語に、市場競争という概念は含まないのか? よく分からない。
これを読んでおられる皆さんの会社では、過去さまざまなプロジェクトがあっただろう。そのうち何割が目的を果たしただろう? 私の見当だが3割成功したならすごいと思う。せいぜい1割か2割ではなかろうか。単なるモデルチェンジならスケジュール通り行くのかもしれないが、新規開発を含むものはスケジュール遅れだけでなく、開発ができずプロジェクト崩れも起きるだろう。
 その多くは外からはわからない。MRJのような広報されたものは多くない。
その多くは外からはわからない。MRJのような広報されたものは多くない。
アメリカのF35戦闘機は問題が次々に発生して完成がどんどん遅れ、どんどん開発費用がかさんだ。とはいえあそこまではまり込んだら逃げようがなく、なにがなんでも達成するしかない。

革新的なボーイング787も難産だったが、生まれてからは育ちが良い。
一方、わずかなモデルチェンジだったはずのボーイング737MAXはトラブル続きである。
言いたいことは、人間が実現しようとしてもなかなかうまくいくものではない。虚仮の一念は岩を通さない。
それは前向きの開発だけでなく、危機に際しての打開策でも同じだ。
電力会社が原発の「メルトダウンを止めろ」と言ってもそれが叶うかどうかは定かでない。まず緊急時において、社員が身の危険を顧みずに働いてくれるかという疑問がある。
一般企業で危険な業務への従事を要求することはもちろん可能でしょう、従業員が納得するなら。
自衛官、消防官が危険な仕事に従事するのは、いろいろあると思います。まずその職を選んだ人が高邁な精神を持ち、危険にもかかわらずその仕事を志願しています。
そしてまた自衛官、消防官は就任するときにその旨宣誓するわけです
通常の企業における就業規則ではそのようなことを求めていません
他方、会社のために行動し殉職したとして、そのときは社葬を出してくれるかもしれないが、100年後も殉職者を祭ってくれるとは思えない。いや100年後、会社があるか定かではない。
話は変わる。
種々の規格や考え方において言葉の意味を考えたい。
まずはISO14001の緊急事態について、
これは問題の種類とか大小に関わりない。今すぐに手を打たなければならないという事態(ありさま、状況)が発生するおそれがあるなら、その対応策を考えなさいという意味です。
工場が火事ならもちろん緊急事態でしょう。すぐさま自衛消防隊は出動し、消防署に火災発生を通報しなければなりません。
シンナー1斗缶こぼしたらどうでしょう?
すぐさまこぼれたシンナーを履きとるなり、布で拭きとらないといけない。ということは、緊急事態であるのも確かです。
緊急事態としたものには、その対応手順を定め、発生に備えてテストし訓練しなければなりません。
 ここまでは異議ありませんね?
ここまでは異議ありませんね?
ハンドラップを倒しても緊急事態かどうか?
放っておけないなら、そりゃ緊急事態でしょう。
おっと、ハンドラップからこぼれたくらいは緊急事態としてないとおっしゃっても、私は文句を言いません。ハンドラップを倒した時の対応手順を、決めて教えて実施しているならですけど、
緊急事態と呼ぶか呼ばないかはまあ好き好きでしょう。でもそのままに放っておけない、すぐに対処しなければならないことなら、どのように対処するのかを決めて、教えて、実施させることは雇用者の義務です。
ISO14001の緊急事態とはコマけえ〜ことだ、事業継続マネジメントシステムで考えるリスクはもっと重大なことなんだ!
そうでしょうか?
事業継続マネジメントシステムだって、前述したように大災害にも戦争にも恐慌にも負けずに事業継続ができるようにしてくれるわけありません。
そりゃそうだよね、なにごともするのは人間というか自分の力、会社の力なんて限界がありそれは非常に小さい。前述したように国家と企業は全く異なる次元です。
それじゃ事業継続のためにどれだけ頑張るのか?
死ぬまで頑張るのか? 一定レベルに達すれば対応を止めて撤退するのか? 各担当者が個々に判断して避難するのか?
組織として、ここまでは頑張らなければならない、この限界を超えたら頑張るのはやめて放棄しなければならない、という基準を決めておかなければならない。
なぜなら組織においてはルールを決め、そのルールで運用するのが鉄則。法治主義と同じです。
ところが不思議に思うのですが、手に負えなくなったときに維持活動を放棄すると語っているBCMってないんですよね。少なくても私が見たものにはない。
内閣府の出している「事業継続ガイドライン
「このトーチカを死守せよ」って、大和魂かよ!
死守せよったって、できないこともある。いやいや、死守せよなんて命令を出す時点で、既に負け戦、実現できないと考えているわけだ。
昔の日本軍は大和魂だったのかもしれないが、現代の事業継続マネジメントシステムなら大和魂ではだめだろう。
大和魂があっても、竹やりではB29を墜とせない、
「事業継続マネジメントシステム(ISO22301)」は、「様々なリスクに備え事業継続にがんばれ」という趣旨であり、「耐えきれなくなった場合には撤退することを定めよ」という語句はない。
ISO規格も無期限の固守命令ですか!? 大和魂は世界に蔓延したのか!
「そんなこともあろうかと」という発想は、ISO規格策定者にはないようだ。チャレンジは必ず成功するのか、成功しなければ死ぬしかないのか?
事業継続マネジメントシステムが登場するときは既に事業が継続できないこともあるわけだし、緊急事態と言われるときには手の打ちようがないときもあるはずだ。
ならば事業継続の努力を放棄する条件を決めろとか、緊急事態対応には対応を放棄する時点を決めとという要求事項があってしかるべきと思うのは私の勘違いだろうか?
勝つか玉砕だという前に、まずそもそも戦争目的とか作戦の目的があるだろう。この目的とはobjectiveでありpurposeではない。purposeは「何事かを行う意図」であり、objectiveとは「達成すべき目標」である。
「あの高地をとれ
実際の旅順攻撃では、203高地攻撃の目的がぐじゃぐじゃになってしまったようだけど。まあ、状況が変われば当初の目的が変わることも仕方がない。
ともかくなにごとも、状況に応じて方針や作戦を見直すべきだ。いったん戦いを始めたなら勝つか全滅するまで戦うではあまりにも作戦が稚拙だ。
大災害にあったときなにがなんでも事業を維持するのではなく、元からその事業の先行きが暗いなら、これを機会にという判断があってもよい。それは被害の程度によって判断が変わるかもしれない。ともかくむやみに泥沼にリソースを注ぎこむことはない。
さて、そんなことを考えると、なんだかぼんやりと見えてきたようだ。そうではありませんか?
簡単に言えば非常事態とか緊急事態といっても、いろいろ種類もあるし大中小の重み付けもある。そしてそれぞれに対して対応策は考えておかなければならないということです。
大問題には対策を考えるが、細かいことには考えてないのも困ります。
ビジネスのコンペティター対応では考えているが、テロ対応は考えてないのも困ります。
そして、カタストロフレベルには考えないことにしているのも困ります。日本人は危険なことを考えると、それが起きそうな気がして考えまいとすることが多い。フラグってやつですか? それでは困ります。常に自分が死んだとき、残された者が困らないように考えておかねば、
| 重大レベル | 環境 | 品質 | 財務 | 人事 | …… | ||||
| 液体漏洩 | ガス漏洩 | ■火災■ | 廃棄物 | ……… | 細分類 | ……… | ……… | ……… | |
| カタストロフ | |||||||||
| 重大 | |||||||||
| 中規模 | |||||||||
| 小規模 | |||||||||
| 平常時 | |||||||||
会社にはいろいろな業務・職務があります。そしてそれぞれにおいて緊急事態が想定できるはずです。
総務なら現役役員が亡くなるのも緊急事態になるでしょう。社葬とか弔問対応は低いレベルでしょうけど。いや、経営そのものにおいては重大なレベルかもしれない。
社員が犯罪を犯せば人事や広報の緊急事態になり、粉飾決算であれば経営にかかわる重大事レベルかもしれない。
いずれにしても緊急事態といっても種類によって所管部門が異なるし、その重大性と規模によって対応すべき範囲と、企業の責任範囲が決まるでしょう。
企業の責任範囲といっても企業が悪いとか最終的に被害を賠償するという意味の結果責任もあるし、異常事態を解消するという実施責任もある。いずれにしても緊急事態対応は、後者に限られるだろう。そしてその実施責任もすべてではない。というか発生者責任と言われても対応できないことが多い。
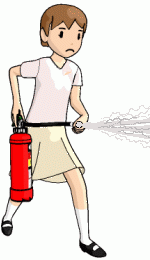
工場から失火して大火災になったとして、工場の自衛消防隊ができることは限定されている。初期消火はがんばっても大きくなれば自分たちだけでは対応できない。
そして火が一つの都市に広がってしまえば消火できないこともある。アメリカの山火事などは消防署どころか軍隊が出てきても手におえず、自然鎮火を待つしかないこともある。それが現実である。
そもそも事業継続マネジメントシステムがあれば、ないときより生存性が高まるのだろうか?
ISOMS規格共通の疑問だが、QMSは顧客満足、EMSは遵法と汚染の予防など規格の意図ははっきりしているが、そのマネジメントシステムがあれば規格の意図が実現できるという保証はない。
もちろん事業継続マネジメントシステムがあれば、天災、テロ、動乱などが起きても、システムがない時より少しは改善されるという理屈も証拠も見たことがない。
そもそもというか、ISO9001認証すればしてないより顧客満足が向上するか? ISO14001認証企業は非認証企業より遵法が良くて汚染が少ないなんてことは聞いたことがない。事業継続マネジメントシステムでは…と思う根拠がないというよりも、思うはずがない。
まあ、ないよりはあったほうが良いという気はする。気はするが……その差はほんのわずかだろうと思う。あるい差なんてないのかもしれない。
■さて、まとめに入る。
QMSとは簡単に言えば、一定条件下で一定品質のものを作るという規格と理解している。
EMSは組織を取り巻く環境が変動しても、環境パフォーマンスを一定に維持しようという規格である。
そして事業継続マネジメントシステムは、組織を取り巻く環境が大きく変化したとき、組織の活動のプライオリティを考慮し維持に努めることが目的と理解する。
下図を見てほしい。昔々私が思い付きで作ったものだ。
縦軸は生産力としているが、それは製造業の場合であって、他の業種、例えば市役所なら行政サービスのパフォーマンスでもいいし、学校なら授業を行う割合でも良い。
横軸は異常事態の度合いとして、何も起きていない平常時から破滅的な状況までを考える。いずれにしても単なる概念図である。
横軸の外乱があったとき、生産力あるいは類似の指標の低下を模式的に示した。
いかなる事態が起きようと生産力を高く維持することが理想だが、カタストロフィレベル例えば東日本大震災ではゼロに近くなるだろう。ともかくどのような事態でも、いかにパフォーマンスを持ちこたえるかが要点だ。
何も対策がないときをグレーの線で示せば、災害など外乱を受けても、できるだけパフォーマンスをあげるつまり上方にカーブを持ち上げることを考えなければならない。
カタストロフレベルの災害では、いかなるマネジメントシステムがあろうとパフォーマンスは向上しない。
だって人間ごときが考えるような対策でどうにかなるならカタストロフィじゃない。
さて具体的なISOMS規格を考えるとどうだろう?
ISO9001はその性質から大幅な向上はないと考える。
ISO14001は青線くらいになるのかなと思う。緊急事態の範囲をどこまで考えるか、そしてその対応をどこまでとるかで変わるだろう。もちろん環境限定である。財務やテロの危機に際して、ISO14001の緊急事態対応が有効であるはずがない。
BCMSであれば紫線くらいの効果があってほしいと思う。とはいえ前述したようにかようなマネジメントシステムが実際に有効である保証もない。
誤解なきよう、私はマネジメントシステムがあれば、ないよりも効果があるとは言ってない。効果がなくちゃ存在意義がないと言っている。
マネジメントシステムを売り込んでいるJABや認証機関は、こういったパフォーマンス効果を実測して公表してほしい。そうすれば会社を良くするなんて歯が浮いたようなことでなく、皆を信用させる効果は大だろう。
だが私は思う、
認定機関にしろ認証機関にしろ、このようなデータを持っていたとしても、恐ろしくて公開はできないだろう。
改善できる数字が大きければそれを維持しなければならず、低ければ……
![]() 本日のそんなこともあろうかと……
本日のそんなこともあろうかと……
ドラマだとトラブルや危機が度重なっても「そんなこともあろうかと」と、そのつど打開策や秘密兵器が現れ危機を乗り越えていく。だが現実はそんなことはない。
一度や二度ピンチをかわしても、いつかは避けきれず試合終了となる、それが現実だ
であっても、万が一に備えて対策をとるのは当然だ。一度だけでも回避できれば、できないよりも生存率は高まる。神ならぬ人の身、成しえることはそれくらいだ。その努力を笑ってはいけない。
だが安全性を高めようとして、あまりにもリソースを投入しても主客転倒だ。そのさじ加減がリスク管理だ。
思い出したことがある。半世紀も前のこと、当時の同僚がものすごく高額な保険に入っていて、月々の支払いが大変だと語っていた。独身だったのに、なんでそんなに保険をかけていたのか?
実は事業継続マネジメントシステムについてははるか8年も前に、グリーン認定というお話で論じたことがある。それから8年間私は進歩しなかったのか、そのとき既に悟っていたのか定かではない。
注1 | ||
注2 | ||
注3 |
2006年に東芝は、原子力発電の大手ウェスティングハウス(WH社)を買収した。当時同業他社は顔色を失った。 しかし2011年の東日本大震災で原子力発電の評価は反転し、原子力発電需要がゼロになった。その後も巨額損失隠しなどが発覚し評価を落とした。 | |
注4 |
"震災から8年"「東日本大震災」関連倒産状況(2019.02.28) 2000社 震災9年、被災企業の3割が休廃業(2020.03.06) 1700社 「東日本大震災関連倒産」(2016.03.01) 1900社 | |
注5 |
| |
注7 | ||
注8 |  「あの高地をとれ」とは、1953年のMGMの戦争映画。
「あの高地をとれ」とは、1953年のMGMの戦争映画。戦争映画といっても戦いはない。リチャード・ウィドマーク扮するライアン軍曹が、民間人を一人前の兵士に鍛える物語である。 ラストでライアン軍曹は昇進もせず彼女にも振られるけど、巣立っていく新兵たちから尊敬と感謝を受ける。 軍曹にとっての高地は、彼女でも階級でもなく信頼だったのだろうか? |
外資社員様からお便りを頂きました(2020.10.11)
いつも乍ら、本旨に無関係な部分ツッコミでご容赦を。 靖国神社 >逆に言えば国家は戦死者との契約を無視しているのだ。 お気持ちは判りますが、そもそも靖国神社の存在が、戦前と敗戦後で法的にも国家体制の中でも異なるのですから、無理ですよね。(お判りの上でのコメントと思いました) 読者向けの蛇足ですが、戦前の靖国神社は国家管理で運営は内務省・旧陸海軍の3者協議。 祭神になるには、陸海軍からの承認が必要でした。 敗戦後のGHQ指令で、解体と宗教法人になれとの選択で宗教法人となり国家との縁が切れました。 占領から復帰した時点で、戦前と同じ国家管理への道への復帰として「靖国法案」が国会で審議。 ですから戦死者との契約は、国民の代表である国会で否決されました。 これをいうならば戦前の「官幣社」などは、神と国家との契約とも言えますが、これも同様に放棄。 政教分離原則は戦前から問題になっており、国会答弁では官幣社や国家神道は非宗教だと政府見解があるので、これは宗教では無いという政府の判断。(明治15年 内務省通達による神社非宗教論) ならば「靖国神社における神とは」、この問題は戦前から専門家の間では議論になっており、本来は法的な位置づけや、政教分離原則との整合性も国会で徹底検討されるべきだったのでしょうね。 それが、曖昧であったツケが、GHQからのツッコミや、戦後 靖国法案の廃案にも繋がったのだと思います。 せめて、海外の非宗教的な戦死者追悼施設のような配慮や法的整合性も考慮していれば、もっと違う展開もあったのだと、その点は残念です。 表題に戻れば、重要な原理原則論は、しっかりと明確にすべき所をあいまいにして、敗戦という緊急事態で対応を誤ったという感想です。 |
外資社員様 毎度ありがとうございます。 ご存じと思いますが、このウェブサイトの発祥は、靖国問題でした。 私の叔父二人が戦死し、おやじの兄弟たちも老いて亡くなり、私の世代の従弟たちも上から順にかたづきつつあります。今は私の息子世代になっていますが、彼らは全国に散らばり叔父世代の墓はみな生前住んでいた地域にあり、戦死した叔父の焼香には来ないんじゃないかなと思います。私の息子さえ、私が生まれるはるか前に戦死した大叔父の冥福を祈るという心情にはならないでしょう。 私が子供の時、叔父たちがみな都会に出て行ってしまい、唯一田舎に残った親父がお彼岸、お盆、戦死した命日にお墓に行くときに、私を叔父の墓に連れていき、冥福を祈ると親父に教えこまれました。 そんな私自身も都会に住み着くと田舎に帰るのも年に2回程度、それもあと10年でしょう。それに私が死ねば家内はこちらに墓地を求めるといいます。まあ今や親せきも住んでいない田舎の墓地に、骨を埋めても家内も息子たちも困るだけです。そうなればだれが叔父たちの冥福を祈ってくれるのか。すぐさま無縁仏ですか、ひどすぎます。 2000年頃、首相の靖国参拝でおおもめにもめたとき、私は戦死者を国が大事しろ、具体的には首相靖国参拝しろと抗議するためにこのウェブサイトを開設しました。あれから19年になります。全然進展はありません。 まあ、そういうわけで靖国には敏感です。 国家の責任といっても靖国神社を国が管理するとは違うと思います。毎年国会議員が参拝しただけでサヨク新聞、サヨク政党は大騒ぎです。正直言って、天皇陛下だって参拝の義務があると思います。根拠とかなんかの理屈ではなく、日本の象徴を名乗るなら、日本を代表して参拝するのはアプリオリです。 毎年、天皇陛下、首相、野党党首を含めて参拝していただけるなら、田舎の叔父の墓に線香あげに行けなくなっても私は安心できるというものです。 千鳥ヶ淵の施設なんて言わないでください。あんなちゃちなもの、国の施設とは恥ずかしい。靖国はいきさつがあるからというなら、もっと立派な施設を作ってほしい。それと一般戦没者と戦死者はやはり位置づけが違うと思います。まあ、それはまた別の論点です。 私が死ぬ前に、戦死者を祭ることをしっかりしていただきたいと願うばかりです。 |
うそ800の目次にもどる
ISO14001:2015年版規格解説へ