- p.10�@���̎d���ƃ}�l�W�����g�V�X�e��
���Ђ̃E�F�u�T�C�g����邱�Ƃ��ɂ��āA�v���d�l�̖��m���������ɕK�v���A�ύX�E����̎d�g�݁A�ӔC�E�����̖��������ă}�l�W�����g�V�X�e���̏d�v��������Ă���B
�Ƃ�������낤�Ƃ��Ă��邪�c�c���Ⴊ�s���Ƃ��Ȃ����A���グ�Ă��鎖�����ǂ̋K�i�v���ƑΉ����Ă���̂����s���m�ł��܂�ǂ��o���ł͂Ȃ��B
�uISO9001�̓����v�̃��[�N�V���b�v�@�ip.111�j��uISO14001�̓����v�̃��[�N�V���b�v�A�ip.127�j�ł��������Ƃ����������A�w�i����̐ݒ�Ƃ��̐����Ȃǂ��Ƃ��b�Ƃ��Ă̏o���������̂��B
�����ԌÂ����u������Ƃ̂��߂�ISO9000 �����Ȃ��ׂ����@ISO/TC176����̏���(��2)�v�Ƃ����{������B���̒��Ńp�������ɂ����A�i���ۏɓw�߂��q�l�̐M���镨�ꂪ����B�������A���̖{�ł͒��ꂽ���ƑK�i�v�����ԂƂ�������Ή����Ă���B
���Ђ�_���������Ƃ��͐�s�����̒����͕K�{���BISOMS�̖{�������l�Ȃ�A�ߋ��ɏo�ł��ꂽ�L���Ȗ{�͂���ǂ���Ă���Ǝv���B���ꂭ�炢���A���Ŋ�����^������̂������Ăق����B
- p.21 �����Ȑ��{�ƃj���[�A�v���[�`
���̖{�ł́A�C�M���X�̔F�ؐ��x����ɂ��ĕ��y�����Ƃ���A�X�ɃC�M���X���F�ؐ��x��ISO9001���̗p�����̂͐挩�̖������������L���Ă���B
���������Ď������M���Ȃ��̂����A�C�M���X��BS5750�ŔF�ؐ��x���J�n���āAISO9001�����肳��Ă���1987�N��ISO9001�ɍ��킹���悤�Ɋo���Ă���B�L���������܂��Ȃ̂����B
�C�M���X��Google�Ō����������͂�����Ƃ����؋��͌�����Ȃ��������A1995�N�쐬�̂��̂�BS5750�ő�O�ҔF���s���Ă����ƋL�q���Ă�����̂͂�����(��3)�B
- p.31 �}�l�W�����g�V�X�e���F�ؐ��x�Ƃ�
���낢��Ɨǂ����Ƃ������Ă��邪�킩��Ȃ����Ƃ�����B
�ЂƂ́u�F�v�̐������Ȃ��B�F��������Ȃ閼�_������̂��A����������̂��A���v������̂��S��������Ȃ��B����͂��ЂƂ������Ăق����A�Ƃ������K�v���B
����ISO�F��25�N�ւ���Ă������A�����ɔF�̌��ʂ�������Ȃ��B��������ς���ƔF�̑��݈Ӌ`�͉����낤�H
ISO�F�؋@�ւ̐R�����������W�܂��ď������{���B���҂����͏\�ɂ��̗L�����𗝉����Ă���͂����B���̂悤�ȋ��҂ɂ��ЂƂ������������肢�������B
���_�A�F����Ă��Ȃ��F�؋@�ւ͔F���Ă���F�؋@�ւƓ������炢���݂���B���{�ł�JAB�̔F����Ă��Ȃ����Ƃ���A�m���W���u�ƌĂ�Ă���B
���̖{�ł͔F�؋@�ւ͂��ׂ��炭�F�����悤�ɋL�q���Ă���B�����̂Ƃ���͐����s�����낤�B
���̖{�́u�͂��߂Ɂip.3�j�v�ŔF���Ă���g�D���炢�낢��Ƒ��k���Ă��邱�Ƃɑ��Ẳł���ƋL���Ă���B�Ȃ�ΔF�؋@�ւ̔F��̗L���ɂ��Đ������Ă��Ȃ��̂͑傫�����r�ł��낤�Ǝv���B
- p.34 �l�X�ȃ}�l�W�����g�V�X�e���K�i
p.34 �Љ�E�ƊE����̗v���ɉ�����}�l�W�����g�̕K�v������A���܂��܂Ȏ�ނ̃}�l�W�����g�V�X�e���K�i���a�����Ă��܂����B
��u�A�ڂ��^������B�����������̂��I�ƒr�㏲�̂悤�ȃZ���t����邪�A�}�l�W�����g�V�X�e���K�i�͗v������č��ꂽ�������B�Ȃ獡���ݔF�،������킸�������Ȃ�MS�K�i�͂ǂ������̂ł��傤�H �{���͗v������ĂȂ������̂ł��傤���H
JAB�F���ISOMS�F�،���
| ISOMS�K�i�ԍ� | �K�i���� | 2022.05.10���_
�F�،��� | 2020.03.25���_
�F�،��� |
| ISO9001 | �i���}�l�W�����g�V�X�e�� | 23,232 | 27,372 |
| ISO14001 | ���}�l�W�����g�V�X�e�� | 12,846 | 14,894 |
| ISO/IEC27001 | ���Z�L�����e�B�}�l�W�����g�V�X�e�� | 13 | 10 |
| ISO5001 | �G�l���M�[�}�l�W�����g�V�X�e�� | 4 | 7 |
| ISO13485 | ��Ë@��i���}�l�W�����g�V�X�e�� | 195 | 231 |
| ISO22000 | �H�i�}�l�W�����g�V�X�e�� | 1,146 | 1,001 |
| ISO55001 | �A�Z�b�g�}�l�W�����g�V�X�e�� | 76 | 60 |
| ISO45001 | �J�����S�q���}�l�W�����g�V�X�e�� | 227 | 12 |
�ǂ����c�F�،����͐L�тĂȂ��ǂ��납�����Ă���̂�����悤�ł��i�����Ȑ��j
�u�v���ɉ����āv�Ƃ́A���s�I�ȏ�k�Ȃ̂ł��傤���H
- p.40 PDCA�T�C�N��
ISOMS�K�i�̉����ǂނƁA99%�̖{��PDCA���̗p���Ă���Ə����Ă���B
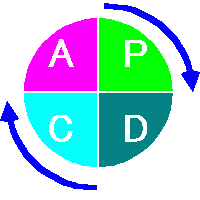 ����100%�f�ʂŐ^�ʖڂɕ����̂����A�d���ł����ł�PDCA�łȂ��v���Z�X�̍s��������̂��^�₾�B
����100%�f�ʂŐ^�ʖڂɕ����̂����A�d���ł����ł�PDCA�łȂ��v���Z�X�̍s��������̂��^�₾�B
���Ԏ������A�ł��}���K���ʔ���������̓p�X�A�_���������Ĕ��Ȃ����A���������̓}���K��ǂ܂��������A�����_�����オ�����c�cPDCA�ł͂Ȃ����H
�l�Ԃ����łȂ������ł��A�ڕW�����肻���ڎw�����s�����Ƃ�ΕK�R�I��PDCA�ɂȂ�Ƃ����v���Ȃ��B�܂���������PDCA��m��Ȃ����낤�Ȃ�Č����Ă͂����Ȃ��B
�A���ł��𒎂ł��AA�n�_����B�n�_�Ɉړ����Ă���Ƃ��A������ז�����Γ�x�O�x�͓����Ӑ}�������[�g��ʂ낤�Ƃ��邪�A�₪�Ē��߂ĕʃ��[�g��T��悤�ɂȂ�B
����͂܂���PDCA�ł͂Ȃ��ł��傤���H
- p.41 �g�D����芪���̗���
p.41�uISO��p�iISO�R���̂��߁j�̓����E�O���̉ۑ�����肷��̂ł͂Ȃ����Ƃɗ��ӂ��܂��傤�v
���h�ȕ����ł���B����łȂ��S�ꂻ���v���B���̐S�\���ōŌ�܂œ˂��ʂ��Αf���炵���c�c�Ǝv���B
�������Ⴆ�Ί����ʂɂ����u���e���]���v�Ƃ��u�����ʂ̓���v�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�ĕ��͂��o�ꂷ��̂͂Ȃ��H �ߋ����疼�̂��قȂ��Ă��Ă��������������͂���Ă���Ƃ����l���͋N���Ȃ����̂��낤���H
���̂͂Ƃ������A���ւ̉e�����l���A�@�K�����l���āA������Y���Ƃ���p���l���������ʁA�N�x�v��Ƃ������v�悪����Ă���ƍl���͋y�Ȃ��̂��낤���H
���⒘�҂������߂Ă�����Ƃł́A�N�x�v��⒆�����v��ł͊����ʂ�@�K���̓����Ȃǂ��l�����Ȃ��Ōv��𗧂ĂĂ����̂�������Ȃ��B���̒��͍L������B
�Ƃ�������邱�Ƃ���т��Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�M�O�������ď����Ă���̂ł͂Ȃ��A�v���t���ŏ����Ă���̂��H �ߋ��̌o����m�������Ƃɂ��Ăł͂Ȃ��A�z���ŏ����Ă���̂��H
- p.44 �g�b�v�}�l�W�����g�̖����Ƃ�
�ǂ�ł��Ăǂ������肪�����Ƃ������A���������Ǝv���B
�g�b�v�}�l�W�����g�����鎖���Ȃ�đg�D�����߂邱�Ƃł���BISOMS�K�i�Ō��߂Ă��邩�炱�̖����₠�̐ӔC���g�b�v�}�l�W�����g�ɂ���Ƃ������z�͂��蓾�Ȃ��B
�����̑g�D�ɂ́A����̒��Ƃ���Ă���l�łȂ��A���ƂƂ��g�b�v�̌����҂Ƃ��g�D���Ől�]������l�Ȃǂ����ٌ��������Ă���ꍇ������B����͐E���ƌ����̌���������Ă��邱�Ƃł��萳���ׂ����낤���A�����łȂ��Ȃ�\���ɐE���͋@�\���Ă���͂����B
- p.45 ���j�Ƃ�
���̍l������j�́A��ʂ�ISO�{�ɏ�����Ă�����̂Ƃ͈قȂ�B�ڂ����͎����ߋ��ɏ������u���j�ĉ��Ȃ̂�v���Q�Ƃ��Ăق����B
���j�Ƃ͉������m��ɂ́A���ꎫ�T�������Ă��d���Ȃ��BISOMS�K�i�̒�`���p��œǂݕԂ����Ƃ��őP�ł���B
���������E�ɂ͉p�p���T��Y�ꂸ�ɁA
- p.47 �\3-4-1�@�ӔC�E�����̊��蓖�Ă̗�
�}�����uISO�ӔC�ҁv�Ƃ����̂�����܂��āA�u����MS�̊m���A���{�y�шێ����m���ɂ���`�������A���P�ɕK�v�`�̎��{�������ɕ���v�ƋL�ڂ��Ă���B
����͈Ӗ��s���ł���B�̂̊Ǘ��ӔC�҂̂��ƂȂ̂��낤���H
�K�i�ɂȂ��p��Ƃ����d���������Ȃ��ł��������B
- p.51 �v��Ƃ�
�O�ɂ��q�ׂ����A���X�g�����̌v��Ōڋq�����̌���Ɣ���A�b�v�����グ�Ă���B
�^��_��������B
�ЂƂA����A�b�v���ɂƂ邱�ƂŁAISO�F�͔���A�b�v�ɂȂ���Ƃ����F����^����̂ł͂Ȃ����낤���H ���͂�������O����B
�ӂ��A�ڋq�����̌���Ȃ炻�̎w�W�ƖڕW�l�������Ȃ���Όv��ł͂Ȃ��B
���̖{��ǂl���A�̗p�����ƐV���j���[�J�����ڋq�����̎�i�Ƃ݂Ȃ����ƔF�����āA���l�̌v����쐬���Ē����ꍇ�A���̔F�؋@�ւ̐R������OK����̂��낤���H
- p.52 �ړI�Ƃ�
�u�ړI�v���u�ڕW�v���ƂȂ�A�ڕW�����������낤�BISO9001�F1987����g���Ă���R���i�j���錾�t���B
ISO14001:1996��objective��ړI�Atarget��ڕW�Ɩ��̂��g���u���̎n�܂肾�����B2015�N�ł�objective�͖ڕW�ƂȂ����̂�����A�ړI�Ƃ���Ӑ}���킩��Ȃ��B
���ꂩ��{�肾���A���낢�낲���Ⴒ�������Ă���̂��݂ȍ폜���Ă��܂��AISO14004�F2016�́u�\A.2-�����E���i�E�T�[�r�X�A�����ɔ��������ʁA�ڕW�A���{�v��A�w���A�^�p�Ǘ��A���тɊĎ�����̗�v���y�^�b�Ɠ\��t���Ă������ق������ɗ����낤�B�����ق����ꔭ�Ŕ[�����邾�낤�B
�����Ƃ�������������ɐR�������Ƃ��c�cJQA�ł͂Ȃ������c�c�R���������܂�ɂ��A�z�Ȃ̂ŁA���̕\�i������2004�N�Łj�������Đ�������Ɓu�K�i�[��莄�i�R�����j�̂ق����������v�ƌ����Ă��̕\���̂����BJIS�K�i�[���������Ƃ��Ȃ��̂��I ���̔y�ɂ͎��炲���������������B
- p.56 �͗ʂ��m�ۂ��鏈�u�Ƃ�
�����݂͕ۗL���Ă��Ȃ��K�v�ȓ����E�Z�p�E�Z�\�E���i�Ȃǂ͊J���Ƃ��{������̂ł͂Ȃ��A�����Ă���A�̗p����Ƃ����ق��������B���̒��̓����������Ȃ艽�N���҂Ȃ�Ăł��Ȃ�����B
���̖{�ł������Z���X�ł��邪�A�u�͗ʂ̂���v����V�K�̗p���邱�Ƃ�Ɩ����̂��̂��A�E�g�\�[�X����v�ƋL�q���Ă���B���������̂Ƃ��̗͗ʊm�F�̕��@�Ƃ��m���ɂ����؋��Ȃ���̂��ǂ��������Ƃ������Ƃ��ۑ�Ƃ��Ďc��B
�����͂ǂ��܂ŗv������̂��H �����̐R���ł͐��|���_�ɂȂ�̂���ł���B
�����Ƃ������R�����̗͗ʂ́A�R�����I����Ă���ł���������Ȃ��B
����͂��̖{�̎���͈͂ł͂Ȃ���������Ȃ����A�͍ڂ��Ă��Ȃ������B
- p.59 �^�p
�^�p�̏d�v���ɂ��Ă͉��������ĂȂ��B�����������̍��Ԃ�ISO�K�i�����������ŏ����B�������Ƃ��Č��߂�ꂽ���Ƃ��m���Ɏ��s������Ă̂���ԓ�����ǂˁB
- p.61 �p�t�H�[�}���X�]��
20�N�ԋ^��Ɏv���Ă��邱�Ƃ�����B����͓���Ǘ����B�d�����������ǂ����A�܂蔄��A�J���A���B�A���Y�A�i���A���S�A�o�Η��A�\���A�������������̂�������5W1H��N���ǂ̂悤�Ɍ��Ă���̂��H
�ȒP���Ă��B�Ǘ��҂ł���B�����̐i���Ȃ琻���W���A�J�����������͊J���ے��A�H��ŃP�K�l���o�ĂȂ����Ȃ瑍�������A�����������Ɍ��܂��Ă���B���ꂪ�E�����B
�����ǂ�����������Ǘ���ISO�K�i�ɂȂ���ˁB
�������u9�p�t�H�[�}���X�]���v������A���̒��Ɂu9.1.1��ʁv������B�����ǂ��̕��͂�ǂ�łȂɂ�������Ǘ����d�v�����ēǂ߂邾�낤���H
������ǂ̉�Ђ�����Ǘ��ȂǏd�v�łȂ��Ǝv���Ă���̂��B����K�i�쐬�҂�����Ǘ��ȂǏd�v�łȂ��ƍl�������炱�������������Ȃ��̂��낤�B
�O���́u�^�p�v���d�v���Ǝv���ĂȂ��낤�ˁB
���̖{�̒��҂��A�����č��ɂ��Ă̓_���_���Ɓc�c���Ƃ��A���ߍׂ��������Ă��邪�A����Ǘ��ɂ��ẮA�����Ă���̂��E���Ȃ��̂�������Ȃ��B
�����č��Ō���悤�Ȃ��Ƃ́A����㒷���m�F���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��B�����č��Ō����Ă���x�ꂾ�B
| 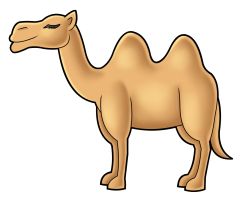 |
| ���N�_�͊y����Ȃ��� |
�݂��PDCA�����̂͑�D��������ǁAPDCA�̃T�C�N���^�C���Ƃ��Ď��̃T���v�����O���[�g�Ȃǂ����l�ɉ�������Ƃ��Ȃ��B
����͊T�O�����͒m���Ă��Ă��A���H���Ă��Ȃ�����ł͂Ȃ����Ǝv���B�{��ǂ�ŁuPDCA�͑厖�ł���v�ƌ�邾���Ȃ�y���ˁA
- p.61 �����č��Ƃ�
p.62 �u�����č��ɂ́A�傫��������2�̖ړI������܂��B1�ڂ́A�}�l�W�����g�V�X�e���K�i����߂�v��������g�D������ݒ肵�����[���A�ڋq����̗v�������ɓK�����Ă��邩���m�F���邱�ƁB2�ڂ́A�Ӑ}�������ʂɑ��Ăǂ̒��x�B�����Ă��邩�m�F���邱�Ɓv
41�y�[�W���uISO��p�iISO�R���̂��߁j�c�c����̂ł͂Ȃ����Ƃɗ��ӂ��܂��傤�v�Ƃ܂Ƃ��Ȃ��Ƃ�����Ă������A�O�������ƁA����20�y�[�W�i�ނƖY��Ă��܂����悤���B
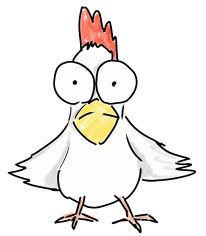
���̎O���Ƃ́A���i���Ƀj���g���͂��܂茫���Ȃ�����j�O�������ƖY��Ă��܂����ƁA��������悭���Y�ꂷ��l�̂��Ƃ������B
�����č��͉��̂��߂ɂ���̂��H ������͂����藝�����Ă��Ȃ��ƁAISO�K�i�Ή��̓����č�������悤�ɂȂ�B�����̋K�i�ŔF����Ƃ��ꂼ��̋K�i�Ή��œ����č�������悤�ɂȂ�A�w�E�����Ɨv�����������킹�čs���悤�Ɍ������āA����R���ŖJ�߂�ꂽ�肷��B
�l����܂ł��Ȃ������č��͈�����Ȃ����낤�B�����ISO�R���Ō������낵���B�����Ƃ��i�D�G�ȁj�R�����͊�Ƃ̎菇���Ɋ�Â��ē����č������Ă���ƁA
 ISO�K�i�v��������ԗ����Ă��邩�ǂ����킩��Ȃ�����s�K���ƃA�E�g�̃[�X�`���[�������肷��B
ISO�K�i�v��������ԗ����Ă��邩�ǂ����킩��Ȃ�����s�K���ƃA�E�g�̃[�X�`���[�������肷��B
�����������͂�������������������B�@�ˁ@�u�K�i�Ȃ�Ēm����v
�������̎��̘_�Ɉًc�E�^�`������A���œ��_�����Ă��炢�܂��B
���̍l���́�ISO�Ή��̓����č��ȂǂȂ����Ƃ������̂ł��B
����͉̂�Ђ̓����č��ł��B
- p.72 �ړI���l����
�u�}�l�W�����g�V�X�e�������̖ړI�m�ɂ��܂��傤�v
�܂��^��ł���B���ɑ��݂��Ă����Ƃɂ������}�l�W�����g�V�X�e���\�z�Ƃ͂ǂ�ȈӖ��Ȃ̂��낤�B�܂��}�l�W�����g�V�X�e�������邱�Ƃ͂ł���̂��낤���H
�g�D�ł���Ȃ���ׂ��炭�}�l�W�����g�V�X�e����������Ă���B�}�l�W�����g�V�X�e���������Ȃ��g�D�͑��݂��Ȃ��B
���҂́u�}�l�W�����g�V�X�e�������v�Ƃ������̂��A�����Ȃ邱�Ƃƍl���Ă���̂��낤�H�H
�Ƃ��������̕����͊��ɏo�Ă���41�y�[�W�uISO��p�iISO�R���̂��߁j�c�c����̂ł͂Ȃ����Ƃɗ��ӂ��܂��傤�v�ɖ�������悤�ȋC������B
���Ȃ�^�₾���A�}�l�W�����g�V�X�e�����\�z���邱�Ƃɂ��u���㑝���v�u���i�i������v�u�g�D�̒m���x����v�u�[���Z�k�ip.14�j�v�Ȃǂ����P�����Ƃ��Ă���B
���҂̓}�l�W�����g�V�X�e��������ƁA�����������Ƃ��\���ƍl���Ă���̂��H
���͒��҂̍l�����킩��Ȃ��B�͂����肢���Ă���Ȃ��Ƃ͕s�\�Ƃ͌���Ȃ����A�֑�L�����낤�B
���́up.84�R�����郁���b�g�v�ł�����Ɛ����������A�����Ŏ��������˓I���v(��5)�̊��Ⴂ�ł͂Ȃ��낤���H
- p.73 �g�D��m��A�K�i��m��
�}4-1-1�u�����̎d�g�݂�K�v�ɉ����ďC�����č\�z�v
����ɂ͑S�������ł���B�ł͂��邪�A�Ȃ����ׂĂ̍��ڂɂ����āA���̔��z��O�ꂵ�Ȃ��̂��傫�ȋ^�₾�B
�o���_�ɂ����āA�����̎d�g�݂�K�v�ɉ����ďC������Ƃ����Ȃ���A�e�_�ɓ���Ƃ����Y��Ă��܂��̂��s�v�c�ł���B
- p.74 �S�̂Ɏ��m���A�^�p���n�߂�
�O���ł��q�ׂ����A�F�̂��߂̊����͑S�̂ɋy�Ԃ��Ƃ͂Ȃ������Ή��ōςނ��Ƃ��قƂ�ǂł���B����đS�̂Ɏ��m����K�v���A�傰���ɉ^�p���n�߂邼�ƍ��߂�������Ӗ����Ȃ��B����Ȃ��ƃC�x���g����Ȃ��A�E����ʂ��Ēʒm����ςނ��Ƃ��B
����ISO�F���邱�Ƃ��Г��Ɏ��m�����Ȃ��������Ƃ�����B�����ĂقƂ�ǂ̏]�ƈ����]�v�Ȏd��������K�v���Ȃ����炾�B
ISO�F�Ƀ`�������W���邱�Ƃ��Г��Ɏ��m���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƌ�����R�����������B������T���Ă��A���̗v�������ishall�j����������Ȃ������B
 �R�����͎����̐R�����ŏd�v�łȂ��Ƃ��s���炵���B
�R�����͎����̐R�����ŏd�v�łȂ��Ƃ��s���炵���B
���̌o������ISO14001�̐R���ōH�꒷���u�ŏd�v�Ȃ��̂͊������ł͂���܂���B�i�����A���S���A���v���c�ŏd�v�Ȃ̂ł��v�ƌ�����B
����ƐR�����́u�����ŏd�v�ƔF�����Ăق����v�Ƃ����B
�����o�J���A�A�z����2���Ԃ���c�c�����������l�����ʗp����ƔF�����Ă���̂ł��傤�˂��`�A
- p.75 �}�l�W�����g�̌`��
�uISO�}�l�W�����g�V�X�e���K�i�ɏ�����Ă���}�l�W�����g�̘g�g�݂͂܂��Ɉ�ʓI�A�W���I�Șg�g�݂ł����āA�}�l�W�����g���̂��̂ł͂���܂���v
�ًc�����I
ISOMS�K�i�Ƀ}�l�W�����g�̘g�g�݂͏�����Ă��܂���B���������V�X�e���̎O�v�f�́A�g�D�E�@�\�E�菇�ł����AISOMS�K�i�ɂ͂���炪�������v����v�����Ă��邾���ŁA�d�l��\���������Ă����Ȃ����v�����Ă����Ȃ��B
- p.77 �\�z�ɂ�����S���ҁi�����ǁj�̖���
ISO�����ǂȂ���̂�ISOMS�K�i�ɂ��Ȃ����A�K�v�ł͂Ȃ��B�����ċK�i�ɏ����ĂȂ��B
���҂͎����ǂ̖����i�K�v���j�Ƃ��Ď���1�`3���ڂ������Ă���B�K�i�ɂȂ����Ƃ����߂�Ƃ������Ƃ͔F�؋@�ŗL�̗v�������Ȃ̂��낤���H
���F�F�؋@�ւ��Ǝ��ɗv��������lj����邱�Ƃ͉\�ł���B���������̂Ƃ��A�lj������v�������͏��ʂɂ��Č��J���邱�Ƃ����߂��Ă����͂����B�ߌY�@���`(��7)�Ȃ瓖�R���B
���ł�ISO17021�ɂ͂������B�ŐV�łł͊m�F���Ă��Ȃ��B
�����ǂ̖���3���ڂɂ��Ď��̍l�����L���Ă����B
- �K�i�𗝉����A���Ђ̎d�g�݂Ɏ�����邱�Ƃ��哱����
�g�D���K�i�𗝉����邱�Ƃ͕K�v�ł���B�������҂�p.73�ɏ����Ă���悤�ɁA�]���̎d�g�݂�ISOMS�K�i�v�������Ă��Ȃ��Ȃ�A�����lj����邱�Ƃ��F�̂��߂̍�ƂƂȂ�B
���R����͕����I�ŏ������ł��낤�����K�͂Ȃ��Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ����낤�B����Ď����ǂ͕s�v�ł���B
- �K�i�ŋ��߂��Ă���C�x���g�����d��
�C�x���g�Ƃ��ē����č���}�l�W�����g���r���[�������Ă���B���x�������Ă��邪�A�����������͉̂ߋ�����s���Ă�����c�Ă͂߂邱�ƂɂȂ�B���R�ߋ�����Õ��傪����킯�ŐV���Ȏd�����lj������킯�ł͂Ȃ��B����Ď����ǂ͕s�v�ł���B
- �F�؋@�ւ̑�����S��
�F�؋@�ւƂ̐R�������̒����A�Г��̓��������A�����Ȃǂ̎��A��p�����Ȃǂł���A�����S���Ɉ˗�����ςނ��Ƃł���B����Ď����ǂ͕s�v�ł���B
���҂̈Ӑ}���킩��Ȃ����AISO�R�����͎����ǂ��K�v�Ȃ̂��H ��Б��̑����Ƃ��ĕK�v�Ȃ̂��H�A�ʓ|���������Ƃ͂��ׂĎ����ǂɈ˗��������̂��낤���H
- p.80 �`�[���̗v��
�u�s�Ǖi�̒ጸ�Ɍ����Ďd�g�݂��\�z�����ꍇ�i�㗪�j�v
���҂�p.51�u�v��Ƃ́v��p.72�u�ړI���l����v�Ń}�l�W�����g�V�X�e�������̖ړI���u����A�b�v�v��u�i������v���ɏo���Ă��邪�A�}�l�W�����g�V�X�e���̓���������Ύ�������ƍl���Ă���̂��낤���H
���̓}�l�W�����g�V�X�e�����Ȃ��g�D�Ƃ������̂����݂���Ƃ͎v���Ȃ��B������}�l�W�����g�V�X�e���̓����Ƃ����Ӗ���������Ȃ����A���̖{�ɏ����Ă���̂łƂ肠�������������B
�ʂ̊ϓ_������A���̖{�̌��u�}�l�W�����g�V�X�e���̓����v�Ƃ͊Ԉ���Ă�ISO�F�̂��Ƃł͂Ȃ����낤�B������IAF/ISO�����R�~���j�P�i2010�j�ł�ISO9001�ɑ���F�肳�ꂽ�F���Ӗ�������̂Ƃ��Ď��̂悤�ɏ����Ă���B
�u�K�����i�邽�߂ɁA�F�肳�ꂽ�F�v���Z�X�́A�g�D��ISO9001�̓K�p�����v�������ɓK�������i���}�l�W�����g�V�X�e���������Ă���A�Ƃ����M������邱�Ƃ����҂���Ă���v
ISO�F�Ƃ́A����ȏ�ł��Ȃ�������ȉ��ł��Ȃ��B�}�l�W�����g�V�X�e���������Ă��u����A�b�v�v�u�i������v�Ȃǂ̎���������Ƃ͂܂���������Ă��Ȃ��B
JAB�P���̔F�؋@�ւȂ�IAF/ISO�����R�~���j�P�d����͂����B������JAB�ɔF�肳��Ă���F�؋@�ցiJQA���܂܂��j�Ȃ炻��𗝉����Ă���͂��ł���A�������o�ł��Ă��邱�̖{�͂����ł���͂����B�Ⴄ���H
�F���Ȃ���ISO�K�i�v�����������悤�ɂ����ꍇ�́u����A�b�v�v�u�i������v�Ȃǂ���������Ƃ����_�@�͉\���B�����A���̏ꍇ�ł������Ȃ邱�Ƃ𗧏܂��͎����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�Ⴆ�ΔF�؊�Ƃ͔�F�؊�Ƃ������v�����傫���Ƃ��i���N���[�������Ȃ��Ȃǂ̃f�[�^����邱�Ƃ����邾�낤�B
���F�}�l�W�����g�V�X�e�����Ȃ��g�D�����݂���̂����t�̈Ӗ�����l���Ă݂悤�B
���Ȃ݂�organization�Ƃ̓����O�}���p�p���T�ɂ���
a group such as a club or business that has formed for a particular purpose
planning and arranging something so that it is successful or effective
the way in which the different parts of a system are arranged and work together
����̖ړI�̂��߂Ɍ������ꂽ�N���u���ƂȂǂ̃O���[�v�ŁA���ꂪ�����܂��͌��ʓI�ł���悤�ɉ������v�悵�A�V�X�e���̂��܂��܂ȕ������z�u����A�A�g������@�i����Q��j
���ꂩ��l����ƁA�}�l�W�����g�V�X�e���������Ȃ��W�܂�͑g�D�iorganization�j�ł͂Ȃ��悤�Ɍ�����B
- p.80 �����ǂ��i�����j�ꐶ�������Ƃ��Ă��A���͂�����ꂸ�A����ɋL�^���c���K���͂Ȃ��Ȃ��Ă����܂��B
�������������邢�͌`�[������̂�h�����߂Ƀ}�l�W�����g�V�X�e����������̂ł͂Ȃ��낤���H �������ɐE�����������s���ȁu�����ǂ����ށv�Ƃ����s�ׂ̈Ӗ������͉����낤�H ���P���J����
���̍l�������A�����ɗᎦ���ꂽ���̌����́A��Ђ̌��܂�����Ȃ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ����낤���B
�����ǂ��ꐶ�����ɗ��ނƂ��܂������K�v�Ȃ��B��Ђ̃��[���͂��ꂾ�A���Ƃ������Ƃ��O��ł��Ȃ��Ƃُ͈�ł����B
��Ђ͖���I�ł���K�v�͂Ȃ��B�����ɑ��鍑���̕����Ƃ͈قȂ�A��Ђɂ����Ă͐ӔC�������������ł͂Ȃ��B�@�ɔ����Ȃ�����K��������]�ƈ��ɖ��߂ł��邵(��4)�A�]�ƈ��͏]��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���R�]��Ȃ��]�ƈ��ɑ��Ă͒����������s����B
��Ђ���߂��菇��O��ł��Ȃ��Ȃ�A��Ђ̕]���������邾�낤������悩��M������Ȃ��B
�u�}4-4-1�`�[���̎�ȗv���v�Ƃ��Đ}�����Ă��邪�A����Ȃ��̗v���ł͂Ȃ��B�v���͏]�ƈ��̃����[���̒Ⴓ�A�Ǘ��҂̖��\�A�o�c�҂̐ӔC�����ł����Ȃ��B
ISO�R�����Ƃ��ẮA��ЋK�������炳���邱�Ƃ̂ł��Ȃ��g�D�͔F�ɒl���Ȃ��ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������̂悤�ȉ�Ђ́A�F���x���ɒB���Ă��Ȃ��B
�u�}4-4-2�`�[���Ō�������̂���ւ��ip.83�j�v�Ƃ����}���`����Ă��邪�A�����猩��ƌ`�[���̌����̂���ւ��Ƃ����v���Ȃ��B
- p.84 �R�����郁���b�g
���낢��Ə����Ă��邪�AISO�F�̐^�̖ړI�ł���IAF/ISO�����R�~���j�P�i2010�j�����p�����A�����ɏ�����Ă��邱�Ƃ����Ă��Ȃ����Ƃ͑傫�Ȗ�肾�B
�����ɏ�����Ă���A�O���̖ځA���P�̃g���K�A�ӎ�������ʂȂǂ͔F�̖ړI�ł͂Ȃ��B���˓I���v(��5)�ɕ���Ĕ��˓I���l�Ƃ����ׂ���������Ȃ��B
������ISO�F���邢��ISOMS�K�i�������}�l�W�����g�V�X�e�����ړI�Ƃ��鉿�l�łȂ��̂͂������A���̌��ʂ��������邱�Ƃ��ۏ����킯�ł��Ȃ��B
���˓I���l�ł͂Ȃ��A�{���I�ȉ��l���Ƃ����Ȃ炻��𗧏��Ăق����B
- p.94 �}�l�W�����g�V�X�e���R����
�R�����ɋ��߂�����̂����ڂ��ċL�q����Ă���B
�s�v�c�Ɏv���̂����AISO19011�F2018�u�}�l�W�����g�V�X�e���R���̂��߂̎w�j�v��7�� �R�����̗͗ʋy�ѕ]���ɋL�ڂ���Ă���K�v�Ƃ����͗ʂƑ傫���Ⴄ�B
ISO19011�ł͑傫�������āA�l�I�����A�m���y�ыZ�\�i�}�l�W�����g�V�X�e�����L�̂��̂��܂ށj�ł��邪�A���̖{�ɂ���R�~���j�P�[�V�����\�͂╶�͗͂͒m���y�ыZ�\�̒��̊�{�I�Ȓm���y�ыZ�\�̈ꍀ�ڂɉ߂��Ȃ��B���̍��ڂ͏d�v�ł͂Ȃ��̂ł��傤���H
����҂Ă�AISO�K�i�ɋL�q���ꂽ���̂��d�v�łȂ��͂��͂Ȃ��c�c
��6�͈ȍ~�́A�eISOMS�K�i�ɂ��Ă̊ȒP�ȉ�������邪�A���̌�������ɂ͂Ȃ��������̂␔�N�����ւ����MS�K�i�������A��Ԋւ肪�[������ISO14001�ɂ��Ă̂݃R�����g����B
- ��.120�u�}7-2-1 ���܂��܂Ȋ����ʂ̃C���[�W�v
�}���Ɋ����ʂ̗���L���Ă���B���̕\�����u�r���̊����ʁv�u�p�����̊����ʁv�Ƃ����\�L�ɂȂ��Ă���B
�ׂ������ƂɃP�`������C�͂Ȃ����A����͓K�Ȃ̂��낤���H ���m�Ɍ����u�r���Ƃ��������ʁv�Ƃ��u�p�����Ƃ��������ʁv�ł͂Ȃ��̂��낤���H
���ۂɖ{���ł��u��������鎑�ށA�r�o����鐅��p�����Ȃǂ������ʂƂ��ċ������܂��v�ƋL�q���Ă���B
�u�r���̊����ʁv�Ƃ����Ȃ�A�u�����ʁv�͏L���ApH�A�F���A���x�ȂǂɂȂ�̂ł͂Ȃ����H
�傫�Ȗ��ł͂Ȃ����A�g�D�ɂ���Ċ����ʂ̂Ƃ炦�����~�N���ɂ���ꍇ�A�}�N���ɂ���ꍇ�Ȃǂ����肦�邾�낤���A����ɂ��Ă����̕\�L�͏����Ⴄ���낤�Ǝv���B���������H
�����Â����u���}�l�W�����g�V�X�e���̍\�z�ƔF�̎����(��6)�v�Ƃ����{�ɐ����Ȋ����ʂ̍l������������Ă���B�Q�l�ɂ��邪��낵���B
����������A�ߋ��̖{������̂łȂ���Ώo�ł��鉿�l�͂Ȃ��B
- p.121�u�����ʂ̒��ɂ́A�@�߂̏��炪���������߂���ꍇ������܂��v
������u���������߂��Ȃ��v�ˁu���炵�Ȃ��Ă��悢�v�ꍇ������Ƃ������Ƃ��H
�w�͋`�����܂ߔ��������낤���Ȃ��낤���A�@�K���͏��炵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��͎̂����ł���B
��{�@�Ȃǂ̍��ɑ���w���������A��ƁE�����̋`���ƋL�q���ꂽ�Ȃ珇��`���͂���B���̕��͂̕\���͋^��ł���c�c�Ə����Ȃ��ƁA���̕���ǂ܂ꂽ�����猩�����Ƃ����肪���邾�낤�B������`�����ł������Ă����B
�^����łɁc�c�u���������߂�v�Ɓu�������Ȃ����߂�v��2��ނ���̂ł��傤���H
- ��.122�u����`���̐o���ɍۂ��āA�ł��邾���L���o�����Ƃ́A�L���ɋ@�\���邽�߂̍H�v�̈�ł��v
���̕���ǂނƊ撣��Ηǂ��̂��Ǝ���B��������Ȃ����낤�B�@�͘R��Ȃ����炵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B���߂āu����`���̐o���ɍۂ��āA�R��Ȃ��c���ł���悤�A���@���H�v���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v���炢�����˂Ȃ�Ȃ��B
�ǂ������̒��҂͖@�����Ƃ����ӎv���ア�̂ł͂Ȃ����H
- p.123 ���e���]��
�^�C�g�������e���]���ƂȂ��Ă��邪�A���̌���ǂ���������Ă����̂��낤�HISO14001�ł͊��e���]���Ƃ�����͈�x���o�ꂵ�Ă��Ȃ��B
ISO14004�ł́u6.1.2.5�@�����������ʂ̌���v�̒��L���u�����������ʂ̌���́A���e���]����v�����Ă��Ȃ��v�ƋL�q���Ă���Ƃ���ň�x�̂ݎg���Ă���B
�������̖{���u�����������ʂ���肷�邽�߂Ɋ��e���]��������v�Ƃ�����|�Ȃ�K�i�ɔ����Ă���B
- ��.123�u�_���@�i�X�R�A�����O�@�j�v�Ɓu��c�ɂ����@�v��Ꭶ���Ă���B
�_���@�̐������ɂ��āA�ǂ��l���Ă���̂����������Ƃ��낾�B
����Ƃ��̓�ȊO�̕��@�ɂ��Ăǂ��l���Ă���̂������������B
���_���w�E�ł���Ƃ���܂ŏڏq���Ă��Ȃ����A�ǎ҂Ƃ��Ă͒��҂̍l�����K�Ȃ̂��ۂ���₢�����B
�O�q(��6)�v�������A�����ʂ̌���A�����������ʂ̌�����@�́A�i�R�������������j��O�҂ɐ����ł��闝�_�I�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ��K�v���B
�ǂ��������邪�u���̊����ʂ����߂���@��ISO�R�����ɖJ�߂��Ă܂��v�Ȃ�ď��h���Ƃ��s���ۂɍu�߂����l�����邪�A🤣�������Ȃ��B
ISO�R�������s���̖@���߂����錠�Ёi�e���́j������̂��ǂ����B
���̂�\�h���邽�߂̊Ǘ����K�v�Ȃ��̂͂��ׂĒ����������ʂƂȂ���@�łȂ���ΈӖ����Ȃ��B���Ȃ��Ă��s���ɂ͒ʗp���Ȃ��B
�����I�����������ʂƊǗ����ڂ͈Ⴄ��ł����H �����������ʂ��Ȃ킿�s���ɓ͂��鐔���Ƃ��Ǘ����`���̍��ڂł���ˁH
- ��.123�u�g�D�̖{���Ɩ��ɂ͊��Ƀ}�C�i�X�̉e����^���銈������łȂ��A������u�v���X�̊����ʁv����������A�����ɂ��Ă����肷�邱�ƂɂȂ�܂��v
�܂��u�v���X�̊����ʁv�Ƃ������̂�ISO14001�ɂ͂Ȃ��B�̂ɓ��肷��`�����Ȃ��B
�Ƃ������Ƃ͂��̕��͂͋K�i�ɔ����Ă���B
���ɂ������������ʂɃv���X���}�C�i�X���Ȃ��Ƃ������Ƃ҂͗������Ă���̂��낤���H �������Ă��Ȃ��Ȃ����{���������i���Ȃ��B
���̌����ɋ^�`�������������ǂ����B�ًc������ł����_�������Ǝv���܂��B
�E�L�v�Ȋ����ʂ͕s�łł���
�E�L�v�Ȋ����ʂ͗L�v�ł���
�E�L�v�Ȋ����ʂ��ĂȂɂ�
�{���ł��uISOMS�K�i�̓O���[�o���X�^���_�[�h���ip.22�j�v�Ƃ���B
���̓C�M���X�ƃ^�C�̍H��̊��S���̊Ǘ��҂ɒ��ڕ��������A���̒n�ł͗L�v�Ȋ����ʂƂ������t�����݂��Ȃ����Ƃ͊m�F�ς��B�C���^�[�l�b�g�ł�����������Ȃ��B
���{����Ȃ�O���[�o���X�^���_�[�h�ł͂Ȃ���ˁH
- ��.127�u�����ʂ́A�e�v���Z�X����o�����@���̗p���܂����v
���̗̍p�����u�o�����@�v���L�q���Ăق����B
- ��.127�u�J���[�V���b�v�ł́A�H�ނ�G�l���M�[�B���āA�����v���O�������o�ĕt�����l����܂��v
P.123�ł��q�ׂ����AISO14001�́u�ڍׂȃ��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g��v��������̂ł͂Ȃ��iA.6.1.2�j�v�Ƃ��邾���ŁA�v�������ł͂Ȃ��B
�Ƃ͂����A���҂��l����Ώ۔͈͂ɂ��Ė��m�ɂ����ׂ����B�R���ɂ����đΏۂ������Ƃ������c�_�͍���B
�Ƃ������ƂŁA���ꂾ���Ń��C�t�T�C�N����c���������ƂɂȂ�̂ł����H
���C�t�T�C�N�����Ăǂ��܂ők��́H�@�≮�܂ŁH �A����܂ŁH
���̂ւ���͂����肳���Ă������������B
�ʓ_�ł��邪�A�����v���O�����Ƃ�����蒲���v���Z�X���Ǝv�����A�����ł��������Ǝv���͍̂��ڂ̏��Ԃ��B
���̖{�ł�
- �J���[�V���b�v�̊��}�l�W�����g�V�X�e��
- �J���[�V���b�v�̊����ʁE���e��
- �J���[�V���b�v�̃��C�t�T�C�N��
- �J���[�V���b�v�ɂ���ĈقȂ���}�l�W�����g
�ƕ���ł���B
�����Ŋ����ʂ������ă��C�t�T�C�N��������̂ł͂Ȃ��B�u���C�t�T�C�N���̎��_���l�����Ċ����ʕ��тɂ���ɔ������e�������肷��iISO14001:2015 6.1.2�����ʁj�v�ł͂Ȃ��̂��H
�Ƃ���ƍ��Ԃ̏���
- �J���[�V���b�v�̊��}�l�W�����g�V�X�e��
- �J���[�V���b�v�̃��C�t�T�C�N��
- �J���[�V���b�v�̊����ʁE���e��
- �J���[�V���b�v�ɂ���ĈقȂ���}�l�W�����g
�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���݂̏����̋L�q�ł͓ǎ҂͗����H�ɋꂵ�ށB
- ��.123 �J���[�V���b�v�ɂ���ĈقȂ���}�l�W�����g
������ǂ�ő傢�Ɉ�a��������B��Ƃ͉��̂��߂ɑ��݂���̂��Ɩ₦�AISOMS�K�i�̂��߂ł͂Ȃ��̂͊ԈႢ�Ȃ��B��Ƃ͑n�Ǝ҂̋N�Ɨ��O���������邽�߂ɑ��݂���̂��B
�u�L�@�͔|�����H�ނł������������J���[�����v�Ȃ�A�����������������ʂ̊Ǘ��A���e���̒ጸ��}�邱�ƂɂȂ�A�u�w����Ώۂɒl�i���育��Ń{�����[���̂���J���[�����Ȃ�v�����B�����邽�߂Ɋ����ʂ̊Ǘ��A���e���̒ጸ��}�邱�ƂɂȂ�B
��Ƃ̗��O��}�l�W�����g�V�X�e���̊֘A�Ƃ������v���C�I���e�B����������F�����Ă��Ȃ��Ƃ������Ȃ��ƂɂȂ�B
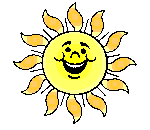 ISO�F�ɂ����āA�V�����ƒn�����Ƃ���������������
ISO�F�ɂ����āA�V�����ƒn�����Ƃ���������������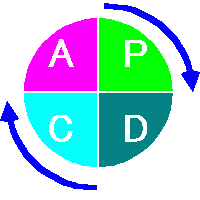
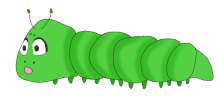


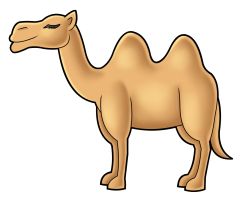
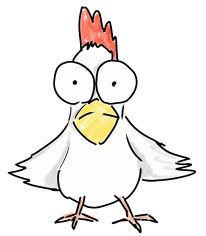
 ISO�K�i�v��������ԗ����Ă��邩�ǂ����킩��Ȃ�����s�K���ƃA�E�g�̃[�X�`���[�������肷��B
ISO�K�i�v��������ԗ����Ă��邩�ǂ����킩��Ȃ�����s�K���ƃA�E�g�̃[�X�`���[�������肷��B �R�����͎����̐R�����ŏd�v�łȂ��Ƃ��s���炵���B
�R�����͎����̐R�����ŏd�v�łȂ��Ƃ��s���炵���B



