「経営に寄与する」とのたまわくのであれば、審査機関は経営コンサルタントに転業したのであろうか?
などと驚いていたのだが(冗談)最近驚くべき審査(これも冗談)を見聞きした。
そんなことをきっかけに同業者、知り合いに声をかけ、ISO14001の審査所見の面白い事例(ISO事務局にとっては面白くない)を集めてみた。
すべて実際のものである。なお、これら事例は複数の審査機関(特に名を秘す)の書いたものであるが、どの指摘がどの審査機関かはコンフィデンシャルである。
では、はじまり、はじまり・・・
|
「適用範囲が環境マニュアル第2章に書かれている。ISO規格では適用範囲は第4章第1項なのでそれに合わせることを推奨する。」
|
|
今年度の目標設定において、昨年度の実績値よりもゆるく設定されているものがあり、適切でありません。
|
うーーーん、このような発想では社内で作るのではなく、すべて購入することが環境負荷を下げるという理屈なのだろうか?ところでこの所見報告書には要求事項の項目の記載がなかった。根拠がない不適合ってあるのだろうか?
|
4.5.2 過去一年間に事故が散発しています。再発防止が不十分です。
|
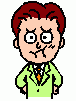 この担当者は「いやあ、まいったよ、ここのところさまざまなトラブルが起きてさ、問題だらけなんだけど、原因はいろいろなのよ」と自嘲しておりました。
この担当者は「いやあ、まいったよ、ここのところさまざまなトラブルが起きてさ、問題だらけなんだけど、原因はいろいろなのよ」と自嘲しておりました。それと技術上の制約、あるいは技術が確立していないのであれば、ISO規格4.4.6運用管理以前のことである。
|
4.3.2、4.5.4 「環境関連該当法規等要求事項一覧表」に、改正された法規制が反映されていませんでしたが、これを内部監査で見つけていません。
|
ISO14001アネックスA.5.5 参考1では「環境遵法性監査はこの規格の範囲ではない」と書いてあったようだが・・・あるいは私の思い違いかもしれない。そして監査員の技量からいっても無理があるのではないか?
|
重要側面でないものが、目的及び目標になっています。
|
|
近隣から騒音の苦情に対して、実測値は法基準内であり、かつ行政と協議して処理されていますが、再発防止・予防処置の観点から十分と言えません。
|
|
グリーン調達は有害化学物質を含んでいるものを購買しない活動を進めているが、それだけでなく包装材料なども含めて総合的に推進すること
|
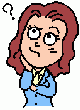 本当に驚いた!
本当に驚いた!|
環境関連該当法規等一覧表に不足している法規制が見られます。 (具体的証拠)RoHS指令 ← ロース指令またはローズ指令と読みます。 |
|
不適合の定義において「計画値の5%以下を2ヶ月連続した場合」を不適合としているが、その方法は合理的ではありません。
|
|
コミュニケーションの記録において、記録のリストには4種類の記録がリストされていますが、実際の記録は1種類しかありません。
|
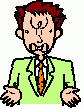 その会社の担当者に聞くと、リストに挙げていた行政からの指導や近隣からの苦情の記録などがなかったとのこと。
その会社の担当者に聞くと、リストに挙げていた行政からの指導や近隣からの苦情の記録などがなかったとのこと。|
法的要求事項等に基づく、行政への届出手順について検討の余地があります。
|
|
4.3.3環境目的・目標 著しい環境側面、法的及びその他の要求事項、利害関係者の見解、運用上及び事業上の要求事項などについて個々に配慮すると目標策定のプロセスが明確になります。
|
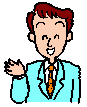 「目的目標を設定するに当たり、○○審査機関の○○審査員に立ち会ってもらい決定することに改定します。これにより目的策定のプロセスが明確になりました。」
「目的目標を設定するに当たり、○○審査機関の○○審査員に立ち会ってもらい決定することに改定します。これにより目的策定のプロセスが明確になりました。」|
目的・目標の一部に数値目標のないテーマがあります。
|
しかしながら、測定可能でなくても不適合にはできない。この審査員はISO14001:2004ではなく、自分の頭の中のISO規格によって審査しているらしい。
だって where practicable という条件がついているから。
|
目標未達成の是正処置として、目標値を下方修正したものがあります。継続的改善と不適合の原因除去という観点から妥当でありません。
|
「納期は絶対厳守しなくてはならない。しかし、徹夜で仕事して納期を守る方法もあるし、お客さんと交渉して納期を伸ばしてもらう方法もある。」私はこの方の下に10年いました。大変尊敬しております。既に引退して今は碁会所に入り浸っているそうです。
悲しいことだ
|
ISOについて 大変ISOにお詳しいようですね しかしなぜそこまで審査機関に恨みがあるのでしょうか 審査員は悪意はないと思いますし、過去ISOで日本が悪くなったとも思えません もっと前向きな思考をしたほうが良いと思います |
通りすがり様、お便りありがとうございます。
正直申し上げまして、私は審査機関全体に対して、恨みつらみはありません。
しかし、過去に相対した特定の審査員に対して恨みつらみがあります。
善意であっても、質の悪い審査を行い、企業に害をなしている審査員がいるのは事実。悪意がある・ないではないのです。質が悪いか否かが問題なのです。
この質の悪い審査員が日本のISOを、第三者審査登録制度を悪くしているという事実は否定できないと考えております。
前向きに進むためには、日本から質の悪い審査員を払拭することが必要であると考えております。
通りすがり様も、ご自身の体験を反芻すれば審査員の間違いによって会社に迷惑を受けたことが多々あるのではないでしょうか?
そのようなことを改善することが、負のスパイラル脱出の礎となるでしょう。
|
「審査所見 2005.05.14」は過去に拝見したはずなのですが、今更ながら爆笑を誘う指摘事項が粒ぞろいですね。 これはオモシロイです。当社が過去に受けた爆笑事例など足元にも及びません。 ところで、通りすがり様のコメントに意義があります。 6年もたっているので、もうISOに対するお考えも変わっているかもしれませんが。 大変ISOにお詳しいようですね しかしなぜそこまで審査機関に恨みがあるのでしょうか おばQ様は、極めて初歩的な審査員の規格解釈の誤りを逆指摘しているだけです。恨みではないし、批判していますが批難ではないでしょう。 だいたい、大金を払ってこんなバカバカしい指摘しかもらえないのであれば恨みたくもなるというものです。 審査員は悪意はないと思いますし、過去ISOで日本が悪くなったとも思えせん 悪意がないのならもっとタチが悪いです。自分の行為が正しいと信じ込んで間違ったことをするのを「確信犯」といいます。人類の歴史を紐解けば、そんな実例は山ほどあります。 だいたい、会社をよくするためのISOがその目的どおりに機能しているかどうかをチェックするのが審査なのに、その審査指摘がブレーキをかけてどうするのと言いたいです。アホな指摘がどれほどその会社に迷惑をかけているかを自覚していない審査員は、それだけで重罪というものです。 こうした誤った認証制度の運用によって、何十年にも渡って社会は莫大な損失を被ってきました。そして今は、環境という美名を隠れ蓑に国家レベルで陰謀が行われていますが、ISOはその片棒を担がされています。 アホ審査員は、さしずめその一味といった役割でしょう。 もっと前向きな思考をしたほうが良いと思います ではどのような思考が「前向き」なのでしょうか? このようなアホ丸出しの指摘、それも役に立たないどころか被害を与えるだけの指摘を甘んじて受け入れることが前向きだとはとても思えません。 |
ぶらっくたいがぁ様 毎度ありがとうございます。
いやはや年月が経つのは早いものです。
それにゲーテはすべてを語ったと言われますが、私もISOについてすべてを語ってしまったようです。
老兵は消え去るのみ・・まあ、後少しですから
ISO14001規格は2004年11月に改定となり、現在は移行期間中なので不適合ではないそうだ。経過措置の切れる2006年5月以降は是正が必須となるという。
驚くべき発想である。
いったい環境マニュアルの章の番号とISO規格の章の番号を一致させよという要求事項はあるのだろうか?
考えてみると、章の番号をあわせろという前に、ISO14001では環境マニュアルを作れという要求もないのだが?
ISO規格の項番とマニュアルの対照表を作れといっている審査機関がある。それはJABコードに則り適正である。
しかし章立てを規格の項番に合わせろというのは聞いたことがない。 実は私も似たような体験がある。
97年ころの話だが、4.3.3目的目標と4.3.4プログラムをひとつの章にまとめたマニュアルを書いたら、審査員から不適合といわれ、やむなく規格に合わせて分けたことがある。
これからの進展を見守ろう