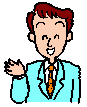 本日のテーマは「そんなこたあ、つまらんことよ」ということである。
本日のテーマは「そんなこたあ、つまらんことよ」ということである。具体例なことを基に話を進めよう。例えば、「ISO14001 4.5.5 記録の管理」という条項では、いろいろと記録が具備する要件とか管理上の要点を定めている。
これは要求事項であるから、これらの要件はすべて満たすように記録を管理する手順を決めないといけない。4.5.5では手順であり手順書とは言っていないが、4.1で文書化した手順といっているので現実的には必須だ。
このとき、「手順書」をどういう構成で作るべきかは重要・重大な検討事項である。
会社によってはISO対応で「○○手順書」などというものを一生懸命に作っているところがある。よく見るとその会社には以前から会社の「規則」が存在していたりする。会社の業務というのはたくさんある。定款で定める本来業務、つまり設計、製造、販売、サービスなどはもちろん、それを支える人事、総務、広報、法務、監査・・・そして我々の仕事である環境管理などきりも限りもない。
「手順書」とは固有名詞ではない。ISO規格に限らず法律でいう「手順書」とは「会社の手順を定めた文書」を意味する。どの会社にもそういう文書は存在するが、会社によってその名称は「会社規則」とか「要領書」とか「指示書」とか「規程」とか「規定」などいろいろあるだろう。
国語辞典によると「規定」は動詞なので、名詞である「規程」が正しいようだ。もっとも有名家電メーカーでは上位の会社規則を「規程(きほど)」と呼び、下位の会社規則を「規定(きさだ)」と使い分けているところもある。
世の中は広い、ISO規格に限らず、薬事法対応で「手順書」を作り、電気事業法対応で「保安規定」を作り、省エネ法対応で「エネルギー管理基準」を作るなど、その会社の本来の規則(文書体系)と別に作ったりしているところがるが・・・それはまったくお笑いである。
当然、それらすべての業務において文書管理もあるし記録管理もあるし、教育訓練もあるし・・・とこれもきりも限りもない。
いいたいのは会社でしなければならないことは一次元のものではなく多次元である。簡単に言えば直線ではなく平面的に広がっている。この多様な広がりを持つ業務の手順を文書化する(規則に定める)とき、いろいろな切り口・方法がある。
- たとえば、
- ISO9000に関わるもの、ISO14000に関わるもの、それぞれの顧客対応のものという切り口もあるだろう。
- 総務部、営業部、製造部、などという職制単位にまとめる方法もあるだろう。
- 同様に、総務、人事、経理、営業という業務のカテゴリーで分けるのもある。勘違いなきよう、総務部だけが総務の仕事、たとえば旅費清算とか交際費管理などをしているわけではない。
- 本社、支社、工場という所在地域によって分けるのもあるだろう。
- 要素、つまり記録管理は記録としてまとめる、教育は教育として、要素単位にまとめるという方法もある。
| ISO9001 | ISO14001 | ISO20000 | ・・・ | ||
| 総務部 |
会社の仕事の手順を定める文書体系は どうすればよいのか | 本社 | |||
| 人事部 | 支社 | ||||
| 営業部 | 研究所 | ||||
| ・・・ | 工場 | ||||
| 記録管理 | 文書管理 | 教育訓練 | ・・・ | ||
本来業務においてもまとめかたは種々ありえるが、特にインフラ的な要素は文書化するときに自由度というか選択肢がたくさんあることが理解できるでしょう。
インフラ的な要素、例えば「文書管理」とか「記録の管理」という手順をどういう形で文書化したらよいのだろうか?
いや現実問題として既に会社の仕組みができているのなら、いかにして体外的に説明しようかということが、事務局の課題である。
このとき、ISO規格を基にとか、審査員に理解しやすいように、という安易(?)な選択肢を選ぶことはシステムがバーチャルになるという危険な道の第一歩でもある。
話は変わる。
・・・私の話はいつも変わっているばかり
ISO9001が現れたのは1987年、ISOでマネジメントシステム規格というのを制定したのはそれが始めてだった。ISO9001(87年版)の規格要求事項は要素ごとに定めてあった。つまり文書管理、教育、記録管理・・・業務そのものについてどうこう定めるのではなく、業務の要素が備えるべき要件を要求していた。
これは記憶すべきことである。そして、実はなんと仕事そのものについて要求事項を定めていなかったのである。要素を押さえておけば仕事は間違いなく達成されるだろうと看做(みな)していたのでしょう。
ISO14001(96年)はそういった切り口ではなく、PDCAという切り口で定めている。しかし基本的なインフラ、すなわち文書管理、記録、教育というのはまたそれぞれ一項目としている。PDCAといえば聞こえがいいが、実際に要求事項を明確にしようとすると、ある意味退行というか規格の構成として混乱してきたのかもしれない。このへんが折り合いが難しいところである。完全に仕事の縦軸のみで書くならまた別のストーリーになったに違いない。
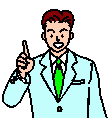 |
環境も品質も包括的なマネジメントシステムの一部であるならば(それは9001や14001の序文で明言している)それぞれの特有なもののみを要求事項として、共通的なものは別のマネジメントシステム規格としてまとめるのが正解ではないかという気もする。
|
さて先行規格であるISO9001の認証しても品質が上がらないという苦情(?)により、ISO9001は品質保証規格から品質マネジメントシステム規格に変質したのが2000年である。
品質保証とは品質を保証することでも、補償することでもない。この品質は大丈夫であると説明することである。そしてPDCAとかプロセスアプローチなどという屁理屈をこねたのである。屁理屈といっては不遜かもしれないが、87年版のそれなりに完成された構成に比べると、ISO9001:2000年版の構成は混乱というか未完成と言わざるを得ない。
未完成であっても良いものは良い。聖家族教会は永遠に未完成でもすばらしい。でも実運用されるマネジメントシステム規格の未完成は混乱を引き起こす。
しかし規格がどういう切り口で書こうが、会社の仕組み、仕事の流れが変わることはない。
10年も前、私が田舎の工場でISO14001の審査をはじめて受けたときのこと、その工場では以前からある「要領書」の中で緊急事態を定め、記録管理を定め、その他の要素を定めていた。審査員は「そういうのではなく、「記録管理規則」とか「緊急事態規則」というふうにしたほうが良いというコメント(不適合でも観察でもなかった)を残していった。
まあ、その審査員なりの思いやりなのか思い込みなのかはともかく、悪意ではなかったとは思う。しかしその審査員は企業の文化というものを理解していなかったに違いない。
会社の規則をいかなる構成で作り上げるのかというような選択は、その組織にあった方法を探り作り上げないとならないものである。他人がどうこう言えるものではない。
いや、現実には大半の企業がそうなのであるが、長い歴史の中で会社の規則が既に存在しているわけであり、マネジメントシステムを構築するというような発想は不遜であり間違いである。ISO事務局を拝命したものは、ISO規格要求と審査員様に会社の仕事がいかにISO規格を満たしているだけでなく、それを上回っているということを説明するかという役割なのである
自慢することかもしれない。 
そして審査員サイドも、組織の文化を理解・尊重して、適合であることを確認しなければならないのである。
別に不適合であることを確認してもらう必要はない。 
今現在、ISO14001の審査員として飯を食っているのは2000人といわれている。この2000人が私程度に規格の趣旨、企業文化の尊重、そしてなによりも社会常識、企業人の常識を持って審査をしているかという問いには ? と応えるしかない。同時にそれは私たち自身が内部監査をするときに自省しなければならないことでもある。
アントニオ猪木ではないが、私は誰の兆戦でも受ける。
そりゃISO規格についての理解が深い人はたくさんいるだろう。しかし、私が書いた、この山ほどのISO900とISO14001に関する拙文に込めた思い以上に、ISO規格への愛を持って、その実現に努めている審査員はいかほどいるだろうか?
私がISOを一番愛している男であると考えているのだが・・・
私自身、私の実体験と先輩から聞いたことや本などで読んだものしか知識がないわけだ。そこからあるべき姿とか判断基準などを決め付けることはできない。規格要求を満たすには無限のバリエーションがあることを認識しておかねばならない。
まとめです。
記録管理などインフラ的事項はISO14001だけでなく、いやISO規格だけでなく、薬事法であれ、個別顧客の要求であれ、みな似たようなものである。そしてそれはまた企業として当然管理しなければならないことでもある。
考えて見ましょう、「記録を識別しなさい」とか「記録の保管には配慮しなさい」というようなことがISO14001だけということはありえない。まず法律があるし、何十年も前からお客様から言われているし、そして自分自身の身の証をたてるために社内の決まりを作っていたのである。(現在完了形でいいたいところです)
ですからそんなことは既に会社の中の規則あるいは企業文化として存在しているのです。
それが現実ではありませんか?
実際の話だが、某社で品質用の文書管理規程と環境用の文書管理規程があり、そのほうが審査機関に説明しやすいからという話を聞いたことがある。いやあ、この会社も審査機関もマネジメントシステムということをまったく理解していないようです。
参考までに ISO14001でもISO9001でも、文書管理や記録管理について文書化した手順を求めている。 だから、そういったインフラ的な基本要素については、会社として共通な手順・・もちろんそれは会社一律の規則ではなく、個々の部門の業務を定めた文書でもよいのだが・・を作っておくことが良い。 ISO14001の要求ではとか、顧客要求ではとか・・・個々に対応するのは効率的ではない。 統合マネジメントシステムなんてものはマニュアルや事務局をひとつにするとかではなく、二つの規格を並べてみて最小公倍数の要件(論理学で言うOR)を満たすものを設計することだと思う。 もちろんそれは管理システムをひとつとするという意味であって、文書の管理方法や記録の保管期限を一律にするという意味ではない。 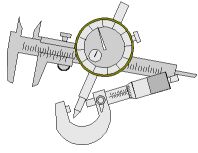 同様の例だが、計測器管理のようなものでは、管理システムは一本化すべきだが、顧客要求や法的に要求されるランクも異なり、費用も異なるので、校正のインターバルや精度などの管理レベルを分けるのは当然である。
同様の例だが、計測器管理のようなものでは、管理システムは一本化すべきだが、顧客要求や法的に要求されるランクも異なり、費用も異なるので、校正のインターバルや精度などの管理レベルを分けるのは当然である。
|
VEM様からお便りを頂きました(06.10.08)
始めまして、だと思います。もし、以前にもお便りしていましたら恥ずかしいのですが、初めてのはずです。 手順書についてを拝読しました いぜんより時よりつまみ読みさせていただいておりましたが、本日手順書についての記事を読ませていただき、安心すると同時に難しい仕事が増えそうだと心配もしてメールさせていただきました。 私は○○会社の営業所で仕事をしており、グリーン経営の担当もしています。グリーン経営とは、運輸部門は環境保全に取り組んで欲しいのに零細中小企業にはISO14001は荷が重かろうとして国土交通省が作ってくれた資格です。事前にレールを準備して下さり、取り組みを始めればすぐに審査をパスさせてくれて、2年ごとにレベルを上げた更新審査を経て8年後のレベル4でISO14001に実質的に近い物にしようというものです。 最初に取り組みを開始したときに、開示されているマニュアルを見て、ほとんどが当社の就業規則や整備手順書やらに記載されている内容なので安心し、一部足りないところを改定したところ、「マニュアルに合わせて新しい規則を作る事業車が多い中で、既存の規則の修正で取り組んだのは良いことです」とのコメントをいただいて審査をとおりました。 ところが、更新時の審査官は、中身はこれでよいのですが、文章の名前がマニュアルと違いますねと散々文句を言いながら審査をし、それでも結果的に紙の上には指摘事項無しとして帰られました。 今日読ませていただいた手順書についての記事に安心したのはそういう経緯を踏まえてです。 ところで、会社としては全ての審査の結果がでていませんので、まだうわさを耳にしている段階ですが、本社では今年の審査の経緯からグリーン経営用の新しい規則を作ろうと準備をしているようです。他社から雛形を取り寄せて集成する大部なものらしく、難しい仕事が増えそうだと苦慮しているところです。 トトカルチョについて、要領を上手くつかんでおりませんが、表の期間中に11月1日が自分にとって記念日ですから、ここに投票させていただきます。 これからも勉強させていただきたいと思いますので、ご活躍を祈念いたします。 |
VEM様 お便りありがとうございます。
私の記憶にもメールボックスにもVEM様の記録がありませんのではじめてだと思います。
グリーン経営についてはパンフレットを見た程度で詳しくは知りません。
なにしろISO14001なら任せろと大口を叩いてはおりますが、利権でもあるのでしょうか環境認証制度は、自治体ごと、省ごとにあるのですから迷路のようです。
私はVEM様のお考えでまったく問題ないと考えます。しかし上司の方としては会社に役に立つということより、ゴタゴタなく審査が進めばハッピーというところがあるのでしょう。それもまたやむを得ません。
わたしも10年前は田舎の工場のISO事務局でした。上司は不適合の件数で査定をするのですからISOの精神も会社のためもありません。月給を下げないためには、なるだけ不適合を出さないようにするしかありません。
やがてそれが私の特技となり、J●Aならこうする、J▲C●ならこうする、B▼Q*ならこうすると審査機関対応の能力を身につけました。すばらしい! かどうか?
ま、なんにせよ芸は身を助けるといいまして、今の仕事にありつきました。
VEM様もサラリーマンですから、すまじきものは宮仕えともいいますので、あまり深刻にならず、状況に合わせて対応するのも処世訓かと思います。
グリーン経営にも、ISO14001でもしかもさまざまな審査機関に対する方法も、エコアクションでも、エコステージでも対応できますというのもすぐれた能力ですから。
ホームページ拝見しました。花と山がお好きな方なのですね。私は田舎育ちですが花も山もあまり詳しくありません。
またよろしくお願いします。
うそ800の目次にもどる