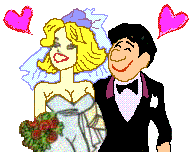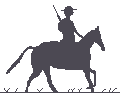第14条2項 (2002.12.30)
第14条2項 (2002.12.30)
「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」
この場合「認める」の否定形ですからその意味するところを考えますと
本日の演題は憲法14条2項は短い文章です。例によって主語はありません。
述部であります「認めない」とはどういう意味でしょうか?
広辞苑によりますと、「認める」の原形は「認む」、そして「認む」の意味は
(1)よく気をつけてみる
(2)目にとめる
(3)見て判断する
(4)見てよしとする
だそうであります。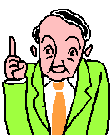
「貴族制度はよく気をつけてみないことにする」とか「貴族制度は見かけない」とか「貴族制度は見ても判断しない」というのでは支離滅裂ですから、まあ、どう考えても(1)〜(3)ではなさそうで(4)らしいのです。
いえこれ冗談でもないのです。すべて意味のある表現です。
すると(4)である『華族その他の貴族の制度は見ても良しとしない』ということでしょうか?- よく気をつけてみる
「○○党は政策への反論を認めない。」- 目にとめる
監査報告書にこの表現をよく書きますよ、「遵法を確認し、異常を認めなかった。」- 見て判断する
我々は北朝鮮の核兵器を分析した結果、それが非常に危険なものであると認めた。
以前、通勤途上、女子高生が語っていたのを小耳に挟みました。英語原文は
『イギリスでは貴族がいてかっこいいわね、日本にはないのね』
『私 伯爵の令嬢だったら良かったのに』
こういうとき、『わしゃそういったものを良いと思わんがな〜』ということなんでしょうか?
Peers and peerage shall not be recognized.
直訳すると「貴族及び貴族階級を認めない」となるとお思いですか?
毎度申し上げますが、このshallは命令形です。英和辞典にある(1)単純未来や(3)一人称疑問文ではなく(2)「二人称平叙文においては話し手の絶対的意思」を示します。ところがrecognizeとは単純に日本語の「認める」とは異なるようなのです。
ISO規格ではshallがあれば必須、漏れたらアウトということになっております。
私の安い英英辞典(厚さ7センチあります)によりますと
(1)なにかを困難であると認識する。
(2)真実であると受け入れる
(3)公式に応じること
(4)公式に(事実を)正当であると認知すること
つまり、日本語の『認める』の持つたくさんある意味の一部と英語のrecognizeのたくさんある意味の一部が重なる程度のようです。もっともすべての単語はすべからくそのようです。まあそんなわけでひとつの言葉を別の言語で言い表そうとすること自体が困難ですが・・・・
今、「日本語は生き残れるか」という本を読んでおります。
言葉というのは文化そのものです。色を表す言葉をとっても、朱、赤、茜、紅、緋などみなニュアンスが違うだけでなく元々はあるものの色を意味したわけです。
同じくレッド、スカーレット、ワインレッド・・・みんな色合いだけでなくその言葉の起源を持っています。日本語の赤をどう訳すかというのは至難の業どころか不可能かもしれません。明治初頭、現在のように遂語の翻訳ではなくストーリーを日本に置き換える方法がありましたが、あれが正解かもしれません。
この文章の主語はもちろん「国」ですから、それを補えば「国は貴族及び貴族階級を承認してはならない」と言えばもうすこし分かりやすいかもしれません。
「承認」という言葉ですと
「遠くの木に止まっている鳥がなんだか分からない」という「認めない」とか
「すれ違った人がおじさんだと分かった」という「認める」とか、
「貴族制度ができてから判断する」という「認める」こと
と違う、ということが分かりました。
「お父さん、お嬢さんをください!」
「とんでもない、どこの馬の骨か分からん奴にかわいい娘を嫁にやれるか!」
というやりとりの結果
「しかたがない、結婚を認めよう」
というテレビドラマによくある「認める」の意味ですよ。
よかったですね、分かりやすくて
ついでに言えば今やこういったシーンは現実にはないでしょうね、もしあれば博物館に飾りたい
ところで次の懸念が出てまいりました。
「recognize」は「公式に認める」「承認」と解釈できることが分かりましたがそれで文章として適正なのでしょうか?
「認める 承認する」ということは偉い人が、臣下が作文してうやうやしく「陛下、このような施策を考えましたので、決裁をお願いします」と申請してきたものを「ヨシ」とか「ダメ」ということです。
これはおかしいですよ、国というのは受身なんでしょうか?
国家というものは意思を持たないのでしょうか? 理念といってもいい。
貴族制度を誰かが立案してくるのを待っているだけなのでしょうか?
ここはひとつたかが将軍だったマッカーサー君の作った作文だけでなくアメリカ憲法も拝見しましょう。アメリカ合衆国憲法(アメリカ大使館訳)これをいかが受け取られますでしょうか?
第9項 No title of nobility shall be granted by the United States
合衆国は、貴族の称号を授与してはならない。
第10項 No State shall enter into any treaty
law impairing the obligation of contracts, or grant any title of nobility.
各州は、次のことをしてはならない。 貴族の称号を授与すること。
「合衆国は貴族の称号を認めてはならない」ではなく「称号を授与してはならない」と明確に断定しています。
国家が主語であり、国家と州の行為が明確です。
いいですね、この表現は決定者が国であることが明確です。
13条や18条でも述べましたが、私たちの日本国憲法ではすべての言い回しがひとごとのような表現となっているのです。
具体的に言えば『貴族制度を認めない』という命題を憲法らしく、法律らしく書くなら、
『国あるいは議会は貴族を認める法律を制定してはならない』
『この憲法は身分制度を禁止する』
あるいはアメリカ憲法のように『国あるいは自治体は貴族の称号を授与してはならない』
となるのではないでしょうか? もちろん言い回しはもっとリファインできるでしょう
ところが、『貴族の制度は、これを認めない。』ときましたね
これって、『ボクチャン、貴族なんか嫌いだもんね、誰かが作っても認めなくないもんね』といっている風に感じます。
この憲法は自尊心が皆無で、責任感がなく、奴隷的発想であり、自分の意思を主張するものではないのです。だから憲法の文章は気品がなく声に出して読むと恥ずかしくなってしまうのです。
それは本条項だけでなく、序文からなのです。
本日のまとめ
私は宣言します。
こんなみじめったらしく恥ずかしい言い回しの憲法を守りたくありません。
日本国憲法の内容をまったく変えないとしても、文章を・文体を・主語を・言い回しを変えないと国民は誇りを持てないでしょう。
現憲法をすばらしいと信じている人々は、自尊心がなく、奴隷的な文章をよしと考えているのでしょう。
いえ、そんな方々は考えることをせず、感じるだけかもしれません。
えっ、読んでもいないんですか?
ところで、100歩離れて、貴族というのは悪いものなのでしょうか?
世界には貴族がいる国はたくさんあります。
イギリスをはじめベルギーには現存してます。フランス、イタリアでは制度としてはなくなっても呼称は生きているとか、
ノーブレスオブリッジてのをご存知でしょうか?
貴族は戦争に際しては真っ先に参戦しなくてはならないという「高貴な義務」なのです。
貴族と呼ぼうと呼ぶまいと、国(それは日本人のことです)のために身命を捧げようとする心を持ち実践する人々は尊敬に足ることを忘れてはなりません。
『敵が来たら、逃げる』と仰った元国会議員は自らの言葉で高邁な精神でないことを暴露してしまいました。
貴族と呼ばれるには奉仕、自己犠牲の精神がなくてはならないのです。
ところで自己犠牲の精神は民主主義国家においては貴族だけじゃいけないのです。
国民全部がその責を負うのです。
小林よしのりは戦争論の中で語っています。
「市民になれ、諸君!
祖国のために死ぬ覚悟のない現代の人々など"私民"に過ぎない」
あなた愛する人のために死ぬ覚悟がありますか
憲法14条2項についてメールを送ります。
「この文章に主語がない。」ということで,当然「国」が主語だろうとおっしゃっていますが,これは明らかな誤りです。憲法とは国民(市民)から統治権力への命令です。つまり,日本国憲法の主語は「日本国」ではなく「日本国民」でなければなりません。憲法14条2項の意味は「日本国民は国家が華族などの身分をつくることを承認しない。」という意味になります。(「認めない」より「承認しない」とすべきという意見には賛成です。)
憲法は国家が国民に対して発するものではなく,国民から国家に向けて,発せられるものなのです。権力者を縛る命令とでも言うべきでしょうか。例え主語がなくても,今僕が言ったような意味になる,と考えるべきなのではないでしょうか。
僕が最近読んだ,宮崎哲弥,宮台真司の「ニッポン問題」という本のなかで二人がそのことについて語っています。ぜひ一度読んでください。
憲法は〔国家から国民〕ではなく〔国民(市民)から国家〕だということを知っていただきたいと,思います。
お便りありがとうございます。
憲法と国民と国家の関係はおっしゃるとおりです。
しかし英語原文が「shall not」であるならば主語はやはり国でないとおかしいです。
それに国民を主語として「日本国民は国家が華族などの身分をつくることを承認しない。」とすればあなたがおっしゃるように「国民から国家に向けて,発せられるもの」としての憲法の文言としては整合しません。
・・・・と考えて私の日本語がおかしいと気づきました。
「国は貴族及び貴族階級を承認しない」
↓
「国は貴族及び貴族階級を承認してはならない」
と上記文言を修正しました。これでご了解いただけますでしょうか?
でもこれまったくアメリカ憲法と同じになってしまいました。
ということはいよいよもって、現行憲法は誤訳であるということなのでしょうか?
文字化けがありましたので独断で助詞などを補っております。(FULL様ごめんなさい)
14条2項について Part 2
憲法14条2項についてのメールに答えていただきありがとうございます。まず僕は佐為さんが憲法の意味を知らないのではないかと勘違いしていたようです。そのため,大変偉そうな文体のメールを送ってしまったことをお詫びします。佐為さんがおっしゃった英文の意味についても大体わかったつもりです。
ただ第一になぜ「整合性がないのか」詳しくご指摘を頂きたいと思います。
権力を制御できる文章になっていない,ということでしょうか。
二つ目は「認める」の意味について、僕の家の辞書では「許可するまたは 承認する」(岩波書店,講談社 等)との意味があった。というような感じになります。
佐為さんの書かれていた駄々をこねるような印象を与える意味はなく,現在も憲法で定められた皇室という例外を除けば,血統主義の貴族制度はないわけですから,この文章は,公権の制限という憲法の意味は果たしているのではないかと考えます。
最後に,この文章をはじめ,誤訳があるとすれば,昭和20,21年頃の政治家や官僚のミスになるわけですが,間違いなくインテリである彼らが短期間とはいえ,なぜそんな初歩のミスを犯したのだと思われますか。お考えを聞かせてください。
お便りありがとうございます。
私も間違いばっかしですから私の間違いもお許しください。
第一の点、
FULL様がおっしゃるように「憲法とは国民から国家に向けて,発せられるもの」であるのなら、「汝・・・することにあるべし」となるはずであって、FULL様が前回お書きになった「日本国民は国家が華族などの身分をつくることを承認しない。」と表記するはずがないと感じたのです。しかし何ですね、憲法を論じていると考えておりましたが、我々は旧約聖書を論じていたのでしょうか?要するに「承認してはいけない」のであって「国民が承認しない」のではないのです。
ご存じなければ「エデンの東」をお読みください。
そのニュアンスの違いを整合しないと表現したのですが・・・・
私の表現に対する思い込みがずれているのでしょうか?ところで、「憲法とは国民から国家に向けて,発せられるもの」なんでしょうか?二点目の認めるですが、
独裁政権が公布しても、占領軍が押し付けても、国民の義務のみを定めても世界的には憲法といっているようです。
イエこれは皮肉とか揚げ足取りではないのです。現実はそんなものだということです。
憲法とは何かと定義すれば「国家と国民の契約」ではなく「国の形を示すもの」とするのが正しいようです。もちろん理想の憲法とは「国家と国民の契約」でしょうけど、
まあこれはどうでもいい話です。私の語る命題は単純素朴でありまして短すぎるために、多々与太話を付け加えて引き伸ばしているというだけです。
最近の辞書は違うのかと広辞苑第4版をチェックしました。
認めるの意味は(1)よく気をつけてみる(2)目に留める(3)見て判断する(4)見てよしとする(5)みどころがあると考える。となっており、第2版の(1)よく気をつけてみる(2)目にとめる(3)見て判断する(4)見てよしとする、とは少し異なっていました。
実は一番の差異は第2版が「認める」の項は「認む」を引けと書いてありますが、第4版では「認む」を引くと「認める」を引けとなっています。わずか40年で変れば変るものです。いずれにしても直接的に「承認する」とはありません。ところで50年前の憲法を理解するには現在の国語辞典ではなく50年前の辞書で判断すべきという論は成り立ちませんか?第三点、分かりませんね、
ただ間違いなく言えることは「日本国憲法は理想でもなければ高尚なものではない」ということです。
護憲という言葉ではなくせめて「憲法9条改正反対主義」とかすべきであって、「平和憲法」とか「理想の憲法」と表現することは憲法を読んでいないという証拠でありましょう。
私は「9条堅持」とか「天皇制廃止」に賛成するか否かは別としてその理屈は理解します。しかし「護憲主義者」が「平和憲法を称えて、天皇制に反対する」その論理が理解できません。
きっと彼らの頭の中は脳みそではなくぬかみそが詰まっているのではないでしょうか?
ぬかみそじゃなくやはり脳みそですなんて混ぜっ返しはなしよ
日本国憲法の目次にもどる