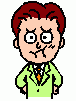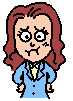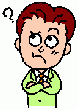「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」
文章としては前1項と同じく、SVOCがありまともそうです。
でもよくよく読んでみると疑問点だらけです。
以下列記します。
- 疑問のひとつは天皇が国民の名で公布するということがあるんでしょうか?
通常の法律、条約は天皇の名で公布します。官報では天皇の御印を印刷できないので御名御璽(ぎょめいぎょじ)って印刷してあります。誰だって御名御璽って聞いたことありますよね?
国民の名で公布するなら天皇としての行為の意義は何でしょうか?
第7条でいう、『天皇が公布する』とは『天皇の名で公布する』ということじゃないですか?
- 疑問のふたつは上記と似ていますがまったく異なるものです。
いかなる文書も制定者以外は改正できない。これは論理的に考えれば当然です。もちろん正しくは制定者個人というより制定権限者ですが、
つまり、日本国憲法は天皇の名で公布されており、これを改正するなら天皇の名で公布するのが当然です。天皇以外の名で公布するなら、それは改正ではなく、憲法破棄あるいはクーデターといいます。
いえ、これは当然ですよね。ISO規格にもありますよ、文書は制定者が改正することってね、
- 会社で課長が決裁したのを部長が覆すことは理屈上できません。できるのは課長を変えることです。通常の会社でそういったことが行われているのは、本来は部長の権限であるものを課長に委譲しているからでしょう。
決裁とか承認って最終判断と言う意味です。最終判断でなければ検認、照査、確認などといいます。
- 昔江戸時代、キリシタンが改宗するにはキリストに改宗を誓うことが必要だったと読んだ記憶があります。変更するに当たってもその切り替え時までは従前のルールが適用されるのは当たり前、
百歩譲って、日本国憲法を制定したときこの条文が入っているのだから、その時点で国民の名で公布することが決められたという解釈もあるかもしれません。
でもそれも論理的におかしいですよね。
天皇が他人の名で国事行為することが許されるのか?という論理的な問題となります。
天皇のお立場で考えれば、他人(国民)の名でもって公布することに道義的に疑問を感じます。いえいえ、自分たち(国民)が勝手にすればって思いますね。
- 疑問その三
この条文を正しく読めば憲法改正は不可能です。驚くことはありません。
第9章にも憲法96条にも改正という言葉が使われていますが、条文を読むと「この憲法と一体を成すものとして」とあります。これは従来の条文を残すという意味です。
『一体とはいったい?』などと駄洒落を考えることはありません。
もとネタアメリカ憲法第5条「この憲法の一部として効力を有する。」を考えると明白です。アメリカ憲法には文言が書き直された条項はありません。建国時の憲法条文がすべて残っており、それ以降のすべての変更は修正条項として本文の後ろに追記されています。類似の国法で矛盾した時は時間的に後ろの法律が優るという「後法優位の原則」により修正されています。
つまり日本国憲法のある条文を改正しようとすると、新しい条文は修正第1条となり本文の後ろに追加されていきます。従来の1条から103条までの条文もそのまま残ります。各種憲法の解説書を見ても日本国憲法もこの考えであると記述しているのはまだ見たことがありません。
もし、制定者が本文の条項を書き直すことを想定していたなら「天皇は、国民の名で、改正された憲法を、直ちにこれを公布する。」と記述したはずです。
よってこの憲法は追加修正手順を定めているが、改正手順について記述していません。
本条項のまとめ
日本国憲法の改正は不可能である。できるのは追加修正のみです。
聞くところによると、社民党委員長土井たか子氏は憲法学者だそうです。
ぜひご教授願いたいものです。
参考までに
日本国憲法英訳というよりマッカーサー草案89条原文
as an integral part of this Constitution
アメリカ憲法第5条
as part of this Constitution
マッカーサーが草案を日本側に要求(提示)したとき、既にアメリカ憲法は11回の修正を行っており、アメリカ側が憲法改正を条文書き換えと考えていたとは思えない。
integralとは「・・・するために必要な」という形容詞であるからこの有無で憲法改正(修正)方法は変わらない。
 96条2項 その2 (2005.03.21)
96条2項 その2 (2005.03.21)
ええ、私は日本国憲法は決して改正ができず、あるのは修正条項の追加のみであると語っておりました。
この考え、何の本も主張も知らずにもうろくしたおばQジジイの頭で考えたことでありまして、オリジナルと思っておりましたが、ある本で大昔、小嶋和司さんて方が、あっしと同じことを唱えていたということを知りました。
残念ながら小嶋先生の説は大勢とはならずこの読み方は消え去ってしまったようです。
でも私のようにISO的解釈であれば到達するという解釈は、正しいとはいえませんが、間違いであるという根拠もなさそうです。
憲法論はISOよりも純粋な論理学から離れているのでしょう。
Baru様からご意見を頂きました。(07.04.15)
はじめまして
国民投票法に関して検索していて、あなたのページを読みました。
一箇所、おそらく解釈間違いと思われるものを見つけましたので、投稿します。
第9章にも憲法96条にも改正という言葉が使われていますが、条文を読むと「この憲法と一体を成すものとして」とあります。これは従来の条文を残すという意味です。
これですが、新憲法(もしくは変更部分)が現憲法と一体を成すと解釈しておられますが、この文の主語は「天皇は」ですから、天皇が憲法と一体を成すと解釈すべきだと思います。
具体的存在である人が、抽象的存在である憲法と一体をなすことはありえませんから、天皇という機関(地位)が憲法と一体と成すということだと思います。したがって、天皇制を廃止しようとすると、まず、この条文を変更し、その後で天皇制に関する部分を変更するという手順を踏む必要がありそうですね。Baru様 お便りありがとうございます。
なんといおうと、日本国憲法は英文を翻訳して作られたというのが実情と思います。
それならば日本文を縦横斜めに読んで検討するのではなく、英文を読んで考えるべきでしょう。
さて、問題となっている文章は
Amendmets when so ratified shall immediately be promulgated by the Emperor in the name of the people, as an integral part of this Constitution.
どう読んでも、考えても、天皇が憲法と一体をなすということはないでしょう。
天皇が憲法と一体として公布するとしか読めません。
英語の読解問題ですね。
もっとも日本語を読んでも『天皇が憲法と一体を成す』とも読めませんよ。
ついでに言えば、この解釈は終戦後法律学者が唱えたそうですが、多勢に無勢で霧散したそうです。
日本国憲法の目次にもどる