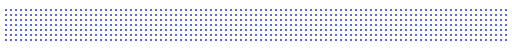はじめに
幸田露伴の『五重塔』では、貧しく世間に評価されない職人の十兵衛が、上人を介して五重塔の棟梁として世間を見返す過程が描かれている。資本主義がたち上がりつつあった明治二十年代は、不景気の後に貧富の格差が拡大する時代であった。露伴は「順々競争の世の中」で徳の高い人間が正当に評価されず不遇であると考えている。そういう人間の感情が「高士世に容れざるの恨み」として作品のテーマになっている。露伴は十兵衛に同情する立場に立ち、十兵衛と上人と源太の三人の世界をあるべき人間関係として描いた。ここに露伴が社会を批判的に捉える視点がある。
十兵衛は周囲の人間からのっそりと軽蔑的に扱われているものの、金銭欲を持たず貧しさに耐え実入りの少ない仕事でも手を抜かない。この十兵衛が、いかにして棟梁になるのか、五重塔を建て世に認められる過程で生じる問題にどう対処していくのか、その時にどういう感情を持つのかに、今も残る日本的精神の特徴が描かれている。
十兵衛が棟梁になる手段
大工の十兵衛は鑿や鉋を持った時の腕前には絶対の自信を持ちながら、腕前を生かす仕事に恵まれない。十兵衛は「鷹揚」で「世才に疎く心よき」気質のため実入りの多い仕事を取りのがしている。その結果、十兵衛は長屋の羽目板や馬小屋などの数仕事に明け暮れ妻子の衣服にも事欠く貧しい暮しを送っている。妻のお浪も「腕の半分でも吾夫の気心が働い」たならこんな貧乏はしないと見ている。ここでは金銭欲をもつかどうか、そのために上手く立ち回るかどうかが貧しくなるかどうかの原因と考えられている。露伴は金銭欲を持たない十兵衛の道徳的資質を高く評価している。
十兵衛の転機となるのは感応寺の改修工事である。人々から慕われている有名な朗円上人が、学徒のためにもう少し広ければとつぶやいた独り言が大工事の契機になり、その独り言が学徒によって広められ「百川海に入るごとく金銭の驚かるるほど」集まった。上人の徳が改築工事をしても使い切れないほどの大金を集める原動力として描かれている。
上人は改築工事で余った大金の使途を相談されて「五重塔を建てよ」と一言指示している。五重塔は初めから計画が予定されたものではなく、資金は余った金でついでのように作られることになった。そのために上人の意志が我欲や執着心からより離れる形をとっている。上人は大金を自由にする立場にあり、それと対照的に十兵衛は貧しさのどん底にある。しかし彼らは金銭欲と無縁である点において一致している。
十兵衛は百年に一度あるかないかの五重塔の建立にあたって命に代えてもやり遂げると奮い立っている。しかし、感応寺は棟梁として名高い源太によって大がかりに改築され、その実績に基づいて源太に五重塔の見積もりが命じられた。十兵衛は源太に比べて改築工事を取り仕切ったような実績がない。十兵衛が源太に対抗するには、源太以上の度量や伎倆や準備などが必要である。十兵衛の意図の正しさや真剣さは実績や準備を含む人生全体によって証明され周囲に認められる。
しかし十兵衛は感応寺の上人への直訴に全てを賭けている。百年に一度あるかどうかわからない五重塔の建立にあたって、棟梁としての実績や伎倆は問題にされずに十兵衛と上人との関係だけに焦点が当てられている。五重塔を建てるにあたっての設計や予算、材料の手配や工事の期間など一般的に想定される条件が問題にされていない。
十兵衛が名乗り出たことの影響はお浪やお吉の反応を通してそれぞれの家庭内の矛盾として描かれている。源太の妻のお吉は「もしこの仕事を奪られたら」源太がどれだけ癇癪を起こすかと心配し、十兵衛の妻のお浪は日頃から世話になっている棟梁の源太と妻のお吉と対立し義理を欠くことになるのを懸念している。また源太の手下の清吉に「幾らか棟梁にも姉御にも心配をさせるその面が憎くって面が憎くって堪りませぬ」と言わせている。彼らは日頃世話になりながら仕事を取ろうとする十兵衛の義理を欠く態度に対して怒ったり心配したりしている。
清吉が「感応時の和尚様に胡麻をすり込むという話だがそれは正気の沙汰か寝ぼけてか」と十兵衛を罵倒している。清吉は軽薄な人間として描かれているが、清吉が指摘するように準備をしないで名乗りをあげることは正気の沙汰ではない。お吉の「あれめにできる仕事でもなく、あれめの下に立って働く者もあるまい」という指摘も十兵衛の弱点をついている。この作品では露伴が否定的に描く人間にむしろ常識が反映している。
上人との面会
十兵衛は寺の用人たちに粗末に扱われて上人に面会できなかった。寺の用人たちは十兵衛の面会を邪魔する極端な俗物として描かれている。寺の用人や小坊主は、粗末ななりをして垢臭いとかぼろぼろの草履を履いていることで十兵衛を軽んじている。それに対して十兵衛は大声で面会を求めている。露伴は十兵衛の情熱を声の大きさや何度も繰り返し叫びつづける姿に描いている。両者は単純な善人と悪人に分けられ、用人たちにたたき出される間際に上人が登場し十兵衛を助け出している。上人は寺の人間とは対照的に「未学を軽んぜず下司をも侮らず」「迂闊な根性にも慈悲のしみ透」人物であって十兵衛を外見で判断しない。また、上人は周囲の人間を一喝して黙らせ「為右衛門汝がただすなおに取り次ぎさへすれば子細はなうてあろうものを」と諭している。上人は十兵衛を助け出し為右衛門を諭す格の違う人間である。しかし、みなりが悪いくらいの理由で面会させない用人がいることは上人の無能でもある。
十兵衛は上人の茶室に上がる時に汚れをはたかず顔を突き合わせるほど間近に座る。この態度は「礼儀にならわねど十分に偽飾なき情の真実」を表すとされている。「舌の動きもたどたどしく」「声の調子も不揃い」「辛くも胸にあることを額やら腋の下の汗と共に絞り出せば」など緊張してぎごちない様子は十兵衛の純粋性として描かれている。礼儀を知らないことや緊張してぎごちない態度自体には積極的意味はない。しかし露伴はこれを小才がきいて上手く立ち回る気質と比較して積極性を持たせようとしている。
十兵衛は、「伎倆もない癖に智恵ばかり達者な奴」が宮を作り堂を請け負うのを見て、「天道様が智恵といふものを我にはくださらない故」世間に認められない不運を上人に訴えた。そこで十兵衛は「私は馬鹿」「意気地のない奴」だけれども「仕事が下手ではない」「嘘はなかなか申しませぬ」と上人に言っている。これは実績を示すことで信用を求める態度ではない。十兵衛の謙遜や正直が棟梁としての重要な要素と意識されている。十兵衛の価値はこの点にある。仕事が下手な人間や嘘を言うような人間との比較ははじめから問題にならない。露伴はこのような程度の低い比較を持ち出さねば十兵衛の感情を描写できない。
上人の提案
>>「かほどの技倆を有ちながら空しく埋もれ名を発せず世を経るものもある事か、傍眼にさへも気の毒なるを当人の身となりては如何に口惜きことならむ、あはれ如是ものに成るべきならば功名を得させて、多年抱ける心願に負かざらしめたし」「木匠の道は小なるにせよ其に一心の誠を委ね、生命を懸けて欲も大概は忘れ卑劣き念も起さず、唯只鑿をもつては能く穿らんことを思ひ鉋を持つては好く削らんことを思ふ心の尊さは金にも銀にも比へ難きを、僅に残す便宜もなくて徒らに北ぼうの土に没め冥途の苞と齎し去らしめんこと思へば憫然至極なり、良馬主を得ざるの悲み、高士世に容れられざるの恨みも詮ずるところは異ることなし、よしよし我図らずも十兵衛が胸に懐ける無価の宝珠の微光を認めしこそ縁なれ、此度の工事を彼に命け、せめては少しの報酬をば彼が誠実の心に得させんと思はれける」
十兵衛は「願はくは上人の我が愚しきを憐みて我に命令たまはむことを」願っている。十兵衛は源太に対抗して棟梁になるために上人の同情心に期待をかけている。それに対して上人は十兵衛の「唯只鑿をもつては能く穿らんことを思ひ鉋を持つては好く削らんことを思ふ心の尊さ」が五重塔の棟梁に相応しいと考えている。上人は十兵衛の心情に報いるものとして五重塔の棟梁の座を考えている。立派な心掛けを持ちながら社会に正当に評価されない人間を世に出すひとつの実例として上人と十兵衛の関係が描かれている。
一方で源太は世間の信望があつく改修工事を取り仕切った実績がある。その上に十兵衛に情けをかける男気もある。従って上人も簡単に排除できない人物である。
>>「二人の願ひを双方とも聞き届けては遣りたけれど其は固より叶ひがたく、一人に任さば一人の歎き、誰に定めて命けんといふ標準のあるではなし、役僧用人等の分別にも及ばねば老僧が分別にも及ばぬほどに此分別は汝達の相談に任す、老僧は関はぬ、汝達の相談のまとまりたる通り取り上げて与るべければよく家に帰つて相談して来よ」
上人は源太と十兵衛に対して、棟梁決定の標準はなく判断すべき人間もいないから二人の相談の結果を受け入れると申し渡している。上人は自分の判断を直接伝えるのではなく、「仏説」によって意思を示している。仏説の内容は、相手のために譲る気持ちを持って協力して事にあたれば必ず報われるというものである。相手のために犠牲になって譲る心のあるものに五重塔の棟梁の座が与えられ、そうでなければ排除される。上人は回りくどい方法をとりながら両者が譲ることを強制している。これは自発的に辞退したという形式を整えその上で上人が決定するという上人にきずがつかないやり方である。
十兵衛の葛藤の質
上人の価値観を受け入れる十兵衛と源太は、我欲と譲る心の間でそれぞれ葛藤する高度の人間として描かれている。十兵衛の葛藤は愚痴や恨みに描かれている。十兵衛は棟梁を譲るにあたって「一生とてもこの十兵衛は世に出ることのならぬ身」だと歎いている。十兵衛は、「ああ情けない、恨めしい、天道様が恨めしい」「浮世の怜悧な人たちの物笑ひになつてしまえばそれで済む」「つくづく世間が詰まらない」と愚痴を並べている。露伴は十兵衛の断念がいかに辛いことか、いかに無私に五重塔の棟梁を願っているかを描こうとしている。ここでの十兵衛の愚痴は雛形を作り上人に直訴したことでやるべきことはすべて終えたと考えていることが前提になっている。十兵衛の感情は、実践的な準備がすくないことに対応しておおげさである。十兵衛の言う世間が詰まらないとは、努力したのに自分の思い通りにならないことに過ぎない。十兵衛は自分の心意気を不当に高く評価し自分はすべての人間を超える高みにあると自惚れている。全力をかけて願う心意気において誰にも負けないと自負している。十兵衛は自惚れの裏返しとして優れた自分が認められないことを大きな不幸だと考えている。十兵衛が五重塔の棟梁を心から望むことと愚痴を言うことは同じレベルの感情である。十兵衛の場合は棟梁の資格があると考える自惚れと自己卑下が同一である。
十兵衛の行動はすべて上人への働きかけに限定されている。十兵衛はこのような一回きりの努力に期待をかけ、瞬間的な情熱で動いている。十兵衛は自分が上人の慈悲心に頼らねばならない孤立的状況にあることは意識されない。十兵衛はこのような上人との孤立的関係の中でのみ棟梁になる可能性があると想定されている。
上人との徳の一致は、十兵衛と源太がいかにゆずるかという点にある。これは競争とは言えない。実践において心構えが試され修正される厳しい経験を経ることが出来ずそれに応じた豊かな感情を生むこともない。十兵衛のように諦めると言って思い悩むか、源太のように二人で半分ずつという連名仕事を考えるかくらいしか道が残らない。
上人の提案によって十兵衛は源太と同等または同等以上の立場に立つことができる。客観的な実績や信用で競争する場合は十兵衛が棟梁になる可能性はない。競争の代わりに譲る心を持つという徳目が上人によって持ち出され、その徳に無批判的であるかどうかが棟梁になる上での決定的な要素になっている。加えて上人は世の中で不遇である人間に対して同情心が強い。こういう世界では貧しく孤立している十兵衛が源太に比べて有利である。十兵衛と源太は上人の謎解きが源太から棟梁の座を奪い十兵衛に有利に働くことを意識できないまま行動している。
>>「天晴名誉の仕事をして持つたる腕の光をあらはし、欲徳では無い職人の本望を見事に遂げて、末代に十兵衛といふ男が意匠ぶり細工ぶり此視て知れと残さうつもりであらうが、察しも付かう我とても其は同じこと」
>>「情無い親方様、二人で為うとは情無い、十兵衛に半分仕事を譲つて下されうとは御慈悲のやうで情無い、厭でござります、厭でござります、塔の建てたいは山々でも既十兵衛は断念て居りまする、御上人様の御諭を聞いてからの帰り道、すつぱり思ひあきらめました、身の程にも無い考を持つたが間違ひ、嗚呼私が馬鹿でござりました、のつそりは何処迄ものつそりで馬鹿にさへなつてゐればそれで可い訳、溝板でもたたいて一生を終りませう、親方様堪忍して下され、我が悪い、塔を建てうとは既申しませぬ、見ず知らずの他の人ではなし御恩になつた親方様の一人で立派に建てらるゝを余所ながら視て喜びませうと元気無げに云ひ出・・・」
源太は十兵衛を欲得抜きで五重塔を願う心意気において認めている。その上で源太は連名仕事を提案している。連名仕事は上人の条件にかなう解決策のひとつである。上人の条件が厳としてある以上は相手のために諦めて全てを譲るか協力して分け合うかの選択しか残らない。
源太にとって連名仕事はほぼ手に入れていた五重塔の仕事を半分譲ることである。お互いに自分一人で五重塔を建てたい気持ちを抑える連名仕事は双方に不満が残る妥協的な対策である。源太は「つくづくそなたの身を察すればいっそ仕事もくれてやりたいような気のするほど、といふて我も欲は捨てきれぬ」と譲るか譲らないかで葛藤していた。源太の情熱からしても半分諦めるのは全て諦めるに等しい。源太の妥協的な提案に対して、十兵衛はそれは情けないやるなら一人でと意地を貫いて連名仕事を拒否している。十兵衛が「すっぱり」諦めたというのは、十兵衛には源太と協力するような方法が頭に浮かびさえしないことを示している。十兵衛は周囲に諦めた場合の惨めさについて何度も同じ言葉を繰りかえしている。十兵衛は状況さえ変わればすぐに棟梁の座に飛びつくような精神をもっている。おまけに瀬戸際で源太に恨み言を並べるのは、源太に責任があるような言い方になっている。譲るかどうかや譲ればどれだけ惨めかというのは仕事の内容と何の関係もない。作品では仕事の内容と無関係なことが仕事を任されるうえで非常に重要な役割を果たしている。
源太は十兵衛に対して「汝一人に重石を背負つて左様沈まれて仕舞ふては、源太が男になれるか」という。十兵衛が断れば源太が一人で立てることはできない。源太がひとりで塔を建てるのは上人の条件に反する。お互いが一人で建てるのが本望なら半分諦めるか全て諦めるかは大差がない。これはお吉が後に指摘する通りである。十兵衛の意地は源太の意地でもある。十兵衛に拒否されると源太は諦めると上人に申し出る、すなわち十兵衛が意地を通すと同じ意地を通すのが源太の男気である。彼らは同じ価値観内部でせめぎ合っている。
十兵衛は源太が帰ってから断った理由をお浪に話している。十兵衛は勢力のある職人の下でその力を利用して利益を得るやり方を「寄生木」として軽蔑していた。十兵衛は連名仕事を自分が「寄生木」になることと同じだと考えている。十兵衛は源太の勢力に依存しない心構えを重要視している。二人で仕事を分ける場合は分担が問題になり仕事の内容に入ることになる。露伴は具体的な協力関係を描写出来ない。
>>「私一人して立派に塔は建つるにせよ、それでは折角御諭しを受けた甲斐無く、源太がまた我欲にばかり強いやうで男児らしうも無い話し、といふて十兵衛は十兵衛の思わくを滅多に捨はすまじき様子、彼も全く自己を押へて譲れば源太も自己を押へて彼に仕事をさせ下されと譲らねばならぬ義理人情、いろいろ愚昧な考を使つて漸く案じ出したことにも十兵衛が乗らねば仕方なく、それを怒つても恨むでも是非のない訳、既此上には変つた分別も私には出ませぬ、唯願ふはお上人様、たとへば十兵衛一人に仰せつけられますればとて私かならず何とも思ひますまいほどに、十兵衛になり私になり二人共々になり何様とも仰せつけられて下さりませ、御口づからの事なれば十兵衛も私も互に争ふ心は捨てをりまするほどに露さら故障はござりませぬ」
棟梁の座を譲る心がけは五重塔の建立の準備をすることとは比較にならない立派なものとされている。譲るのを名誉と考え恵まれないものに助力する価値観が源太に想定されている。ここで源太が欲を強く出せば上人に源太を排除する意志が必要になる。十兵衛が棟梁になるには、源太に相手が自分を抑えて譲ったからには源太も譲る精神がなければならない。こういう精神を想定することで上人の意志は実現される。
棟梁の決定
>>「左様ぢやろ左様ぢやろ、流石に汝も見上げた男ぢや、好い/\、其心掛一つで既う生雲塔見事に建てたより立派に汝はなつて居る・・・はやこの時に十兵衛が仕事に助力せん心の、世に美しくも湧たるなるべし。」
上人は源太と十兵衛の希望を諦めさせることで棟梁を十兵衛に決する。こういう手続きを経て源太を排除したにも関わらず上人は排除したとは考えない。上人の価値観では源太は十兵衛を助力することにおいて半分は五重塔を引き受けたと考えている。棟梁を十兵衛にする決定は、棟梁になりたい気持ちを殺して譲ったことへの報いであるとともに、貧しく哀れな十兵衛を世に出す上人の徳の高さや慈悲深さを示すものである。
上人と源太の協力の意味
>>「昨日にまた上人様から態々の御招で、行つて見たれば我を御賞美の御言葉数々の其上、いよいよ十兵衛に普請一切申しつけたが蔭になつて助けてやれ、皆汝の善根福種になるぢや、十兵衛が手には職人もあるまい、彼がいよいよ取掛る日には何人も傭ふ其中に汝が手下の者も交らう、必ず猜忌邪曲など起さぬやうに其等には汝から能く云ひ含めて遣るがよいとの細い御諭し、何から何まで見透して御慈悲深い上人様のありがたさにつくづく我折つて帰つて来た」
上人は源太が不遇な十兵衛に助力することを徳の実現と考えている。上人は源太の手下のものがひがみ根性をださないように源太が言い含めることを求めた。上人は源太が悟った譲る心を手下の者にまで徹底することこそ十兵衛への最大の援助だと考えている。
源太が十兵衛に援助する「木材の引合い」「鳶人足への渡り」は、源太が長年の仕事の中で築いてきた信頼関係である。この援助は、それがなければ五重塔は建てられないような決定的な援助である。この作品では材料や大工の手配など人間関係における援助がいかに決定的な役割を果たすかが全く理解されていない。これだけの実績と関係を持つ源太は簡単に十兵衛を排除できる。お吉が十兵衛に諦めさせましょうかというのは、この実績に基づく言葉である。しかし、そういう力を持ちながら、その力を恵まれない人間に使うところに源太の行動の意義が認められている。
>> 親方、堪忍して下され口がきけませぬ、十兵衛には口がきけませぬ、こ、こ、此通り、あゝ有り難うござりますると愚魯しくもまた真実に唯平伏して泣きゐたり。
十兵衛はお浪以上に源太への義理人情を強く意識していたことが明らかになっている。十兵衛はこの義理人情を強く意識しながらも、五重塔のためにはそれを破らざるをえない、源太と対立せざるを得ないと考えていた。十兵衛は義理人情を大きな障害として意識しており、それを乗り越えることを露伴は十兵衛の偉大さとして描いている。しかし、日頃世話になっていることが大きな仕事をやめる理由にはならない。義理人情はその時々の利害によって振り捨てられたり重んじられたりするものである。
十兵衛は上人への直訴の時には職人と材料のことは全く考えていなかったのと同じく、職人の手配や材料の仕入れを決定的な援助とは考えない。むしろ受け入れても入れなくても構わない程度に考えている。十兵衛が意地を見せるのは源太が見取り図や京都奈良の五重塔の写しなどの提供の申し出に対してである。十兵衛は決定的な援助を受けながらこの点では源太に頼らないと意地を通している。このあと源太は善意が裏切られたことに腹を立て酒やどんちゃん騒ぎで憂さ晴らしする。これが清吉の不始末を呼ぶ伏線となっている。十兵衛はこのような事情には関係なく仕事に邁進する者として肯定的に描かれ、源太は否定的な印象を与えるように描かれている。ここも十兵衛の道徳心を際立たせるための描写である。
清吉の仕返し
源太の妻のお吉は、源太が五重塔を十兵衛に譲ったことに不満を持っている。のっそりのことなど気にかけずに仕事を取ってしまえば良いと公言するお吉は露伴の考える世間の意見を代表している。露伴がお吉を通して世間を批判的に描いても、お吉の言うことのほうが現実的と思われる。お吉の主張を否定して十兵衛の勝利を描こうとすると、あり得ない偶然を構成しなければならなくなる。その一つが清吉の役回りである。清吉は日頃から源太夫婦に世話になり恩義を感じている。清吉は十兵衛への仕返しに十兵衛の耳をそぎ肩に傷を負わせお吉の憂さ晴らしをした。仕返しを忠誠と信じている清吉の直情的な行為は、源太の名誉を傷つけ上人との関係で源太の立場を悪くした。源太は上人が言い含めたことを守ることができなかった。源太は資材や職人の手配をしながらも表舞台には一切出ることができず、十兵衛との関係でも発言権を失った。一方でこの事件は十兵衛を軽蔑と孤立から救い出して、五重塔の仕事を進捗させる決定的な契機となった。
職人と材料の手配の次に起こる困難は、職人を統率していくことである。事件が起こるまでは十兵衛が命懸けで仕事をしても、職人たちは上辺では十兵衛に従いつつも相も変わらず十兵衛を軽蔑し仕事も怠けがちであった。十兵衛は自分が名前だけの棟梁に過ぎない事を嘆きつつも、この事件が起こるまでは全くの無力であった。
十兵衛が怪我の翌日に仕事場に現れたことで、職人たちの働きぶりは一変した。十兵衛は心配し制止するお浪を振り切って怪我をおして仕事場へ出ることで職人仲間から棟梁としての完全な信頼を得た。今まで職人たちの軽蔑が一変して「一を聞いては三まで働き、二と言はれしには四まで動く」ように変身するのは不自然である。清吉の軽率な行動によって十兵衛が信頼を得る契機がたなぼた式に与えられている。露伴は十兵衛に大工を統率する能力を描く事は出来ずこのような事件を設定している。
妻は十兵衛の傷を心配するだけで十兵衛の情熱を理解できないものとして描かれている。十兵衛は痛みをおして仕事に出る姿勢を持つことを決定的に重視している。この態度が職人をどう統率するかという困難な課題の解決になっている。怪我に耐える事や妻の制止を振り切るのは平凡なことであって、棟梁としての資質を表すものではない。露伴は突発的な事態に一時的に耐える消極的能力を十兵衛の高い能力として描いている。
十兵衛への称賛
完成した五重塔には特殊な称賛がなされている。それは十兵衛が惨めな境遇にありながら道徳心を失わず困苦に負けなかったことと埋もれるべき十兵衛を世に出した上人の徳の高さに対するものである。一言で言うと十兵衛と上人の個人的徳に対する称賛である。十兵衛を軽蔑していた世の中が、十兵衛に対して正しく目を開いたことが、五重塔の建立による社会的な影響である。十兵衛は五重塔によって軽蔑された連中を見返している。個人的に評価されることや見返すことが、大きな仕事を通して得られる成果だとされるのは貧しい精神である。
露伴は貧しく惨めな人間に報いがなければなないと考えている。これは貧しさに対する偏見である。棟梁になって個人的に称賛されることを解決とするなら、貧しさはそれまでの耐えるべき生活としての意義しか持たないものになる。したがって貧しく惨めさを強調して描くほどに、貧しさは報われたときの喜びを倍加する材料に過ぎなくなる。
落成式を前にして未曾有の嵐で五重塔がきしみだすと、為右衛門と役僧の円道は五重塔が倒れるのを心配して十兵衛に使いを送る。瓦が飛ぶような嵐の中を使いに出るものはおらず、褒美の金にあかして掃除人の七蔵爺を十兵衛のもとへ行かせる。この呼び出しは十兵衛の自信と覚悟の表明の機会として描かれている。
まず七蔵が十兵衛の家に行ってみると、十兵衛の屋根が半分めくれて「見るさへ気の毒な」有様であった。七蔵は妻子をこんな目にあわせる十兵衛を気の回らない人間だと軽蔑している。しかし露伴の関心は、棟梁になっても自分のために金を使わないで五重塔に専心する十兵衛の心掛けを描くことにある。激しい嵐の中で十兵衛が泰然とする根拠は「紙を木にして仕事もせず、魔術も手抜きもしてゐぬ」ことである。手抜きやごまかしをしない心構えは、改めて問題にするようなことではない。十兵衛は手抜きをしていないから塔は倒れないと繰りかえし強弁して七蔵を嵐の中に追い返している。上人との信頼関係以外を認めない十兵衛は呼び出しには応じない。嵐の大袈裟な描写は十兵衛の確信を描くための材料として扱われている。
十兵衛は手抜きやごまかしをしないことを信頼関係の根拠としているものの、一般に信頼は実践的行動の結果に対して形成される。五重塔に多くの人間がかかわり実際的な困難を乗り越えてきた場合は、広汎な人間関係の展開がありそれに応じた豊かな感情が形成される。十兵衛は自分がすこしでも疑われると再び恨みつらみを蓄積するという同じ経過を繰り返している。
円道と為右衛門は上人の命と偽って再び七蔵に十兵衛を呼び出させる。この策略によって十兵衛は絶対的に信頼していた上人が自分を信用していないと誤解した。彼らがお互いに絶対的信頼を求める場合は対立を内包している。この些細な誤解を契機にして、「つくづく頼もしげ無き世間、もう十兵衛の生き甲斐無し」と世間への恨みを増幅し、五重塔も「真に果敢無き少時の夢」として否定され「塔も倒れよ」と極端に走っている。このような十兵衛の態度は普通の関係さえ築けない精神の未熟さや経験の浅さを示している。
この事件では再び円道と為右衛門が悪役を演じている。彼らは棟梁の十兵衛を相変わらず軽々しく扱っている。彼らの策略は上人のあずかり知らぬところで行われたことだから上人にはきずがつかない。後に上人と十兵衛の名誉が回復されるというお決まりの展開になる。
十兵衛は「板一枚の吹きめくられ釘一本の抜かるゝとも、味気なき世に未練はもたねば物の見事に死んで退け」る覚悟で嵐の中を五重塔に向かっている。一般に板一枚がはがれたり釘一本が抜けることで信頼が失われることはない。また大袈裟な死の覚悟表明は、仕事に対する誠実さの証明にはならない。
五重塔と対照的に、欲から出資した金持ちの芝居小屋や面の憎い生け花の宗匠の家が被害を受け、江戸で有名な大寺が役僧と請負師の不正による手抜きが原因で倒壊した。彼らの災難は、欲深さや不正に天罰が下ったものとして扱われている。暴風雨の被害による周囲の不幸は、ただ十兵衛の五重塔をひき立たせる材料である。感応寺の五重塔は他の建物と違って手抜き工事や横領がなかったことで倒壊しなかった。ここでは災害の影響や被害には関心がなく、五重塔が微塵も揺らがなかったことだけに関心が向いている。
>>「いづれも感応寺生雲塔の釘一本ゆるまず板一枚剥がれざりしには舌を巻きて讃歎し。いや彼塔を作つた十兵衛といふは何とえらいものではござらぬ歟、彼塔倒れたら生きては居ぬ覚悟であつたさうな、すでの事に鑿喞むで十六問真逆しまに飛ぶところ欄干を斯う踏み、風雨を睨んで彼程の大揉の中に泰然と構へて居たといふが、其一念でも破壊るまい、風の神も大方血眼で睨まれては遠慮が出たであらう歟、甚五郎このかたの名人ぢや真の棟梁ぢや」
ここでも仕事の見事さは板一枚や釘一本さえびくともしないことで証明されている。人々は塔が倒れたら鑿を含んで塔の上から飛び下りる覚悟で十兵衛が風雨をにらんでじっと構えていたことを「名人じゃ、真の棟梁じゃ」と称賛している。為右衛門の策略が、かえって十兵衛の価値を高める機会を与えるたなぼた式の展開になっている。露伴は十兵衛の覚悟の強さを強調するために嵐を大袈裟に描いている。塔に上り風雨をにらむ事は名人と言われる棟梁の心掛けとは別である。
上人は最後に「江都の住人十兵衛之を造り川越源太郎之を成す」と銘を入れた。この銘は十兵衛に五重塔の棟梁の座を譲り十兵衛に助力した源太への報いである。五重塔を建てたことと棟梁を譲ったことは同じ比重があると考えられている。十兵衛は五重塔を建て偉大な棟梁として認知されたにもかかわらず、功績を源太と分けるのを許すとされている。五重塔を建てても手柄を独り占めにしない十兵衛の姿勢が高く評価されている。
これだけの大きな仕事をやり遂げると、次の仕事への大きなステップがあるはずである。しかし十兵衛には五重塔の建立の後に新しい仕事が残っていない。十兵衛が世間に称賛されることで仕事が終わっている。十兵衛が報われることを解決とすると、その過程を二度描くことはできない。報われることが終点である。十兵衛は棟梁になって世間から注目され金も地位も得られる棟梁の座を手に入れた。しかしそれに驕らない態度が貧しい人間とも金持ちとも区別される個性として高く評価されている。
おわりに
この作品では、十兵衛の五重塔を建てたい意志の純粋さや決意の堅固さが表明されている。十兵衛はそういう意志を持ちながらも恵まれない境遇にあると考えられている。そして源太の恩義を振り切る点に葛藤が想定されている。現代でも、善良な意図を持ちながら恵まれない、恩義に縛られて身動きがとれないと感じている場合が少なくないと思われる。このような精神は十兵衛の活躍を高く評価するだろう。また自分の思い通りにならないと世の中を恨みがましく思ったり道徳的批判に転じることもよくあると思われる。
十兵衛は実践より意図だけを問題にしている。十兵衛の場合は、源太に譲ることが客観的に自分の利益になっている。相手のために、あるいは世のためによかれと思って行動して、客観的には自分の都合だけが優先されている。自分の行動の客観的意義に気づいておらず、それを押し通す場合には、お互いの信頼関係は失われる。このような態度は一般にごまかしや責任逃れになることが多い。意図の客観的な正しさは、実践の系列的な流れによって判断される。実践的な精神にとっても意図だけを問題にする態度には対処が難しく、その結果として実践的な精神が孤立し、不満が個別的に蓄積されることも日本の場合は多いと思われる。
一般に社会的に力量を発揮できるような環境を作るのは非常に困難な課題である。露伴は十兵衛を厳しい競争にさらすことはない。それが上人と源太の役割である。露伴は、五重塔の建立という大事業を彼ら三人の世界での心の持ち方の問題に解消している。事業が大きければ大きいほど、より多様な諸関係や利害対立が生じるし、事業を実践していく場面でより多くの人間関係に巻き込まれ、競争の規模も利害対立も大きくなる。このような諸関係が発展すれば、露伴の描いた世界は社会への表面的な批判意識としてだれにも非現実的と思われることになる。しかし同時に諸関係の進展に伴って、このような道徳的な批判意識やあるべき姿を想定する精神は、形をかえて自然発生的に生じる。このような精神は、露伴が文学史の主流からはずれた位置で取り扱われることを不当だと考える批評にも表れている。露伴は表面的とはいえ社会の矛盾を描き、そこに日本人的精神の一面を描写した。現代に生きる我々は厳しい競争が本格的に始まろうとしている時代に直面しているものの、思想上ではここに描かれた精神からなかなか自由ではない。その点で『五重塔』の細かな分析の作業も意味があると思われる。それは明治文学史の研究にも当てはまることである。
文責 寺田
昌雄
このページの先頭に戻る
近代文学研究会の目次に戻る