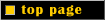
|
関東学院 |
33-12 |
京都産業 | ||
|
13-26 | ||||
|
46 |
3 |
T |
2 |
38 |
|
1 |
4 | |||
|
3 |
G |
1 | ||
|
1 |
3 | |||
|
4 |
PG |
0 | ||
|
2 |
0 | |||
|
0 |
DG |
0 | ||
|
0 |
0 | |||
|
久富(1年) |
FW |
佐藤(4年) |
|
作田(4年) |
野山(3年) | |
|
上田(3年) |
木下(4年) | |
|
三浦(4年) |
池田(2年) | |
|
宮村(3年) |
内野(4年) | |
|
宮下(3年) |
池上(3年) | |
|
神辺(4年) |
岡本(3年) | |
|
箕内(4年) |
平田(1年) | |
|
池村(3年) |
HB |
吉原(4年) |
|
淵上(2年) |
山岡(4年) | |
|
萩原(2年) |
TB |
佐藤(4年) |
|
萩谷(3年) |
奥(4年) | |
|
吉岡(2年) |
鈴木(3年) | |
|
四宮(1年) |
岡田(4年) | |
|
立川(3年) |
FB |
大畑(4年) |
|
やはり関東学院の強さは本物でした。
大学選手権一回戦の対筑波を見て感じたのは、今年の関東学院は大人のラグビーをしている、ということ。ラインアウトの正確さ、固くパックされたモール、ラックへの集散の速さ、一人一人の的確なディフェンス、そしてチャンスと見るやバックス、フォワード関係なくあっという間に形成されるラインなど、社会人に比べればスケールこそ劣るものの、それぞれのプレーの完成度の高さは大学レベルでは群を抜いています。 この試合、破壊力のある京産のフォワードに関東がどこまで耐えられるか、というのも一つのポイントでしたが、そのフォワード戦でも、ラック、モールに対する集散の速さと精度の高さで互角に渡り合いました。 京産大は思っていたよりずっと強いチームでしたが、細かいプレーに対する精度が低すぎます。ボール支配率では優位に立っていたにもかかわらず、ラックやモールでターンオーバーされることが何度あったのでしょう。実力差のある関西リーグでは、その弱点を露呈することなく圧勝してきたのでしょうが、この大一番ではそこを関東学院に突かれてしまいました。やはりここ数年の関西リーグの全体的なレベルの低下が影響しているようです。後の社会人のサントリー対トヨタの試合でも感じられた、関東と関西の厳しいゲームの経験値の差が結果的に勝敗を左右するようになりました。 もう一つは、やはりスクラムにこだわり過ぎ。 明治などもこのパターンで自滅することがありますが、いくら「自分達のラグビー」と言っても、最終目標はあくまでも勝負に勝つこと。スクラムにこだわり、時間をかけてトライを取っても、その時間の浪費が自分達を敗戦に導くのだ、ということを選手が認識すべきでした。終了間際、切り札大畑君を使って取ったバックスの二個のトライは、勝利を確信した関東学院の油断があったにせよ、十分に通用するものだったはず。今後の京産大の課題は「どんな良いチームを作るか」ではなく「如何に勝てるチームを作るか」でしょう。 勝った関東学院。初の決勝進出ですが、前に述べたような理由から、総合力では明治よりこちらが上、と見ます。 ただ気になるのは試合後の春口監督のコメントにあるように『とりあえず国立一勝という目標を達成した』ことで選手が安心してしまうこと。決勝戦を楽しみたいというのも解りますが、これだけのチームを今後また作れる保証はどこにもありません。ここまで来た以上、死にもの狂いで優勝を狙うべき。関東学院の初優勝を阻む要因があるとすれば、その辺りの選手や監督のモチベーションではないでしょうか。 準決勝が終わって国立競技場から信濃町駅への帰り際、関東学院の学生と思われるグループがふと漏らした言葉が気になります。 「今日来て良かったな。どうせ決勝では明治にぼろ負けだろうからさ・・・」 そんなことはありませんよ、関東学院の学生諸君。 今年のチームなら大学日本一は決して夢などではありません。敢えて言わせてもらえれば、今年のチームで日本一になれなければ、当分そのチャンスなど訪れないのでは? と思いましたが、よくよくメンバーを見ると4年生は4人だけ。箕内君やスーパーブーツの神辺君が卒業すると言っても、楽しみな素材も多く、ひょっとして来年の方がもっと凄いチームになるのかもしれません。 |