夏休みに地区の教員を対象とした研修会が開かれることになっています。初心者を対象とした講座(Windowsの基本操作)から,コンピュータ室の管理者を対象とした講座(ネットワークシステムの管理運営)まで,全部で5種類の講座が開かれます。 昨年度,私は,コンピュータ室の管理者を対象とした講座を受講したのですが,今回は講師として,周辺機器の活用をテーマとした講座を受け持つことになりました。 講師をやることについては別に構わないのですが,そのために自分自身が講座を受講することができなくなってしまったのはとても残念です。昨年は,LANの設定やWebサーバーの構築の仕方などを教えていただき,大変役に立ったので,今年もぜひ参加したかったです。 私のように,コンピュータ室の管理者でありながら,講師を引き受けることになった方は他にも数名いるので,コンピュータ室の管理者を対象とした講座のみ,日程をずらして実施してほしいという要望が出されていたのですが,未だ教育委員会からの連絡は来ていません。いつの間にかうやむやになってしまったようです。 「各方面と調整しながら設定した日程なので今さら変更できない」という釈明は分からないでもありませんが,「コンピュータ室管理者=研修会の講師」という図式は当然予想されることだと思うので,やはり最初に立てた計画がまずかったと思います。そしてそのことについて臨機応変に対応できない,融通のきかなさが,いつも感じることですが,お役所仕事の大きな欠点だと思います。 さて,私たち(3名)が受け持つ「周辺機器の活用講座」は,私たちの学校で行われることになっているので,本日他の2名の方に来校していただき,コンピュータ室で研修の具体的な進め方について話し合いました。 機器の増設,ソフトのインストール,テキストの作成など,やらなくちゃならないことたくさんあって,当日(7/28)までは忙しい日々を送ることになりそうです。 受講者の方も分からないことばかりで大変だとは思うのですが,講師の側の方がはるかにしんどいことを痛感しています。 地元のパソコンショップでは,25日0時に「Windows98」が発売されます。 ちょっと恥ずかしいけど行ってみようかと思います。 その前にデータのバックアップをとっておかなくっちゃ。 今夜も眠れません。 昨晩も朝方まで起きていたため,3時過ぎまで爆睡していました。 夕方から学校に出かけ,28日のコンピュータ研修会の準備をしました。 講座の内容は「周辺機器の活用」です。使用する機器は,デジカメ,イメージスキャナ,プリンタ,ビデオプロジェクタの4種類です。20名が参加します。 デジカメは,全員が持参してくる手はずになっているので,そのユーティリティソフトをすべてのパソコンにインストールしておきました。 イメージスキャナは,コンピュータ室にある1台だけでは間に合わないので,自宅のスキャナを持ち込み,クライアントに接続しておきました。ユーティリティソフトもLAN経由で転送してインストールしておきました。 プリンタは,コンピュータ室では,プリンタバッファを使って1台のプリンタをパソコン4台で共有しているのですが,グラフィック関係の印刷が中心なので,間に合わないかも知れません。しかし他校から借りてくるのは面倒なのでこのままでやります。 ビデオプロジェクタは,一人一人には操作してもらわず,こちらからの説明だけで終わらせるつもりなので,コンピュータ室にある1台だけでOKです。ビデオを接続する方法も紹介するつもりなので,自宅のビデオを運び入れておきました。 ところでこの講座で問題となるのは,各学校に導入されている機器が,導入された年度によって異なっていることです。デジカメもスキャナもビデオプロジェクタもプリンタも,そしてパソコン本体も異なっています。 これがある程度使い慣れている方なら,インターフェースが多少違っていてもそれなりに対処できると思うのですが,この研修会に参加するのは,”できない方”ばかりに決まっていますから,スイッチの位置が違うだけでも戸惑われることでしょう。私の学校の機器を用いて行ったことを,自分の学校で生かしていけるかどうかははなはだ疑問です。 そこで,周辺機器の活用という本来のねらいからは少し外れるかも知れませんが,”どのように操作するか”よりも,”どういう場面で使っていくか”という点を重視した内容にしていくことにしました。 デジカメやスキャナで取り込んだ画像はどのような場面で使うことができるか,ビデオプロジェクタを使うとどんなことができるか,などです。 先生方が,授業でコンピュータを使わない(使えない)理由として,”操作の仕方が分からない”ということと,”どんな場面で使えばよいか分からない”ということが大きな理由として挙げられると思うのですが,こういう風にアイディアを提供するかたちで進めていけば,後者の理由を解消するのに多少なりとも役立つのではないかと思います。 機器とソフトの準備が終わりました。明日はテキストの作成です。 日直だったので一日中学校にいました。朝一番に校舎内外の見回りをして,後はずっと職員室での勤務です。 とはいってもお客さんの接待と電話番ぐらいしかやることはないので,ほとんど自分の仕事を行うことができます。 今日は,明日の研修会のテキストを作成しました。 私が担当しているのは,主にソフトウェアの操作に関する部分で,「スライドショーを作ろう」,「カレンダーを作ろう」,「ホームページを作ろう」などです。 実は今回作成したテキストの大半は,これまでに作った校内研修会用のテキストを流用できたので大変助かりました。というか,使えるネタがたくさんあるので,私の学校で研修会が開かれることになったのですけどね。 見出しを書き換え,一部手直しをして終了です。所要時間は1時間ほどでした。 それでも「ホームページを作ろう」だけは,昨年度パソコンクラブで使ったものは「Netscape Gold」対応だったので,「Netscape Communicator」対応のものを新しく作らねばなりませんでした。 3時間で完成しました。 その後,明日の講座で使うテキストだけ印刷を済ませ,今日の作業は終わりにしました。 午後からの研修会に備え,機器・ソフトの最終チェックを今から行います。 (7/28 9:10) 「周辺機器の活用」講座の一日目でした。 予想外でした。うれしい誤算です。 参加者は男性4名・女性16名でほぼ全員が35歳以上です。実習内容は,デジカメで写真を撮り,撮った写真をパソコンに取り込み,ユーティリティソフトを用いて編集し,それらの画像でスライドショーを作成するというものです。 女性の方が多いこと,35歳以上という年齢層,デジカメという機械(笑)を使うこと,ケーブル接続しなければならないこと,ワープロ以外のソフトを使用すること...。 今までの私の経験から考えると,大混乱に陥る条件が整い過ぎています。 決して偏見を抱いていたつもりはないのですが,私はこの年齢層の女性の先生方が最もメカ(!?)に弱いのではないかと思っていました。 35歳以上の世代の女性の方は,学生時代はもちろん,学校にコンピュータが導入されるまでは,パソコンなど一度も触ったことがない方が多いだろうと推測されます。しかも現在は,結婚して育児に忙しく,時間的な余裕も少ないだろうと想像されます。 そしてデジカメなどの周辺機器は,日常生活や日頃の授業において絶対に必要なツールではありませんから,ある程度パソコンを使い慣れている方でも,それほど関心は高くないだろうと思われます。 そんなわけで今日の研修会は”覚悟”して臨んだのですが,こちらが拍子抜けするほどみなさん飲み込みがはやく,順調に進めることができました。 もちろんそうでない方もいますが,ダブルクリックができないとか,FDドライブの場所が分からないとか,別のアプリーケーションを開いているのにそのことに気付かないとか,頭を抱えたくなるような事態は発生しませんでした。ケーブルを接続せずに写真を取り込もうとしていた方はいましたが。 考えてみれば,「周辺機器の活用」などという講座に自ら望んで参加しようという方は,パソコンの操作にはちょっと自信がある,つまりWindowsのごく基本的な操作ぐらいはできる方なのかも知れません。 明日からのコンピュータ研修会の準備を行いました。 明日(8/20)の研修内容はイメージスキャナの操作と名刺作りです。 イメージスキャナは,コンピュータ室には1台しかないので,私とM先生が所有しているものを持ち込み,3台を使って行います。プリンタも,コンピュータ室には5台しかないので,M先生の学校のプリンタをお借りして,10台で行います。 私ができる範囲の準備はすでに済ませたので,あとは明日M先生が持ってくるスキャナとプリンタをセットするだけです。 名刺作りは,1学期末に行った「PTAパソコン講座」で使ったものを流用できますから,特別な準備は必要ありません。 明後日(8/21)の研修内容はホームページ作りとビデオプロジェクタの操作です。 ホームページ作成ソフトには「Netscape Communicator」を使います。これはすでにインストール済みです。 ホームページ作りのテキストは,昨年度パソコンクラブで使ったもの(ただしNetscape Gold用)を流用するつもりだったのですが,手直ししているうちに,結局ほとんど全部書き換える羽目になってしまいました。 テキストの冒頭に,「作品をホームページ形式(html)で作るメリットは?」という文章を載せてみたのですが,こんなので良いでしょうか。まだ1日余裕があるので,アドバイスいただけるとありがたいです。
それから,ホームページの閲覧に関して,先日”発見”した便利な機能を早速使ってみることにしました。コンピュータ研修会用のフォルダを「仮想ディレクトリ」に設定したので,アップロード作業を行わなくてもリアルタイムに更新されるはずです。 それと同時に,任意のファイル名をつけた”白紙のページ”(人数分=20個)と,それらのページにリンクした”コンピュータ研修会トップページ”を作っておきました。受講者がその”白紙のページ”にホームページを作成すれば,わざわざアドレスを入力しなくてもトップページからのリンクをクリックするだけで,各自のページを閲覧することができるはずです。 これらが果たしてうまく機能するでしょうか。少々心配です。 大方の準備は研修会初日(7/28)までに済ませておいたつもりだったのですが,テキストを見直したり,機器やファイルの準備をしているうちにいつの間にか6時間も費やしてしまいました。 ふぅ。いつものことですが。 研修会2日目が終わりました。 イメージスキャナの操作を練習した後,取り込んだ画像を使って名刺作りを行ったのですが,今日は作戦失敗でした。私たち講師3名は,最初から最後までの2時間半,息つく暇もありませんでした。コマネズミのようにくるくるくるくる走り回っていました。とっても疲れました。 前回は,研修内容をいくつかのステップに分けておき,全員ができるようになったことを見届けてから次のステップに進むというやり方で行いました。 ところが今回は,用意した機器(イメージスキャナとプリンタ)の数が少ないので,一斉に行うのは無理です。それに順番待ちによる時間のロスが心配でした。 そこで今回は,とにかくやれることから取りかかっていただこうということで,一連の手順「スキャナの操作−名刺作り−印刷」をすべて説明した後で,作業を始めていただいたのです。そうしたら大混乱でした。もちろんマニュアルは用意しましたし,つまずきそうなところは念入りに話したつもりですけどね。でも頭に詰め込む量が少々多すぎたようです。 しかし気分的にはずいぶんラクなもので,「PTAのパソコン講座」の時は,保護者の方がうまくできないと,自分の説明の仕方が悪かったのではないかと自責の念にかられていたのですが,先生方が相手の今回は,「あ,そうでしたね。さっき説明してもらったことでした。忘れてました。えへへ。」などと答えていただけるので,精神的に疲れることはありませんでした。 今日最大の誤算は,”強制終了”が大量に発生してしまったことでした。わずか2時間ほどの間に5回も発生してしまった方もいたほどです。 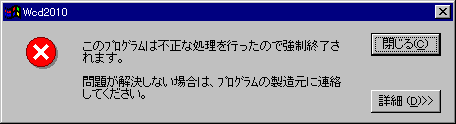 とにかくこのメッセージが出てしまったら一巻の終わりです。(たまに助かることもありますが。) 「PTAパソコン講座」で名刺を作ったときには,強制終了など起こらなかったので,今回は途中でセーブしておくようアドバイスしていませんでした。ですから,皆さん最初から作り直す羽目になってしまいました。 「残念ながらこのボタン(閉じる)を押して,ソフトを終了させるしかありません。」 「作ったところまでは保存しておきたいのですが。」 「できません。」 強制終了ラッシュの原因は,おそらく,名刺に組み込んだ画像のサイズが大き過ぎたことによるメモリ不足じゃないかなと思います。たくさんの画像を組み込んでカラフルな名刺にした方ほど強制終了の発生率が高かったですから。これが24MBしか積んでいない私の学校のパソコンの限界ですね。 そういえば今思い出したのですが,「PTAパソコン講座」のときも,一人だけ強制終了になってしまい,泣きそうになりながら作り直していた方がいたのでした。その点先生方は,日頃から強制終了には慣れているせいか,”最初から作り直し”という冷酷な事実を,(表面上は)わりと冷静に受け止めていたようです。内心ではどう思っていたか分かりませんが。 色々ありました。でも今回の「名刺作り」は,先生方にとっても楽しんでいただけました。 研修を終え,笑顔でコンピュータ室を後にする先生方を見ていると,本当にうれしいです。 疲れ切った様子で帰っていかれると,私たちも悩んでしまいますからね。 でも帰るときに椅子の整頓ぐらいはしてほしいなあ。子どもでもできるよ。それが残念。 研修会&明日の打ち合わせが長引いてしまったので,家に帰らずに学校から直接飲み会に出かけました。 それで今,コンピュータ室にいます。(苦笑) (8/21 1:00) コンピュータ研修会3日目が終わりました。 研修内容はホームページ作りとビデオプロジェクタの使い方です。ビデオプロジェクタの使い方は説明のみで済ませ,ホームページ作りを中心に進めていきました。 今日もほとんど休みなしに動き回りました。2時間ほどの間に1人平均2回程度として計40回以上はコールされたと思います。しかしながら昨日ほどはしんどくありませんでした。 昨日は強制終了などの予期せぬトラブルが頻発しましたし,質問やトラブルの内容も多岐にわたっていたのですが,今日質問された内容は,リンクや画像挿入の仕方など,戸惑うことが事前に予想されていたことばかりだったので,昨日よりも対応しやすかったです。 いや,それよりも,昨日あんなに疲れてしまったのは,ただ単に休みボケのせいだったのかも。 終わりに感想を書いていただきました。社交辞令とはいえ,好意的な内容が多かったのはやはり嬉しいです。 (多くの方から指摘された代表的な意見。) 良かった点 ・講師の方がとても親切に教えてくれた。 ・色々な機器やソフトの使い方を知り,今まで以上にパソコンに興味が沸いてきた。 悪かった点 ・研修で使った機器やソフトが自分の学校にはない(あるいは種類が違う)ので,すぐには役立たない。 ・どの教科のどの授業で機器やソフトを使えばよいかという具体的なアイディアを教えて欲しかった。 良かった点として,研修の中身よりも態度が評価されたのはちょっと寂しいです。 機器やソフトが学校ごとに異なるという問題点はもちろん最初から承知していました。ですが,機種によって操作方法が多少異なっていても,基本的な機能の差異はほとんどありませんから,ただ単に機器の操作方法を教えるだけでなく,データの扱い方(ソフトを使っての活用法)をも提示するようにすれば,それなりに役に立つのではないかと考えていたのです。しかしそれが授業に即したものではなかったため,受講者の方にとっては少々物足りない結果になってしまいました。 毎度のことですが, 機器やソフトを駆使した授業例を紹介すると,まずは使い方などの初歩的なことからやって欲しいと言われます。 それなのに, ごく基本的な操作の仕方を教えると,授業ですぐに役立つようなもっと具体的な内容を扱って欲しいと言われます。 困ってしまいます。 |