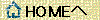
|
緊急提言 今からでも間に合う 1.序 本試験まで2ヶ月をきりました。これから短期合格を狙う方、せっぱ詰まって今年は危ないかもと思っている方、まだまだこれからです。 とにかく残された時間の総点検を行ってください。やみくもに勉強だけしていても良い結果が出るとは限りません。受験勉強は限られた範囲を勉強すれば良いのです。また行政書士試験は合格基準が明確です、競争試験ではなく60%得点すれば受かる試験です。天才や秀才を選ぶ試験ではないのです。合格基準が明確であるということは、ある意味で初学者でも経験者と互角だということを忘れないで下さい。 経営学で良く用いられる「Plan - Do -See」という言葉があります。「計画―実行―評価」ということです。受験勉強においてもこのサイクルが重要なとこは変わりありませんが、自分にあったサイクルを具体的に身に付けることが重要です。受験本や専門学校では最大公約数的なサイクルしか教えてくれません。今から逆転を狙うには、自分なりの方法を考えなければいけないのです。 合格基準が明確であるということは「敵を知る」ということです。明確であるだけで敵の全てを知ったわけではありませんが、かなりの手掛かりになります。孫子の兵法で言えば次に「己を知る」ことが重要になってきます。 「Plan - Do -See」と孫子の兵法との関係はどうなっていると思いますか?前者は戦術とその実行方法を指し、後者は戦略の組み方を指します。 まず戦略を立て、それから戦術(Plan)を考え実行する(Do)のです。最初から完璧な戦略を立てられるわけがないので、後から修正が可能なように全期間戦略と中期戦略を立てた方が自分を見失うこともなく、時間の節約になるという事も頭に入れておいてください。実行の後、評価(See)して中期戦略を修正しないと、玉砕も止むなしという状況に陥ってしまいます。 戦略を立てずに実行すれば、時間を浪費し玉砕の可能性が高くなるのです。今は時間が惜しい時期ではありますが、一度立ち止まって戦略をじっくり練ることが合格への近道なのです。半日でも1日でも費やしてもやる価値があるものなのです。 2.戦略 戦略において重要なのは情報です。行政書士試験の場合は何度も書いたように60%の得点が最低の目標です。ただし、この試験の場合は一般教養科目で出題範囲が広いので、この科目を制するための情報は少ないと考えるべきです。言い方を変えれば運に左右される要素が多いと思って良いでしょう。ですから、確実に合格できる目標は70%であり、現実には80%を目標に置くべきです。 また戦略を立てるのも、法令と一般教養とを分けて立てるべきでしょう。情報量の多い法令を重点的に攻略した方が有利であることは間違いありません。情報量の少ない一般教養にこだわっていては短期決戦では大きく不利になります。理論的には法令100点満点中86点、教養40点満点中0点でも合格できることになっています。法令重視、このことを念頭に入れてください。 全期間戦略 全期間戦略としては、このように法令86%教養0%は非現実的として、法令66%教養50%から法令80%教養60%位までを目標にすれば充分です。そしていつまでに一通りの学習を終え、いつからアウトプット中心の学習に変えていくのか決めてください。全期間が2ヶ月あるのなら最後の2週間は総仕上げのためにアウトプット中心になるでしょうし、全期間が1ヶ月なら最後3日がその期間になるでしょう。全期間戦略はこの程度で充分です。 中期戦略(ここがポイントです) 中期戦略は、残された時間を1週間ごとに区切って考えると良いでしょう。本試験は日曜日の午後に行われます。したがって当然月曜日から日曜日までの1週間を単位にしてください。そして毎週日曜日の夜に残りの中期戦略を修正する必要があります。この中期戦略の修正が受験において最も重要なポイントとなります。やるべきことは決まっており、残された時間は明確です。その中でペースを上げれば対応できるものや、最早一度捨てて余裕が出来たらやれるもの等を区分して中期戦略を修正しないと無駄に試験会場に足を運ぶことになります。 具体的な中期戦略は、人それぞれなので示すことができません。実行可能な戦術の制約(1日の勉強時間等)を受けますし、得意分野・苦手分野が人により異なるからです。ですからここではヒントしか示すことができません。だから自分でじっくりと練る必要があるのです。 法令科目では、公法系と私法系に分けると良いでしょう。テキストや問題集のページ通りに憲法―民法―行政法などという順番にやると効率は悪くなります。公法系の憲法・行政法・地方自治法のブロックと私法系の民法―商法のブロック、その他の法律のブロックに分け、公法系・私法系・その他の順番で行うのが良いでしょう。私法系の民法は奥が深く考えなければならないので、中期戦略の修正を何度かやってコツを掴んだ後にやった方が時間管理の点で楽になります。民法で時間を消費してしまうと全体の計画に大きく影響してしまうからです。 さらに各法律をもう少し細分化しておくことも必要です。憲法なら天皇・基本的人権・国会・内閣など、民法なら総則・物権・債権・親族法などです。1週間に行える量を具体的に把握しておかないと、現実性のある中期戦略は立てられないと思ってください。繰り返しになりますが、中期戦略の立て方と修正しながらでも中期戦略の目標を達成することが合格への道です。ですから、ある部分は流し読みしか出来なくても中期戦略の目標達成を第1優先にすることが重要です。流し読みしか出来なかった部分は、中期戦略の修正の中でどこかに組み入れれば良いのです。 この時期に立ち止まってはいられないのです。一部のために全体を犠牲することは許されないと肝に銘じてください。たまたま本試験でその不充分だった部分から出題されるかもしれません。しかし、計画通りに進められなかった、いわば自分にとって苦手分野に他の分野を犠牲にしてまで時間を投入する余裕があるのでしょうか?苦手分野が進まなかったら、他の分野が早く進むように中期戦略を修正して、苦手分野に手を付ける時間を捻出するのが本来やるべきことなのです。 一般教養科目でも同じです。細分化し中期戦略を立て、それを修正しながらこなして行くのです。特に一般教養科目ではいくらやっても出来ない分野があることは避けられないのです。とにかく先に進むこと、そして必要な得点を得るために、あと何処をどれだけやれば良いのかを把握して中期戦略を修正し、時間を捻出するのです。 戦術 戦術は、この1つ上のぺーじから「自由だからこそ戦術を選べる」を参照してください。付け加えるならば、択一と記述式の対策は分けなくても学習は可能です。5択の問題を1問1答形式(○×問題)に作り変えたり、5択の選択肢の正誤を導き出す論理を書き出すなどの作業で対応できると考えます。記述式の出題は行政法・地方自治法・民法が中心でしょう。ただし、憲法は司法試験と行政書士試験にしかないという特徴のある試験科目なので一応気を付けておいた方が良いでしょう。 3.結 行政書士試験は天才を選ぶ試験ではないし、スペシャリストの資格試験でもありません。全体で60%得点することが出来れば良いのです。そのためには何が必要なのか、中期戦略の立案と修正の過程でそれを見つけることが出来れば、合格にかなり近づくと考えています。皆さんの検討を祈ります。 |
|
|