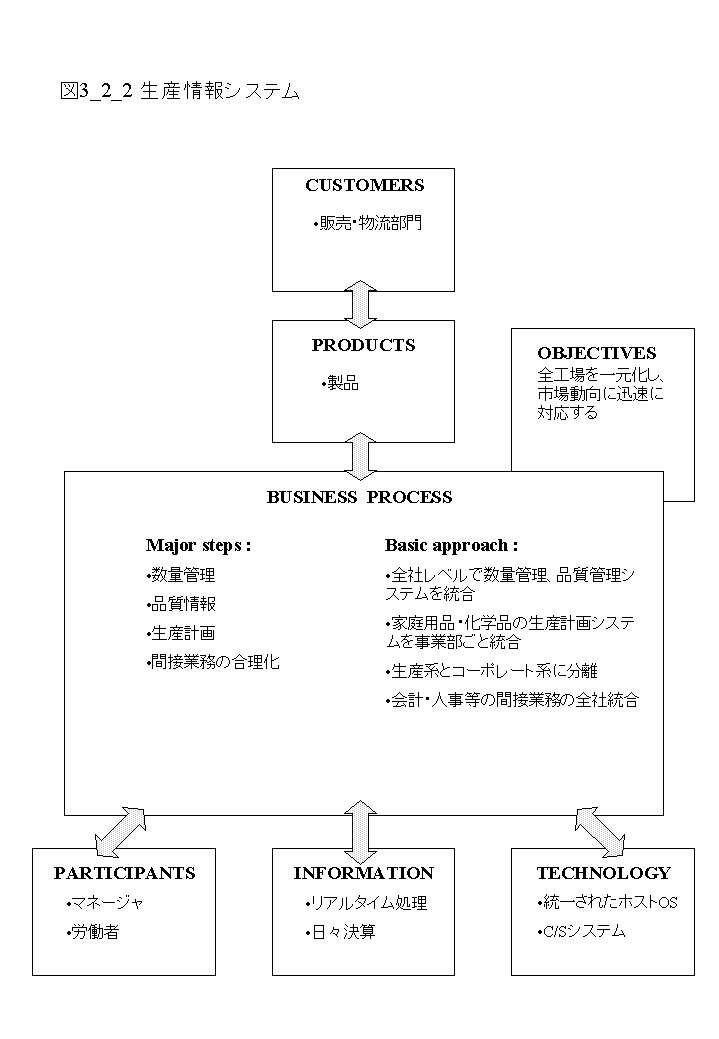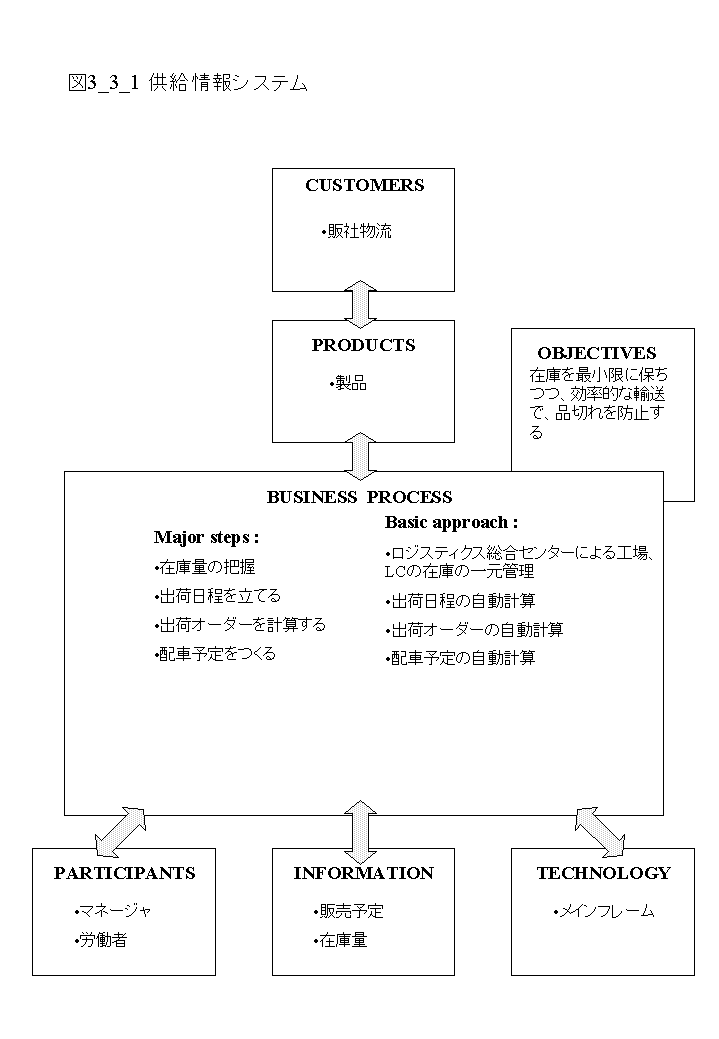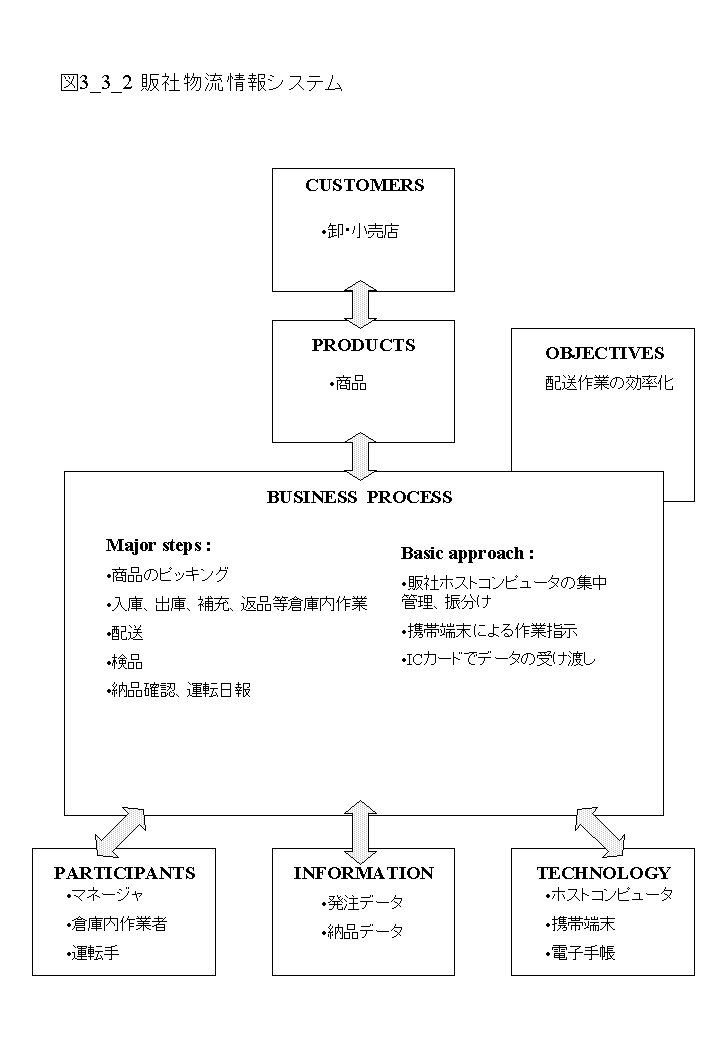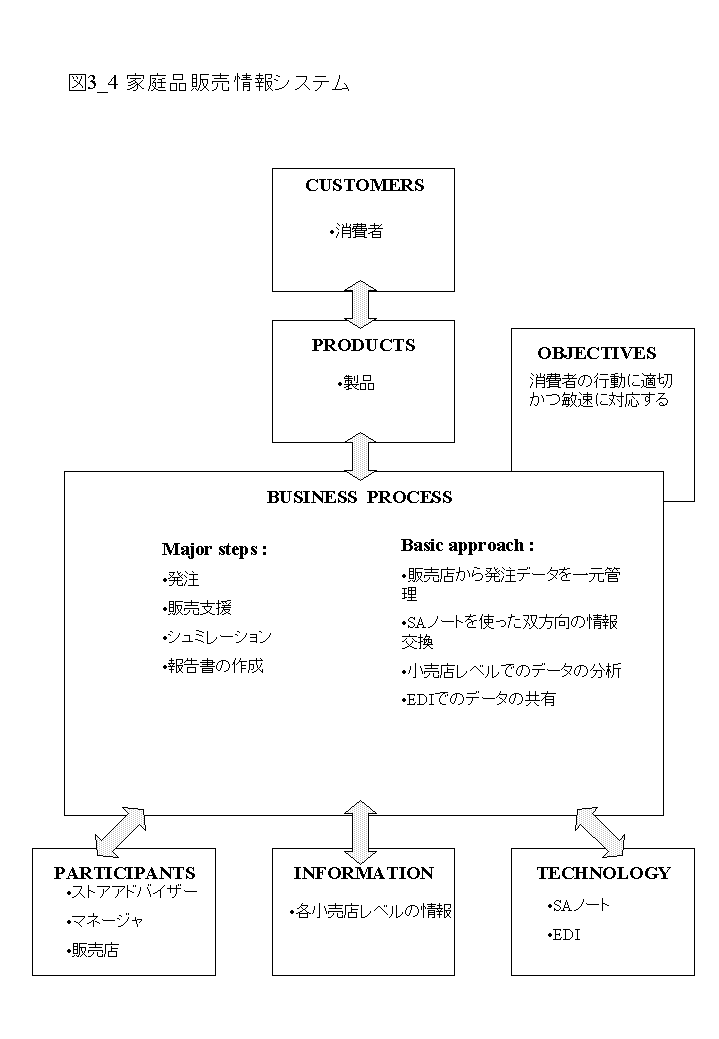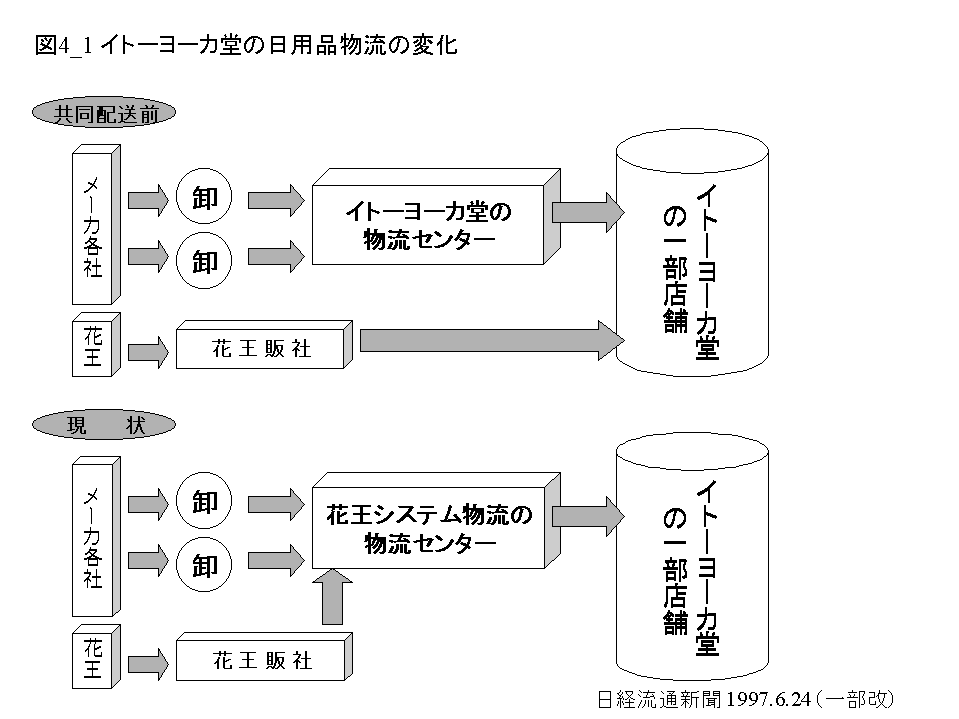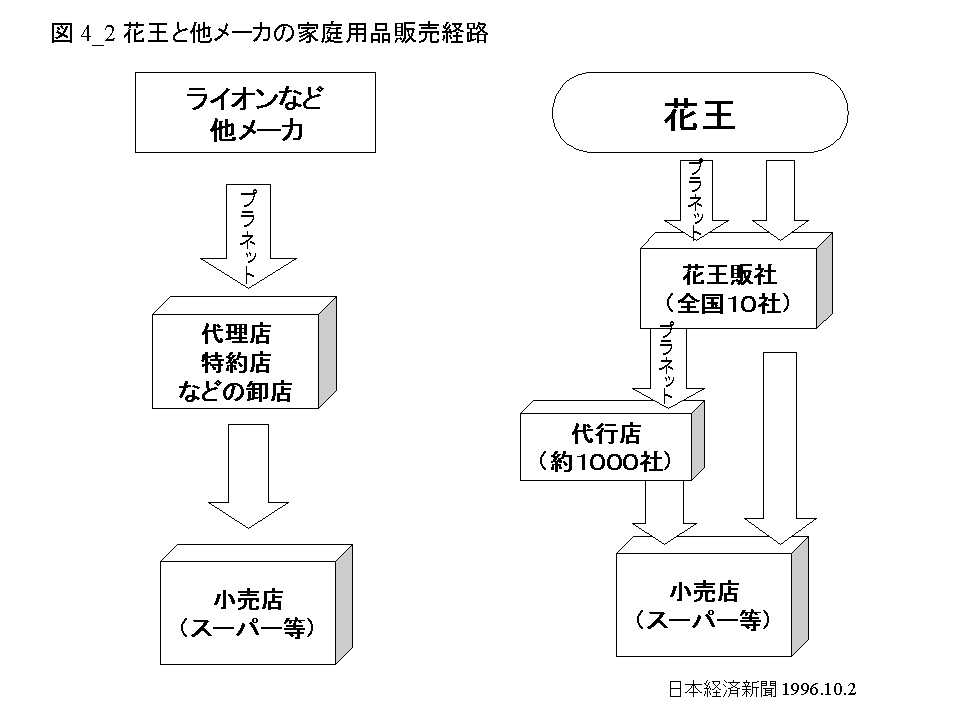1999年1月8日
花王とネットワーク
自社完結型経営から外部資源活用型経営へ
明治大学商学部商学科
村田ゼミナール
小松原 康平
kohei@mars.dti.ne.jp
#1. はじめに
#2. 花王の情報システムと環境
#2.1 花王が目指した自社完結型経営
#2.2 自社完結型経営の限界
#2.3 外部資源活用型経営へ
#3. 生販一体型情報システム
#3.1 生販一体型情報システム
#3.2 生産情報システム
#3.3 物流情報システム
#3.3.1 供給情報システム
#3.3.2 販社物流情報システム
#3.4 家庭品販売情報システム
#4. これからの花王
#4.1 物流システムの開放
#4.2 プラネットへの参加
#5.おわりに
#参考文献:
#参考URL:
1. はじめに
1980年3月期から増収増益を記録していた花王は、1998年3月期に減収となり、増収増益記録は17期連続でストップした。
花王はメーカという枠を超え、生産、物流、販売のすべてを自社でまかなうことで効率化をはかってきた。各部門を情報システムで結び付け、情報を共有化することによって、効率化を追求してきた結果、自社ですべてをまかなえる自社完結型経営を完成させた。これは、消費者の声を生産現場にまで反映させることや、全国の工場があたかも一つの工場のように稼動することが出来るような、常に効率的で無駄を排除した経営を実現した。
ところが、生産、物流、販売のすべてを自前で築き上げる自己完結型経営が、しだいに「悪魔のサイクル」といわれる価格下落のスピードに対応できなくなって来たのである。商品が多様化し、多品種、少量、高頻度の物流を求める現在において、花王の目指した効率化は逆に、少品種、大量、低頻度を目指し構築されていたのである。
そこで花王は、今までの自前主義を180度転換し、ライオンやユニ・チャーム等のメーカーが共同で企画しているVAN受注システム「プラネット」への参加や、販売店への共同配送事業など共同主義へと大変革を行っている。
しかし、これまでの17期連続の増収増益を支えた自前主義も、これからの共同主義の変革も、ネットワークを重要な経営基盤と位置づけ活用する姿勢に変わりはない。
そこで自前主義、共同主義のそれぞれのネットワーク、つまり自前主義の基盤となった情報システムと、これから花王が目指す姿を見ていきたいと思う。
2. 花王の情報システムと環境
2.1 花王が目指した自社完結型経営
花王は1997年3月期、17期連続の増収増益を果たした。最高益の更新は16期連続であった。その年の売上高はライバルのライオンの2倍以上、経常利益では大手化粧品メーカ、資生堂の1.8倍に達する。
この競争力は、花王が追求してきた自社完結型経営に求められる。自社完結型経営とは、原料調達から生産、物流、販売までを垂直的に統合することで、効率化を図ろうとする経営形態である。この経営形態こそが、花王と他のメーカとの最大の違いなのであり、アドバンテージであった。
この自社完結型経営の大きな特徴の一つが、販社制度である。販社は、従来の問屋、卸店にかわる流通機構であり、その目的は小売店と直結する販売組織を実現することにあった(図2_1)。
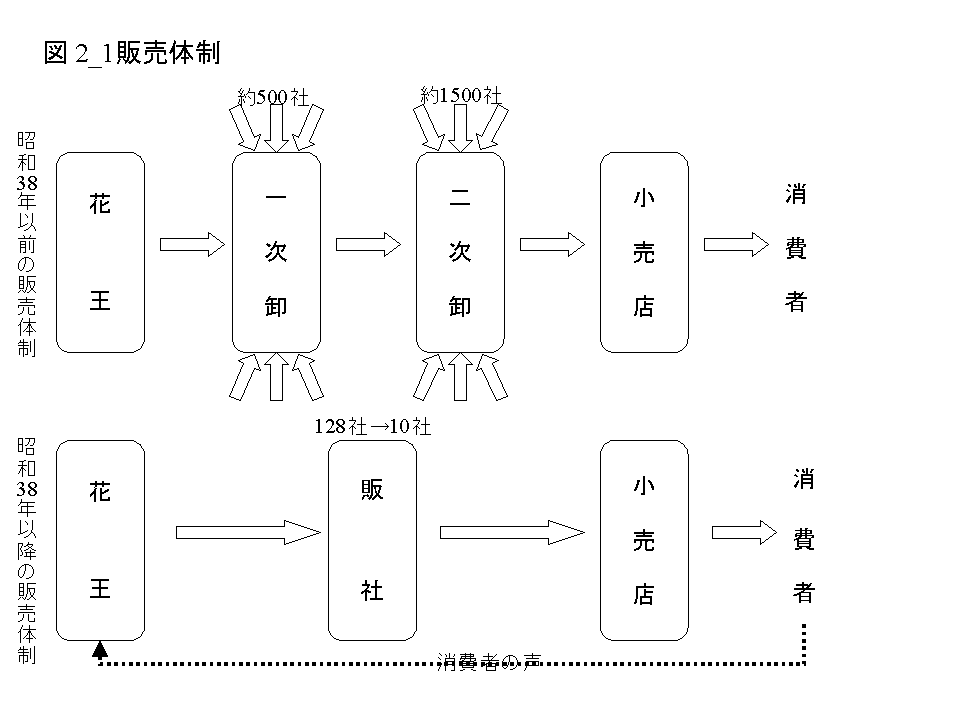 販社制度導入に至った経緯を見てみると、1960年当時、中小スーパーの乱立と乱売競争により、家庭品は価格破壊の状況に陥いっていた。そしてスーパーは問屋に「この価格にしなければ他の問屋で買う」と、価格引き下げを迫ってきた。そこで、花王は問屋レベルでの価格競争を避けるために、花王と複数の問屋の出資により販社を設立したのである。
販社制度導入に至った経緯を見てみると、1960年当時、中小スーパーの乱立と乱売競争により、家庭品は価格破壊の状況に陥いっていた。そしてスーパーは問屋に「この価格にしなければ他の問屋で買う」と、価格引き下げを迫ってきた。そこで、花王は問屋レベルでの価格競争を避けるために、花王と複数の問屋の出資により販社を設立したのである。
販社制度の確立は、商品の価格安定と安定供給を実現し、花王の生販一体化経営を約束することとなった。まず各小売店の販売動向を、販社を通じて正確に把握できるようになり、流通段階の在庫状況がかなり正確につかむことが出来る。また、消費者と花王との間に問屋を経由しないため、消費者ニーズなど鮮度の高い情報を得ることが出来、市場動向を迅速かつ的確に把握することが可能になったのである。
また、自社で物流もまかなう花王は、1970年以降は物流の改革にも取り組でいる。物流拠点を見直し、大型のロジスティクスセンターを建設したり、工場と地域の販社が一体となって、効率的運営を進めることを目的とする供給システム稼働させた。そして、販売、物流、生産の3部門の一体化した管理運営により、更なる効率化を目指し、1994年にロジスティクス総合センターが設立された。情報の一元管理が行われ、販売部門、生産部門からも自由に在庫動向を把握することで、過剰在庫や欠品の防止が出来るようになった。具体的には、販売情報システムが受注データから販売予定を立て、それに基づいて生産情報システムが生産計画を立てる。そして、物流情報システムが工場における出荷日程を自動的に計算し、効率的な物流を行う。各システム間で密なる連携がとれることで、迅速かつ効率的な活動が可能になった。それは高度なロジスティクスシステムにより、売れる商品を売れるだけ生産し、売れるときに販社に送り込むジャスト・イン・タイムの経営をもたらしたのである。
つまり、花王は流通システムすべて、すなわち生産、物流、販売を垂直統合し、すべてを自社でまかなう「自社完結型経営」をすることで家庭用品業界の覇者となったのである。
2.2 自社完結型経営の限界
しかし、生産から物流、販売までをすべて自社でまかない支配することで、家庭用品業界のトップとなった花王だが、その自前主義の経営に転機が訪れている。1998年3月期はも減収となり、17連続の増収増益記録はストップした。
結論から述べると、これまで同社が築いてきた「自社完結型経営」から、「外部資源活用型経営」へと移行してきているのである。
これは同社を取り巻く環境が、急速に変化してきているからにほかならない。
「花王が主力とする家庭用品分野はすでに飽和市場。小売店はそのなかで売上を伸ばすために低価格路線に走る、つまり安くする。それでも売れない。そこでまた安くする。結果、誰も儲からない。」(岩橋昭彦「花王の情報ネットワーク革命」パル出版P97)
メーカも卸も小売りもこのサイクルに否応なく飲み込まれている。この価格下落現象は通称「悪魔のサイクル」と呼ばれている。
そして、もう一つ花王を変革へと走らせたのは、物流システムを有する大手小売りの台頭による、自社物流システムの稼働率の低下である。花王の物流システムは、生産から小売店の店頭までをカバーし、それが価格交渉の大きなアドバンテージとなってきた。しかし、大手チェーンスト等の小売りが自前の物流機構を持つようになり、例えば、セブン?イレブン・ジャパンは、花王に対し各店舗配送から、自社配送センターへの一括納入に切替えさせた。消費の多様化により、小売店の商品の品数が増加し、販売方式が複雑化してきたため、大手チェーンストアでは物流を多品種、少量、多頻度へと変えてきたのである。1994年にセブン?イレブン・ジャパンが、センターは配送を認めさせたのを皮切りに、花王の全物流の2割がチェーンストアへのセンター配送になっている。
センター配送の増加により、大量、少品種、低頻度を目指し構築された物流システムやロジスティクスセンター(LC)の稼働率が低下し遊びが出始めた。これは無駄を嫌い、効率化を図ってきた花王にとって捨て置けないことである。しかしそれ以上に問題なのは、現場での消費者情報が分からなくなってしまうことである。小売店の店頭までを自社のシステムに組み込むことで、鮮度の高い消費者動向、売れ筋や死に筋商品のデータを入手し、商品開発に生かしてきただけに、その痛手は大きい。
こうなると、自社ですべてをまかなおうとして作ってきた、自社完結型経営の閉鎖性が、かえって裏目に出てしまったのである。
2.3 外部資源活用型経営へ
価格下落のスピードに売れ筋商品の開発、発売が追いつかない。自前で築き上げた販売・物流網は効率的だったが、商品が多様化し、様々なルートを使った少量、多品種、多頻度配送に柔軟に配送しなければならないのに、逆に硬直さも目立つ。2.2節で述べてきたように、花王は自社完結型経営の非合理的さを受け、すべてを自社で固めてきた経営の改革を打ち出した。それが外部資源活用型経営である。
その主なものは、物流の再編、業界共同運営VAN(Value Added Network)への参加表明、アウトソーシングの活用、である。
物流の再編とは、これまで蓄積した物流のノウハウとインフラを活用して、他社製品も受託した店舗へ一括配送する、共同配送事業を始めたのである。前述したように、全体の2割がセブンーイレブン・ジャパン等の大手小売りチェーンへのセンター配送へと切り替わっており、そのため稼働率が下がった自社物流システムを有効に活用しようというものである。
業界共同運営VANへの参加というのは、ライバルのライオンや資生堂等の花王以外のメーカが、販社体制に対して設立したVAN「プラネット」への参加を発表したのである。
また、自社完結型経営を支えてきた、受発注や物流等の基幹系システムの運用・保守業務を日本アイ・ビー・エムとアウトソーシング契約した。基幹系システムの根幹である生産システムや、情報システムの企画、開発などの上流工程はアウトソーシングの対象外とし、これまで通り花王が行うとしている。
このように今まで、自前ですべてを築き上げることで効率化を図ってきた花王が、積極的に外部と提携し、外部の力を活用しようとしている。
ただ、自社完結型経営、外部資源活用型経営の両社ともネットワークを最重要視していることに注目してほしい。自社完結型経営では、生産、物流、販売の各部門をネットワークにより結び付け、垂直統合した。そのネットワークの基盤が情報システムである。
そこで次の3章では、生産、物流、販売の垂直統合の基盤となった生販一体型情報システムを見ていく。
次に4章で、外部資源活用型経営のもと、ネットワークを自社内からさらに広げていく花王の姿を見ていく。
3. 生販一体型情報システム
3.1 生販一体型情報システム
生産という川上から、販売という川下までを自社でまかない、効率的に運営するには生産、物流、販売部門の一体化が必要不可欠である。川下は、次に何が、どのくらい流れてくるかという情報をあらかじめ知っていなければならないし、逆に川上は、川下が何を欲しているかを知らなければ、適切な製品を流せない。そして何より、花王の川は生産、物流、販売ととにかく長く、そのうえ全国各地、各部門と支流が広がっている。この長い川を製品という水であふれさせたり、または水を枯れさせないためには、川すべてを一括して管理し、適切に水門を調節しなければならない。すべての部門が、お互いに影響しあっていることに注意しなければならない。そこで、必要となるのが鮮度が高く正確な情報であり、その情報を作り出し活用させる情報システムなのである。
では、どのような段階を経て生販一体化情報システムを構築されたか、大ま大まかな流れを見てみよう(表3_1)。
1963年 販社5ヶ年計画…販社制度の導入。
1970年 流通近代化5ヶ年計画…商取引の計画化、標準化。またコンピュータによる販社の経営管理。
1975年 ロジスティック・システム開発3ヶ年計画…オンライン・サプライシステム、生産数量管理システム、マーケティング戦略デシジョンサポートシステムの開始。
1976年 エコーシステムの導入…消費者の声を開発へフィードバック。
1980年 ロジスティック・インフォメーション・システム…調達・販売・流通ほか、売上・支払いの自動積算までを統合。
1981年 花王マーケティング・インテリジェンス・システム…市場動向をデータベース化しマーケティングに活用。
1986年 POS導入の小売店を中心に販売・流通ネットワークの構築。
1989年 ニューエコーシステム稼動
(表3_1花王の流通改革の流れ)
まず、図2_1でも説明したように、販社制度により価格と供給の安定化をはかり、ロジスティクスの高度化によりジャスト・イン・タイムの物流を可能にした。
それは当初物流系、情報系と個別にシステム化を進めてきたが、それがやがて企業経営全体を見渡した上での全社的なコスト削減運動へと発展した。それがTCR(トータルコストリダクション)運動である。TCRプロジェクトは1986年から、第1次TCR、第2次TCRと順次開始され、1992年から今日へと続く第3次TCRへと受け継がれている。このTCR運動の、よりいっそうの効果を上げるために、生産、物流、販売が組織の枠を超えて一体化した運営を行うことが必要と考えられた。そこで1993年10月「生販一体化プロジェクト」が発足した。
TCRという目的のもと、在庫の削減、欠品解消、物流コスト削減のための生販一体化を支える情報システムを、オルターが提案したWCAフレームワークで示す(図3_1)。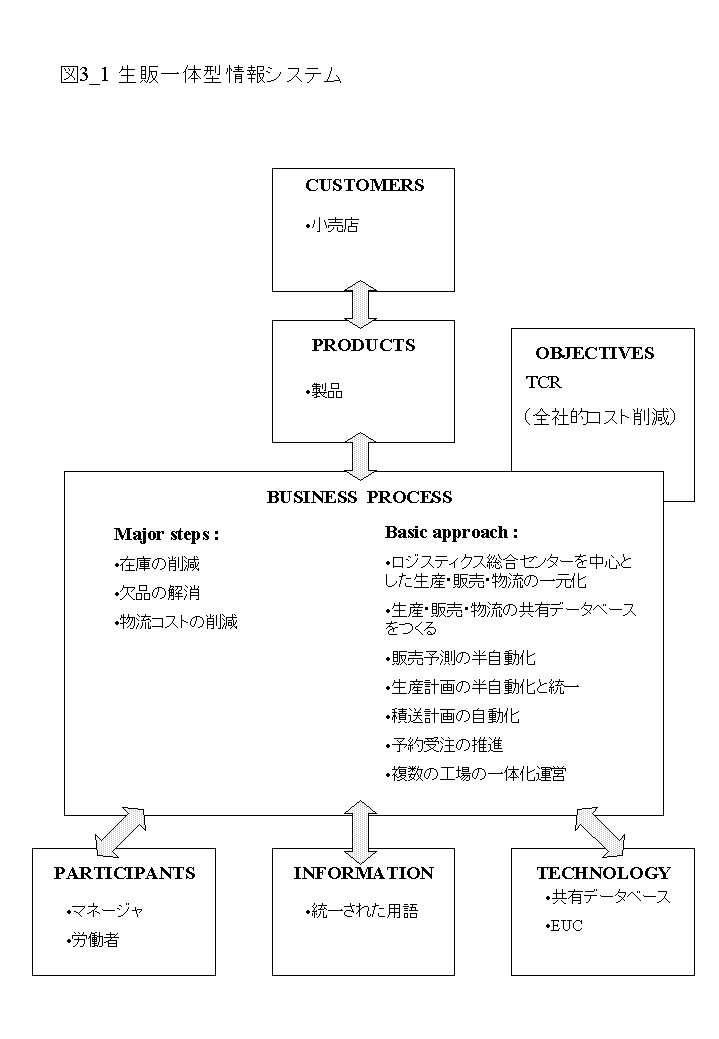
まず、在庫の削減には、組織、販売予測、製品サイクル、販社との取引制度、以上4つの側面が存在する。
組織上の問題とは、まず、全国80個所のロジスティクス・センター(LC)がそれぞれ欠品を起こさぬようにと、それぞれに所属する需給担当者が在庫の確保を競い、結果として在庫があちこちでだぶつくのである。もう1つは、各工場を全社的に管理する組織がないため、各工場が独立して生産計画を立て、工場間での生産や在庫の移動が出来ないという非合理的さであった。そこで、ロジスティクス総合センターを中核とし生産、販売、物流の一元化と、全国の工場や販社、事業部の一体化を進めた。
そして、基礎となる販売予測を半自動化することで、製品の需給を適正にした。それまでの担当者による販売予測は、「販売予測は当たらないのが当然」という認識が生まれるほど予測の精度が低かった。販売予測は、家庭品だけでも600品目以上、そしてそれを、各販社・各LCごとに予測しなければならず、ほとんど不可能に近かったのである。ただし、新しいシステムでも重点管理が必要な新製品などについては、システムで予測はするが、必ず人の手で確認作業することとした。
また、大きな問題として、新旧製品の切替えがあった。改良品の発売直前まで旧製品を供給しなければならず、それに伴う生産ラインの管理が非常に複雑であった。旧製品は売れ残れば滞留品となり、売れすぎれば欠品となる。これが、商品のライフサイクルが短くなっている最近では、ますます大きな問題となっていた。それを、生産の面では生産計画の半自動化、製品の出荷の面では積送計画の自動化により、それぞれの担当の負担を大幅に軽減した。
この他に、情報システムとは別に制度上の問題として、販社との取引制度があった。花王は販社を通じて小売店に商品を流すのだが、会計上、花王本社から販社への売上は、小売店に商品を納入した時点で計上されることになっている。実質的には商品在庫を販社が管理しているにもかかわらず、会計上は花王の資産なのである。在庫負担のない販社は、在庫を確保することで欠品を起こさないようにしようとする。それが在庫の余剰を生み出すという問題点もあった。
次に欠品解消の問題は、LCの必要在庫量が急な大口の取引に対応できない点にある。各LCでは、過去3ヶ月の在庫量の変動から出した販売予定量と、安全在庫を足したものを必要在庫量としている。しかし、LCへの製品の補充が毎日ではないために、キャンペーンや催し物で大口の取引が入ると、1日の必要量が増え、安全在庫でもカバー出来なくなる。そこでストアアドバイザーのSAノートによる予約受注を推進し、生産・供給の円滑化に生かすことを目指した。
物流コストの問題は、輸送ルートや輸送車、コンテナの大きさなど、どれだけ輸送効率を高められるかということであった。輸送車の積載率を高めるために、のちに売れるであろう製品を先送りしておくことがある。これが、輸送の量やダイヤが適正でないと、必要以上の先送りがおこり在庫水準を高めてしまう。前述した積送計画の自動化により、輸送効率を向上させ、かつ先送りを最小限にすることができるようになった。さらに新製品、改良品、品薄品などは、数量が限定され、しかも販売政策がからむので、発売時期と輸送日数などを考慮しつつ限られた数量を適正に配分、輸送しなけらばならない。この複雑な計算も積送計画システムにより労力を半分以上削減できた。
また、倉庫が有効に活用されているかどうかという問題もあった。空いている倉庫があるにもかかわらず、外部に営業倉庫を借りている状況があった。
それを、ロジスティクス総合センターが、各工場を一体化して運営することで、全社的に設備を有効に使い、融通・調節する広域運営を行うことが出来るようになった。
生販一体化を推進するこれら支援システムをつくるには、共有データベースによる情報の一元化・共有化が不可欠である。これは各部門ごとに違い、あいまいになっている用語の統一からはじめられた。例えば「在庫」という言葉も出荷できるもの、輸送中のもの、在庫引き当てされてるものなど、色々な状態を示しており、そのような単語を明確に定義し直した。
そして、出来上がった共有データベース・支援システムに、生産や販売、物流の各部門がアクセスするのはもちろんのこと、業務に携わっているエンドユーザが直接使用できるよう、EUC(エンドユーザ・コンピューティング)環境の整備も進めたのである。
今見てきた生販一体型情報システムは次の4つのサブシステムからなっているとみなすことが出来る。生産情報システム、工場物流(供給情報)システム、販社物流情報システム、家庭品販売情報システムの4つである。これらサブシステムをそれぞれ見ていくこととする。
3.2 生産情報システム
生産情報システムに求められる基本的用件は、市場の動きをタイムリーに反映した生産活動をサポートすることである。しかし、1988年頃までの生産情報システムでは、製品のサイクルの速い市場に対応するには不可能であった。なぜなら、市場に対応するための、全工場レベルでの連携が取れなかったのである。各工場がそれぞれ当時としては最適なシステムを指向した結果、工場ごとに異なったシステムが使われていたからである。システムが異なれば、当然業務の進め方も異なってくる。これでは、全工場レベルで、結合・連携を図って生産活動を行うことが不可能である。
そこで、新たな生産情報システムでは、「一つのシステム、一つの業務スタイル」を目指した。言い換えれば、各工場を密なる結合で、リアルタイムに、効率的に交信することによる「広域一体化運営支援システム」である。
ず、工場の業務を生産系とコーポレート系に分離した。そしてそれぞれを、全社統合、事業部別、分散系に分割した(図3_2_1)。
今まで、それぞれの工場で別々に稼動していたシステムを、数量管理や品質情報など各工場に共通する業務を全社レベルで統合。家庭品生産計画や化学品生産計画、および設備情報、薬事情報は事業部ごとに統合した。会計や人事、会社掲示板などの間接業務も全社レベルで統合することで、ホワイトカラーの生産性も向上した。では、生産情報システムをWCAフレームワークであらわしてみよう(図3_2_2)。
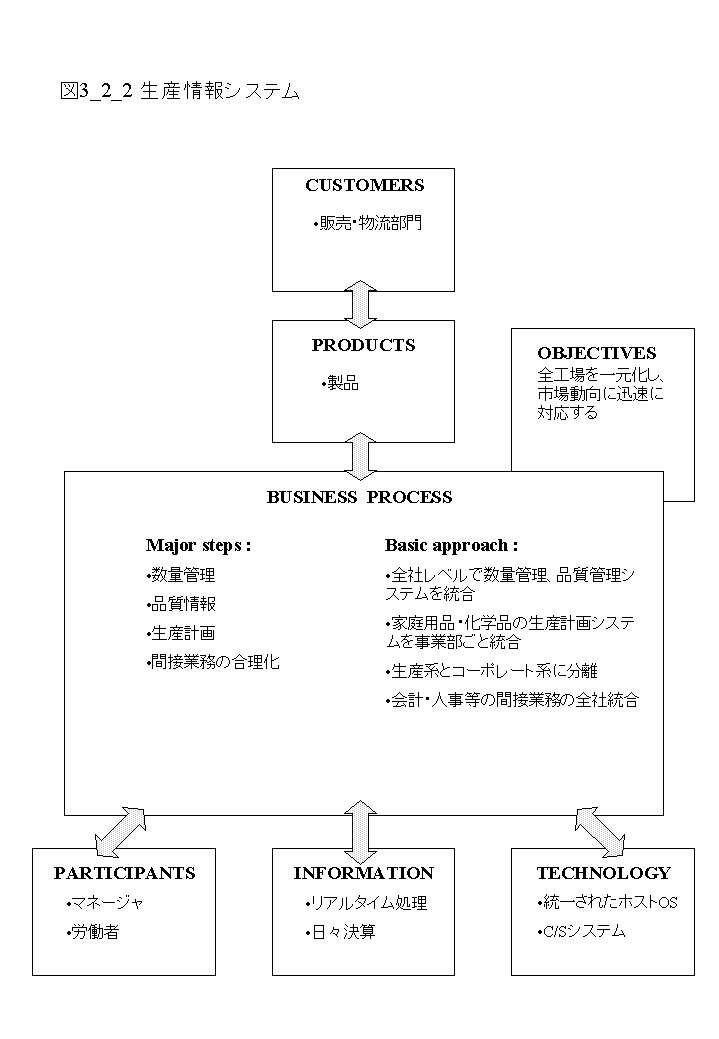
この中で、旧システムから変更された特筆すべき部分は、数量管理のシステムである。製造実績を処理するこの数量管理システムは、従来、データを蓄積して、一日に数回バッチ処理をしていたが、それをリアルタイム処理出来るようにした。これにより鮮度の高い製造実績の情報を見ることでき、生産計画や在庫管理業務の精度を高めることが出来るようになった。また、製造実績の集計処理を月次で管理していたのを、日々管理に切替た。計画見直しや原単位見直しをタイムリーに行うことが可能になったのである。
次にこの生産情報システムのCUSTOMERSの一つでもある物流部門を見てみよう。
3.3 物流情報システム
1960年代後半に販社制度を導入し、家庭品の流通構造を改革し、それを契機に1970年代以降、ロジスティクスの改革に取り組んでいる。ロジスティクスの狙いは、物流の合理化・効率化であり、それは在庫を適正水準に保ち、効率的な配荷、物流コストの削減である。これを花王は情報、物流情報システムを有効に活用することで実現した。
では、花王の物流改革の流れを簡単に追ってみる。
物流改革の当初の目的は、販社制度の流通機構の育成強化と、それによるトータルコストの削減であった。この目的に基づき様々な、改革を行った。
1970年に一貫パレチゼーションと工場自動倉庫を導入した。これは製品を一定のパレットに載せることで、工場自動倉庫からLCへ効率的に輸送するもので、現在も使われている。
1975年には、販社とオンラインで結び、販社の在庫量を把握し、自動的に製品を補充する、オンライン・サプライシステムを開発した。ただし、リアルタイム処理ではなく、一日一回のバッチ処理であった。
1980年からは、量販チェーン店との間で、EOS(電子発注システム)を採用し、受発注のオンライン化を始めた。
1980年代後半からはTCR運動に伴い、大型のLCの建設、物流拠点の統廃合を行った。さらに、1989年から小口取引をまとめて発注する方式や、工場と販社が一体となり効率運営を進める供給システムを稼動させ、工場出荷からLCまでの輸送所用時間を3日から1日へと短縮した。
1993年に、地図データベースを用いた配送スケジュールシステムにより、効率的な配車スケジュール作成の自動化を開始した。
そして、1994年に広域運営を掲げたロジスティクス総合センターが設立され、物流情報の一元化が生販一体化のもと進められている。この物流に関する情報システムは、生産工場から物流拠点のLCまでの工場物流を運営する供給情報システムと、LCから卸・小売店までの販社物流情報システムの2つから構成されいる。
3.3.1 供給情報システム
工場からLCまでの物流の合理化とは、在庫を最小限に保ち、輸送の効率を上げ、品切れを起こさないことである。そのためには、生産、販売部門との連携は不可欠である。そこで、ロジスティクス総合センターが中心となって生産、物流、販売の情報を一元化し、それを活用した。この供給情報システムをWCAフレームワークに基づいて表したものが図3_3_1である。
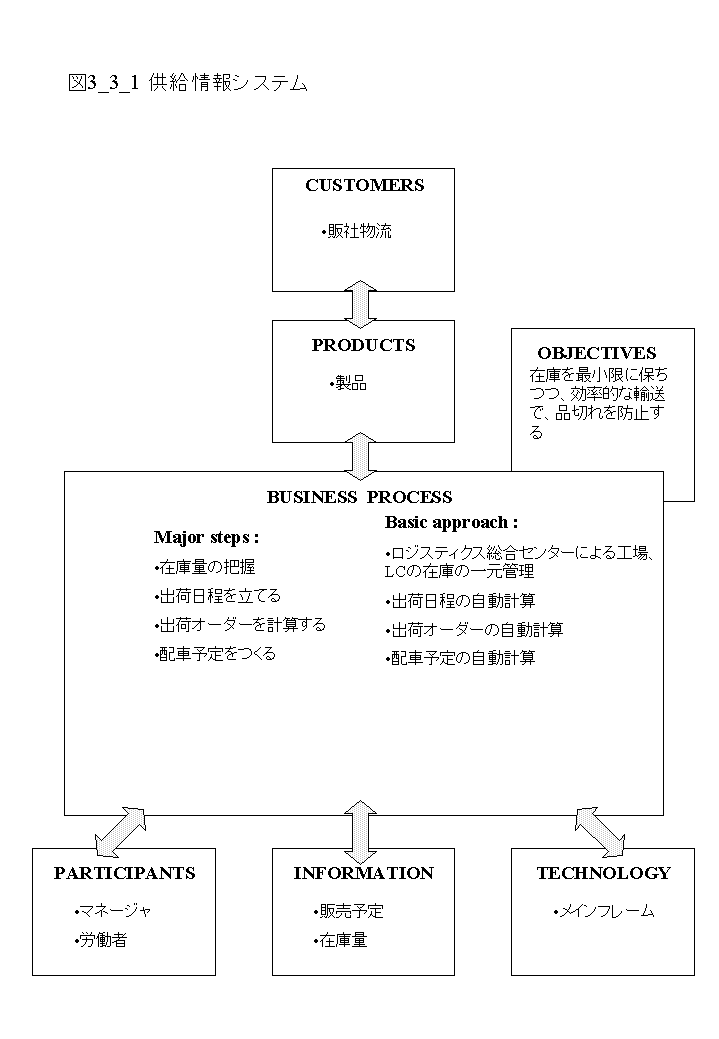
各工場の物流、各LCの在庫動向をロジスティクス総合センターが一貫して管理しているので、過剰在庫や欠品はほぼ完全に避けられるのである。これにより、在庫量の大幅な削減と欠品率の抑制が達成できた。
ただし、この供給システムは、すべての商品には適用されない。売上の75%をしめる主要商品「A管理品」を対象にしている。これは、石鹸や洗剤など日常的にある程度まとまったロットで配送される商品である。新製品や贈答品など、市場の開拓等のマーケティング戦略と関連するものは、商品それぞれの販売戦略にもとづき、個別に出荷スケジュールが立てられる。
「A管理品」は、販売予定をもとに、工場における出荷日程が自動ではじき出される。さらに、在庫状況、受注状況、予約状況に基づいて日々の出荷オーダーが計算され、毎日の出荷予定が修正される。そして、配車予定を立てるのだが、新供給システムによって、受注から出荷までの期間が旧システムの4日間から2日間に短縮された。
生産と在庫の状況がリアルタイムで把握、管理されることで、商品の生産・供給を、主要製品に関しては、ほぼ100%自動供給出来るようになったのである。
3.3.2 販社物流情報システム
物流拠点LCから卸・小売店まで商品を配送するのが販社物流であり、それを支援するのが販社物流情報システムである。このシステムの目的は、配送作業の効率化である(図3_3_2)。
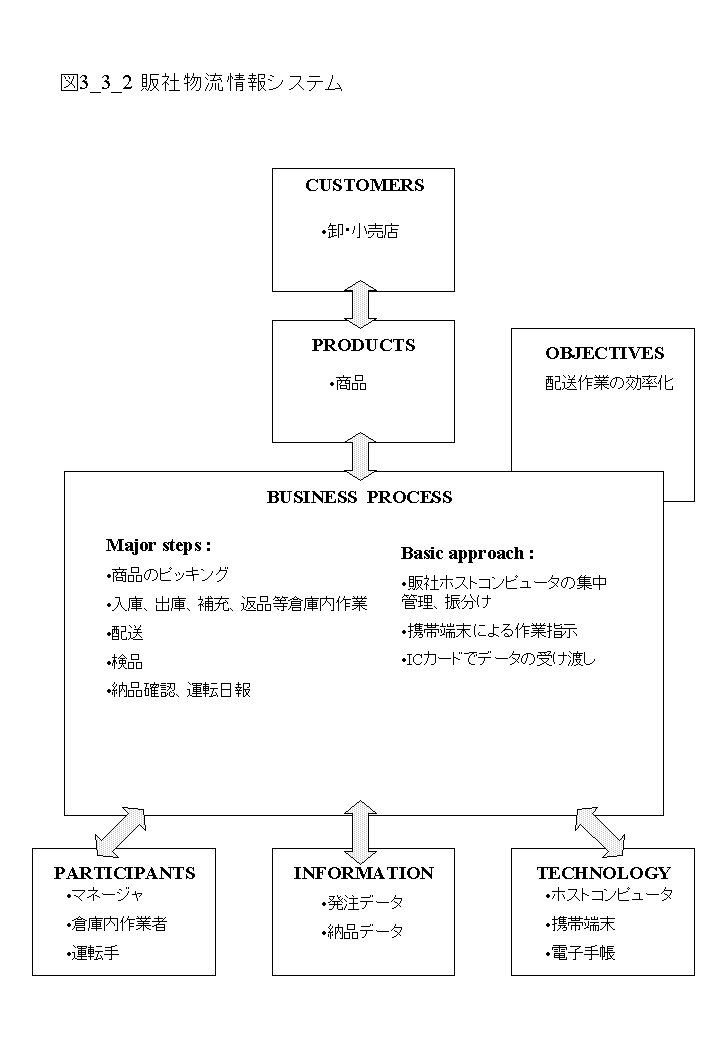
EOSやSAノート(後述)から送信される小売店の発注データは、東西2個所の販社ホストコンピュータに蓄積され、それが全国のLCへ自動的に振り分けられる。そして、出荷指示にもとづき、地域・配送時間別に商品のピっキング作業が行われる。
一方、LC倉庫内での製品の入庫、出庫、補充、返品作業などの日常業務は、携帯用端末を使うことで、標準化した。携帯用端末機が作業手順を表示するので、経験や知識のない作業員でも即刻仕事に取り掛かれるようになった。
そして次の配送作業では、運転手に配送に必要な情報が記憶されたICカードが渡される。ICカードには、配送順路、配送先店舗、商品、数量等の伝票データが書き込まれている。これを電子手帳に挿入し、指示内容を確認しながら配送を行う。
店頭では、運転手は検品作業を行いICカードに記録するのだが、一品ずつ手作業で検品をするので時間と手間がかかる。これを効率化するために、大型チェーン店ではEDI(Electronic
Data Interchange)による「ノー検品化」を進めている。納品前に出荷データを店舗に送信しておくことで、運転手による検品作業を省く。
納品の確認をICカードに入力し、LCでICカードを返却することで、納品確認や運行状況がコンピュータに転送される。運転日報が不要になるのである。ICカードは、配送の効率化だけでなく、運転業務のマネジメント的役割もになっているといえる。
3.4 家庭品販売情報システム
販社制度で流通機構を改革した際、販社にオフコンを導入し、本社と販社を結ぶ情報ネットワークを構築したのが、販売情報システムの始まりである。
この販売情報システムにより各小売店の販売動向、発注データ、そして流通段階の在庫状況が明確に把握できるようになった。商品別に、納入店舗数、納品量などを集計し、その結果、的確な在庫管理と生産供給が行え、さらに消費者動向を反映したマーケティング戦略を展開できるのである。
そして、消費者の価値観やニーズが多様化し、家庭用品の市場競争が激化する中で、消費者の行動に適切かつ敏速対応するため、家庭品販売情報システムの更なる広域化をはかり、情報の一元化をすすめた。これをWCAフレームワークで示す(図3_4)。
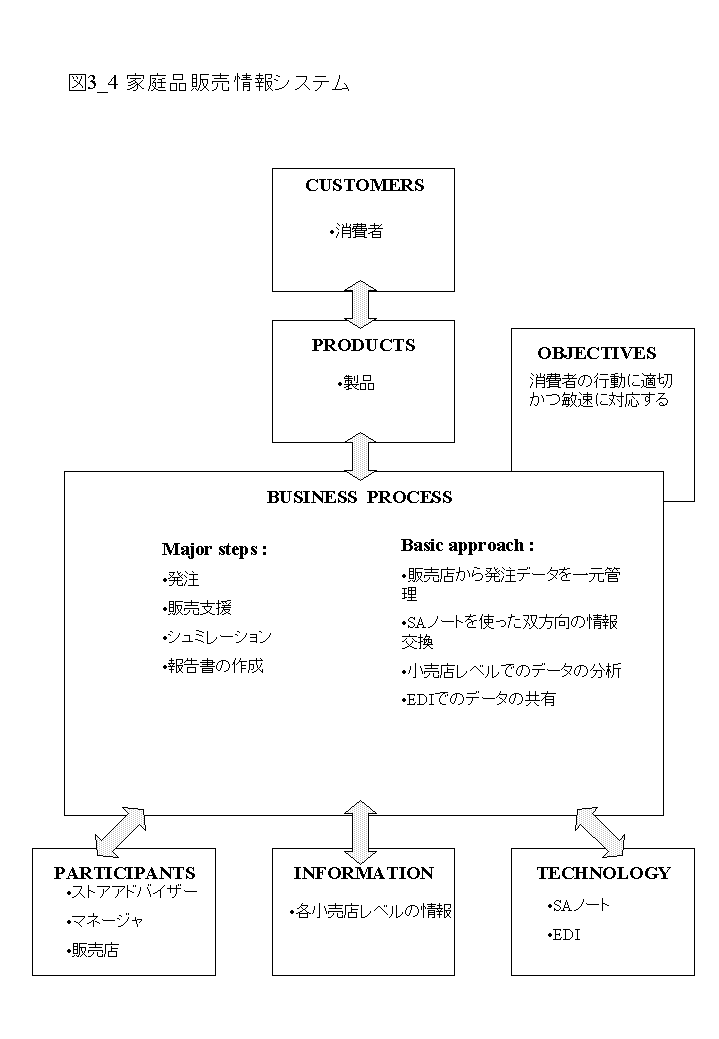
まず、コンピュータ拠点を東西2個所にすることで、データの一元化をはかり、従来の販社別、拠点別運営から切り替えた。
販売活動においては、エリアマーケティングを行ない、変化と多様化の進んだ家庭用品市場を正確に把握・分析出来るようにした。それを支援するのがSAノートと呼ばれるストアアドバイザー(SA)の携帯用パソコンである。
SAは各小売店をまわり、店舗ごとの販売計画を立て、商品を受注し、受注結果を本社に送信する。双方向データ通信機能を備えたSAノートの導入により、受注データの送信だけでなく、販売活動に必要なデータをいつでもホストコンピュータから引き出せる。店舗ごとの過去の販売実績を使い、シュミレーションし、販売計画を立てることがきわめて簡単に出来るのである。また、SAノートによりSAの煩雑な作業、例えば、報告書や資料の作成、営業日報の記入などの時間が飛躍的に減少し、一人が一日でまわれる店舗数が増えたのはもちろん、SA本来の業務である商談に集中することができるようになったのである。
また、SAノートとともに販売革新の一躍を担うのが、大手チェーンとすすめているEDIによる情報の共有である。商品情報の共有により検品や伝票の廃止、請求・支払いをオンラインで行うことが可能になるのだ。
以上が、生産、物流、販売を垂直的に統合する上で、情報システムをどのように活用しているかを見てきた。
4. これからの花王
4.1 物流システムの開放
花王は1996年6月に物流子会社「花王システム物流」を設立した。この「花王システム物流」を通して、他社製品を一括配送することを発表し、イトーヨーカ堂の一部店舗と神奈川県の中堅スーパーで開始している(図4_1)。
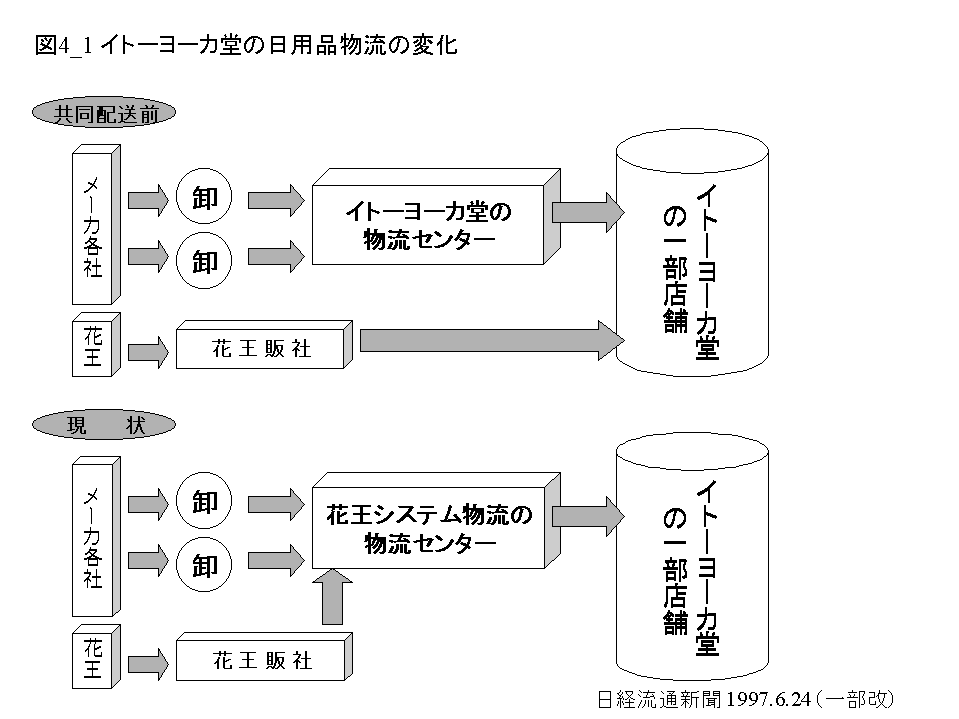
他社製品も花王の物流センターに一度配送させ、そこから花王が各店舗にまとめて配送するというものである。2.2節でも述べたように、セブン?イレブン等の大手チェーンストアへのセンター配送が、物流全体の2割にもなった。これに対し、花王は他社商品も同時に運ぶことで、物流コストを下げ、小売店への付加価値の高いサービスを提供するとしている。
付加価値とは、例えば、シャンプー、洗剤、石鹸などを売り場別に商品を同一の箱に詰め納品し、店頭での商品補充の手間を省力化させるのである。またピッキング精度をさらに向上させて検品作業を不要にすることなどがあげられる。
これが構想できたのも花王の誤配率の低さにある。花王の誤配率の低さは驚異的で、1997年の6月から開始したイトーヨーカ堂への共同配送事業でもそれが決め手となった。それまでイトーヨーカ堂が委託していた物流業者の衣料品の誤配率は0.15%、日用雑貨は0.05%。これも相当な精度であったが、花王の誤配率はそれよりも一桁少ない際だった精度を確保していた。しかも、配送コストも今までの業者よりも低いのである。
小売り側にとっても、悪魔のサイクルという価格下落に対し、店舗作業の合理化、在庫管理の徹底、仕入れコストの削減と取り組んでいるが、中堅スーパー等にとって大幅なコスト削減を図れるのは、物流しか残っていない。
「花王が物流の代行事業をスタートさせたというのは影響力大だといえます。先進的なコンピュータ技術を駆使し、限界に近いまでの効率化、合理化、高速化を実現してきた花王のノウハウが、今様々なビジネスの場面で求められはじめていると言えるのではないでしょうか」(岩橋昭彦「花王の情報ネットワーク革命」ぱる出版P121)
物流の改革をしたいが、自分たちではそれだけの資金も設備もノウハウもない。しかも花王のように巨大な物流センターをもってしまうと、かえって非効率になり、ついてはコストの上昇につながりかねない。
そんな小売店の思惑を、センターへの一括配送の増加により、物流システムの稼働率低下で無駄が出てきた花王が、見事に利用したのである。
そしてこの物流代行事業に対応するため、大型の物流センターを集約し、小型の配送拠点を増やし、より地域に密着した配送体制をしこうとしている。
4.2 プラネットへの参加
物流の開放とともに、花王が打ち出した戦略として、業界共同運営VAN「プラネット」への参加がある。
「プラネット」はVANを介して卸店間と受発注、決済、在庫確認等を処理しており、現在119社が参加している。
花王の参加表明を「プラネット」は当初、拒否しようとしていたが、参加メーカが増えれば増えるほどコストは下がるという理由から、受け入れた。
このVAN「プラネット」は、そもそも販社制度により独自の流通システムをもつ花王に対し、他のメーカが手を組み1985年に設立したものなのである。「プラネット」の株主にはライオン、ユニ・チャーム、資生堂、サンスター、ジョンソン、クレアラシル、エステー化学、牛乳石鹸など花王のライバル企業が名を連ねている。代理店や特約店は「VAN」に接続された端末から発注などの作業を行い、メーカは「VAN」を利用しデータを受け取る。花王販社のネットワークを協同で持っているようなものである。
「プラネット」への参加は、これまで自前主義を掲げ、またそれを強みとして成長してきた花王にとって、180度の方向転換である。また花王に対抗してきた「プラネット」側も、その花王を受け入れるという、業界すべてが変革の時に来ている。
花王は参加の理由を「経営効率化を目指す代行店からの要望が強くあったからだ」と説明している。代行店とは販社の手が届かない遠隔地や小規模小売店に商品を卸している各地の卸店で、この卸店が扱う家庭用品は、花王全体の4分の1にのぼる。こうした代理店は花王だけの製品を扱うのではなく、「プラネット」にも参加し、他メーカの製品の受発注も専用端末を通して行っているので、花王の情報システムの端末と両方をそろえなければならず、そのコストと手間に不満が強まっていた。そこで花王が「プラネット」に参加し、こうした不満を解消するためとしている(図4_2)。
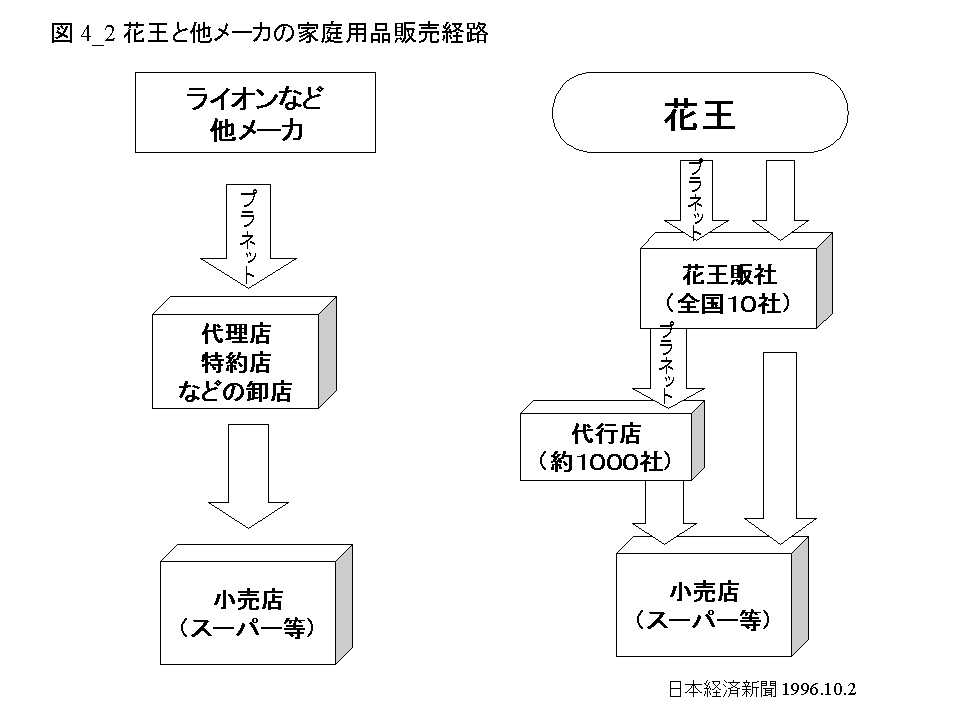
しかし、これは表向きの理由と思われる。その裏には、すべての取引業者が共同でコストを押さえる努力をしなければ、悪魔のサイクルという現在の状況を打破できないという危機感があるのではなかろうか。そして、その打開策こそ、メーカー、卸、小売りすべてを網羅したオンラインシステム、EDIなのであろう。
EDIはメーカと小売りをオンラインで結び、小売り店と販売や在庫などの情報を交換することで、半自動的に商品発注を行うシステムである。EDIでは、小売店のコンピュータから入力された発注のデータが、発注伝票などの紙媒体を使わずに、直接メーカ側に送られ処理される。メーカ側は、実際の納品の前に、その配送車の積荷のデータを小売店に送信しておく。これだけで、多くのコストと手間を省くことが出来るのである。
花王はジャスコ等との間ですでに始めているが、EDIをこれ以上広めようとしたら花王一社の努力では不可能である。しかも、多くのメーカが集まった「プラネット」がEDIを開始し、それがEDIのディファクトスタンダードとなってしまえば、花王は排除されてしまう危険性すらある。
しかし、花王が「プラネット」に参加したということは、業界全体のEDI化に拍車がかかる公算もでてくる。
今まで見てきたように、販社制度のネットワークは花王が他社と差別化し優位に立っているポイントでもあった。だが、EDI化が業界で進んで行けば、他社も効率化された物流を行うための情報システムを持つことが出来、花王の優位性も失われる。
では、これからの花王がさらに成長するために目指しているものは何なのであろうか。自社完結型経営から、外部資源活用型経営へと変わろうとしている花王が目指しているものについて、5章で私なりの考察を述べようと思う。
5.おわりに
自社完結型経営の先に花王が目指しているもの、それはずばりECRではないかと思われる。
ECR(Efficient Consumer Response)とは消費者により高い価値をもたらすことを目的として、小売業や卸売業からメーカまでが緊密に協業することとされている。協業により、各企業の社内効率だけではなく、流通経路全体の効率を上げ、消費者がより高品質な商品を選択できるための環境作りと、オペレーションコストや在庫量の削減を目的としている。
つまり消費者の価値を最大にし、かつ低コストで商品を消費者に届けるとうシステムを作ること。これこそがECRなのである。
消費者の価値を高めるためには、消費者の購入行動をそのままシステム全体に伝わるような仕組みが必要である。そして、それにはメーカから卸店、小売店まですべての業者の垂直な統合だけでなく、水平な統合も求められる。
これこそまさに花王および家庭用品業界が行おうとしていること、そのものではなかろうか。花王が「プラネット」の一員となったことで、業界全体のEDI計画が進み、メーカ、卸、小売りを網羅したオンラインシステムが出来るならば、そのシステムを使ってのECRの実現も現実味を帯びてくる。
「ECRとは顧客に焦点を合わせた対応システムで、そこではすべての取引業者が共同精神のもとに顧客価値を最大にするために、そしてコストを最小にするために力を合わせて仕事をする。製販同盟とか一対一の関係でという覇権主義的な考え方ではなく、すべての取引業者が力を合わせて顧客満足度の向上を図り、コスト削減に努力しようということである。(中略)品質が良いことなど当たり前、安いのも当たり前、顧客の満足できる値頃でなければその商品を買わず、他の商品を買う。(中略)こういった時代にあって顧客の求める価値とは何かを考え、それを効率効果的に提供するのがECRであり、このハードルが超せなければメーカも、卸売業も、小売業も、生き残れない」(東京花王販売副社長
島村光一)
自社完結型経営から、他社提携型経営への転換は、大改革のように映るかもしれない。しかし、自社完結型経営を築き上げた花王の経営と、ECRは重なる部分が非常に多い。
販社制度により消費者のニーズや動向など、鮮度の高い情報をすばやく収集する。コスト削減、欠品解消、流通の効率化、市場動向への迅速な反応をとことん追求するために生産、物流、販売を垂直統合した。これらはまさに、ECRの縮図ではないか。規模は違えどもネットワークを有効に活用する点も同様である。
何より花王の基本理念「“よきモノづくり”を通して顧客の心を打つ満足を」は、ECRの掲げる消費者の価値を最大にすることとまったく同じである。そして、これからも花王は消費者の満足を追求するためには、大改革もいとわないはずである。
参考文献:
「Information systems a management perspective」Steven Alter (The Benjamin/Cummings
Publishing Company, Inc.)
「花王の情報システム革命」平坂敏夫 (ダイヤモンド社)
「花王の情報ネットワーク革命」 岩橋昭彦 (ぱる出版)
「花王の高収益システム」 溝上幸伸 (ぱる出版)
「超卸売業」 島村光一 (日本工業出版)
参考URL:
「花王ホームページ」http://www.kao.co.jp/index-j.html
「花王の流通戦略」http://www.mictokyo.co.jp/mic/cnc/writer2/kaou1.htm
「佐野ゼミ・研究室」
http://www.isc.meiji.ac.jp/~sano/keieikagaku/
「プラネット」 http://www.planet-van.co.jp/
「Iga’s
home page」http://www.kbs.keio.ac.jp/~migarasi/ecr/6syou.html
「Pont」http://home.saison.co.jp/SIS/pont/VOL10/t3.html
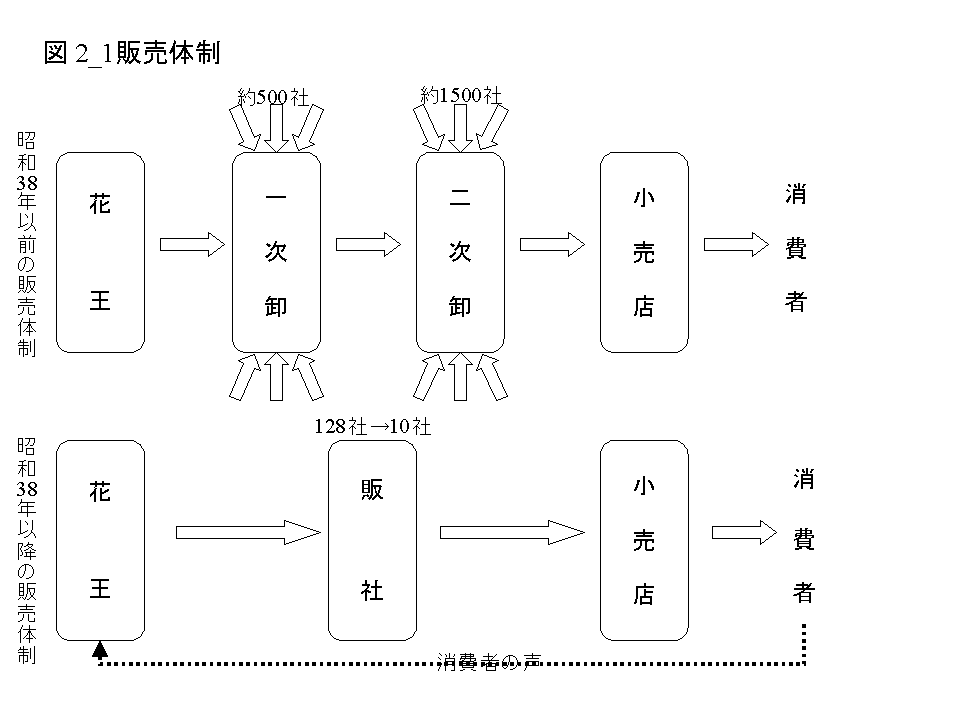 販社制度導入に至った経緯を見てみると、1960年当時、中小スーパーの乱立と乱売競争により、家庭品は価格破壊の状況に陥いっていた。そしてスーパーは問屋に「この価格にしなければ他の問屋で買う」と、価格引き下げを迫ってきた。そこで、花王は問屋レベルでの価格競争を避けるために、花王と複数の問屋の出資により販社を設立したのである。
販社制度導入に至った経緯を見てみると、1960年当時、中小スーパーの乱立と乱売競争により、家庭品は価格破壊の状況に陥いっていた。そしてスーパーは問屋に「この価格にしなければ他の問屋で買う」と、価格引き下げを迫ってきた。そこで、花王は問屋レベルでの価格競争を避けるために、花王と複数の問屋の出資により販社を設立したのである。