
celeron300Aを500MHzで常用する
前編 準備&お手軽クロックアップ

MyPCのCPUはceleron300A(SEPP)です。最近安くなったので衝動買いした物ですが、128kのL2キャッシュを内蔵し、しかもそれがCPUと同クロックで動作するというなかなか嬉しいCPUです。
それまで使っていたceleron266が外部バスクロックの変更のみで112*4=448で動いてくれたので、今回の300Aをクロックアップしたらどのくらい速くなるのか興味が湧いてきました。
さすがにマザーにハンダごてを入れるような改造はえらく疲れる(ぢつは最近、老眼(!)で近くの物や細かいもんが見えにくいのじゃ。。)ので、お手軽レベル1(?)の範囲でオーバークロックすることにします。
んで、まずは目標を500MHzオーバーとして挑戦してみることにしました。
私の購入したものはBOXパッケージで Made in Malaysia 98430978 SL32A
と刻印されていました。
最初にバスクロックだけをBIOS設定で上げて、どこまで正常動作(Win98起動〜ベンチ実行終了)するか試してみます。
現在の設定は
です。結果、
| 100*4.5=450MHz | OK |
| 103*4.5=463.5MHz | OK |
| 112*4.5=504MHz | NG(OS起動せず) |
さすがに500MHzオーバーは無理か。。ハズレではないようですが、当たりでもないというところでしょうか。
ん〜、それにしてもどうしてバスクロック設定が103の次は112なんだろう(って、PLLに文句言ってもしょうがないッスね)
メモリのアクセスタイミングを変えてみてもダメなので、次にVcore(CPUコアに供給する電源電圧)を変更することにしました。これ以外にもメモリやチップセットに供給している3.3V系の電圧Upという方法もあるのですが、まずはCPUにマージンがあるかどうか調べてみたいと思います。
slot1マザーの場合、CPUタイプを自動判別してVcoreを固定するので、2.0V以上に設定する方法の一つとして、いわゆる「マスキング」を行います。方法は雑誌等あちこちで紹介されているので詳しく書きませんが、celeronのカードエッジにある接点のうち特定の番号の接点をテープ等で絶縁することで、マザーに目的のCore電圧を生成させるようにするお手軽な方法です。
マザー上でコア電圧生成ICのVID0〜VID4ラインをカットしてジャンパピンを取り付けるよう改造すると後々の電圧変更が楽になるのですが、頻繁に変更するのでなければ上記マスキング方式がおすすめです。
| core電圧 | R6 | A119 | A120 | A121 | B119 |
| 2.1V | short | mask | mask | mask | mask |
| 2.2V | open | mask | - | mask | mask |
| 2.3V | short | mask | - | mask | mask |
| 2.4V | open | - | mask | mask | mask |
まずVcoreを2.2Vに設定してベース112MHzに設定したところ、やはりOS(Win98)起動時にエラーが発生。そこで奥の手としてベースを103MHzに戻し、Win98起動後にSoftFSBで112MHzに変更したところ、ハングもせずに動いている様子。ちょっと希望が見えたかな・・・?
調子に乗って、ベンチ(Final Reality)を実行しようとしたら、思ったとーり、フリーズしてくれました。
うーん。。MPEGキャプチャもエラーになるし、Super-piもエラーになるし、使いもんにならんなー。
実はウチのPC、スロット(PCI/ISA/AGP)が全てカードで埋まっているという状態で、バスクロックを上げてしまったことでクロックに付いて来られないカードが出てきたのかも・・という不安もありました。
ちなみに、カード類は
です。
次にVcoreを2.3Vに上げてみます。Win起動後、いろいろなアプリやベンチを試してみましたが、どうやらちゃんと動いてるようです。メモリタイミングを最速設定にしても大丈夫でした。ほっ・・・
とりあえずはこれで問題なさそうです。あまり電圧を上げてCPUの発熱と寿命(どのくらい縮むのでしょうか?)を心配するのもナニなので、このくらいで止めておこうと思います。。
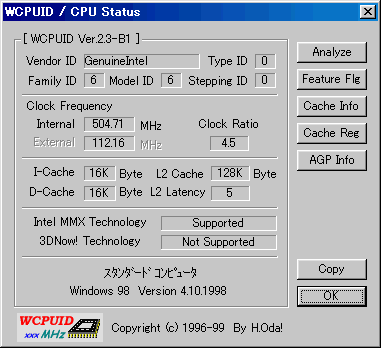
Super-piで円周率104万桁の計算時間を測定したところ、3分41秒と、ついに4分を切るタイムが出ました(^O^)うひうひ。
しかし、504MHzで「常用」するには当然の問題が・・・
現在CPUクーラーはBOX版に付属の純正ヒートシンク&ファンそのままなので、ベンチマークを実行しようものならどんどんCPUが加熱してしまい、心臓に良くありません(CPUに悪い、の間違いだってばさ)。
今は冬で気温も低いのですが、夏場はすぐにイっちゃうことでしょう。次のテーマは冷却!です。
まず、ケースの風通しを良くするために、ケースファンの排出側にあるパンチメタルを鉄ノコとハンドニブラで「うりゃ〜」と切り取っちゃいます。ガジガジ切っちゃいます。

ファンの回転中に誤って指を突っ込むと痛い(ホントに血が出たです>わし)ですが、風量が増え、想像以上にケース内温度が下げられました。しかも風切り音が少なくなるのでとても静かになります。一石二鳥とはまさにこのこと。
CPUの冷却は空冷が簡単なので、なるべく大きなヒートシンクを装着してあげることにします。幸いヒートシンクメーカのアルファ社がいろいろなヒートシンクを扱っています。ここでは1コ単位で通販もしてくれるので助かります。
今回は、P126CM60というヒートシンク、ファン、celeron用バックプレートのセットを入手しました。
 |
 |
えらく高さがあるので、うちのマザー(AX6B)ではメモリスロット4本のうちCPU寄りの2本が犠牲になります。
しかもマザーにある背の高いコンデンサがヒートシンクに当たって装着できない・・・(T_T)
しょうがないのでマザーを改造しない宣言は撤回、ハンダごてで邪魔なコンデンサ2つを取り外し、寝かせた状態で付け直しました。
ヒートシンクとファンをあわせた重量が結構あるので、固定にはceleronが丁度はまるように溝を切ったアクリル棒をPII用のリテンションステーにかませて、ずれが起きないようにしました。

今はこんなんなってます。見難くてすまん。
今回お世話になったツール