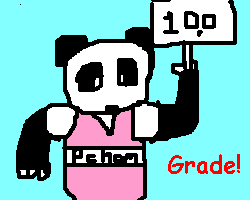
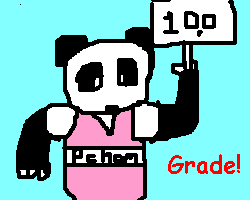
若い時代のチェ・ゲバラを描いた作品――ということだけれど、チェ・ゲバラというのはいい男だねえ。美形だねえ。実際はどうか知らないけれど、こういう映画では美形が主人公を演じるのはとても重要だと思う。
主人公が美形ゆえに、こころが躍る。見ていて本当に楽しい。
南米大陸の広さ。その広さを広いと感じない青春のこころのたくましさというか、無邪気さというか、自分勝手さというか……そういうことがすべて許されるのは、主人公が美形だから。美形でなかったら、向こう見ず、幼稚、単なるわがままな、どうしようもない男に見えてしまうだろう。
これが映画の不思議なところだ。
主人公が美形であるがゆえに、思わずもう一度20代をやり直したい、いや、今からでも知らない世界へ旅に出たいという欲望に突き動かされる。
で、わくわく、にやにやしながら(自分の青春時代にもそういう感情があったなあ、という「にやにや」です)見ていると……。
だんだん変わってくる。
美形の若者にすぎなかった主人公の顔つきも、国境を超え、見知らぬ人に触れ、交流するにしたがって、何かをもっとはっきり見ようとする意志をもった目の、厳しい顔に変わってくる。
(このあたりから、うーむ、美形でないと、思想家になれないかも、革命家になれないかも、なんて思い始める。)
後半のクライマックス――ハンセン病の患者との交流に――ここは、あ、革命家は本当にすごい。自分の思想を確立するとはこういうことか、と美形であるかどうかを忘れてみとれてしまう。
ハンセン病の療養所を去る前日。医療スタッフたちが誕生日のお祝いをしてくれる。そのパーティーではなく、川の向こうの、隔離された患者たちとの一夜を求めて、主人公は夜の川を泳ぐ。
このシーンがどきどきする。はらはらする。
そして、川を泳ぎきり、患者達のもとにたどりついたとき、主人公の世界は一段と輝く。その輝きは、患者達の反対側、つまり、患者を隔離し、差別していた人たちの目には明確にわかる輝きだ。「こっへ帰って来い」と言っていたスタッフ達が思わず拍手する。祝福する。
美形が単なる顔の形ではなく、思想として目の前に直立してくる感じだね。
そして、この瞬間、自分のいるべき場所をはっきり自覚し、そこで生きている人間は誰もが美形なのだと気がつく。
チェ・ゲバラは美形なのではなく、美形になったのだ。
自分のいるべき場所をみつける――それは青春時代にしなければならない人間の仕事なのだろう。
*
ところで、この映画は、チェ・ゲバラの青春時代に、ハンセン病がどのように理解されていたかということも克明に伝えている。
差別は、実際に患者に接する人々の間でも根強く残っていた。患者達は隔離されるだけではなく、隔離されている現場でもう一度理不尽差別、非人間的な扱いを受けていた。患者のせわをする修道女たちが偏見と差別を育てていた。
差別はいつでも、直接的に差別する人がいて生まれる。人と人との直接的な接触の場で生まれ、その外部へと広がっていく。
もちろん、その逆もある。
修道女たちの非人間的な対応の仕方に若いチェ・ゲバラ(とその友人)は反発し、積極的に患者達と接する。修道女たちがつくった規則を破り、直接、患者と触れ合う。
フットボールをし、リズムセッションをこころみる。そのときの患者達のいきいきとした表情。豊かな才能の発露。こうシーンも非常に美しい。差別されないとき、人はすべて輝く。命の輝きを取り戻す。美形になる。
患者達が美形になったがゆえに、チェ・ゲバラは自分のいるべき場所を見つけたのだ。他人を美形にする――他人を幸福にする、それが自分が幸福になる唯一の方法だとわかったのだ。