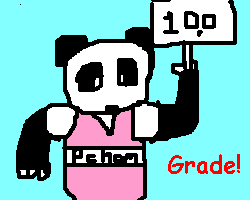
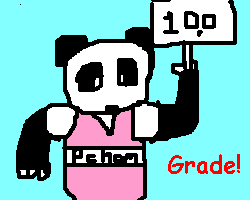
子供のときに芸者の 置屋に売り飛ばされたチャン・ツィイーが、苦労の末、押しも押されもせぬ芸者になる、という話。
アメリカ映画が日本の芸者を描くのだが、いわゆる水揚げによって 特定の男に莫大な金を払わせてはじめて芸者として花柳界に公認されるということ、また、戸籍上の妻にはついにはなれないことなどよく調べている。それらも ふくめて、アメリカ人がこういう娼婦とも呼びにくい女性の職業制度をどう感じ取るか興味のあるところではあるが。
現在のアメリカ映画の多くがそうであるように、アクション映画の ようにカメラがよく動く。そして日本とは思えないような灰色の荒々しい自然。日本の監督ならこうは撮らないだろうな、と思わせる日本家屋や瓦屋根のうすぎ たない雰囲気。そのなかでの、カメラや女優が動き回ることによる、静よりも動が強調される着物や扇の艶やかな色彩。これも日本の監督ならより静的に、環境 と女優がともすれば対立的に見える色彩の面でもより調和的に撮るのだろうなあ、という気がする。私の目から見れば、ちょっと座り心地が悪い気がしないでも ない。別に意識的にではなく、国民性によって自然にそういう撮り方になってしまうのだろうか。
着物の着こなしもチャン・ツィイーやコン・リーやミシェル・ヨー と、日本人の桃井かおり、工藤夕紀とは微妙にちがう。前者には着物独特の圧ぼったさがあるのに対して中国人勢ではスリムな印象があって、ガウンをきっちり 身につけているように見える。芸者独特の鬘がほとんど見られないのは、あれをアメリカ人の美意識が受け付けないからだろうか。ともあれ、アメリカ人が日本 人にあるいは東洋人に対して抱く異国情緒の見栄えに、私は別の角度から「異国情緒」を抱かざるをえなかった。
芸者の世界というより は、女の情念を芸者を借りて描いたということかなあ。 アメリカを舞台にしても女の情念は描けるだろうけれど、日本に設定することで、非日常的に情念を追求できるという利点があると同時に、それではどうしても 絵空事になってしまうという問題点も出てくる。 キモノダンシング(?)だけではなく、三味線とか、小唄とか、そういうものも描いてほしかったなあ。 ということは別にして、役所広司の演技力に関心。 振られる損な役どころなのだけれど、まるで結末を知らないかのように、チャン・ツィイーに胸をときめかせる。 思わず、おいおい、台本をちゃんと読んだのか? 最後は振られる役だと知っているのか、といいたくなるくらい。 主役はやめて脇役に徹するとすごい役者になるだろうなあ。 この映画で一番気になったのは、「日本人」なのに英語を話す……ということではなく、チャン・ツィイーが「怒り肩」で和服が似合わないということ。 和服は「なで肩」じゃないと美しい線が出ない。 まるで夏休みの小学生がお祭りに浴衣を着ていくような感じしかしない。