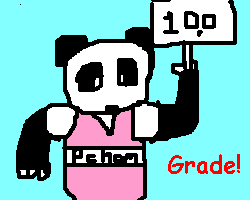
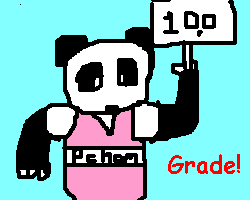
娔撀 僗僥傿乕僽儞丒僗僺儖僶乕僌 庡墘 僩儉丒僴儞僋僗丄僩儉丒僒僀僘儌傾丄僄僪儚乕僪丒僶乕儞僘丄儅僢僩丒僨僀儌儞傎偐
僆儖僙儞(10寧1擔)
fwjf9271@mb.infoweb.ne.jp
偪傚偭偲丄嬃偒傑偟偨丅嬞敆姶偺惁偝偼擣傔傑偡丅惁偄偭偰巚偄傑偡僷儞偪傖傫@傑偩傑偩尵偄偨偄(10寧1擔)
偱傕丄偁傑傝偵擺摼弌棃側偄強偑懡偄傫偱偡丅
偁偲丄僼儖儊僞儖丒僕儍働僢僩偲惁偔偩傇偭偰尒偊偰丒丒丒
朻摢偺夞憐僔乕儞偼丄昁梫側傫偱偟傚偆偐丠偁傟偱丄儔僀傾儞偺柍帠偲僴儞僋僗偺巰偑慜採偵側偭偰偟傑偭偰娤側偔偪傖側傜側偔側傝傑偟偨偟丅側傫偐慡偰偑擺摼偱偒側偄傫偱偡傛偹丒丒丒
摿偵丄傢偑傑傑擇摍暫偺堊偵丄偁傟傎偳柍慄婎抧傪峌寕偡傞偲偒斀懳偟偨暫巑払偑丄嫶傪庣傞偺偵斀懳偟側偄偺偐丒丒丒偁傫側偺儔僀傾儞偺傢偑傑傑偱偟傚偆丒丒丒傛偟傫偽庣傞偲偡傞側傜丄傎傫偲慜偺柍慄婎抧偱偺尵偄崌偄偼側傫偩偭偨偺偭偰偍傕偭偰偟傑偄傑偡偟偹
惁偔晄枮偑巆偭偨塮夋偱偟偨偺偱丒丒丒弶傔偰棃偰惗堄婥偱偡偑婜懸偟偰傒偨偩偗偵偪傚偭偲斶偟偐偭偨傕偺偱昡壙偼仛仛偱偡偹
慜偵彂偄偨乽愴憟曻婞偺寷朄偱堢偭偨擔杮恖偲傾儊儕僇恖偱偼妋偐偵尒曽偑堘偆偐傕偟傟側偄乿偲偄偆揰偵偮偄偰丄偁傞價僕僞乕偐傜斸敾偝傟傑偟偨丅楉撧(10寧1擔)
乽斀摦揑帺崨傟乿偲偄偆斸敾側偺偱偡偑丄偪傚偭偲堄枴偑傢偐傜側偐偭偨丅
巹偑傟偄側偝傫偺巜揈偐傜姶偠偨偺偼丄妋偐偵擔杮恖偺懡偔偼乽愴憟亖埆乿偲偄偆帇揰偱愴憟傪尒偰偟傑偄偑偪偩丅愴憟傪昤偔偺側傜斀愴揑側棫応偑柧妋偵傢偐傞傛偆偵偟側偄偲偄偗側偄丄偲峫偊偑偪偩丄偲偄偆帇揰偼妋偐偵偁傞偲巚偆丄偲偄偆堄枴偱彂偄偨丅
偄傢偽丄巹帺恎偺斀徣傪偙傔偰丄偦偆彂偄偨偺偱偡丅
幚嵺丄巹偼丄偙偺塮夋偐傜乽斀愴偺儊僢僙乕僕乿傪嫮偔姶偠庢傞偙偲偼偱偒側偄丅偱偒側偄偐傜丄斸敾偟偰偄傞偺偩偲巚偆丅偙偆偟偨斸敾偺巇曽偼弮悎側塮夋昡壙偺巔惃偲偼堘偆丄偲尵傢傟傟偽偦偺捠傝偩偲巚偆丅偟偐偟丄巹偼丄偳偆偟偰傕斸敾偟偨偄丅(偟偮偙偄偱偟傚丅)
*
偟偐偟丄巹偵偼偳偆偟偰傕晄壜夝丅
弌偩偟偺30暘偺塮憸偑丄偳偆偟偰傕丄偦傟埲屻偲偮側偑傜側偄丅
巹偑巚偄弌偡偺偼丄偨偲偊偽亀僔儞僪儔乕偺儕僗僩亁偺愒偄儅儞僩偺彮彈偺偙偲丅
僔儞僪儔乕偼丄懡偔偺恖乆偺側偐偐傜愒偄儅儞僩偺彮彈偵栚傪巭傔偨丅偦傟偼丄儌僲僋儘偺塮憸偺拞偱1屄強偩偗愒偄怓傪偟偰偄偨丅偦偺愒偄儅儞僩偑丄僈僗幒偱嶦偝傟偨恖乆偺堖椶偺拞偵崿偠偭偰偄偰丄儕儎僇乕偱塣偽傟偰偄偔偺傪僔儞僪儔乕偼尒傞丅
偦偺弖娫丄僔儞僪儔乕偑壗傪姶偠偨偐嬶懱揑側愢柧偼側偄丅偗傟偳丄偳偒偭偲偟偨偲巚偆丅娤媞偼丄傗偼傝愒偄儅儞僩偑儕儎僇乕偱塣偽傟偰偄偔偺傪尒偰丄偳偒偭偲偡傞丅
偙偺偲偒丄娤媞偺怱偲僔儞僪儔乕偺怱偼廳側傞丅僗僋儕乕儞傪挻偊偰堦偮偵側傞丅
偦偆偟偨弖娫偑亀僾儔僀儀乕僩丒儔僀傾儞亁偵偼姶偠傜傟側偄丅
8恖偑懱尡偟偨僲儖儅儞僨傿乕偺嶴寑偑丄儔僀傾儞傪媬弌偵峴偔夁掱偺偳偙偐偱斀鋶偝傟傟偽丄娤媞偼8恖偲怱傪捠傢偡偙偲偑偱偒偨偲巚偆丅
僲儖儅儞僨傿乕偺嶴寑偺懱尡偑丄娤媞偲庡栶偺8恖偲偺怱傪偮側偖鉐偵側偭偰偄側偄丅
偱丄壗偺偨傔偵丄偁偺嶴寑傪昤偄偨偺偐傢偐傜側偄丅偦傟偑傢偐傜側偄偐傜丄偦傟埲屻偺峴摦偑扨偵乽婾慞乿偵偟偐尒偊偰棃側偄丅
巹偺姶偠傞晄枮偼丄偦偆偄偆偙偲偱偡丅
傑偨丄巹偑乽僾儔僀儀乕僩乿偲屇傫偩偺偼丄偨偲偊偽亀僔儞僪儔乕偺儕僗僩亁偺愒偄儅儞僩偺偙偲丅愒偄儅儞僩傪栚寕偟偨偺偼僔儞僪儔乕偺屄恖揑側懱尡丅(塮憸傪偲偍偟偰丄巹偨偪偼偦傟傪捛懱尡偟偰偄傞丅)偦偺懱尡偑丄儕儎僇乕偱塣偽傟傞愒偄儅儞僩偱孞傝曉偝傟傞偲偒丄僔儞僪儔乕偺怱偑摦偄偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅傢偐傞偐傜姶摦偡傞丅僔儞僪儔乕傪嫋偡婥帩偪偵側傞丅嫟姶偲偼偦偆偄偆傕偺偩偲巚偆丅
偦偆偟偨嫟姶傪屇傇偨傔偺乽僾儔僀儀乕僩乿側懱尡偑亀僾儔僀儀乕僩丒儔僀傾儞亁偱偼昤偐傟偰偄側偄丅嫟姶傪屇傇偨傔偺昤幨偑丄乽僲儖儅儞僨傿乕偺嶴忬乿偲乽媬弌寑乿偺夁掱偵搊応偟側偄丅
弌棃帠偼堦夞偩偗偱偼丄乽帠幚乿偲偟偰嫮偔報徾偵巆傜側偄丅宍傪曄偊偰孞傝曉偝傟偰乽帠幚乿偵側傝丄怱傪摦偐偡丅偁偳偗側偄彮彈偺愒偄儅儞僩偑丄柦偺側偄梞暈偺嶳偵側偭偰孞傝曉偝傟傞偲偒丄偦偙偵柧妋側帪娫偲帠幚偑晜偐傃忋偑傞丅偦傟傪柧妋偵堄幆偡傞晹暘傪丄巹偼乽僾儔僀儀乕僩乿側傕偺偲屇傫偩丅
亀晛捠偠傖側偄亁偺惵擭偑丄嫼敆揹榖偱晛捠偺揹榖偺傛偆側岥挷傪彈偵幎傜傟丄嫼敆忬傪妶帤偱彂偄偰丄僶僇偩偲嵞傃幎傜傟傞丅孞傝曉偡偲偒丄偦偙偵惵擭偺乽埆傪抦傜側偄怱乿傒偨偄側傕偺偑晜偐傃忋偑傞丅斵偺屄惈丄僾儔僀儀乕僩側傕偺偲偟偰偼偭偒傝尒偊偰棃傞丅
偙偆偟偨弖娫偑巹偼岲偒偩丅偦偺弖娫偵丄恖娫惈偑尒偊傞偐傜偩丅
恖娫惈丄偲偄偆偙偲偵娭偟偰尵偊偽丄巹偼偐側傜偢偟傕乽慞椙乿側傕偺偩偗偵傂偐傟傞偺偱偼側偄丅
偨偲偊偽亀僗僂傿乕僩丒僸傾傾僼僞乕亁偺嵟屻偱丄彮彈偑塕傪偮偔丅斵彈偼亀僴乕儊儖儞偺揓悂亁偺暔岅(儀價乕僔僢僞乕偺巇帠傪偟側偑傜孞傝曉偟撉傫偱偄偨暔岅)傪巚偄弌偟丄懌偺埆偄彮擭偲帺暘偺嫬嬾傪廳偹傞傛偆偵偟偰丄塕傪偮偔丅
偦傟偼偁傞堄枴偱偼巆崜偩偟丄偙傢偄弖娫側偺偩偐丄偦偺嫲晐偺弖娫偵巹偼彮彈偑戝岲偒偵側傞丅傎傟偰偟傑偆丅扨側傞乽栶乿偩偭偨彮彈偑丄僗僋儕乕儞傪挻偊偰丄恖娫偲偟偰偁傜傢傟偰偔傞偐傜偩丅
塮夋偺拞偱昤偐傟偨偁傞屄恖偺懱尡偑斀暅偟丄宍傪偐偊傞弖娫丄偦偙偵偦偺恖偩偗偺乽楌巎乿偲偄偆傋偒僾儔僀儀乕僩側姶忣偑惗傑傟傞丅偦偺弖娫傪昤偄偨嶌昳偑巹偼岲偒偩丅
亀僾儔僀儀乕僩丒儔僀傾儞亁偱偼乽僲儖儅儞僨傿乕偺嶴寑乿偑丄8恖偺側偐偱孞傝曉偝傟側偄丅
偙傟偼丄偲偰偮傕側偔婏柇側偙偲偩丅
*
傟偄側偝傫偑乽擟柋乿偲尵偆尵梩偱昞尰偟偰偄傞偙偲偼丄傛偔傢偐傝傑偡丅(偙偺巹偺彂偒崬傒偺壓偵丄傟偄側偝傫偺暥復偑偁傝傑偡)
8恖偺媬弌寑偼丄慜敿偺30暘偲娭學側偄傕偺偲偟偰尒傟偽丄偡傋偰擺摼偑偄偔偺偱偡偑丄慜敿偺30暘偲偺娭學偑巹偵偼傢偐傜側偄丅
戞擇師戝愴偑夁崜側傕偺偱偁偭偨偲偄偆偙偲傪昞尰偡傞偺偑栚揑側傜丄偦傟偼媬弌寑偺夁掱偱昞尰偡傟偽廫暘側婥偑偡傞丅
偁傟偩偗偺儕傾儖側塮憸偱昞尰偡傞偺側傜丄偦偙偱昞尰偟偨傕偺偑丄偳傫側傆偆偵8恖偵塭嬁偟偨偐傪昤偐側偄偲丄偦傟偼扨側傞乽奊乿偵側偭偰偟傑偆丅斵傜偺乽懱尡乿偵側傜側偄丅僾儔僀儀乕僩側帪娫偵側傜側偄丅偩偐傜丄娤媞偵偼丄偦偺嶴寑偺堄枴偑揱傢傜側偄丄巹偼偦偆巚偆丅彮側偔偲傕丄巹偵偼揱傢傜側偐偭偨丅尒偰偄偨30暘偼妋偐偵嬃湵偟偨偑丄媬弌寑偑恑傓偵偟偨偑偭偰丄嵟弶偵尒偨30暘偺塮憸偑乽奊乿偲偟偰偟偐巚偄弌偣側偔側偭偨丅
巹偺姶惈偵栤戣偑偁傞偺偐傕偟傟側偄偑丄巹偼巹帺恎偵栤戣偑偁傞偲偄偆偙偲傪擺摼偱偒側偄偺偱丄偙傟偼僗僺儖僶乕僌偺昤偒曽偵栤戣偑偁傞偺偩丄偲巚偭偰偟傑偆丅
*
暥嬪傪偮偗偰偍偄偰丄偙傫側偙偲傪彂偔偲曄偵姶偠傞偐傕偟傟側偄偑丄巹偼亀僾儔僀儀乕僩丒儔僀傾儞亁偼偡偛偄塮夋偩偲巚偆丅偡偛偄偐傜暥嬪傪尵偄偨偄丅
乽傕偟偁偺偡傋偰傪尒偰丄偦傟偱傕側偍偐偮丄忋晹偺柦椷偩偐傜1恖偺暫巑傪媬 弌偡傞偲偄偆擟柋偵柦傪偐偗傞丄偲偄偆偺偼丄巹偵偼傢偐傜側偄丅乿偲僷儞偪傖 傫偼彂偄偰傑偟偨偑丄僄僪儚乕僪丒僶乕儞僘偼堦搙婣傠偆偲偟偰傑偟偨偹丅忋晹 偺柦椷偩偐傜擟柋偵柦傪偐偗傞棟桼偑傢偐傜側偄偺偑擔杮恖偩偐傜偩偲巹偼巚偆 偺偱偡丅慡偰傪尒偰偒偨偐傜偙偦丄崱偝傜摝偘弌偣側偄偱偟傚偆丅戞堦丄擟柋偵 柦傪偐偗側偄偭偰丄偳偆偡傟偽偄偄傫偱偡偐丠偁偺応偱僩儉偲奆偑偠傖乣偙偺傑 傑僼儔儞僗偺揷幧偵巆傞偐丠偭偰尵偭偰塀傟傞偺偱偟傚偆偐丠孯柋偐傜摝偘偨傜 偦傟偼戝嵾偱偡丅偦傟偵丄僩儉側傫偐偼偙偺擟柋傪廔偊傟偽崙傊婣傟傞両壠懓偵 夛偊傞両偲偦傟偩偗傪峫偊偰偄偨傛偆偱偟偨偹丅懠偺擟柋乮廵寕愴摍乯偵偮偐偝 傟偨傜丄戝夦変傪偡傞偐丄愴憟偑廔傢傞傑偱崙傊偼婣傟傑偣傫丅偱傕丄儔僀傾儞 傪尒偮偗傟偽崙傊婣傟傞両偳偆偣柦傪偐偗傞側傜偦偭偪傪慖傇偺偱偼側偄偱偟傚 偆偐丠偳偪傜偵偟傠慖戰偺梋抧偼梌偊傜傟側偄偺偑孯偱偡偗偳丅偁傗(9寧30擔)
傗偼傝丄偙偺塮夋偵偟傠懠偺戞俀師悽奅戝愴傕偺偵偟傠擔杮偱偼岞奐偡傞傋偒偱 偼側偄偐傕偟傟傑偣傫偹丅僪僀僣偱偼庴偗擖傟傜傟偰偄傞傛偆偱偡偗傟偳丄偦傟 偼傗偼傝僫僠僗乛僸僢僩儔乕偑愴憟愑擟幰偩偭偨偐傜偱偟傚偆偐丠擔杮偱偼乽孯 崙庡媊乿偑埆偐偭偨偲偄傢傟丄偦偺庡媊帺懱亖乽僫僠僗乿偺傛偆偵側偭偰偟傑偭 偰偄傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丠乽僫僠僗乿偺傛偆偵侾偮偺僌儖乕僾偱偁偭偨応崌 偦偺僌儖乕僾傪寵偄偵側傞偙偲偼娙扨偱偡偑乽孯崙庡媊乿傪埆幰偵偡傞偙偲偱 乽孯乿亖乽埆乿偵側偭偰偟傑偭偰偄傞傛偆側姶偠傪庴偗傑偡丅妋偐偵乽孯乿偑峌 寕懱惂偵偁傞応崌丄偦傟偼乽埆乿偲側傞偲巚偄傑偡丅偟偐偟乽孯乿傪崙杊偺偨傔 偺慻怐偲巚偊偽堦奣偵埆偄偲偼尵偊傑偣傫丅偦傫側偺棟孅偩偲尵傢傟偰偟傑偆偐 傕偟傟傑偣傫偑丄偦傟偑廬棃偺傾儊儕僇偺峫偊偱偼側偄偱偟傚偆偐丠
偦偆偦偆丄儐僟儎恖偺暫巑偑僪僀僣孯偺曔椄払偺峴恑傪尒偨帪丄帺暘傪巜偟偰 "Jew, Jew"偲尵偭偰偄偨偺偑偲偰傕報徾揑偱偟偨丅
偳偆傕側傫偐丄暥帤偽偗偟偰偟傑偭偨傒偨偄偱丄儊僀儚僋偐偗偰 偡偄傑偣傫両戝娭 惓榓(仛仛)(9寧30擔)
偦傟偑丄彂偒捈偦偆偲偟偨傫偱偡偑丄偍傕偄偩偣側偄偱偡丄丄丄丅乮偆偆乣乯
懡暘丄乽僩儉丒僴儞僋僗偑尰嵼偺帺暘偵嬯偟傓傓巔傛傝乿傒偨偄側偙偲傪 彂偄偰偨傛偆側婥偑偟傑偡丅乮偱傕丄側傫偐堘偆側偁乯
偲偙傠偱丄傁傫偪傖傫偼 Mr.Showbiz 偺儁乕僕尒傑偟偨偐丠
乮偨傇傫丄僠僃僢僋偝傟偰傞偲巚偆傫偱偡偑丄丄乯
偁傟偱偼丄Saving Private Ryan 偑98揰偵側偭偰偨傫偱偡偑丄乮妋偐乯
屄恖揑偵偼偦傟偵偼戝偒側媈栤傪妎偊傑偟偨丅
巹偺係偮傏偟偼 Deep Impact 傛傝忋 偲偄偆堄枴偺係偮側傫偱偡偑丄丄丅
僾儔僀儀乕僩丒儔僀傾儞偺榖戣偱惙傝忋偑偭偰偄傞傛偆偱偡偹丅奆偝傫恀寱偵尒 傜傟偰偄傞傛偆偱丄妋偐偵偦傟偩偗偺壙抣偑偁傞嶌昳側偺偱偟傚偆丅巹偼乮偙偪 傜偺乯岞奐弶擔偵尒偨偺偱偡偑丄側傫偲偄偆偐堘榓姶偲偄偆偐丄媈栤偽偐傝偑巆 傝傑偟偨丅偦傟偲摨帪偵丄峏偵撍偭崬傫偱偙偺塮夋偺帠傪峫偊傞婥偵偝偣偰偔傟 側偐偭偨偺偼側偤偱偟傚偆偹丅偦偺棟桼偼偲峫偊偰傒傑偟傚偆偐丅僷儞偪傖傫(9寧30擔)(傑偨彂偄偰偄傞)
乮侾乯僪儕乕儉儚乕僋僗僽儔儞僪偵懳偡傞傾儗儖僊乕徢忬丄嫅斲徢忬丅傾儈僗僞 僢僩偱傕偦偆偩偭偨偗偳丄岅傝岥偑妸傜偐偡偓傞傫偱偡傛丅嶌傝庤懁偺偙偩傢傝 偺傛偆側傕偺偑嶍偓棊偲偝傟偰傑偡丅偦傟偼丄墲乆偵偟偰屄恖偺曃尒偲偐丄惗偄 棫偪偲偐丄晄婍梡偝偲偐偑斀塮偝傟傞傕偺偩傠偆偗偳丄偦傟傪攔偡傞偙偲偱丄媝 偭偰摢偱偭偐偪側棟孅塮夋偵側偭偰偄偨偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅
乮俀乯嵟弶偺俁侽暘偼塮夋帄忋偵巆傞椡嶌偱偁傞偙偲偼巹傕摨姶偱偡丅偟偐偟丄 杮曇偺傎偆偼梊憐弌棃偨愝掕偩偟丄暔岅偲偟偰栚怴偟偄揥奐傕偁傝傑偣傫丅傑偨 丄儅僢僩丒僨乕儌儞墘偠傞庡恖岞偺昤偒曽偑栦愗偱丄斵偑搊応偟偰偐傜堦曊偵嫽 枴傪幐偭偰偟傑偄傑偟偨丅乽偙傫側搝偺堊偵柦傪棊偲偡側傫偰偽偐偘偰偄傞乿偭 偰側偭偨偲偨傫偵偹乮偦偆巚傢偣傞偺傕娔撀偺堄恾偩偭偨偺偱偟傚偆偐丠乯丅斵 帺恎偼婜懸偝傟偨捠傝偺栶傪偦偺傑傑墘偠偰傑偟偨偑丄偦傟偩偗偲偄偆姶偠丅夁 嫀俁嶌乮乽愴壩偺桬婥乿乽儗乕儞儊乕僇乕乿乽僌僢僪丒僂傿儖丒僴儞僥傿儞僌乿 乯偑偳傟傕怴慛偩偭偨偩偗偵惿偟傑傟傑偡偑丄偙傟偼斵傪巊偄偒傟側偐偭偨惢嶌 懁偑埆偄偐側丅偪側傒偵丄Rounders偲偄偆斵庡墘偺怴嶌傕尒偰傑偡偑丄偙傟傕斵 偑偙傟傑偱僗僋儕乕儞偱尒偣偰偒偨僉儍儔僋僞乕傪偦偺傑傑帩偭偰偒偰嶌偭偨塮 夋丅巹偑朞偒偰偒偨偺偱偟傚偆偐丠丅偲偄偆傛傝傕丄斵偺嵟戝偺攧傝偱偁傞丄庒 幰屌桳偺乽惵偝乿偲偄偆傕偺偑丄幚偼偦偺傑傑偱偼戝曄栰曢偭偨偄傕偺偩偲偄偆 偙偲傪抦偭偨忋偱丄偦傟傪忔傝墇偊傞椡丒婓朷偑忋弎偺俁嶌偵偼姶偠傜傟丄Ryan 傗Rounders偵偼寚偗偰偨偺偱偼偲巚偄傑偡丅堄奜偲巊偄偵偔偄攐桪偺傛偆偵巚偄 傑偡丅
乮俁乯
扟撪>楉撧偝傫偑彂偄偰偄傞傛偆偵丄妋偐偵丄偙偺塮夋偼乽愴憟曻婞乿偺寷朄偱
扟撪>偭偨擔杮恖偲傾儊儕僇恖偱偼丄尒曽偑堎側傞偲巚偆丅
巹傕偦偆憐憸偟傑偡偑丄傾儊儕僇恖偱傕丄尒傞悽戙偵傛偭偰傕堘偆傜偟偔丄幚嵺 愴抧偵晪偄偨曽偲偦偺榖傪暦偄偰堢偭偨悽戙偱姶憐偑堘偄傑偡偹乮偙傟偼擔杮偱 傕摨偠偱偡偹乯丅巹偑堄尒傪暦偄偨曽偼俆侽嵨偔傜偄偱偟偨偑丄塮夋偵偼斸敾揑 側棫応傪庢偭偰傑偟偨丅
摍乆丄塮夋偺庡戣偲偼娭學側偄偙偲偽偐傝彂偄偰偟傑偭偰偡傒傑偣傫丅偱傕丄巹 偼偙偺塮夋偐傜愴憟傪峫偊傛偆偲偄偆婥偵偼側傟傑偣傫偱偟偨丅僗僩乕儕乕偺抐 曅傪挌擩偵廍偭偰偄偗偽丄偦偙偐傜壗偐傪峫偊傞偒偭偐偗偵偼側傞偺偩傠偆偗偳 丄偦偺抐曅偑宷偑偭偰偄偐側偄丅慡懱偑尒偊側偄丅僗僺儖僶乕僌偺偙偩傢傝傊偲 岦偐偭偰偄偐側偄丅
傟偄側>偙偺塮夋偺尵偄偨偄偲偡傞偲偙傠偼愴偭偰偔傟偨暫巑偼奆晛捠偺恖娫
傟偄側>偩偭偨偲偄偆偙偲偱偼側偄偱偟傚偆偐丠
偲彂偐傟傞偺傕堦偮偺尒曽偲巚偄傑偡偑丄偦偆偄偆嫵孭偲偐儊僢僙乕僕傪庴偗庢 偭偰丄帺暘偺拞偵庢傝崬傓偙偲偵偼偳偆偟偰傕嫅斲斀墳傪帵偟偰偟傑偆偺偱偡丅 側偤偩偐傛偔傢偐傜側偄偺偩偗偳丄傕偟偐偟偨傜乽枹抦偲偺憳嬾乿偲乽僔儞僪儔 偺儕僗僩乿偱巹偺拞偵攟傢傟偨僗僺儖僶乕僌娔撀偵懳偡傞怣棅搙偑嬤擭偳傫偳傫 掅壓偟偰偄傞偐傜偐傕抦傟傑偣傫丅
偙偺塮夋偵偮偄偰偼丄側偤偩偐丄彂偄偰傕彂偄偰傕彂偒偒傟側偄暔傪姶偠傞丅愇嫶丂彯暯(仛仛仛仛)(9寧29擔)
巹偑姶偠偰偄傞晄枮傪丄傕偆堦搙丅
偙偺塮夋偺儊乕儞僗僩儕乕偼丄儔僀傾儞偲偄偆擇摍暫傪扵偟弌偟媬弌偡傞偙偲偵偁傞丅
偦偺擟柋偵僩儉丒僴儞僋僗埲壓8恖偺暫巑偑偁偨傞丅偙偺8恖(僼儔儞僗岅丄僪僀僣岅偺偱偒傞1恖偼暿偩偑)偼丄慡堳僲儖儅儞僨傿乕忋棨偺嵺偺惁嶴側愴応傪懱尡偟偰偄傞丅娤媞偺偳偓傕傪偸偔丄惁愨側愴応傪懱尡偟偰偄傞偼偢偱偁傞丅
偟偐偟丄偦偺懱尡偑丄媬弌寑(媬弌傊岦偐偆夁掱)偱晜偐傃忋偑偭偰棃側偄丅
偙傟偼戝曄婏柇偩丅偁傟偩偗偺嶴忬傪栚寕偟丄懱尡偟偨偺偵丄偦偺懱尡偑嬶懱揑偵峴摦偵斀塮偝傟側偄偲偄偆偺偼丄晄帺慠偡偓傞丅
慜夞傕彂偄偨偑丄亀晛捠偠傖側偄亁偺惵擭偼丄桿夳斊偺嫼敆揹榖偺偐偗曽傪嫵偊傜傟丄幚嵺偵偦偺偐偗曽傪儅僗僞乕偟偨偁偲丄妶帤傪愗傝敳偄偰嫼敆忬傪彂偔偲偄偆傛偆側偙偲傪偡傞丅偦偙偵偼丄乽懱尡乿偑斀塮偝傟偰偄傞丅偦偟偰丄乽懱尡乿傪斀塮偟側偑傜傕丄斵偵偼偐傢傜側偄偲偙傠偑偁偭偨丅憡庤偑抝偑扤偱偁傞偐抦偭偰偄傞偺偩偐傜妶帤偺嫼敆忬偵堄枴偼側偄丅偦傟側偺偵妶帤偱嫼敆忬傪彂偔丅乽偲傫傑乿側偺偩丅偦偺乽偲傫傑乿偝偑丄斵偺恖娫惈傪晜偒挙傝偵偡傞丅慞椙惈傪晜偒挙傝偵偡傞丅偦偺慞椙惈備偊偵丄彈偼抝傪垽偡傞傛偆偵側偭偰峴偔丅(偦傟偑庤偵庢傞傛偆偵暘偐傞丄擺摼偱偒傞丅)
恖娫偺峴摦偲偼偦偆偄偆傕偺偩偲巚偆丅
懱尡偑偦偺恖娫傪曄偊丄摨帪偵懱尡偵傛偭偰傕曄傢傜側偄晹暘偑懚嵼偡傞丅偦偺崿嵼偺巇曽偑恖娫偺杮幙傪柧傜偐偵偡傞丅
亀僾儔僀儀乕僩丒儔僀傾儞亁偵偼丄偦偆偟偨晹暘偑側偄丅
傋偮偺尵偄曽傪偡傟偽乧乧亀晛捠偠傖側偄亁傪尒偰偄傞偲丄偩傫偩傫乽偲傫傑乿側桿夳斊偑岲偒偵側偭偰棃傞丅偙偺抝丄偄偄抝偩側偁丄偲巚偭偰棃傞丅偲偙傠偑亀僾儔僀儀乕僩丒儔僀傾儞亁偱偼丄僩儉丒僴儞僋僗偼偄偄抝偩側偁丄偄偄恖娫偩側偁丄偲偄偆姶憐偑惗傑傟偰棃側偄丅
偙傟偼偮傑傜側偄丅
僗僺儖僶乕僌偺塮夋偵偼丄偍偆偍偆偵偟偰偙偆偟偨恖娫偑弌偰偔傞丅偄偄恖娫側偺偐傕偟傟側偄偑丄偦傟偼嵟弶偐傜嵟屻傑偱偄偄恖娫偺傑傑偱偁傝丄僗僩乕儕乕偺拞偱丄偼偭偲婥偯偔傛偆側恖娫偺枴偑側偄丅
(桞堦丄亀枹抦偲偺憳嬾亁偺儕僠儍乕僪丒僪儗僀僼傽僗偑丄曄壔偟側偑傜恖娫偺枺椡傪尒偣偨乽栶乿偩偲巚偆丅)
巹偼丄婎杮揑偵丄偙偺栶幰偑岲偒丄偲巚偊傞傛偆偵昤偗偰偄側偄塮夋偵偼働僠傪偮偗偨偄丅働僠傪偮偗傞暼偑偁傞丅
恖娫偑恖娫偲弌夛偄丄岎棳偡傞偺偼丄憡庤傪岲偒偵側傝偨偄偐傜偩丅
偩偐傜乧乧偲偆偄偆偺偼偨傇傫榑棟偺旘桇偐傕偟傟側偄偑丄巹偼丄亀僞僀僞僯僢僋亁儕僺乕僞乕偺偍偽偝傫偑岲偒丅
塮夋偺拞偺乽栶乿偼僨傿僇僾儕僆偱偼側偄丅偱傕丄僨傿僇僾儕僆偦偺傕偺偲嶖妎偟丄偆偭偲傝偡傞偍偽偝傫偑岲偒偩丅
儈乕僴乕偲偄偆偲斲掕揑側嬁偒偑偁傞偗傟偳丄巹偼儈乕僴乕偑岲偒丅
栶幰偼偁傞帪偼慞恖傪傗傝丄偁傞偲偒偼埆恖傪傗傞丅偦偺栶偑慞恖偱偁傟丄埆恖偱偁傟丄偦傟偼栶幰杮恖偱偼側偄偗傟偳丄栶幰杮恖偲巚偄崬傒丄偁傫側偄偄抝(彈)側傜丄偩傑偝傟偰傕偄偄丄棤愗傜傟偰傕偄偄丄偲巚偄側偑傜丄尒偰偄傞娤媞偑岲偒丅
斵彈偨偪偼丄偳偙偐偱乽恖娫乿偦偺傕偺傪尒偰偄傞丅偦偺乽恖娫乿傪尒敳偔椡偑岲偒丄偲尵偊偽偄偄偐側偁丅
偱丄亀僾儔僀儀乕僩丒儔僀傾儞亁偵栠偭偰偄偆偲丄偙偺塮夋傪尒偰丄僩儉丒僴儞僋僗偼偄偄恖娫偩側偁丄偲巚偆娤媞偑偄傞偩傠偆偐丅
愴応偵庢傝巆偝傟偨偲偒偼丄僩儉丒僴儞僋僗偵彆偗偵棃偰傕傜偄偨偄側偁丄偲巚偆恖娫偑偄傞偐偳偆偐丄媈栤丅
偦傫側慺杙側怣棅姶傪堷偒弌偡傛偆側恖娫昤幨傪丄僗僺儖僶乕僌偼偱偒側偄丅
偦偙偵斵偺堦斣偺栤戣揰偑偁傞偲巚偆丅
偙偺嶌昳偺嵟戝偺斶寑偼丄幚偼僗僺儖僶乕僌帺恎偵偁傞丅僗僺儖僶乕僌偼彮側偔偲傕亀塮夋亁偦偺傕偺偺朙偐側嫵梴偑偁傝丄亀塮夋亁偲亀價僕僱僗亁偺偄偄壛尭側绠鐞傪柍幾婥偵妝偟傫偱偄傞偩偗側偺偵丄忢偵帺暘偑嶌傞亀塮夋偵娭偡傞榖戣亁偵偮偒傑偲傢傟傞丅乽僨價儏乕摉帪偼廏嵥傇傝傪敪婗偟偨偺偵丄攓嬥庡媊偵娮偭偰丄偨傑偵怱傪擖傟懼偊偰僔儕傾僗側嶌昳傪嶣傞偲懯嶌偽偐傝乧乿丄偙偆偄偭偨栦愗傝宆偺丄偟偐偟丄偐側傝揑妋偱偼偁傞尵愢偼丄偁傞庬偺嬒峵傪廃傝偵攇媦偝偣偰偄傞丅偦偆峫偊傞偙偲偵傛偭偰丄変乆偼亀彜嬈庡媊偲塮夋偵娭偡傞榖戣亁偱埨掕偟偨峔恾偑摼傜傟傞偐傜偱偁傞丅娤媞傗儅僗僐儈偑僗僺儖僶乕僌偺亀彜嬈庡媊亁傗丄偨傑偵嶣傞僔儕傾僗側塮夋偺僥乕儅傪偁傟偙傟栤偄偐偗傞戅孅偝偼丄偙偺亀塮夋偵娭偡傞榖戣亁偑傕偨傜偡嬒峵偵婲場偡傞丅偦偺嬒峵偺拞偵偄傟偽丄亀塮夋亁傪娤側偔偰嵪傓偐傜偱偁傞丅偨偑丄巹偼亀塮夋亁傪娤傞偮傕傝偱偙偺塮夋傪娤傞丅亀愴憟偺斶嶴偝亁側傞亀塮夋偵娭偡傞榖戣亁側偳偳偆偱傕傛偄丅傑偢朻摢偺愴摤僔乕儞偩偑丄庤帩偪僇儊儔偲橂嵴嶣塭偺慻傒崌傢偣側偺偩偑丄傎偲傫偳慜幰偑堷偭挘偭偰偄傞丅偙偺僔乕儞偵愴憟儕傾儕僘儉傪姶偠傞偲偄偆偺偼丄偳偆偐偲巚偆丅傓偟傠傂偨偡傜亀塮夋亁揑側僔乕儞側偺偱偼偁傞傑偄偐丅巹偼偙傟傪朻摢偺亀塮夋亁愰尵偩偲巚偭偨丅偨偩偟丄昹曈偺抧宍忋偺暯偨偝傕偁偭偰橂嵴嶣塭偺妱崌偑彮側偔丄偍偞側傝偺僗儘乕儌乕僔儑儞傕偪傚偭偲旲偵偮偄偨丅偟偐偟丄朻摢偐傜偙傟傪傗偭偰偺偗傞戝抇偝偼丄偙偺塮夋偺僥乕儅塢乆偱偼側偔丄亀塮夋亁揑側惁枴側偺偱偁傞丅偦傟偐傜丄亀塮夋亁岲偒傪帺擣偡傞恖側傜扤偱傕偡偖偵暘偐傞傛偆偵丄儔僗僩偺峌杊愴偼亀幍恖偺帢亁偦偺傕偺偱偁傞丅塉偼崀偭偰偄側偄偑丄朻摢偲堘偄丄帪愜憓擖偝傟傞橂嵴僔儑僢僩偑岠偄偰偄傞丅庤帩偪僇儊儔偲偺慻傒崌傢偣偵惗棟揑側傕偺偵慽偊偐偗傞嫮偄傕偺傪姶偠偨丅屻丄敿夡偟偨壠偱僼儔儞僗恖晇晈偑柡傪拞戉偵戸偦偆偲偡傞拞偺廵寕愴偺僔乕儞丅擇摍暫偑寕偨傟偰傕偑偒丄塉偑崀傝偟偒傞丅偙傟偼偄偐偵傕丄俽丒僼儔乕揑偱偁傞丅偙偺僔乕儞傕巹偼婥偵擖偭偰偄傞丅僗僺儖僶乕僌偵僨價儏乕摉帪偺僉儗偑挿偄娫傒傜傟側偐偭偨偺偼丄斵偑亀儌僲亁乮椺偊偽亀僕儑乕僘亁偱嶭偑奀拞偱堷偭挘傞偙偲偱朶傟傑偔傞扢宆偺僽僀丄亀寖撍亁偺僩儔僢僋偺婄乯傪岻偔昤偗側偄傛偆偵側偭偰丄曄偵僪儔儅傗捖晠側姶彎偱夋柺傪枮偨偦偆偲偡傞傛偆偵側偭偨偐傜偱偁傞丅寛偟偰攓嬥庡媊偵懧棊偟偨偐傜偱傕丄恖娫偑昤偗側偄偐傜偱傕側偄丅杮暔偺僗儁僋僞僋儖偑昤偗側偔側偭偨偙偲偑嵟戝偺栤戣側偺偩丅偟偐偟丄偙偺塮夋偱偼丄偦偺尷奅傪彮偟業掓偟側偑傜傕丄亀塮夋揑亁側僉儗傪偁傞掱搙塻偔暅妶偝偣偰偄傞丅偦偺堄枴偱慺惏傜偟偄嶌昳偱偁傞丅傟偄側(9寧29擔)
奆偝傫偑嵟弶偺俁侽暘偺帠傪堦斣懡偔彂偄偰偄傞偺偑偲偰傕巆擮偱偡丅
偙偺塮夋偼僲儖儅儞僨傿乕嶌愴偺偙偲偩偗傪昤偄偨偺偱偼側偄偟丄儔僀傾儞傪彆偗傞偨傔偵俉恖傕偺暫巑偑媇惖偵側偭偨偲偄偆偙偲傪僥乕儅偵偟偨塮夋偱偼側偄偐傜偱偡丅愭偺戝愴偵晧偗丄孯戉傪帩偮偙偲偑傑傞偱埆偄偙偲偱偁傞偐偺傛偆偵嫵堢偝傟偰偒偨崱偺擔杮偺恖偵偼傢偐偭偰傕傜偊側偄塮夋偐傕偟傟傑偣傫丅偙偺塮夋偺尵偄偨偄偲偡傞偲偙傠偼愴偭偰偔傟偨暫巑偼奆晛捠偺恖娫偩偭偨偲偄偆偙偲偱偼側偄偱偟傚偆偐丠
巹偑偡偛偔僔儑僢僋傪庴偗偨偺偼僩儉丒僴儞僋僗偺墘偠傞暫巑偑尦偼崅峑偺嫵巘偱偁偭偨偵傕偐偐傢傜偢丄愴憟偑婲偒偰偟傑偭偨偨傔偵柍棟傗傝庁傝弌偝傟丄偦偺忋丄彨峑偵偝偣傜傟偰偟傑偭偨偲偄偆偙偲偱偟偨丅
偨偩偺崅峑嫵巘偑悢廡娫偺僩儗乕僯儞僌傪庴偗偨偩偗偱彨峑偲偟偰偺敾抐傗峴摦偑偱偒傞偱偟傚偆偐丠怑嬈孯恖偱偝偊摢偑偍偐偟偔側傞傛偆側嫬嬾偵晛捠偺巹偨偪偲曄傢傜側偄恖乆偑憲傜傟偨偲偄偆偙偲傪恎偵偟傒偰姶偠傑偟偨丅
傎偐偺暫巑偨偪傕傑偩傑偩巕嫙側偺偵丄偁傫側栚偵偁傢側偔偰偼側傜側偐偭偨側傫偰丄側傫偰愴憟偼柍堄枴側偺偩傠偆偲巚偄傑偟偨丅揋偩偭偰摨偠巕嫙偩偭偨偠傖側偄偱偡偐丅
偁偲丄巰傫偩暫巑偑彂偄偨庤巻偑恖偐傜恖傊偲搉偭偰峴偔偺偼姶摦揑偱偟偨乣丅
偁偭丄偦偆偦偆丄傁傫偪傖傫丄廵偱懪偨傟傞偲捝傒偼偁傑傝姶偠側偄偦偆偱偡丅
巹偺嫵偊巕偑懪偨傟偨偲偒偦偆偩偭偨偲偄偭偰傑偟偨丅捝偄偲偄偆傛傝偼僔儑僢僋偱乮捝傒偑傂偳偡偓偰丠乯傢偐傜側偄傑傑憱偭偰摝偘偨偦偆偱偡丅偱丄憱傟側偄偺偱壗偱偐側乣偲巚偭偰懌傪尒偨傜寕偨傟偰偨傫偱偡偭偰丅
婥晅偄偰偐傜傕捝傒偼偁傑傝側偔昦堾偵峴偭偨偦偆偱偡偑丅丅丅
偦傫側傕傫側傫偱偡傛乣丅戞堦丄僲儖儅儞僨傿乕偵幚嵺偵峴偭偨恖払偑偙偺塮夋傪尒偰偁傑傝偺儕傾儖偝偵嬃偄偨偭偰偄偆偔傜偄偱偡偐傜丄巹偨偪偑側傫偩偐傫偩尵偆偙偲偠傖側偄偭偡偹丅
壺撧偝傫偺彂偄偰偄傞乽愴憟曻婞乿偺寷朄偱堢偭偨恖娫偲傾儊儕僇恖偱偼丄偙偺塮夋偺尒偊曽偑堘偆偲偄偆偺偼杮摉偩偲巚偆丅僷儞偪傖傫(仛仛)(9寧28擔)
巹偼妋偐偵愴憟亖埆偲偄偆帇揰偱偙偺塮夋傪尒偰偄傞丅
偦傟偼偦傟偲偟偰丄偒偺偆彂偄偨偙偲傪彮偟曗懌丅
偙偺塮夋偼僨傿僥傿乕儖傪攔彍偟偰偄傞--偲彂偄偨偑丄巹偺彂偄偨偙偲偼丄偨傇傫揱傢傝偵偔偄偙偲偑傜偩偲巚偆丅
僿儖儊僢僩傪寕偪敳偔廵抏丄奀拞偵傑偱撏偒恖偺柦傪扗偆廵抏丄廵偺媇惖偵側傜側偔偰傕帺暘偺扴偄偱偄傞廵偺偨傔偵恎摦偒偑偲傟側偔側傝揗傟偰巰偸暫巑丅偁傞偄偼帺暘偺榬傪廍偄忋偘偰傆傜傆傜偲曕偔暫巑丅巰懱偺偦偽偵懪偪婑偣偰偄傞嫑偺巰懱偺嶳丅
偦傟傜偼愴応偺僨傿僥傿乕儖偱偼側偄偺偐丅妋偐偵僨傿僥傿乕儖偱偼偁傞丅偟偐偟丄偦偺僨傿僥傿乕儖偑偦傠偄偡偓偨偲偒丄偦傟偼僨傿僥傿乕儖偱偼側偔側傞丅乽慡懱乿偵側偭偰偟傑偄丄屄恖偺懱尡偵斀塮偟側偔側偭偰偄傞丅
僲儖儅儞僨傿乕嶌愴偵嶲壛偟丄惗偒巆偭偨恖乆偼丄乽嶴忬偼偙偺偲偍傝偩偭偨乿偲偄偆偐傕偟傟側偄丅乽僨傿僥傿乕儖偼偙偺偲偍傝偩丅姰慡偵昤偒偒偭偰偄傞乿偲偄偆偐傕偟傟側偄丅
巹偼丄偟偐偟丄媈栤偩丅
巹偨偪偼偳傫側懱尡偵偟傠丄偡傋偰傪尒傞傢偗偱偼側偄丅壗偐傪妋幚偵尒傞丅偦偟偰丄偦偺妋幚偵尒偨傕偺偵塭嬁偝傟側偑傜丄師偵偁傜傢傟傞傕偺傪尒傞丅帇慄偼丄偳偙偐偱尒偨傕偺偵塭嬁偝傟側偑傜丄師偺悽奅傪榗傔偰尒偰偟傑偆丅偦傟偑屄恖揑帇栰偺尷奅偱偁傝丄朙偐偝偩丅柺敀偄偲偙傠偱偁傝丄巋寖揑側偲偙傠偩丅
偦偺榗傒偑丄偙偺塮夋偵偼側偄丅恖娫偺帇慄傪榗傑偣偰偄偔儕傾儕僥傿乕偑側偄丅偙傟偼晄巚媍側尰徾偩丅
巹偑僨傿僥傿乕儖偲屇傇傕偺----偦傟偼丄偨偲偊偽亀晛捠偠傖側偄亁偺乽嫼敆忬乿偺晹暘側偳偩丅
抝偼彈偵乽桿夳斊偼丄偦傫側揹榖偺偐偗曽側偳偟側偄乿偲幎傜傟側偑傜偩傫偩傫桿夳斊偺婥帩偪偵側偭偰偄偔丅偱丄嫼敆忬傪彂偔偲偒丄桿夳斊偑偡傞傛偆偵妶帤傪愗傝敳偄偰偼傝偮偗傞丅偦傟傪尒偰丄彈偑傑偨幎傞丅乽憡庤偼偁傫偨偺惓懱傪抦偭偰偄傞丅摻柤側傫偐偵偟偨傜堄枴偑側偄乿
抝偼傗偭偲乽桿夳斊乿傜偟偔側偭偨偲巚偭偨偺偵丄偦偺峴摦傪傑偨斲掕偝傟偰偟傑偆丅--偙偺夁掱偑乽僨傿僥傿乕儖乿偲屇傇偵傆偝傢偟偄晹暘偩丅
恖娫偼壗帠偐偵塭嬁偝傟丄曄傢偭偰峴偔丅偦偟偰丄曄傢偭偨晹暘傪傑偨斲掕偝傟傞嬊柺偵弌夛偄丄嵞傃曄傢傞丅偙偺曄壔偑昤偐傟偰偄傞偲偒丄偦傟偼乽僨傿僥傿乕儖乿偑恀偵昤偐傟偰偄傞偲尵偊傞丅乽屄恖揑側懱尡乿偑曄壔偵傛偭偰乽恖娫慡懱偵偮側偑傞懱尡乿偵偐傢傞丅
偦偟偰丄偦偺曄壔偼丄巹偨偪偵丄帺慠偵擺摼偱偒傞傕偺偱側偔偰偼側傜側偄偲巚偆丅帺慠偵擺摼偱偒傞丄偲偄偆偺偼丄曄側尵偄曽偵側傞偑丄乽偁丄偦偆偐乿偲婥偯偐偣偰偔傟傞傕偺偑側偔偰偼偄偗側偄丄偲偄偆堄枴偱傕偁傞丅亀晛捠偠傖側偄亁偺抝偑妶帤傪愗傝敳偄偰嫼敆忬傪偮偔傞偍偐偟偝偼丄彈偵巜揈偝傟丄柧妋偵側傞偙偲偵傛傝丄傛傝怺偔擺摼偱偒傞丅
亀僾儔僀儀乕僩丒儔僀傾儞亁偵栠傞偲丄偁偺寖偟偄嶴忬傪惗偒敳偄偨8恖偺暫巑偼丄杮摉偵偁偺嶴忬傪尒偨偺偐丄偲偄偆媈栤偑巹偵偼巆傞丄偲偄偆偙偲偑堦斣偺栤戣揰偩丅
傕偟偁偺偡傋偰傪尒偰丄偦傟偱傕側偍偐偮丄忋晹偺柦椷偩偐傜1恖偺暫巑傪媬弌偡傞偲偄偆擟柋偵柦傪偐偗傞丄偲偄偆偺偼丄巹偵偼傢偐傜側偄丅
僩儉丒僴儞僋僗偑晹壓傪壗恖幐偭偨丄偲偄偆偙偲傪尵偆偑丄杮摉偵偦偺偙偲偵愑擟偲斶偟傒傪姶偠偰偄傞偺側傜丄巆傝偺晹壓偺柦傪庣傞偙偲傪戞堦偵偡傞傋偒偱偼側偄偺偐丅斵偼丄偙偺嶴忬傪愗傝敳偗偨晹壓偺壗恖偐傪懠恖偵擟偣丄怴偨側擟柋(傛傝婋尟側擟柋)偵慖傝偡偖偭偨晹壓傪楢傟偰峴偔丅
偦傟偑愴憟偲尵偊偽愴憟側偺偩傠偆偗傟偳丄偳偆傕偟偭偔傝偙側偄丅傕偭偲嬯擸偑昤偐傟偰偄偄偺偱偼側偄偐丅偙偙偱偼斵偼乽屄恖揑側懱尡乿傪偟偰偄側偄丅嶴忬傪乽屄恖揑乿偵庴偗巭傔偰偄側偄丅愴応偺僷乕僣丄暫巑偲偟偰偟偐庴偗巭傔偰偄側偄丅
忋棨偡傞慜偐傜偺乽庤偺恔偊乿側偳偱偼側偔丄斶嶴側愴偄傪偔偖傝敳偗偨嵀愓偑丄斵傜偺媬弌寑偵帩懕偟偰昤偐傟側偗傟偽側傜側偄丄偲巚偆丅
僲儖儅儞僨傿偺斶嶴側忬嫷偲媬弌寑傪偮側偘傞傕偺丄乽屄恖揑側懱尡乿傪丄偙偺塮夋偼傑偭偨偔昤偄偰偄側偄丅
偦偺偨傔偵丄慜敿偺愴応偑丄姰慡偵暘棧偟偰尒偊傞丅斶嶴側愴偄偼乽懱尡乿偲側傜偢丄乽奊乿偵側偭偰偟傑偭偰偄傞丅
偦傟偑巹偺戝偒側晄枮偩丅
戝曄栤戣偺懡偄塮夋偩偲巚偭偨丅儅乕儀儕僢僋(9寧28擔)
弌偩偟偺愴摤僔乕儞偼敆椡偑偁傞偲偄偊偽偄偊傞偐傕偟傟側偄偑丄傑偢偙偙偵栤戣偑偁傞丅
慛傗偐偡偓傞丅奊偵側傝偡偓偰偄傞丅僲儖儅儞僨傿乕偵忋棨偟傛偆偲偟偨弖娫丄僿儖儊僢僩傪傇偪敳偐傟摢傪捈寕偝傟暫巑偑巰偸丅奀拞偵傕廵抏偼旘傫偱棃偰丄暫巑偺嫻傪捈寕偡傞丅愒偄寣偑奀拞偵暚偒弌傞丅暫巑偼巰偸丅亅亅偦傟傜偺巰偼姰帏偡偓偰斶嶴偝偑側偄丅偁傑傝偺尒帠側巰偱偁傞偨傔偵丄斶嶴偲偼尵偄偵偔偄丅
朇抏偱曅榬傪幐偭偨暫巑偑帺暘偺榬傪廍偄忋偘傞僔乕儞傕偦偆偩丅旤偟偡偓傞丅妸宮偝偲丄徫偄偲偲傕偵偁傞摨忣偑側偄丅廥偝偑側偄丅
巹偨偪偼晛捠丄彫巜偺愭傪愗偭偰傕丄傑傞偱庤弍傪偟側偄偲巰偸傫偠傖側偄偐偲巚偆偔傜偄捝偑傝丄偆傠偨偊傞丅恖娫偼丄偦偆偟偨廥偝偵傛偭偰偄偒偄偒偲婸偔偲偒偑偁傞傕偺偩丅
偦偆偟偨尰幚偲斾妑偡傞偲丄偦偙偵昤偐傟傞愴応偼愴応偲偟偰姰帏偡偓傞丅
偙偺姰帏偝偼丄僨傿僥傿乕儖傪昤偔傆傝傪偟側偑傜丄僨傿僥傿乕儖傪姰慡偵攔彍偡傞偙偲偵傛偭偰側傝偨偭偰偄傞丅
偙偙偵偙偺塮夋偺堦斣偺栤戣揰偑廤栺偝傟偰偄傞偲偄偭偰傕偄偄丅
廵偺堦寕偵傛偭偰巰偸偺偱偼側偔丄偨偲偊偽懌偺彫巜偵旐抏偟丄捝偑傝偆傠偨偊丄媰偒傢傔偔暫巑偑偄傞偲偟偨傜偳偆偩傠偆乮幚嵺偼偄傞偲巚偆乯丅堦弖偵偟偰柦傪側偔偡暫巑偼丄彫巜偺偗偑偱傢傔偒偪傜偡暫巑偵斾傋傟偼偼傞偐偵斶嶴偩丅斵偼妋偐偵愴憟偺斶嶴偝傪揱偊偼偡傞丅偟偐偟丄斶嶴偡偓偰尰幚揑偵偼巚偊側偄丅娤媞偲塮憸傪寢傇僨傿僥傿乕儖偑側偄偨傔偵丄斶嶴偝偑乽奊乿偵側偭偰偟傑偭偰偄傞丅
偙偺僷乕僼僃僋僩側愴応偺斶嶴偝偺偁偲偵丄僷乕僼僃僋僩側僸儏乕儅僯僘儉偑墘偠傜傟傞丅
俁恖偺孼傪側偔偟偨堦恖偺暫巑丅斵傪愴応偐傜媬偄弌偡偨傔偵俉恖偺暫巑偑嬯摤偡傞丅
恖娫偼扤偱傕婾慞揑側峴堊傪偡傞丅婾慞揑側峴堊偑昁偢偟傕埆偄傢偗偱傕側偄丅婾慞揑側峴堊偡傜偱偒側偄偺偑丄晛捠偺恖娫偱偁傞丅偱偒側偄偐傜乽婾慞揑乿偲斸敾偡傞偙偲偱丄帺暘傪偲傝偮偔傠偆丅
晄巚媍側偺偼丄弌偩偟偺姰帏偵斶嶴側愴摤僔乕儞傪懱尡偟偨偼偢偺斵傜偑丄傎傫偺傢偢偐側掞峈偱婾慞揑側峴堊傪偱偒傞丄偲偄偆偙偲偩丅
傕偭偲偁偮傟偒傗妺摗偑昤偐傟傞傋偒偱偼側偄偺偐丅傕偭偲丄侾恖偺偨傔偵側偤俉恖偑丄偲偄偆巚偄擸傒偺僨傿僥傿乕儖偑昤偐傟傞傋偒偱偼側偄偺偐丅
儔僀傾儞傪媬偆偙偲傛傝傕丄斵傪媬偍偆偲偡傞夁掱丄偦偺峴偒偮栠傝偮偡傞偙偙側偺摦偒丄鐣弰偵偙偦丄傎傫偲偆偺恖娫偺僪儔儅偑偁傞偼偢偩丅
傑偨丄懠恖偺柦偱偼側偔丄帺暘偺柦傪庣傞丄偦偺偨傔偵愴偆亅亅偲偄偆恖娫偑丄愴応偵偄偰傕偄偄偺偱偼側偄偺偐丅恖傪嶦偡偺偑夣姶偩偐傜恖傪嶦偡偩偗偩偲偄偆恖娫偑偄偰傕偄偄偺偱偼側偄偐丅
偙偙偱偼偦偆偟偨恖娫傕昤偐傟側偄丅婾慞偝偊傕僷乕僼僃僋僩偱偁傞丅
偦偟偰丄偙偺斶嶴偺姰帏偝偲婾慞偺姰帏偝偑寢傃晅偗傜傟傞偲偒丄偦偙偵偼塮憸偲僗僩乕儕乕偺姰帏偝偑巆傞偩偗偱偁傞丅
愴憟偲偄偆峴堊偦偺傕偺傊偺斸敾偑傑偭偨偔寚擛偟偰偟傑偆丅愴憟偵傛偭偰恖娫偑嬯擸偟側偗傟偽側傜側偄偲偄偆帠幚偑寚擛偟偰偟傑偆丅
侾恖偺暫巑偺柦傪媬偆偨傔偵嬯摤偟丄巰傫偱偄偭偨俉恖偺暫巑乮俀恖偼惗偒巆偭偨偺偩傠偆偐乯傪巚偆偲偒丄巹偨偪偼妋偐偵丄偦偺俉恖偺柦傪扗偭偨愴憟偲偄偆傕偺傪憺傓偩傠偆丅斸敾偡傞偩傠偆丅
偩偑丄愴憟偼丄僸儏乕儅僯僘儉偺偨傔偵嬯摤偟偨俉恖偺柦傪扗偭偨偐傜憺傓傋偒傕偺側偺偐丅
偦偆偱偼側偄偼偢偩丅
堦斣娞怱側栤戣偑丄偙偺塮夋偱偼寚擛偟偰偄傞丄偲巚偆丅
乽擔忢乿偲偄偆帇揰偑姰慡偵寚擛偟偰偟傑偭偰丄傎傫偲偆偵乽塮夋乿偵側偭偰偟傑偭偰偄傞丅
弌偩偟偺愴摤僔乕儞偺敆椡備偊偵丄巹偼仛俀屄丅偙傟埲忋偼偮偗偨偔側偄丅巹偺側偐偱偼丄偙偺塮夋偼僗僺儖僶乕僌偺嵟埆偺塮夋偱偁傞丅
丂慡偔梊旛抦幆側偟偱尒偵峴偭偨偺偱偡偑丄偦傟偑偐偊偭偰傛偐偭偨丅傒側偝傫偑偍偭偟傖傞傛偆偵嵟弶偺俁侽暘傎偳偼偨偩偨偩乽埑姫乿偺堦尵丅偙傟傑偱塮夋傪壗昐杮偲尒偰偒傑偟偨偑丄偙傟傎偳偺僔儑僢僋傪庴偗偨偺偼弶傔偰偱偡丅丂偁傗 乮仛仛仛仛乯(9寧28擔)
丂僉儕儎儅偝傫偼乽愴摤偺條巕偑丄堦愗偺墘弌傕姶忣傕嫴傑傟傞偙偲側偔墑乆偲孞傝峀偘傜傟乿偲偍偭偟傖偄傑偡偑丄巹偼偙傟偙偦僗僺儖僶乕僌偺堄恾偟偨偲偙傠偩偲巚偄傑偡丅乽巰乿偐傜暔岅惈傪揙掙揑偵攔彍偟丄娤媞偵愴応偺椪応姶傪枴傢傢偣丄揻偒婥偡傜嵜偝偣傞丅偨偩偨偩楢懕偡傞柍堄枴側巰丅僗僺儖僶乕僌偼丄嬤戙愴偵偍偗傞戝検嶦滳偲偼寢嬊偙傫側傕偺偩偲偄偆偙偲傪丄偦偺慺惏傜偟偄塮憸偺杺弍偲岠壥揑側墘弌偱岅偭偰偔傟傞丅
丂惓捈尵偭偰丄巹偼偙偺塮夋傪尒側偑傜帺暘偼愴憟傪暘偐偭偰偄傞偮傕傝偱側偵傕棟夝偟偰偄側偐偭偨偺偩偲嫮偔姶偠偰偟傑偄傑偟偨丅偦傟偩偗偱傕偙偺塮夋傪尒偨壙抣偑偁偭偨偲巚偄傑偡丅惗敿壜側暯榓庡媊偵柍堄幆偵娒偊偰偟傑偭偰偄傞擔杮恖乮摉慠巹傕娷傔偰乯偵偼丄偄偄僋僗儕偐傕偟傟傑偣傫丅乮暔岅廔斦偺恖傪嶦偣側偄捠栿乮丠乯偺偔偩傝偼埨堈側暯榓庡媊傊偺傾儞僠僥乕僛偱偟傚偆乯偙偺塮夋傪僗僺儖僶乕僌棳偺斀愴塮夋偩丄偲妵偭偰偟傑偆偺偼傕偭偨偄側偄丅
丂 丂拞斦偺拞偩傞傒傗尰嵼偺儔僀傾儞偺僔乕儞偵偼懡彮偺丠偼偁傞傕偺偺丄愴憟塮夋傪乽娤傞乿偺偱偼側偔乽姶偠乿偝偣偰偔傟傞婱廳側塮夋偱偼側偄偱偟傚偆偐丅偩偐傜偙偺塮夋偼惀旕僗僋儕乕儞偱尒傞傋偒両乮偨偩乽柺敀偐偭偨乿偲偄偆姶憐偼傗傔偰傎偟偄偐側丒丒丒乯
丂揰悢偼仛仛仛仛丄傂偝傃偝偵峫偊偝偣傜傟傞塮夋偱偟偨丅儅僢僩丒僨僀儌儞偼憦柧側岲惵擭栶偑帡崌偆側偁丅
僲儖儅儞僨傿乕忋棨嶌愴偺強丄偐側傝徴寕揑偱偟偨丅
偁偦偙傑偱丄媞娤惈傪帩偭偰愴憟傪昤偄偨塮夋偼側偄偲巚偆丅
偁傞堄枴偱偼巆崜偐傕偟傟側偄偗偳丄偁傞堄枴偱偼変乆偵嵟傕愴憟偺恀幚傪揱偊偰偄傞傛偆側婥偑偡傞丅偙傟偩偗儊僨傿傾偑敪払偟偰偄傞偺偵丄寢嬊愴憟偺恀偺巔偑壗側偺偐丄偦偙偱壗偑婲偙偭偰偄傞偺偐丄杮摉偵抦傞偙偲偑偱偒側偄偙偲偵婥偯偄偨丅偁偺僔乕儞偼丄壓庤側斀愴儊僢僙乕僕傛傝傛偭傐偳岠壥偑偁傞偲巚偭偨丅
偲偙傠偑丄乮偙偙偐傜偄偪傖傕傫側偺偩偑乯偼偠傔偑徴寕揑側傇傫丄偁偲偺晹暘偑偟傝偡傏傒偵巚偊偨丅偮傑傝丄巹偺拞偱偼拞偺僗僩乕儕乕偑偦偺徴寕揑側晹暘偵晧偗偰偟傑偭偨丅
巹偵偼丄僩儉僁楧闐圖岰喚鑐洧椓恽擺哤暍槎咰挗酑鍯敘奀鏑洧鍩偁偺俉恖偺拞偺媬岇學乮柤慜朰傟傑偟偨乯偑巰偸僔乕儞偺傎偆偑婰壇偵巆偭偰偟傑偆偺偩丅
壗偐丄巹偺側偐偱偼乽俉恖偑侾恖傪媬偆偙偲偺堄枴乿傛傝乽愴憟偺斶嶴偝乿偑巆偭偨偺偩偑丄偙偺姶偠偐偨偱偄偄偱偟傚偆偐丠
側傫偐丄徯夘婰帠偲偐尒傞偲慜幰偺曽偑慜傊偱偰傞偺偱丄偦偆偄偆偙偲側傜傛偔暘偐傝傑偣傫偱偟偨丄偲偄偭偨姶偠側偺偩丅
偨偩丄傕偪傠傫丄堦弖壒偑墦偔側傞僔乕儞側偳傛偔偱偒偰傞偲巚偆丅
尒偵偄偭偰懝偼側偄塮夋偩偟丄傕偪傠傫儗儀儖偼崅偄偺偱仛係偮丅
偍傑偗丟 傾僷儉偺斵偑傛偐偭偨偲桭払偲偄偭偰傑偡丅
僀僊儕僗恖偭傐偄偱偡傛偹丠
側傫偐師偼儘僶乕僩丒僇乕儔僀儖乮僼儖丒儌儞僥傿偩傛乯偲嫟墘傜偟偄偺偱妝偟傒偱偡偹丅
僷儞偪傖傫偐傜僉儕儎儅(9寧27擔)
乽僩儉丒僴儞僋僗(偩偲巚偆)乿埲壓丄暥帤壔偗偟傑偟偨丅
帪娫偑偁傝傑偟偨傜丄惓偟偄暥帤傪偛楢棈偔偩偝偄丅
塮夋偑巒傑偭偰10暘偲宱偨側偄偆偪偵丄傕偆尒偨偔側偄偲巚偄巒傔偰偄傑偟偨丅僟僌儔僗丒僞僈儈(9寧26擔)
惁嶴傪嬌傔偨僲儖儅儞僨傿乕忋棨嶌愴偲偦傟偵懕偔愴摤偺條巕偑丄堦愗偺墘弌傕姶忣傕嫴傑傟傞偙偲側偔墑乆偲孞傝峀偘傜傟傑偡丅偦偺忬嫷偼丄暫巑偺憰旛傗摦偒丄尵梩尛偄偵帄傞傑偱帠幚偦偺傑傑偵嵞尰偝傟偰偄傞偦偆偱丄惢嶌幰偺偙偺擬堄偼妋偐偵偡偛偄偙偲側偺偱偟傚偆丅
偦傟偱傕巹偑偙偺塮夋傪妝偟傔側偐偭偨丄娔撀偑偙偺塮夋偱堦懱壗傪尵偄偨偐偭偨偺偐傢偐傜側偐偭偨偺偼丄忋塮帪娫偺傎偲傫偳傪愯傔傞愴摤僔乕儞 - 1944擭偵幚嵺偵婲偒偰偄偨偙偲偺拤幚側嵞尰 - 偼丄娽傪偟偭偐傝尒奐偄偰堦弖偨傝偲傕摝偝偢惓帇偟偰偄側偔偰偼偄偗側偄偺偵丄巹偵偦傟偑弌棃側偐偭偨偐傜偱偟傚偆偐丅壗搙偐婄傪偟偐傔偰偼夋柺偱偼側偔旼偺忋偵抲偄偨姄傪尒偰偄偨傝偟偨偐傜偱偟傚偆偐丅
乽愴憟偼僀儎偩乿偲偄偆偛偔僔儞僾儖側姶憐傪書偔偵偼丄梘棨掵(?)偺慜曽偵偄偨暫巑偑丄價乕僠偵拝偄偨搑抂偵摢傪懪偪敳偐傟偰懄巰偡傞偺傪尒傞偩偗偱傕偆廫暘偩偭偨傫偱偡偑...丅
塮夋偺朻摢偲嵟屻偵乮夋柺偄偭傁偄偵傊傫傐傫偲東傞惎忦婙偲堦弿偵乯搊応偡傞丄崱擔傑偱慞偔惗偒丄惗偐偝傟偰偒偨榁儔僀傾儞擇摍暫傕壗偩偐搨撍側姶偠偩偭偨偟丅
乽懜偄媇惖偺傕偲偵崱擔偺傾儊儕僇偼偁傞偺偱偡傛乿側傫偰扨弮側偙偲偱傾僇僨儈乕徿偺岓曗偵側傞傢偗側偄偟側偀丅傕偭偲偄傠偄傠側堄尒傪暦偄偰丄傕偆堦搙峫偊偰傒偨偄偱偡丅偼偄丅
墶昹偱弶擔弶夞俋丗侽侽偱偡丅惾偼丄傎傏枮惾偱偟偨丅僀儞僌儅儖(9寧20擔)
梊崘傕側偔丄杮曇偵擖偭偰偄偒傑偡丅
偦偺屻偼丄僆儅僴價乕僠偺愴摤偑廔傢傞傑偱乽偁偭乿偲尵偭偨傑傑丄岥傪暵偠傞偺傪朰傟偰傑偟偨丅
儎僋僓塮夋傗儅僼傿傾傕偺偺嶦偟偺応柺偱偼丄乽偙偆傗偭偰嶦偝傟傞傫偩側丅乿偲丄捁敡偑棫偮傛偆側塮夋傪婔偮偐尒偰偄傑偡丅偱傕丄愴憟塮夋偱偼乽巰乿偲尵偆傕偺傪丄偄傑偄偪儕傾儖偵姶偠偨傕偺偼偁傝傑偣傫偑丄偙傟偼丄傑傞偱帺暘偑墶偱僇儊儔傪夞偟偰偄傞嶖妎偵娮傝傑偟偨丅
乮廬孯僇儊儔儅儞偵傕堌宧偺擮傪帩偭偰偟傑偄傑偟偨丅乯
揺偵妏丄偁偺愴摤偑廔傢傞傑偱偼丄懅傪傕偮偐偣偸忬懺偱恑傫偱偄偒傑偡丅
偁偺懱尡乮尰幚偼丄偝傜偵偁傫側傕傫偠傖側偄偱偟傚偆偑乯傪偟偰偟傑偆偲丄恖娫傕曄傢偭偰偟傑偆偱偟傚偆偹丅
僉儏乕僽儕僢僋偺乽僼儖儊僞儖僕儍働僢僩乿偺傛偆偵乭儅僔儞乭偵側傜側偄偲偲偰傕偠傖側偄偑丄惛恄偑夡傟偰偟傑偆偐傕偟傟傑偣傫丅
乮偁傟偼丄夡偟偰偐傜峴偐偣偰傞偺偐丅乯
夵傔偰丄廬孯偟偨偠偄偝傫払偑乽惗偐偝傟偰傞乿丄乽塣偑椙偐偭偨乿偲偄偆堄枴偑丄敾傝傑偟偨丅巹偵偼丄偦傟偩偗偱戝廂妌偱偡丅
岥愭偠傖側偔丄怱偱傢偐偭偨偺偱偡偐傜乮彮偟偱偡偑乯丅娤偰椙偐偭偨偱偡丅
偁偲丄姶怱偟偰偟傑偆偺偼愴摤応柺偱僼傿儖儉偺怓挷傪旝柇偵曄峏偟偰偄傞偲偙傠丅
偁傟偑梋寁丄僪僉儏儊儞僞儕乕傐偝傪忴偟弌偟偰偄傑偟偨丅
崱夞偼丄撪梕偵偮偄偰偩偗偺姶憐偱偡丅
巹偺惎偼丄係偮丅
尭揰偼丄揋懳暫巑傊偺懳墳偑婾慞揑丅
忦栺堘斀偩傠偆偲拠娫傪嶦偟偨恖娫偑偦偙偵偄偨傜丄偦偄偮傪嶦偟偰傕偁偺忬嫷偱偼丄帺慠偩偲偍傕偄傑偟偨偑丅偦傟偑愴憟偱偟傚偆丅偨傇傫丅
尒廔傢偭偨屻丄崅峑惗僇僢僾儖偑乽僲儖儅儞僨傿乕忋棨嶌愴偼丄壗擭丠乿偲丄楌巎偺僥僗僩傪偟偰偄偨丠偺偑丄側傫偲傕斶偟偐偭偨偱偡丅傕偭偲丄尵偆帠側偄偺偱偟傚偆偐偹偉丅偼偀丅擔杮偺彨棃偼偔傜偄偭偡丅
俀俇擔偺擔杮岞奐慜偐傜榖戣偵側偭偰偄傞僗僺儖僶乕僌偺嵟怴娔撀嶌昳乽僾儔僀儀乕僩丒儔僀傾儞乿傪堦懌憗偔愭峴僆乕儖僫僀僩偱娤偰偒傑偟偨丅梊憐偟偰偄偨埲忋偵惁偄塮夋偱偟偨丅
塮夋偺朻摢偱丄楢崌崙孯偺僲儖儅儞僨傿乕忋棨偺応柺偑偁傞偺偱偡偑丄偙偺僔乕儞偱傑偢懪偪偺傔偝傟傑偟偨傛丅僲儖儅儞僨傿乕忋棨嶌愴偲尵偊偽丄僫僠僘丒僪僀僣偺攕杒傪寛掕晅偗偨愴偄偱楢崌崙偺戝彑棙偲偄偆僀儊乕僕偑嫮偐偭偨偺偱偡偑丄帒椏偵傛傟偽丄偙偺嶌昳偱昤偐傟偰偄傞僆儅僴價乕僠偱偺愴摤偼丄奀偑愒偔愼傑傞傎偳偺戝寖愴偩偭偨偲偺偙偲偱偡丅庤帩偪僇儊儔傪巊偭偨晄埨掕側塮憸偑偙偺寖愴傪惗乆偟偔嵞尰偟偰偄傑偡丅僇儊儔偼愨偊偢暫巑偺栚偲側傝丄奀偵愽傝丄抧傪攪偄丄敋寕傪梺傃傞偺偱偡偑丄愴摤僔乕儞偱偙傟傎偳偺椪応姶傪懱尡偟偨偺偼弶傔偰偱偡丅
嶰恖偺孼傪堦搙偵幐偭偨暫巑傪曣恊偺傕偲傊婣娨偝偣傞偨傔偵丄俉恖偺暫巑偑柦傪偐偗偰儔僀傾儞擇摍暫傪媬弌偡傞偲偄偆嬝偩偗傪暦偔偲丄偄偐偵傕傾儊儕僇恖偑婌傃偦偆側旤択偺傛偆偵傕巚偊傑偡偑丄朻摢偺愴摤僔乕儞傪尒偨偩偗偱丄偦傫側惗偸傞偄塮夋偱側偄偙偲偑偼偭偒傝偲暘偐傝傑偡丅
忋塮帪娫偑俀帪娫俆侽暘偁傞偺偱偡偑丄廔巒挘傝偮傔偨嬻婥偑棳傟偰偄偰丄偝傎偳挿偝傪姶偠傑偣傫偱偟偨丅僋儔僀儅僢僋僗偱丄晄婥枴側壒傪棫偰偰僪僀僣偺愴幵偑尰傟傞応柺側偳懅偑媗傑傞傎偳偺嬞敆姶偑偁傝傑偟偨丅
僫僠僗亖埆丄楢崌崙孯亖惓媊側傫偰偄偆埨堈側掕媊晅偗傪偣偢偵丄愴憟偲偄偆忬嫷偵抲偐傟偨恖娫偺巔傪嫊忺傪攔偟偰恀偭岦偐傜昤偄偰偄傞揰偼偲偰傕岲姶偑帩偰傑偡丅
偨偩堦偮擄傪尵偊偽丄儔僗僩僔乕儞偼僗僺儖僶乕僌偺昤偒曽偑恊愗偡偓偰丄偐偊偭偰偁偞偲偝傪姶偠偰偟傑偄傑偟偨丅傕偭偲偝傝偘側偔昤偄偨曽偑梋塁偑巆偭偨偲巚偆偺偱偡偑丄椺偊偽働儞丒儘乕僠娔撀偺乽戝抧偲帺桼乿偺傛偆偵丒丒丒丅
峳搨柍宮側屸妝戝嶌偱偼怑恖揑側忋庤偝傪敪婗偟丄僔儕傾僗側僪儔儅偱偼揙掙偟偨儕傾儕僘儉傪尒偣傞僗僺儖僶乕僌娔撀偭偰傗偭傁傝扅幰偱偼偁傝傑偣傫偹丅
梋択偱偡偑丄儅僢僪丒僨僀儌儞偭偰庱偑懢偄側偀偲巚偄傑偟偨丅屻傠偐傜尒傞偲丅摢偺暆偲庱偺暆偑傎偲傫偳摨偠偱偟偨丅
昡壙偼仛仛仛仛偲仛敿暘丄偮傑傝侾侽侽揰枮揰偱俋侽揰偱偡丅