「安物のブランデーで濡らした菓子のような批評」
(2016/12/21(水曜日))
たまたま家人が長い間、詩集を批評するブログをやっているので、拙宅には詩集が送られてくることが多いし、Facebookでも、家人の「友だち」リストから「友だち」を申請して、「友だち」を増やしたので、しぜん、「詩人」の言動をみたり、接することが多くなった。しかしすぐにうんざりしてきた。一応、詩集を出し、おもに詩を書くという活動をしている人々を、詩人と呼ぶが、まず、それらの人々の多くのなにが絶望的かというと、他人のことなどまったく関心を持っていないということである。他者と関わる場合も、自分の関心に添ってである。それになにより、そういった詩人たちは、集団を作り、朗読だの、いわゆる「パフォーマンス」をし、政治家のように、権威におもねて、きれいごとを言い合う関係を作り、それ以外のものはないものとする。当方のように、突然詩集を出しても、まるで無視である。まあ、私は彼らのように、百万円かけて二、三百部作った詩集をバラまいてもいないが。たいていは、詩集は、『現代詩手帖』が毎年年末に発行する、詩人の住所録がおもな号の、住所を見て、自作をバラまくのである。
詩集を制作するのは、今では、その『現代詩手帖』の思潮社だけでなく、土曜美術社、ふらんす堂、書肆山田だったかなー? そういうところの多くなっていて、ほかにも初見の出版社名ながら、りっぱなハードカバーの詩集を出しているところも多々ある。一方で、いかにチャチなつくりの「私家版」もある。
りっぱな作り(ハードカバー、型押し金箔題字)も多く、費用は百万円ぐらいかかているのではないかと思われる。そういうのには、たいてい「まえがき」や「あとがき」がついていて、思い入れもことさら深いのだろう。百万円詩集を毎年出せる金持ちもいる。そういうりっぱな詩集をつくり、自分が権威を思える詩人に送り、残りをテキトーに(?)バラまき、それで、なにか詩人のようなものになったつもりで、結構態度がでかい人があまりにも多い。ちょっとした賞でもとればなおさらである。
こういった人たちは、とにかく「ほめ言葉」が大好きで、少しでもケチをつけようものなら、もう次は詩集は送って来ない。なかには、最初から、その詩人が権威と信じるべつの詩人(大御所と彼らは思っているのだろうが)の「跋文」(ほめことば)付の詩集もある。いったい、ほめ言葉が付いていなければ、成立しない詩集って、なんなんだ?
詩人は他人には関心を持たないから、バラまいても、「ありがとうございます。じっくり読ませていただきます」なんて、Facebookのニュースラインに書き込んでも、たいていはろくに読んでないのでないか? つまり、百万詩集のおおかたはゴミ箱行きである。なんともったいない! そういう費用を、それこそ難民の人々のために寄付すれば、どれだけ世の中のためにたつか? しかし、詩人は、きれいごとはいくらでも書いたりいったりするが、基本的に他人や世界のできごとには関心を持たない。
また、短歌や俳句を「習っている」と人々もいて、そういう人々は、習えば、なにかを習得できると思っている。だいたいこういう態度は、かなり横着なのである。普通は、悩みながら、ひとりで、ある分野を模索していくところを、これらの人々は、でんと構え、「さあ、教えろ」という態度である。しかし、自分がそういう態度であることにはまっく気づいていない。
詩人でも歌人でも、自称、他称、「有名人」、「大御所」、「プロフェッショナル」等が存在して、それらの人々は、上に挙げたアマチュアを「食い物にしている」(笑)。
基本的に古典を読み、いまの時代と切り結んで、オリジナルなものを試行していことする、かつての世界の詩人たちがあたりまえにしていたことを、今の「詩人」「歌人」「俳人」と、自称、他称する人々は怠っている。まったく困ったものだ、と思っている時、40年近く前に書かれているが、以下の大江健三郎氏の文章に出会い、おおいに励まされたので、引用しておく。
大江氏は、自らは作らないが、詩歌の深い愛好者であり、よく考えてみれば、氏の作品のタイトルは、オーデンなどの詩の一行であることも多く、もしかしたら、作品全体も、詩なのだと考えることもできると、最近思うようになった。
*****
「ぼくが戦後に刊行された俳句・短歌集の、すべてを読んだ気さえする! もちろん斎藤茂吉の仕事が、その中心にあった。子供の経験の基本的性格においてではあるが、僕はある言葉を微細に動かすしかたによって、ほとんど宇宙的なものが大きく動くのを見る驚きを、芭蕉と茂吉にあたえられた」
「僕の経験と観察では、散文作家にとってもっとも難かしいジャンルは短歌である。それは散文作家に俳句より御しやすいと感じさせる言葉の構造であるから、散文作家はその罠におちいりやすい。おそらく『歌のわかれ』の中野重治氏よりも技術的・詩的にすぐれた短歌をつくりうる散文作家とは、もう考えにくいのではあるまいか? しかも中野重治氏は文字どおり歌に別れをつげたのであった」
「太宰治の自殺においてひとつだけ奥ゆかしいところがあったと思うのは、技巧派としては最上の部類の言葉の専門家のかれが、その辞世としては自作のかわりに伊藤左千夫の歌を書きのこしたことである。三島由紀夫の筆名はほかならぬこの歌人に由来するということであるけれども、しかし当の三島の辞世を思い出すならばノノ」
「あらためていう必要もないことかもしれぬが、専門の研究者、批評家と作家との関係は、おたがいドライに批評的であることが最も望ましい。肯定、否定のいかなる評価であれ、そこに重くるしい感情移入の傾斜がはいりこむと、生産的な意味があることは稀だし、きまって永つづきしない。僕の年代の作家たちは(しかもとくに僕はといっていいであろう)、平野謙氏からいかに多くの文学的な励ましを受けたかはかりしれぬが、それはつねにドライに批評的な文章によってであった。したがって作家の側からも、この先達にドライに批評的な文章によって反撃することができた。僕はもっとも感情移入のすくない言葉で、われわれの時代の真の文芸批評家に感謝をあらわしたい。愛によってであれ憎悪によってであれ、安物のブランデーで濡らした菓子のような批評は、あらためて新世代の批評家たちにそのやり方が頻用されるのを見るにつけても、厭な抵抗感がこみあげてくる」
(大江健三郎「詩が多様に喚起する」=わが猶予期間(モラトリアム)3、大江健三郎全作品 第Ⅱ期、1、(新潮社、1977年発行)所収)
******
この「安物のブランデーで濡らした菓子のような批評」という表現がすばらしい。さすがノーベル賞作家(笑)。
そのような「批評」が、今の文学(詩、俳句、短歌すべて含めて)界を覆い尽くしている。

★★★
「演劇は終わった」
(2016/12/20(火曜日)
高校の時演劇部にのめり込んで、大学もそのまま演劇科へ行ってしまったので、演劇を観る習慣はずっとついていた。常に最先端の芝居を観てきたつもりだ。
しかし、今の時代、演劇は終わったと私は感じて、もうどんな芝居も、観たいとは思わなくなった。
そうでなくても、人々は、かつてのアングラ芝居のような様相を呈し始めている(笑)。
かつてアングラで名を馳せた「老人」たちがなにか芝居をして、「はしゃいでいる」のをSNSなので目撃することがあるが、果たして、それがどれだけ持続できるのか? 演劇とは、ある意味、「運動」であった。
かつて演出家の鈴木忠志が「演劇の一回性」ということを言ったが、それとはまったく違う意味で、一回かぎり(上演期間と関係なく)のものなら、それは「まつり」である。
かつての、すでに無名人にも戻れない人々が、集まって、なんらかの芝居をする。しかし、それならの「老人たち」は、ふだんはいったいなんで食っているのか? 年金はちゃんとあるのか? 親戚ではないからどーでもいいが(笑)、自然と疑問がわく。
なかでも著名な某氏は褒め称えていたが、それがどんなに高尚な深い内容でも、どこか惨めさを誘う。誰も「ピコ太郎」には勝てない(笑)。というか、「ピコ太郎」をくだらないと批判しようと、世界は「ピコ太郎」の時代なのである。そういうときに、亡霊のようにわき出た、かつてのアングラ演劇人たちは、なにか大きくズレしてしまった人々のように見える。
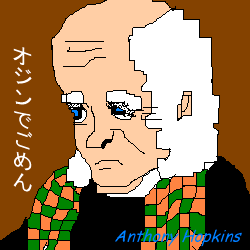
★★★
Topへ