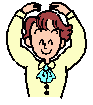飛行機の座席の背もたれに入っているもの なーんだ?
なんてなぞなぞではありません。誰でも知ってます。
通常は4点セットでございます。
・緊急時の対応を書いたマニュアル
・げろ袋
・航空会社の宣伝誌
・通信販売のカタログであります。
飛行機の中では新聞をもらわないと、こんなものを読むしかありません。
といいましても、まさかげろ袋を読む人はいないだろうけど・・・
緊急時マニュアルというのを読んでいる人なんているんでしょうか?
航空会社の季刊誌とか月刊誌なんて、ちと名の売れた教授とかタレントなどが書いているんですが、毒にも薬にもならないくだらないエッセーばかりで気の抜けたビールかサイダーのようなもの。
「これで原稿料をもらって恥ずかしくないのか?」と叫びたくなるようなしろものです。
さて、残るは通信販売のカタログしかありません。
通信販売のカタログといいましても、これが多種あります。
グッチだ、ヴィトンだ、シャネルだとブランド品が並んでいるだけものは手にとっても面白いものではありません。
いったいあんなカタログを見て誰が買うのでしょうね? いまどきヴィトンでもロレックスでも欲しけりゃ店に行くとか、ネットで安いところを探すのではないでしょうか?
飛行機の中で買ったなんて自慢にもなりませんし、お安くもありません。
海外の航空会社に乗ると、カタログ誌といいましても、ちとバラエティに富んでおりまして高級品のカタログ誌ばかりではございません。雑貨などが載っていて、見ていて楽しくなるものがございます。おもちゃ箱をひっくり返したと言う表現がぴったりといいましょうか・・・
先日乗った飛行機から頂いてきまして、暇があるとそのカタログを開いて見ております。これがとても楽しいのです。私を窃盗犯などと言ってはいけません。望遠鏡の広告の隣には、ヘッドホンステレオ、その裏にはなぜかトースター、そして次のページにはゴルフの手袋、模型飛行機、大きなクッション、ドッグフードの餌入れ・・・・
ご承知とは思いますが、座席においてあるこれらには「YOUR FREE COPY」あるいは「ご自由にお持ち帰りください」と書いてあります。
ご注意! 緊急用マニュアルには持っていくなと印刷してあります。
いったいこのとりとめのなさはどこからくるのか?それとも、この並びに何か規則性があるのだろうか?と考え込んでしまいます。
とにかく何度ページをめくっても飽きることはありません。
それぞれにお値段がついていて、買おうとすれば誰でもネットで申し込みしてカードで支払うこともできるのです。
そんなふうに楽しいひと時をすごしておりますと、昔のことを思い出しました。
昔、1970年頃のお話であります。
今も昔もアメリカ軍は世界中に展開しており、軍人も軍属もそれらの家族はものすごい数がいたわけです。そういった軍関係者のための通信販売のカタログがあったのです。
当時、私の働いていた会社ではそのカタログに載っている商品を作っていたのです。もちろん直接載せているような大会社ではなくそれにリストアップしていた会社から注文を受けて製作していたのです。そういった関係で私はカタログを一部いただいたことがありました。
それはけっこう大きな本でA4サイズくらいで厚さが数センチあったような記憶があります。そのカタログをめくりますと、ありとあらゆる種類の品物が載っていました。
・オーディオ機器
・カメラ
・家具
・おもちゃ
・衣類
・セクシーな下着
・靴
・バッグ
とにかく何でもありました。 そういったリストに載せてもらうということは当時の日本企業にとって大きな売り上げが期待できたのです。
もちろんですが、そのリストに載せてもらうためには審査があってまともな品質でないと取り上げてもらえなかったのです。
私はそのカタログを見て、ああすごいなあ!と感心しました。当時はアメリカの経済力、国民所得は日本と桁違いでした。アメリカの生活は垂涎(すいぜん)の的でした。
服にしても靴にしても、よだれが出るようなものがたくさん載っていました。当時の我々には手に入らない欲しいものばかりだったのです。
そのカタログを見ることは、アメリカの臭いをかぐことであり、豊かさというものを知ることでした。
本当はアメリカの庶民レベルだったのですよね。
このたび飛行機から頂いてきた雑貨のカタログのイメージはその米軍のカタログとそっくりでした。
たくさんの品物がごった煮のように所狭しと並んでいます。
豊かさの象徴であることは間違いありません。
ただ、この30数年で私たち日本人も豊かになりました。これらのおびただしい商品を見てもため息をつくことはありません。
気に入って欲しいと思えば、躊躇なく買える身分になったのです。
すばらしいことじゃないですか?
私は自信を持って言えます。この日本を高度成長させ、世界でも豊かな社会を作ってきたのは我々の世代であり、この私もそれに参加し貢献したということです。あの当時、勤めていた会社で生産能率を上げようなんてさまざまな試行をしてうまくいかなくて、残業した後に夜遅く上司や仲間と安い酒屋で酒を飲みながらまた議論し、いいアイディアが浮かぶとまた会社に戻ってテストをしたりしたものです。そんなことを思うとカタログ誌を見ていてちょっとリッチな気分になりました。
そんな情熱があったのですね、私だけでなく日本人みんながそうだったのではないでしょうか?
そんな向上心、チャレンジ精神が今の日本を作ったのです。
タイトルがどう関係するんだって?
単にカタログの表紙に書いてあったフレーズに過ぎませんがな、
ひとりごとの目次に戻る