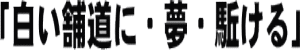|
| Part 1 往路5キロ・外堀通り |
|
白い一本の舗道はどこまでも平坦にみえる。心地のいい直線を遠くはるか地の果てまでのばしている。 現実の道路は時に微かな起伏をみせたり、上り坂と下り坂を繰り返したり、右に左に大きなカーブをきったりしているが、ひとたび走り出してしまうと、津村典子の眼にはつねにまっすぐにみえてくる。 ペタッ、ペタッ、ハッ、ハッ。ペタッ、ペタッ、ハッ、ハッ……。乾いた舗道を蹴って足がひた走る。右、左、右、左、ペタッ、ペタッ、ハッ、ハッ、右、左、右、左……。 調子がいい。すごくいい。今日は、とくに調子がいい……。津村は軽い昂ぶりを覚えつつも、まるで暗示をかけるように、たえず自分の躯に言って聞かせている。 道路の両側を埋めつくしている人びとの顔の背後には四角い巨大なビルが連なり、そのはるか上空に青空があった。壁のように連なる人びと、どの顔も明るい表情で、やってくるランナーを待っている。先頭集団が見えてくると、どの顔もいっせいに車道のほうに乗り出してくる。小旗をふりながら出迎える眸が動いている。 激しくうち振られる小旗のウエーブは、走っている彼女たちによりそいながら、どこまでも併走してくる。 短いかけ声、かん高い声援が飛び交い、拍手がわきあがる。それらは一瞬たりとも絶えることはなかったが、小旗の乾いたざわめきに入り乱れてしまい、走っている津村典子の耳には、頭上に舞う風が裂けているようにしか聞こえてこなかった。 津村は走り始めると何でもかんでも楽観的に考える。マラソンランナーはひとたびスタートしてしまえば、もう走りつづけるしかみち途はない。周りの風景が流れてさえいれば、それでひとまず安心できるのである。 彼女はひたすら前をゆく選手の背中をみつめている。タンザニアからやってきた二人、肩を寄せ合うようにして併走している。褐色の肌、無駄のない筋肉、真上から陽の光が当たると、彼女たちの顔には野獣のように精悍な表情が浮かびあがる。足を跳ねあげるようにして走る彼女たち、フォームからみるかぎり、危険性のないランナーのようにみえる。彼女たちが持ちこたえるであろう折り返しまでは、恰好の風よけになりそうだ。 とつぜん集団がざわめいた。道路の中央で先頭に立っていたルーマニアの選手が左側に進路を変えて、ピッチをあげはじめている。彼女を追っかけるようにして、誰もが左側に斜行してゆく。隊列がばらけて、縦長になりはじめた。津村の前をゆくタンザニアの二人も左側によってゆく。 「ドリンク、ドリンク!」 沿道の誰かが大声で叫んでいる。 耳覚えのある声である。サポートにきているチームメイトたち……。そうだ。最初の給水ポイントだ。 津村は若月玲奈の顔をちらとみた。誘われたように見つめ返してきた若月に彼女は、「給水をしっかりとれって、コーチから指示が出ているよ」と、眼で合図を送った。「付いてくから、先輩、案内してくださいよ」若月の眼は笑っている。「甘ったれるんじゃないよ」津村はにらみかえしながらも、若月をひっぱりはじめている。 給水はバトルである。躯がぶつかって転倒したり、足を踏んづけられたり、思わぬ陥穽が口をひらいて待ち受けている。何人ものライバルがいっせいに同じテーブルめがけてやってくる。走ってきたスピードをゆるめることなく、左手で自分のボトルを素早くかっさらわなければならない。 初マラソンのとき津村は五キロ地点でボトルをとりそこなった。中盤でいちどトップ集団から遅れたのは、最初の給水に失敗した動揺でリズムを失ったからである。二度目のとき、五キロ地点では躯が給水をもとめていなかったが、練習のつもりでボトルだけはとった。 津村は注意深く周囲に眼をこらした。給水がうまくゆくかどうか。彼女は最初の給水ポイントにレースのゆくえを占ってみようと思った。 彼女はテーブルの番号を確かめながら、意識して若月の先に立った。五番テーブルが見えてきたとき、彼女は若月に合図を送るかのようにちらと振り向いた。オレンジとコバルトブルーのボトルがテーブルの中央にならんでいる。ボトルにくくりつけた針金の大きな輪、その頂点から垂らしたリボンが微かにゆれているのが見えた。 テーブルの脇に走りこんだ津村は、スピードを緩めることなく素早く腕を伸ばした。次の瞬間には針金の輪をひっかけた腕に、オレンジのボトルがぶらさがっていた。 うまくいった。 ちらと振り向くと若月もコバルトブルーのボトルを腕にぶらさげていた。思わず眼と眼が合った。練習どおり……と、言いたげに彼女の眼が笑っているようにみえた。 若月はコーラの炭酸ぬき、津村は濃度を薄めたスポーツドリンク、それがボトルの中身である。 津村はキャップをとった。ごくりとひとくち飲みくだしてひとたび咽喉を押しひろげてから、一息に半分ほどを口に流しこんだ。ドリンクは液体の塊となってすとんと胃に落ちていった。 完璧……。 津村は口のなかでつぶやきながら、空になったボトルを歩道に向かって素早く投げた。 最初の給水がうまくいったせいなのか。なぜか躯が軽くなったように感じた。 「いいかい、けっして急いじゃいけない。たとえ急いでも、急いでいることを、ぜったい他の連中に気取られないことだ」 温まってきた津村の躯の底から、野島明弘の声が鮮やかによみがえってきた。 わたしのことを、いつも……。いつも、私のことだけを……。監督は、見てくれているのだと、彼女はあらためて自分に言って聞かせる。 脳裏にあらわれた野島と向き合いながら、眉間にうっすらと汗の滲む男の容貌に青年の輝きを、つよく感じた。その光が津村の記憶のなかに息づいている野島をあらためて照らし出した。 二年まえの一月であった。 津村は大阪国際女子マラソンを忘れはしない。彼女にとっても、彼女を送り出した監督の野島明弘にとっても初マラソンであった。 「監督、わたし……」 津村は野島の部屋に駆け込んだ。大会を翌日にひかえた深夜である。 床についても彼女は眠りに落ちることができなかった。うとうととしてもすぐに眼が醒めてしまう。浅いまどろみのなかで夢をみた。夢のなかで若月は右脚を引きずりながら走っている。なにも痛みを感じないのだが、右脚を故障している。なぜかそういう状況のなかにいて、彼女は後ろから追ってくるランナーたちにどんどん抜かれてゆくのである。 「いったい、どうしたんだ?」 「わたし、走れそうにありません」 津村は野島の顔をみたとたんに、思ってもみなかったことを口走っていた。体内にひそんでいた弱気の虫が暴れはじめたのである。彼女は自分で言っておきながら、すぐに自分の言ったことを、いったいどのように受けとめていいのか思案にくれていた。 「走れないって、それは、いったい、どういうことだ?」 笑っていた野島の顔に、とつぜん硬い線がうきあがった。 「右足に、まだ、ちょっと違和感があるんです……」 津村はおそるおそる上目づかいで野島をうかがい見た。 野島の顔をみていると、なぜか考えもしなかったことが口をついて出る。津村はそんなもうひとりの自分の存在をあつかいかねていた。 一カ月ほどまえ、右ふくらはぎに軽い肉離れの気配があった。けれどもトレーナーの指示をまもり、それほど練習量を落とすこともなくのりきってきた。 「なんか、モヤっとしてるんです。ほんとうなのです」 津村は言いつのったが、野島は無表情であった。しばらくは黙ってどこか遠くをみつめていた。 「このままでは、迷惑をかけることになります。会社にも、監督にも……」 津村は声を落とした。 「足のほうは、もう、だいじょうぶだ」 「でも……」 「おれが、保証してやる」 野島はそういって、こみあげてくる笑いをこらえながら、「トレーナーが大丈夫だと言っている」と、真正面からまじまじと津村の顔をみた。 「それに……」 二日まえから下痢がつづいている、と津村は言った。 まったくの口から出まかせだった。 「そんなことは、もう、聞きたくないぞ」 野島はきっぱりとした口調ではねつけて、津村のほうに向き直った。 「おい、ツムラ、おまえなあ、いったい、誰のために走るんだ?」 「それは……」 監督の……と、言いかけて、津村はあわてて咽喉の奧に押しもどした。 「会社が全社あげて応援してくれるといっても、走るのはおまえさんだよ。誰のためでもない。おまえさんが自分のために走るんじゃないか。ちがうか? そのおまえさん自身がほんとうに走れない……というのなら、それはもう、しかたがない。今からすぐに引きあげる」 野島は猛烈な形相とでもいうべき神経を顔中にはりつめながら、まくしたてた。 「さあ、どうするのか。自分でさっさと決めろ?」 野島に返答を迫られて津村は夢から覚めたようにわれに帰った。まるで心の底まで見透かされているようで顔が赤くなった。 「わかりましたよ。いいですよ。走りますよ。出なかったら、出て負けるよりも、よけいに叩かれそうですからね。もう、脚が折れても走りますよ。カントク、わたしのホネをしっかりひろってください」 津村はあえて強がってそのような口を利くことのよって、躯の奥底に巣くう弱気の虫を断ち切った。 「まかしておけ。いいか、うまくいけばメダルだ。だがな、たとえ失敗しても、誰ひとりも怒らない。なんといっても初マラソンなんだからな」 野島の眼もとは和み、母のような慈愛にみちた笑みをたたえていた。 野島のひとことで津村は深い眠りに落ちることができた。思いのほか心がやすらぎ、全身がくつろいだ。 翌朝もいつになく快く目覚めた。テレビをみながら柔軟体操をしはじめていると、いきなり電話が鳴った。モーニングコールを頼んだ憶えもないのに、と不審におもいながら受話器をとった。相手は野島だった。すぐに部屋にこい、という。声の調子は前夜と同じように和らいでいた。 「脚はどうだ?」 津村の顔をみるなり野島は訊いた。 「だいじょうぶです」 「腹のほうは?」 「あれは、どうやらキムチの食い過ぎのようでした」 津村が照れ笑いすると、野島はやにわにあゆみよってきた。そして、いきなり胸もとに抱き寄せられた。彼女はとっさのことで息がつまった。 「ツムラ、おまえさんの痛いところ、おれが全部もらった。だから安心しろ。いいか」 野島は静かに津村の頭を撫でながら、「だから、何も考えずに、思いっきり走ってくればいい」と言うのだった。 津村は野島がしゃべるたびに動く喉仏の動きをなんども盗み見ていた。頭を撫でる手の動きもごく自然で、それは情欲の気配とはまるで無縁の奇妙な誘惑とおもえた。むしろ、つねに彼女との距離をわすれてはいないという、心の中にある抑制のようなものが、かれの動作の端ばしから感じられた。 「監督、エッチですね」 津村はわざと身をよじってみせたが、野島はそんな挑発にのってはならないと自らに言い聞かせるかのように、「おまえさんを呼んだのはほかでもない。五歳のときに亡くなったというお母さんのかわりに、おまえさんを抱きしめてやりたかったんだよ。かわいいわが子を戦場に送り出すお母さんみたいに……な」と冷静な口調で言ったのだった。 野島明弘……。 津村が強く意識するようになったのは五年前、大学四年の夏だった。 ムーンストアの夏合宿に参加してみないか。陸上部の顧問を通じて、野島から声をかけられたとき、きっと何かのまちがいだろうと最初はとりあわなかった。 ムーンストアといえば実業団陸上の強豪である。全日本実業団駅伝では、六年もつづけて優勝争いにからんでいる。 津村は高校、大学時代を通じて、まったく無名だった。そんな自分に、実業団チームのトップが興味をもつはずがないと思ったのである。関西の大学にいた津村は全日本レベルでの実績がまったくない。大学四年間は八〇〇メートルと一五〇〇メートルで競技をつづけてきた。関西の大会ではなんどか入賞したこともあるが、三位までに入ったのは二度だけである。三年のとき、いちどだけ一五〇〇でインカレの出場権を獲得したが、肉離れで棄権した。大阪で行われる全日本大学女子駅伝では、三年つづけて三区の三、八キロ区間を走ったが、区間成績一〇位が最高だった。 実績のない大学陸上の中距離選手に、ムーンストアのようなトップクラスのチームから声がかかった。夏合宿に呼ばれるのというのは、ほとんど入社が内定したにひとしい。津村はまるで信じられなかった。 野島明弘といえば陸上界で誰一人知らない者はいない。関東でも万年最下位だったムーンストアをわずか二年で全日本実業団駅伝の四強に育てあげた。科学的なトレーニング法で注目をあつめている。高名な監督が自分を指名したと聞いても、津村はあまりにも唐突すぎて実感というものがまるでなかった。 津村がはじめて野島と顔を合わせたのは、札幌郊外にあるムーンストアの特設グラウンドだった。 合宿初日のその日はスポーツ記者たちが一〇人もかけつけていた。かれらは北海道ハーフマラソンに出場する三橋亜希子の取材にきていたのである。 三橋亜希子はそのころムーンストアのエースだった。駅伝では勝負を決める最長区間を走り、かならず区間賞を獲る。彼女はその年の一月、熊本でハーフマラソンの日本最高をマークして、ロードの第一人者として注目をあつめていた。夏の北海道ハーフでは世界最高をねらわせると野島はメディアに広言していた。 グランドでは濃いエンジのランシャツ姿の選手たちが、きびきびと走りまわっていた。日焼けした顔に、真上からの初夏の光が当たって、選手たちは誰もかれも野鹿のようで、ひかりかがやいていた。 記者たちの眼はひときわ背の高い三橋を追いつづけていた。 速く走ったあとに、それと同じくらいの距離を軽くジョギングで流し、また速く走る。三橋は独りで黙々と同じ練習を繰り返していた。 「あれは、どういう練習ですか?」 記者のひとりは解っているくせに、あえて野島に語らせようとする底意をひめて質問をぶつけた。 「ごらんのとおり、レペテーションですよ」 野島はかれらの作戦にのらなかった。何もかも察しているというとぼけた笑顔がおもしろかった。 「何本くらいやる予定ですか?」 「そんなもの、おれには、わからないよ」 野島はいきなり声を立てて笑った。 「一本、何秒ぐらいでやるんですか?」 「さあな、ぼくはストップウオッチを持ってないからね」 野島は表情を変えなかった。 かれは怪訝そうな顔をしている記者たちをちらとみてから、さらに言葉をついで、「それに、このグラウンドだけど、一周どれくらいあるのか、正確なところは、よくわからないんだ」と言った。 反復回数もタイムもとらずにレペテーションをやっている。常識では考えられないトレーニングである。 黙りこんだ記者たちからもれた低い溜息が横にひろがった。かれらは〈あきれてモノも言えない〉といわんばかりに、たがいの顔を見合っていた。 記者連中は野島を胡散臭そうにみていた。津村の眼にも野島が三橋亜希子のようなトップランナーを指導している監督には思えなかった。 「おい、キミたち、ムダだよ。三橋に聞いても……。彼女もきっと何も数えてないだろうからね」 野島は記者たちの腹を見透かすように言い放った。 かれは思考停止したかれらの一人ひとりの顔に視線をそそいだ。そして空疎な笑いがよどんでいるさまを堪能するまで愉しんでから、「あのね。自分の躯をどこまで追い込んだらいいか。それは本人しかわからないんだ。私なんかより三橋のほうが、ずっとよく知っているんだよ」と口をきった。 野島は記者たちのまえで話していたが、かれらを見てはいなかった。かれの視線は記者たちの頭上をこえて、居心地悪そうに突っ立っている津村のほうに向けられていた。 「タイム、反復回数……、そんなものはどうでもいいとはいわないが、それほど大事なことじゃない。いちばん大事なのは、その効果を本人自身が感じながら、トレーニングをつづけること……だ。機械じゃないんだからな。人間というやつは……」 野島が自分をみすえていることに津村は気づいた。 津村は率直にうなずきながら、さすがだと思った。野島は少なくとも選手を道具のように考えてはいない。女子陸上は駅伝によって人気スポーツになったが、ある意味でそれは「女性」としての人格否定を代償にしていた。実業団チームの監督の一部には女子選手を「女性」としてあつかわない連中もいる。かれらの戦略はまず「生理のあるうちはまだ二流だ……」と言い放って、女子選手をマインド・コントロールするところからはじまる。現実に生理のあった選手が、「たるんでいるぞ」と叱りつけられたという話を、津村も耳にしたことがあった。 あのとき……。野島の視線に躯ごと囚われてしまったのだと、津村は思っている。 身体をやや前のめりにして、ひたすら津村を凝視する野島のどこか切なげで、それでいて熱っぽい瞳のなかに、無類のやさしさを垣間見たせいかもしれない。 あれから四年あまり……。現在では躯だけでなく、精神までもすっかり野島にあずけてしまっている。 かれは一目みただけで体重の増減まで言い当てる。走ったあとの顔色で、ただちに心拍数や血液中のヘモクロビン、ミオグロビンの量も察するだろう。躯に変調があったときなども、野島にはごまかしがきかない。津村はそれが怖い。 先頭集団は首都高の高架下をぬけた。左手前方に後楽園ドームがみえてきたが、津村の眼のまえには、あいわらずまっすぐにのびる白い一本の舗道があるだけだった。 「折り返しまでは、誰かの背中をみながら、行きなさい。周りの選手たちはね、鏡なんだよ。わかる? 相手の姿に自分を映して考えるんだ。わたしはあんなふうにはならないぞ……とね」 津村の耳に、またしても野島の声が聞こえてくる。彼とともにいると思うだけで心がなごむ。その息づかいにも何気ない仕草にも、津村はほんとうに心の通う人とともにいる安らぎを覚える。 彼女は右側にいる若月をちらとみた。 躯をやや前傾にして、ひたすら前をゆくエチオピアの選手の背中を凝視している彼女の瞳の中にも野島がいるようにみえた。 若月玲奈は津村の同僚である。彼女もまた五年まえの夏、北海道の合宿に呼ばれたひとりで、翌年の春、ともにムーンストアに入社した。同期入社にもかかわらず高校出の若月は津村のことを「先輩、センパイ」と呼んで、やたらもちあげる。 ともに入社二年目で駅伝チームのレギュラーになった。駅伝を走るとき、たがいに力強い同士だった。津村は何度か若月からタスキをもらうことがあったが、タスキとともに彼女の勢いまでもらって突っ走った。「かわいい」後輩だと思っていたが、彼女がマラソンを走るようになってからは、そんな余裕はなくなった。 津村の初マラソンの大阪国際だった。招待選手ではなく一般参加の津村典子はマラソンランナーとしてほとんど無名だったが、優勝候補にあげられていたロシア、イギリスの二選手と最後までトップを争った。トラック勝負でやぶれて三位に終わったが、日本人には負けていない。若月の初マラソンはその一年後だった。大阪国際マラソンンといえば、好記録が出るので有名な大会だが、若月は初マラソン国内最高であっさりと優勝してしまった。スタートから先頭に立って、そのまま独走でゴールまで駈けぬけた。そのレースぶりが津村にはかわいくなかった。 津村はそれから二カ月後の名古屋国際マラソンに出場している。二度目のマラソンで優勝が期待されていたが、名もないケニアの選手にまたしてもトラック勝負で敗れてしまった。 二度とも最後の勝負どころで踏んばれなかった津村にくらべて、若月には勢いというものがある。陸上関係者の期待も若月に集まっている。 若月もまた、自分のすべてを野島にあずけたつもりでいるのだろう。彼女の翳りのない無垢な瞳がみつめているのは、地獄の底まで墜ちてゆくこともいとわないと思わせる監督にちがいない。 津村は若月をちらとみて、ほんの一瞬に微笑んだ。若月への敵意をひたかくした照れ笑いではない。彼女の眸に映っている野島に勇気づけられたのである。 前のページに戻るにはブラウザの「戻る」ボタンを押して下さい。 |