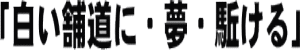|
| Part 2 往路7キロ・白山通り |
浜松町一丁目の交差点を目前にしたとき、野島明弘はふいにピッチをゆるめた。第一京浜はそこから少し右に切れ込むようにして新橋に向かってのびている。行く手の中空に架かるJRの高架がほのみえた。 「監督、こっちです」 野島を追い越した三橋亜希子は、信号を渡らないで左におれた。 日比谷通りの御成門に向かっては、そこからだらだら坂がつづいている。 「おい、そんなに急ぐなよ。まだ時間はあるだろう……」 野島は息がすっかりあがっている。 「監督、あれ、あれ、どうしたんです。息が粗いじゃないですか」 三橋は肩をゆすって笑い、「先に走り出したのは監督ですよ。急がなくてもいいのに……」と、上目づかいに彼をながめ、その唇が皮肉っぽく笑った。 「そうだったな」 野島は苦笑いした。 大門で地下鉄を降りたときから、かれは走りつづけている。階段を一息にかけあがり、地上に飛び出してからも、そのまま軽いジョッグでやってきたのである。 四〇歳なかばをすぎた現在でも野島は、朝のロード練習で選手たちの伴走役をつとめている。相手が女子選手だというせいもあるが、それほどひけをとることはない。 地下鉄大江戸線の大門から、日比谷線の御成門まで、わずか六〇〇メートルあまりである。走ったといえる距離ではないのに、野島は肩で息をしている。ユニフォームの上に分厚いグランドコートを着ているせいもあるが、何よりもこの数日間つづいた睡眠不足が多分に影響していた。前夜もほとんど眠っていなかった。 赤十字社の前にさしかかったとき、通りを挟んで右手に愛宕消防署、芝警察署が見えてきた。 「ほら、もう、すぐ、そこですよ」 三橋は行く手左側のビルを指さしている。 御成門交差点の手前にあるそのビルは大阪に本社のある大手家電メーカーの東京支社である。野島たちの勤めるムーンストアとは、ながねん取引関係があり、選手サポートの基地として駐車場を借り受けてあった。 ビルの正面玄関にひろがる駐車場には、すでに陸上部のマイクロバスとワゴン車が停車していた。応援にやってきた部員たちは、いましがた横断幕をもって日比谷通りのほうへ出ていったらしい。 「それじゃ、先に行ってますから」 三橋は彼女たちを追って、すぐに日比谷通りに向かっていった。 野島はワゴン車のドアに、肩をぶつけるような恰好でからだ躯を押しこんでいった。車内ではコーチの松沢剛士がひとりカーテレビをのぞきこんでいる。 「いま、どこだ?」 野島は松沢の背中に声をかけた。 「飯田橋のハローワークです」 松沢の声は昂ぶりのせいか、いつになくトーンがあがっている。 「六キロ手前だな?」 「どうします? 五キロが一六分〇八秒ですからね」 松沢は信じられないというように首を振った。 野島が五キロのラップを知ったのは地下鉄の大門だった。階段をかけあがって地上に出ると、やにわに携帯電話が鳴り出したのである。 電話の主はコーチの諸星正和だった。大会記録どころか世界最高のラップさえも上回っている。野島の代わりに監督ルームに詰めている諸星は昂ぶった声で叫んでいた。 野島は松沢にうながされてテレビの前に座った。ランナーたちはすでに外堀通りの坂ををくだりきろうとしている。 世界選手権代表選考会をかねた東京国際女子マラソンは、一二時一〇分に代々木の国立競技場をスタートしていた。外国招待選手九人、国内招待選手は一一人である。そのなかに野島が監督として指導にあたってきた若月玲奈と津村典子の二人がふくまれている。 代々木の国立競技場のマラソンゲートをとびだしたランナーたちは、周回道路を経てから、外苑東通りを北に向かって進む。四谷三丁目の交差点からは新宿通りに入り、四谷見附から外堀通りを飯田橋方面に向かってゆく。初めの三キロまでは、ほぼ平坦だが、外堀通りにさしかかる三キロすぎからは傾斜のきつい下り坂が三キロあまりもつづく。 テレビカメラは前方からトップ集団をとらえている。二四人から二五人ぐらいが折り重なるようにひしめいている。画面いっぱいにひろがっていたトップ集団は、だんだんと縦長になろうとしていた。ペースはさらにあがっているようである。 「このままだと、一〇キロは三二分二〇秒そこそこで来ますよ。どうしますか?」 「どう……と言われてもなあ。そういう流れなんだからな……」 野島は独り言のようにつぶやいた。 最近のマラソンでは、トップ集団から棄てられてしまえば、その瞬間にすべてが終わってしまう。マラソンはトラックの一万メートルを四回つづけて繰り返す競技だと考えたほうがいいほど、スピードが優先されるようになった。 「行かせるぞ。このまま」 「そうですか。わかりました」 松沢はドアからころがるよう車に外に飛び出した。 七キロ地点で待機しているコーチの結城真人に携帯で電話をいれるという松沢に、野島は「それから、顔色をよくみて、状況をくわしく報告しろ……とな」と早口でまくしたてた。 野島が津村と若月に声をかけたのはスタートの三〇分まえだった。競技場のグラウンドに降りてゆくと、二人はウオーミング・アップをはじめていた。 「ちょっと固いんですよ」 気遣わしげに声を落としたのは、朝から二人に付き添っているコーチの諸星だった。 津村と若月はたがいに顔を背け合うかのように距離をとり、思い思いにジョグを繰り返していた。 声をかけてもすぐには表情が溶け出してこなかった。諸星が言うとおり、ひたすら自分の穴にこもっていた。 津村にとってマラソンは三度目、若月にとっては二度目になる。だが二人が同じマラソンレースを走るのは初めてのことである。マラソンは個人競技である。駅伝を走るとき、彼女たちはたがいに力強い同士であったが、マラソンでは先輩も後輩もありはしない。二人は距離のとりかたが分からなくてとまどっているようだった。 「いいんだよ、これで……」 野島は微笑しながらひとりごちた。 個人競技であるマラソンは闘争である。ライバルを圧倒し、打ちのめすことによってなりたつスポーツである。津村も若月もマラソンランナーとして独り立ちする道をえらびとったからには、そういう宿命から逃げられないのである。 「気負いが裏目に出なければ、いいんですがねえ」 諸星は小声でつぶやきながら、両手をあげて二人に合図を送った。 「監督、こんなふうに言いたいんでしょう。レースに勝つのは、やるべきことをちゃんとやった者だ……とか」 野島の口まねまでして、ひょうきんに声を立てて笑ったのは津村典子のほうだった。 口数の少ない津村がいつになく饒舌になっている。それは緊張していることの裏返しであるとも思えた。そんな津村をちらと見て、若月は蔑むように薄笑いした。 「そうだ。マラソンというものは、ごまかしがきかないんだ。大事なのは、そのレースのために、何をやったか……だ」 野島は喋りながら、いったい同じ台詞をなんど繰り返してきたかだろうか……と、自分でもあきれかえっていた。 津村も若月も「またか……」というようなうんざりした表情をつつみかくしていた。二人とも野島から視線を背け、思い思いにどこか遠くを仰ぐように見ていたが、それはむしろ野島の話を真剣に聞こうとしていることの裏返しであった。 「いいかい。オマエたちはやるだけのことはやった」 野島はもういちど、津村と若月の顔をかわるがわるのぞきこんだ。 「自信を持っていいんだ」 満面笑みをたたえて、かれは静かにひとりうなずきながら、「さあ、行って来なさい」と、最後に気合いを入れるかのように二人の肩を軽くたたいた。 「この際、たとえ先輩でも蹴落とします……か」 若月はふいに低い声でぽつりと言うと、津村がすぐに、「まさか、お手をつないでゴールイン……というわけにもいかないしね」と、切り返しながら、ちらと野島のほうに意味ありげな視線を投げてきた。にやりとした貌に日ごろの津村らしからぬ自己主張が感じられた。 二人を送り出したあと、野島は待っていた三橋から、グランドコートとサングラス、マフラーを受けとって、足早に競技場をとびだしてきた。 大門までは二一分、三橋の道案内で野島は地下鉄の大江戸線に乗ってやってきたのである。競技場内にある監督ルームには、あえてもどらなかった。 テレビ画面にきりとられた先頭集団は水道橋から白山通りにはいった。七キロ地点の三崎町は目前である。日大経済学部前にいる結城からはまもなく連絡がはいるだろう。 野島は松沢が運転席に置いていったストップウォッチを手にとった。 傾斜のきつい下り坂でのペースアップはあらかじめ織り込みずみだが、想定したラップをはるかに上回っている。五キロから六キロまでのラップは三分〇八秒、六キロから七キロのラップも三分一〇秒を切りそうな勢いである。 狭い画面のなかに選手たちは折り重なり、ひしめきあっていた。カメラワークによってときおり六、七番手につけている津村と若月の姿がときおりちらと見えてくる。左右の腕ふりでバランスを保つ津村、前傾姿勢をくずすことなく、足首のバネでしなやかにストライドをのばす若月、二人とも練習のときと少しも変わるところがなかった。不思議なことに変わらないということが、逆に不安の種子を呼びこんで、野島は落ち着かなくなった。 カーテレビの小さな画面に、津村と若月は瞬時にあらわれ、そして瞬時にかき消えてゆく。画面を通してであるにせよ、まちがいなしに肉眼でとらえたと思っても、姿を消してしまうと、まるで自分が勝手にテレビ画面に思い描いた幻影であったかのように、あいまいにぼやけてしまう。実況するアナウンサーやゲスト解説者の声は聞こえても、選手たちの吐く息、頭や顔面、肩や腕から噴く熱気をはらんだ汗、そして足音すらも聞こえてこないからである。 野島はテレビの音声を消した。 すると画面の向こうから、いきなり選手たちの足音がまるで潮騒のようになだれうってきた。 タッ、タッ、ハア、ハア、タッ、タッ、ハア、ハア……。 ペタッ、ペタッ、ハッ、ハッ、ペタッ、ペタッ、ハッ、ハッ……。 折り重なってうねるように聞こえてくる足音のなかから、野島は津村と若月の足音を聞き分けることができた。息づかいも、風をきる腕振りの音さえも探しあてることができた。それらはランナーたちが走りぬけた痕跡をとどめるかのように、ランナーたちが走り去ったあとも、しばらくは空にただよっていた。 津村と若月は、このレースできっと世界選手権への出場を決めるだろう。野島はなぜかそんな予感がしてきた。 ほとんど無名にひとしかった二人を指導してきた野島は、彼女たちとは躯をつうじて、躯のことばで語り合い、たがいに思いや気持ちをぶつけあってきた。 津村が軽快なピッチで機械のように正確にきざみつづける歩幅や、若月の力強い腕振りが空に描きつづける模様、路面を蹴る足がもたらすリズムから、顔や肩口の発汗のようすまで、彼女たちはひたすら躯でのみ訴えかけてくる。 彼女たちが躯で語ることばを野島は視覚、聴覚、嗅覚などを同時にシンクロさせ、想像力をもって、正確に、慎重に、細やかな心づかいで受けとめてやらねばならない。それが監督・コーチの仕事だと野島は思っている。 集団をひっぱっているのはケニアとエチオピアの選手である。信じがたいようなラップを積み重ねてきた。ともに無名の選手である。持って生まれた天性のバネを活かしただけの走法からみて、あと五キロもすればスピードはにわかに落ち、テレビ画面にも映らなくなるだろう。科学的なトレーニングによることもなく、彼女を走り続けさせているのは天性の才能と体力だけである。まったく危険性のないランナーだとみていいのだが、ヨーロッパのレースではラビットが、そのままワン・ツウ・フィニッシュしたという例もないわけではない。無謀と思えるほどペースが速くても、相手がデータのないアフリカ勢だけに、無条件で先にゆかせるには危険がはらんでいる。優勝を争う主力がいずれも中団につけているのは、玉砕覚悟でひた走る危険性のないランナーなのかどうかを、後ろでしっかり見定めようとしているためである。 携帯電話が鳴っている。 ちりちり……とかすかに震えているのは、脱ぎ捨てたグランドコートのポケットのなからしい。松沢も気配を察して車内にとびこんできた。 「あっ、カントク……」 受話器の向こうにいるのはコーチの結城真人である。昂ぶった声、何やら急きこんだ息づかいをともなっている。 「二二分二五秒……です」 「ああ、見てるよ」 「集団は全部で二四人、招待選手はみんないます」 「で、どんなぐあいだ?」 「二人とも真ん中より少し前です」 「何か変わったことは?」 「とくにありません。ほかの何人かはスポンジをとりましたが、二人は見向きもしませんでした」 「どんなツラしてる?」 「落ち着いてますよ。それに、なかなかいいリズムなんですがね……」 結城の濁った言葉じりに不安の影がただよっている。 かれは思いがけない展開にとまどい、ほとんど思考停止状態になっているらしい。監督の指示を待っていた。 先頭集団の流れにそのままのって行かせるのか。いったんは集団から置いてゆかれても、あくまで想定したペースを忠実にまもらせるのか。序盤だからこそ、はっきり指示を出してやる必要があった。 野島のムーンストア陸上部では、全員が出場選手のサポートにあたっている。監督、コーチだけでなく、部員たちも携帯電話とトランシーバー型の小型テレビを持って沿道に立っている。野島が一声かければ、ただちに二人のコーチやマネージャー、あるいは沿道で待機している部員たちを通じて選手に伝えられる。 「楽そうか?」 「楽すぎるぐらいです」 「汗は……」 「まったく、かいてません」 「なら、そのまま行かせよう」 野島は落ち着いた口調で言った。 「いいんですね。それで……」 結城は声をふるわせている。 「いいんだ」 野島はきっぱりと言いきった。 どんなペースにも対応できる。二人ともどんなスピード競争にも耐えられる。それだけの練習は出来ている。 「ところで、結城……」 野島はふいに昂ぶった声になったが、相手の結城が「はあ? なんでしょう」と、まのびした声をあげたので、「いいんだ。また、連絡する」と言ってあわてて電話を切った。 現実のレースは七キロを通過したばかりだが、野島の脳裏に明滅しているのは、往路の三三キロすぎ、皇居壕端の光景であった。最大の勝負どころは三八キロ付近からはじまる坂ではなくて、むしろ日比谷公会堂から水道橋までの四キロにあるとみていた。 仮想のトップ集団が、次つぎにかれの脳裏に現れてきた。選手たちは、それぞれ前に出たり、肩をならべて併走してみたり、前をゆく選手の背中に胸をふれんばかりにくっついてみたり、それぞれが思い思いに執拗な牽制をくりかえしている。選手たちはそれぞれ相手の出方を注意深くみまもっている。自分いがいの選手たちのペースとリズムを本能的にきびしくはねつけ、誰かひとりのリズムが先頭集団をひっぱることを徹底的に拒否している。相手の走るリズムのすべてを躯で感じとり、機先を制するチャンスをねらっている。集団が砕けてちりぢりになるスパートの瞬間が野島の脳裏に何通りも浮かんでは消えていった。 かれの脳裏に去来する仮想のトップ集団にいる選手たちが、自分の敵をみつけてやにわに動き始めるとき、なぜかきまって日比谷公園から皇居前の壕端にさしかかる三二キロから三三キロに向かう風景が選手たちの背後に流れている。 レースはまだ序盤戦なのだが、野島はすでに勝負どころの昂奮を先取りして、体内の血を疼かせていたのである。結城と電話で話していて、ふいに昂ぶったのは、そのせいであった。 世界をめざすマラソンランナーを育ててみたい……。それは陸上部の監督を引き受けとき、野島が心ひそかに描いた夢である。 漠然としていた見果てぬ夢がかたちになるかもしれないと思ったのは、津村典子と若月玲奈に出会った五年前からである。かれはその瞬間から自分の夢を津村と若月の夢として育み、目標のレースに向かって着実にステップを踏んできた。東京国際マラソンはそんな野島にとって総仕上げのレースであった。 トップ集団はあと一五分あまりで芝公園まえにやってくる。 「さあ、おれも、ゆくぞ」 野島はワゴン車を飛び出した。 これが最後のマラソンなのだ。おれが勝負をかける最後のレースなのだ。 野島は人知れず口のなかで、ぶつぶつとつぶやきながら、日比谷通りのほうに向かってゆっくりと走り出した。 前のページに戻るにはブラウザの「戻る」ボタンを押して下さい。 |