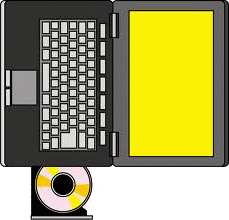12.08.18
ISOケーススタディシリーズとは本日は、非製造業の環境教育の第二回目(第一回目はこちら)でございまして、業務から見た環境法規制であります。
一般的に自社に関わる環境法規制を調べるということは、様々な法律について「この法律はこういう規制をしています。だからこういう設備が該当します」ということを延々と習い、あるいは自ら読んで、そして自分の工場あるいはオフィスが果たしてそれぞれに該当するのだろうかと、これまた延々と考えることになる。そして9割方、途中で道に迷い難破して、結論にたどり着いても誤っていることが多い。それでも環境法規制を勉強したぞ、調べたぞという気分にだけはなるというのが大方のところではないだろうか?
間違いないことは精神的にも肉体的にもだいぶ疲れるということだ。
「法律を覚えるぞ」とか「法律を勉強するんだ」という行政職や学究の徒ならともかく、一般企業の総務の担当者が、そんなアホみたいで効率の悪いことをしていては時間がいくらあっても足りないし、面白くもない。なによりも賃金をもらう時間にそんなことをしていては問題じゃないか。
当たり前に考えれば、オフィスの備品や廃棄物から、しなければならないことを逆引きする方法を教えてくれよという発想になるのではないだろうか?
私自身、危険物管理や作業環境測定に関わって35年以上、公害防止関係に関わって20年弱になる。
おっと、ここでPRTR法に関わって15年とか容器包装リサイクル法に関わって20年なんていうと嘘だとばれる。なぜ嘘かわからないようでは、環境担当者などと名乗ってはいけない。 なお、危険物とは私のような人物をいうのではない。消防法で可燃性、助燃性のものをいうと定めている。日本の法令は、みなこの定義を流用している。 |
私がそんなことを考えるはずがない、ウソだろうとお思いの方は、私の憲法に関するおびただしい駄文をご笑覧あれ。 実はこの駄文を書くことによって、ISO規格を読む力量が付いたように思う。要するに文字解釈を追及すること、よく考えることが大事だと思う。 |
いや、必要がなければ勉強する必要がなく、覚えることもないというのが正しいのだろう。私が英語が上達しないのは、いつも周りに英語が得意な人がいて私が話す必要がないからだろう。
さて、ケーススタディ本題に入る。
山田は自分自身が環境保護部に異動になってから法規制を勉強したが、それはけっこう大変だった。それで、法規制から届や資格者を調べるのではなく、設備や廃棄物などから届や資格者を調べる仕組みを作って、それを教えべきだという考えに至った。
藤本と五反田には、実態から法規制を調べる逆引きの方法で教えるように方向を示していた。山田の指示を受けた二人は、社内の情報システム部門を巻き込んで環境法規制把握システムというべきものをこしらえていた。今回の講習会では、そのシステムの使い方を教える予定である。
「業務から見た環境法規制」の講師は五反田が担当した。
「普通は環境法規制を学ぶというと、どんな法律があるのかということから始まります。しかし、本日は会社にはどんなことをしているか、どんなものがあるかということから考えるという方法を教えます。もちろん、自社にある設備や業務を知らなければ、どんな管理をしなければならないとか、どんな届をしなければならないかがわかるはずがありません。 この方法は、環境法規制について、しかもみなさんの会社の設備や業務の実態を元にして、現行法規制との関係を調べて鷽八百社の環境保護部が作成したデータベースと皆さんの会社の実態を比較するによって可能になります。 もちろんそれは、グループ企業が活用できる情報システムがあってこそ可能になります。 現時点は必要を満たしていると考えていますが、みなさんの会社の事業セグメントが変わればこのデータベースに関係する事項を追加しなければならないことになります」 | |
「質問です。我々は何も調べなくて、提示されたもの・・・まだ聞いてなく、これから教えていただけると思いますが、たぶん電子的か紙に書かれた項目をチェックすればよいだけということでしょうか?」
| |
「そうですと言いたいのですが、実は我々が整備しているのは国レベルの法律や告示、通知だけなのです。ですから都道府県、市町村のレベルの条例や要綱は網羅していません。それでこのシステムでわかるのは国レベルの規制だけです。 みなさんの所在している自治体の規制については、ご自身で調べてもらう必要があります。ですが、そういったものはあまり数多くないと思いますので、所在地の市役所あるいは商工会議所などに問い合わせれば間に合うと思います」 | |
「なるほど、わかりました」
| |
「今ご質問ありましたが、実際の仕事の方法はチェックリストというのではなく、パソコンの画面上に表示される問合せに各社の実態を入力することになります。具体的には鷽八百グループのイントラネットの画面から、各社の実態を入力すると、その結果どのような届や資格者が必要かが出力されます。 また例えばエアコンを廃棄する場合を選ぶと、何をしなければならないかが出力されます。 ここにパソコンがあります。今、初期画面を示しています」 |
|
|
「大きな項目として、建物の管理、調達、輸送、営業、イベント、環境債務というカテゴリーがあります。 建物の管理というのは、オフィスが所在しているビルの、エネルギーつまり電気やガス、空調設備、自家発電設備、PCB、廃棄物、下水排水、その他オフィス全般です。 調達というのは、商品の仕入れだけでなく、オフィス用品、PPC用紙の購入、内装工事、清掃や警備の業務委託、その他があります。 輸送とは、自社保有の車を運行することや、荷物の輸送を依頼するなどをいいます。 営業とは、マーケティングと実際に受注して販売することです。 工事を行う会社もあると思いますが、今回参加のみなさんの会社では工事をしていないことを確認しています。 イベントとは、営業や広報などで発表会や展示会を行うこと 環境債務とは、土壌汚染や地下水汚染などの管理と対応をまとめています」 | |
「質問、その膨大であろうと思われるチェックリストはいつ使うのですか? 毎年、チェックを行えということでしょうか?」
| |
「定期的に行うのではなく、必要な都度と考えています。そもそも法規制を毎年、調べようなんていう発想はおかしいですよね。ISO14001というものが現れた時から、法規制を調べましょう、いつ調べていつ見直しますという決まりというか悪弊が発生したのです。はっきり言って、それは間違いです。 本当はそうじゃないですよね。新しい設備を入れた時とか、新事業を企画したとき、法律が改正されたと市役所や商工会議所から通知が来たとき、設備を廃棄するときなど、そういう機会というかトリガがあったときに、法律に関わるかどうか調べて、必要なことをするというのが素直な発想ではないでしょうか?」 | |
「うーん、発想はわかりますが・・・・
弊社ではISO14001認証しているのですよね。それで、わかるでしょう。そういう常識から考えるとあたりまえの素直な発想の方法が、ISO審査で通るだろうかという懸念があります。もし、ISO対応の仕組みと本当の法律を調べる仕組みの二つを運用しなければならないとなると、手間が余分になりますね」
| |
「アハハハ、そういうご心配ですか。はっきり言います。今までしていたISOのための毎年の法規制のチェックを止めるべきでしょう。それで問題はありません。 そもそもISO規格に法規制を毎年調べろなんて書いてありません。書いてあるのは最新化を意味する『維持する(ISO14001:2004 4.3.2 第一行)』だけです。 もし審査員とトラブれば、私どもが支援して問題を解決しましょう。それに、失礼ですが、今までのISO対応で毎年法規制を見直していたものが、時間ばかりかかって、実際の仕事に役に立っていなかったのではないですか?」 | |
「おっしゃるとおりです。毎年審査員からああだ、こうだと言われて、仕組みばかりが複雑になってきて、仕事に役に関係なく、審査員のために資料を作っているとしか思えない状況になっています」
| |
「アハハハハ、そういう無駄を止めるということも今回の講習会の目的の一つです。二日間ですが、みなさんのお仕事の無駄をなくすという意味で、効果を出せるものと考えています」
| |
「ISO14001の悪弊というか、無駄排除をこの講習会に期待しています」
| |
|
|
|
電気をクリックすると更に階層が下がります」 |
|
「皆さんの会社の実態をこの画面に使用量を入力することになります。自社の実態を入力すると、何をする必要があるかが、表示されます その結果、省エネ規制が受けるかどうか、何をするかが表示されます。電気使用量やガス代は、そりゃ調べてもらわなくては困ります。なにもしないで自動的に進むようにはできません。 自社ビル、あるいは全館賃貸している場合、電気使用量に関わらず、オフィスはエネルギー管理標準を作らねばなりません。規模が小さくても法律ではそうなっています。まあ、工場の機械設備と違い、オフィスの省エネ、節電基準といえば、無駄を消す、空調温度の規制、設備更新時には省エネ機器を検討する程度でしょうけど・・ またオフィスビルにテナントとして入居している企業は、ビル管理会社の指示に従う義務があります。一部賃貸しているテナントの場合はこれでおしまいです。 自社ビル、あるいは全巻賃貸している場合で電気使用量が法で定める以上ですと、省エネ規制があります。 昔は電力や重油を大量に使っている工場は省エネを推進する義務がありました。その後法律が改正されて、工場だけでなくオフィス、デパート、劇場、レジャーランドなどにおいてもエネルギーを大量に使用するところは省エネ推進義務が生じました。最近の法改正では個々の工場やビルが対象ではなく、企業全体のエネルギー使用量でみるようになり、一定規模以上では省エネ義務があります。 なお省エネ法で規制対象になる規模は、コンビニ30店舗で該当すると言われています。 ですから、特に大きな会社でなくても該当します。もちろんコンビニは24時間営業で、冷凍ショーケースなどがあり、けっこう電気を使いますが、販売会社だって営業拠点が20か所あれば該当するかどうか細かく計算する必要があります。 昨今、原発の停止や原油の高騰などいろいろ状況が変わっていますが、電気1kWhは一般家庭で23円、企業で15円くらいか、それよりちょっと上でしょう。難しいことを考えずに、全社での1年間の電気代が9000万以下なら法規制はうけないと考えてよいです。空調や自家発電に、石油やガスを使っている場合はそれも合わせなければなりませんが、まあ大量に消費しているところはないと思います」
「質問」
| 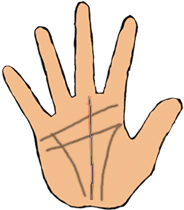 一人が手を挙げた。
一人が手を挙げた。
「はい、どうぞ」
「省エネ義務があるとのことですが、商売が伸びて使用量が増えたら、どうすればいいのですか?」
「そうですよねえ〜、どうすればよいのでしょう? まあ、ここはひとつ節電の推進や可能ならLED照明を考えるということで アハハハ」
「ああ、そういうことですか。わかりました」
「ともかくここで電気エネルギーを一定量以上消費していると入力すると、やるべきこと、管理標準作成、エネルギー管理統括者選任、エネルギー管理企画推進者選任、定期報告書作成提出などと、その様式、記入事例などが表示されます。必要なら、そのまま記入することで報告書ができます。 エネルギー管理士が必要な場合ですが、普通の非製造業のオフィスにそんな人はいないと思いますので、社内にいないと入力すると、対応案が表示されます」 あまり詳細に書けないし、ここに書いただけで、業務から関係規制をたどる方法を伝えられたかどうかわからない。たぶんわからないだろう。 ともかく、法律から規制内容を知るという方法は、回りくどくて実務に使えない。それができる人は専門家だけだ。一般の担当者は、会社の設備や状況から何をしなければならないかを知りたいし、それが理想なのだ。 と言いたいことをご理解いただければここの目的は果たす。
「先生、質問」
「私は先生じゃありません。でなんでしょうか?」
「世の中に、有料で法改正情報を定期的に送信してきたりするサービスがありますが、実際には、信頼できるのか怪しいし、実際にいろいろ質問したことがあるのですが、的確な回答をもらえませんでした。 行政に相談に行くのも足が重いし・・・とそういう実態からみて、これは便利だし、なにか不明なことがあれば本社の環境保護部が対応してくれるわけですね」
「そうです」
「しかし、便利なのは良いのですが、これは今後ずっと環境保護部のお世話になるというのも問題ではないでしょうか? こちら側にとっても、環境保護部側にとっても、長期的に考えると大丈夫なのでしょうか?」
「おっしゃる通りです。私どもがこの方法を構築するときいろいろと考えました。 最近は環境法規制といっても、皆さんような販売業であっても容器包装規制とか省エネ規制とかたくさんあります。そういった規制を、担当されている皆さんが熟知されていれば理想的です。 しかし環境法規制といっても100件以上と言われています。そして環境法規制を調べることは簡単ではありません。 考えてみれば、法律の読み方や、法律、施行令、省規則を各社の、あるいは各事業拠点の担当者全員が知らなければならないということはないと考えました。必要なことは、法で定めることを実施することなのです。つまり環境管理をしっかりしなければならないけれど、担当者全員が法律に詳しくなることが必要ではないということです」
「はあ? どういうことですか?」
| 五反田は以前、藤本や山田と議論した概念図をホワイトボードに書いた。
必要な力量の分担のイメージ図
「環境管理をするための力量はハンパじゃありません。しかし、それを一生懸命みなさんに勉強してもらうことが、会社のためにも、みなさんのスキルためにも良いことなのかと考えると、どうでしょうか? 少なくても、担当者がベテランになるばかりが、それを満たす方法ではないことは明白です。 私どもは、システムでそれをバックアップして担当者の負担を軽くするという方法を考えたのです」
「なるほど、私個人のことを言えば、環境管理は仕事全体のワンノブゼムでしかありません。しかも担当者は何年かごとに異動になります。一人前になるには・・いや、私自身一人前になっていないと思いますので、そのように仕事を支援する仕組みがあるということはありがたいことですね」
「皆さんには本来業務というものがあるはずです。特に販売会社の総務部門となれば、少人数でビルの管理だけでなく、安全衛生、労務、地域対応、情報セキュリティ、まあなんでもかんでも担当しているわけです。法律を調べるとか、ましてISOのためなんて主客転倒です」
| ●
その後、五反田が情報システムのあらましを説明した後、各受講者はノートパソコンを利用して、それぞれデータ入力というか、それぞれの会社の実態で環境法規制が関係するかどうかを確認する練習を行った。● ●
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私が現役時代、このような業務の実態から、どのような規制を受けるかを逆引きできる資料を作っていた。紙ベースではあったが。そのメンテナンスも毎年というか法改正や環境省の見解が替わるたびに改定していたが、それは大変な仕事だった。
更に言えば、使う側からすれば紙を読むのではなく、モニター画面でキー入力するだけで済むようなシステムを作るべきだったろう。言い訳ではないが一度ならず、そういった仕組みを作ろうとやってはみたものの、それをやるにはCGIが使えないとならず、htmとスタイルシートくらいしか使えない私の力量では無理な話だった。企業においては何事かをなすには、人徳だけではなく、予算がなければ実行できません。
おっと、人徳もありませんでしたが・・
実をいって環境監査に行くということは、ここで書いたデータベース的なものが頭に入っていることが前提である。
「お宅ではどんな法規制が関係しますか?」なんて監査員(審査員だって同じだが)語るようでは、そもそも監査員になるべきではない。訪問先の設備や業務を見たり聞いたりして、ああ、この法規制に関わるな、だからこういったことをしなければならないなと見当をつけて、それをしっかりと実施しているかを確認するのが監査というものである。
ということは、遵法監査を行うためには、法規制全般についての知識がなければだめですよ♪
このぶんでは、1日半の講習会を書きおえるのに、2月かかるのではないかと・・・・
つづきは → その3へ
名古屋鶏様からお便りを頂きました(2012/8/18)
随分前にVOCの調査で「環境省の下請け」なる調査会社が来たことがあります。そこで「役所に要望することはあるのか?」という質問があったので「民間の9割は法律の専門家なぞ置かないような中小企業だ。そうした企業のために『どのような設備にはどのような規制が掛かるのか』の逆引き一覧を作成して欲しい」と注文したことがあります。まぁ「貴重なご意見(ry」なのでしょうけどw
|
名古屋鶏様 毎度ありがとうございます。 行政がどこまでサービス(決して無償の行為という意味ではありません)するかということは議論の余地があるでしょう。 また、実際問題からすれば、事業の実態を知らなければ正しい逆引き辞書は作れないように思います。私は販売店やアセンブリーの製造業についてならある程度知っているとしても、プロセス工業、食品製造などになれば、まったくわかりません。 逆引きで法規制をわかるように、教えられるようになるには、ものすごいプロフェションが必要だと思います。 |
ケーススタディの目次にもどる