環境報告書の発行日は、6月末の企業が多かった。それにはいくつか理由がある。
まず日本の会計年度は4月はじまり3月締めなので、環境報告書のデータも会計年度に合わせているのがほとんどだ。それで4月初めから作業を開始すると、頑張っても6月頃になる。
それから多くの会社では株主総会が6月にある。今から20年前から10年前までは、環境報告書は立派な会社の証明のように見られていて、環境報告書を株主総会に配布したいとは誰でも思いつく。そんな訳で、6月末に発行していた会社が多かった。
過去形で言うなら、今は違うのか?
そう、現代ではあまり無理せず正確な情報をまとめようという風潮となり、無理して株主総会までに発行する会社は減った。言い換えると環境の重要性というか注目度が下がったのだろう。
JQAは当初から11月発行(報告期間は2019年4月から3月)だった。これはかなりゆとりがある。今年も11月9日に2020年版が発行された。
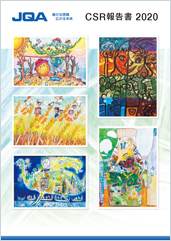 JQAは2009年から環境報告書を出している。我が国にJAB認定のISO認証機関が36社(2020.11.22時点)あるが、過去現在、環境報告書を日本語で発行したのはJQA以外ない。これは立派なことだと申し上げておく。(環境報告書を広報しない認証機関があるかもしれない)
JQAは2009年から環境報告書を出している。我が国にJAB認定のISO認証機関が36社(2020.11.22時点)あるが、過去現在、環境報告書を日本語で発行したのはJQA以外ない。これは立派なことだと申し上げておく。(環境報告書を広報しない認証機関があるかもしれない)
とはいえ、2009年からというのは日本では超遅いほうだということも申し上げておく。例えばパナソニックは1997年からだ。日本の一流企業はみな20世紀から発行している。
JQAの「環境報告書」も2014年から「CSR報告書」と改名し、それ以降 社会貢献やコンプライアンス体制の広報が増えたが、代わりに環境情報が減った。2020年報告書は表紙込みで40ページあるが、環境情報はたったの3ページである。これでは環境パフォーマンスの広報としてはちょっとプアだろう。
本日は「JQA CSR報告書2020」を見て、感じたこと・考えたことをコメントする。
もっとも私がまともに読んだのは環境のパートのみだ。
- 省エネ(*CSR報告書 p.28 以下同じ)
2019年目標 実績 評価 使用エネルギー(原油換算)(注1) 1,500kl以下 ★1,488kl★ ★🌞 達成 原単位(売上1億当たり)(注2) 2018年実績1%削減 6%増加 ★☁ 未達成★★ 上記を見て、いろいろ思うことや疑問に感じたことがあるだろう。
- エネルギー使用量が目標1,500klに対し1,488klと1%も多く達成したことは、すごい成果だと思うかもしれない。
注:エネルギー使用量削減はどこでも乾いたぞうきんを絞っている状態であり、目標を1%越えるなんてめったにない。
- 原単位当たり1%削減とは省エネ法と同じだ。第二種エネルギー管理指定工場等に該当しないとしても、環境貢献事業としてはいささか目標が低いのではないか?
ましてや目標を超えているのだから、せめて1.5%くらいにすべきではないのか。 - 使用エネルギーの目標値をクリアしているのに、原単位で目標未達どころか6%も悪化しているのはどういうことなのか?
- 数値目標はともかく、そのために行う施策が書いてない。施策は目標達成に見合っているのだろか?
改善計画は積み上げると使用エネルギー削減と原単位当たり削減の目標になっているのか? - などなど
ちょっと待て、2018年以前の状況はどうなのだろう?
まずは原油換算のエネルギー使用量の推移である。年度 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 原油換算
(kl)計画 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 実績 1343 1329 1427 1422 1394 1399 1488 これを見れば省エネの目標設定そのものが、まったくおかしく不適切だと思うのではないだろうか?
毎年の計画が前年実績より高いのだ。要するに達成して当然の計画を立てて達成したと喜んでいるわけだ。
だが原油換算の目標は、達成すればいいというものではなく、地球温暖化防止のためではないのか。それに省エネ法で定める第二種エネルギー管理指定工場等(注3) に該当しないにしても、削減努力義務はある。
この計画値は削減のためというよりも、法規制を受けないことを目標にしているとしか思えない。次に原単位の経時的推移を見てみよう。
2015 2016 2017 2018 2019 売上(億円) 148 145 153 157 158 使用エネルギー(原油換算 kl) 1,427 1,422 1,394 1,399 1,488 原単位(kl/億円) 9.64 9.81 9.11 8.91 9.42 原単位推移(2015年=100) 100 101.8 94.5 92.4 97.7 上表を見てわかるように、使用エネルギー量は4%内の変動しかない。原単位当たりのエネルギー使用量の変化は、主に売上(報告書の表記は「事業収入」)の増減によるだけである。そのせいか削減計画、つまり削減するための施策を立て実行するという削減努力は見られない。
これはもはや削減計画ではなく、単なる次年度の使用エネルギー予測であり、原単位試算に過ぎない。なおこの目標設定と削減計画の放棄というか不在は過去から同様であり、私は昨年のCSR報告書を読んだ時も批判している。こんなふざけた環境目標を、私は全く評価しない。
こんな数字を目標にするなら、「当機関は環境負荷が少ないから(実際は少なくはない)、当機関自身の省エネを推進することより、審査や検証あるいはコンサルタントによって日本企業の省エネを推進することを環境目標とする」というテーマにすべきではないのか?ところで、表からもわかるようにJQAは現時点第2種エネルギー管理指定工場等に該当しないがスレスレである。
だが第2種に該当しなくても努力義務は全く同じである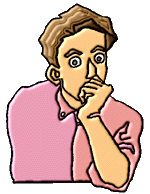
(注4)。
違いは行政のチェックが入るか入らないかの違いだけ。当然、第2種に該当しなくても、エネルギー管理標準を定めるとか原単位当たりエネルギー年1%以上の削減活動をしているはずだ。
であればなぜ第2種指定にならないことを目標としているのか不思議である。むしろ事業拡大をし、第2種、いや第1種に該当してもしっかりと省エネを推進していくということを目標にしたほうが妥当だと思う。町工場ならめんどうな法規制を受けないようにしようと考えるかもしれない。そしてエネルギー使用量が少ないならそれも許される。しかしJQAは町工場じゃない。マネジメントシステムの認証機関であり、報告書などの検証機関である。
JQAが環境・社会に貢献する事業だと自認しているなら、絶対にこんな安易というかいいかげんな目標を立ててはいけない。信用を失うだけでなく、JQAの審査員が受査企業に遵法を語ってもまともに聞いてくれないだろう。
こういう組織に、環境報告書の検証とかエネルギーマネジメントシステムの審査を頼みたくなるか、よく考えてほしい。 - エネルギー使用量が目標1,500klに対し1,488klと1%も多く達成したことは、すごい成果だと思うかもしれない。
- 事業を通じた環境貢献に関する環境目標
- 事業部門 ISO(p.29)
2019年度環境目標 取り組み 進捗状況 登録組織の環境活動向上★ ISO14001認証の拡大★ ★⛅ 60〜99%★★ テーマも取り組みも昨年と全く同じであり、昨年も非論理的で意味不明と論評した。
目標としている「登録組織の環境活動向上」とはなんだろうか?
取り組みにISO14001認証の拡大とあるから、単純にISO認証していない企業に認証させることではない。JQAがEMS以外のMS規格を認証している企業(i.e. 登録組織)に対してEMS認証させることなのか? そう考えないと「目標」と「取り組み」が論理的につながらない。
だが「ISO14001認証の拡大」とは「目標」のようであり、「取り組み(施策)」ではない。施策が「ISO14001認証の拡大」とはどういうことなのか? 良いアイデアがないから適当な言葉を埋めただけか?
次に「進捗状況」が2019年の進捗は60〜99%とあるが、それは何が60%なのか?
普通の組織で進捗は60〜99%でしたという報告がありえるか?
 今月の売上げは目標は60から99%の見込みですなんて語ったら、出直して来いと言われそうだ。まあ60〜65%ならあるかもしれないけど、
今月の売上げは目標は60から99%の見込みですなんて語ったら、出直して来いと言われそうだ。まあ60〜65%ならあるかもしれないけど、
どんな会社でも目標を5%外れたら大騒ぎ、60%なら関係する部長・課長・担当者の左遷は間違いない。一方上限の99%なら「良くやった」で終わるだろう。
まあ仮に60%としよう、「登録組織の環境活動向上」の60%達成したのか? ではその分子はなんで、分母はなんだ? いやいや、分子と分母がわかれば範囲を示す必要などなく、ズバッと一つの数字を出せるだろう?2017 2019/03 2019/12 JQA 総認証件数 10,931 11,837 10,129 JQA 内ISO14001認証件数★ 3,547 3,406 3,387 残念ながらJQAが上表でISO14001以外の認証している企業の数は不明である。またJQAがISOを認証していなくて他の認証機関がISO14001認証している可能性もあるが、その数も不明である。
進捗率が60〜99%ということは、JQAがISO14001以外の認証している企業の中で、認証した件数がその差額の最低60%になったということなのか? 上に注記したように非認証組織の数字が分からないので何とも言えないが、過去何年も同じ目標、同じ取り組みを掲げしかも毎年60%以上、ある年は100%以上の成果を出していて今も続けているとは訳が分からない。
過去のCSR報告書に記載されている同じ目標についての達成状況
過去のCSR報告書 ★記載ページ★ ★達成成果★ ★2017年CSR報告書★ p.33 60〜99% 2018年CSR報告書 p.28 60〜99% 2019年CSR報告書 p.28 100%以上 2020年CSR報告書 p.28 60〜99% なにをもって進捗を表しているかわからないが、2020年末においてJQA認証企業のうち、ISO14001未認証企業が5割存在するということはどう理解すればよいのか?
注:JQAのMS全規格の認証組織が10,129組織あり、ISO14001認証組織が3,387組織である。仮にISO14001認証組織がすべて他のMS規格の認証を受けているとしてJQAの認証組織の実数は6,742組織となり、内ISO14001認証割合は5割である。
もちろん残り6,742組織が、他のMS規格を重複して認証している可能性もある。正確なことはわからないが、つじつまが合わないと思う私の考えはご理解いただけるだろう。表の数字を見ただけではISO14001以外を認証している企業に対して、ISO14001認証が進んでいるようには見えない。さて、進捗が66〜90%とはなんだろう? そもそも進捗の表記が60〜90%と幅があるとは成果(それが何かも不明だが)を正確に把握しているとは思えない。となるとISO14001 9.1.1 c)に不適合ということでよろしいだろうか?
ともかくこの論理が全く理解できない。 - その他の事業部門
安全における環境目標は
「各種技術基準・規格に基づいた製品試験や電磁環境試験など適合性評価事業を通して信頼性の高い製品の供給と安全な暮らしを支援し、環境負荷の低減に貢献する」
 ISO14001:2015の目標の定義は「達成する結果」である。上記の環境目標とされたものは、業務そのものではないか。その業務においていかに環境負荷の低減をするかが活動であり、数値であろうと定性的なものであろうとその達成すべきものが目標である。
ISO14001:2015の目標の定義は「達成する結果」である。上記の環境目標とされたものは、業務そのものではないか。その業務においていかに環境負荷の低減をするかが活動であり、数値であろうと定性的なものであろうとその達成すべきものが目標である。
次に計量における環境目標は
「温度計および湿度計の校正業務の拡大を通じて正しい温度管理、湿度管理を推進し、CO2 の排出削減に貢献する」
上記目標を達しても、それは単なる定型業務である。校正業務が世の中で行われている温度管理や湿度管理に貢献することは当たり前であり、校正業務において、省資源、省エネ、その他の改善を図らなければならないはずだ。
もし上記目標がISO14001の目標を満たすなら、JQAはISO審査で一般企業が「当社においては社内規定に基づき、粛々と職務を執行する」というものを環境目標としていれば適切と判断するに違いない。
だがISO14001からすればそれはおかしい?
その他、「MT、JIS、地球」の部門の目標も上記と同様な現状維持だけである。
手順に定めてある通り粛々と仕事することは、単なるOperationである。
そして目標の記述は定量的でなく、定性的でさえない。あまりにも漠としていて、どう言い募っても環境目標とはいいがたい。最大限譲歩してもせいぜいが環境方針レベルじゃないか。
これがISO審査で適合判定を受けるはずはない。JQAの環境目標はISO規格に不適合でよろしいのか?
実際には具体的な目標を定めて、成果の達成・未達成を判定基準を定めて評価しているのかもしれない。だがこの報告書からはそのようなことは読み取れない。
社外に出す報告書に、このような不可解なことを書くのが信じられない。
- 事業部門 ISO(p.29)
■環境負荷の全体像の数字に理解できないところがある。(p.30)
エネルギー投入量の原油換算と、アウトプットの温室効果ガスの排出量の数字のつじつまが合わないように見える。
もしかしたら電気の購入先の一次エネルギーの違いとか、二酸化炭素排出係数の異なるものが混じっているのかもしれない。正確な数字であると思うが、関連がわかるような記述が欲しい。省エネをしていた者には非常に関心のある数字であると申し上げる。
■品質の取り組み 技術力の維持・向上を図っています(p.33)
ISO審査員に対して、「「目からうろこの環境法」とともに、「環境法の基礎の基礎」の審査実践編を行いました」とある。
教育訓練の成果をどう評価するかは、いつも議論となるところだ。教育訓練をすることを力量強化の指標としてよいのか? その結果として実際の力量が向上したことを指標とすべきかである。
このCSR報告書において、ISO審査員の力量向上を教育訓練したことをもって成果としていることから、一般企業についても教育訓練を実施することによって要求を満たすと考えていると理解する。
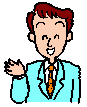 ISO9001:2015では「力量を身に付ける処置をとり、とった処置の有効性を評価する(7.2 c)」とある。JQAは、この後段がなくても規格要求を満たすと考えているわけだ。
ISO9001:2015では「力量を身に付ける処置をとり、とった処置の有効性を評価する(7.2 c)」とある。JQAは、この後段がなくても規格要求を満たすと考えているわけだ。
もちろん審査員にも、「教育訓練の実施をもって力量があると判定すべき」と周知されていることだろう。いや、皮肉ではない。審査において後段を要求するなら、自組織に対しても同様に判断するだろう。
おっと、失礼、
JQAにおいてはしっかり研修の成果を確認し力量の向上を評価していますか。それならぜひとも力量を示す指数とその確認方法をご教示いただきたくお願い申し上げます。
■JQAの概要(p.39)
感想というか老婆心であるが・・・この時世でもJQAの売上は順調に増加している。しかしISO認証関係は微減が続いており、売り上げに占める割合は減る一方だ。
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 売上(億円) | 148 | 145 | 153 | 157 | 158 |
| ISOの占める割合 | 53% | 49% | 49% | 48% | 46% |
| ISO売上推定(億円) | 78 | 71 | 75 | 75 | 72 |
注:JQAのCSR報告書には総売上のみ数値が記載されている。ISO売上推定額はグラフから読み取った。
生物だけでなくどんな製品やサービスにも、そしてビジネスモデルにも寿命がある。むしろ第三者認証というビジネスモデルが30年も継続したという事実は不思議とさえいえるだろう。JQA内部ではISO認証事業の今後が検討されていると思う。
かって検査機関だったJMIが、第三者認証ビジネスに進出しJQAと改名したように、今 新たなチャレンジのときなのかもしれない。
昔、JMIに種々の試験でお世話になり、JQAとなってからISO審査も受けた人間として、更なる発展を祈念する。
![]() 本日の希望
本日の希望
JQAの環境活動を、ISO14001の要求事項を満たすように改善してほしい。
ひとつ、環境目標策定においてにISO14001規格に準拠していただきたい。JQAの目標を参考に作成した受査企業についてはISO審査において問題なく適合判定をすると理解するが、それでよいのかと疑問をもつ。
ひとつ、CSR報告書の環境パフォーマンスを具体的な数字で示してほしい。イメージだけの環境報告書では、環境報告書ガイドライン制定以前の20世紀末の環境報告書ようだ。
ひとつ、もっと多様な環境データを公開してほしい。内部監査でカテゴリーがAとかでなく具体的に、順守評価結果の内容など知りたいことは多々ある。
なお、昨年もJQA環境報告書の読書感想文を書いております。ご一読いただければ嬉しいです。残念ながら昨年から一歩も進歩が見られない。
環境報告書を検証する機関なら、国内外に範を垂れてほしい。
 原油換算とは、使用エネルギーには電気、ガス、石油などがあり、それらを合計するために、それぞれのエネルギー量を原油に換算する。換算係数は省エネ法で定められている。
原油換算とは、使用エネルギーには電気、ガス、石油などがあり、それらを合計するために、それぞれのエネルギー量を原油に換算する。換算係数は省エネ法で定められている。 | ||
売り上げが増えれば使用エネルギーが増えるのは当然だ。だから単純に使用エネルギーを減らすことを法律で定めているのではなく、売上とか生産数量などで使用エネルギーを割った原単位当たりエネルギー使用量を削減することになる。 | ||
省エネ法で工場やビルなどで、原油換算3,000kl以上だと第1種エネルギー管理指定工場等に該当し省エネ義務、有資格者の配置、管理体制の構築などが要求され、1,500kl以上だと第2種エネルギー管理指定工場等に該当して第1種より緩いが省エネなどの規制を受ける。 | ||
うそ800の目次にもどる