私の住むマンションは上水道である。当たり前というかもしれないが、農村とか市街地から離れた団地では、
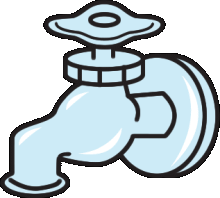 公共の水道でないことも多い。家内の実家は、元は簡易水道だった。
公共の水道でないことも多い。家内の実家は、元は簡易水道だった。
さてふた月に一度水道使用量の通知兼請求書がくる。
我が家は老夫婦二人暮らしで、月々の水道使用量はほぼ13立米である。季節が変わってもあまりこの使用量は変わらない。電気料金が季節によってサインカーブのようになるのに対して、水道料金は年間を通じてほぼ平だ。毎日風呂に入り、毎日出すものを出すことに変わりないからだろうか。
注:立方メートルのことを立米と書いて「リューベ」と読む。
ちなみに面積はm2を平米と書き「ヘイベイ」と読む。
夫婦二人の家庭の水使用量が13立米なら、一人はその半分で一日210リットルになる。果たしてこれは多いのか少ないのか?
日本の水道水使用量の平均は224リットルという。我が家は多少少ないがほぼ平均だ。もちろん家族数によって一人あたりは変わる。当然だが同居家族が多いと一人当たり水使用量は少なくなる。1人と2人の差が小さいがなぜだろう? また5人暮らし以上になるともう一人当たり水量は減らない(変わらない)ことがわかる。
ともかく我が家が二人で13立米というのは日本の平均だ。
| 世帯人数 | 使用水量 m3/月 | 一人当たり m3/月 | 一日一人 リットル/日 |
| 1 | 8.2 | 8.2 | 265 |
| 2 | 15.9 | 8.0 | 258 |
| 3 | 20.4 | 6.8 | 219 |
| 4 | 24.3 | 6.1 | 197 |
| 5 | 28.5 | 5.7 | 184 |
| 6以上 | 33.9 | 5.7 | 184 |
 ところで、少し前「グレタと立ち上がろう」という本を読んだ。そのときグレタお嬢さんの国スウェーデンでは、一人一日の水使用量がなんと115リットル
ところで、少し前「グレタと立ち上がろう」という本を読んだ。そのときグレタお嬢さんの国スウェーデンでは、一人一日の水使用量がなんと115リットル
そりゃ、すごい!
もちろん日本は高温多湿であるのに対し、スウェーデンは寒冷である。スウェーデンの最南端が北緯55度20分だが、こなた北方領土を除く日本の最北端は北緯45度31分。緯度10度の違いは111キロ、スウェーデンはとんでもなく北にあるわけです。
注:北方領土をなぜ除くのか!とお叱りがあるかもしれない。この場合は人間が生活で使用する水の量を考えているので、日本人が住んでない土地は対象外です。
水道使用量は気温によって大きく違う。寒冷地は少なく、暑い地域は多く、冬は少なく夏は多くなる。これは直観的に理解できるだろう。汗をかけば洗濯物も増えるし風呂にも入るだろう。場合によっては風呂に2回入ることもあるだろう。
その伝でいけば、我が家が夏冬通して使用水量が変わらないのは不思議である。
国内では北海道・東北が少なく沖縄が一番多い。これは世界的にそういう傾向にある。ただシンガポールは川も地下水もなく、隣国マレーシアから水を購入しており、ある意味水は戦略物資だから節水が徹底されているようで151リットルと異常に少ない。
とにかく日本は…もちろんアメリカやカナダも日本と同様だが…節水に努めればスウェーデン並みにできるのだろうか?
まず家庭で水はどのように使われているのか?
東京都水道局のウェブサイトで家庭での水の用途は次のようになっている。
| 用途 | 割合 |
| 風呂 | 40% |
| トイレ | 21% |
| 炊事 | 18% |
| 洗濯 | 15% |
| 洗面など | 6% |
都市や地域によって異なるが、千葉県住みの私はそう変わらないだろう。ましてや私は千葉都民だったし…関係ないか
我が家の現状を把握すると、
- 風呂
我が家の風呂の容積は334リットルとなっているが、お湯を満タンにしても無駄だ。それに我が家はエコキュートなので、お風呂を満タンにすると台所でお湯を使うときタンクが空になっている恐れがある。実際親戚の子がTDLに遊びに来た時は朝シャンでお湯不足になった。
というわけでお風呂はいつも200リットルくらいで使っている。我が家でお風呂の使用水量を今より減らすにはどうすればよいか?
まず元々が334リットルの湯船だから今より入れるお湯を減らしたら、体が全部沈まない。
湯船を交換しても200リットルがゼロになるわけではなく、規格で最小の容積が230リットルでやはり160リットルくらい入れる必要がある。となると削減量は一日40リットル、月1200リットル(たった20円削減!)にしかならず考えるまでもない。お風呂でなくシャワーにすればどうだろう?
お風呂は温まるとかシャワーは気持ちいいとかいうことは除いて、単純に使用水量だけ考えるとして、
シャワーは毎分10リットルほどお湯を出すそうです。使用時間を10分として100リットル。ひとりならシャワーのほうが使用水量が少なく安くつくでしょうけど、二人なら風呂と変わりません。3人シャワーをしたらエコキュートのタンクが空にはならないが、オールモストである。ちなみに銭湯ではシャワーは10秒もすると自動的に止まってしまう。ああいう使い方をすれば水量は少なくなるだろうけど、あれは洗ったのちに湯船につかるという前提だと思う。実際にシャワーだけの人は洗い場ではなく別のシャワーを使う人が多いし、そもそもシャワーするためだけで銭湯に来る人は少ないだろう。
- トイレ
家内は「フラッシュ水は常に大で流せと」口を酸っぱくして言う。家内は排水管などを考えると大のほうが良いのだという。貧乏人の私は、大は大、小は小で流している。
我が家のトイレは10年前のものだから、最近の形式でなくTOTO CS370というもので、大8リットル、小6リットルである(注2)。
一日にトイレを使用する回数は、女が大1,小7、男70代が大1,小7とある(注3)。 男は年齢が高くなるほど小の回数が増えるとあるが、女性の加齢による変化は見当たらなかった。ともかく上記から我が家でのトイレフラッシュ水の使用量は、
フラッシュ水使用水量=8×9+6×7=114リットル
となる。
風呂に比べて意外と多い。各国で使用する水を減らそうと、フラッシュ水の規制があるらしい
(注4)。 規制値は大小それぞれでなく、平均してのようで、算式は[大1+小(2〜5)÷(合計回数)]で厳しいところで3.5リットル、多くは6リットル以下となっている。
一番厳しいのはサウジアラビアで、シンガポールとオーストラリアが次いでいる。いずれも水のない国である。この計算では我が家は6.7リットルとなり、現在の外国の基準では少しオーバーとなる。10年間ですごく少量の水ですむようになったものだ。
日本では2021年現在標準で大4.8リットル、最新型では3.8リットルとなっている。4.8リットルにしたとき一日77リットルとなり現在より37リットル減となる。
月1.1立米、私の住んでいるところは広域水道企業団で月使用量11〜20立米のとき立米17円である。月17円削減、年200円削減になるわけだ。このための投資は便器とタンクの更新で30万くらいらしい。ウーン、それじゃ回収に1500年…検算してみたが間違いない…かかることになる。便座やタンクの寿命は40年は持たないだろう。考えるだけ無駄だ。
お金がかかるというのは、誰かが中抜きしているわけではなく、採取、加工、運搬にそれだけ手間がかかることであり、すなわち環境負荷が高いということだ。水の使用量を減らそうとトイレ設備を更新するのは地球にやさしくないのは間違いない。
どっちみち水回りとか電気関係というのは20年とか30年ほど長期間使うことが前提で、設置するときとき最新のものにするという考えであればよいと思う。
話は変わるがビルのエレベーターは表面は10年くらいでリフォームするが中のかごとか機械は25年くらい使うのが普通だ。ものを長く使うというのは環境保護の基本だろう。
さて、パレートの原則から大物から考えてみたが、どうも改善効果がなさそうだ。でも小物も一応考えよう。
- 炊事
まず今どき土のついている野菜、根菜を洗うってことはまずない。野菜はキレに洗われてパックされているものを買うので、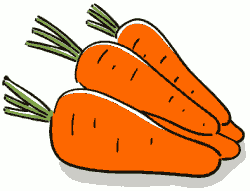 ジャンジャン水を流して洗うことはない。
ジャンジャン水を流して洗うことはない。
お米を研ぐといっても二人分2合炊けば一日分だ。コメとぎシェーカーを使っても使わなくても、元々大量の水を使っていたわけではないから大きな影響はない。最近では無洗米も4割近くなってきたという。
食器洗いは数が少ないから手洗い。お茶やコーヒーを飲んだら即手洗い。食洗器は客が大勢来たときとか夜洗うのが億劫になったときくらいしか使っていない。データによると食洗器のほうが手洗いより使用水量が少ないらしいが、我が家のように絶対量がすくないときはどうなのか?
- 洗面
私なんぞ水道の水を両手ですくってジャブジャブしておわり。家内にしても鏡の前に立っている時間は長いが顔を洗うのに使う水はコップ一杯程度じゃなかろうか?
- その他
なお、我が家はマンションだから庭も植木ももちろんなし。
ベランダには、何年も前に家内が息子から母の日にもらった植木鉢が1個、娘が結婚した時おいていったサボテンが数鉢ある。水をくれるといっても極めてわずかだ。
以上から我が家の水使用状況は次のようになる。
| 東京都平均 | 我が家 | |
| 風呂 | 40% | 48% |
| トイレ | 21% | 27% |
| 炊事 | 18% | 7% |
| 洗濯 | 15% | 15% |
| 洗面など | 6% | 2% |
| 合計 | 100% | 100% |
我が家では風呂とトイレの割合が大きく炊事が少ない。まっ大した偏移でもなくバラツキの範疇だろう。
グレタお嬢さんの国に比べて、我が家の水の使用量は倍らしいから、削減する方法を考えたが、どうもできそうにない。もちろん投資して風呂交換、トイレ交換などをすれば今より月2立米削減できそうだが、それでも一人一日177リットルで、スウェーデンの115リットルには遠く及ばない。
しかもそのためには数十万の投資が必要となり、その回収には2000年くらいかかる。企業でも家庭でも、そんな投資計画が通るはずは絶対にない。
いったいスウェーデンで一人一日115リットルは、どのようにして実現されているのだろう?
まずお風呂はやめてシャワーにして一日おきにして一日当たり50リットルになる。次にフラッシュ水は一般的な4.8リットルとして大1、小7として
フラッシュ水使用量=4.8×(1+7)=38.4リットル
注:4.8リットルは大小流した時の平均値規制である。
これで88.4リットル、残は26.6リットルしかない。
毎日シャワーも風呂も入らないけどシャンプーだけした場合、シャンプーで使うお湯の量を少なめに見て10リットルとして、残り16.6リットル。炊事でお米を研ぐとか炊くのはもう無理気味だ。食器洗いの分は一人3リットル、洗面器に水を張って3〜3.4リットル、朝顔を洗ったらもうその日は顔を洗ってはいけません。
ところで人は水を取り入れないと二日で死んでしまう。
人の必要な水の量は成人の場合、体重1キログラムにつき35ml必要だそうです。もちろん水という形でなくワインやミルクであろうと果物であろうと良いわけです。
日本人の男女合わせて平均体重は57.6kgだそうです
必要量=57.6×0.035kg=2リットル
まさか水は外出先で取りましょうとか、水道水を飲まずペットボトルの水を飲もうなんてのは主客転倒でしょう。
要するに、一人一日115リットルというのはかなり厳しそうだ。
とここまできてもう一度スウェーデンの水使用量をネットで調べた。
なんと別の資料
これによると世界平均がひとり年間68m3であり、これは一人一日186リットルになる。もちろん半分は平均以下ではあるが。
タイは一人一日80リットルとあるが、毎日行水してるしトイレ後は水で洗うから、とてもこれに収まるとは思えない。水道以外からの水はカウントしていないとか裏があるような気がする。
ともかく我々日本人がスウェーデンに負けるなとシャカリキになることはなかろう。
すべてにおいてエントロピは増大するといわれるが、物事は時とともに妥当なところ妥当な方向に進化していく。
 お盆に砂や石を入れて揺するとだんだんと落ち着いてくるようなものだ。水の使用方法も、そういう淘汰圧とでもいう力を受けて高きから低きに流れているのではなかろうか。
お盆に砂や石を入れて揺するとだんだんと落ち着いてくるようなものだ。水の使用方法も、そういう淘汰圧とでもいう力を受けて高きから低きに流れているのではなかろうか。
要するに現状が異常におかしいとか無駄が多いということはないということだ。むしろ無数のカットアンドトライによって最善状態になっているのだろうと感じる。
![]() 本日のまとめ
本日のまとめ
水は貴重だ。大切に使おう。
とはいえすべては費用対効果、そしておかれた環境によって決定される。
 新規投資をする場合は投資効果を考えなければならない。
新規投資をする場合は投資効果を考えなければならない。
……当たり前のことでした。
無理しちゃって最新設備を入れたり、環境に良いからと高いものを採用することは全くありません。
だいたい高いものは環境に悪いし、お財布にも悪いって決まってるのです。
注1 | 注2 | |
注3 | ||
注4 | ||
注5 | ||
注6 |
TOTO 水と地球の、あしたのために 5/30 追加 「水の世界地図」を読んだ。この本は水に関するいろいろなデータをビジブルなグラフで表していて面白くわかりやすい。しかしデータが古いと思われるところがいくつもあり、また出典が不明なデータもある。 参考にするのはよいが、この本を根拠にするのは危険だと思われる。 |
うそ800の目次に戻る