話をするとき、あるいは文章を書くとき、注意しなければならないことはたくさんある。
まず伝えたいことが通じることが重要であるし、意味を取り違えられないこと(誤解)ももちろんであるし、同じことを言うにも相手に納得してもらえるように相手の利益・メリットを示してセールスパーソンとなれるかどうかも大事なことだ。
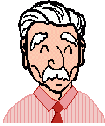 そのためには、話が聞く人に合わせてわかりやすくなければならないし、論理的につじつまが合わないとか、引用した証拠や文献が適正か、その他瑕疵があってはならないことも大事なことである。
そのためには、話が聞く人に合わせてわかりやすくなければならないし、論理的につじつまが合わないとか、引用した証拠や文献が適正か、その他瑕疵があってはならないことも大事なことである。このウェブサイトに頂くご意見にも話がかみ合わないと感じるだけでなく、おいおいそりゃ論理が違うぞとか、論点はずしも多い。あるいは反論として理屈ではなく誰それが言ったとかという理屈で押しまくる方もいる。
私の仕事の環境監査でも、駄駄こねとか、支離滅裂とか、自己満足で倫理の破綻など、わきで聞いていれば吹き出すようなおもしろいことがたくさんある。もちろん当事者である私にとってはおもしろくもなんともなく、そんな相手を説得するのは小学生に説明するようで時間ばかりかかって仕方がないのである。
偉大なる(皮肉である)毛沢東が反面教師という言葉を使ったが、どのような事例も参考になる。偽者を知るには本物を見ることが質屋の勉強だそうだが、悪い事例を知ることもヘボをしないために必要なことだろう。よって本日は話し合いあるいは議論でこんな戦法はいけないよというのを・・・
- 言葉の意味を正しく使うこと
護憲という意味が人によって憲法を遵守することであったり、改正に反対することであったりする。
日本語として間違った使い方、誤解を招く使い方はいけません。
一般的に積極的に誤解させようと使う方が多くていけません。
- 責任逃れ的表現
「・・ではないでしょうか」
あなたはそう思っているのか、いないのか? はっきりしろといいたい。
「だれそれはこう語っていた」
あなたはそれに賛成なのか、反対なのか? 旗幟鮮明にしないと私は発言を留保する。
最近、日本語に朝ひるという動詞が追加されたというが、まさに責任逃れ的言い回しは、テピィカルな朝ひるである。
監査報告で「適正に運用されていることが確認できなかった」なんて文章を見かける。
監査とは「監査基準が満たされている程度を判定するためのプロセス(ISO19011)」なのだから、結論は「監査基準が満たされていることを確認した」か「監査基準が満たされていないことを確認した」しかない。「監査基準が満たされていることが確認できなかった」はありえない。
もし監査員の力量不足なら「監査員の職をまっとうできず辞します」というのが正しいし、被監査側が協力しなかったなら「監査証拠の提示を受けず監査をまっとうできなかった」と報告すべきである。
ちなみに監査員は依頼者に報告責任があるであって被監査側には無関係である。
- 強弁、駄々こねもまずい
わかりやすく表現することは大事だが、断定、言い切り、は裏づけがないといけません。
「そういうことになっているのです」と言う方がいる。
そうなんですか? 私は「そうなっていないのです」としか言いようがない。
ご自身のルールを主張するのも結構だが、数学に例えれば公理ならともかく、定理レベルならそれを立証してほしい。法律とか少なくとも業界では慣習となっていることの説明がいる。
法律に適合しているか、反しているかという基準での議論のとき「そういうことになっているのです」ということはない。法令あるいは環境省通知○年○月○日何々によるくらいは言ってほしい。根拠なく主張してはいけません。公理(こうり)とは最も基本的な仮定で証明は不要
定理(ていり)とは公理などを基に証明された命題
- 権威を引用するのはあまりよくない
- 本当かどうか裏を取られることがある
ISO審査で言えば、「JABが言ってます」なんていえば、その場で電話をかけられたり、「UKASがいってます」なんていえばEメールで問い合わせる。もしハッタリだったら引っ込みがつかない
- 権威と思って提示したものが相手にとって権威ではなく蔑視対象であることもある。
朝日に書いてありましたなんて言っちゃいけない。2ちゃんでは朝日と反対のことをするとうまくいくと言われている ノーベル賞受賞者といってもその分野以外はただの人、平民である。
ノーベル賞受賞者といってもその分野以外はただの人、平民である。
トランジスタの発明でノーベル賞をもらったショックレーの人種主義を知っているか?
ノーベル文学賞受賞の大江健三郎は事実に反して沖縄の軍による自決を書いた。
森村誠一も旧日本軍についてうそを書いた。まあ彼はノーベル賞はもらっていないが・・ - 知識のない人に対しては効果がない
知識のない人、例えば私のような者にとって誰々が言っていたと言われても誰々を知らないのである。知らない場合、かしこまる人もいるだろうし、なんとも感じない人もいるだろう。私は田舎者なので後者である。
権威というか有名人というか、そういった人の語った言葉を引用するのは、その人が広く知られ好かれていて、かつその言が客観的で普遍性があり、更に自分の言葉よりかっこいい言い回しの場合に限られる。
- 本当かどうか裏を取られることがある
本日のダジャレ
かきまわしとは、
言い回しに対する書き回しとかきまわすことにかけただけですよ
木下様からお便りを頂きました(07.10.07)
・・・ こういうこと書き込むと失礼かもしれませんが、佐為様がこれほど生産的な方だとは存じませんでした。私だったら「もっとわかりやすい日本語で書いてね。」で終わってしまいます。 |
おお!木下様 ご無沙汰しております。お元気ですか?
そうですね、これを書いたのはお分かりと思いますが、はとぽっぽ様のお便りについてのコメントというか指導のつもりなのです。
こんなへんぴなウェブサイトでもいろいろな方からお便りを頂きます。
木下様もそのお一人でした。
私だけでなく、私が師と仰ぐ何人ものかたが後輩に表現とか論理構成についてご指導しているつもりです。それは主義主張に関わらず守るべきこと、それを満たさないと世間では相手にされないというベースラインなのです。
木下様のようにご理解いただいた方もいらっしゃいます。先輩の意図を理解することができず疎遠になってしまった方もいます。それも仕方ありませんが、その方は今までのアプローチ、表現では世の中で誤解を生むのではないかと懸念します。
今回の場合は・・・まあどうしようもないので、変わった切り口でお話したつもりです。
もっともご本人はご覧にもならないでしょうが・・
少なくとも木下様はお読みいただいたわけです。ありがたいことです。
ひとりごとの目次にもどる