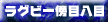|
 ※更新が分かりにくいので最新のモノを一番上にしました。 正確なハンドリング。正確なパスワーク。わき出るようなフォロー。堅固なディフェンス。
スクラムハーフ、ピショットの軽快な球さばき(ピショットがパスする姿はリコーの月田選手に似ていると思う)。スタンドオフ、ケサダの正確なプレースキック。 後半35分、アイルランドゴール前のスクラムから素早く展開したサインプレーは練りに練ったものだろう。 ジャパン戦では披露するまでもなかった精度の高いプレーだった。 この試合を見るとジャパン戦は明らかに手を抜いていた気がする。 本気を出せば、スクラムでゴリゴリ押すだけのフォワード一辺倒のチームではなく、堅いディフェンスと高いボール継続の意識に裏打ちされ、展開力のある非常に質の高いチームなのだ。 敗れたアイルランドも終了間際の15人ラインアウト、15人モールなどは乾坤一擲の気迫を賭けたプレーだった。勝つために様々な手段を考案し、それに挑戦する。これこそがワールドカップだ。 アルゼンチンの準々決勝の相手はフランス。 今の段階ではスタンドオフ、カスタニエードを欠いたフランスよりも実力は上のように見るが・・・。 イングランド対トンガ 101(13T12G4PG)-10(1T1G1PG) スコアだけを見れば驚くような結果だが、退場者が出たため、仕方のないところだ。 前半半ばまでは何とか食らいつき、好試合の期待を持たせたトンガだが、ラインアウトで完敗、スクラムも押され気味。相変わらず反則が目立ち苦しい戦いが続く。そして遂に事件は起きた。 ハイパントをキャッチしようとしたイングランドFBがまだ空中にいるにもかかわらず、パントを上げたトンガのタプエルエルがハードタックル。FBは顔面から着地した。この危険なプレーに怒ったイングランドのPRヴィカリーがタプエルエルに殴りかかり、もみ合いになった瞬間、何を思ったか、遠い位置にいたトンガのPRタウーが走り込んできて別の選手にランニングエルボースマッシュ。 ものの見事にヒットし、あわれイングランドの選手はノックアウト。このプレーでタプエルエル、ヴィカリーがイエローカードを提示された後、最後にタウーが呼ばれレッドカードで一発退場。残り50分をトンガは14人で戦わねばならなくなってしまった。まあ、トンガも懲りないというか何というか・・・。 地力に差がある上に1人少ないとあっては、勝敗は決まったも同然。その後はイングランドのトライラッシュで、こんな大差になった。後半のトンガは、日本人にとってはブルームフォンテーンの悪夢を思い起こさせるような試合内容だったが、それでも前後半で101点。後半は0-70。いったいどうすれば145点も取られるのだろう? あらためて不思議な気がする。ひょっとして、あの時のジャパンも実は1人ぐらい少なかったのでは・・・・・・。まさかね。 イングランドは、これでB組の2位を確定し、プレーオフの相手はフランスかフィジー。大差がついたせいか、後半雑なプレーが目立ったのがやや気になる。 野球の試合などでは、打線が爆発し大勝したチームが、次の試合では突然沈黙することがよくある。不安は残るが、地元トゥイッケナムだけに有利なのは間違いないだろう。 トンガ対イタリア 28(3T2G2PG1DG)-25(1T1G6PG) 試合の面白さでは今までの予選リーグの中で一番。ボールが良く動き、互いに自らの力のすべてを発揮したナイスゲーム。見終わった後、日本にもこんなゲームをしてもらいたいと切実に思った。 前半はトンガペース。相変わらず反則が多く、4つのPGを決められるが、2つのトライを奪い、18-12と6点差で折り返す。 後半12分、イタリアはトンガ22mライン内でのマイボールラインアウトからモールを作って押し込み、HOアレッサンドロがトライ。ゴールも決まり、18-19と逆転。その後もPGを決めを18-22とリードを拡げる。そして、ここから一進一退の攻防が延々と続く。 4点差のまま、ノーサイドの笛が刻々と近づいてくるなか、残り5分、トンガは決死の覚悟で攻撃を続ける。自陣からでも常に攻める姿勢を忘れず、15人が集中してボールを繋ぐ。イタリアゴールライン前まで攻め込み、長い攻防の後、遂に途中出場のFLファタニがボールを持ってポスト脇のインゴールにダイブ。ゴールキックも決まり、25-22と逆転。ここでロスタイムに突入。しかし、その直後、トンガがハーフウェイライン付近で反則を犯すと、イタリアは迷うことなくペナルティゴールを選択。 このプレッシャーの中、SOドミンゲスが蹴った50m近いロングキックは見事にゴールバーの上を通過し、同点。これでノーサイドかと思われたが、まだプレーは続いた。トンガ最後の攻撃。連続支配し、イタリア陣10m付近でのラックから出たボールを、FBトゥイプロトゥが約45mという距離にも関わらず、乾坤一擲のドロップゴール。トンガの夢を乗せたボールは高々と夜空に舞い上がり、ゴールバーを越えて見事に成功。そしてここでノーサイド。 歓喜に沸くトンガ陣営。観衆からは惜しみない拍手が送られ、アナウンサーは"amazing goal"を連呼。ラグビーの醍醐味を堪能した素晴らしい試合だった。トンガは次のイングランド戦でもかなりの好勝負を演じられるかもしれない。イングランドが気を許せば、史上最大の番狂わせが起こる可能性もゼロではないような・・・。 南アフリカ対スペイン 47(7T6G)-3(1PG) スペインの素晴らしい戦いぶりに感動を覚えた。 客観的に見て、スペインは日本より弱いチームだ。国立競技場での壮行試合を見ても力の差は明らか。それでもこの試合では、体を張ったディフェンス、時折見せるビッグタックルと分厚いフォローで南アフリカに簡単にトライを許しはしなかった。 南アフリカのボール保持率が90%以上、前後半を通じてほとんどスペイン陣で戦ったことを思えば、このスコアは驚異的だ。スペインの最後まであきらめないディフェンスに手を焼いた南アフリカは、後半になると、温存していたファンデルベストハイゼンとスキンスタッドをたまらず投入。ゴール前ではなりふり構わぬスクラムトライさえ見せ、場内から激しいブーイングを浴びていた。天下の南アフリカが20回以上ものノックオンをしたのもスペインの厳しいプレッシャーのせい。 スペインの選手たちも試合後は満足そうな表情だったし、観客も満足したことだろう。翻って、今の日本が南アフリカと戦った場合、この点差に抑えられたかどうか? ここまで懸命なディフェンスを出来たかどうか? それを考えると、スペインの頑張りに感服するとともに、日本の不甲斐なさに改めて失望を覚える。 オーストラリア対アイルランド 23(2T2G3PG)-3(1PG) 結果的にはノートライで完敗の形に終わったが、アイルランドの健闘に拍手を送りたいような試合だった。 ”格下のチームが実力差のあるチームと闘う時、どうすればよいのか”もこのアイルランドやスコットランド、あるいはトンガなどが教えてくれる。とにかく死に物狂いのタックル、骨惜しみしないフォローなしには試合にならない。 実力差はあっても、ゴール前でそう易々とはトライを与えないのが、レベルの高いラグビーだ。 注目選手に挙げたウッド選手も大活躍。特に、後半ゴール前に攻められながらターンオーバー。ボールを奪い返した彼が、オーストラリアの選手をステップで2人交わし敵陣にロングキック。そしてそのボールをロングチェイスした場面など、まったく彼の運動量には感心させられる。日本にも早くこういう選手(特にフォワード)が出てこないものだろうか? 解説の宿沢氏は”物足りなかった”と語っていたが、私はそうは思わない。ディフェンスの厳しい好ゲームだったと思う(特にアイルランドにとっては)。 日本対サモア 9(3PG)-43(5T3G4PG) 「やはり無理か・・・」と「もう少し何とかなるはず・・・」という気持ちが複雑に交錯した。 敢えて結果論で言うなら、今年からパシリムにサモアが参加したのは不運だったのかもしれない。そこで、勝利を治めてしまったことも・・・。 冷静に分析すればプロとアマチュアの差。24時間ラグビー漬けに浸れるプロとそうではないアマチュア。大きな違いだ。プロならば怪我など許されない。だから当然体作りから入る。サモアの選手と日本の選手。例え身長体重が同じでも、サモアの選手はみな分厚いまでの筋肉という鎧に覆われている。 そしてプロは同じ過ちは二度と繰り返さない。 パシリムでサモアを敗戦に追いこんだジョセフのサイド攻撃は徹底的に研究されていた。 彼が持ち込んだボールでノットリリースを取られチャンスをフイにしたことが4度。 もちろん”彼を使うな”というのではない。 ただ、先日のシンポジウムで慶応の上田監督がいみじくも言った「ジョセフを止められた時、どうするのか?」という不安が見事に適中してしまった。その場合の手段が見えなかった。上田氏の慧眼だったと言うべきなのだろうか? 松田の故障交代にしても、そういった万一の場合を想定してメンバーを組むのが監督のはず。 「練習でもFBをやってないし、ついついWTBの位置に体が動いてしまった・・・」と語る急造FBの大畑ではあのディフェンスも致し方ない。 サモアの凄まじい当たりの前では、一人や二人の負傷者が出るのはある程度予想されたこと。 なぜ、平尾、或いは三木をリザーブに入れて置かなかったのか? 彼らでは心許ないというのなら、何故大畑や増保にFBの練習をさせておかなかったのか? 平尾監督の采配に疑問符が付くのも事実だ。 それでも、この試合、すべてが日本にとって悪い方向へと働いた一面もあった。 縦も横も狭い競技場。嵐のような雨と風。もちろん、それはマコーミック主将が言うようにイコールコンディションには違いないが、スピードを身上とし、オープンに展開する日本にとっては明らかに不利な条件だった。その上、何故か日本が風上に立った時、風は少し弱まったようにも見えた。 救いは、あんな負け方をしても常に前向きの発言をするマコーミック主将。 チャレンジを身上とする彼の体に染みついた精神なのか・・・。 彼がキャプテンとして存在する限り、後ろ向きの発想はありえない。 それを信じよう。残り二試合・・・。 ニュージーランド対トンガ 45(5T4G4PG)- 9(3PG) 点差は開いたがなかなかの好ゲーム。 トンガの頑張りが目立った。ニュージーランドが何度かゴール前に迫っても、凄まじいばかりの体を張ったタックル(日本のレフェリーなら安易に「危険なタックル」と取ってしまうような)でなかなかゴールラインを割らせない。 ロムーの個人技やクロンフェルドのサポートの前にトライを奪われはしたものの、最後まで当たり負けせず、時折見せ場を作って、今大会の本命ニュージーランドに楽な戦いをさせなかった。(この健闘を見ると日本ももう少し何とかならなかったのか、と思った・・・) ニュージーランドは初戦という事もあるため、こんなものか。 交代出場したSHケラハーのスピードに乗った走りと前大会の活躍を思い起こさせるロムーのぶちかましが印象的だった。三洋電機に所属するトンガのセミィはいつのまにか金髪になっていた(というよりトンガの選手は全員髪を染めていたような・・・)。SOブニポラも相変わらずの好プレーを見せていた。途中、第一列がいなくなり、一度交代したWTB(!!)がフッカーのポジションに就いて場内の喝采を浴びていた。 ウルグアイ対スペイン 27(4T2G1PG)- 15(5PG) 誤解を恐れずに言えば、レベルの低い年の早明戦のような試合。かたやスクラムのごり押しだけが売り物。かたや、積極的にオープン展開するもののノックオン、パスミスのオンパレード。ワールドカップとして見るレベルではなかった。スペインのノックオンだけでも20回ぐらいあった。 で、結果的にスクラムで圧倒した明治が勝ったということ。 後半G前で延々と10分以上もスクラムが組まれる様を見ているのは非常に退屈で、やる方はともかく、見る立場としては、ああいう試合展開はいかにつまらないかというのを再認識した。(全然関係ないが、ウルグアイってユルグアイと発音するんだね。なんかお腹を壊したような変な気分…。またまた関係ないが、ユルグアイのFBの走りはサントリーの永友選手の走り方にそっくりだった) フランス対カナダ 33(4T2G3PG)- 20(2T2G2PG) 前半カナダも健闘したが、フランスの順当勝ち。 三大会連続出場になるベテランLOベナジが相変わらずの強さを見せ、攻守に大活躍。期待のSOカスタニエードは、時折その片鱗を見せたものの、まだ出来は完全ではないようだ。この試合でもちょっと怪我をしたようで、彼の回復振りが今後のフランスのカギを握りそう。 カナダはペナルティをもらうと、ほとんど速攻。パシリムでの日本を参考にしたような戦い振りだった。が、やや回しすぎたか? 選手ではFBスチュアートのハードタックルと超ロングキックが目を引いた。ワラビーズのノリエガにそっくりなPRスノウも頑張っていた。前半終了間際、攻守の要のSOリース主将が交代したのが響いたか? 局面でのプレーの精度の差が得点の差となり、あと一歩及ばなかった。 結局、「五カ国対抗」と「パシフィックリム選手権」のレベルの違いが勝敗を分けたような試合だったと思う。 フィジー対ナミビア 67(9T8G2PG)-18(2T1G2PG) フィジアンマジック炸裂。 ワールドカップ前は、ディフェンス面を不安視され、スタメン出場さえも危ぶまれていたセブンズの王様SOセレビが、その変幻自在のステップとパス回しを存分に披露。格下のナミビアから立て続けにトライを上げ、67点を奪い圧勝。 ナミビアも最後まで切れずにしぶといディフェンスを見せたが、やはり力の差は明らか。(ただし、フィジーの二つ目のトライは明らかにミスジャッジ。インゴールに届いていない。これは不運だった)フランス、カナダからも格好の草刈り場とされそうだ。そうなると、やはり3位の最高チームはこのプールから出ることになり、日本は苦しくなる。 ウェールズ対アルゼンチン 23(2T2G3PG)-18(6PG) 開会式後の第一試合。 地元ファンの期待を一身に担って登場したウェールズだが、そのプレッシャー故か、全体的に動きが重い。開始早々、ニール・ジェンキンスが、左中間40m程の彼にとってはイージーなペナルティキックを外したことにもそれは現れていた。前半終了間際、FLのトライで波に乗るかと思われたが、その後もアルゼンチンの早い出足の前に大苦戦。自陣からの展開で、1トライを加えたものの、SOケサダが確実にPGを決めて追いすがるアルゼンチンに最後まで食い下がられ、5点差と薄氷を踏みながらの勝利。地元開催というプレッシャーは予想以上のものらしい。五カ国対抗の後半戦や、その後の連勝街道驀進中の試合とはまるで違ったチームになっていた。 ウェールズの本来の力はこんなものではないはず。 今後、どこまで勝ち進めるかは、プレッシャーを克服できるか? にかかってくるのかもしれない。 アルゼンチンは良く健闘した。ケサダのキックも見事だったし、CTB陣、FL陣のディフェンスも素晴らしかった。 両チームともかなりキックに頼った堅実な試合運びになったのは、降り続く雨の影響も多少はあったか? 翻ってジャパンに当てはめれば、やはり雨が降ると勝利への道はかなり厳しくなる。 |
MAIN