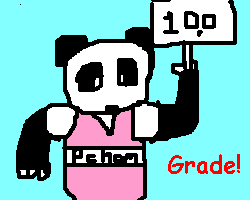
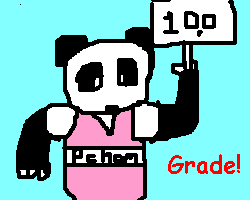
監督 スティーブン・スピルバーグ 主演 トム・ハンクス、トム・サイズモア、エドワード・バーンズ、マット・デイモンほか
(10月1日までの採点は、『プライベート・ライアン』に掲載しています。
まず最初に、そちらをごらんください。)
キリヤマ(10月8日)
「感想文の感想文」になってしまいますが...。shiro(10月7日)
まだそんなことを言うかと思われるだろうけど、私の疑問はやはり「凄惨な戦い を、自分が戦場にいてそれを目の当たりにしていると錯覚させるほどリアルに再現 して見せる意図は一体何なのか」ということと、「それを見ることに一体どんな意 義があるというのか」ということです。戦闘の様子はひたすら圧倒的で冷徹で、見 てる側に「戦争はこんなにバカバカしいことなんだ、無意味なことなんだ」と感じ るスキも与えない。そんなウェットな感傷はお断りだと言わんばかりのように感じ ました。
ここまで徹底的にやっておいて、ただただ見せることが映像作家の意図するとこ ろ、どう見て何を感じるかは観客次第、ってことはないですよね...。
皆さんの感想を読んで初めて、戦闘の合間合間の兵士たちの表情や言葉の端々に 細やかな感情が織り込まれ、表わされていたようだとわかりました(笑)。私には それに気づく余裕はまるでなかったどころか、そういう場面の記憶があいまいなの です。砲弾で吹き飛んでしまったんでしょうか。戦闘の場面とそれ以外のバランス が、私には悪すぎたみたいです。
この映画の主役がアメリカ兵なのでアメリカに限定して話をしますが、「体験の 再認識」の件を読んで思ったのは、アメリカ人 − 少なくとも軍人・元軍人 − に とって戦争というのは、(それがどこで、誰が起こしたものであろうと)必ず「ア メリカの自由と独立と正義を守るため」の誇り高い行為であって、それが悪いこと だとか繰り返してはいけないことだとは考えないみたいだということです。D-Dayの 修羅場を生き残った人たちが、あのあまりの凄惨さ、不条理さを思い出したくなく て、その記憶を胸の奥深くにしまいこんだまま今日まで生きてきた。それを責める わけにはいかないかもしれない。しかし第二次大戦後も朝鮮・ベトナム・湾岸と同じ ことが繰り返されてはその度に多くの若い人たちの命が失われていることを考える と、いつまでたってもその「犠牲」は無意味であり続けるんじゃないかと私には思 えます。
私は戦争でこんなに辛い経験をした、と話す時、そこに「アメリカの名誉のため に戦った私と今日の自由で繁栄するアメリカ」だけではなくて、「戦争なんて愚か なことだ」というメッセージが伝えられていれば、少しは違うことになっていたの になぁ、と思う。
もし「戦争は悪いこと」なら、過去にそれに関わっていたことはあまり他人には 話したくないだろうけれど、「戦争を繰り返すのはバカバカしいことだ」と思える のなら、どんなに嫌なことも伝えていくことが必要だと思う。これはもちろん日本 人にも求められていることですが。
気になったのは「軍隊を持つことがまるで悪いことであるかのように教育されて きた今の日本の人」とか「生半可な平和意識に無意識に甘えてしまっている日本人 」といったように、"戦争をしない日本" を良しとしないような言葉です。たとえば 日本が毎年、どれだけ莫大なカネを米軍のために使い、土地や施設や人材を提供す ることで米軍の戦争行為の一翼を担っているかを考えれば、"戦争をする国" に対し て負い目を感じることはないと思います。
世界中どの国も軍隊や兵器を擁していて、その上でしか平和(戦争のない状態) は有り得ないと考えるのが正しいのでしょう。だからこれは理想主義者の寝言だけ ど、軍隊なんてないほうが良いに決まっている。私は軍隊が災害救助に活躍するこ とはわかっているし、阪神大震災の発生した数分後には米軍が救助活動を申し出た ことも知っています。でもやっぱり軍隊はあくまで殺人と破壊と諜報活動のために 訓練されている人間の集団であって、その本質は戦争状態にあってもなくても変わ ることはないと思います。
「軍隊はいらない」と言う人が「何をそんな絵空事を」とバカにされて笑われて いるのをテレビで見たことがあります。ヤだなぁと思いました。
沖縄県民としては、そこらを歩いている若い米兵のお兄ちゃん達が、この映画の 「若い兵士が虫けらのように簡単に殺され、ゴミのように海岸に打ち寄せられてい る」場面なんかを見て、名誉の戦死って言われたって、あんな人間の尊厳のかけら もない不様な死に方じゃないか、ヒーローだの America remembers. だの言われた って嬉しくないやい、とでも思ってくれたらいいかな、なんて思います。
映画には直接関係ないことばかり書いてすみませんでした。
はじめまして。私は星5つつけます。ねこ娘(10月3日)
映像的な凄さとは別に、私がこの映画に見たテーマは、映画中の二つのせりふに集約されています。
"Fubar"
"Earn this"
一人を助けるために八人が犠牲になるのは、ヒューマニズムでしょうか。
とんでもない。そんなことに全く意味は無いのです。だからf**ked upなんです。自分の命が無意味な作戦に投入されていて、自分ではどうすることも出来ない。もちろん登場人物達は何とかそこに意味を見出そうとはしますが、彼らの心の底には既に諦めと絶望があります。偽善のように聞こえるせりふも、絶望の淵を覗き込んでいる自分を慰めるために吐いているだけで、自分たちだってそんなこと信じちゃいないんです。
けれど、彼らは同時に完全な絶望に対してわずかな疑いを持っている。
本当に無意味なのか。実は何かあるんじゃないのか。それを希望と呼んで捜し求めるには、悲惨な場面を体験しすぎてしまった。けれど捨てることも出来ない。非常に宙ぶらりんのまま、彼らは最後の橋の攻防戦に巻き込まれます。
そして最後の "Earn this"。「俺のやってきたことに意味があったかどうかは分からない。だがもしあったとすれば、その意味を引き継いでくれ」というふうに聞こえました。ライアンの立場から見ると、「彼らの死に意味があったかどうか、それは自分のこれからの生き方で証明される」ということになります。そしてそれこそが、戦った世代から我々若い世代への重いメッセージ---過去の戦争の犠牲と惨禍、それを意味あるものにするか、無意味なものにするかはこれからの世代にかかっているのだ---なのではないか、と私は受け取りました。
ところで字幕ではこのせりふは何と訳されていたのでしょう?
プライベートライアンみてきました.reina(10月3日)
なんだかすごい迫力でやられてしまった感じです.
あまりにも激しくて、兵士達が静かに語り合う場面では眠くなってしまうような..動と静がはっきりしている、まさに戦争映画ですね.
ショッキングな場面もけっこうあって、私の前のプロレスラーのようなでっかい男性は、はじめの30分で退場してしまいました.
斜め前の若い男の子も、いったん退場してました.
どんなにリアルに当時を再現していたとしても、あくまでも映画の一場面としか思えなかったのは、私だけでしょうか.
戦争を知らない私がみても、当時の兵士の気持ちにはとても近づけないなー、という感じ.1/100万も感じられていないと思います.
唯一、トム・ハンクスの表情が、言葉にはならない複雑な感情のすべてを語っているような気がしました.
彼の表情は「フェラデルフィア」「フォレスト・ガンプ」などと同じではなかろうか..しかし、戦争という背景に浮かび上がる彼の表情は明らかに今までとは違う「どうにもならない」感情が、伝わってくるから不思議です.そのへんが、この映画のねらいか!?
結局、ひとりのために8人が犠牲にならなくてはいけないのか、その答えはどうでもよく思えたし、期待していたほどの大作ではないような気もするけど、なにか言わずにはいられない作品ですね.
星は、★★☆です.
追加
戦争映画を、まじめにみたのは初めてなのですが、感動というか、たくさんの人が死んでいく、その意味なさをあらためて痛感しました.
現実、いまも内戦が続いている国がありますよね.地雷で手足を失った人の映像をみると、こんなにたくさんの人を傷つけて、何が不満なの?何に勝ちたいの?と、思ってしまいます.
私はサンドイッチのシーンをまったく覚えてないんですが(スピルバーグごめんね)、多分誰だって食欲をなくすような体験をしたけどそんなことに参っていては敵に撃たれてしまう、負けてしまう、ということが言いたいのではないでしょうか?狂気の中にある日常のことがよけいその場のおかしさを強調しているのでは?いちいち食欲を失っていたら戦争に勝てません。それを教えることによって、どれだけ戦争ということが気違いじみたことなのかを見せてくれていると思います。それに、ただの小道具ではなく、実際にそういう状況だったのでしょう。パンちゃん(10月3日)
余談ですが、この撮影にはいる前にトムハンクス以下8名(だったっけ?)は軍に入るときに行われる"Boot camp"を体験したそうです。軍に入りたいな、と思っても、この特訓が嫌で諦める人もいるくらい。また、この特訓に耐えられずにやめる人もいるくらい大変なものです。俳優だからといって楽な訓練を受けたのでは、兵士らしさが出ないと思ったトムは途中で全員がやめようといったにもかかわらず、続けるよう説得したそうです。この中に入れなかったのがマット・デーモン。マットも行きたかったようですが、行かせてもらえませんでした。このため、撮影が始まると「あいつだけ楽な思いをして。。。」と他の俳優たちは彼等とマットの間に距離を置いたそうです。それが、自分の命を犠牲にしてまでライアンを助けにいった兵士たちとライアンとの間にできた溝になったんですね。撮影に入って初めてなぜ自分だけキャンプに参加できなかったがよくわかったとマット君が言ってました。やっぱりスピルバーグはすごいと思うぞおおお。でもジュラシックパークは好きになれない。
私はサンドイッチは全く違った印象をもった。麗奈どんだよ〜ん(10月2日) reina@osula.com
自分たちは激しい戦闘をくぐりぬけ、やっと生き延びた。こいつらは、あの惨状を知らず、のうのうとうまいものを食っている、コーヒーものんでいる。ばかやろう。
でも、軍隊だから、そんなことは言わない、言わずにぐっとこらえる--見たいに感じたけど、なんだかトム・ハンクスの表情が理解できなかった。
そうか、食欲をなくしていたのか。
通訳役の兵士が最後の最後になって銃の引き金を引くシーンは、あしたかさんのいうように、印象深い。
*
一つ一つのシーンについて感じたことを比べてみるのもいいかもしれないなあ。
これだけの大作だ。一回じゃ、印象なんか言えない。
私は、フランスの少女が泣きながら父をぶつシーンが大好き。思わず笑ってしまったけれど、子供の気持ちがはじけていた。
ほかのシーンとうまくつないで考えることができないんだけれど(つなげて考えなくていいのかもしれないけれど)、本当に忘れられないシーンだ。
またまたまた書いてます。(笑)パンちゃん(10月2日)
確かに最初の30分とその他をつながって考えてはいけないかもしれない。
あれはただ単に、ノルマンディー上陸=「勝利」としか教わっていないアメリカ人たちが、自分のおじいちゃんたちがどんな体験をしたのかわかるように作られたのではないでせうか?私はスピルバーグをものすごく尊敬してるので、良く見てしまっているのかもしれないけど、シンドラーとライアンではやっぱり全然違うと思います。自分の親戚が殺された、それも宗教がユダヤ教であるという理由だけで虐殺されたスピルバーグだからシンドラーには普通以上の思い入れがあっただろうし、当然キャラクター描写も本当に気持ちが伝わるものになったと思う。それに、シンドラー本人自体が、心のある人間だった。反対に「ライアン」に出てくる人間は本来の「キャラクター」が戦争に置かれて消えてしまった人達ばかりだ。その「人間らしさ」の欠如がかえって、彼等をリアルにしていると思う。
アメリカではこの映画を見て初めて第2次世界大戦について話した元兵士達がたくさんいます。もう皆おじいさんになってますが、この映画見て新たに自分達が経験した事がどのように大変なことであったか再認識したようです。軍では映画公開後特別にカウンセラーを設け当時戦争に言った人達の世話をする施設を作りました。実際に公開後すぐにたくさんの電話が絶えなかったそうです。あのような経験をした人達が祖国に戻ってきたとき、前とはまるっきり別人になってしまっているんですね。この映画を見て、なぜ別人になってしまったかが良くわかったように思えました。
体験の再認識か。うーん、やはりアメリカから見るのと日本人が見るのとでは違う。はっとした。あしたかのつもり(★★★)(10月2日)
体験の継承という視点から見つめなおせば、麗奈さんのいう「普通の人」という表現もよくわかる。トム・ハンクスが「元教師」という設定に驚くというのも理解できる。
最初と最後のアメリカ国旗のアップの意味もわかる。国旗の背後には、こういう歴史がある。歴史をきづいた人々の苦闘がある、ということを明確に伝えようとしているのだと思う。
しかし、そうか。アメリカでは「ノルマンディー上陸=勝利」という感じで教科書は書かれているのか。体験は風化しているのか。
日本の教科書はどうかな。「ノルマンディーの上陸=第二次大戦の転換機」という、とらえ方だろうか。そこでは、アメリカの兵士がどんな体験をしたか、というのはアメリカ以上に想像しないことだ。たぶん、全く想像しないと思う。
(それはパンちゃんだけ、という指摘が聞こえそう。戦争放棄の憲法で育った私たちは「戦争=悪」という視点で戦争映画を見てしまいがち、と書いたら、「私たち」ではない、と指摘されました。)
私はスピルバーグはとても好き。でも、この映画では好きになる部分が見つからなかった。
だから、みんなからどこが好きだったか教えてもらいたい。それがわかったら、もっとスピルバーグが好きになれる。そう思って、何度も何度も書いてます。
麗奈さんの今回の書き込みで、ちょっと好きになった。パンちゃんの採点は★★★に変わった。麗奈さん、ありがとう。誰かもう一個★を増やして。
私の感じたところは「フーバー・・・」といって溜息をつく兵士の表情がこの映画での戦争のイメージかな・・と思います。ダグラス・タガミ(10月2日)
任務を実行するミラー隊長のその理由も戦争を物語ってますね。「教師だった事を誰も信じないくらい顔が変わった。 国の妻さえ・・・・・でも胸を張って、ライアン二等兵を母親の元へ生還させた!と自身をもって言いたい」 とゆう、助けても自分が母国へ帰れる訳でもないのに・・。 自分の参加した戦争が何の為か、理由は自分で付けるしかない状態。
アパムは顔が変わる過程にある兵士の役でしたね。
墓穴をほってから、殺されそうなドイツ兵を助けようとして、でも、そのドイツ兵は自分の名を叫ぶ仲間をナイフで突き刺して殺し、階段でヘタってる自分は見逃してくれる、が、最後はホールド・アップしながら自分の名前をニヤついてつぶやくそのドイツ兵を射殺してしまう。
この時、すでに顔が数段階変わっている。 戦闘を重ねつつミラーの様になって行くだろう事を示唆しているのかも・・。
ライアン救出の任務を渡される直前、ミラーが積み上げられたハンバーガーを見つめてる場面がありましたね・・・。
細かい場面に、まだまだたくさんメッセージが写しこまれてるかも知れません。 リピーターになりそうです。
こんにちは。ダグラス・タガミです。
今回のライアンは、すごいですね。
私は今考えると、オマハビーチの戦闘シーンで脳みそがしびれて、 後半の内容は、ただ観ていただけでした。
しかし、変だなー。と思うのが、 オマハの死闘を乗り越えて中継基地(?)にたどり着いたときに、 ”サンドイッチ”等のアップシーンがありました。
死の淵から這い上がって、すぐにあのシーンだけは納得できませんでした。
(関係ないですが、私もバイク事故の大怪我で死にかけましたが、 そのときは、一週間ほど食欲なんてありませんでした。)
あのシーンに何を言わせたかったのか今でも判りません。
戦闘との対比として使ったのならば、幼稚じゃないかなと思っています。 私が泣けなかったのは、単にミラー大尉に感情移入できなかったからです。 多分パンちゃんの言っていることが、私が感情移入できなかった理由の ように感じています。
でも、今更戦争映画で、これだけ見た人に影響をあたえるものを作る スピルバーグは、すごいですね。確信犯でしょうけど。
(試写会での高倉健さんのコメントも「すごい」の一言だったらしいです。)