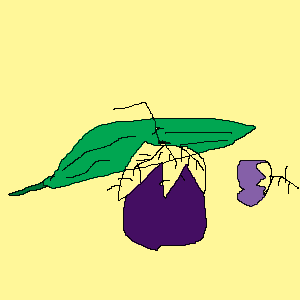 俳句の快楽
俳句の快楽俳句は、「これならわたしにもつくることができると、たやすく思いこませる特質をもっている」と、ロラン・バルトは、『表徴の帝国』(宗左近訳 ちくま学芸文庫、太字強調はすべて引用者)の中の「意味の家宅侵入」と題する章で書いている。また、次のようにも……。
「俳句は羨望をおこさせる。その簡潔さが完璧の保証となり、その単純さが深遠さの確認となるような(簡明さこそが芸術の証明だとする古典派的神話、即興にこそ第一の真理があるとするロマン派的神話、この二つの神話のせいで、こういうことになるのだが)さまざまな《印象》を、鉛筆を手にしてそこかしこで書きとめながら生のただなかを散歩したいと夢みなかった西洋の読者がなん人いるであろうか。俳句は近寄りやすい世界である。そのくせ、じつはなにごとも語ろうとはしない」
「俳句の《不在性》(旅に出た主人の不在、現実ばなれした精神、この二つの場合をあわせての不在性なのだが)、これが人をそそのかす張本人となって、家宅侵入を、貪欲の大罪を、意味の貪欲をまねきよせる」
また、俳句の評釈についても、正確に評している。
「俳句について語ることは、純粋に、ひたすら、俳句を繰り返すことだけのこととなるであろう」
われわれは、ソシュールの言う記号の惰性の世界に埋もれて、俳句に関するイメージを拭いさることができない。さまざまな通俗化した言説に逆らって、みずみずしい言葉の体験として俳句の快楽に身をゆだねることができない。しかしたとえば、フランス語に訳された芭蕉の次のような句が、ふたたび日本語に訳されたのを目にする時、そこには西洋の「記号」をまとった芭蕉がおり、かえって、「なるほどそういうものか」と新鮮な気持ちになったりする。
たとえば、こんな句。
すでに四時……
わたしは九回起きたのだ、
月を賞でるために。
(こゝのたび起きても月の七つかな)
あるいは、こんな句。
なんと素晴らしい人であることか、
稲妻を見て、
『生ははかないものだ』と思わぬ人は!
(稲妻にさとらぬ人の尊さよ)
(2004/5/20)
上記の文章を見た(読んだというよりも)、プリミティブなアタマのオッサンが、プリミティブな人間にありがちのプリミティブな問い(嫌がらせが目的ではあるが)を筆者が持っているある掲示板に書いてきた。ほうっておいたが、あまりもしつこいので、(ふーむ。ネット上には有象無象がいる。ネット上で文章を発表している以上、そういう「プリミ系」にも対応しなけらばならいかもなー……と思い、上記の文章をもう少しわかりやすく、解説してみる。
まず、そのオッサンは、「おまえの文章は全編引用だけだ、ドロボー!」と言うのである。そうかなー……、ま、多少、引用は多いような気がするが、それは、冒頭に文献を紹介しておかなければと思った結果なのだし、第一、論文的に厳密であろうとしたら、自然、資料を明確にすることは必要な態度である。引用をまったくせずに、上記引用箇所を、べつの言葉で言いかえることもできるが、それでは、厳密さからはやや遠のくし、本稿の目的とするものとも違ってくる。つまり、身辺雑記をたらたら書き流したエッセイのようなものであれば、それほど、「出典」にこだわることもないだろう。
そのオッサンの場合、まず、「引用」と「盗用」の区別がまるでついてない。「引用」とは、広大なテクストの海から、自分が書こうとすることを「証明」する「資料」として提出するものである。また、「盗用」とは、他人の作品を、さも自分の作品であるかのように人前に提出することである。
だから、ゴダールの映画ではないが、ある意図のもとに、古今東西の作家や思想家の文章が、「切り取られ」、「ある順序で」ただ並べられているだけでも、それは、なんらかのことを言わんとする「作品」となりうる。それにしても、上記拙稿を「全編引用」だけというのも、ひどく乱暴な言い方である。
試しに、引用部分を着色し、字数を数えてみた(プリミ系をオッサンは、「数えた」と言うと、ほんとうに指折り数えたと思うだろうが、エディタ上で、数えたい文字を「選択」し、「文書フォーマット」をクリックすれば、全角と半角の合計文字数およびバイト数が出てくる)ら、「」部分をおまけしても(笑)、引用=506字、全字数850字で、引用部分は、全体の59.5%。約60%となる。
ソシュールの言う記号の惰性:ソシュールという「言語学者」は、本を一冊も書かなかった人である。だから、「ソシュールの言う」とは、ソシュールが、その「講義」で言っていたということであり、その記録は本になっているが、これにはいろいろ問題があったことは、現代思想に関心のある人なら知っている人もいるだろう。しかし、このソシュールという人の考えたことは、その後の世界の思想を大きく転換させるもととなったものである。これに関しては、丸山圭三郎という人が研究所を出していて、非常に明確にソシュールの思想を解説している。それを簡単に言ってしまえば、世界には、まずモノが存在して、その名前があるのではないということである。つまり、言葉とともに、そのモノが存在する。言葉があるから、モノがあるのである。そして、「記号」とは、ある言葉が、ある社会なり集団の中で持つ意味である。たとえば、「芭蕉」という言葉は、日本という社会では、ある一定の意味を持つ。そういう意味は固定化され、普通、疑ってもみない。それを、「記号の惰性」と読んだのである。しかし、注意しておきたいのは、「記号」ということを言い出したのは、ロラン・バルトであって、ソシュールではない。バルトは、ソシュールの考えを借りたのだ。そして、そういう固定化した記号を疑えと言ったのだ。
しかし、バルトは、日本に一週間滞在して、日本についての印章記のような『表徴の帝国』を書いた。その彼にとっては、日本は、「記号」が固定化されていないように見えた。しかし、実際は、複雑な記号が絡み合っていただけなのである。
西洋の「記号」をまとった芭蕉:プリミ系オッサンは、「え?西洋の記号をまとった芭蕉ってどこにいるの?」と書いていた。この人には、レトリックが通じないのか(笑)? 「西洋の記号まとう」とは、すなわち、西洋社会の意味づけのなかで「読まれた」芭蕉である。だから、元禄4年(1691年)芭蕉47才(私は常に満年齢を使う)の時の句、
九(ここの)たび起(おき)ても月の七ツ哉
の仏訳からの和訳が、
すでに四時……
わたしは九回起きたのだ、
月を賞でるために。
のようになり、オリジナルの句とはかけ離れたものになる。実際、上の和訳の仏語が、どのような文章だったかは、『表徴の帝国』のオリジナル・テクスト、『L'empire des signes』が品切れ状態なので未だ入手できないでいるのでよくわからない。ただ、全集をWeb紀伊国屋の洋書部に注文してあるので、そのうちわかるとは思う。
オリジナルの芭蕉の句の解釈としては、芭蕉はこの3年後には死んでしまうのだから、この時も、すでに「寝苦しかった」のではないか。9回というのは、正確な回数を数えていたのではなく、頻度の多さを言っているのではないか。何度も起きてみるのだが、まだ外は暗い……空には、月が白々と出ているばかりだ。でも、もう七ツか、いや、まだ七ツか……。七ツとは、「七ツだち」という言葉があるように、旅に発つ時の時刻である。ほんとうに、「月を賞でるために」九回も起きたのか?もしそうなら、
九たび起きては月の七ツ哉
になっていたのではないか? とにかく、挙句の助詞の「も」には、時間の感覚、それも、「長く思う時間の感覚」があり、それを、仏訳→和訳は、落としているように思う。
「芭蕉」という日本社会の意味=記号から解き放たれ、西洋の意味=記号をまとわされている「詩人」がそこにいる。この「詩人」は、すでにわれわれの知らない人だ。
「なるほどそういうものか」と新鮮な気持ちになったりする。:つまり、西洋人にとっては、「芭蕉」は、「俳諧」の「宗匠」でもなければ、僧形の老人でもない。芭蕉は、ただのBashoなのである。そういう人が、
すでに四時……
わたしは九回起きたのだ、
月を賞でるために。
という「短詩」を作った。その詩を読む西洋の読者には、連句の宗匠であるも、弟子たちのことも、「旅を住処」としたことも見えない。何も持たず、ほとんど乞食のような格好をし、旅先のパトロンの家々に泊まったり、施しを受けたりして暮らしたことなどは考慮の外にある。ただ、ある詩人がいて、「月の賞でるために九回起きた、そして、その九回目が朝の四時……」というような詩を書いた、それだけである。つまり、俳句というものを意味に転換してしまっては何も残らない。「なるほどそういうものか」と新鮮な気持ちになり、もう一度、なにげなく見過ごしていたオリジナルにあたる──。
九(ここの)たび起(おき)ても月の七ツ哉
じっとこの句を見つめる……。そのとき、いかなる光景があなたの目に浮かびますか?
★つづく★
(2004/9/3)