�L�v�Ȋ����ʂƂ������t������B
�����ԑO�̂��Ƃł��邪�AISOTC�ψ��ɒ��ځu�L�v�Ȋ����ʂƂ����T�O������̂ł��傤���H�v�Ƃ��f���������Ƃ�����B���̕������ȕ��ŁA�����������������������ɎO���������Ă��_�����f�����B
|
�L�v�ȑ��ʂ�����A���v
�ȑ��ʂ�����̂��낤���H 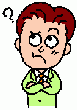 |
���������Ƃ���Ȃ��̂�����킯���Ȃ��ƍl���Ă��܂����̂ł�����Ĉ��S���܂����B
�������A�L�v�Ȋ����ʂƂ������z�����������Ƃ����O�ɁA�L�v�Ȋ����ʂ����l�X�͂������������ʂƂ͂Ȃ�Ƃ����߂炦��������Ă���̂ł͂Ȃ����H�@����Ă��邩��L�v�Ȋ����ʂƂ������z���łĂ�����A�l���L�v�ȑ��ʂȂǂƌ��̂��Ɖ��ɂ܂���Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӂ��ɍl���Ă���܂��B
���Ƃ��A�p���������Ǝ҂Ƃ����̂������ʂɎ��グ�Ă����Ƃ͌��\����܂��B
�͂����Ĕp�����Ǝ҂Ƃ����̂͊����ʂȂ̂ł��傤���H
�����Ĕp�����Ǝ҂������ʂƕ߂炦��l���������ĂA�L�v�Ȋ����ʂƂ������z�Ɏ���̂͊ԈႢ�Ȃ��Ƃ������K�R�̂悤�ȋC������B
���ꂾ���ł͂Ȃ��A�ً}���̑��ʂƂ���펞�̑��ʂƂ������z�ɂȂ�A����Ƃ���Ă��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����낤���H
�܂��A�K�i�{���ł͊����ʂɋً}�������펞������܂���B
�����ʂ͂���Ȃ��c�����Ȃ����Ƃ��������ł��B
���₵����ISO�Ɋւ���Ă��܂��Ƃ�������ɂ͋K�i���ËL���Ă����܂��傤�@ |
�v�������ł͂Ȃ��K�i�̃A�l�b�N�X�ɂ����āA�����ʂ��Ƃ炦��ɂ͒�펞�����łȂ��ً}���Ƃ�������Y���ȂƂ���܂��B
����͗v�������ł͂Ȃ��������ł����A�ǂ��ǂ�ł���펞�̊����ʂ�c������A�ً}���̊����ʂ�c������Ȃ�Ă����Ӗ��ł͂Ȃ����Ƃ͖����ł��B
���ɁA�ً}���̊����ʂƂ����펞�̊����ʂ�����̂ł͂���܂���B�����ʂɂ���Ē�펞���L�ӂ̂��̂���펞�ɗL�ӂȂ��̂�����̂��Ƃ������Ƃł��B
-
�Ⴆ�A�p�����Ƃ������ʂ��������Ƃ����̑��ʂ͂��낢��Ȋ��e��������܂��B
- �ۊǏꏊ����̐��������̉\��������܂��B
- �Ёi���j�Ȃǂ̊댯������ł��傤
- ���L�̔������ƂȂ邠�邩������Ȃ�
- �p����������̕N��������ł��傤
- ���̂ɂ���Ă͕�����������肷����̂�����ł��傤�B
����ƌ����Ă��j������ː������͔p�����̑ΏۊO�ł��B - ���������͓]�|��R�k�Ƃ����ً}���ɔ������邩������Ȃ����A������N���͒��I�Ȃ��̂ł��傤�B
�����Ē�펞�ł���A�ً}���ł��ꂻ�̊����ʂ������ɊǗ����邩�Ƃ������Ƃ�4.4�ȍ~�̖����ƂȂ�܂��B
4.4.7�łً͋}�����z�肳�����̂ɂ��āA�\�h���邽�߂́A���������ꍇ�̑Ή��菇�����߂Ȃ����Ƃ���܂��B�����āu�\�ȏꍇ�v�͎��ۂɃe�X�g���Ă݂Ȃ����Ƃ���܂��B
�P���ł͂���܂����@�e�X�g�ł���B
|
�K�i�ɉ������V�X�e���ł���Ȃ�A��펞�ł���A�ً}���ł���A�菇���i�K����v�̏��j�ɗ������ׂ����ƁA�Ή����ׂ����ƂȂǂ������Ă���͂��ł��B�����ĂȂ��Ƃ����4.4.6�̑��s�ᔽ�ł��B
�����Ă���ɏ]���ċ��炵�A�]���҂��菇�ʂ�Ɏd�����ł���̐������A�]���҂͂�������ɏ]���Ďd�������Ă���͂��ł��B
�ً}�����\�z����邱�Ƃɂ��ẮA����I�ɂ��̗v�̏��Ƃ���ɂł���̂��e�X�g�����܂��B�e�X�g�Ƃ͎菇���ǂ����ǂ������`�F�b�N���邱�Ƃł���A�K�n��ړI�ɂ���̂ł͂���܂���B�K�n�ɂ��Ă�4.4.2�Ŋ��Ɋ������Ă���͂��ł��B
�����𑽂��̐R�����͊��Ⴂ���Ă���B�����Ă��ׂĂƂ����Ă������炢�̎����ǂ��Ԉ���Ă���B ���ɏ]���҂̗͗ʂ��s���ŋً}���̑Ή����ł�����A�����4.4.3�ւ̕s�K���ł�����4.4.7�̕s�K���ł͂Ȃ��ł��傤�B ���ۂɂ�4.4.7�ŕs�K���ɂ��Ă���R�����͂������܂��� �ł͂Ȃ��ً}���Ԃɂ��ăe�X�g�����߂Ă���̂��H ��펞�ɂ��Ă͓���Ɩ����s���Ă���B�����炻�̎菇���K�����ۂ�������Ɩ��ɂ����Č�����Ă���B������킴�킴�菇���ǂ������e�X�g���Ȃ��Ă��悢�B�������A�ً}���ԂƂ͌�ӂ��猾���ē��픭�����Ȃ��B��������ʂɃe�X�g�E���s����K�v������̂��B ��펞�A�ً}���̂�����̎菇�ɂ��Ă��]���҂����{�ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�4.4.2�̗v���ȑO�ɁA��Ƃ̑����̂��߂ɂ͓�����O�̘b�ł���B |
�u���펞�͗ʓI�ȍ팸�A�ً}���͔������X�N�y���������̑ΏۂŁA���펞�͗ʂ̍팸���s���ً}���̌P���͕s�v�v�Ȃ�Č��R���T�����R���������܂��B
���������ۂ��ƌ����O�ɁA�܂��O�ɏq�ׂ��悤�ɔ���̒�`�����߂Ă����Ȃ��Ă͘b���i�݂܂���ˁB
�ł����S�ɊԈ���Ă��邱�Ƃ�����܂��B
�K�i�ł͊����ʂ��Ǘ����邱�Ƃ����߂Ă��܂����A���P���邱�Ƃ����߂Ă��܂���B
���j�𗧂Ă��炻����l�X�Ǝ��s���P���邱�Ƃ����߂Ă��܂����A����Ɗ����ʂ̓C�R�[���ł͂���܂���B���������j��ړI�ڕW�����߂�Ƃ��Ɋ����ʂ��l�����邱�Ƃ����߂Ă��邾���ł��B
�����Ƃ����܂��ɂ͊��ړI�͊����ʂ���I�ԂȂ�Č���Ă���R�����A�R���T���̂ق����A���ړI�͊����j�̓W�J�������̂ƌ��l��葽�����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
|
- ����āA
- ��펞�ɗL�ӂȑ��ʂł����Ă��팸������`�����v�����Ȃ�
- ���펞�ɗL�ӂȑ��ʂł����Ă��팸���s���K�v�͂Ȃ�
- �ً}���̔������X�N�y���ȂNj��߂Ă��Ȃ�
�������邱�Ƃ͗ǂ����Ƃł����A�������Ȃ��Ă����Ȃ� - �ً}����L���鑤�ʂł����Ă��P�������߂Ă��Ȃ�
- �ً}���ł��낤�ƂȂ��낤�ƁA�Ɩ����s����͗ʂ��K�v�ŁA�͗ʂ��Ȃ��ꍇ�͋���P�������Ȃ���Ȃ�Ȃ�
- �ً}�����z�肳�����̂ɂ��Ă͉\�ł���e�X�g�����Ȃ���Ȃ�Ȃ�
������������|�ŗ������Ă����낵���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
 PCB |
�u�ŋ߂Ƃ��ǂ�PCB���b��ɂȂ�܂��ˁv�Ɛ�������������Ă��܂����B
�u���������ƍ����|���������Ă܂����A�̐S�̏����{�݂��Ȃ��Ȃ������ɓ����Ă��Ȃ��悤�ł��ˁv�Ǝ�
�u���͂ˁA���Ђɂ�PCB�̓������g�����X�������ł����A�����������ʂɂȂ��Ă��Ȃ��̂ł��B�v
�u�ʂ�PCB���ЂƂ̒����������ʂɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B�p�����Ƃ���������̒��Ɋ܂܂�Ă���悢�킯�ł����E�E�v
���͂Ȃ�ł��f��Ƃ��v�����ނƂ������Ƃ͂��܂����B�v����Ɍ��ʂ��K���ł���Ηǂ��̂ł����āA���@�͂ЂƂł͂Ȃ�����I�ȍl���Ƃ��A�v���[�`�͂ЂƂ����Ȃ��Ȃ�Č��ߕt���邱�Ƃ͂���܂���B
���������̕�
�u�����A�p�����ɂ�PCB�����Ă��Ȃ���ł��B���͊����ʂ𐔒l�v�Z�Ō��߂Ă����ł����ǁA������W�����������Ă�PCB�������������ʂɂȂ�Ȃ���ł��B�v
�����A�V��f�q�ł���B�i�_�W�����ł��B�킩��Ȃ��Ă��Y�ނ��Ƃ���܂���j
���͖ق��Ă����B�uISO�R���ł͐R���������ꂶ�Ⴀ���傤���Ȃ��˂ƌ����Ă���Ă܂��B�v�Ƃ̂���
���̐R�����A���̂܂�܂̗͗ʂȂ̂��A���邢�͂��̉�Ђ������ł����������̂��E�E�E���ɂ͂킩��܂���B
�ЂƂ킩�邱�Ƃ́A����ȉ�Ђ��⎖���Lj��́uISO����Ă܂��v�Ƃ��u���z�����Ă��܂��v�Ȃ�Č���Ăق����Ȃ��ƌ������Ƃł��B
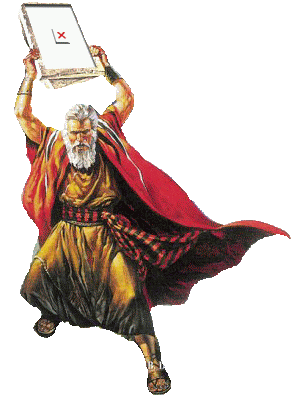 ISO�̐_�l������A�_��������ł��傤�B
ISO�̐_�l������A�_��������ł��傤�B�c�O�Ȃ���AISO�̐_�l�����Ȃ��̂��A���Ă��������_�l�łȂ����߂��AISO�̐_�l�̗��i�����Â��j�ɑł���ĖS���Ȃ����l�͂��Ȃ��悤�ł��B
�����玄���a���҂Ƃ��Č��˂Ȃ�܂���B�@
���������܂ł���Ȃ�����Ȃ����Ƃ����ё����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��傤���H
��R�l���炨�ւ���܂����i08.04.10�j
��펞�A���펞�A�ً}���̋敪�� �͂��߂܂��� ���A���镔�i������q��Ђɋ߁A�h�r�n�Ǘ��ӔC��C����Ă���҂ł��B ��N�A�h�r�n�P�S�O�O�P��e��Ђ̎x��������A���Ƃ��擾���A���݂Ɏ����Ă��܂��B ���݁A�����ʒ��o�ł̒�펞�E���펞�E�ً}���敪�ɂē����������Ă��܂��B��������K���ł��B �����ʂ̒��o�ɂ����āA�{���ɒ�펞�E���펞�E�ً}����K���敪�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��傤���B |
��R�l�@���ւ肠�肪�Ƃ��������܂��B
�K�i�ɂǂ������Ă��邩�Ƃ������Ƃ��o���_�ł������܂��B
ISO14001�F2004��4.3.1��ǂ݂܂��Ƌً}������펞�Ƃ������t���Ȃ��悤�ł��B
���߂�Ȃ����A���������������͕s�K�ł���ˁB�ً}������펞������܂���B
�����A�l�b�N�X�i�t�^�j�̒����u���R�\�m�ł���ً}���ԂƂƂ��ɁA�ʏ�y�є�ʏ�̑��ƏA���Ƃ̒�~�y�ї����グ�̏��l������Ɨǂ��v�Ƃ��邾���ł��B
�A�l�b�N�X�͗v�������ł͂���܂���B���̏؋��Ɂushall�v�ł͂Ȃ��ushould�v�Ƃ������t���g���Ă��܂��B
�u�����ʂɂ͂���Ȃ����グ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������Ƃ�ISO14001�̗v���ł��B���̂Ƃ��ɖY��Ȃ��悤�ɂ��낢��Ȍ�����Ꭶ���Ă��钆�Œʏ�A����A�ً}�Ƃ����Ƃ炦���������Ƃ������Ƃł��傤�B
�������A�R���Ή������łȂ��M�Ђ����̂𖢑R�ɖh�����߂ɂ�������ϓ_���猩�Ċ����ʂ𒊏o���Ă������Ƃ͑厖�ł��B
�����A���ً͋}���̑��ʂƂ���펞�̑��ʂƂ����\���͏����s�K���Ǝv���܂��B���낢��Ȋ����ʂ������āA����ً͋}���ɊY������̂��A��펞�ɊY������̂��Ƃ����������K�Ȃ悤�ȋC�����܂��B
��Ɏ����ƁA�c���ɂ��낢��ȑ��ʂ���ׂāA�����ɒ�펞�A���펞�A�ً}���Ȃǂ̕]������ׂāA���ꂼ��ɊY�����邩���Ȃ����̐���������悤�ȃC���[�W�ł��B
�Ⴆ�Ώd���Ƃ��������ʂ����グ���Ƃ���ƁA��펞�̑��ʂƂ��Ă͒Y�_�K�X�r�o�A�����͊��A��C�����ȂǂȂǂ�����A���펞�Ƃ��ċ������̘R�������̑�������A�ً}���Ƃ��Ă͉ЂƂ��R�����Ȃǂ�����ƂƂ炦��ׂ����Ǝv���܂��B
�C���[�W�}������t�ɂ���ƁA��펞�̑��ʂɂ͏d��������Y�_�K�X�r�o�A�����͊��A��C�����Ȃǂ�����܂��B���펞�ɂ͏d���̘R�����̊댯������܂��B�ً}���ɂ͏d���ɂ��Б����E�E�ƂȂ��Ď��E�����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
������ ��펞 ���펞 �ً}�� �菇�� �d�� �L�� �L�� �L�� �d���g�p�菇�� �d�C �L�� �| �| �d�C�G�l���M�[�Ǘ���� �p���� �L�� �L�� �L�� �p�����Ǘ���� OA�p�� �L�� �| �| �����p�i�戵�K�� PCB�@�� �| �| �R���� PCB�Ǘ��K�� �E�E �E�E �E�E �E�E �E�E
���̎��菇�����ǂ��쐬����̂��ƍl����ƍ������܂��B
�d���Ƃ������ʂƍl����ƁA�戵�菇���ɒ�펞�̒��ӁA���펞�̒��ӁA�ً}���̒��ӂƂ܂Ƃ߂₷���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�Ƃɂ����@����莖�̂�Q���h�����߂ɂǂ����ׂ����A�ƍl����悢���ƂƎv���܂��B
�R���ŁA�u�ً}���A��펞�A���펞���l�����Ă܂����H�v�ƕ����ꂽ��u�������ł���v�Ɖ�����悢�Ǝv���܂��B
���������܂��āA�K�i���肩��10�N���o�߂������ǂ��A���ʂ̓�����@�����ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B����������肵�����ʂ��K���A�R�ꂪ�Ȃ������R���Ƃ������A��Ђ̎d���̏�ŏd�v�Ǝv���܂��B
�p���t�@���l���炨�ւ���܂����i09.07.19�j
�����Ǎu�� ���ׂ��܁@�p���t�@���ł��B ��P�Q�ɂ��Ăł����A�L�v�ȑ��ʂ����グ�邱�Ƃ����́A���_�ɂȂ�̂ł��傤���B�����ʂ�L�Q�A�L�v�ŕ����邱�Ǝ��̂����������A�Ƃ�����|�ł���Ȃ痝�����܂����A�h�r�n�̎g�����聁��ʏ]�ƈ��ւ̋���A�Ƃ����_���猾���A�������ق����ǂ��悤�Ɏv���܂��B�Ζ���͐����Ƃł����A�L�v�ȑ��ʂ̈��Ƃ��ĕ����܂���P������܂��B�P�S�O�O�P�̐^�����͊����X�N�}�l�W�����g�ł͂���܂����A�]�ƈ��ɋƖ��̊��e�����ӎ�������A�Ƃ����_�ł͌��ʂ���A�ł��B |
�p���t�@���l�@���x���肪�Ƃ��������܂��B
���́A�����ʂƂ������t�Ƃ������T�O����ʎЈ��S�����m�邱�Ƃ��Ȃ��A��������K�v���Ȃ��Ǝv���Ă��܂����A����͂Ƃ肠�����u���Ă����܂��傤�B
�p���t�@���l�����������悤�ɁA�����@�����ʂ�L�Q�A�L�v�ŕ����邱�Ǝ��̂����������@�ƍl���Ă���͎̂����ł����A����͋K�i�ɂ��������Ă��邩��咣����킯�ł͂���܂���BISO14001�̖{���͉����H�ƌ����A���������Ƃ�������X�N�}�l�W�����g�ł���A���̂��߂Ɋ����ʂ��Ǘ����邱�Ƃł��B�������L�v�ȑ��ʂƂ������z����́A�����ʂ��Ǘ�����Ƃ��������I�Ȃ��Ƃ�Y��Ă��܂������ꂪ���邱�Ƃ�S�z���܂��B
�܂������̐l�X���L�v�ȑ��ʂƂ������Ƃ�����Ă��܂����A���̐l������������p�^�[���͑傫�����̓��ނɂȂ�܂��B
�@�L�v�ȉe���݂̂��Ƃ炦�Ă��āA�L�Q�ȉe�����������Ă���P�[�X
�Ⴆ�Ε��͔��d��CO2���o���Ȃ�����L�v�ȑ��ʂł���Ƃ����B������ƍl��������������ƂɋC�Â��B�o�[�h�X�g���C�N�͈ȑO������ی�_�҂���莋���Ă��邵�A�ŋ߂̓��M�̑�ʎ�������Ă���B���̑��A�������A�i�ϖ��A���Ɩ��ȂLj����e���͑��X����B
�����ǂ��e���ƈ����e���𑍍����ėL�v���Ƃ����Ȃ�A��ʂ̗L�Q�Ƃ����Ă��鑤�ʂɂ��Ă��L�v�ȉe���ɂ��Ĕz�����ׂ��ł��傤�B�������o���@�B���A�ŕ��E�������܂߂����ׂẲ��w�������A�d�C���g���G�A�R�����A���ׂĂ̓g�[�^������Ɛl�Ԃ��܂߂����ɗL�v�ȉe�����傫�����瑶�݂��Ă���킯�ł��B
�A�����P�����Ɗ����ʂ����Ⴂ���Ă�����̂ŁA�L�v�ȑ��ʂƏ̂��鑽���͂��̃^�C�v�ł���B
�Ⴆ�A�Â��^�C�v���G�A�R�����C���o�[�^�G�A�R���Ɍ������邱�����A�L�v�ȑ��ʂ̗�ɂ����Ă����������B�����悤�Ȃ��̂ɁA�A�сA�p�����̕��ʊǗ��A�L�Q�����̑�ցA�ʋ��Ԃ���d�Ԃɕς��邱�ƂȂǂ�L�v�ȑ��ʂɏグ�Ă���l������B�����������������̂͊����ʂ��̂��̂ł͂Ȃ��A�����ʂɂ��Ẳ��P�������B�`���̗���l����A���ׂẴG�A�R�����C���o�[�^��������L�v�ȑ��ʂ͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂��낤���H�@���邢�͂��������������̃G�A�R�����o��������A�C���o�[�^�G�A�R���͓˔@�L�Q�Ȋ����ʂɍ~�i����Ă��܂��̂��낤���H�@�����l����Ƃ��������Ǝv���܂��H
�����Ȃ��̉�Ђŕ����܂���P��L�v�ȑ��ʂƂ��Ă���킯�ł��B����͇A�^�C�v�̗L�v�ȑ��ʂ̂悤�ł��B�����܂���P�͗L�v�Ȋ����ʂł���Ƃ��邱�ƂɁA�傫�Ȗ��͂Ȃ��Ǝv����ł��傤���H
���͑傫�ȊԈႢ���Ǝv���̂ł��B�����A�ԈႢ�ł��邾���łȂ���Ƃ̊���������Ă��܂��ƍl���܂��B
�����܂���P�͈������Ƃł͂���܂���B�������������܂肪�Ⴂ��荂�������ǂ��̂͂Ȃ����Ƃ����ƁA�܂��d��������A���ʂȃG�l���M�[���g��Ȃ��A�������鎑��������A�p����������ȂǂȂǂ̌��ʂ����҂ł��܂��B �������ǂ��l���Ă������܂����͊����ʂł͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B�p���t�@���l�����������悤�Ɋ����X�N�Ǘ��ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�@�����X�N�Ǘ��Ƃ����Ȃ�A�Ǘ����ׂ����̂͗�ɋ����������E�p�����E�G�l���M�[�Ȃǂł͂Ȃ��̂ł��傤���H
�܂��A�����ɂ����Ă��g���[�h�I�t������܂��B�����܂����𐄐i���Ă����Ǝ����E�ޗ��ɍ����v�������邩�����ꂸ�A����͊����ׂ������邩������܂���B�����������������Ȃ�����G�l���M�[��������邩������܂���B��͂�{���̊����ʂ��ǂ̂悤�ɊǗ����Ă������A��������P����̂��Ƃ����X�^���X�ōl����ׂ��ł��B�����܂���P�͊����ʂł͂Ȃ��A���ʂ̉e�����ɘa���邽�߂̕���̈�ł���ƔF�����ׂ��ł��傤�B
�ɒ[�ȗ�ł����A���i�̃��C�t�T�C�N�����l��������Ꮏ�ȍޗ���p���ĕ����܂肪�Ⴂ�������e�������Ȃ���������܂���B�����œK�A�S�̕s�K�Ƃ͂����������Ƃł��B
�Г��I�ɐ��������₷������L�v�ȑ��ʂƂ������t������Ƃ����̂́A���������֓I���z�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�ނ�������ʂȂǂƂ������t�������邱�ƂȂ��A�P�Ɋ��e����ጸ���܂��傤�ł͂܂����̂ł��傤���H
�p���t�@���l���炨�ւ���܂����i09.07.21�j
���ׂ��܁@�p���t�@���ł��B�����̃��X���肪�Ƃ��������܂��B ����́A�������������������e�ɁA�S�ʓI�ɓ��ӂł��B ���w�E�̒ʂ�A�����ʂƊ����P�������������Ă���܂����B ���N�A������Ƃ��Ă������Ƃ��A�L���C�ɐ��ꂽ�悤�ȋC�����Ă���܂��B ����܂ŁA�����܂���P�̂悤�ȁu�L�v�ȑ��ʁv����肵�A�ړI�ڕW�Ɍf���A���P��i���Ǘ�����A�Ƃ������@�́A�O���R���ŖJ�߂�ꂱ������A�����ɓ�������_���w�E���ꂽ���Ƃ͂���܂���ł����B �Ȃ̂ŁA��a����������A����ŗǂ��Ǝv������ł���܂������A�u�L�v�v�ƌ����Ă��܂����u�ԂɁA�{���A�K�i�ŊǗ����ׂ����ڂ������Ă��܂����X�N�͂���܂��B �����Ə��́A�o�c�҂̕��j�ŁA���Ƃ��A�����ɔ���ƐR����Ђ̈ӌ��ɋt�炤���ƂȂ��A���ۑS�����͑S���Q���Ƃ��邱�ƂƂ��Ă��邽�߁A����������Ȃ��X�^�b�t����ŁA�ړI�ڕW���ǂ��ݒ肷�邩�A�Ƃ������ꍇ�Ɂu�L�v�ȁv���ʂƂ��āA�����܂���P�̂悤�ȃe�[�}���f���Ȃ����Ǝw�����Ă��܂����B ����ǁA�K�i�̈Ӑ}���l����ƁA����͎ד��A�ł��ˁB�g����o���K�A�ł͂���܂����A�傫�ȑg�D�i�֘A���͉�Ђ��܂߂�ƂP���l���y�������܂��j�䂦�A�S���Q������߂邩�A�Ƃ������f���܂߁A�O���C���ɕK�v�ȃG�l���M�[���v���ƕ�R�Ƃ��Ă܂��B���A�K�i�̐����������ƃV�X�e�����P�̕����������m�ɂȂ����A�Ƃ����_���܂߁A���w�E�������������ƂɊ��ӂ��Ă���܂��B ���肪�Ƃ��������܂����B �p���t�@�� |
�p���t�@���l�@���x���肪�Ƃ��������܂��B
���̂��ł��ˁA����Ȃɋ��k���邱�Ƃ͂���܂���B�ʂɈ������悤�Ƃ��Ă���킯����Ȃ����A����ǂ��납�ǂ����Ƃ����悤�Ƃ��Ă���̂ł�����B
���͑S���Q�������ėǂ��Ǝv�����A�܂����������e�[�}�͂�������Ǝv���܂��B�����ݓd�C�܂őމ����邱�Ƃ͂���܂���B�Ƃ肠�����X�^�b�t����ɍl���Ă��炤���̂Ƃ��ẮA
�������猾���邱�Ƃ̓X�^�b�t����͎d�����̂��̂������ʂł���A�d�������P���邱�ƃC�R�[���������C�R�[�����v�g�傾�Ƃ������Ƃł��B- ���i�Ƃ��������ʂ�����܂��B
�v����͕����ʂ肱�ꂪ�Y�����܂��B���̊����ʂ̈��e�������炵�A���l�����߂邱�Ƃ͏I��肪����܂���B���������Ȃ��A���Ɋ����⍡��K�����������Ȃ镨�����g��Ȃ����ƁA�����H���̏����������ł���邭�Ă��ǂ��悤�ɂ��邱�ƁE�E�����܂���������͂��ł��B�����o���_�Ƃ��Đ��i�Ƃ��������i�����ʁj�Ȃ̂��A�����܂����Ƃ��������i�����j�Ȃ̂��̈Ⴂ�͑傫���ł����A���i�Ƃ��ĂƂ炦��L������Ō��邱�Ƃ��ł��A�����܂����͂��̎�i�̂ЂƂƂ����������ł���ł��傤�B- �w���Ƃ����B�Ƃ��������ʂ�����܂��B
�w����̊����גጸ�x���A�A���G�l���M�[�̍팸�A���[�_���V�t�g��^�����[�g�̌����ȂǁA�A�����̊댯���h�~�A������I��肪����܂���B- ���B��A�O����A�q��Ђ̊Ǘ��Ƃ��������ʂ�����܂��B
��O�҂Əd�Ȃ�܂����A���e���̒ጸ�AEMS�\�z�x���A���@��X�N�Ǘ��̎x���A�������@�A���w�����̑�։��x���ȂǁA���܂��ɍs���Ă���ł��傤�Ɩ����̂��̂��������ł����A�����ʂ̊Ǘ��ł�����e���̒ጸ�ł��B- �}�[�P�e�B���O���邢�͌ڋq�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����Ƃ������ʂ�����ł��傤�B
�c�Ƃ͂��q�l���i�̎g������āA�܂�����ׂ����炷���@�E�E����͎g�p���̔�p�ጸ�ł�����͂��ł��B���i�p�����̒��ӎ����̓`�B�A���q�l�̐����z���グ�đO�H���ɓ`���邱�ƁA�s�꒲���Ȃǃ}�[�P�e�B���O�����Ǝ��Ƃւ̃t�B�[�h�o�b�N�B�c�ƕ��傪���Ă��邱�Ƃ��̂��̂ł��B
���Y�v��̐��x���グ�Đ��Y�v��̕ύX�����Ȃ�������A���f���`�F���W��p�����镔�i�Ȃǂ����Ȃ����邱�Ƃ̓Y�o�������גጸ�ł����A���v�g��ł��B- �C�x���g�Ƃ������ʂ�����܂��B
�W����ɂ����Ĕp�����팸��K�������A�P�Ɏ��А��i���`���邾���łȂ����ӎ�����Ǝ��Ѓu�����g�̌���i���ꂪ�Ȃ�����Ӗ�������܂���j
�����ʂ̔c���Ƃ������܂Ƃߕ��͂��̑g�D�ɍ��킹�čs���ׂ��ŁA���܂肪����킯�ł͂���܂���B�܂肻�̉�Ђ������ʂ��Ǘ����邤���œs�����悢�傫���ɂ��ėǂ��̂ł��B
���Ƃ���������̋@�B�����鎞�A���Â������ʂƂ��Ă��悢���A���邢�͋@�B�̎�ނ��Ƃɑ��ʂƂ��Ă��ǂ����A���邢�͓���{�݂Ƃ܂Ƃ߂Ċ����ʂɂ��Ă��ǂ��ł��B�v����ɂ��̉�Ђ��Ǘ����邤���ŁA�܂�菇���A����A�L�^�Ȃǂłǂ��܂Ƃ߂�Ηǂ����Ƃ������ƂŌ��߂�悢�B�����Ĉ�ʓI�ɊԐڕ���̎d���͑傮����ɂȂ�̂����ʂł��B����̎d���ƈႢ�S���҂̍ٗʔ͈͂��L�����A�܂������n�͂���Ȃ�ɓ����g���Ďd��������̂ŋƖ����ׂ��Ȋ����ʂɕ����邱�Ƃ͕s�K�Ȃ̂ł��傤�B
���ó��B
���Ȃ�Č��t�������ς�Ǝ~�߂Ă��܂��āA���Ȃ��̎d�����������āA�y�ɑ����ǂ����ʂ��o����悤�ɂ��܂��傤�Ƃ����Ηǂ��̂ł��B
�����l����ƗL�v�ȑ��ʂǂ��납�A�����ʂƂ������t���A������z���Ȃ�Č��t���g��Ȃ��Ă��Ԃɍ����܂��B ����ǂ����܂��傤�Ȃ�Č������Ƃ�����܂���B
�������͎��Ɣ��W�̂��߂Ɏd�������Ă���̂ł��B�������Љ�̗v���⎩�R�ی���z�����܂��B���z�����i�łȂ���Ό��݂͔���܂���B���@�ᔽ������E�E�ʂɊ��@�����łȂ��A�A�o�Ǘ��̊O�ז@�ᔽ�ł��A�Z�N�n�������k���ł��Љ�狊�e�����͓̂����ł��B���̂��N�����ΎЉ�I�ᔻ����A�ň��̏ꍇ�͎��Ƃ͂����܂��ł��B
�ˁA�����l����Ɗ������I�ƍl���邱�Ƃ����������Ȃ��ƂȂ�ł��B
�܂�Ȃ��b�ł����E�E���̘b�͂���������т܂��B
�����O�A�ǂ����̐V���Ёi������ł���j���L����Ƃɑ���CSR���傪���邩�Ƃ����A���P�[�g�����܂����B
�����̉�Ђɂ�CSR���Ƃ��Љ�v���Ȃ�Ƃ��Ƃ������傪�����������ł��B
������CSR�̍Ő�[���s����Ƃɂ͂�����������͂Ȃ����������ł��B�Ȃ����ƕ����ƁA���̂悤�ȍl���͉�Ђ̒��ɐZ�����Ă���̂ł킴�킴CSR����ȂǕs�v���Ƃ̂��Ƃł����B
�����Ȃǂ������������i�ł͂Ȃ��̂ł��傤���H
�c�ƂƂ��v�̓��C���ł����玖�Ƃ����Ă����ȏ�s�v�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B�������X�^�b�t����́A�Ј����Љ�I�K�͂���������Ɛg�ɂ���Εs�v�ɂȂ��Ă��܂��̂ł��傤�B���R�A�����傾���łȂ��A���̂��߂Ƃ������z�����������s�v�ɂȂ�܂��B
�p���t�@���l���炨�ւ���܂����i09.07.22�j
���ׂ��܁@�p���t�@���ł��B�����ɖ������g���������̂������A���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B ���������܂ŁA�����ԓ��������ł��܂����B���E�̃G���[�́A�X�^�b�t����̊��ڕW�ݒ�v���Z�X�Ɂu�L�v�ȑ��ʂ̓���v�Ƃ����X�e�b�v����ꂽ���Ƃł��B �u�������P�v�̂悤�ȉۑ�́A�u�����ʁv���o�R�����A�u�����j�v��W�J����i�����Ə��ł́A�u���Ɗ����̑S�i�K�ɂ����Ċ������̗\�h�ɓw�߂�v�Ƃ�������������܂��j���ŖڕW�ݒ肵�Ȃ����A�Ǝw������Ηǂ��B����Ȃ�A����قǑ傫�ȋO���C���A�Ƒ��Ȍ�����������Αf�l�ɂ͂킩��Ȃ����x�̔��C���ɉ߂��܂���B ���̂����́A�����ɂ�4.3.1a�j���ɕs�K���A�Ƃ����̂͏��m�ł����A���ƕ���̊����ʂ́A�ƂĂ��Ȃ����̂���������܂��̂ŁA�X�^�b�t����͑��ΓI�ɉe��������������A���Ə��S�̂ł͖���������A�ŊO���R���͓˂��ς˂����ł��B ����A��R�Ƃ����̂́A�X�^�b�t����̊������ۂ��Ƃh�r�n�P�S�O�O�P�̘g�g�݂���O���K�v�����邩�ȁA�Ǝv��������ł��B �h�r�n�P�S�O�O�P�́A�����̗̂\�h���Q�g��h�~�ƁA�R���v���C�A���X�O��ɂ̂��肵�ēK�p����̂��������g�����ł����āA�J�̐R���@�ւ�ƊE�����T���U�炩���Ă���u�o�c�Ɏ�����v�Ȃ�đ匾�s����L�ۂ݂ɂ���ƁA�����̌o�c�V�X�e���Ɉ��e�����y�ڂ����ƂɂȂ�܂��B�u�L�v�ȑ��ʁv�Ŋ����Ă�����a���́A�u�������P�v�̂悤�ȉۑ�̉����ɗL���Șg�g�݁A�d�g�݂��K�i�͈�A���Ă��Ȃ����Ƃł����B����́A������O�̂��ƂŁA�K�i�{���̎�|����E���A�������̂˂�������Ă����A�Ƃ������Ƃɉ��߂ċC�t���܂����B���肪�Ƃ��������܂����B �p���t�@�� |
�p���t�@���l�@���x���肪�Ƃ��������܂��B
���E�̃G���[�́A�X�^�b�t����̊��ڕW�ݒ�v���Z�X�Ɂu�L�v�ȑ��ʂ̓���v�Ƃ����X�e�b�v����ꂽ���Ƃł��B
���̂悤�Ɏv���܂��B�Ȃɂ������ʂƂ��L�v�Ƃ����@�̌��t���g�킸�Ƃ��A�̂���̓����ŏ\���Ԃɍ������Ƃ��Ǝv���܂��B
���ƕ���̊����ʂ́A�ƂĂ��Ȃ����̂���������܂��̂ŁA�X�^�b�t����͑��ΓI�ɉe��������������A���Ə��S�̂ł͖���������A�ŊO���R���͓˂��ς˂����ł��B
��ًc����
���ƕ���̑��ʂ͑傫����������Ƃ������Ƃ͓��ӂł��B
�������X�^�b�t����̑��ʂ����āA����Ɠ����ł��邱�Ƃ�F�����ׂ��ł��B
SONY���d���R�[�h�Ɋ܂܂�Ă����J�h�~�̂��߂ɐ��S���̑����o�����Ƃ����̂͗L���Șb�ł��B
�������傲�ƂɂȂ�Ȃ����Ǘގ��Ȏ���͑��X�����Ă���܂��B
���Ƃ��A�����̃t���[�Y�ő����ɂȂ������������܂����B����́u���̐��i�͏ȃG�l������d�C����C�ɂ��Ȃ��Ŏg�����v�Ƃ����悤�Ȃ��̂������悤�ɋL�����Ă��܂��B
���Q���o���Ƒ�ς��I�Ƃ����͎̂����ł����A����Ɠ����悤�Ɏ��ށA�c�ƁA��`���邢�͂ǂ�ȕ��傾���ďd��Ȋ����ʂ������Ă���ƔF�����ׂ��ł��傤�B
YOSHIDA�l���炨�ւ���܂����i2012.11.17�j
���E����E�ً}�̌� �������������������̂ł��� �����ʂ̓���ɂ����āA���E����E�ً}�@��z�肷��Ƃ��������Ƃ��s�Ȃ��Ă��܂��B �������Ȃ���A����3�̊��������܂���B �Ⴆ�� �@��큁�ʏ�̐��Y �@���큁�̏�ɂ���Ē�~������� �@�ً}���R�d�ɂ��Д��� �Ƃ�����ɍl����悢�̂ł��傤���B ����ŁA�l�b�g��Ō��������̉�Зl�̊����ʂł� �@��큁��������Ă����� �@���큁�����R�k���Ă����� �@�ً}����������� �ƂȂ��Ă��܂����B �����R�ꂽ���_�ŁA�ً}�̂悤�ȋC������̂ł����E�E�E�B ����3�̕��ނɖ��m����`������̂������������������Ȃ��ł��傤���B �ȂɂԂS�҂ł��̂ŁA����̎d���̂܂��������邩�Ǝv���܂��� ���w���̂قǁA��낵�����肢���܂��B |
YOSHIDA�l�@���ւ肠�肪�Ƃ��������܂��B
�����O��q�����Ĉ�u�A�M���b�Ƃ��܂����B�����g�c�h�j��搶����c�b�R�~���������̂��ƁE�E
�����łȂ����낵���̂ł����A�����g�c��搶���{�l�ł���A���̒t�قȐ��������Ă��������������B
ISO14001�ł͒�����������y���Ă��܂���B�A�l�b�N�X�ł͂��낢��ȏ�ǂ����ׂĂ���Ȃ��c�����Ȃ����Ƃ������Ƃł�������܂���B
�ł����炻�̉�Ђ�S���҂̎�i�D�݁j�ɂ���āA��펞�A���펞�Ƃ�������ōl���Ă��ǂ��ł��傤���A��̂��́A�Ⴆ�Ώd���̒�펞�A���펞�Ƃ�������ōl���Ă���낵���ł��傤�B
���ꂪ�܂�����܂��B
���ɁAISO�K�i�ł͔��펞�Ƃ������t���̂��̂�����܂���i�A�l�b�N�X�͒P�Ȃ�Q�l�ł��j���̉�ЂŔ��펞�ƌ��߂悤���A�ً}���ƌ��߂悤���������i�D�݁j�ł��B
�Ƃ���Ŋ����ʂ��펞�A���펞�A�ً}���ƕ����Ă����Ђ������ł����A������č���I�ɂ͂��������Ǝv���܂��H
��펞�Ȃ炻�̔��Ό�͔��펞�ł����A�ً}�̔��͕���ł��傤�B���̂ւ�͂ǂ��ł������ƌ����ǂ��ł������̂ł����A��펞�A���펞�A�ً}���ƃ����N�t���Ƃ������K�i��ɂȂ�Ƃ͎v���܂���B�����҂͂ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��������Ă����̂��A���ɂ͂킩��܂���B
�Ȃ��A�ߋ��ɂ������悤�Ȃ��₢���킹������܂����̂�����������Q�l�܂łɂ��ǂ݂��������B
�m��� ���Ό� ��� ��肵�Ă��ĕς��Ȃ����ƁA�܂����̂��� ���� ���܂��܂Ȍ��ۂɂ����āA�������ȏ�Ԃɓ��B����܂ł̉ߓn�I�ȏ�ԁB���̔��ΊT�O ���� �����Ɠ����ł��邱�� �ً} �����ɑΉ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƁA�܂��͂��̂���
ISO14001�̖ڎ��ɂ��ǂ�