ISO第三者認証の信頼性が低下している。それは認証を受けた組織が不祥事を起こして毀損しているからだ。そんな声がISO業界から上がり、その結果、JABもJACBもねじり鉢巻で認証を受けた組織が悪さをしたらとっちめるぞと大声でいい、各社から代表が集まってどんなときには認証を停止するとか、いかにもISO屋らしくその仕組みを考えて手順や基準に落とし込んだ。
大儀である。 
では手にした新兵器でバッサバッサと認証の停止をしているのだろうか? 認証の取消をしているのだろうか?
誰だってそれが気になるでしょう?
私は仕事が速い、もちろん個人的なことだって思い立ったが吉日ってやつですぐにする。先送りとか、寝かしておくとか、棚に上げておくということは絶対にしない。そういう性格は海軍下士官だったオヤジ譲りである。
歳をとればとるほど自分が親父そっくりだということに気づく。30年以上前、親父が生きていたときは大嫌いだった。自分と似ているから嫌いなのだろうか?
|
ということで早速調べることにした。
まあこんなことは難しくともなんともない。JAB(日本適合性認定協会)のウェブサイトにアクセスして認証停止とか取消のデータが載っていないかを見た。すると不思議なことに「マネジメントシステム適合組織検索」というページはあるのだが、「不祥事により認証停止・取消されたマネジメントシステム適合組織検索」というページは見つからなかった。(2010.07.04現在)
JABは時代に即した情報公開をしていないのか、それとも認証停止とか認証取消を把握していないのだろうか?
よくわからない。
だが適合組織の数値とリストが10日ごとに更新されていることから、認証停止などの情報は把握しているのではないだろうか? とすれば情報公開していないことになる。
井口さんに問い合わせなければ・・
井口さんとはJABの専務理事、もちろん面識はない
井口さんとはJABの専務理事、もちろん面識はない
ともかく、日本のISOの元締めであるJABではISO認証の停止や取消の情報が得られないとわかったので、私はJABが認定している認証機関のウェブサイトをあたることにした。
JABが認定しているマネジメントシステム認証機関は50組織である(2010.07.04現在)。
「50組織なのに認定番号が57まであるのはどうして?」なんて一休さんにでてくる「どして坊や」のようなことを語ってはいけません。大きな声では言えないけど廃業したり身売りしたりしたからですよ。
日本にはJAB認定でない認証機関もあるのにJAB認定だけでよいの? そういう質問大好きです。でもJAB認定でなければJABの指示に従う必要はないので、この場合は関係ないとみてよろしいでしょう。 |
イチバーン 財団法人 日本規格協会審査登録事業部(JSA)
ニバーン 日本検査キューエイ 株式会社(JICQA)
サンバーン
と、ひたすらクリックして、その認証機関のウェブサイトのどこかに認証停止や認証取消の会社のリストをアップしていないかを目を皿のようにして探すのみです。
結論を言います。
まずほとんどの認証機関は認証を停止したということを表記していません。あるいは認証停止がないのかもしれませんが、ないなら「ない」と書くということも情報公開上必要なことでしょう。
なんせ、ISO審査員は「記録がなくてもそのファイルを作っておいて、作成した記録がないことを明確にしておくことが必要です」なんて語っているのだから。
|
横柄無視かもしれません・・・
ではいよいよ成績発表です。
認証停止/取消のウェブサイトへの公表している認証機関と件数(2010.07.03現在)
| 略称 | 認証機関名称 | 08年 | 09年 | 10年 |
| JICQA | 日本検査キューエイ 株式会社 | 0 | 0 | 2 |
| LIA-AC | 財団法人 日本エルピーガス機器検査協会 | 0 | 1 | 0 |
| BCJ-SAR | 財団法人 日本建築センターシステム審査部 | - | - | 2 |
| JACO | 株式会社 日本環境認証機構 | 2 | 3 | 1 |
| BL-QE | 財団法人 ベターリビングシステム審査登録センター | - | - | 1 |
| - | - | 0 |
注: |
「0」はウェブサイトにおいてないと記載されている場合 「-」はウェブサイトで言及していない場合 |
情報公開という観点で、この6社が優れていると私は認めます。特に過去3年間を表示していた3社には最優秀賞を上げます。
実を言って表彰どころか当たり前という気もするのですが・・
これ以外の認証機関は認証停止があったともなかったとも書いてありませんでした。もし私が見落としていたなら、一般人が目に付くようにリンクしていなかったということです。
私が謝罪する必要はなく、それはネガティブポイントということです。
さて、最初のテーマである、不祥事多発に対応するために認証停止や取り消しの手順や基準を定めたことによって、認証停止や取消が増えているのかということについてですが、どうでしょうか?
毎年倍々で増えているようにも思えますが、なにしろ絶対数が少ないのでなんともいえません。とにかく認証機関の1割しか情報公開していないし、また情報公開している認証機関も過去3年間しかデータを出していません。抜取検査なら危険率95%くらいでしょう。
危険率5%じゃありませんよ
よって、認証停止が増えているかいないかはコメントできません。しかし、認証機関そして認定機関の情報公開は少しも進んでいないということがわかりました。本日の結論
認証機関の情報公開を進めなければ日本の夜明けは来ない
坂本龍馬の言葉
認定機関と認証機関を洗濯いたし申候
外資社員様からお便りを頂きました(10.07.05)
佐為さま、いつも有難うございます。 ISO認証停止に関連して、不思議に思っていることがあるので、ご意見を伺えれば幸いです。 認証機関が「不祥事により認証停止・取消」をするということは、ISO認証に合格することは「不祥事を起こさない」ということを保証しているのでしょうか? もし、ISO認証と不祥事の関係が無関係ならば、不祥事を起こそうが認証の合否は無関係ですよね。 私の会社では技術系の認証をしていますが、その認証結果は、個別の製品に対するもので、その会社が不祥事をおこそうが無関係です。 また、試験では、市場での不具合が起きようが、認証結果も変わりません。 但し、市場で不具合があれば、その技術的な原因分析をして、本来 認証試験で検出するべきものならば、試験方法を見直して、受験した会社には再受験を要請します。 よくある例では、試験サンプルと、量産品で使用部品が異なっていることなどがあり、このような場合には量産品での再試験が義務となりますし、先の認証結果はサンプルが異なるので無効とします。 同様に考えれば、ISO認証を受けた会社が不祥事を起こした場合に、その原因を分析しているのでしょうか? その原因が認証試験の内容と無関係、例として経営者の個人的資質や思想などに起因していれば認証で見つけられる訳がありません。 ならば、認証会社は自己の「無謬」を申してるべきと思いますし、何ら恥じることはないはずです。 もし、不祥事に関する原因を分析しないのならば、そのような認証試験 自体に信頼性がないのかもしれません。 または、受験前の免責事項として「本認証は社内のプロセスを認証するもので、その合格は会社が不祥事や反社会の有無を保証するものではありません」と言えば良いのだと思います。 高いお金を払って受験した会社の認証結果を「無効」とするには、それだけの根拠が必要と思います。 それが自身の認証プロセスの無謬性をいわずして、無効としているならば不思議な感じがします。 |
外資社員様 毎度ありがとうございます。 審査登録証には「これは遵法を保証するものではない」と大書してあります。 *ISO認証といいますが、発行するのは認証書ではなく登録書です。不思議です。 しかしISO認証企業に事故や違反が発生していることから、認定機関と認証機関が法違反などがあった場合は認証を停止や取り消したりすると言い出したのが3年前。昨年はそのプロシージャも整備(?)されました。 更に笑ってしまうことには、ISO9001なら品質保証、ISO14001なら環境と限定しないで、企業の不祥事、つまり談合(独禁法)や輸出管理などの違反があれば認証を取り消すのだそうです。 ISO9001認証は品質保証だけでなく、ISO14001は環境管理だけでなく、要するに企業犯罪、事故、その他の不祥事がないことが条件となっているのが現実です。もっともまだセクハラとか下請法違反で停止や取消になったのは見聞しておりません。 つまりもう論理とか常識ではなく、認証している企業は完璧に公明正大、品行方正、学力優秀(?)でなければならないということのようです。 ISO仲間は「そのうち経営状況が悪くなると認証を取り消すのではないか」と冗談を言います。いや、冗談ではなくなるかもしれません。 つまり21世紀の現代はISO認証は栄光あるプライズとなったのでしょう。 しかし疑問はありますね。イエスキリストは我が目に梁があるのに人の目のごみを取り除こうとするなとおっしゃったとありますが、認証機関や認定機関が己の目の中の梁に気がつかないとは・・笑止 2010年7月1日付けのISO認証件数が今日公表されました。過去3ヶ月でISO9001は579件減少、ISO14001は134件減少でした。それぞれ1.5%と0.7%になります。一年で6%とか3%減ったら大変です。3年継続したら間違いなく第三者認証制度は崩壊です。もう第三者認証制度は断末魔で関係者はパニックなのでしょうか? 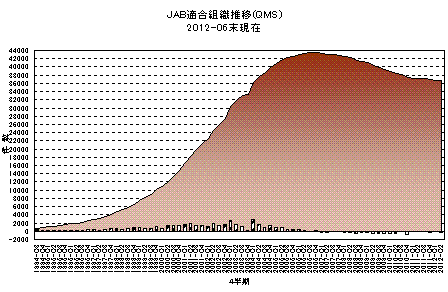 |
外資社員様からお便りを頂きました(10.07.06)
佐為さま ご回答ありがとうございます。 更に疑問が湧いてきます。 審査登録証には「これは遵法を保証するものではない」と大書してあります。 ならば、余計に遵法上の問題を理由に認証取り消しが不合理となります。 認証という枠組みを忘れて、法でいう委託契約としてとらえれば、認証を取り消すということは、契約時に訴求して「解除」ということになります。 佐為さまは法学部でお勉強したのでよく御存じと思いますが、契約解除が出来るならば、相手側(認証された会社)の債務不履行か、相互合意が必要と思います。 相互合意の点で言えば、高い費用を払った相手が合意するのでしょうか? 債務不履行があるというには、認証する側が「遵法を保証するものではない」と自ら言っていますから、それを理由には出来ないし、なにより自分が決めた手順で「認証」しているのですから、自己の無能か認証プロセスが不適切だったという理由しか思いつきません。 となると、認証取り消しは、認証会社の債務不履行となり、費用の返却と損害賠償が伴わないといけないですね(笑) 実際には、「試験に伴う合意事項」などで、「不法行為等があった場合には取り消すことが出来る」というような事前合意で縛るのでしょうね。 ならば、その内容がとても興味深いです。 |
外資社員様 毎度ありがとうございます。 ひとつ勘違いがあります。私は法学部で学んだことはありません。実社会で学んだだけです。 認証という範疇と不祥事の範疇は重なっていません。ですから不祥事があるから認証取消だというのは合理・不合理の範疇ではありません。簡単に言って、もう論理ではないのでしょう。ただたとえば脱税をした会社がISO認証を取り消された場合、認証停止は契約違反だと民事訴訟に訴えるとは思えません。日本人はおとなしいので、己が悪いと黙っているのではないでしょうか? ともかく、認証を停止・取り消す側の論理は、坊主憎けりゃ袈裟まで憎い、郵便ポストが赤いのもみんな私が悪いのよ・・そんな思考というか感情ではないのでしょうか? 現実の社会では企業はみな大人ですから、そんな認証機関や認定機関のハチャメチャな論理というか、駄々コネを子ども扱いして無視しているというのが現実でしょう。なぜなら私のように「おかしい」とか「間違っている」なんて発言している方はいません。しかしじわじわと認証を取りやめるとか、どうせ認証するなら安い会社に転注するというところが増えているということは心の中はやはり穏やかではないのでしょう。 まあ、どう考えても外資社員様がおっしゃることは正論であり、義のないはかりごとが世の中に通用するはずがありません。 しかし認定機関や認証機関の当事者がそれに気がつかないのでは救いがありませんね |
外資社員様からお便りを頂きました(10.07.09)
佐為さま お陰さまで、ISO認証機関と あまり付き合いのない私でも、どうやら問題点が見えてきました。 1)認証会社は、世間と顧客に向かっては「認証は、企業不祥事の有無(または査察)とは無関係」と公言している。 2)一方で、自身が認証した会社に不祥事があれば、それを理由に(?) 認証を取り消している。 3)2)の場合に、認証プロセスと会社不祥事の相関性は明確にしない。 (その理由は、1)で免責しているから?) 認証会社のHPや資料をみると、必ず「コンプライアンス」という文字があります。 コンプライアンスとは、遵法の意味が多いですが、法律以外の私法(会社のルールや国際規格等)、及び運用の厳格さや合理性が期待されるのは当然と思います。 すくなくとも、1)を宣言して、2)を行うのは、まったく合理性がありません。 自己の合理性がない審査機関が、何を指導しようが説明しようが、お客は従うとは思いません。 ですから、私が認証会社の立場ならば、少なくと2)の前には審査プロセスの妥当性の検証を自主的に行い、その結果として 自己の審査と不祥事が無関係ならば、2)は行わず、調査結果を公表します。 なぜならば、それが自身の審査プロセスの無謬性の補強につながるからです。 また検証プロセスの検証の結果、本来 審査で見つけられるものであれば、審査プロセスを改善します。 その場合でも、「法は遡及せず」の原則がありますから、2)は勝手にできず、顧客の同意は必須と思います。 法理の原則にあっていないことをすれば、「コンプライアンス」を口にする資格はありません。 ということで、不祥事発覚した場合に、自己の審査プロセスを見直さなければ発展はなく、3)のようにそれをしないならば、2)はやってはいけないことになります。 |
外資社員様 毎度ありがとうございます。 基本的におっしゃること、そのとおりでございます。 しかし彼らの立場というか利害から見れば、第三者認証制度の価値を高めねばならず、そのためには不祥事が起きた会社を認証していてはまずいとかんがえたのでしょう。 なぜそう考えたのか?と問われても私は当事者ではありませんのでわかりません。 きっと外資社員様や私にはわからない事情があるのでしょう。 |
外資社員様からお便りを頂きました(10.07.15)
ISO認証取り消し、調べてみると不二屋の事件の時に、経産省がJABや認証機関の団体に対して、「不祥事がでるとはISO認証はどうなっておるか?」と問い合わせが出たのが契機みたいですね。 http://blog.goo.ne.jp/conshin4/e/88f26404cc3b70d69b107cc139c62101 (同様な記事がいくつかあります。) この時に、「ISOは社内体制、仕組みを審査するもので、不祥事の有無は会社のモラルや、姿勢の問題です」と言いきれなかったのでしょうね。 考えてみれば、車検に通っていようが、車両が原因の事故はありますし、三菱トラックの車軸折問題も、「車検でなぜ見つからない」は問題になりませんでした。 なぜならば、車検は 車が正しく設計されている(加重に対して余裕あり)を前提にして、検査をするからです。 個人的意見ですが、経産省からの問い合わせに対して、審査の無謬性に自信を持って答えられなかったから、会社側の体制で問題点を探し出して、相手のせい(嘘をついた、データを隠した)にしたのでしょうか。 そのような報告を経産省にしたならば、同様なことを その後やることは当然のように思います。 いづれにせよ、自己の合理性に破たんを生じた認証は、自ら価値を低めたと思います。 |
外資社員様 毎度ありがとうございます。 第三者認証制度は民間の制度だと常日頃行政も、認証制度側も語っているのですから、経産省も口を挟むことはないはずです。 しかし、それぞれに大人の事情(子供の事情?)というのがあるのでしょう。 結局は外資社員様のおっしゃるように、自己の合理性に破たんを生じた認証は、自ら価値を低めた に違いありません。 そして迷惑をこうむるのは一般企業であるようです。 ただ、今となってはあと何年この制度が持つか持たないかというのが興味あるところです。 |
うそ800の目次にもどる