11.09.03
| 著者 | 出版社 | ISBN | 初版 | 定価(入手時) | 巻数 |
| 池井戸 潤 | 講談社文庫 | 978-4-06-275803-1 | 2007/8/10 | 695円 | 全一巻 |
2年位前から、E教授をはじめとして多くの方々が、ISO認証企業が虚偽の説明をすることにより、不祥事が起きて、ISO認証の信頼性が低下しているという説を語っている。
| 虚偽の説明 |  | 不祥事 |  | 信頼性低下 |
そんな中にこの本があった。タイトルを見ただけで買い込んだので、配達されるまで小説とは知らなかった。私はいい加減な人間である。では本日はこの本をネタに駄文をひねる。毎度のことではあるが、読書感想文ではない。この本を読んで頭に浮かんだ妄想を書くのである。
我々は日常生活において、常に真実を語っているのだろうか?
どうも、そうではないように思える。
「奥様、どちらへ」
「ちょっとそこまで」
そこまでというのはどこまでなのだろうか? パチンコでうさ晴らしとか、サラ金に行くのよとか、ホテルで浮気とか、そんな真実を語ってもしょうがない。交わされる言葉は人間関係の潤滑剤であり、ジャストグリーティングというか、挨拶に過ぎない。
裁判で被告人は、自分に不利になることを語る義務はない。もちろんうそをついちゃいけないが、事実すべてを語らなくても罪にはならない。弁護士だって有利になることだけを語って不利になることを語らなくても良い。もし神に誓って有利も不利もすべて語らなければならないのであれば、論理的には検事も弁護士もいらないことになる。
己に不利になることもすべて語る義務があるなら、民事訴訟は起こらないことになるのだろうか?
|
不動産の場合、重要事項説明といって隠さずに説明しなければならないことがある。どっかの大手不動産が土壌汚染を隠して(以下略)
- もし、人間がうそをつけないようになったら、社会は崩壊するのではないだろうか?
- 「あなた行ってらっしゃい、お気をつけて」
「あなたなんて、車に轢かれればいいわ」 - 「ちょっと事情があって2万ほど貸してくれないか」
「総務のA子とホテルに行くので2万ほど貸してくれないか」 - 「あなたが好きよ」
「本当はB君が好きなんだけど、B君にはCさんがいるから、あなたで手を打つわけよ」 - 「僕はサンゾウのかんちゃん待ちだ。タンヤオだけだけどドラがあるから8000点だ」
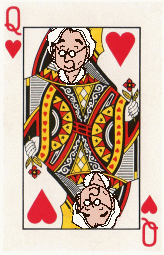
マージャンやポーカーは不可能になる。
中 中 一
萬二
萬三
萬◎ ◎
◎◎◎◎
いや、崩壊するのではなく、世の中面白くなるかもしれない。
ISO審査において、真実のみを語らなければならないという義務はあるのだろうか? 少なくても偽証について法廷以上の要求はありえないように思える。そして、もし認証組織に真実をすべて語れという要求を突きつけるなら、審査員も真実のみを語らなければならないのは当然だろう。
現実を考えれば、すべての審査員は真実を語るどころか、ISO17021を守っているだろうか?
オープニングで異議申し立てを説明する審査員は何割いるのだろうか? 私の知る限りJ●△の審査員は100%説明しているが、J▲○○の審査員で異議申し立てを説明しているのは、半分はいない。せいぜい1割くらいではないだろうか。パワーポイントには異議申し立てを小さなフォントで書いてあるが、ほとんどの審査員は説明するときにそこを飛ばす。
J▲○○の社長さん、現実を知っているのですか!
この場合、「認証組織には異議申し立ての権利がありません」と言えば虚偽の説明であるが、説明しないだけであるから虚偽の説明には該当しないのであろうか?
これが虚偽の説明に当たるかどうか、ぜひとも知りたい。 虚偽の説明に当たらなくても、ISO17021違反はまちがいないように思うのだが・・ |
説明すべきことを説明しないことは虚偽の説明に該当しないとしても、語ってはいけないことを語ることは明らかに虚偽の説明に該当するだろうと思われる。
例えば、「環境方針に社会に公開すると書いていないので不適合です」と現実に不適合を出している審査員は「不適合でないという事実に反することを述べているのだから」虚偽の説明をしているといってよいのであろう。それとも単に審査員の力量不足なのだろうか?
そういえば「有益な側面がありませんね」と不適合にするのも、事実と異なることであるから虚偽の説明に該当するのだろうか?
いやいや、もっとティピカルな虚偽の説明もある。
「これはUKASがいっているのです」というのは前世紀には良く聞いた。
「JABが要求しているのです」というのもある。もっともJABはUKASほど破壊力はなかった。なにせジャブだから。
私は何度もそれを聞いて黙ってしまった。その頃は、まだうぶだったのである。 しかしあるときUKASに本当かどうか問い合わせのメールした。 そして、そんなことはありませんというご返事をいただいた。 インターネット時代には、地球の裏側にでもすぐ問い合わせできる。
うそをつくならもっとうまいうそをつけ |
そんなことを考えると、私の知る限り審査でなされている虚偽の説明はあきらかに審査員がしているほうが多いように思える。いや、認証組織が虚偽の説明をしているのは見たことがない。まさか、あなた「JABがコレでよいといっているのです」なんて企業が説明しているのを聞いたことがありますか?
-
審査員による、虚偽の説明によって信頼性が低下したことは間違いない。
- あるときの審査
「これはだめです。このようにしなさい」
企業は言われたとおりにしました。 - 次回審査
「なんでこんなことしているの、だめ!」
企業は言われたとおりにしました。 - その次の審査
「これは間違えている、直しなさい」
企業は言われたとおりにした結果、前に戻りました。
こんなことが津々浦々で起きたんです。ISO審査員そして認証機関の信頼性はゴムの緩んだ靴下のように下がるばかりです。
なにしろ、来る審査員、来る審査員によって、語ることが違う。
では虚偽の説明によって不祥事が起きるのだろうか?
そもそも不祥事とはなんだろうか?
実は明確な定義はないようだ。いったい不祥事とは法に違反する事実を意味するのだろうか。それともその事実が社会に知られることを意味するのだろうか?
この辺の定義をしっかりとしてくれないと、虚偽の説明と不祥事の関連がわからないではないですか!
いやそれどころではない。ISO認証の信頼性が低下していると語っている人々は、そもそも信頼性とはなにかを定義していないし、低下していると言いながらその指標を示していない。これこそ虚偽の説明だろうか?
ところでMS認証懇談会なるところで「MS認証・認定に係る情報公開の開始」というものを見つけた。例のアクションプランというものの一環である。
ここにアップされているのが虚偽の説明でないことは検証しているのだろうか? その検証機関は認定されているのだろうか?
いやあ、簡単に虚偽の説明とか不祥事とかいうけど、考えるとフカーイ話で面白い。
本日の願望
あとでこの本の作者が今話題の「下町ロケット」を書いた人だと知った。では次はISO認証にまつわる企業小説を期待したい。
本日の苦情
なんで小説「不祥事」とこの駄文が関係するのかという声が聞こえてくるようだ。
単に、この本を読んで頭に浮かんだ妄想ですってば
外資社員様からお便りを頂きました(2011.09.05)
不祥事 によせて 佐為さま こんにちは 不利益な事を言うはずがないという、お話を伺ってなるほどと思いました。 アメリカ映画では警察が逮捕する時には「弁護士を呼べる、真実を語る必要があるが自分の権利を侵害することには黙秘する権利がある」など被疑者の権利を説明します。実態は不明ですが、知人が交通違反で捕まったときには言われたので、少なくともカタチとして定着しているのだと思います。 私も逮捕はありませんが、民事の裁判には会社側の証人として出たことがあるので、「真実を語る」という宣誓をした時に、「不利益な事を言う必要がない」という説明を受けました。 審査結果が会社にとって重要なのは言うまでもなく、ならば受験者が「不利益な事を言わない」は、当然と思います。但し裁判とは大きな違いがあります。 上記の裁判では、被告は不利益な事を言わないが真実は言うという前提で行われます。ですから、問題を明示できないならば、検察側の問題です。 ところが、ISO審査では「能力がある」ことを審査会社が証明するのですから、問題の指摘は目的ではなく、能力がある(可能性)証明が出来れば足ります。ですから、能力があっても、達成できない場合は審査側の問題ではありません。こちらでも問題になる審査は裁判の如く「問題の指摘」が目的になっているように思いました。審査は裁判の如くなってはいけないと思います。 |
外資社員様 毎度ありがとうございます。 まずアメリカではミランダ警告といって、警察官が容疑者を逮捕するときに言い渡すことが義務づけられています。 なぜミランダというのかというと、誘拐・強姦の罪で収監されたミランダという人が、逮捕の際に黙秘権を知らされなかったことから釈放されたことにちなむそうです。 裁判と審査の違いですが、どうでしょうか? 私の知る限りウソとか虚偽といえるようなものではなく、例えば「水質汚濁防止法の測定記録を見たい」といわれたとき、「それは別の建物にあるので、ここにある大気汚染防止法の測定記録でどうですか」程度のことはありますね。測定記録を捏造したりするのはウソのレベルではなく、犯罪でしょう。 実話ですが、審査員がある資料を見たいといって企業担当者が渡そうとしたら「ああ、もういいです」と言いました。しかしその審査員は最終日に「資料を求めたが提示されなかった」として不適合にしようとしまいた。その担当者が私のところに来て、「あの審査員おかしいんじゃないか」と言いましたね。私もそう思います。 その後さんざんやりあって取り下げさせましたが、お詫びもせず、勘違いだとも言いませんでした。 そんな体験は多々あります。審査対応も大変です。 |
たっか様からお便りを頂きました(2011.09.06)
銀行員なんて こんばんは はじめて独り言を入力させていただきます。とある銀行ではたらいている銀行員です。この銀行、昔ながらの体質なのか、変に従業員保護のようなインチキというか中途半端はシステムがあり、本当なら銀行での不正やセクハラ等普段言えないことを、電話を使っていうところがある。 このシステムを変に利用しているやつがいる。仕事が出来なくて、数字がとれなくて、上司に注意をされるとそのシステムに電話するやつがいる。 またそれを保護しているのか、訴えられた上司はとばされるというどうにも納得にいかない状況の中、私たちは働いている。今の上司は、へたに注意すると電話されてしまうから、ほどほどにしておけ・・・の状態。だから、やつは仕事ができなくても数字がとれなくても指導もなければ、注意もされず、態度だけがどんどんとでかくなっていく。何かあれば電話するわよ的な態度で・・・そのとばっちりを受けるのが、文句をいわれながらもちまちま働いている私たちなのだ。 どうしても我慢できなくなって、ここに入力してしまいました。どうにかならないものでしょうか。やつは、現在59歳、銀行員とはとてもみえない身なりで仕事をしている。(ほとんどしていないが・・・) それでも給与を支払っている銀行がバカらしい。 |
たっか様 書き込みありがとうございます。 高卒で田舎の会社で現場で働いていた私から見ると、銀行員ってかっこいいですよね! 昔は銀行員の嫁にしたいなんていわれていたものです。もちろん銀行員にしてもピンキリなのでしょうけど、一般企業特に製造業の現場から見れば、貴族というか身分が違いましたね。 たっか様がうらやましいですよ。 ところで問題は二つあると思います。 一つは内部通報制度の運用の問題であり、もうひとつは業務管理の問題ではないでしょうか。 内部告発というと聞こえは悪いですが、現在は公益通報制度というものが法律で定められています。ここでご注意いただきたいのですが、内部告発すれば正義かといえばそうではありません。そんなことが通用するなら無法地帯ですよ 通報したことがまさしく法に違反していた事実があった場合、適切な処置がとられるべきであるということが法律です。ですからそこから考えられることは二つあります。一つは御社が法の意図を取り違えて内部告発されるとそれを信じて行動しなければならないと考えているかもしれません。それなら、そのことを内部通報すべきではないですか。もう一つのケースは、実際に通報されるような不適切な事実があるのかもしれません。その結果、通報者を腫れ物に触るように取り扱っていることも考えられます。 私にはわかりませんが、いずれにしても御社の問題です。御社の取締役、あるいは内部通報制度の担当者(担当役員)がどう考えるかでしかありませんね 残念ながらお力にはなれそうありません。 業務管理の問題というのは、管理職は法と就業規則に則り正しく管理しているのか、過去より適正に運用していたのかということが第二の観点です。内部通報制度がない時代だって過半数どころか、ほとんどの企業はまっとうに仕事をしていたはずです。そうでなければ日本は無法国家だったわけですから。御社の場合はどうだったのでしょうか? 時間外、セクハラ、いじめ、銀行は特に取引先に対して上位にあたりますから付け届け、接待その他あったのかもしれません。そういったことが内部通報制度の仕組みができてから問題だと発言する人がでてきたならそれはそれで結構なことかもしれません。あるいは、今までの管理がデタラメだったということかもしれません。 まあ、傍目には立派な職業、高賃金、名誉ある嫁に出したいとみられていても、大変なのでしょうね。 とはいえ、現場労働者も大変なのですよ。まあ、生きていくということは大変なのです。お互いにがんばりましょう。 |
ダストコマンダー様からお便りを頂きました(2011.09.22)
おばQ様こんにちは。 そもそも不祥事とはなんだろうか? 実は明確な定義はないようだ。いったい不祥事とは法に違反する事実を意味>するのだろうか。それともその事実が社会に知られることを意味するのだろうか? この辺の定義をしっかりとしてくれないと、虚偽の説明と不祥事の関連がわ>からないではないですか! その通りだと思います。 不祥事云々はどなたかの作文なのでしょうけれど、デッチあげるにしてももっと正確な定義付けをしていただきたいものです。 法令違反の程度は同じでも、タイミングにより大新聞にデカデカと載ったり地方新聞の片隅にしか取り挙げられなかったりしますね。 そしてそれを載せているマスコミはどれだけの関連知識があるのでしょうか。近時の不祥事報道は二流週刊誌とまるで変わらない扇情的なものに映るのですが。 |
ダストコマンダー様 毎度ありがとうございます。 お気を悪くしないでほしいのですが、ダストコマンダー様もマスコミについて誤解されています。 新聞での不祥事報道はどのくらいあるのかといいますと、実はあまり数多くありません。特にISO認証企業と不祥事を結びつけた報道、例えば「排水基準を超えた水を違法に排水していた○○社は環境管理が優れている企業に与えられるISO14001を認証していた」というふうな記述は、朝日新聞で過去10年間に29件、読売新聞で35件です。これを多いとはいえないでしょう。(私は自分で数えました。こういうのは裏づけなしに語るとけたぐりをくらいます) ですから数は少ないのだけど記事を読んだ人が、その実態つまり発生件数などを把握せずに、単に不祥事が多い、ISO認証企業でも不祥事が多いというイメージのみが残像のごとく残るのではないでしょうか? いずれにしてもデッチアゲとかデカデカというのは思い込みの可能性が大きいです。そして問題は多くの読者がそう記憶してしまうということです。そこが報道の難しさであり、私たちが正しい判断をできない理由だと思います。 環境ホルモンが危ないという報道は覚えていても、環境ホルモンなるものは存在しないようだというSPEED98報告を覚えている人は少ないです。善意の人とは法律では事実を知らない人のことですが、事実を知らない人が善意で行うことではあっても、良い結果とは限りません。 私たちも誰それが悪いという前に、よく情報収集を行い、リスク、つまり重要性と発生確率をあわせて判断しなければなりません。私自身肝に銘じます。 |
うそ800の目次にもどる