13.11.06
マネジメントシステム物語とは今日は日曜日だ。川田は誰もいない事務所で一人机に向かっている。机に向かってはいるが、何も読んでいないし、何も書いてもいない。腕組みをして窓の外を見ている。
だが川田の頭の中では、いろいろと考えている。
うーん、この会社は確かにトラブルが多い、問題が起きると徹夜してもその当面処理はするものの、その再発防止対策は徹底されず定着もしない。だから川田が来てからだけでも、似たような問題が何度も起きている。
例えば倉庫で部品が混入したことは、ここ半年で数回起きた。先日は前工程で「ロット管理が必要」という注意書きを貼りつけて払い出したら、後行程ではそれを余計なものが付いていると取り除いてしまい、混入するという事故があった。ああいったことは連絡を密にすれば防げるかもしれないが、根本的には部品の識別表示のルールが決まっていないからだ。
その後、現場の人にヒアリングしたら、今使っている払い出し伝票さえもちゃんとしたルールに基づいたものではなく、何年か前に現場の担当者が考えて作ったというじゃないか。だからその伝票を誰が書くのか、どこからどこに行くのか、複写の1枚目はどうするのか、2枚目は、3枚目は、ということも決まっていない。現場で適当に運用しているだけだ。良く言えば現場の改善だろうし、悪く言えば無管理で現場が好き勝手にしているといえる。ともかく現状を是とするわけにはいかない。これはやはり規則がないからなのだろう。ないなら作るしかない。
川田はまた考えを進める。
だが、伝票の規則を作れば済むというものではない。そもそも規則というものが自分ひとりで存在できるはずがない。絶対神のように、ありてあるものじゃないんだ。その規則を裏付けるものというか仕組み、例えば「この会社では規則を作る」という宣言なりが必要になる。その宣言なり規則を作るということも、規則で決めることになるだろう。当然、その規則で、「従業員は規則を守らなければならない」ということも決めなければならない。なぜ規則を守るのかということは、明言しておかなければならない重要なことだ。
しかし、この会社で文書といえるものは、部品の図面と金型図面だけらしい。いやそれを採番するルールがあった。ところがそれは会社全体のルールではなく、設計課のルールだと聞いたことがある。設計課のルールが会社全体に通用するわけがないが、会社のルールがないからそれを援用しているわけだ。それもおかしなことだ。
そうすると、会社の規則を作るという規則をつくることがまず基本だな。
川田は立ち上がり給茶機まで歩いていく。社長が紙コップがもったいないというので、今は各自がコーヒーカップを持ってきて使っている。お茶、紅茶、コーヒーなどいくつかのボタンがある。どれもおいしいとは言えないが、それ以外となると建物の外まで行って自販機で買うしかない。とりあえずコーヒーのボタンを押す。
 薄いコーヒーの香りが付いた黒いお湯が流れ落ちる。流れが止まると川田はコップをつかみぐいと飲む。そういえば今日は、朝起きてから昨夜コンビニで買ったサンドイッチを冷たいミルクで食べただけだ。暖かいものはこのコーヒーもどきが最初かと川田は少し情けなくなった。
薄いコーヒーの香りが付いた黒いお湯が流れ落ちる。流れが止まると川田はコップをつかみぐいと飲む。そういえば今日は、朝起きてから昨夜コンビニで買ったサンドイッチを冷たいミルクで食べただけだ。暖かいものはこのコーヒーもどきが最初かと川田は少し情けなくなった。不味いとは思いながら、それを二口で飲みほした。そしてまたコーヒーのボタンを押した。
コーヒーカップを持って窓際に行く。正門から入ってくる人がいる。川田は近視の眼鏡をかけているが、このところ過労のせいか視力が弱くなったようで、その男がだれかわからない。眼鏡を目に押し付けて目を凝らすと、組合委員長の伊東のようだ。彼も専従じゃないから組合の仕事は休日にしているのだろう。
ふと思いついたことがあり、川田は組合事務所に行ってみることにした。
●
●
組合事務所のドアをドンドンと叩く。といってもガラス戸だし、脇には大きな窓があるから伊東の姿は見えている。伊東もこちらが来たのを知っていた。●
伊東が立ち上がりドアを開けた。
「川田取締役、何かご用ですか? 電話していただければ私が行きましたのに」
| ||||
「忙しいですかね、少し話をしたいんだが」
| ||||
「いや、特に重大なことじゃありません。来月この町の労働組合の協議会がありますんで、その準備ですよ」
| ||||
「準備と言うと?」
| ||||
「アハハハハ、こんな私でも壇上で話をすることもあるのです。今日はその台本を考えているのです」
| ||||
「大変だね。ちょっと相談していいかな?」
| ||||
「どうぞ、どうぞ、そのために来たんでしょう」
| ||||
川田は中に入り、テーブルに座る。 伊東がお茶を持ってきた。 | ||||
「伊藤さんはこの会社は長いと聞いたんだが」
| ||||
「そうです。創業時に入社しました。俗に第一期生と呼ばれています。創業時は現地採用が40人くらいで、幹部は 今残っているのは現場では10数人かなあ。最近は事故がないけど、昔は安全装置がいいかげんで、というかとりはずしたりしていたもんで、指をなくしたりすることが多く、事故があると当事者だけでなく嫌気がさした人は辞めていったからね。 幹部では二年前まで横山さんという方が顧問でいましたが、高齢でおやめになりましたね」 | ||||
「実を言って昔話を聞きに来たわけじゃないんだ。私は今この会社の規則というかルールを作ろうとしているんだ。聞きたいことは、創業時から今まで、会社の規則というのはなかったんだろうか?」
| ||||
「会社の規則ですか・・・ありましたよ。ええとね、会社ができたときのこと、 | ||||
「うんうん、それでそれはどうなったのだろう。今でも残っているというか、生きているのだろうか?」
| ||||
「川田取締役、考えてごらんなさい。素戔嗚は社員が1万人もいる大企業でしょう。仕事も多様で、職制も細かく分かれている。そのように大きな会社の規則が、当時従業員40数人の会社に合わないのはあきらかです。子供が大人の服を着るようなものですからね」 伊東は昔を思い出そうとしてしばし沈黙した。 | ||||
「例えば・・・・素戔嗚の規則ではA課でなになにして、それをB課に伝え、B課はどのような処理をしてC課に引き渡すなんてのがあったとしますとね、ここではA課もB課もC課も同じ部門だったりするわけです。そんなの文章の固有名詞だけ入れ替えたら意味がないですよ」
| ||||
「なるほど、それで・・」
| ||||
「規則といってもたくさんありました。なくてもなんとかなるものは自然に消えたということでしょうか。もちろん必要なものは残ったわけです・・・そのままの姿ではありませんが。 例えば設計がお客様の図面から金型図面を作る手順とか、どのように図面番号を付けるというようなことは、担当者が暗記するとか口約束では動きません。ですからそういうものは残りました。今設計課のルールというのはその頃の残渣です」 川田はそれを聞いて驚くとともに納得した。なるほどそういう歴史があるのだ。 | ||||
「それ以外のルールはどうなりましたか?」
| ||||
「設備管理の点検要領など、現場の即物的なものは生き残っていますね。コンプレッサーの点検要領とかノギスの校正要領なんてのは今もありますね。だけどそれが存在する根拠となった規則は失われてしまいました。つまり点検要領を作れとか誰が決裁するとか、校正でしたら国家標準につながることなんて決めていた規則はなくなってしまいました」
| ||||
「消えたというのは具体的にはどういうことですか? あるとき会社が規則を廃止すると決めたわけですか?」
| ||||
「うーん、はっきりとは思い出せませんが、要するに規則を見て仕事をする人がいないから、会社の手順が変わっても職制が変わっても規則をメンテしなくなり、いつしかファイル棚から会社規則集がなくなったような気がします。 取締役、こんなこといっちゃ不謹慎かもしれませんが、ひとつの文明が崩壊するってことって、こんなふうじゃないんでしょうかねえ。よくSF小説とか映画で、この文明が滅んでしまって中世とか石器時代に戻ってしまうのがありますね。そんなのを思い浮かべますよ」 | ||||
「なるほどなあ〜、文明が滅んでしまったか、この会社にぴったりかもしれないな その言い方なら、私は文明再興をしようと思っているんだけど」 | ||||
「それは非常に難しいでしょうねえ。歴史に学ぶという言葉もありますから、そのためには過去の歴史において文明を再興するにはどうしたかを調べたらどうですか。 いや、そういうことは不可能に思えますよ。ありえるとすると、まったく新しく文明を築くことじゃないですかね」 | ||||
「初めに言ったように、私はこの会社の規則を作ろうとしてるのだけど、それについてなにか意見はないかな?」
| ||||
「あいまいなままに仕事をしている今の状態がまずいのは誰でもわかります。ですから規則を作るというのは必要ですね。でもあまり大げさな創業時のようなものを作っても定着しないというか、それ以前にこの会社では使えません。もっとコンパクトで中小企業に見合ったものでないとダメでしょうねえ。 それからこの会社の人間は文章を読むのが苦手なのが多いから、マンガとか写真を使って、文章を少なくすることです」 | ||||
「委員長ありがとう、大変ためになった。しかし委員長は物知りだなあ。組合運動でなく会社幹部になろうなんて考えなかったのですか?」
| ||||
「アハハハ、第一期生に大卒が二人いましてね、星山専務と私でした。彼はそのころ購買の担当者で、私は工学部出なので現場スタッフでした。創立から数年したとき、この会社も組合を作らないとならないと初代社長が言い出して、星山と私を呼んでどちらかが委員長になれっていうんですよ。星山は会社幹部になる道を選び、私は残り物を取ったというわけです。 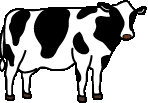 いや、それは冗談です。本当は私の事情です。当時、酪農をしていたオヤジが倒れましてね、都会でサラリーマンをしていた私が田舎に戻ってきたという状況でしたので、あまり会社をメインに考えていなかったのです。
いや、それは冗談です。本当は私の事情です。当時、酪農をしていたオヤジが倒れましてね、都会でサラリーマンをしていた私が田舎に戻ってきたという状況でしたので、あまり会社をメインに考えていなかったのです。ところが委員長ってのも暇じゃありません。このように休みも会社に出ています。酪農の方は、親父はとうに亡くなりましたが、母親と家内が乳搾りをしています。高校生になった息子も手伝ってくれますしね、 この会社で働いている人で、わざわざ面倒な組合をやろうなんて人はいません。それでそれからずっと委員長ですよ」 なるほど、伊東もそういう過去があったのか。 | ||||
「それで現場の係長にもならず、万年現場スタッフなのか?」
| ||||
「大企業ならともかく、この会社で課長とか部長になってもうれしくないでしょう。星山専務とは入社時から仲がいいんです、彼も取締役になるときはそうとう悩みましたよ。取締役となると万が一のとき、責任、お金の意味ですがね、そういう責任を負うことになるのではないかと心配してましたね。私はどうせ素戔嗚の子会社なんだから大丈夫だと説得して、本人もやっとその気になったんです」
|
川田は伊東の話を聞いて、この会社は労働争議が多いと聞いていたが、伊東はそんなに過激ではないように見える。しかも星山専務と仲が良いという。いったいどんなことで労働争議があったのだろうと疑問に思った。今後機会があれば星山専務に聞いてみようと思う。
●
●
川田は事務所に戻ってきた。●
伊東委員長と話をして良かった。確かに規則は会社の規模によって姿かたちが異なるだろう。服装と同じく規則も体に合わせて大きさが違うはずだ。それに服装に、TPOがあるように、フォーマルが良いこともあり、カジュアルが良い場合もあるだろう。現場の人が使う規則が法律のような文章では不似合いだろう。
とりあえずどんな規則から作って行けばよいのだろうか?
伝票の問題もあったし、倉庫保管の問題もあった。ともかくどれかひとつ作ってみようと考えた。
規則を作るときまずなにからはじめるのだろうか?
まずフォーマット、様式を決めなくちゃならない。それに番号体系もあるな、
いやもっと本質的なことだけど、何を決めるかと言うことがある。それには対象の仕事を良く調べ、具体的にはっきりと記述しなければならない。読んだ人がその通りに実行できなければ意味がない。
川田は持っていたシャープペンを机に放りだして腕組みをして窓の外をながめた。
傍目にはなにもしていないように見えるが、いろいろと考えてはいる。
規則の様式は素戔嗚の規則を参考にしようか、それには見本をもらうことにしよう。そうだ!規則を作る規則があったはずだ。それも、もらおう。規則体系をどうするかというのもある。
電話して必要なものを送ってもらうのもあるが、一度福島工場に帰って文書管理担当者の話を聞いてみようと思った。
なにか光明が見えてきたようで川田の気持ちが明るくなった。
●
●
●
月曜日、幹部会が終わるとすぐに、川田は素戔嗚の福島工場の文書管理課に電話した。
●
●
「川田です。そう元製造部長の川田です。ちょっと会社規則について詳しい人と話したいんだが・・」
| |
「はい、お電話代わりました」
| |
「私は製造部長だった川田だけど、ちょっとお願いがあるんだがね。 今出向していてね、その会社には会社規則がないんだよ。それで文書管理とか、伝票の規則とかを作ろうと考えているんだけど、素戔嗚電子の会社規則を作る規則ってのがあったよね、それをもらえないかな。それをみて規則を作ろうと思うんだ」 | |
「ご存じと思いますが、会社規則は社外秘なのです。まあ川田部長ですから、よろしいと思いますが・・ 本題ですが、あのですねえ、規則というのはその工場にあわせて規則体系の構造とか個々の規則様式も決まると思うのですよ。大企業の体系とか様式をそのまま小さな会社で使用しても、ちょっとというか全然あわないのではないでしょうか?」 担当者は組合委員長と同じことを言う。 | |
「じゃあ、どうしたらいいんだろう。つまりここに会社規則がない中小企業があるとしてだ、そこで会社規則を整備しようとするとき、どんな手順で進めればいいのかアドバイスをいただけないかな?」
| |
「一般論は言えないと思います。というかすべての会社はユニークであるわけですから、その会社にあった会社規則はすべてユニークなものになると思います。つまりお宅の会社の仕組み、仕事や情報の流れ、社員の意識、俗にそういったものを企業文化といいますが、それらを十分に調べて、それを尊重して作り上げるものなのです」
| |
「規則とか手順書が企業文化と関係があるのだろうか?」
| |
「文書というと広いですが、会社の規則いや正確に言えば規則の全体は会社のシステムそのものです。現在ではシステムと言うとコンピューターを使ったなにごとかを処理する仕組みに使われることが多いですけど、本来システムの意味は支配体制とか社会制度のことです。 会社の仕組みを決めた規則全体、具体的にはその全体をファイルした会社規則集は、会社のシステムそのものなのです。ですから会社規則はその企業の文化そのもののわけです。1本1本の規則も・・・あ、規則は1本2本と数えます・・・すべてその会社の文化、慣習を基に作られないと意味がありません」 | |
「うーん、おっしゃることはその通りだと思うけど、具体的にはそれってどうしたらいいということなの?」
| |
「会社規則あるいは手順書といってもいいですけど、あ、また専門語ですが、手順書とは法律で社内文書を意味します。そういう文書の専門家にお宅の会社の実態調査を依頼して、アドバイスをもらうというのがいいのではないでしょうか」
| |
「君が会社規則の専門家なんだろう。私からお宅の部長に依頼をすればこっちに来て指導してくれるのだろうか?」
| |
「正直言って、私では力不足でしょうねえ。実を言いましてこの仕事に就いてまだ1年少々なのです。私の師匠にあたる人が適任だと思います。ただ忙しい人だから、お宅に行ってくれるかどうかわかりませんが」
| |
「私が先方の上司に依頼するよ。その師匠って誰だろう?おれが知っている人なら、直接話してみるが・・」
| |
「品質保証課に佐田って人がいましてね、この人がこの工場では文書管理とか会社規則について一番詳しいです。佐田さんは歩く会社規則集なんて呼ばれていますよ」
| |
川田はその名前を聞いてギョとした。川田は佐田が嫌いなのだ。
| |
「その佐田と言う人に頼めば、こちらに来て指導してくれるのかな?」
| |
「直接言ってもご本人も対応が難しいでしょう。製造管理部の上野部長はご存じでしょう。上野部長は気さくな方ですから協力してくれると思いますよ。でも、私から話を持っていくのも筋違いでしょうから、川田部長から直接上野部長に依頼してもらった方がありがたいですね」
| |
「わかった。それじゃすまないが、とりあえず会社規則を作る規則を送ってくれないか。FAXだと文字が崩れちゃうから、コピーして郵便で送ってもらうとうれしいなあ。俺の会社の宛先は総務で聞いてくれ」 注:1990年頃、インターネットはまだ一般化していなかった。 |
●
●
●
翌日の午後、川田宛に宅配便が届いた。A4サイズで厚さが10センチ近くある。例の会社規則を送ってくれと頼んだものだなと思いつつ、開封した。すると中身は川田が頼んだ会社規則を作る規則だけでなく、福島工場の規則一式が入っていた。しかもしっかりしたパイプファイルにとじられている。川田はちょっとうれしくなった。●
●
これを参考にして一つ作ってみよう。
●
●
●
次の日曜日、また川田はひとり事務所にいた。福島工場から送ってもらった工場規則を読んでいる。工場規則の根拠を示す「工場規則管理規則」というものがある。まずこれが基本かと手に取る。A4で4ページくらいだ。規則としてはボリュームが少なく、文字数はあまりない。●
●
工場規則管理規則
第一条 当工場は、工場内の業務手順を工場規則として定める。
②工場規則には、規則、規定、細則の三種類を設ける。
(1)規則はカテゴリーごとの業務の概要を示し、決裁は工場長が行う。
(2)規定は規則に基づき、個々の業務の実施事項、手順などを定め、決裁は文書管理を担当する部長が行う。
(3)細則は規則及び規定に基づき、数表、リスト、及び詳細手順などを定め、決裁はその業務を担当する部長が行う。
・
・ ・ |
川田はまず第一条を読んで考えてしまった。今まで会社規則とか工場規則というものを見たことはあったが、その中身をしげしげと読んだことはなかった。いろいろなことに気が付いた。
まず②というのがポツンとあるのが気になる。間違ってワープロしたのだろうか? それとも①が漏れてしまったのだろうか? しかし素戔嗚の規則で、そんなポカミスがあるとは思えない。
それから細かく書いているのに驚いた。ひとつひとつのことをこのように規定というか定義していったら、それだけで大変なボリュームになる。
この会社で作る規則もこんなふうに細かく書いていったら、何人で何日くらいかかるものだろうか?
川田は立ち上がり給茶機でコーヒーを注ぐ。窓から外を見ると伊東委員長らしき人物が駐車場に車を停めて組合事務所の方に歩いていく。彼も大変なんだろうなあと川田は思う。
川田はしばし外を眺めていたが、意を決して机に座った。とにかく今日は何か一つ作ってみよう。考えるだけではどうにもならない。そう思ったとき、机の上にある先日のトラブルの際に現場からもらってきた払い出し伝票が目に入った。よし、今日は払い出し伝票の規則を作ってみよう。
川田は福島工場が送ってきた中から、規則の様式を探し出した。それをみると白紙にタイトルを書き、条文を書くことになっている。規則の末尾に、制定日と改定日それに決裁者書名がある。これに
注:天皇陛下のサインを
|
ながめているうちに、払い出し伝票のルールをこんなおごそかな規則で決めるのではなく、もっと下位の文書で決めるべきではないかという気がしてきた。いや伝票の使い方を決めたものを規則と呼ぶのはおこがましいから仮に要領書とでも名付けよう。
川田はワープロに「払い出し伝票要領書」と入力する。
それから払い出し伝票の目的を書かなければならないと考えた。目的とは何だろうか? 前工程から後行程に何という部品を何個、いつ引き渡したかということを表示することだろう。川田はそれを文章にするとどう書けばよいのだろうかと、またしばし考える。10分以上かけてなんとか数行の文章を書いた。
次に伝票の形を示す必要があると思う。川田は伝票をワープロで罫線を使って書き表す方法を知らなかった。写真を撮って貼りつけたいと思ったが、それはかなわぬことである。
注:当時まだデジカメはない。日本で最初のデジカメは1993年に富士フイルムが発売した。 |
次に伝票のそれぞれのマス目に何を書くのか、担当者欄にはサインをするのか押印するのか、使用済の伝票の処理はどうするのかも書かなければならないが、川田は運用の実態を知らないので手順を書けないことに気が付いた。
とはいえ川田は半分想像も含めて、払い出し伝票手順書をなんとかまとめてみた。A4サイズで3ページになった。それをプリントしてから伝票の現物を空白部分にノリで貼りつけた。
初めて作った規則あるいは手順書もどきではあるが、川田はちょっとうれしかった。なにしろここに出向して半年、ちっぽけではあるが初めての成果物だから。
●
●
川田は書き上げた払い出し伝票手順書を持って組合事務所に行った。昼前に伊東委員長の姿を見たのだからまだ事務所にいるだろう。●
案の定、組合事務所のガラス戸から中に伊東がいるのが見えた。
川田が近づくと伊東も気が付いてドアを開けた。
「やあ、川田取締役、お互いに休みなしですねえ〜」
| ||||
「まったくだ。もう演説の台本はできたんですか?」
| ||||
「なんとかね、読んでくださいよ。ご批判頂けたらうれしいです。 おっと、私ばかりが話しちゃいけないですよね。取締役のご用はなんでしょうか?」 | ||||
「いや、私も恥ずかしながら払い出し伝票の手順書というのをつくってみたんだ。委員長に読んでいただいてご批判を賜りたいと伺いました」
| ||||
「それじゃお互いの文章を交換して読書会でもしましょうか。 ちょっと待ってください、お茶を入れましょう」 | ||||
| ||||
「取締役、それじゃ、私からいいですか? うーん、なんというのかなあ、これは客間に飾っておくような感じですね。居間に置いて日常使うものではないですね」 | ||||
伊東はそんなことを言う。
| ||||
「どういうことでしょう?」
| ||||
「これは払い出し伝票の手順書という名前ですから、これを読む人は現場の作業者でしょう。その人はこれを読んだら、どこに伝票があるのか、伝票の書き方、ハンコを押すのかサインで良いのか、伝票をどうするのか、つまり現物に貼り付けるのか、箱に貼るのか、単に箱に放り込んでおくのか、使用済伝票を保管するのか捨てるのか、そんなことが分ることを期待して読みます。 もちろん現場の作業者ですから、長い文章はごめんです。でも、この手順書にはどこに伝票があるのかも、伝票の書き方も、書いてありません。 書いてあるのは、払い出し伝票とはなにものか、その目的は何か、そして様式が書いてあるだけです。 うーん、大変申し訳ありませんが、この取締役が書かれた手順書は現場で使えるとは思えません」 | ||||
「だいぶ手厳しいなあ。とはいえ、ご批評をありがたく頂戴いたします。 では私の番だが、なんというか、文章が口語、話し言葉そのものなんだけど、ちょっと演説としてはくだけすぎていないだろうか? 壇上で語るには軽すぎるような気がするなあ」 | ||||
「おっしゃる通りだと思います。でも私はわざとそういう文章を書いているのです」
| ||||
「わざと?」
| ||||
「そうです。こんな田舎町の組合幹部には、総評(下記注)のように社会主義に染まった現実離れした人なんていませんよ。総評の連中は、会社をつぶすことが目的じゃないかと思えますね。 しかしうちの会社に限らず私の知っている一般組合員も組合幹部もみな保守なんです。彼らはイデオロギーとか闘争なんて無縁ですし、難しい言葉を語っても理解できません。彼らの期待は、自分たちが働く会社がつぶれず、安定した賃金がもらえることです。私もそうですがね。 そんな人たちを前にして、鉢巻をして、こむずかしい理屈を語ったり、絶叫しても呆れられソッポ向かれるだけです。ですから自分の仕事や会社を少しずつでも改善していこうよ、それが積み重なればより良い暮らしができるよと普段着の言葉で語るべきだと考えているのです」 注:総評とは日本労働組合総評議会の略称 | ||||
「なるほど、私もその心で手順書を書かなくてはならないんだね」
|
ISOに関わっている人の多くは、会社の文書とはいかなるものなのかを理解していないようです。そういう人が「ISO文書」なんて言葉を作ったりしています。
本日の駄文は、そういった人たちに、会社の文書とはなにか、いかなる体系であるべきか、それはどのようなものを具備すべきかというようなことを教えるためのものです。
何ですって !? お前に教えられるまでもないですって?
おかしいなあ、ISO雑誌なんか見ると、見当違い、間違い、勘違いの文章があふれているのですけどね・・・
N様からお便りを頂きました(2013.11.06)
参考になります ISOを認証している組織も審査する側も、肝心の“文書”を見ているのか不安になります。前回、今回、参考になるというか身につまされるというか・・・ 参考になります。感謝! ところで「川田部長」はこのまま改心してゆくのでしょうか? |
N様 毎度ありがとうございます。 N様が勘違いしていることがふたつあります。 一つはストーリーは私が作っているのではなく、N様をはじめとする多くの方のコメント(ツッコミともいう)によって、流れ流れていくのが山田太郎君の時からの恒例です。 もうひとつは川田部長が改心するというと、ある時点で切り替わるというニュアンスかと思いますが、川田部長自身が日々の体験から学んで行くという解釈の方が適正かと思います。それに、そんな悪人じゃありませんよ。近くにいたら付き合いにくいスノブでしょうけど |
マネジメントシステム物語の目次にもどる
| Finale Pink Nipple Cream |
 前回までのあらすじ
前回までのあらすじ

