15.01.15
日本が太平洋戦争に負けて、アメリカ軍が日本を占領して彼らが新しい憲法を作ったとき、「前文」というのがあるのに日本の憲法学者が驚いたという話がある。それまでの日本の憲法や法律には「序文」も「前文」もなかった。いや、古事記には「序文」があるじゃないかとおっしゃる人もいるかもしれない。だが古事記の「序文」は本文が成立してから何百年もしてから後に、誰かが付け加えたという説が有力である。なお「日本国憲法は日本人が作った」なんていう説があるが、それはまったくのうそ800というか護憲主義者のファンタジーである。日本国憲法は初めに英文ありきであり、日本は拒否権もなくそれを受け入れるしかなかったというのが正しい。(注1)
憲法制定後相当な期間、憲法に疑義があるときは英語原文を読んで判断するという語句があったと聞く。だから平和憲法を守りましょうなんてのは、サヨクの妄想か扇動である。まして「9条にノーベル賞を」というのは敵国のスパイ活動にすぎない。
ところで憲法を守ろうとか護憲というのはどういう意味なのであろうか? 私は憲法違反したことはなく、憲法違反する人は裁かれるべきだと考えている。 護憲を叫ぶ輩が言うのは、憲法改正をしてはいけないということなのだ。 それっておかしくないか?
そう言えば数年前、憲法改正を主張した議員を憲法違反だと言ったサヨク議員がいた。お前は憲法9条を知っていても憲法96条を知らんのか!最近は、「憲法9条は変えてはならないが憲法1条は廃止すべきだ」と語るサヨクもいる。 それじゃ護憲も六軒もあるまいし、七賢人とも思えない・・( ゜Д゜)
|
わき道にそれてばかりではいけない。ここは憲法を論じるところではなく、ISO規格を棚卸するところであった。
ここで棚卸とは、期末に商品や全材料の在庫を数え資産を確認することではなく、欠点をあげつらうことである。
|
「序文」がそれほど文字数が増えているのは、重要だからなのか、あるいは単なる定向進化なのか、どうなのだろう? 定向進化であるなら、いつしか本文よりも膨大になり、オオツノジカの巨大な角のように生きていくのに支障になってしまうのだろうか?
日本国憲法はおいといて、本日は「序文」の中のこの0.2項について愚考する。いや序文はおおいに議論する価値がありそうだから、その第1回である。今回はタイトルについて考えたい。
「狙い」の原語は「aim」であるが、「target」とは違うのだろうかという初歩の初歩から始まる。
書籍の英英辞典やネットの英英辞典をみると、ターゲットとは具体的に達成したいこと・目標であり、エイムとは漠然とこうしたいというニュアンスとある。「あなたと一緒に住みたい」というのがターゲットであり、「あなたと幸せな家庭を築きたい」というのがエイムらしい。となると「環境マネジメントシステムの狙い(aim)」とあるのだから、これは「環境マネジメントシステムの目指すもの」程度なのだろうか?
もちろん人が作ったものは形あるものであれ、かたちないものであれ、思想であれ、なにかを目指そうなにかを実現しようという目的、狙いがあるのだろう。
だがちょっと待ってほしい(朝日新聞的表現である)
環境マネジメントシステムには狙いがあるのだろうか?
なにかを実現しようとして環境マネジメントシステムというものが作られたのであろうか?
基本に戻って考える。
環境マネジメントシステムとは何だろうか?
定義3.4では環境マネジメントシステムを「マネジメントシステムの一部で、環境側面を管理し、順守義務に適合し、脅威及び機会に関連するリスクに取り組みために用いられるもの」とある。
マネジメントシステムは組織が存在すれば、組織の属性として存在する。システムとはそもそも社会制度とか支配体制という意味であり、システムを持たない社会は存在しないというか、システムを持たないものは単なる存在であって社会ではない。
「社会」とは元々西欧語「society」の訳である。 「society」とは英英辞典によると「considered in relation to the laws, organizations etc that make it possible for them to live together」とあり、直訳すると「ルールに基づく関係、共同して生きるための組織」である。複数の人間が生きていても相互関係がなければ社会ではなく、社会でなければ社会制度(システム)はない。 西部開拓時代、人里離れて暮らす金鉱探しやハンターは社会には属していなかったと思う。もちろん獲物を売買するときは他の人間と接触しただろうが。だが金鉱探したちはお互いに離れ暮らしていても共通のルールを有していて彼らの社会は存在していたはずだ。 |
「環境マネジメントシステム」を「用いられるもの」としているが、そもそもが「マネジメントシステム」の「part」であるから「用いられる部分」というのが適切ではないのだろうか。
|
では今のことを基に序文の0.2を考えると、「環境マネジメントシステムの狙い」というのはなんか表現がおかしいような気がしてくる。実は0.2項の本文を読むと、「環境マネジメントシステムの狙い」ではなく「環境マネジメントシステム規格の狙い」が書いてあるのだ。だからこのタイトルを「環境マネジメントシステムの狙い」でなく「環境マネジメントシステム規格の狙い」とすればまったくおかしくない。
即断は禁物である。冷静な対応が求められる。(これも朝日新聞的表現である)
なぜ「環境マネジメントシステムの狙い」なんておかしな、というか間違ったタイトルを付けたのだろうか?
この間違いは日本語訳だけでなく英語原文もそうなのだ。
とすると規格を書いた人たちが環境マネジメントシステムについて勘違いしたのだろうか? いや完璧に間違えていたということもありそうだ。
タイトルが「環境マネジメントシステム」でなく「環境マネジメントシステム規格」あるいは「この環境マネジメントシステム」なら意味が通るような気もする。そうすれば一般名詞としての「環境マネジメントシステム」ではなく、ISO規格のことであるという言い訳も通るのではないか。
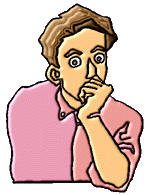
それに関連するが、英文は「Aim of an environmental management system」である。
「an」の意味するところが私には解らない。
次のようなことがあるのかもしれない。
- 推定その1
すべての組織は環境マネジメントシステムをその属性としてもっているから、たくさんの組織に付随している環境マネジメントシステムのひとつを例にとって、その目的について論じているのか?
- 推定その2
環境マネジメントシステム規格には多々ある。例えばISO14001とかエコステージとかエコアクション21といったものだ。だからこのanはその中のひとつであるISO14001を意味するのだという発想もあるかもしれない。だがそれならtheとかthisではないかという気もする。
- 推定その3
単純にstandardという語を落してしまった。それもありがちといえばありがちですね。0.2項本文で「the purpose of this international standard」を主語として始まっていますからね、
タイトルのほうにスタンダードを書き忘れたのかもしれません。それがデフォだ、スタンダードというのかも?
まあダブスタということで
アレ、変なことに気が付いた。Aim of と purpose of は同じ意味だったのだろうか?
というのはタイトルは「Aim of an environmental management system」なのだが、本文は「the purpose of」を語っているのだ。詳細は英語原文読んでください。
でもそうすると規格の文章のレビューが不足しているって言えませんか?
そうだとすると、新たな問題が・・・
さて、ともかくこの0.2のタイトルがおかしいということはおかしくないようだ。そして、そのおかしさはタイトルにとどまらず、序文にとどまらないような気がする。序文だけでなくISO14001全体も心配です。だって「環境マネジメントシステム」と「環境マネジメントシステム規格」の違いを分からない人たちが、もとい、違いを気にしないような人たちが作った規格を、あなたは立派だと思いますか? 信頼できますか?
序文からして、これほど基本的、根源的な間違いをしているので、4章の要求事項を真面目に読む気が失せたのは私だけだろうか?
「序文」がだめなら「本文」もダメというのは日本国憲法を見ても明らかです。
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した(日本国憲法前文 第2節第1行)」
もう、これは完璧、完全、絶対の間違いです。現実とかけ離れていることは明白です。東アジアには平和を愛する国ばかりではありません。戦闘状態にない日本から、罪のない日本人を誘拐した北朝鮮、日本を足蹴にする教育を一生懸命している韓国、ウソの歴史を真実だと発信している中国、いやはや、どこに平和を愛する諸国があるのでしょうか? 反面、日本を貶め、搾取し、侵略しようとする諸国には事欠かないようです。
もし日本国憲法についての愚考を読みたいって方がいるなら私の憲法判定表をご覧ください。
まあ、いないでしょうけど
「序文の、それも環境マネジメントシステムって言葉ひとつに、イチャモン付けんじゃねー、こまけーんだよ」という声が聞こえてきそうだ。
そうだろうか? ここをちゃんと理解した人がちゃんと記述していないなら、そんな規格は土俵に上がるべきじゃありません。
「なあに、かえってこのくらい穴があったほうがいいんだ」とおっしゃる方がいるかもしれません。おっとこれも朝日新聞的表現でしたね。
ちょっと気になったのだが・・・・定義は3章にある。だからそれ以前にある「序文」や「背景」は定義された意味で使われていないということはあるのだろうか?
おっと、だとしても意味が通じないことには変わりないのだが・・・
注1: |
参考文献 大森実「マッカーサーの憲法」、講談社文庫、1981 西 修「日本国憲法の誕生を検証する」、桐原書店、1994 西 修「日本国憲法を考える」、文春文庫、1999 島村力「英語で日本国憲法を読む」、グラフ社、2001 |
注2: |
ISO規格は発行後5年を経過する前に、規格の必要性が継続しているか、必要性が継続しているならば規格は改正せずに維持することを確認することで良いか、それとも改正する必要があるかを検討する決まりになっている。
| 注3: |
あなたの持っているISO規格対訳本の汚れは要求事項の章だけで、序文や付属書の部分はきれいであることに1000クレジット賭けよう。
|
うそ800の目次にもどる
ISO14001:2015解説に戻る