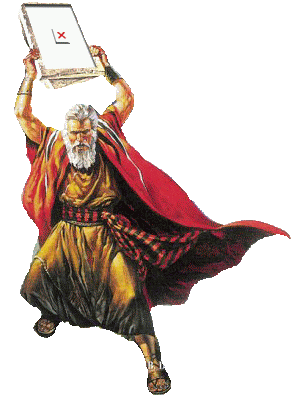
和文は水が水質に変わったが、原文はwaterのままで変わっていない。
これについて偉大なる寺田さんは「水は(物質としてではなく)媒体としての水を差している」から水質に変えたと解説している。
「ISO14001:2004要求事項の解説」(2005、寺田博・吉田敬史 共著)p.42
果たして媒体としてではない水を無視して良いのかという疑問もありますが、偉大なISOの予言者に疑義を呈しては命が危ないから止めておきます。
*これはISO14001:2015のDISを基に2015/6/2に書いたものである。
今後、改定や正式版が出れば見直ししたいと思うが、しないかもしれない。そこのところはご了解してお読みいただきたい。
大気、水、土地、天然資源、植物、動物、人及びそれらの相互関係を含む、組織の活動を取り巻くもの 参考 ここでいうとりまくものとは、組織内から地球規模のシステムまで及ぶ。 (ISO14001:1996より)
|
大気、水質、土地、天然資源、植物、動物、人及びそれらの相互関係を含む、組織の活動をとりまくもの 参考 ここでいうとりまくものとは、組織内から地球規模のシステムまで及ぶ。 (ISO14001:2004より)
|
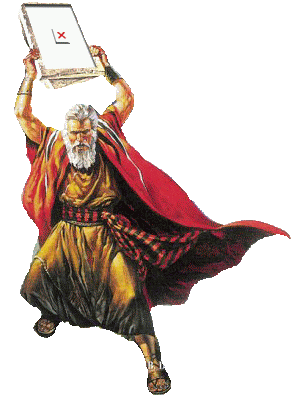
大気、水、土地、天然資源、植物、動物、人及びそれらの相互関係を含む、組織の活動をとりまくもの。
(ISO14001:2015DISより)
|
某ISOTC委員は、「システムとはインプット、プロセス、アウトプットだ」と語りました。そのお考えは間違っていると思いますが、仮にそうだとしたらシステムとは外部との関係そのものです。 システムの本当の意味は社会制度とか支配体制のことです。もっともそうとしても人間同士の相互関係に他なりません。 |
注: |
1986年のISO8402では品質を「製品又はサービスが、明示してある又は暗黙の要望を満たす能力として持っている特性の全体」でありました。昔の方がハッキリしていたようです。 時代とともにあいまいに、霞がかかってくるのはどうしてなのでしょうか? |
環境の定義 環境の定義を読まさせて頂きました。今頃何を言っているのかと思いました。 ISO14001の出発点は、環境の定義ですよね。私は長らく品質・環境の管理責任者をしていました。環境側面を「課題」若しくわ「仕事」に置き換えて環境側面を捉えていました。著しい環境側面は、品質関係ならISO9001で対応。その他の重要な課題は色々あります。もちろん自然環境は含まれますが、その他に経営環境も含まれなんでも有りで、ISO9001も14001に取り込めるとは思いますが、会社の都合でそうはいかないところもあります。将来はISO14001一本でなれば良いとは思っています。 |
CORON様お便りありがとうございます。 ご意見が私の書いたものに対してポジティブなのかネガティブなのか、いささか理解に苦しみますが、それはおいといて、ご見解についてコメント申し上げます。 一般に「環境」といっても、大気、水、土地、天然資源、植物、動物のような人間に関わらないものという意味合いもありますし、経済環境、地域環境、家庭環境、職場の雰囲気という人間関係的な意味もあります。それは英語でも同じようで、ISO14001の定義の後半の「人及びそれらの相互関係を含む」が前述の環境のどこまでを包含するのかは、規格文言からだけでは私はわかりません。ですからこの文章から事業環境すべても含まれるという捉え方もあるかもしれません。しかし、私はそうではないと考えます。 ISO14001規格の守備範囲はどこまでかと考えるには、規格文言だけでなく、EMS規格は何のために存在するのかということを考える必要があります。ISO14001は遡ればリオ宣言になります。1992年にリオでの環境と開発に関する国際会議で想定していた環境は、組織をとりまくものすべてではないと私は考えます。リオ宣言を思い出してほしいのですが、そこでは27原則まで並んでいました。後半の方には女性の役割、パートナーシップ、伝統の尊重などもありますが、その意図は「人類は、自然と調和しつつ健康で生産的な生活(第1原則)」でした。「自然」と訳された英語の「nature」は日本語の「自然」ではなく「人間によってコントロールされない物質界のすべて」ですから、リオ宣言が意図していたのは広義の環境でないのは明白です。ですからビジネス上の人と人、企業と企業の関係などはnatureではなく環境に含まないと思います。 これらを踏まえるとISO14001での環境の範疇は「自然」との関わりであり、先述した前半であるとみなすべきでしょう。 そして規格の意図である「遵法と汚染の予防」も当然、「環境遵法と環境汚染の予防」となるでしょう。もっともここでも広義の環境を入れるとまた元の木阿弥ですね。狭義の環境と言いましょう。 御社では環境とは組織をとりまくものすべてであるという認識とのこと。それはそれでひとつの解釈であり、どうこういうつもりはありません。「自らが想定した環境」に対応した環境マネジメントシステムを構築し運用すればよいと思います。もっともそのときは広義の環境になりますから、環境該当法規には営業活動では商法、民法、会社法、独禁法、外為法その他、開発には知的財産関連、製造物責任その他、職場では労働三法、労働安全、人権関連などが関わります。つまり事業に関わるものすべてということになります。 当然ながら、その場合の環境側面はおっしゃるように品質側面とか安全側面だけでなく、営業に関する環境側面、それは環境側面ですが契約に関すること、お金の授受、製品の納入などを含むことになります。もちろん開発関連でも職場関連でも同様です。 そこまでではなく、大気、水と言った自然環境だけでなく少し範囲が広いんだよという程度問題なのでしょうか? そのときはそれなりになると思いますが、いずれにしても環境側面も環境関連法規制もそれに見合ったものになるのでしょうね。 それと私の基本的考えというかISO認証に対するスタンスは、企業ありきというものです。事業推進にあたっては事業環境をとりまくものすべてが対象です。それをすべてISO14001の考え方でできるのかとなると、できないでしょう。結局ISOMS規格は標準化なのです。独創性、企画、開発ではない創造ということについてISOMS規格はお門違いだろうと思います。 もうひとつISO9001にしても14001にしても認証規格です。認証とはcertificateですから「一定基準を満たしていると認めること」。ですからそれを基に会社の仕組みを作るという発想はありえません。事業推進のためには様々な機能が必要であり、ISO規格は対象とする分野の要素について具備すべき条件を規定したものにすぎない。結局ISO規格を基になにをするということはできない。仕様だけではものはできません。 それから「将来はISO14001一本でなれば良い」(原文ママ)とおっしゃっていますが、ISO26000に比較すれば守備範囲は東京湾と太平洋くらい違いますし、ISO26000だって企業経営から見たらほんの一部であるわけです。ここはひとつ、ISO14001は単に組織の環境管理機能が具備すべき最低限の基準程度に考えた方がよろしいかと思います。 じゃあ、私が書いた環境の定義という文はいったいなんだとなりますか? 私は規格改定のたびにゆれる考え方、それは原文もありますし翻訳もありますが、それを揶揄しているだけです。おっと、環境の定義だけでなく、ISOMS規格そのものが対象ですけど |