15.10.19
今でも、つまり21世紀になって15年もたった2015年末でも、著しい環境側面を点数で決めろという人がいる。驚くべきことである。平成の世で、キリスト教徒は磔だとか、身分をわきまえろというような時代錯誤ではないか。最近のこと、以前関わっていた会社でISO14001認証しようとしてコンサルを依頼した。そのコンサルは環境側面を点数で決める方法を指導したそうだ。それを聞いたとき、なんでいまどきISO認証するの!と口から出そうになったが、その会社としては2015年版になると難しそうだから、今のうちに認証しておけば自動的に改定版に移行できるだろうと読んだらしい。認証してもどんなごりやくがあるのかはなはだ疑問ではあるが、まあそれはともかく、本日はそういうおかしな点数法を唱える人をフルボッコ、いやとどめを刺すために書く。
4半世紀以上前になるが、私が生産現場にいたとき、小集団活動に参加していた。毎年期首に職場ごとの改善テーマを決めて問題を解決して品質や生産性を向上させるってのがセオリーであり、期末に目標を達成すると、そのグループは表彰されて大きな顔をしたものである。
ではそこから話を始める。
今ライン不良が継続的に発生していて、不良を減らす対策をしようとしたとする。 不良の状況は下記のようであった。 |
|
さて他の条件が変わらないとしたら、どれから手を付けたらよいだろうか? 一番素直な考えでは月の損害額の大きなものから手を打つということだろう。 ひと月の不良による損害額を計算すると |
|
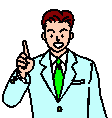
|
この場合、計算結果一番金額が大きい不良Dの対策から取りかかろうと判断しても間違いはないだろう。 あるいは場合によっては、例えばDは技術が確立しておらず現場の手におえないから、次善の策としてBから始めると決定してもそれはそれでかまわない。間違っても損害の少ないAから始めようという発想はないだろう。 |
え、あまりにくだらないことを語っているとおっしゃる。
世の中で、いや会社でも微分積分とか4次方程式を解くなんてことはめったにありません。研究所でもないかぎり多くの場合、一次方程式とか少し難しくても連立方程式を使えば解決することが多いのです。
そして現実には問題を解くのに一次方程式程度使えばよいのに、それさえ考えつかないことが多いのです。あなたも経験あるでしょう?
しかしどんな問題とか対策において上記の決定方法が使えるわけでないのはもちろんです。
上記の不良対策の優先順序の決定においては、対策をするかしないかを決定する自由(権利)が企業にあるからこの方法が使えるのです。選択の決定権がない場合には、この方法は採用できません。
どんな場合かって?
ではいきます。
ある企業で次のような課題があった。
- 課題A
市条例で10か月後から騒音規制が厳しくなる。その対策として機械更新をするか防音壁を作らなければならない。
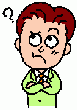 困ったぞ!
困ったぞ!
- 課題B
当社は省エネ法の対象であるが、既に乾いたぞうきんを絞っている状況で、これ以上の削減は難しい。
困ったぞ! - 課題C
お得意様から今後、その会社の敷地内の駐車場に停めるにはエコカーでなければならないというお手紙を頂いた。しかし現在当社ではすべての社有車は通常のガソリン車であり、このままでは客先の中に入れることができず外の駐車場に停めなければならない。
さて、困ったぞ!
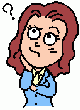
- 課題D
当社のPRTR報告を集計するためには従来はエクセルで計算していたが、省力のために情報システムで自動的に算出できるようにしたい。しかし街のソフト屋に相談したら軽く1千万を超えそうだという。
これは大金だ!困ったぞ
人間は誰でもなに物かが欲しいとか何事かをしたいという願望があり、それにはきりも限りもありません。個人でなくて会社でも同じです。これが欲しい、こうしたい、こうすれば改善になる、こうすれば今より儲かる、そんなものばかりでしょう。でもサイフの中のお金には限りがあります。欲しいもの全部を手にしようとすると、塀の中に入るか欲求不満で格子つきの病院に入ることになります。どちらも嫌なあなたはまっとうなことをするしかありません。
さて、工場長であるあなたはどのように判断すべきでしょうか。つまり、どれをやれ、これはしないと決定するでしょうか?
上記課題の中で実行する優先は何で決まるでしょうか?
まさかあなた、それぞれの課題についていくつかの側面で点数をつけてプライオリティを考えますか?
例えば
| 法規制 | 客先要求 | 品質改善 | 費用削減 | 安全 | 総合効果 | |
| 課題A | 5 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 |
| 課題B | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 |
| 課題C | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 課題D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
じゃあ点数の一番大きな課題Dを実施して、課題Aと課題Bは翌年にまた検討することにしよう・・・
あなたはそんなことを絶対にしないはずです。 もしそんなことをしたら、手が後ろに回ります。 | 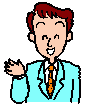 |
非常に簡単ですよね。
法律は否が応でも守らなければなりません。もちろんいろいろな理由で法律を守らない人も多いです。排ガス規制を満たすエンジンが作れないときに、現在の我々の技術ではできないから恥ずかしながらディーゼルエンジンの車を出すのは諦めようという判断をした会社もありました。しかしまっとうな手段ではなく、排ガス検査のときだけきれいに燃焼させ、通常走行時には排ガスが汚くても燃費を良くしようという
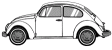 悪魔のささやきに負けてしまった車メーカーもありました。いや私はフォルクスワーゲンのことを言っているのではありません。悪魔でも仮定です。
悪魔のささやきに負けてしまった車メーカーもありました。いや私はフォルクスワーゲンのことを言っているのではありません。悪魔でも仮定です。上記課題において法律は守らなければならないのですから、なにをおいてもまずは課題Aを実施するのは必然です。そうしなければ操業できないのですから。もし資金や技術その他の理由によって対策できないときは、廃業するというのも潔いかも知れません。
あるいは次善三善の策として、市と話し合ってなんとか施行時期に猶予をお願いするとか補助金をお願いするというのもありかもしれません。いずれにしてもなんらかの手を打つはずです。
課題Bについてはどうでしょうか?
省エネ法で定める削減ができなくても、実は罰則はありません。罰則がなければ法を犯しても良いということはありません。しかしこの法の意図や規制内容を考えなければなりません。景気動向とか市場の変化によっては目標を満たせないことはままあることです。ですから今年は無理ですが二年後までにはちゃんとしますよという報告をするという対応もあります。法は守らなければならないと考えているあなたのことですから非常に心苦しいでしょうけど、ここはじっと我慢の子
課題Cはどうするか?
もしどうしても客先駐車場に停めないとならないなら、しょうがありません。とりあえずは1台エコカーをリースしましょう。そしてあの会社にお邪魔するときはエコカーで行くんだということを言明しましょう。
そうではなく外の駐車場に停めても問題ないならエコカーを購入することもなさそうです。あの客先を訪問するときは構外のコイン駐車場に入れろと営業マンに言っておきましょう。
課題Dは?
通常ソフトが使えなくなるのはOSが変わるときでしょう。
| OS名称 | 発売年 |
| windows 3.1 | 1993 |
| windows 95 | 1995 |
| windows98 | 1998 |
| windows ME | 2000 |
| windows XP | 2001 |
| windows VISTA | 2007 |
| windows 7 | 2010 |
| windows 8.1 | 2012 |
| windows 10 | 2015 |
1000万かかりそれを6年で回収するには、年間160万円の人件費を削減できなければならないのです。1時間1万として160時間削減できなくちゃ意味がありません。
お宅の会社では160時間、つまり一人1か月まるまるかかっていますか?
私が2000年頃エクセルで計算していた時、かかった時間はまあ二日三日でしたね。それじゃ1000万回収するには60年かかります。
PRTR法ができる前から福島県にはPRTR条例があったのだよ。
「よしウチはPRTRの計算に情報システムなんて作らない。エクセルで計算しろ」というのが経営判断ちゅうもんであります。
そもそも回収できないことをしようってのは頭がおかしいのです!
くだらないたとえ話でしたけどお分かりいただけましたでしょうか?
言いたいことは、法律で決められていることや客先要求など、やらなくちゃならないことはしなくちゃならないってことなんです。それはお金には換算できないし、かかる費用を比較することは意味がないということです。世の中には絶対的なものと相対的なものがあり、相対的なものは点数で比較できても、絶対的なものはイチ・ゼロしかありません。
不良対策や改善は相対的なものですから何をするか選ぶことができ、そのためには効果をお金に換算して、効果が大きい方から手掛けていくというのは当たり前のことです。
しかし法律で定められていることとか、安全上手を打たなければならないことは絶対です。個人や企業が好きだ嫌いだということはできません。ですからお金に換算する意味もなく、改善効果を比較することも意味がないということなのです。
そもそも環境側面とは何か、基本に帰って考えてみましょう。
環境側面てなんですか?
ISOのプロフェッショナルであるあなたは、そんな基本的、初歩的なことはもう十二分にご理解されていますよね。環境側面とは管理手順や基準を決めてしっかりと管理しなければならないものです。それぞれの環境側面について文書化した手順を作ることもあるかもしれないし、教育訓練をして担当者はいつでも適正な仕事ができるようにしなければなりません。そして環境側面の管理状況は常に監視して逸脱のないようにコントロールしなければなりません。言い換えると環境側面とはそのようなものであり、それ以外の何ものでもありません。
確認しておきますが、環境側面は改善対象ではありませんよ、管理対象です。なにを改善対象とするか否かは、その組織が決めることであり、環境側面から取捨選択するのではありません。環境目的・目標の決定にあたっては環境側面も考慮しろと規格にはありますが、環境側面を改善しろということは過去からのいずれの版にも書いてありません。
おっと、世の中には環境側面と環境目標の違いを理解していない審査員も企業担当者も多いのです。 困ったことです |
つまり、環境側面を決めるには必要なお金の比較とか改善効果を考えることはなく、法規制とか事故の危険を考えて、やらなくちゃならないことを著しい環境側面に決めるのでしたよね。
そのような絶対にしなくちゃならないものを決めるに当たって、お金に換算する必要はないのですから点数法というのは元々無縁というかお門違いなのです。考慮することはただふたつ、法規制を受けるのか?、安全に関わるのか? というだけです。
法規制に関わるのか否かを点数で決めようってのは、もう社会人として異常です。そんなこと法律に書かれています。そして安全にかかわるのかということを点数で決めようとする前に、過去の事故、ヒヤリハット、そういうことを調べるべきでしょう。
! |
リスクとは発生確率と影響の大きさの積とか語る人は多い。しかし最近はリスクというものに発生確率は関係ないという意見が多い。安井至などは発生する恐れがあるなら、必ず発生すると語っている。それを前提にどうするかを考えるのだ。 東日本大震災以降、私もそう思う。 100年に一度の大雨もいつか必ず来るし、1000年に一度の大地震も必ずいつか起きる。 20年ほど前、私がタイで仕事をしていたとき、ものすごい豪雨があり、新聞とかタイ政府はこんな雨は1000年に一度しかないといって1000年雨と呼んだ。ところが、次の年には前年以上の豪雨があった。そのときはなんと2000年雨と呼んだ。これはあまり関係ないか・・ もっとも頻繁に起きる程度の地震には対策するが、東日本大震災規模の地震が起きたら、諦めてひたすら念仏を唱えて最期を迎えるという覚悟もまた立派なことだと思う。私はそういう覚悟がないので大地震の時どうするかを常に考えている。 地震ではないが、中国は侵略しないと信じて日本の防衛に反対する人もそういう発想のようだ。どんな宗教を信じてもかまわないが、まわりの人を巻き込まないでほしい。 |
ダメ押しで具体例をあげましょう。
廃棄物処理法は最高の刑罰が五年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金で、水濁法は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金だ。廃棄物処理法の方が水濁法よりも罪が重い、だから廃棄物処理法は絶対に守らなければならないが、水濁法はやむをえなければ違反しても良いなんて発想は・・・
えっ、あなたはそういうお考えですか?
ここまでいってもまだ環境側面は点数で決めるのだとおっしゃる審査員、コンサルがいるのなら、その方がたは策士策に溺れた哀れというか愚かというか環境管理には不要な人間でしょう。人間ではなく妖怪か廃棄物かも?
💢 |  1997年、環境側面の決定方法を○○方式と揶揄されている○○認証機関で環境側面研修コースを受講したときのこと、講師がいいました。 「みなさん、数字で計算すると法規制を受けるものが漏れることがあります。ですから法規制のかかるものは無条件で著しい環境側面にするという仕組みにするとよいでしょう」 今でもそのアホ講師のご芳名を覚えている。鈴木某といったなあ〜 その方は自分が語っていることの矛盾に気がついていないのだ。あれから20年、今はまともになったのか? ご存命かどうかは知らないが |
しかし、そうするとまた別の疑問が沸いてきました。 「環境側面とは決定するもの」なのでしょうか? ISOマニアのあなたから突っ込みを受ける前に、言い直させてください。 「著しい環境側面は決定するもの」なのでしょうか? | ? |
2004年版では
「4.3.1b」環境に著しい影響を与える又は与える可能性のある側面(すなわち著しい環境側面)を決定する。」とあります。
2015年版においても和文は
「6.1.2 組織は、環境に著しい影響を与える又は与える可能性のある(すなわち、著しい環境側面)を決定しなければならない。」
いずれにしても「決定する」という記述になっている。では「決定する」とはどういうことなのか?
「決定する」の日本語の意味を再確認しよう。
【決定する】[動詞]
1 |
物事をはっきりと決めること。物事がはっきりと決まること。また、その内容。「会議の日取りを―する」「―権」
|
2 |
裁判所が行う判決以外の裁判。口頭弁論を経ない点で判決と異なり、個々の裁判官がなす命令と区別される。「公訴棄却の―」
|
しかし環境側面は関係者が議論すれば決まるものでも、裁判官若しくは権威者が決定すれば反論の余地なく決まってしまい、それで支障がないものでもないように思える。環境側面はそういう性質ではないのではないか?
前述したように環境側面とは法に関わるとか安全上問題であるものであり管理しなければならないものなのだから、「決定する」という言葉は不向きのように思える。
その性質なり他との関係(法規制を受けるとか)を調査すれば、自動的に決まってしまうものではないのだろうか? そのような法律を読んで規制対象か否かを調べることを、日本語で「決定する」という語を使うのは不適ではないのだろうか?
伝家の宝刀、原文を確認しよう。
ISO14001 6.1.2
The organization shall determine those aspects that have or can have a significant impact on the environment, i.e. significant environmental aspects.
日本語訳で「決定する」と訳されている語は「determine」である。ではこの語の意味を英英辞典ではどのように説明しているのか? ロングマン英英辞典を利用した。
1 | to find out the facts about something [= establish]: ex. Investigators are still trying to determine the cause of the fire. 「調査員はまだ火災原因を特定しようとしている」。 ex. The aim of the inquiry was to determine what had caused the accident. 「調査目的は事故原因を究明するためです。」 |
2 |
if something determines something else, it directly influences or decides it: ex. The amount of available water determines the number of houses that can be built. 「利用可能な水の量がそこに建てることできる家の数を決定します。」 |
いずれの文例でも「調査した結果なにかが分る」あるいは「調査した結果なにかが決まる」という意味で用いている。その判定には人間の意図、恣意、思惑が介在することはないようだ。この「determine」の意味を示すには「決定する」は不適ではないだろうかと思う。
ところで決定するといっても、私の知っている英単語では「determine」と「decide」がある。
このふたつは意味が違うのか、どんなふうに違うのか?
違いを示す例文を見つけた。
Decide is to choose or make a decision. Determine means to figure something out.
「decisionは何かを決定すること、determineは問題を解決すること」。
つまり「decide」は目的や状況を考慮して「決心して決めること」であり、他方「determine」は「なんらかの課題を解決すること」なのです。その結論は個人的見解ではなく客観的証拠にもとづいて必然的に導き出されるという意味でしょう。
ちなみに消防庁の規程では火災原因を究明することを「火災原因の決定」という表現を使っている。ただしこの場合は「調査員は、原因決定資料の発見入手及び被害状況の把握に努め、すべての火災に対しその実況を綿密詳細に見分しなければならない。」というような文章が前後にあり、調査結果でてくるものと読める。つまりこのような文脈において用いられる「決定する」はまさにdetermineなのだ。JIS規格の形容詞の付かない単なる「決定する」とは、そのニュアンスは大きく異なるのではないだろうか。翻訳されたJIS規格の文章では、前後になにもなく「決定する」だけがあり、単純に「俺が決めるんだ」と読める。
そんなことを考え合わせると、ISO14001で「著しい環境側面を決定する」と訳したのは、はっきりいって誤訳であろう。本来ならコンテキストから本来の意図が通じるように語を補うか、別の言い方をすべきであったと考える。
前者の例としては「調査して著しい環境側面か否かを決定する」。後者の例としては「著しい環境側面に該当するかを判断する」というようなものがあるだろう。
上記はとりあえず考えたものであり、もっと良い言い回しがあったらご提案願います。
いずれにしてもわざわざ愚かな人間が決定するまでもなく、著しい環境側面はアプリオリとして存在するように思える。アプリオリという表現はおかしいというかもしれないが、それなら同じ状況においても企業によって目的の決定は異なることがあっても、著しい環境側面は異なることはないという言い回しではどうだろう。そもそも担当した人によって環境側面が異なるなら、それをもって不適合になるはずだ。なにしろ環境側面とは法規制を受けるものや事故の恐れのあるものなのだから。
とりあえず以上で本日の出し物である「環境側面が計算ではいけないわけ」の講釈を終わります。点数法にトドメをさすことができましたでしょうか?
もし、私の論に間違いがあるとか見当違いも甚だしいとお怒りの方がいらっしゃいましたら、ぜひとも議論をしたいと思います。まあ議論するまでもなくそういった方のお勤め先では、きっと法違反が起きたり事故が起きたりすると思います。
おっとあなたが審査員である場合は、法違反や事故が起きてもあなたが困ることはないかもしれません。しかしISO14001の意図が遵法と汚染の予防であるわけですから、あなたが良い審査員ではない、審査員に不向きであるという、あなたにとっては人格を否定されることになるでしょう。それの方がきついんとちゃいますか?
環境側面を決定するのに点数法を使ってはいけません。
使わなくても良いのではなく、使ってはいけないのです。

これからも環境側面を点数で決定する方法を説明する人たちが生き残るほうに、500クレジット賭けよう。
たぶん、いや決して私がこの賭けに負けることはないだろう。しかし私が賭けに勝ってもうれしくはない。
じいじ様からお便りを頂きました(2015.10.20)
もしかして本日の結論の冒頭に「著しい」が抜けてませんでしょうか? 本文中でも、突っ込まれる前に云々とあったので、どうしようか迷ったのですが、あえて、ご連絡差し上げた次第です 毎日「ダジャレ」を楽しみにしておりますとともに、うそ800の週2回の更新も楽しみにしております うそ800は、およそ3年弱かかりましたが、全部読み終えました 大変勉強になりました。おかげさまで、私は社内では異端児になりました(笑)が、同調するものもちらほら出始め、そのうち天動説から脱却するであろうと期待しております 今後も期待しております |
じいじ様 お便りありがとうございます。 私は間違いなくじいじ様より年輩だと思いますが、いまだじいじと呼ばれる立場になってないのが残念です。もっともこれは私の努力ではなく、息子娘の努力に期待したいところですが、我が豚児は期待に応えてくれません。 さて、「著しい」が抜けていることは、おっしゃるとおりです。じいじ様だけでなく、たこ親父様からも厳しい突っ込みを受けました。お許しください。 たこ親父様への回答にも書きましたが、実際問題として私たちは環境側面を調べて、そこから著しい環境側面を決定するぞ!なんてことはしていないはずです。そもそもが規格に書かれた手順と現実は異なると思います。まあ、そんなこと言ってもしょうがないですが。 3年もかけてうそ800をお読みになられたとは、私の方が感動してしまいます。 正直言いまして退職してからは以前から付き合いのあった人から相談が年に数回ある程度なので、現実の審査でどんなやりとりがあるのか、なにが旬の問題なのかわかりません。そういう意味ではもうISOに関することを書いてはいけないのかもしれません。原監督じゃありませんが、引退時期を考え中です。 |
たこ親父様からお便りを頂きました(2015.10.20)
2月に初めて連絡したものです。その節は文字化けしていたにしたのにもかかわらず、丁寧にフォロー頂きありがとうございました。今回の環境側面の件、従来から悩んでいた案件の1つであり、これまでの関連貴記事と合わせとても興味深くまた参考になった次第です。 早速ですが質問があります。記事の中の「環境側面とは管理手順や基準を決めてしっかりと管理しなければならないもの」は、いわゆる「著しい環境側面」(4.3.1のb))に相当しているように思われるのですが如何でしょうか? またそうすると、ISO規格でいう第1段の環境側面(4.3.1のa))はどのように考えますか? 規格ではこのa)の第1段環境側面はシステムを適用する範囲内であれば原則「すべて」となり、影響の軽重は関係なくなり膨大な項目になって現実的でないと思っています。因みに私は過去の審査機関の監査において、作業者間の連絡に使うPHSの電力について環境側面に挙げられていないとの指摘があり、これに対し挙げる価値は無いと一人やりあったことがあります(賛同者はありませんでした)。 尚、小職所属の組織では点数方式を最初から今も継続しており、周囲からは何の疑問も上がっていません。また、前回の審査機関の審査では、改善の機会と称して「有益な環境側面」を捉えておいたほうがよいでしょう旨の審査報告書を受けました。 以上 |
たこ親父様 毎度ありがとうございます。 おっしゃるように「著しい」が抜けています。抜かしたというのが本意に近いのですが。 そもそも我々は日ごろから仕事をしていて、無意識のうちに著しい環境側面を把握していると思います。というか、そうでなければ事故や違反を犯してしまいます。それでわざわざ著しい環境側面を決定することも必要でないと同様に、環境側面を特定するという行為が意識的に行われているとも思えないというのが私の本音です。 ISO規格文言からたどれば、環境側面を特定して、その中から著しいものがどれか!と決定するのでしょうけど、それは実態と異なると考えております。 ともあれ、著しいが抜けていると同様に環境側面を特定するのはどうするのかとなると思います。 現実問題として、会社の機械、器具備品、存在するものすべて、会社の業務すべて、一挙手一投足すべてが環境側面であろうと思っています。具体的には機械は法に関わらなくても音を出さなくてもすべて環境側面であるのは間違いないですし、事務作業においても電卓、ボールペン、電池、クリアホルダー、出張、外出、顧客回り、銀行取引、発注という行為、駐車場、警備業務、すべからく環境側面であることは間違いありません。 そういう現実を踏まえると環境側面を特定するというステップは無用のように考えています。 たこ親父様が例に挙げた「作業者間の連絡に使うPHSの電力」は環境側面であることは間違いありませんが、著しくないことも間違いなく、わざわざとりあげて「著しくありませんでした」というのは審査員の、機嫌取りでしかなく、無用・無意味でしょう。私なら即認証機関に電話して「次回はもっとましな人を派遣してよ」というところです。 点数方式については・・まあ・・貴社が意味があるとお考えなら続行すればよく、はなから決めているものになるようにする儀式であるならばどうかと思います。 有益な側面となりますと、これもまた審査員のご機嫌取りに過ぎないように思います。 なお、現在の日本の認証機関で公式に「有益な環境側面ががあるぞ」と語っているところはないはずです。ですから「それは認証機関の統一見解ですか? じゃあその文書をください」と顧客(貴社)として質問するのはおかしくないです。もし実際にそんな文書なり要求を公式に語ったら面白いですね。
|
たこ様からお便りを頂きました(2015.10.22)
環境側面、御礼 環境側面に関する貴重な警鐘に対し、重箱の隅を突っついてケチをつけたのではないかと恐縮しています。 規格の環境側面a)とb)の順番と、実態の順番が異なっていること、長年のもやもやが大分解消した次第です。あえて言えばa)はb)の見直しの際に用いられているのがより自然の感じがします。しかしながらこのように解釈するのは少数であり、今回の改訂でも明確にはなっていないようで、小職の小さな組織内でも理解されるか自信が無いのが本音です。 別件ですが、無知の事例を1つ。 以前の審査機関の審査で審査員から「プロセスアプローチ内部監査」なるコメントがありました。形式的なISO要求事項に対する適合性を主にしている内部監査に対するコメントですが、当組織ではこの意味を理解できませんでした。そしていわゆる事務局(小職も含)内ですったもんだして出した結論が、「プロセスアプローチを重点的に監査対象にした内部監査」です。現時点でこの解釈は訂正されていません。(尚、私は本HP記載のプロセスアプローチ関連記事を読んでいましたが、理解していませんでした。主はISO9001内容と把握していました。無知をお笑いください。) 引き続き種々ご指導頂きたく。 |
たこ様(たこ親父様?) まいどありがとうございます。 いろいろなご意見があるのは楽しいことです。私の意見も多くの中の一見解にすぎません。誹謗中傷ではない議論は誰とでも楽しく感じます。 以前、審査員の方から「お前が書いているようなごう慢な審査員はいない」というお叱りを頂いたことがあります。実はその審査員とはあいまみえたことがあり、ごう慢な方だと内心反発した思い出がありました。審査員や認証機関の方が、己自身を知らないのだなと感じました。もちろんそのまま返事には書きませんでしたけど。 おっと、私の話はそれていけません。 環境側面についてのご意見、おっしゃるとおりです。私も常々そう感じてきました。 思うにISO規格を作った人たちは、現実の会社でのお仕事を知らないのではないかと思っております。環境の「か」の字も出ない時期から、いや仕事はすべてにおいて、起承転結があって行われるわけではありません。事業(ゴーングコンサーン)は1回限りのイベントではありませんから、発祥してから必要に応じていろいろな業務が追加され、機能が追加されていくわけです。ですからISO規格に書いてあるように、環境側面を特定して、著しい環境側面を決定して、その対応を決めなさいなんて流れは、まったく何もないところから出発する場合だけでしょう。そんな文章を読めば、実務をしている人は呆れますよ。そんな文章を読んで、じゃあ、環境側面を調べようなんて考えるのは、環境管理をしたことのない人だけでしょう。 少しでも環境管理に関わっていた人なら、ええと著しい環境側面はあれとこれだな。環境側面?なもの会社の設備機械、器具備品、業務、行為それら全部じゃないか、と思うでしょう。ですから2004年版の規格でいえば、「計画された若しくは新規の開発、又は新規の若しくは変更された活動、製品及びサービスを考慮する」ところからが日常の仕事のはずです。そして例えば新規設備を入れるときは、環境配慮だけでなく、安全、衛生、メンテナンス、定期点検、法定点検、仕事の効率化、費用回収などを全部ひっくるめて検討し対策するわけで、環境のために○○を、安全のために○○を、というおかしな区切り方の文章を読むと実態とあまりにもかけ離れていることに呆れます。 規格を作った人はそういう切り口が現実的だと思ったのでしょうか? 俺たちは環境の規格を作っているのだから他のことは知らねと割り切ったのか、そこのところが理解できません、 まあ、規格とはたてまえというか単なる目次で、実際の仕事とは違うというのが現実の対応方法なのでしょう。いずれにしても規格を基にあるいは規格を優先して会社の仕組みを作ったらうごくはずがありません。 そういうことが世の中の悩みだろうと思います。 次のお題はプロセスアプローチ審査ですね。 私はISOの内部監査以前に、品質監査をしていましたし、環境監査もしていました。ISO規格のないとき品質監査とはどういうものかといえば、監査基準は会社の規則を守っているかを点検することでした。そしてそのとき「会社規則の○○を守っていますか?」とかいう質問では通用しないということを身で感じました。自分自身、会社で仕事をしていたわけですが、会社規則など読んだことがありません。ただ上司から指導され命令されたことをしていたわけです。上司は会社規則を読んで教育し命令していたわけです、あるいは上司も会社規則など読んでいなかったのかもしれません。ですから現場の人を監査するとき、相手が理解でき回答できるように聞かなくてはなりません。そしてそのほうが監査として有効だと気が付いたのも当然です。つまり監査とは監査基準を基に質問するのではなく、現実を基に質問することなのです。監査の目的というかアウトプットを出そうとすると必然的にそうならざるを得ないのです。 具体的には、あなたの仕事はなんですか、どんなことをするのですか、その仕事の要点はどこですか、それは何に書いてありますか、仕事をした結果なにか記録しますか、基準を満たさないときはどうしますか、そういう聞き方になるはずです。 私はISO規格の項番順監査しか知らない人たちが、後になってそれに気がついてプロセスアプローチ監査なんて優雅な名前で呼んだのだろうと思っています。 もちろん項番順監査がまったく使えないわけではありません。監査基準がISOでも顧客からの要求でもあるいは社内規則でも同じですが、初めに監査を行うときには要求事項が満たされているか否かを確認するためには項番順で行う必要があるでしょう。もちろんその場合でもプロセスアプローチで行う方法もあるでしょうが、いくつかの理由で項番順でおこなった方が良いのです。 卑近なことでは手間がかからず漏れがないと効率が良いからということもありますが、より重要なこととして作業している人、監督している人に対して、なぜそれをするのかという意識づけの意味でそれが定められているからだということを知らしめる効果があるからです。まあ、いろいろあるということです。 私は既に引退した老人です。気が向いたらあるいはご質問あればまたお便りください。 |
レイシオ様からお便りを頂きました(2015.10.26)
プロセスアプローチ審査 おばQ様 いつもHP更新を楽しみにしております。 さて、聞いた話ではありますが、2015規格改正を前に契約先の審査機関が暴走し(経営向上に努めるべく気をつかって)、「2015はそれが主流だ」、と、(半ば強制的に)プロセスアプローチ審査なるもので審査を行ったようです。 当該プロセスアプローチは、なぜか改善目線で行われており、排水処理管理等において、なぜこの数値が基準値なのか、この数値内で良いのであればギリギリのところで管理し、薬品投入を減らす等できるのではないか、等々の切り口で現場にコメントして回ったようです。 そもそも論で、排水処理場に経費削減等を望んでおらず、排水処理場の適正運転、設備のトラブル等への対応、長期保全等を望んでいるのであって、その運転管理を外部委託している身としては、「ギリギリで管理されるより、余裕をもった管理をしてもらった方が安心できます!」と、声を大にして言いたいです。 もう、ここまでくると審査ではなく、望んでもいない今猿のような気がします。 いろんなプロセスアプローチがあるのはわかりますが、本来のプロセスアプローチとは、その人が(組織、設備が)なんの仕事をしているのか、どこが重要な管理ポイントなのか、そのことを記載した文書はあるか、ヒヤリングした内容と実態(又は文書)に差異がないか、想定している緊急事態はどんなものか、それは実際の設備と過去の事故事例等と比較して妥当なものか、という視点で現場実態から調査する手法のことであり、まちがっても、改善の切り口なる本来の目的と異なるものを、見つけ出すものではない |
レイシオ様 毎度ありがとうございます。 初めて聞くお話です。レイシオ様のお話を読む限りそれはプロセスアプローチとも審査とも全然関係ない審査もどきではないかという感じがいたします。
しかし審査員がなぜそんなに力んでいるのか、疑問です。付加価値のある審査をして売り上げを上げろなんてハッパをかけられて、どうしたらわからずに右往左往しているのでしょうか。ねじり鉢巻きで悲壮な覚悟なのかもしれませんね。 ともかくそのような審査をプロセスアプローチ審査と称されたのでは本当のプロセスアプローチ審査が泣いてしまうでしょう。 あえてコメントするなら下表のようなことでしょうか?
|
うそ800の目次にもどる