19.10.28
今回は「組織」について考える。「組織」は1996年版から定義されて使われているが、その定義というか使い方にいささか納得できない。
私が知る限り「組織」の意味 and/or 使い方がおかしいと語る人はみかけたことがないから、私がおかしいのだろうか? あるいは私が第一発見者なのだろうか? 後者ならうれしい。
ISO14001:2015では、本文である4章から10章で117回も「組織」という語がつかわれている。
さて本題である。
これほど頻出語である組織はどう定義されているのだろう?
この定義では「組織」は一般的な組織の意味で、環境に関わるとかISO認証する組織と限定していないことを確認願いたい。
では2015年版ではどうか?
となっている。
おお! この定義では環境目的を持つ組織に限定されているのだろうか?
つまり一般的な組織ではないということか?
お待ちなせい、
ISO14001:2015では「環境目的」という語は使われておらず、定義されてもいない。
ここの「目的(3.2.5)」は定義で「達成する成果(objective)」とされており、環境に限定されない企業の様々な領域での目的を意味すると注記されている。
しかし本文中では、いずれにおいても「組織」の意味は、定義通りの「自らの目的を達成するため,責任,権限及び相互関係を伴う独自の機能をもつ,個人又は人々の集まり」という意味ではない。すべてが「この規格要求事項への適合を目指す組織」の意味で使われている。
規格で「組織は……しなければならない」ということは、「認証するためには……しなければならない」という意味である。
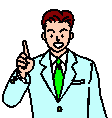 あなたは「そりゃ当然だ、ISO認証を得るためには規格要求を満たさなければならない」とおっしゃるかもしれない。
あなたは「そりゃ当然だ、ISO認証を得るためには規格要求を満たさなければならない」とおっしゃるかもしれない。それはおかしい。定義の組織は認証するつもりのないものも含むのだ。
この規格は認証したい組織についてだけ述べているというなら、そう定義すべきだ。我々は厳密な文字解釈のISOの世界に生きているのだ。
前述したように、ISO14001では版に関わらず「組織」の定義は一般論としての定義であって、特にISO認証を目指す組織のことではない。それでありながら本文の「組織」は、すべて認証したい組織なのだ。そうでなければ「規格要求事項への適合を図らねばならない」などとは書かないだろう。
お疑いなら117カ所の組織をチェックしてほしい。
見方を変えると、規格適合を目指す組織だけでなく、すべての組織にISO規格の要求事項への適合を求めるとは悪い冗談だ。
こんなことは法律や契約書なら大きな間違いだ。いや間違い以前に、文章を読んで意味が通じない。法律の読み方が身についている人が、ISO14001を読めば理解に苦しむというか、理解できるはずがない。ダメな文章であることは理解できるだろう。
正しい記述というか意味が通じるようにするには、この規格の序文の「0.5この規格の内容」を定義に持ってきて「この規格への適合を実証したい組織」とすべきではなかろうか?
上記に示された目的である「ISO認証したいとか、外部に宣言する組織」なら規格に適合する必要がある。しかし一般語としての組織全般についてこの規格要求を満たすべきという文章は単なる間違いに留まらず、病的である。
素直にISO規格を読めば、存在する企業や行政機関に限らず全ての組織はISO14001を満たさなければならないことになる。そりゃ独裁で憲法違反だよ!
 |
でもそれってISO規格が強制力があるというよりも、笑いものになりそうだ。神が愛なら力ではなく、神が力なら愛ではない。力がない独裁者は道化である。ISO規格は大言壮語を語る道化師か?
冗談や拡大解釈はおいといて、もともとISO14001の目指すところは、組織の目的、環境負荷、レベルによって、遵法と汚染の予防のために要求事項全てを満たすことではなかった。ISO規格は第三者認証のためだけでなく遵法と汚染の予防のための指針でもあるはずだ。
そもそもISO14001のタイトルは初版ではRequirementではなくSpecificationであった。だからISO14001:1996版の「序文」には次のような一文があった。
サポーズ、ある企業が認証を目的とせず、ゆえにISO規格のすべての要求事項を満たすのではなく、自分たちが選択したものだけを実行したとして、それを批判されるいわれはない。三歩前進より一歩前進は小さいが、なにもしないことに比べれば無限大である。
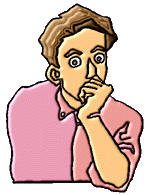 |
ところで「環境側面」は「側面」ではないし、「環境目的」も「目的」と違う。だけど「環境側面」も「環境目的」もちゃんと定義され、文中では定義通り使われていた。 だから「環境側面」は「環境」とも「側面」とも無関係な「環境側面」という概念なのだと思えば納得できる。「援助交際」が「援助」とも「交際」とも無縁なのと同じである。 だが規格本文の中の「組織」には「環境」も「認証」もついていない。だから定義と本文の組織の意味が違うことに25年経っても納得できない。 |
規格文章を整えるために定義を見直すべきだろう。一か所修正すれば済む。
死んでも定義を変えたくないなら、本文中の「組織」の前に「規格適合を望む」を追加すべきである。このときは117カ所も直さねばならないが……
大変なことに気が付いた
規格適合を望む組織が規格要求を満たすのはトートロジーだ
規格適合を望む組織が規格要求を満たすのはトートロジーだ
ところで法律ではその法律で定義した語については「特定○○」という表現をする。公害防止組織法の「特定工場」、騒音規制法の「特定施設」、
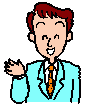 省エネ法の「特定貨物輸送事業者」や「特定旅客輸送事業者」、化管法の「特定化学物質」、容リ法の「特定容器包装」をはじめ、環境以外の法律でも「特定個人情報」、「特定役員」、「特定郵便局」、「特定調味料」、「特定行為」、「特定措置」、「特定地域」などなど。
省エネ法の「特定貨物輸送事業者」や「特定旅客輸送事業者」、化管法の「特定化学物質」、容リ法の「特定容器包装」をはじめ、環境以外の法律でも「特定個人情報」、「特定役員」、「特定郵便局」、「特定調味料」、「特定行為」、「特定措置」、「特定地域」などなど。すべて「この法律では○○を特定○○という」と定義されている。
そもそも特定とは「特に指定すること」「特に決めたもの」をいうのであって、「特定のボーイフレンド」とか「特定の気象条件」という使い方をする。
完璧に誤解を予防するために文中の「組織」を「特定組織」とすべきだろう。法人税法や金融商品取引法の「特定組織」と同じでカッコいいじゃないか
うそ800の目次にもどる
ISO14001:2015解説に戻る