注:本文において複数の英単語の熟語のとき、単語の間に中点「・」を入れた。
私は技術史が好きで、図書館で分類コードが技術史(図書分類コード502)となっているものを、順繰りに借りてきては読んでいる。死ぬまでに読み尽くそうと思っている。死ぬ前に読み尽くしても心配ない、そのときは近くの千葉工大とか日大の図書館を利用させてもらうつもりだ。
最近、ねじの歴史の本(注1)を読んでいると、「ねじは螺旋であるが、間違ってスパイラルと呼ばれることが多い」という文章があった。
|
| |
|
|
基本的に英語でも日本語でも、螺旋と渦巻は全く異なる意味であり言葉である。
ちなみに英語で螺旋はhelix(ヘリックス)である。ヘリックスとは聞きなれないが、この形容詞形であるhelical(ヘリカル)は、ヘリカル・ギア
一応、SpiralとHelixをアメリカとイギリスのGoogleで検索してみた。和訳は私である。
- Spiralとは、
- U.S.A Wikipedia
厳密には、二次元曲線である渦巻のことを指し、三次元曲線である螺旋の意味はないが、しばしば混用される。 - Dictionary.com
一点から常に離れ/近づきつつ、その点の周りを回る点が作る平面上の曲線 - Merriam-Webster
中心または心棒に巻き付けたり、広げたときの形
- U.S.A Wikipedia
- Helixとは
- U.S.A Wikipedia
コルク栓抜きまたは螺旋階段状の形状 - Dictionary.com
直線を描いた平面を円柱の側面に巻き付けたときに直線が作る曲線 - Merriam-Webster
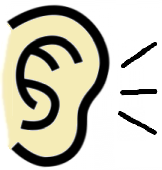
丸棒にひもを巻き付けた形
外耳の縁
円筒や円錐の側面に一定の傾斜角度でひかれた曲線
- U.S.A Wikipedia
私もうっかりというか、今までスパイラル・アップというものをまじめに考えたことがなかったが、ねじ山をたどればねじの軸方向に三次元的にずれていくが、渦巻きをいくら進んでも同じ平面上だ。となるとヘリックス・アップはあっても、スパイラル・アップというのは語義矛盾である。
いや、数学的な定義はそうであっても、日常的にはSpiral Upという言い方はあるのかもしれない。
アメリカGoogleとイギリスGoogleでスパイラル・アップという言い方はあるのかググりました。
数学とか工学など専門的な場においては見つかりません。日常の表現としては使っている事例がいくつかありましたが。そのときSpiral Upの意味は次の二つでした。改善とか進歩するという意味合いはないようです。
| To move, proceed, or lead up in a spiral path or motion. | 渦状の道または形に進む・動くこと | |
| to increase rapidly | 急増すること |
なお、U.S.Aのアマゾンでは「Spiral Up」というタイトルの本もあった(怪しげな宗教の本だった)。
だがしかし、ISO14001は"スパイラル・アップを要求している"のではなかったか?
ボケ始めた私の記憶ではそうだったような気がする。
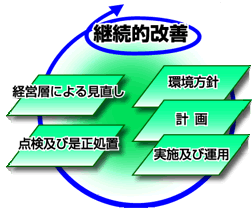 ISO規格をJISに翻訳した人は、Helix(らせん)とSpiral(うず)の違いが、分からなかったのだろうか?
ISO規格をJISに翻訳した人は、Helix(らせん)とSpiral(うず)の違いが、分からなかったのだろうか?
スパイラル・アップと聞いても、スパイラルを渦ではなくらせんと思っていた人はらせん状に上昇することをイメージするかもしれないが、母国語の人がSpiral Upと聞いたら違和感があるに違いない。
それともISO規格を作った人が間違えたのか? 興味を惹かれました。
Spiral Upという英語の言い回しがないと知り、謎が深まるばかり、心配になった私は、過去のすべてのバージョンの14001と14004の英文と和文を確認しました。
驚きました。
私は20数年間もISO14001はスパイラル・アップを要求していると思い込んでいました。
規格名 ⟍バージョン★★ | ISO14001 | ISO14004 | ||
| 英文 | 和文 | 英文 | 和文 | |
| 1996 | なし | なし | なし | なし |
| 2004 | なし | なし | なし | なし |
| 2015 | なし | なし | なし | なし |
しかし改めて読み直すと、ISO14001にもISO14004にも、英文にも和文にも、本文はもちろん序文にも付属書にも、一度たりとも「スパイラル・アップ」という言葉が記述されたことはありません。
いや、ちょっと待ってください。ISO14001でスパイラル・アップという言葉が使われたのは、間違いなくISO14001の初版からです。しかしそれ以前に存在しているISO9001:1987やISO9001:1994に記載があったかもしれません。
確認しましょう。
↓
ありませんでした。
するとスパイラル・アップとは「真夏の夜の夢」であって、私はシェイクスピアの森で妖精に騙されていたのでしょうか? もしかして、私以外の人はスパイラル・アップなんて聞いたこともなかったということなのだろうか?
つまりISO14001に関係するウェブページが240万件あるが、その内5%がスパイラル・アップを記述しているということになる。
5%とは少ない……そういわないでください。「ISO14001」で検索した結果のウェブサイトには、PDCAとか継続的改善だけでなく、内部監査や環境法規制もあるし、ISO14001の内容に関わらない認証機関やコンサルの宣伝のウェブサイトとかもあるわけです。そんないろいろあるISO14001をキーワードに見つかるウェブサイト全体の5%にスパイラルアップが記載してあるということなのです。
これは少ないとは言えないでしょう。
であればISO14001とスパイラル・アップはコインの表と裏、夫と妻のように離れがたいものらしい。私が夢を見ていたのではないことは間違いない。
ISO規格(英語)にもなくJIS訳にもないとなると、誰かが「ISO14001はスパイラル・アップしなければならない」あるいは「ISO14001とはスパイラル・アップだ」という趣旨のことを言いだしたに違いない。
環境側面は点数じゃないとダメとか、有益な環境影響という、ISO14001のガセネタあるいは都市伝説なのだろうか?
だって誰も言い出さなければ、無から有は生じない。そして私も含めて多くの人がそれを聞いて信じた(間違いを刷り込まれた)わけだから。
その結果、今現在のISO14001に関わるウェブサイトの5%においてスパイラル・アップを語っているという事態になっているのだ。
おっと、ISO規格にはないが、英米でスパイラル・アップという考えが語られ、それが日本に入ってきたという可能性もあるかもしれない。
すぐさまアメリカのGoogle、イギリスのGoogleでも「Spiral Up ISO」で検索しましたが、なしのつぶてでした。もちろん「Helix Up+ISO」でも検索してみたが、ノーヒットノーランである。
そもそも英米で「Spiral Up」や「Helix Up」を検索してもヒットしないということは、かの国々ではISO14001でスパイラル・アップもしくは類語が使われていないということだ。
となるとやはり日本で言い出した人がいたことは間違いない。
それはたぶん1997年頃、今をさかのぼること四半世紀も前になる。
スパイラル・アップという言葉があろうとなかろうとどうでもいいじゃないか、shallが付いた要求事項でもないのだから、そうおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。
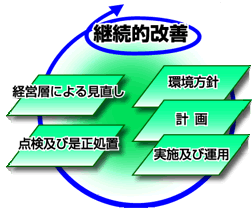 でもそう簡単ではないのです。というのは1997年頃、環境マニュアルにPDCAの絵がなければ審査員にマニュアルに記載することが必要ですと言われた。そしてISOコンサルは客が審査でトラブらないように、必ずこの絵を盛り込んでおくように指導したのです。
でもそう簡単ではないのです。というのは1997年頃、環境マニュアルにPDCAの絵がなければ審査員にマニュアルに記載することが必要ですと言われた。そしてISOコンサルは客が審査でトラブらないように、必ずこの絵を盛り込んでおくように指導したのです。
前述したようにPDCAの絵はshallと関係ありません。それなのにどうしてマニュアルにないと不適合!となったのか今となると不思議極まりない。
私自身マニュアルにPDCAの絵を入れろと言われたとき、あの くっだらない 絵が、いかなる価値があるのか私にはわかりませんでした。
不肖おばQは我が渾身の力を注いで書いた環境マニュアルを、くだらない絵で汚すのを嫌い、「私の円を踏むな!」と叫んだのですが、天皇陛下より偉い審査員閣下には通じませんでした。
哀れアルキメデスはローマ兵に殺されてしまったのです。
しかし規格の本文にも序文にも付属書にも登場しない言葉が、なぜこんなにも必須だとか重要な言葉と思われてきたのか? その因果関係というか、風説の流布の起承転結を研究することは、ISO研究者(オイオイ)として研究し解明しなければならないと感じた。
ISO規格にないスパイラル・アップという言葉をISO関係者が使っていると私が言っても、本当かよ、証拠があるのかと問われるでしょう。先のウェブサイトの検索結果で数字はわかりましたが、認証機関などが使っているかどうかわかりませんものね、
それでJAB認定の認証機関がスパイラル・アップという語をウェブサイトで使っているかを調査しました。
2020.08.03時点でEMS審査にJAB認定を受けている認証機関35社とJABのウェブサイトをサルベージした。
| ★スパイラルアップ★ | ★認定機関+認証機関数★ |
| あり | 13社 |
| なし | 23社 |
36社中13社、36%とは意外と少ない結果であった。
私の想像だが、意外と少なかったのは、21世紀の現在は認証機関のウェブサイトで規格の解説を行う必要がなくなったからではないだろうか。ウェブサイトで規格解説をしていたならもっとたくさんのスパイラル・アップが見つかったのではないだろうか。
驚いたことにISO認証制度の元締めであるJAB(日本適合性認定協会)のウェブサイトにも多数あり、中には「環境マネジメントシステム運用状況調査報告書」というJAB作成の文書の副題が「環境ISOの自律的スパイラルアップ」であった。スパイラル・アップという語はJAB認定らしい。
では書籍はとなるが、初心者用の解説本においてはほとんどスパイラル・アップ(またはスパイラルアップ)という語が使われている。(2020.08.04 津田沼駅前 丸善店で確認)
しかしまっとうというか専門家の書かれた解説本においては使われていない
私がまともと思う本では、規格にある通りのことしか書いていない。概ね、「規格にプラン・ドゥー・チェック・アクトといわゆるPDCAサイクルによるアプローチとして示されている」という文言がある程度だ。
それが解説本か?と言われると、何も足さない何も引かないのがあるべき姿としか言いようがない。
 特段説明をするまでもなく、社会人をしていればすべてにおいてこのPDCAループで仕事をしているだろう。
特段説明をするまでもなく、社会人をしていればすべてにおいてこのPDCAループで仕事をしているだろう。
言い換えると、この図に改めてスパイラル・アップという語を与えなければならないという理由もなさそうだ。
というか図の中で矢印が上方に向かっているところに、継続的改善と書いてある。元々規格にある継続的改善だけでは何か不足だったのだろうか?
継続的改善よりスパイラル・アップと名付けたほうがインパクトがあると考えたのか?
だがそれならば Continual Improvementを、継続的改善でなくスパイラルアップと訳したほうが良かったような気もするが……英語が堪能な人がそれはいかんと言ってポシャり、どうしてもスパイラル・アップを捨てきれない人が規格にはないが、説明会とか自著において使いだし、みんながその尻馬に乗ったということだろうか?
この語を作り出したために、ISO14001は「どんどんと良くしていかなければならない」という認識を持たせたのではないかという気がする。あるいはそういいだした人が、そういう強迫観念に囚われていたのかもしれない。
ISO14001はそもそも改善が第一義ではなかったはずだ。誤解されるかもしれないが、たかが一つのシステム規格を作り、それに基づいて環境管理をすれば持続可能性が担保されるなんて考えたなら、その人の頭を疑う。いくらリオ会議で持続可能を実現するための規格を求めたとしても、それは不可能である。本気で持続可能性を実現しようとするなら、人間の存在を再定義し、存在可能数を決め、人間の生き方に新たなる十戒を有無を言わさずに従わせることが必要条件になるだろう。
ISO14001とはそんな大層なものじゃない。規格の意図は「遵法と汚染の予防」であり、汚染の予防として自然への悪影響を削減しようというのは当然だ。だが無制限に努力を求めたわけでもない。つまり更なる改善を行うことは経済的にも技術的にも
EVABATを明言しているということは、持続可能性が第一義ではなく実行可能性を優先したということだ。人間にはできることと、できないことがある。仮に規格に絶対環境を悪くするなと書いたところで環境が良くなるわけではない。現実を踏まえた大人の規格であること、故にそれを満たしたところで、持続可能性が実現できるわけではない。
 もっともスパイラル・アップがいかなるものは分からないが、永遠にスパイラル・アップを続けても持続可能性は実現しないだろう。
もっともスパイラル・アップがいかなるものは分からないが、永遠にスパイラル・アップを続けても持続可能性は実現しないだろう。
ところでSDGSバッジを胸につけている人は多いけど、彼らはバッジを着けると持続可能性が実現するとでも思っているのだろうか?
誰か EVABATバッジを作ってくれ! 人間にできることを実行しようという有志は、EVABATバッジを胸に着けてSDGSバッジ族に対抗しようではないか、 |
まあ、そこんところを理解していない人が、熱意か悪意かスパイラル・アップという語を持ち込んだことにより、最低何件かの環境目的目標を持たねばならないという発想となり、環境影響の微小な組織においても無理やり改善項目をつくりママゴトに堕ちてしまったのが実態ではないのか?
そんなママゴトをするくらいなら、理想は不可能、できることは有限、我々はEVABATを尽くしている。文句を言うな!と言い切ったほうがよほど前向きであり実質的であった。
それを理解していないと、ハトポッポのように考えなしに「温室効果ガス25%削減
小泉環境相が2019年CO25での発言(注7)が後ろ向きだ、化石時代だと、内外の評判が最低だが、私は小泉環境相が悪いとは全く思わない。真面目さ正直さでは、ハトポッポは小泉環境相の足元にも及ばない。
まあ普天間も何も、ハトポッポのクルクルパーの結果である。鳩山が生み出した負の遺産は、失われた20年以上のダメージがあった。
| 〇 | × | |||
|
できないことは「できない」 と言ったほうが良いのか? |
 |  |
できもしないことを「やります」 と嘘ついたほうが良いのか? |
民主党もその後進である立憲民主党も、できもしない理想を語り、他人が理想を実現できないことを非難する。
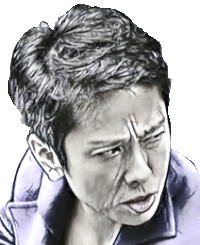
|
| 極道の女 |
政治家とは理想を追求することではない。今を少しずつ良くしていくことなのだ。理想を語っても現実を良くしてくれない政治家は政治家ではない。国民の寄生虫、歳費の盗人でしかない。いや、最近は防災に手を打たない、無作為の殺戮知事がいる。誰とは言わないけど、
閑話休題
ISO14001にスパイラル・アップが入り込んだ経緯を究明することはもう不可能だろう。しかし最初にスパイラル・アップという語を持ち込んだのはいったい誰だったか?
そのお方は、ISO14001を理解していなかったと同時に、英語も達者ではなかったと推測する。
こう書けば、ふざけるな!と怒鳴って正体を現すことを期待する。
いつかスパイラル・アップという言葉が使われなくなるときが来るのだろうか? それも興味がある。
![]() 本日の振り返り
本日の振り返り
ISO認証制度は普及発展段階の信頼性を確立する過程において、規格解釈の間違いとか審査員の不正行為など幾多の阻害を受けてきた。スパイラル・アップという考え方とそれを盛り込めという要求も、そのひとつだ。
そして、そういった怪しげな考えや間違えた解釈を排除できなかったISOの権威者たちも、また阻害要因(要員かも)であったことは間違いない。
もちろん私のようなISO認証制度の鼎の重さを問うプロテスタント・不満分子を論破し排除しなかったことも問題だろう。私を排除することなど簡単だ。「ISO規格にあるPDCAの絵がないから不適合です」なんて語るバカ審査員を一掃すれば、私が生息しているニッチはすぐに消滅してしまう。
しかし今だにISO審査に存在する、怪しげな新興宗教、おかしな解釈がはびこっているから私は発言しなければならない。
注1 |
「ねじとねじ回し」ヴィトルト・リプチンスキ・春日井晶子訳、早川書房、2003、p.125 | |
注2 |
はすば歯車とも言い、歯車の歯が軸に平行でなく傾斜が付いているもの。 歯が回転軸に平行な平歯車よりも強度があり、また回転が静かというメリットがある。 デメリットとしては歯が傾いているので回転方向だけでなく軸方向に分力がかかる(スラストという)ので、軸受けにはスラスト軸受けを使用しなければならない。これを嫌うならねじれ方向が反対のものを組み合わせた山歯歯車を使う。 | |
注3 |  電波を放射したり受けたりするアンテナの長さは、電波(搬送波)と共振しなければならないので、波長の長さとの比率が決まっている。そうしないと放射効率がものすごく落ちてしまう。だから無線をかじった人なら、アンテナを見れば電波の波長(逆数は周波数)の見当がつく。
電波を放射したり受けたりするアンテナの長さは、電波(搬送波)と共振しなければならないので、波長の長さとの比率が決まっている。そうしないと放射効率がものすごく落ちてしまう。だから無線をかじった人なら、アンテナを見れば電波の波長(逆数は周波数)の見当がつく。しかし長いアンテナは扱いが大変なので、放射効率は落ちても実用を優先して、まっすぐのままでなくコイル状に巻いて見かけ上短くすることがある。これをヘリカル・アンテナという。 トランシーバーについている、長さ30センチ以下の黒いゴムのようなアンテナはみなこれである。 | |
注4 |
「ISO14001:2004 要求事項の解説」吉田敬史・寺田 博、日本規格協会、2005 「ISO14001:2015 要求事項の解説」吉田敬史・奥井麻衣子、日本規格協会、2015 | |
注5 |
EVABAT(Economically Viable Application of Best Available Technologyの略。イババットと読む。)とは、経済的に実行可能な範囲で最適な技術・対策を行う意味であり、ISO14001の目指すところである。というか神ならぬ人には、それ以上のことができるはずがない。  EVABATは1996年版では序文に明記していたが、2004年版以降では記載がなくなった。どうしてだろう? 人間はそういった制約を超えたと傲慢になったのだろうか?
EVABATは1996年版では序文に明記していたが、2004年版以降では記載がなくなった。どうしてだろう? 人間はそういった制約を超えたと傲慢になったのだろうか?グレタ・トゥーンベリは間違いなく、EVABATという考え方を理解してない。知っていればあんな駄々こね発言はできません。 それとも彼女は神の声を伝える | |
注7 |
外資社員様からお便りを頂きました(2020.08.06)
おばQさま なるほど、言葉の意味とは重要で、それを探るにはまさに原典を漁れですね。 「スパイラル・アップ」が和製英語である事は、ご高察から明白なようです。 こういう時は、初出がどこにあるかを探るのが一般的ですが、出始めは、お書きのように1997年くらいでしょうか? 経緯を見るとISOとは独立して、経営コンサルがPDCAサイクルの中で言い始めて、それがISO14000に結びついて、日本の中で定着したように思えます。(想像です) もしその通りならば、「スパイラル・アップ」の英語としての誤用はISO以前のからあったかもしれません。 もう一つ気になったのは、「スパイラル・アップ」の概念で、これを要求し、目的とするのは明白な改善の方向がある前提ですね。でも現実は、そんなに簡単ではありません。 おばQさまも何度も指摘されておりますが、会社経営の観点は多角的である必要がある、ある面でエネルギーの削減が出来ても、それが他の面で歩留まり低下や単価アップにつながったら対策の意味がありません。 そういう意味では、「アップ」は環境面での評価軸のみならば、経営から見れば「それで何?」という事になりそうです。 昨今 話題の、レジ袋削減。 マイバッグの利用は決して悪い事ではないと思いますが、買い物という行為だけ考えても、事前にバッグを用意する事は、買える商品量を規定します。 マイバッグに入らなかったので、レジで追加でバッグを買っている人は良く見かけます。 だから購入という行為から見れば、都度 適切なバッグや梱包方法を提供するのは当然ですね。 環境面で言えば、本当にレジ袋が海洋投棄されて海洋生物に深刻な影響を与えているのか? この防止だけを言うならば、レジ袋はゴミ回収時に利用して焼却すれば良いだけです。 海洋に投棄されているゴミは、どう考えても漁業用のものが多いし、海外から流れてくるゴミはどう考えても、日本の漁民や海岸の困りものなのは知られているはずです。 にもかかわらず、おさかなクンがCMで「大変だぁ」と言えば、レジ袋は環境に良くないと刷り込まれます。結局、スパイラル.アップは、英語の意味そのままに、同一平面をグルグル回って、UPの部分は思い込みなのかもしれません。 |
外資社員様 毎度コメントありがとうございます。 スパイラルアップという言葉は、今現在いろいろな方面で使われているようですが、ネットをググってみると、どの分野でも古くからスパイラルアップという言葉が使われていた証拠・痕跡は見つかりませんでした。 例えばスパイラルアップが社名につく会社は不動産屋、自己啓発教育会社、介護施設、経営コンサル、ウェブサイト制作など多々あります。これらの創業がいつかとなると、2010年代がほとんどで、見つかった中で最古は2000年創業でした。時期的にみると、ISOでスパイラルアップが使われるようになったのより遅いのは間違いないです。 社名はともかく、おっしゃる通りISO14001を見るスタンスがおかしいですよ。「環境が最重要です」と語る審査員は大多数です。でもそれって大きな勘違いですよね。品質やコストや反社もあります。最近はセクハラ、LGBT、透明性、みんな大事です。どれかひとつでも下手を打てば、大問題です。持続可能性といいますが、地球がほころぶまで会社を持続することが経営者にとって最大の課題でしょう。 外資社員様がマイバッグを例にされましたが、類似のものはたくさんあります。いまどき国内企業においては事故を除いて定常的な大気汚染などありません。光化学スモッグの原因である揮発性有機化合物は中国からというのは間違いないようですし、PM2.5の半分以上は中国から来るのも間違いありません。しかしなぜか中国に「しっかりせい!」と叱りつけるような政治家も学者もおらず、国内企業に厳しくするだけってのも… なんにせよスパイラルアップを念仏のように唱えているだけでは向上するはずありません。ISOに限らず、いろいろとしがらみがあって素直な考えは通用しないのですね、 |
うそ800の目次にもどる