わざわざ断ることもないが、ここで私の言いたい放題をしている。もちろん私の論に異議、苦情があるでしょう。ぜひとも抗議メールをいただけたらうれしいです。
大いに議論をしましょう。見解の相違をぶつけ合うことによって新しいアイデアが生まれ進歩があると信じております。
ISO認証を受ける多くの会社で、従来から存在し実際の業務に使われる文書と、ISO審査の際に見せる文書が違い二重になっているということは、20世紀から言われている。自分のところは違うと思っていても、ISOのために文書を作っているなら同じことだ。ISOのための文書管理規定、環境側面を決めるための規定、環境法規制を調べるための規定、そんなものはいらないと考える。
それは間違いだ、無駄なことをするな、従来からのものを見せればよい、そんなことが言われて21世紀になってからはそのようなことは減ってきている。
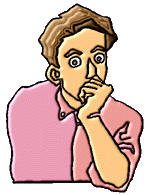 |
だが今も見聞きすると皆無にはなっていない。
ISOの求道者を自称する私でも、しょうがないなあ〜と諦めているが、良いことではない。悪いことなのだ。なぜ悪いかといえば、無駄な仕事すなわち企業の損出であるし、従業員が何の役にも立たないことをすることは勤労の倫理そして人間性に反するだろう。そして最終的には日本の国際競争力を損なっているわけだ。
なぜにそのような無駄なことをするのかとなると、いろいろな理由が考えられる。
ひとつにはISO認証のためにはそうすると教えられたか、あるいは間違ったアプローチだと知っていても、審査で無用なトラブルが起きることを防ぐために審査員にわかりやすい文書体系にしたということもある。
もちろん右も左も分からず、ISOコンサルに言われるままにやったという会社も多いだろう。
なぜなぜ分析というのがあるらしいが、なぜアプローチを間違えるのか、なぜ審査員にわかりやすい体系にするのかとなると、規格の文章がおかしいからだ。
どのようにおかしいのかといえば、どの要求事項でも、「環境側面に関する」とか、「環境パフォーマンスを」…などと頭に「環境」を付けているからだと考える。
そもそも実際の仕事というものは、環境だけ独立しているわけではない。生産や販売という本業はもちろん、環境も品質も安全もセクハラ防止などもひっくるめて行っているわけで、当然社内のルールは、ある仕事において判断すべきこと実行すべきことがひとつの手順書(一般語であり実際には規定とか規則と呼ばれる)に定められているのがふつうである。
なぜなら一人の管理者/担当者が、どんな業務でも執行するときに参照する文書が一つなのはあるべき姿である。たくさんの文書を参照しては仕事にならない。
もし新設備導入の際に検討すべき事項が、環境関連の法規制の調査、届け出、資格取得、教育訓練などを決めた手順書があり、品質関連としての別の手順書があり、安全・衛生関係の手順書があり……という文書体系であれば、仕事にならないだろう。
具体的に言えば、新しい設備を入れるときに、行政の届け出として保健所、県の環境課、市の消防署、監督署、町内会との話し合いなど、一つにまとまっていなければ仕事にならない。
だから私が見知っている企業ではみな新設備導入、新入社員教育、資産廃棄、社外工事という区分けで手順書があり、環境だ、品質だ、安全だ、セクハラだ…という区分けではない。
当たり前だとおっしゃるならたいへんうれしい。きっとあなたの会社ではISO9001のための手順書はなく、ISO14001のための手順書もなく、会社にある手順書はすべてISO認証以前から存在し、会社の業務に沿って作成されているはずだ。
そのように本質をとらえて考え、実行する力量があればよい。
しかしかって私が見聞きした多くの会社はそうではなかったし、今も古い仲間から入る情報ではかなりの会社ではISO対応の、
規格改定があっても規定改定をしないのかと問われたなら、あたりまえだと応える。会社の歴史はISOMS規格よりも古いのだ。長年運用され検証されてきたものに、瑕疵があるはずがない。
おっと、わき道にそれた。
ISO規格のための文書が存在するのは、前に述べたように、ISO規格では要求事項には常に「環境についての」という枕詞が付いているからだというのが本日の主張だ。
例を挙げよう。
5.1 a) 環境マネジメントシステムの有効性に説明責任を負う。
5.3 a) 環境マネジメントシステムが、この規格の要求事項に適合することを……
6.1.3 a) 組織の環境側面に関する順守義務を決定し、参照する。
6.2.2 組織は、環境目標をどのように達成するかについて計画するとき……
7.1 組織は、環境マネジメントシステムの確立、実施、維持及び継続的改善……
(ISO14001:2015から引用した)
「環境について」という形容詞句があれば、「環境についての手順や基準」を決めなくてはならないと読むのは素直な姿勢だと思う。
だが上記に例に挙げたものは
5.1 a) マネジメントシステムの有効性に説明責任を負う。
5.3 a) マネジメントシステムが、この規格の要求事項に適合することを……
6.1.3 a) 組織に関する順守義務を決定し、参照する。
6.2.2 組織は、事業目標をどのように達成するかについて計画するとき……
7.1 組織は、マネジメントシステムの確立、実施、維持及び継続的改善……
と読むのが正しいのではないか?
いや、そう書くのが正しいはずだ。
それとも規格策定者は、ワシは環境についてしか責任はない、他のことはどうでもいいと言うのだろうか?
ともかく読んだ人が間違えたアプローチをするのは、規格の文言に問題があるのではないだろうか。いやそんな婉曲話法を使うことはない。ダブルスタンダードを引き起こしたのはズバリISOMS規格の文章が悪いのだ。
文章自体が本来のあるべき姿と離れているだけでなく、あるべき姿を示していない。これはEMS規格が環境マネジメントシステム限定であるというかもしれないが、管理で実務を行っている者から見ればバーチャルとしか思えない。
注:上記でEMS規格といったが、すべてのISOMS規格は同じである。
「審査で無用なトラブルが起きることを防ぐために審査員にわかりやすい文書体系にする会社もある」と前述したが、そんな会社があるのだろうか?
あるのだ。
ISO審査がしっかりとプロセスアプローチに則って行われればよいが、力量のない審査員は項番からスタートし、要求事項に対応する証拠を探そうとして見つけることができないと不適合にする。
規格が「環境○○をすべし」という文章の現実から、審査は「環境○○をしている証拠」探しになっているのが現実である。
注:プロセスアプローチで行う方法では、現実や企業の文書を見て、そこに規格要求が織り込まれているかを確認する。だからISOのための文書でなくても規格適合・不適合は判断できる。
もちろん現実をみて審査してくれと言えればよいが、それができない審査員がいるのが現実である。ならば審査員に分かるような文章にするのが予防処置であり、審査員にとってありがたいことだ。過保護だね、
じゃあ、規格全文の要求事項を見直すべきなのかとなると、私はそうではないと考えているのだ。
規格要求事項とは「○○しなければならない」と言っているだけだ。それをいかに現実にするかは組織の責任というか、組織の権限である。あまり細かいことをいうべきではない。
では何が問題なのかといえば、序文であろう。
序文とは規格の趣旨、意図を示すものだ。ISO14001は持続可能性を実現するためのツールであると述べている。そしてマネジメントシステムがいかなる貢献ができるのか、どのように構築すべきかが書かれている。
序文の構成はおかしくない、現状でいい。ただ語っている言い回しが婉曲・遠慮しすぎなのか、そもそもダブルスタンダードを想定しているのかはわからないが、組織のマネジメントシステムに組み込まれなければならないということを語っていない。そこが問題だと考える。
以下、主要なセンテンスについて例を挙げて説明する。
- 0.3 成功のための要因 第一文
環境マネジメントシステムの成功は、トップマネジメントが主導する、組織の全ての階層及び機能からのコミットメントのいかんにかかわっている。冒頭に「環境マネジメントシステム」とあるから審査員は環境マネジメントシステムがどう規定されているかを調べようとする。だがそもそも環境マネジメントシステムとはISO規格が考えたバーチャルなものに過ぎない。企業に存在するのは組織のマネジメントシステムと、そのなかに環境にかかわる部分(まさに環境マネジメントシステムの定義である)が存在するのみなのである。
だから「環境マネジメント」あるいは「マネジメントシステム」にすべきである。注:ISO14001から「環境マネジメントシステム」という語をすべて排除しても、何ら問題がないことを確認願う。「マネジメントシステム」という語をなくしては、表現が困難になることもご確認願いたい。
なお「環境マネジメント」という語は、定義されず一般語として規格の中で多用されている。改善案(1)
環境マネジメントの成功は、トップマネジメントが主導する、組織の全ての階層及び機能からのコミットメントのいかんにかかわっている。改善案(2)
私はどちらでもいい。
マネジメントシステムの成功は、トップマネジメントが主導する、組織の全ての階層及び機能からのコミットメントのいかんにかかわっている。
- 0.3 成功のための要因 第3文
トップマネジメントは、他の事業上の優先事項と整合させながら、環境マネジメントを組織の事業プロセス、戦略的な方向性及び意思決定に統合し、環境上のガバナンスを組織の全体的なマネジメントシステムに組み込むことによって、リスク及び機会に効果的に取り組みことができる。2020.11.24
下記、段下げ部分の表現を全面的に見直しました。意図は変わっていないつもりです。
この文章は概ね納得だが、誤解しやすいのではないだろうか?
下記の文章の単語ひとつひとつと翻訳は対応しているのだが、元のニュアンスが伝わらないように思う。
Top management can effectively address its risk and opportunities by integrating environmental management into the organization's business processes.
確かに「トップマネジメントは、環境マネジメントを組織の全体的な事業プロセスに、組み込むことによって、効果的に対処できる」なのだが、それでは「組み込まなくても、効果的に対処できる場合がある」と受け取られる。
集合の記号で書けば
現状は……「組み込むこと」 ⊃ 「できる」という表現であるが、
正しくは…「組み込むこと」 = 「できる」ではないだろか。
そのためには表現を裏返しして、
「トップマネジメントは、環境マネジメントを組織の全体的な事業プロセスに、組み込まなければ、効果的に対処できない」としたほうが統合しなければならないという意図が表現できたのではないだろうか。改善案
トップマネジメントは、他の事業上の優先事項と整合させながら、環境マネジメントを組織の事業プロセス、戦略的な方向性及び意思決定に統合し、環境上のガバナンスを組織の全体的なマネジメントシステムに組み込なければ、リスク及び機会に効果的に取り組めない。
- 0.3 成功のための要因 第4文
この規格をうまく実施していることを示せば、有効な環境マネジメントシステムをもつことを利害関係者に確信させることができる。前述したと同様に、「環境マネジメントシステム」は「環境マネジメント」あるいは「マネジメントシステム」にすべきである。
改善案
この規格を運用し目的を達することにより、組織のマネジメントシステムが環境マネジメントに関して有効だと利害関係者に確信させることができる。
- 0.3 成功のための要因 末尾
環境マネジメントシステムの詳細さ及び複雑さのレベルは、組織の状況、環境マネジメントシステムの適用範囲、順守義務、並びに組織の活動、製品及びサービスの性質(略)によって異なる。環境マネジメントシステムというものが組織のマネジメントシステムの一部なのだから、環境を省いても問題ない。環境マネジメントシステムという語を使わないようにしたい。
改善案
組織のマネジメントシステムの詳細さ及び複雑さのレベルは、組織の状況、マネジメントシステムの適用範囲、順守義務、並びに組織の活動、製品及びサービスの性質(略)によって異なる。これによってISO14001は環境以外の手順についても要求する恐れがないかという懸念は無用である。要求事項は本文で記され、そこには環境にかかわることしかないからである。
- 0.4 Plan-Do-Check-Actモデル
環境マネジメントシステムだけがPDCAなのか?
そもそもISOMS規格が現れる前から、会社の仕事はPDCAで行われている。そうでないものがあるだろうか(反語である)
わざわざ書くこと自体ナンセンスだ。改善案
削除する。 - その他
言うまでもないことだが、その他の個所についても整合性が取れるよう修正するのはもちろんだ。
1996年版の序文の最終行は
この規格に規定する環境マネジメントシステムの要求事項は、既存のマネジメントシステム要素と独立に設定される必要はない。場合によっては、既存のマネジメントシステム要素を当てはめることによって、要求事項を満たすことも可能である。
という文章であった。「可能(possible)である」というのも変な気がする。もっとこなれた日本語訳がないのだろうか。
意図としては、私が述べていることそのまんまである。
しかしこれも腰が引けている。ISO14001規格策定者は弱気なのか、自信がないのか?
本来なら
この規格に規定する環境マネジメントの要求事項は、既存のマネジメントシステム要素と独立に設定しないこと。可能な限り、既存のマネジメントシステム要素を当てはめることによって、要求事項を満たさなければならない。
とすべきだろう。
過ぎたことは仕方がないが、1996年版のこの文言を次版以降「会社のマネジメントシステムは唯一である」と明確すればよかった。
しかし規格改定のたびにそうはならず、逆行してきた。
2004年版では
組織がこの規格の要求事項に適合した環境マネジメントシステムを構築するに当たって、既存のマネジメントシステムの要素を適応させることも可能である。ただし、マネジメントシステムの様々な要素のいずれかを採用するかは、意図する目的及びかかわりのある利害関係者によって相違することがあろう。
となった。
細かいことはどうでもいいが、大きな後退であったと考える。
何度も言うが、私の狙いは組織のマネジメントシステムは唯一無二であり、「環境マネジメントシステム」という語を排除することなのだ。
そして2015年版では、とうとうこの「既存のマネジメントシステム要素を当てはめること」という文言がなくなってしまった。
改悪これに極まれり。
話が前後するが、なぜマネジメントシステムは一体でなければならないのか?
単純に言えば、一つの組織には一つのルール体系しか存在しないからだ。二つ存在するなら、その守備範囲は明確に分かれていなければならない。さもなければそのシステムは正常には動作しないだろう。
環境マネジメントシステムと品質マネジメントシステムは別物ですという言い分は通用しない。なぜなら文書管理、その他の支援と呼ばれるカテゴリーは他のマネジメントシステムと共通事項である。だがそれだけではない。環境側面、順守義務、計画なども環境独自とか・環境単独で運用されるものではない。
例えば、法律を調べて環境関連だけとりまとめたものが実用になるのか?
環境にかかわる法規制ではなく、当社がかかわる法規制は何かと調べなければ仕事する人ではない。
己の職務で法違反がなければ、隣の部署で法違反があっても良いのか?
現役時代のISO審査で、会社が規制を受ける法規制をまとめたものを見せたら、審査員が「ISO規格では「環境側面に関係する(ISO14001:2004 4.3.2)」とあるのだから、環境だけをまとめなければならない」とのたまわった。
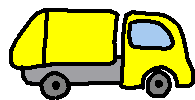 この発言をした審査員は、実際の仕事をしたことがないのがバレバレだ。廃棄物処理委託契約書で廃棄物処理法だけに適合していればよいのか?
この発言をした審査員は、実際の仕事をしたことがないのがバレバレだ。廃棄物処理委託契約書で廃棄物処理法だけに適合していればよいのか?
冗談ではない。印紙税法も関係するし、反社会勢力の排除は自治体の条例にある。場合によっては下請け法もかかわる(注:リサイクルなどを合わせてひとつの廃棄物処理委託契約書にした場合など)。
仕事の常識のない人、会社で働いた経験のない人を審査員にしちゃだめでしょう。
私の持論である。
環境マネジメントも品質マネジメントもあるだろうが、環境マネジメントシステムなんてないし、品質マネジメントシステムもない。あるのは唯一無二の組織のマネジメントシステムだけなのである。
まとめである。
文書体系が二つあるのが問題なのではない。そもそもISOのための文書などない、ISOのための仕事はない、品質と環境のマネジメントシステムが異なるわけはない。
ISOのために無駄な仕事を増やしているのは規格の読み方が悪いのだ。
しかし間違えて読んでしまう原因は規格の文言にあり、まず序文を見直さねばならない。
組織にはマネジメントシステムは一つしかない。怪しげな環境マネジメントシステムなどという言葉を使うことはない。それをはっきりさせれば誤解は起きず、ISO認証も運用も改善されるだろう。
具体例を挙げれば、内部監査は業務監査に一本化しよう、会社には事業計画しかない、従業員はISOという言葉を忘れよう。ただひたすら会社の手順書を遵守し仕事に励めばよい。簡単だし、楽でいい。
ISO審査の際には、規格の用語を使わずに審査をしてもらう。それができない認証機関はお断り。
ISO規格策定者は、己の作った規格が皆に喜ばれ使われて冥利に尽きるだろう。
![]() 本日の願い
本日の願い
ISO14001規格では「環境マネジメントシステム」という言葉が、さまざまな誤解を招いている。
この解決は、「環境マネジメントシステム」を使うのを止めて、序文に「この規格の要求事項はすべて組織のマネジメントシステムに盛り込め」と記せば間に合うのだ。
もちろんISO9001その他でも同様である。
共通テキストに、序文にそう盛り込むことを追加してほしい。
今までの審査員のチョンボとか、規格解釈の勘違いなどと違い、前回からだんだんとアブナイことを書いている。夜中にどなたか訪問してくるのではないかと懸念する。
いやそれよりも、昔の私の上司とかISOの恩師からお叱りがくる可能性は高い。
キョン様からお便りを頂きました(20.09.29)
私が勤めている事業所もISO14001認証を返上することになりました。 20年近く前、隣席のISO取得担当が社内規程とは別に環境規程を作らざるを得ないと言い出した時びっくりしたこと、プレ審査の時「こんな二重帳簿規程があるか」と審査員が怒り出すのではと思っていたこと、昨日のように思い出します。 振り返るとなつかしいものですね、それでは。 |
キョン様 お便りありがとうございます。 認証返上ですか! すごいですね。私の知る多くの企業で「認証いらない」「止めたい」と語っていますが、決断できずズルズルと続けているところがほとんどです。 私も多くの会社と付き合いがありましたが、私がかかわったところでは国内で6社、海外で2社くらいしか返上したところはありませんでした。 その決断は勇気というよりも、社内の根回しとか説得が大変だったと思います。賞賛に値します。 これからは無用な仕事をしていた分、御社の効率向上、改善の推進ができるだろうと思います。 頑張ってください。 |
うそ800の目次にもどる
ISO14001:2015年版規格解説へ