退屈なので2015年版の規格解説の書いてない項目について書こうかと暇人は考えた。
まだ書いてない項番がいくつかあるので、とりあえず今回は是正処置について一文をひねる。
是正処置というのは簡単に言えば<問題が起きたとき、発生した悪影響を取り除くのはもちろん、発生原因をなくす>ことです。つまり再発防止をしなければならない。
そう聞けば、なるほどとか、当たり前と思うでしょう。でも、それって本当でしょうか?
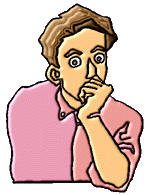 |
朝寝坊して遅刻したといったとき、悪影響とは何だろう? みんなの心証を悪くした。たびたびすれば査定が下がるかもしれない。ひょっとしたら重要な会議とか人と会う約束に遅れるかもしれない。だが前日客先との打ち合わせが真夜中までかかり寝坊したなら上長はお疲れといって、更に午前中は休んでも良かったのにと言ってくれるかもしれない。
あるいは過去何度も遅刻してもう一度遅刻したら解雇するぞなんてWarning letter を頂いているならただ事ではありません。
ちなみに……遅刻して解雇されるのかとなるとどうでしょうか?
過去、遅刻で解雇されて裁判となった事例は多々あります。あるものは会社勝訴、あるものは労働者勝訴といろいろです。会社が適正な指導警告をしていたとか、労働者側が遅刻後いかに対応したかなどによって判決が異なるようです。
そんなことを考えると、問題が起きたとき必ず悪影響を取り除く処置が必要なのか、再発防止が必要なのかは一概に言えません。
ISO規格では「是正処置は、環境影響も含め、検出された不適合のもつ影響の著しさに応じたものでなければならない」とある。つまり重大ならしっかりやれ、重大でなければ手を抜けということだと思う。まあ妥当な考えだろう。
しかし規格には、「是正処置は……応じたものでなければならない」とあるのだから、すべての不具合に対して「環境影響を取り除くこと、再発防止をすること」をしなければならず、ただ完璧にするかそこまでしないかの裁量を与えると読める。
決して小さな不具合については、環境影響を取り除くことをしなくてよいとか再発防止をしなくてもよいのではない。
納得いかないことがある。
2004年版「4.5.3 不適合並びに是正処置及び予防処置」
Actions taken shall be appropriate to the magnitude of the problems(以下略)
取られた処置は……ものであること
2015年版「10.2 不適合及び是正処置」
Corrective actions shall be appropriate to the significance of the effects of the nonconformities encountered(以下略)
是正処置は……でなければならない
2004年版の和訳は、なぜ「取られた」と過去形なのだろう? 原文は単に受け身を表す過去分詞というだけだ。だから原文をそのまま訳せば「取られる処置は……ものであること」となる。
日本語訳にするとき「取られた」と過去形にしたことは「是正処置は必ずしたはずだが、それは重大性を考慮しているか」という意味に思える。
あるいは2004年版は主語が是正処置でなく処置だから、処置は必ずしているはずということか?
ともかくいくら探しても<是正処置はしないこともある>という記述はない。
実を言って私の審査を受けた経験では、審査員は不具合について必ず是正処置をどうしたか聞いてきた。現在の規格の文章では、悪影響は取り除くが是正処置(再発防止)をしないという選択はないのだから、不適合があれば審査員は是正処置を確認するのは当然だ。
こちらは面倒だから説明しやすい不適合だけを見せ、その是正処置を説明して終わるのを常とした。審査員も微妙な問題を見せられても困るだろう。
ともかく世の中にはパーフェクトなんて存在しない。できることもあるができないこともある。先立つものは金だ。
それとシステムの不適合ならともかく、技術的とか設備的に確率的な問題というのもあるし、技術そのものが確立していないものもある。
だから規格にはっきりと、
「取るべき処置及び是正処置はその影響の重大性と費用対効果を考慮し、実施する範囲と程度を決定しなければならない」
とするべきではないだろうか?
述部は「決定してもよい」ではなく「決定しなければならない」とするのは、上記囲みに書いたように営利企業としては当然だ。
もちろん法違反や消防が出動する事故が10年に一度発生することは許容するなんて、乱暴なことを言うつもりはない。
帳票の書き間違いとか、計測器の校正漏れなどは正直言って確率的に発生する。それはお前の働いている会社のレベルが低いというかもしれない。そう言われるとそうかもしれない。
もちろんどんな課題にだって対策はあるだろう。記載ミスをなくすためにタブレット入力にするとか、校正漏れをなくすために期限が過ぎたらラインが動かなくなるタイマーを仕込むとか、完璧を期す方法は考えられる。だがすべて費用対効果という制約を逃れることはできない。
そして人間とは間違える生き物である。孔子は過ちて改めざる云々と語ったが、改めても再び過ちを犯すのも世の習い。あなただって間違いをしているはずだ。
もし是正処置は完璧に行っているという組織・会社があるなら、そこでは絶対に再発していないはずだから、検認も内部監査もいらない。
それにさ現場でも事務でも新人教育中は、不具合がバンバン出るのは当たり前。それを指導するのも是正処置に入るのだろうか? 教育期間中は指導であり是正とは言わないのか?
ノイズなどの影響を受けるものや自動制御では、目的を達するためにフィードバックをかけるのは必然だ。
外部ノイズ、ヒューマンエラー、部品の劣化などにより管理限界を超える状況は不適合であるが、それを補正して目的を達するシステムであれば、システムとしては不適合がない。
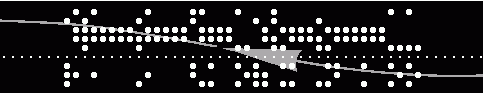
ということは、不適合か適合かを判断するのは部分ではなく最終目的であることになる。
ちょっと待て、不適合の定義は何だ?
JISQ9000:2015 3.6.9 不適合
要求事項(3.6.4)を満たしていないこと。
要求事項は
明示されている、通常暗黙に了解されている業務として要求されている、ニーズ又は期待。
である。
品質ならFOBならぬ「顧客渡し」時点だろう。環境なら外部への影響時点ではないだろうか?
というと、業務プロセスを考えたとき、何をもって不適合と定義するかはその組織が決定することだろう。
客に渡すまでに不良をはねる仕組みがあればライン不良は不適合でないとしてもおかしくない。事務処理で課長、部長の検認や決裁時にチェックし異常を差し戻し見直しをさせているならそれは不適合でないとしてもおかしくない。
また日常決裁というお仕事をしていると、部下を読んで内容を確認しなければならないこともあり、その結果仕事のやり直しを命じることも日常的に発生する。もしそんなことしてないなら管理者はいらない。
つまり不適合をなくすことはできないけど、外部への影響をなくすためにシステムを見直すことは是正処置だろう。当初発生し不適合とされた現象をなくしてはいないが、その現象を外部に影響しないようにシステムを見直すことは是正とは言わないのか?
えっ!私の言っていることがわからない?
例えば、このタクシー券、時間と出発点目的地がおかしいんじゃないか?なんてあなた部下に聞いたことないですか?
いまどきマニフェスト票を起票している会社もないだろうけど、伝票の埋まってないマスを記入しろと言ったとかあると思うねえ〜
その結果、最終決裁や経理に行く前に処置すれば不適合ではないとしているのではないか?
そういう検認とかをどう考えているのだろうか?
![]() 本日の疑問
本日の疑問
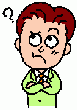 再発防止策をして完全に再発しなくなったことってありますか?
再発防止策をして完全に再発しなくなったことってありますか?
もちろん○○という部品が壊れやすいから、その部品をなくしたという対策はあるでしょうけど。
新聞記事や雑誌を見ている限り、どの会社も改善の種は尽きないようだけど……
![]() 本日の続編
本日の続編
この項番の記述にはなんか引っかかるのですよ。なんか文章というか考えそのものが、論理的でないような気がするのです。
本日もフィードバックループ内で収まっているなら不適合ではないという考えと日常管理での検認・決裁により指導と是正については生煮えです。今後納得できないことで腹ふくるるときは続編を書きます。
うそ800の目次にもどる
規格解説の目次に戻る