- お断り
- まずタイトルに「4」が付いているのは、過去に三度 同じ題で書いているから。
- それから長文ですからお時間がない時は止めといたほうが良いです。
「持続可能性」とは広辞苑では「保ち続けることができる・中断しないでいられる」ことの意味。だが昨今、特に環境問題や地球温暖化騒ぎで使われている「持続可能性」は日本古来の意味ではなく、英語の「Sustainability」の訳語である。
では英語ではどんな意味なのか、まずは英英辞典を引こう。
複数の英英辞典を引いてみたが、いずれも二通りの意味があった。
- the ability to be maintained at a certain rate or level.
特定の能力を定められた合格率や水準に維持する能力。
able to continue for a long time
長時間継続できる能力 - avoidance of the depletion of natural resources in order to maintain an ecological balance.
生態学的バランスを維持するための天然資源の枯渇の回避。
able to continue without causing damage to the environment
環境に害を与えることなく継続できること
1番目が昔からの語義だろう。2番目は環境問題が大きくなってから追加された意味合いに思える。
一見「Sustainability」は、日本語の「持続可能性」と同じように思える。
しかしmaintainは英語では単純に「現状を継続する」というより「周囲の変化に応じて対応する」というニュアンスがある。日本でも「機械のメンテナンス」という場合はそういう意味合いを持つ。
それからa long timeはどれくらいの期間をいうのか?
日本語では長期間といっても、対象によって時間的長さが異なると思う。食品なら数週間なら長期間だろうし、車なら数年、建築物とか道路なら十年単位だろうか。環境で長期間とはgeneration(30年)なのかcentury(100年)なのかmillennium(千年)なのか?
英語で久しぶりをIt's been a long time.と言うが、普通long timeというと半年以上らしい。
英英辞典では時間にlongを使った時の意味は
continuing for a large amount of time, or for a larger amount of time than usual
ものすごく長い時間、または通常よりも長い時間のこと
いずれにしてもlong timeは永遠とか終わりないことではなく「終わりのある長期間」だ。
もう10年も前のこと、環境の講演会で大学の先生の話の後、持続可能性とは何年間を想定しているのかと質問したことがある。
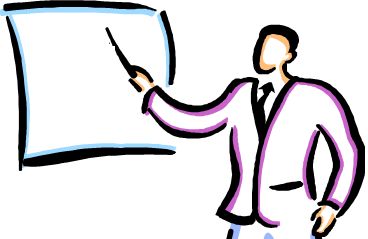
その先生は「永遠です」という。私は人間が考えられる期間とは、せいぜい数百年か長くても千年程度ではないかと再度質問した。
その先生、少しも騒がず「永遠とは永久で終わりがないことだ」とのたまわく。そして私がクレームでも付けているかのように罵られた。イヤハヤ
日本語の語義から言えば先生の理解は間違いないだろうけど、Sustainabilityの語義からは私が正しいのではないだろうか? そしてなによりも期間を考えない施策も実施計画もあるはずがない。
注:IPCCとは国連気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change)とあるように各国政府がメンバーであり、報告書の冒頭に「政策決定者向け」と付いていて各国の政策決定者に対する報告書なのである。
どの国でも政権が続くのがせいぜい10年ならば、100年後に責任を持てるはずがない。
ではこれを踏まえて、本日は持続可能性とは何年なのか考えたい。
えっ!今までは前振りかという声が聞こえた。
そうなんです。そして前振りは長く、本番は短いってことが多いんです。
「バイオスフィア」という言葉を聞いたことがありますか? バイオスフィアとは「生物圏」と訳され、生物が住まう領域のことで、早い話 生態系が存在する領域のこと。
「バイオスフィア2」という言葉を聞いたことがあるかもしれない。20世紀末にアメリカの砂漠に密閉された大きな温室を作り、そこで農業や畜産を行い空気の循環を含めて自給自足生活を実験した。
開始早々に、植物の炭酸同化作用だけでは酸素が不足し、農業や畜産どころか実験者の健康に支障が出て実験は中止された。いかに持続可能が難しいかということだ。
大規模なものでなく、外気と遮断された小さなビンの中に作られた生態系もバイオスフィアと呼ぶ。エコスフィアとかパーフェクトアクアリウムなど称しているものもあるが、商品名かもしれない。商品として売られているものは、普通の水槽の形でなく球形のガラス容器が多い。
 | |||
基本は太陽光を受けて水草が酸素を作り、その酸素で植物プランクトンが成長し、それを動物プランクトンが食べ、それをエビが食べ、老廃物を分解するバクテリアがいてという生態系になる。
非常に小さなエネルギーの生態系だから、水草もエビも増殖・繁殖はできず個体の寿命が来るとおしまいのようです。
エネルギーからみると、太陽光が入り、食物連鎖を通じて仕事をして、エントロピーを排出するという単純なものです。
これを大きくしたのが前出のバイオスフィア2であり、更に大きいのが地球の生態系です。
地球は熱機関ともいわれます。
熱機関とは高校の物理で習うはずですが、熱エネルギーを運動エネルギーに変える仕組みをいいます。熱エネルギーとは高温と低温の差です。いくら高温でも温度差がないと仕事ができません。
地球の場合は太陽と宇宙空間の温度差で仕事をします。仕事といっても飛行機や船を動かすのではない。もっと大きな仕事です。
| 太陽 | 6000K | Kはケルビンと読み絶対温度(摂氏+273度)のこと | |
| 太陽光 | |||
| 地球 | 300K | 仕事(風を起こす、波を作る、台風を作る) | |
| 赤外線 | |||
| 宇宙空間 | 3K |
地球は太陽エネルギーでどんな仕事をしているのかというと、地球の大気と海水を動かすことです。もちろん仕事量としては地球の自転・公転そして月の引力の方が大きいでしょうけど、生命活動に関わる観点からは熱機関の働きが大きいでしょう。
生命が発生したのは海岸近くの水たまりだったという説があります。波打ち際の水たまりで海の満ち引きと、寄せては返す波によって単純な化合物から複雑な化合物が作られ、それが生物に進化したといいます。
今現在も風、雨、嵐を起こし、また大気を撹拌することにより気温の差を少なくし、大気組成を平均化しています。温室の植物が枯れやすいのは、風がないためと言われます。また都市部で発生する排気ガスは滞留するとどんどん濃くなるのを、拡散させて分解しやすくしている。ありがたいことです。
もちろん台風や集中豪雨も起こします。でも台風が来なければ良いわけではありません。台風が来ないと水不足になり飲料水だけでなく農業に多大な支障が起きる。風がなくなれば風媒花もこまるけど、気温の差が拡大する。
当たり前ですが、高温熱源と低温熱源がないと仕事をしません。ものすごく熱い物体があってもそれだけではエネルギーを取り出すことはできない。
太陽からくる可視光線は地球の大気を素通りします。というか地球の大気を通過した光を感知するように生物が進化したわけです。
赤外線しか通さない大気を持つ星なら、そこの生物は赤外線を感知するようになり、X線しか通過しないならX線を感知するようになるはずです。だって感覚器官は生存のために、危険を避け食物を見つけるためのもので、生存に役立たないものをわざわざ身に着けるはずがありません。
実は地球温暖化とは低温熱源がなくなることなのです。
地球で仕事した光はエネルギーを失い波長の長い赤外線になる。それをより温度の低い低温熱源に引き渡さなければならない。
しかし本来なら大気を通過して宇宙に出ていく赤外線が、大気中に二酸化炭素が増えるとそれに反射されて、どんどんと地球の気温が上がってしまうというのが温暖化する理屈だ。
おお、なんだか持続可能性につながってきたような気がする。
ともかく持続可能性のために高温熱源と低温熱源が必要なことが分かった。
低温熱源はなくなることはまずない。というか宇宙は膨張しているから、今絶対温度で3Kといわれるが、これが更に冷えていくことは間違いない。だって断熱膨張は冷えることに決まっている。
高温熱源である太陽の寿命はどうかというと、現在と同程度のエネルギー放出は今後60億年くらい続くらしい。
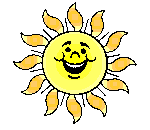 そのころになると中心部の水素が使い尽くされ、だんだんと外側の水素が核融合するようになる。そうなると太陽は膨張して赤色巨星となり、その大きさはなんと金星の軌道よりも大きくなる。
そのころになると中心部の水素が使い尽くされ、だんだんと外側の水素が核融合するようになる。そうなると太陽は膨張して赤色巨星となり、その大きさはなんと金星の軌道よりも大きくなる。
70億年以上経つと水素を使いつくし、今度は水素の核融合からできたヘリウムを核融合し始め、更に重い原子を作り出すようになる。こうなるとドンドン太陽は小さくなるというか縮んでしまう。そして最後はドーン爆発してその後は小さな燃え殻だけが残るというのが科学的予想らしい。
太陽のおかげで発生した生命や生態系は、太陽とともに終わるのはやむを得ない。地球に生命が存在できるのは60億年後までだ。
となると持続可能とは永遠ではなく、どう頑張っても60億年以内であるようだ。
注:永遠とは、物事が時間とともに変化するのに対して、過ぎ去っていく時間に関わりなく不変のものをいうそうだ。 前出の大学の先生は、宇宙が消滅してもなお持続可能は存在すると考えていたのだろうか?
ところで、太陽系の死刑執行が60億年後といっても、それまで地球の生態系が続くわけではない。過去より地球の生物の大量絶滅はたびたび起きた。地層の研究などから5回は間違いなくあったそうだが、6回以上という説もある。
大量絶滅とはどんなことだろうか?
- スノーボールアース
地球ができあがり、地表が冷えてやっと単細胞生物が現れたと思ったら、地球全体が凍り付くスノーボールアース(全球凍結)になった。スノーボールアースになったのは3回あったそうです。生命は水と酸素による化学反応ですから、生きていける温度範囲がある。下は化学物質の溶媒である水が凍るとダメ、上はたんぱく質が固まる42℃を超えるとダメです。
スノーボールアースのとき、やっと地球に生まれた命はどうしたのでしょうか?
地熱・火山などでほんのわずか凍らず残った水面で生き永らえたという説があります。地上に命があるのは奇跡の重なりですね。なお氷河時代はスノーボールになったわけではない。現代より平均気温で6℃くらい低かっただけです。そして氷雪におおわれていたのは欧州や北アメリカ大陸北部だけです。
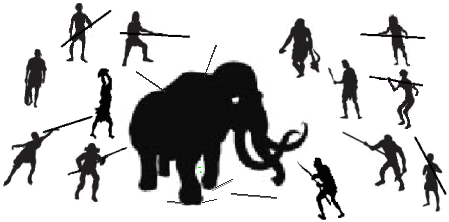 それ以外の地域は今より低温ではありましたが、森林も草原もありました。そして我々のご先祖は狩りをしたり、木の実を取って暮らしていました。
それ以外の地域は今より低温ではありましたが、森林も草原もありました。そして我々のご先祖は狩りをしたり、木の実を取って暮らしていました。
社会の教科書に、洞窟から銀世界を眺める原始人の絵がありましたが、あれはたぶんスカンジナビア半島あたりじゃないのでしょうか。間違っても日本列島ではありません。 - 酸化性大気への変化
嫌気性生物の楽園だった地球を、酸素という毒ガスで殺戮したシアノバクテリアの出現はご存じの通り。それはまさに、世界中にサリンをまき散らした様な悪行です。
酸素を毒ガスというと驚くかもしれないが、老化は活性酸素のせいだともいわれます。我々酸素で生きている生物も、酸素となんとか折り合いをつけて生きているのです。
我々人類も動物も植物も、みな殺戮者の子孫である。被害者はみな死んじゃったから文句は言われない。 - 海洋無酸素事変
海洋無酸素事変なんて戦争のような名前ですが、あるとき海水が無酸素状態になったそうです。赤潮と呼ばれる現象も酸素がなくなってプランクトンや魚が死ぬ現象ですが、これはそれが全地球規模で起きたそうです。しかも1度でなくわかっているだけで3度あったそうです。
水中や海水中の酸素濃度は最高で約8ppmですが、2ppmになると生存困難となります。海洋無酸素事変ではこれが0ppmになったわけ。注:正確にはmg/lとppmは等しくないが、わかりやすくするためにppm表示にした。
- 隕石落下
白亜紀には子供たちの大好きな恐竜を、皆殺しにした隕石衝突があった。まあ細かく言えば諸説あるが四捨五入…じゃなかった、切り捨て。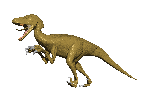
隕石が地球に衝突するとき地上から隕石が見えるのか研究した人がいる。月の距離だと直径が10キロならまず目視ではわからない(注1)。
大気に突入すると白熱して見たくなくてもすごい光と熱線で気が付くでしょうけど、それはほんの一瞬のこと。
今は望遠鏡で宇宙を見ているから遠くにある時から気が付くだろうけど、早く見つけても逃げようがないなら死ぬまで気が付かないほうが幸せのような気もする。
大量絶滅といってもすべての生物が死んだわけではない。大量絶滅直後に生き残った生物は急速に進化したといわれます。
どんな社会でも生態系でもランク付けされている。金持ちと貧乏人、偉い人と偉くない人、いじめっ子といじめられっ子、食べる生物と食べられる生物。自然環境が安定していれば、その序列も変わらない。
しかし一旦 大量絶滅が起きると生態系も食物連鎖もシャッフルされる。新しい環境に合わない生き物は死滅するしかない。今までふんぞり返っていたエスタブリッシュメントがその地位を追われ、最下層にいたものがトップに躍り出ることもある。
 |
|
ネズミって、僕の ことじゃないの? |
恐竜が滅びなければ、我々哺乳類は今のゴキブリのような生活をしていたかもしれない。そして恐竜から進化した竜人が、文句を言いながら殺虫剤の代わりに殺哺剤をまいて哺乳類どもを駆除しているんじゃないかな。オフィスにはネクタイをしたラプトルがパソコンを叩いていたりして……
ともかく地球に生命が誕生してからの40億年の間に最低5回、実際には更に数多い絶滅があったはずだ。となるとこれから地球に住めなくなる60億年の間に7回以上の大量絶滅が起きておかしくない。そして大量絶滅が起きるたびに、それまでの覇者は表彰台から蹴落とされ、新たなヒーローがとって代わるだろう。
人類も次の大量絶滅までしか万物の霊長を称することは許されない。
ということは人類にとって持続可能できるのは60億年後でなく、次回大量絶滅までの期間となる。大量絶滅はカンブリア紀末期の4億8800万年前から現在までに6回起きているから、8100万年間隔に起きていることになる。最後に起きた白亜紀の大量絶滅から既に6600万年経過しているから次回大量絶滅まで1500万年しかない。
60億年から一挙に1%以下の1500万年になってしまった!
種には寿命があるのか?
ここでいう種とはタネのことではない。生物学の「界・門・綱・目・科・属・種」という分類の階層の種こと。
 |
|
の標本 |
種が同じなら交配が可能、というか交配できる範囲を種という。同じホモ・サピエンスである黒人と黄色人種は子供を作れる。チンパンジーはヒト科まで同じだが、チンパンジー属・チンパンジー種で、属のレベルで人と異なるから、人とチンパンジーでは子供を作れない。
過去より数多くの生物の種が現れて消えていった。それが進化であり自然淘汰である。ゴキブリは3億年前から生きているというけど、同じ種が生き残っているわけではない。体の形態は似ているけど、種は別だ。
一説によると我々ホモ・サピエンスという種の寿命はあと680万年というのもある
一説によると現在存在する種は、過去から現在まで存在した種の1割もないという
しかし種が絶滅するのは当たり前だ。生物は環境に適応したものだけが生き残り、そうでないものは滅びる。それが進化である。
また種として存続するには一定数の個体数がいなければならないが、あまりにも種が多くなれば種が存続できる個体数を切ってしまうのではないだろうか?
ともかく個体の寿命でなく種の寿命を考えると、ある程度時間が経つと別の種に交代するか、あるいは自分たちの一族から変化した新種に、今までのニッチを渡して退場するというのは当たり前に思える。
「利己的遺伝子
そういう見方をすると、絶滅危惧種を守れとかレッドデータブックがどうとかいう発想は無意味に思える。
どの時点でも生息している生物の種は過去から登場した生物の1割以下とすると、現在の形態の生物発生をカンブリア紀以降とすれば、種が存在していたのは平均4800万年となる。ヒト種が表れてから20万年といわれるから、あと4780万年存続するのかとなると、どうもそうは思えない。そもそもそんなに長続きした種は存在しない。
となると1割というのは種レベルでなく属レベルなのだろうか? 仮に属とするとホモ属は200万年前には登場していたから、あと4600万年続くことになるのだが、そんなに長く生き残るとは思えない。
もちろんホモサピエンスが滅びる時が、ホモ属の滅びる時ではない。サピエンス種が最後のホモ属でなく、現生人類より進化したホモ属ミュータント種が現れる可能性のほうがはるかに大きい。ともかく現生人類の終末はデルタt理論から60万年後となる。
太陽系の終焉なら持続可能性は60億年だったが、大量絶滅で考えると1500万年になり、種の寿命があるとすると60万年とだんだん短くなってきた。
これは困ったことなのか、そうでもないのか?
さて、今地球温暖化で騒がれているが、地球は氷河期と間氷期を繰り返している。いつかは次の氷河期が来るのは間違いない。人類の文明は氷河期になっても持続可能なのだろうか?
現在の文明を維持するという前提なら、それはいささか難しそうだ。CO2問題を乗り越え、エネルギー問題をクリアしても、資源枯渇はどうなるのか?
まず次の氷河期はいつからなのか?
学者によってさまざまだが、いつ氷河期になってもおかしくないという人、本来なら氷河期になっているのだがCO2によって気温を上げているという説、1万年後という説、5万年後という説、さまざまです。
でも気が付きましたか?
持続可能の期間はいろいろなケースを考えるほどどんどん短くなって、氷河期から考えると1万年あるいはゼロとなってしまいました!
前出の大学の先生は、氷河期になっても持続可能はできると考えていたのだろうか?
いや生存はできるかもしれないが、「将来世代のニーズを損なうことなく現在の世代のニーズを満たす経済」というものが実現可能なのか?
ここまでで、持続可能なんてムリ、今の人々や次世代の人々のニーズを満たすことはできないことははっきりした。
当面の課題である地球温暖化を止めても、それは真の持続可能どころか、現在の文明を延長するだけ、しかもそれが短期間であることも明白だ。
持続可能性だと騒ぐ人が多いが、彼らはいかほどの長きにおいて持続可能性を考えているのだろう? 前出の大学の先生のように「永遠」と考えているなら、それは理屈から不可能だ。
ここで改めて持続可能性の公になっている唯一の定義であるブルントラントの報告書「我ら共有の未来」にある「将来世代のニーズを損なうことなく現在の世代のニーズを満たす経済」を考えよう。
読み直してみれば、それは生活水準も生活様式も政治体制も言及していない。言い換えると、ここで言っている持続可能とは「生存が可能なら持続可能である」と読めるのではなかろうか?
単純に言えば人間が生き延びるなら持続可能ではないか?
そもそもニーズとあって、ウォンツではない。どちらも欲しいことに変わりないが、ニーズは必要、ウォンツは欲望である。
我々は普段欲しいものがどちらなのか意識してないし、自分自身わかっていないと思う。
コーヒーを飲みたくなったのは、のどが渇いたからなのか、少し休みたいのか、人と話したいなのか、その他さまざまな理由があるだろう。いずれの場合も、コーヒーは目的でなく手段だ。暑くてのどを潤したいなら、水道水で間に合う。休みたいなら道端のベンチで間にあう。
| needs | ≠ | wants |
最低限のニーズに合わせた世界なら必要とする資源もエネルギーも、大幅に減少するだろう。
資源が枯渇した時代になれば独裁専制の支配体制であっても、ニーズを満たせばOKと言い切ってよいのではないか。おっと、私が独裁を勧めるわけではない。
サポーズ、1500年頃の戦国時代、小氷期で作物が取れず人口支持力が乏しいときに、どうやってもみんなが豊かな暮らしができるわけがない。みんなが貧しくというのも、自然環境によっては最適解かもしれない。
逆に現代の世代が、地球温暖化上等!資源枯渇関係ねえ!将来の世代なんて見たことねえ!と自分勝手に決めつけて、今のために湯水のごとく資源を消費してもそれを咎める理由もない。
イギリスや欧州の森林を丸坊主にして産業革命を推し進めた人たちを、森を残していてくれたらと恨む人がいかほどいるのか? 同じく、5世紀くらい後、21世紀の人たちがCO2を減らしていてくれたらというものだろうか?
ともかく持続可能性とはどういうものかを、はっきり定義しなければ、それが実現可能か不可能か論じることはできない。
![]() 本日のお悔み
本日のお悔み
本文に書いた講演会での某教授とのやりとりは偽りのない事実です。その先生は何年も前に退職しましたが、今月お亡くなりになったと知りました。
願わくはここに書いたことを先生にぶつけてご意見を聞きたかった。残念ながらそれは叶わじ、ご冥福をお祈りいたします。合掌
なんか最近 長くなるばかり。前回は8,000文字。今回は短くと思いましたが、結果は限界を超えて8600文字。
読む方も大変でしょう。これからは5000字以内を目指します(ホントかな)。
注1 |
6550万年前に衝突した隕石の直径は10キロから80キロといわれている。なにせ大昔のことだから正確なところはわからない。これは月の距離にあると視野角4秒しかない。よほど光を反射しないと、まずわからない。そして秒速10キロ以上とすると月の距離から衝突まで10時間しかないから、見えてから逃げる間もないだろう。 「恐竜を絶滅させた「隕石」は「凶悪な角度」で地球に突入した」 | 注2 | 注2.5 |
「生物はなぜ誕生したのか」ピーター・ウォード他、河出書房、2020 |
注3 |
利己的遺伝子とは1970年代イギリスのリチャード・ドーキンスによって提唱された、存続するのは遺伝子であり、人間を含めて生き物は遺伝子の乗り物に過ぎないという発想。 | |
注4 |
「環境都市の真実-江戸の空になぜ鶴は飛んでいたのか」箱崎光男、講談社新書、2008 |
外資社員様からお便りを頂きました(2021.04.20)
おばQさま いつも興味深い内容を有難うございます。 私もSustainableの期間って、どのくらいか疑問をもっていたので、とても参考になりました。 比較文化論でいうと、欧米人 キリスト教では時間軸は一本線。 神が「光あれ」から始めて、世界を作って、キリストが降誕して、人は死後に「最後の審判」を受ける。 だから、始めと、終わりがある一本線、 だから永遠が無限なんて考えなくて、最後の審判までという事ですね。 その後の時間:楽園には時間なんてないのでしょう。 だから、持続可能なのは、いづれにせよ限度があります。 ご指摘の「永遠だ」とノタモウた先生もそうですが、気軽に永遠なんて使って欲しくないですね。東京オリンピックのマスコットも、「ミライトワ(未来永遠)」ですって。 永遠は不変でないと実現不可能でしょう、でも未来は変化するからやってくる。 これほど矛盾と欺瞞に満ちた名前はありませんね、そのせいか東京オリンピックは、過去ないほどに問題を抱えてしまいました。 仏教の世界でも印度で出来ただけあって、数字や時間単位を大事にします。 弥勒菩薩は56億7千万年後に現れて世界を救うそうですが、永遠の先ではありません。 輪廻の概念は一本線ではなくて、ぐるぐると回る螺旋のイメージでしょうか。 それでも仏教でも永遠なんて言いませんからね。 >最低限のニーズに合わせた世界なら必要とする資源もエネルギーも、 >大幅に減少するだろう。 仰る通りなのです、実態を見れば資源に配慮した紙は茶色で白い紙よりも高い。 航空会社も25年までに持続可能エネルギーに転換とか言っていますが、その燃料は現在のものよりもきっと高いのです。 つまり、この手の運動は、より高いものを世間に受け入れさせるためのマーケティング手法なのでは無いかと思います。 コロナが終息して旅行が出来るようになった時に、環境に配慮した会社の飛行機が30%高くても乗りますという人ならば、それでOK. それでも安い方がいいやという人は、いるのです。 本当は安い航空会社のビジネスクラスに、環境配慮航空会社のエコノミー代金で乗れれば最高ですが、安い会社は全席エコノミー。 結局、環境に配慮は、お金に余裕がある人が、よい多くの金を払う為の満足感なのだと思います。その証拠に、発展途上国や中進国では流行らない、先進国だけが騒いでおります。 |
外資社員様 毎度ありがとうございます。 >航空会社も25年までに持続可能エネルギーに転換とか言っています >が、その燃料は現在のものよりもきっと高いのです。 >つまり、この手の運動は、より高いものを世間に受け入れさせるため >のマーケティング手法なのでは無いかと思います。 ずばりそうでしょう。「不都合な真実」なんて嘘っぱちの本を書いたゴア元副大統領は、真摯な環境保護者じゃなくて、新エネルギーの関係者です。 まっ、それを言っちゃ新エネ反対側だった息子ブッシュは、石油資本とグダグダでしたけど。 いずれにしても環境保護ではなくお金の話でしょう。しかしかっこいい話を聞いてそれを信じている学者やマスコミがヨタ話を増幅して広報しますから一般国民は騙されてお金を出して、貧乏くじ引くのは日本と決まっています。 今だGHQとか日本管理委員会なんてのが機能しているんでしょうね。戦後レジュームの……とこぶしを振り上げても、振り向けばみな環境保護、地球温暖化を止めろって人ばかり。嗚呼、無情 |
うそ800の目次にもどる