お断り
このコーナーは「推薦する本」というタイトルであるが、推薦する本にこだわらず、推薦しない本についても駄文を書いている。そして書いているのは本のあらすじとか読書感想文ではなく、私がその本を読んだことによって、何を考えたかとか何をしたとかいうことである。読んだ本はそのきっかけにすぎない。だからとりあげた本の内容について知りたい方には不向きだ。
よってここで取り上げた本そのものについてのコメントはご遠慮する。
ぜひ私が感じたこと、私が考えたことについてコメントいただきたい。
何年前になるだろうか? 東京メトロに乗っていて、「江戸しぐさ」と書かれたポスターを見た。
 |  |
ほう、江戸時代はそんな風な気遣いをしたのか感心し、自分もそう努めようと思った。
私が地下鉄で「江戸しぐさ」のポスターを見たのはそれっきりだ。なぜかその後、地下鉄でそのようなポスターは見たことがない。
ところがところが、最近読んだ本に「江戸しぐさ」は真っ赤なウソと書いてある。「江戸しぐさ」なる言葉は1980年以前にはなかったそうだ。要するに近年になって作られたものということだ。
もちろん1冊だけでは心もとない。まして否定派の本を読んだだけでは一方的だ。肯定派・推進派の本も読まねば何とも言えない。
というわけで図書館に行ってタイトルに「江戸しぐさ」のある本を探した。
検索すると図書館蔵書は16点だった。当然のことだが、「江戸しぐさ肯定本」と「江戸しぐさ否定本」があるわけだ。ともかくその中から5冊借りてきた。
図書館蔵書が意外に少なかったので、家に帰ると書誌データベースとアマゾンでタイトルに「江戸しぐさ」の付くものを検索した。
その結果が下表である。
| 区分 | 市図書館蔵書 | BOOK or JP | アマゾン検索 | |||
| 出版年 | 肯定 | 否定 | 肯定 | 否定 | 肯定 | 否定 |
| 1986 | ● | |||||
| 1987 | ||||||
| 1988 | ||||||
| 1989 | ||||||
| 1990 | ||||||
| 1991 | ||||||
| 1992 | ● | |||||
| 1993 | ||||||
| 1994 | ||||||
| 1995 | ||||||
| 1996 | ||||||
| 1997 | ||||||
| 1998 | ||||||
| 1999 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2001 | ● | ● | ● | |||
| 2002 | ||||||
| 2003 | ||||||
| 2004 | ● | ● | ● | |||
| 2005 | ● | |||||
| 2006 | ●● | ●● | ●●●●● | |||
| 2007 | ●●●● | ●●●●● | ●●●●● | |||
| 2008 | ●● | ●●●●● | ●●●●●● | |||
| 2009 | ●●● | ●●● | ||||
| 2010 | ● | ●●● | ||||
| 2011 | ||||||
| 2012 | ● | ● | ● | |||
| 2013 | ● | ● | ●● | |||
| 2014 | ● | ● | ● | |||
| 2015 | ● | ● | ● | |||
| 2016 | ● | ● | ● | |||
| 2017 | ||||||
| 2018 | ● | ● | ● | |||
| 2019 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2021 | ||||||
三つの検索結果が違うのは当たり前だ。その理由は、
- 図書館蔵書は、市図書館司書が決めたり利用者の依頼により購入し、貸出しが長期間なければ廃棄される。もちろん市によって購入基準も廃棄基準も異なる。
- 出版書誌データベースは、各出版社から提供された、現在販売している紙と電子書籍の情報であり、中古しか入手できないものは載らない。だから上の表は2022年9月時点である。
- アマゾンは、出品されている新品及び古本、並びに過去に出品された古本が表示される。アマゾンで売買されない本は載らない。
各年に出版された点数を正確に知るには、過去の毎年の出版年鑑(2019年で休刊)から数え上げないと分からない。だから上表は各年に発行された正確なデータでないが、考えを進めるにはこの程度で十分だろう。
この表から分かることとして、
- 「江戸しぐさ」がタイトルにつく本は1986年が最古である。 アマゾンでは過去に出品されたことがあれば、それ以降は物がなくても「出品なし」と表示されるから、それ以前はないと推定される。
- 「江戸しぐさ」の出版が活発になったのは、2004年以降である。
- 否定派の本は最古で2014年出版であること
- 肯定派の本は2015年が最終で、それ以降出版されていない。
どちらが正しいか多数決で……となるわけではない。証拠による裏付けのある本と、そうでないものでは存在意義が違う。
2014年に否定派の本が出た後、2015年に発行された肯定派の本はそれ以前から計画していたものだろうが、それ以降肯定派の本が皆無ということで形勢は決定的と推察する。
 批判本が出たのちに、様々な場所で複数の歴史学者が、元々「江戸しぐさ」という言葉はなく、それを講(勉強会のようなもの)で教えていたこともなく、また「江戸しぐさ」本の中で書いている明治維新時に江戸しぐさを教えていた人たちに対する弾圧も虐殺もなかったと論じている。
批判本が出たのちに、様々な場所で複数の歴史学者が、元々「江戸しぐさ」という言葉はなく、それを講(勉強会のようなもの)で教えていたこともなく、また「江戸しぐさ」本の中で書いている明治維新時に江戸しぐさを教えていた人たちに対する弾圧も虐殺もなかったと論じている。
それだけでなく、否定派の本が出版された以降、否定派と肯定派の書簡交換も公開討論もなく、肯定派が否定派を否定する本を出版していないこと、などから社会的には肯定派は否定派と争う気がない……ということは否定派を否定する根拠がないとして、「江戸しぐさ」は否定されたとみなされている。
気になることがある。肯定本の波は2010年頃におさまっている。最初の批判本が出る3年前である。批判本が出版される前から、ネットでは批判されたのだろうか?
そこでGoogleで2000年〜2010年に期間限定して、キーワード「江戸+しぐさ」で検索し、上位約150件を肯定・批判・その他に分けた。「江戸っ子のしぐさ」などは除いた。
| 年 | 肯定 | 否定 | その他 報道・広告 |
| 2000 | ● | ● | |
| 2001 | |||
| 2002 | ● | ||
| 2003 | ● | ||
| 2004 | ●●●●● | ●● | |
| 2005 | ●●● | ||
| 2006 | ●●●●●● | ●● | |
| 2007 | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● | ●●●●●● | |
| 2008 | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●● | ● | ●●● |
| 2009 | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●● | ●●●●● | |
| 2010 | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●● | ●●●●●● |
書籍と同じくして2004年から「江戸しぐさ」に関するウェブサイト/ブログは急速に増えた。しかし2007年頃には飽和してきたように思える。それは書籍も一緒だ。
ところで上表を見ると、「江戸しぐさ」の露出が大きくなった2000年以降を見ても、「江戸しぐさ」を批判するウェブサイトもブログなどもほとんど存在していない。
ということは「江戸しぐさ」という運動あるいはファッションは、批判勢力がないにもかかわらず2010年頃には既に成長の限界に来ていたのかもしれない。
恐竜が滅んだのは、元々種の寿命の末期だったところに隕石が落ちたからという説もある。
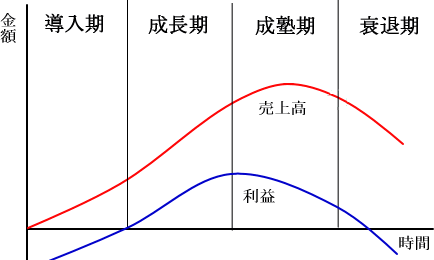 左図は一般的な製品ライフサイクルの模式図である。「江戸しぐさ」は、成長期を過ぎ成熟期に入りつつあるときに、批判本が出て急速に衰えたのかもしれない。
左図は一般的な製品ライフサイクルの模式図である。「江戸しぐさ」は、成長期を過ぎ成熟期に入りつつあるときに、批判本が出て急速に衰えたのかもしれない。
いっときは多方面で「江戸しぐさ」のありがたみが称えられ、学校教育の場でも教えられたが、批判を浴びて「江戸しぐさ」はマナー向上のポスターに使われることもなくなり、学校教育の場からも消えつつあるという。
辞書に載っている言葉だが、その記載は否定的である。
- 2022年の今、ネットの辞書では次のように記載されている。
- ニコニコ大百科
江戸しぐさとは、江戸時代、江戸の町人、商人のマナーだったと一部の残念な人たちによって主張されている捏造しぐさである。 - weblio辞書
と学会会員で歴史研究家・作家の原田実は、江戸しぐさは1980年代に芝三光によって「発明」された全く歴史的根拠の無いものであるとの疑義を呈している。 - コトバンク
江戸しぐさの実在を裏付ける史料は2015年時点で確認されていない。
果たして江戸しぐさは、あったのか/なかったのかとなれば、私は断定できないが、なかったように思う。その理由を述べる。
江戸しぐさの本家・家元の越川禮子が書いた「日本人なら知っておきたい江戸しぐさ

まず文章のテンションがものすごく高い。言葉ならテンションが高くなることもあるだろうが、文章のテンションが高いとなると、まさに信仰を語っているようだ。現在なら催眠商法の語り口というのだろう。
正直言って調べるために読むと思わなければ、冒頭の10ページも読んだら放り捨てたいレベルだ。
ではどんなところが胡散臭いのか。
- p.64 「肌の色の違う人も差別しない」
織田信長の黒人の臣下とか家康の臣下の三浦按針など、江戸時代以前から黒人や白人が日本に来て住み着いた事例があるのは存じている。
だが一般庶民の暮らしにおいて混在して暮らしていたという記述を、学校教科書、小説、随筆などで見かけたことはない(注2)。
肌の色が違うとは黒人や白人のことではなく、日本人の中の違いだというかもしれない。待て、次を読んでくれ。 - p.65 「異文化との共生を奨励した」
本当ですか? キリスト教の禁止は異文化との共生に反するのではないのでしょうか?
異文化の意味ですが、ウィキペディアでは「「外国文化」の同義語としてのマクロ的な視点と、「同一コミュニティ内」においての属性や習慣による価値観の違いを示すミクロ的視点に大別される」とある。
この本で異文化とはミクロ的意味だと言うのか? だけど武家と商家を異文化というなら、奨励される以前に共生は必須で必然だ。 - p.101 「江戸では『です』と断言できるのは、自分が体験して実感したことだけに許された」
へえ!この本全編に「です」が使われてますけど、著者 越川禮子が体験していないのは間違いない。せいぜいが「師匠芝三光は語った」ではないのでしょうか? - p.140「手を洗う習慣を身に着けさせた」
江戸商人の心構えとあるが、本当とは思えない。江戸時代は刀傷を小便で洗う時代だ。日本人はきれい好きと言われるが、ものの本によると食前の手洗いは戦後に奨励されて、その結果赤痢を減らしたとある。そもそも有名なゼンメルワイス医師は19世紀半ば、日本なら江戸時代末期のことである(注3)。 日本人がきれい好きだったとしても、石鹸もなくきれいな水もなければきれいにならない。実際に、天然痘、ハシカ、インフルエンザなどの大流行は数年おきにあり、流行時には江戸の人口の3〜4%が亡くなったという
(注4)。 明治の御代になってからもコレラが何度(1877/1879/1886/1890/1895)も流行した。まだ抗生物質もなく、下水道もない時代だったが、最大の原因は用足し後に手を洗う習慣がなかったせいだというウェブサイトや本は多々ある。
なお1918年スペイン風邪と呼ばれたインフルエンザの世界的流行は日本でも猛威を振るい、3年間で48万人が亡くなったといわれる。
内務省衛生局(今の厚生労働省に相当)が対策として「流行性感冒予防心得」をだし国民に自衛させた。その内容は「病人、咳をする者には近寄らない」、「沢山人の集まっている所(芝居、活動写真、電車など)に立ち入らない」、「咳やクシャミをする時はハンケチ、手ぬぐいなどで鼻、口を覆う」ことが重要であると記してあるが、手洗いに言及されていない。
これからも手を洗う習慣が、江戸時代に普遍的なものであったはずはない。ひょっとして「江戸しぐさ」を知っていた人たちが虐殺されたから、その知識が失われたのだろうか?注:内閣官房 新型インフルエンザ対策 スペイン風邪(後半)
どうもこの本を書いた人は、想像上の江戸時代を描いているのではないのか?
- 本を書くとすると、書く内容は主に三つだろう。ひとつは学んだこと、ひとつは自分で見つけたこと、ひとつは自分が考えたことになる。
学んだことならその元となる書籍やメディア、講義、師匠の言葉などがあるはず。自分が見つけたことなら発見した状況とか、論理的な展開があるあず。
この本には出典の記述が一切ない。書籍から得た情報なら章末や巻末に、書名・著者・出版社・発行年・文章を引用したら記載のあるページを表記する。あるいはマスメディアから得た情報なら、月日・メディア・番組を書く。
この本は、素晴らしい講釈を語っているが、その根拠となるものが一切ない。お説によると、明治維新時の江戸しぐさ弾圧により文献一切が失われたとか、師匠から口伝でしか伝えないとかいうが、それを立証する証拠もないという
(注5)。 勝海舟が江戸しぐさを尊ぶ人たちの脱出を手助けしたそうだが、勝海舟は明治32年まで生きた。勝海舟のような言いたい放題の人なら何か手掛かりを残しているだろう。
要するに引用なのか、著者が発見したのか、著者の創作か分からないのである。
|
? いろいろと考えて、思いついたものがある。 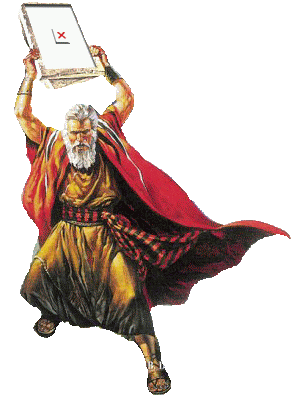 ひょっとして自分たちはユダヤ人のように選ばれた選民であり、今まで迫害を耐え忍んできたという物語を欲したのか?
ひょっとして自分たちはユダヤ人のように選ばれた選民であり、今まで迫害を耐え忍んできたという物語を欲したのか?そう考えると、迫害者からのエクソダス、ゲットーに身を潜め、ジェノサイドを生き残り、聖地を奪還して国を再興する、まさにシオニズムである。 だけどその教典が「江戸しぐさ」では、旧約聖書に比べてちょっとショボイ。 |
江戸しぐさというムーブメントを簡単にまとめると、
1970年代に芝三光という人が「江戸の良さを見直す会」を作り、そこで古い良き習慣を広めたのが始まりらしい。それが1980年代に読売新聞が取り上げたことから「江戸しぐさ」という名称でだんだんと知られるようになった。
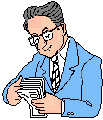 最古の書籍が1986年というのは納得できる年代だ。
最古の書籍が1986年というのは納得できる年代だ。
そののち強力な宣教者 越川禮子が表れて、マスメディアを使い多数の書籍を出版し、地下鉄のポスターに使われ、小学校の道徳教育まで使われるようになったという流れが、「江戸しぐさの正体」に記されている。
言うならば、マナーからルールへではなく、マナーからビジネスに進化したのである。
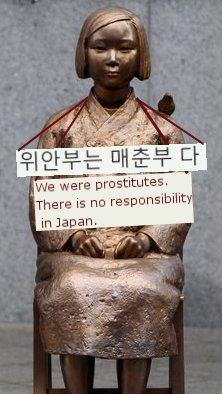 ご存じない人もいるかもしれないから簡単に説明する。
ご存じない人もいるかもしれないから簡単に説明する。 大人になると、兄弟二人とも刑務所とシャバを行ったり来たりの人生を歩み、弟は40くらいのとき喧嘩で殺され、兄は60過ぎに刑務所で病死した。(実話である)
大人になると、兄弟二人とも刑務所とシャバを行ったり来たりの人生を歩み、弟は40くらいのとき喧嘩で殺され、兄は60過ぎに刑務所で病死した。(実話である)



