日本は法治国家
官報に掲載されても、公布された時はいつかという問題が起きる。企業にいて毎朝官報を見ている人は例外中の例外だ。多くの人は例えば道路交通法の改正は運転免許書き換え時に知るくらいだろう。
しかし時によっては厳密にいつかが問題になることもある。そういうことがあるので、東京で売り出す(入手できる)朝8時半とされている
ところで官報に載るのは法律の制定・改定だけではない。皇族の行幸や行啓、外国との条約締結、大臣や次官などの人事、破産、司法試験や技術士などの国家試験の合格者発表、行旅死亡人の公報などである。
私が現役時代、勤め先は9時始業であったが毎日7時半にはパソコンを立ち上げ、官報や夜の間に溜まったeメールの片づけをするのが習慣だった。もちろん官報に法改正が載る前に業界団体などから情報が入っているから、初めて知ったなんてことはない。もっぱら自己破産者とか行旅死亡人などをながめていた。行旅死亡人というと行き倒れのことだが、孤独死で身元が分からない人も入る。
■行旅死亡人の公告の内容はなかなか読み応えあるものが多い。
本籍・住所・氏名不詳、男性、年齢30〜40歳くらい、身長168cm、体格中肉、黒色短髪、青ダウンジャケット、黒長袖セーター、ジーンズ、白スニーカー、所持品現金4,351円、青ショルダーバッグ、黒革財布、スイカ
上記の者は、令和○年〇月〇日、○県○市〇町〇番地の○○川○○橋の下で発見されました。
遺体は火葬にして、遺骨を保管してありますのでお心当たりの方は、○市〇課まで申し出てください。
令和○年〇月〇日 ○県○市長 ○○
■個人破産の場合の記載はみな同じだ。知っている名前は一度もなかった。
省エネについての規制基準は国が定めるもの、つまり法律とか施行令などしかない。一方 廃棄物の規制については廃棄物処理法
だから産業廃棄物の規制の細かいことは環境省に聞いても答えがもらえない。所在する県の判断による。A県では産廃、B県では特管産廃ということは普通にある。家庭ごみの分別方法が市町村によって違うのはご存じの通り。
注:都道府県や市町村のことを地方自治法で「地方公共団体」と称するとしており、地公体と略す。
地方自治体(自治体)は正式呼称ではなく通称である。地方自治法があるのに地方自治体でないのは謎である。
最近私は家庭ごみについていろいろと書いている。そんなわけでこのところ地方公共団体の例規集を読むことが多い。例規とは地方公共団体の条例や規則の総称。条例とは地方議会の議決によって制定されるもので、規則とは地方公共団体の長がその権限で定めたもの。
消防などは複数の市町村が共同して事務組合を作って運営しているところもある。そこで制定したものの名称は、条例・規則・規程などいろいろである。
似たようなものに要綱があるが、これは地方公共団体職員の業務の手順などを決めた内部規定であり、外部に対して法的な拘束力はない。
実際には要綱に基づいて規制しているケースがあるが、あってはいけないものであり、要綱行政と呼ばれる。
前置きが長くなったが、会社で廃棄物の仕事をしていると、扱うものの9割が産業廃棄物であり、法律、施行令で間に合う。それで所在地の例規を参照するなんてことはめったにない。

一般廃棄物が1割もあるのかと問われるかもしれないが、工場が田舎にある場合はあわせ産廃
家庭から出るごみは100%一般廃棄物となり、その取扱いは法律でなく例規を基にすることになる。ということで最近、例規を見ることが多くなったわけです。
えっ、何でそんなことをしているんだって?
なんででしょうねえ〜、暇だからでしょうか?
当然であるが都道府県や市町村などの地方公共団体が定めた条例なども公告される。通常は月1回発行の「○○市広報」という新聞があるはずだ。ただし条例全文が載るのでなく○○条例が可決されましたということと、概要が数行載るだけのことが多い。
昔は自分が住む市の条例全文を読みたくても、手軽にみられるものではなかった。それで市役所に行って条例を見せてくださいとペコペコ頭を下げてお願いしたものだ。まさにお役人様って感じじゃないか 💢
もし会社の労働組合から市会議員を出しているなら、議員に口をきいてもらうと反対に職員がペコペコして対応するなんてことになった。
どちらにしても感じがよくない。
1990年代末、タイでISO14001認証を指導したとき、工場で環境管理をしていたタイ人が市に環境関係の条例を見せてほしいと行ったら、何のために調べるのだと問い詰められて逃げ帰ってきたことがある。
日本人駐在員はそれを聞いて笑っていたが、日本だって1980年代中頃までは似たようなものだった。
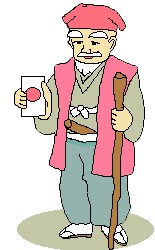 まさに水戸黄門に出てくるお代官様である。
まさに水戸黄門に出てくるお代官様である。
TVドラマ水戸黄門が視聴率を稼いだのは、公務員の態度が悪く嫌な思いをしていたので、ドラマで黄門様が悪い代官を懲らしめるのを見てカタルシスを感じたからではないのか。
しかし1990年頃になると公務員が偉いなんて風潮は一掃され、市会議員の紹介など無用となった。
水戸黄門がはやらなくなったのは、お役人が上から目線を止め市民と同じレベルで話すようになったからだ。今はもう水戸黄門のドラマをみて憂さを晴らす必要がない。
例1:1970年代初頭、パスポートのために戸籍抄本を取りに市役所に行った。すると窓口のオバサンに、なぜ戸籍抄本が必要なのか、なぜパスポートを取るのか、なぜ海外旅行に行くのか、無駄使いしないで貯金して親孝行しろと多くの人が見ている窓口で説教を食らった。
お前、何様だ! お役人様か…
例2:結婚して休日に婚姻届けを出したら平日に来いという。やむなく持ち帰ったが、あとで休日でも良いことを再確認した。不勉強にもほどがある。それとも面倒くさかったのか?
実を言って家内との思い出の日に入籍しようとしたのだが、そんなわけで全然関係ない日になってしまった。まっこの歳になればどうでもいい話ではあるが…
例3:生後半年の息子を連れて引っ越しの手続きしにいったら、窓口が赤ちゃんが泣いてうるさいからおいてこいと言う。俺が泣いちゃうよ。
市役所はサービス業だと認識していないようだ。
そんな時代もあったのだ。水戸黄門に懲らしめてほしいという気持ちはわかるだろう。
そして20世紀末になり、市条例をインターネットにアップするようになると、自分の部屋で北海道から沖縄まで、市町村の例規は無料で見放題という素晴らしい時代になりました。
全国の例規をみるのは ⇒ 全国自治体リンク
とはいえ例規は細かなことまで書いているわけではない。例規を読むと
「第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等による廃棄物の減量、資源化及び適正な処理を図るために必要な事項を定めることにより……」
なんて格調高く(皮肉だ)始まり、法律のコピーのような文言が延々と続く。
そして実際に知りたい分別方法とか粗大ごみを出すとき払う金額などは出てこない。
例えばあなたの街の家庭ごみの分別は何に決まっているのかご存じだろか。
たぶん回覧板で配られた「○○市 分別ガイドブック」という冊子とか「家庭ごみの出し方」なんてチラシを見ているのではないでしょうか。それって権威あるというと変ですが、それに従えば問題がないのでしょうか?
市から配られたといってもそれを信用する根拠はあやふや。私もネットにある市のごみ出しチラシや冊子を20件近く見ましたが、表紙に○○市とあっても担当部署も問い合わせ先も書いてないものもあり、中には発行年の記載がないのもありました。
一生懸命 冊子通り分別していたら「奥様、分別が間違ってるわ、今は違うのよ」なんて言われては涙が出ます。
では分別はだれが何で決めているのでしょう?
廃棄物処理法の第6条で「市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない」とあり、その第2項第3号で、「(計画の中で)分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分(を定めなければならない)」とあります。
つまり廃棄物の分別方法は例規(条例や規則)でなく、「○○市一般廃棄物処理計画」というものの中で決めているということになります。
「一般廃棄物処理基本計画」の制定方法や内容についての策定指針を環境省が作り、各自治体に通知している
しかしなんだね、法律で市町村は○○を作れとあると、どんなものを作ったら良いのか分からないだろうと、所管省庁がひな形を作って全市町村に通知するというのだから、はたから見たらおんぶにだっこだ。
そいうものは多々ある。
消防法では「火災予防条例」を作れという文言はないが、「市町村条例でこれを定める」という文言が11か所ある。本来なら法律に基づき市町村の消防部門はそれを具体化した条例を作成制定しなければならない。
しかしそれは大変だろうと、消防庁は「○○市(町・村)火災予防条例(例)」というひな形を作り全市町村に通知している。
これは市町村が自分で条例を作れないのか、あるいはおせっかいなんでしょうか?
それはともかく各市町村の火災予防条例は、ほとんどひな形に同じだが、多少は自治体特有の事情で修正していることもある。
ともあれ市町村の条例を読んでいると面白い。法律のように格調高い文句が並んでいると、これはきっとひな形通りだろうと予想がつく。訥々とした文章の例規は、その市町村が必要に迫られたことで自ら作文したものらしい。
私がなぜ例規を読んでいるのか?
だって日常生活する上で市の行政サービス…言い換えると規制が、どういう風に決まっているのかを知るのは絶対に必要なことだ。単に町内会から配られたチラシ一枚を根拠にゴミ出しするのはいささか不安だ……あなたは不安ではありませんか?
それに住んでいる土地についていろいろ知ることは面白いし役に立つことだと思う。
老人になると地域研究とか、郷土の歴史などを学ぶ人が多い。それは面白いが若い人こそ自分が住んでいる市がどのようなものなのかを知る必要がある。
今私が手に取って見ているのは習志野市の一般廃棄物処理計画だが、初めに面積、人口があり、「市の性格、東京のベッドタウンであることなどを考慮して……」と始まる。それはごみ処理だけでなく、市の過去・現在・未来の要約であるし、読めば市の置かれた状況について詳しくなれる。
自分の住んでいる市を知ることは自分の市を好きになることだ。市民であるなら、住んでいる市の人口、人口の推移、面積、民力、ごみの量、平均年収、問題点、市の施策、都市計画くらいは知っていたほうが良い。そういう知識、情報があれば地方選挙
あなたの住んでる市の住民税は、近隣の市に比べて高いか安いかご存じですか?
例規は廃棄物だけではない。眺めると面白い。
 国民栄誉賞というのがあるが、市によっては条例で市民栄誉賞を設けているところがある。市民に敬愛され、社会に明るい希望を与えることに顕著な業績があつた者だそうだ。どんな人が受賞するんでしょうねえ〜
国民栄誉賞というのがあるが、市によっては条例で市民栄誉賞を設けているところがある。市民に敬愛され、社会に明るい希望を与えることに顕著な業績があつた者だそうだ。どんな人が受賞するんでしょうねえ〜
名誉市民というのもある。市に功労のあつたもの又は広く社会の進展、学術文化の興隆に貢献したも功績が顕著であるものだそうです。
イメージとしては市出身のスポーツ選手は市民栄誉賞で、産業育成とか学者は名誉市民なのでしょうか?
普通名誉市民というと市に貢献した市在住でない人に、市民と同様な権利を認めるものですが、ちょっと違うか?
アメリカでは名誉市民になると選挙権まで持てる。
議会とか選挙とかの例規を読むと、議会傍聴とか市営駐輪場の管理などがわかります。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う職員の時差出勤に関する規程なんてのもあります。
消防にはもちろん○○市火災予防条例があります。私が会社で仕事で参照していたのは火災予防条例でしたが、消防というカテゴリーの中では階層はずっと下のほうなのです。トップは消防署の設置とか消防組織を決めたものです。確かに考えてみればそうです。
システムの三要素はなにか?といえば、組織、機能、手順
まずは消防というお仕事をするための組織を作るわけです。次に設置した部門に消防に必要な機能を割り振り、それらの機能を達成するために手順を定めることになる。
私から見ると手順である火災予防条例がすべてであったけど、消防全体から見ればほんの一部分だったわけだ。
私は近隣の市の例規集しか見ていないが面白いことに気が付いた。市川市・船橋市・習志野市を見比べると船橋市が一番ボリュームが多い。そりゃ船橋市は人口64万、市川市50万、習志野市17万だから三市の中で人口は多いが、人口が多ければ条例が多いという理屈はない。
気が付いたのは船橋市は中核市だということだ。
中核市とは人口20万以上でその市の市議会の議決と県議会の議決を経て総務大臣に指定を申請し、指定を受ける。中核市になると県が持つ事務権限(要するに県がしている仕事や許認可)の一部を移譲される。
ということで中核市になると産業廃棄物関係の事務を取り扱うことになる。単に申請を受けて事務処理するだけでなく、業者の管理監督がとんでもない大仕事になる。もちろん廃棄物だけでなく、中核市になっていろいろ仕事が増えただろう。
 熱海市の土砂崩れは自然災害とか造成ではなく、不法投棄によるものと言われる。そんな問題が起きれば監督機関(市町村)の責任は重大だ。
熱海市の土砂崩れは自然災害とか造成ではなく、不法投棄によるものと言われる。そんな問題が起きれば監督機関(市町村)の責任は重大だ。
船橋市は中核市になって大変だ。とはいえ政令指定都市以外では船橋市は一番人口が多いのだから、私は中核市になりませんとはいえなかったのだろうね。
注:熱海市は人口3万で中核市ではない。だから産廃業者の許認可は静岡県であり、問題解明と対策の責任は熱海市ではなく静岡県にある。
![]() 本日のお勧め
本日のお勧め
市民も条例を読むべきだ。読めば役に立つこと間違いなし。
実を言って、私も今までまともに読んだことがなかったのだけどね。
えっ!タイトルが羊頭狗肉だって?
いよいよ私のコピーライターの腕が冴えてきましたか、フフフ
注1 |
法治国家とは制定された法律に基づいて、政治を行う国家。対義語は人治国家で中国のような国である。 必ずしも法治国家は民主主義ということではない。専制国家であっても法治国家のこともある。 また法治国家であれば法律はすべて文書化されていなければならないかというと、成文憲法のないイギリスもある。しかしイギリスはまとまった憲法はなくても裏打ちする法律や判例があり、法治でないとはいえない。現実的には文書化されていない法治国家は存在できないのではないだろうか? 法治国家とISOマネジメントシステムのアナロジーを考えると一文書けそうだ。 | |
注2 | ||
注3 |
正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」である。 一般廃棄物を地方公共団体が処理することは第6条にある。 | |
注4 |
あわせ産廃とは、本来は産業廃棄物であるが市町村が一般廃棄物とあわせて処理することが必要と認めて、市町村が処理するもの。 実際はあわせて処理することが必要というより、小規模少量の産廃を市がサービスで処理してくれているような意味合いだ。 | |
注5 | ||
注6 |
選挙は次の種類がある 衆議院議員総選挙…小選挙区選挙と比例代表選挙があり、解散と任期満了の場合がある。 参議院議員通常選挙…参議院の議員の半数を選ぶ。 地方選挙…………都道府県、市町村の首長と議員を選ぶ。解散と任期満了の場合がある。 | |
注7 |
アメリカ軍におけるシステムの定義である。そもそもシステムとは社会体制とか制度のことであり、それは組織と機能と手順が基本となる。 |
うそ800の目次に戻る
     |